
末木文美士 『死者と霊性の哲学 ポスト近代を生きぬく 仏教と神智学』 」 反近代・反世俗としての 〈霊性主義〉 ・ 末木文美士の逸脱
書評:末木文美士『死者と霊性の哲学 ポスト近代を生きぬく仏教と神智学』(朝日新書)
嫌な予感が当たってしまった。
本書著者の末木文美士は、一流の仏教学者である。その末木が、昨年(2021年)11月に増補版として刊行した『増補 仏典をよむ 死からはじまる仏教史』(角川ソフィア文庫)について、私は「仏典と対座する〈真剣勝負の書〉」と題するレビューを書き、仏教各派に偏りなく真っ向対座するその姿勢に好感を持ち、きわめて高く評価した。
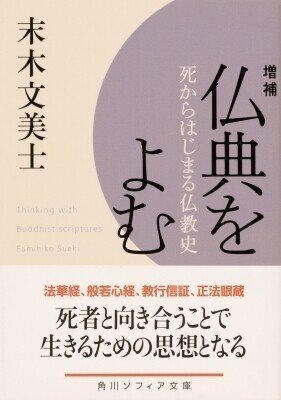
しかし、その後に気づいたことなのだが、私はそれ以前(2020年2月28日)、同じ著者の著作について、かなり手厳しい評価を下していたことを思い出し、さて、どちらの評価(あるいは直観)が正しかったのだろうか、と気になっていた。
その手厳しい評価とは、末木の『日本思想史』(岩波新書)に対するレビュー「〈叩き台〉としての日本思想史」におけるものであった。
この『日本思想史』は、「日本の思想史は、西欧由来の思想や哲学という観点からだけでは、十全に描ききれない」と考えた末木が、自身の専門とする「仏教思想史」や「仏教史」の観点から、それを見直すことを試みた著作であった。

私は、末木のこの意欲作について、その意義を認めた上で、次のような注文をつけていた。
あえて言うならば、「はじめに」において、著者が語る「現代思想」批判は、やはりいただけない。
『 長い間、日本人にとって過去の自分たちの思想は、まともに考えるべき対象とはされてこなかった。思想や哲学と言えば、西洋から輸入されたものを指し、最新流行の欧米の概念を使って、その口真似のうまい学者が思想家としてもてはやされた。思想や哲学は一部の好事家の愛好品か、流行を追うファッションで十分であり、そんなことに関係なく、国も社会も動いてきた。』
著者は、このあたりの文章について、「あとがき」で、
『「はじめに」の文章はいささか過激に見えるかも知れないが、私の渾身からの願いである。』
と書いて正当化しようとしているが、『渾身からの願い』であろうがなかろうが、的外れで不適切な批判は、的外れで不適切なものでしかない。それは、飛行機をハイジャックしてビルに突っ込むのと、本質的に大差ないのである。つまり、「言論」というのは、「気持ち」だけで済む問題ではないのだ。
本書を読んでもわかるとおり、『思想や哲学と言えば、西洋から輸入されたものを指し、最新流行の欧米の概念を使って、その口真似のうまい学者が思想家としてもてはやされ』るというのは、今も昔も同じである。
最澄や空海が現代に生まれていたら、流行思想家にはなれるかも知れないが、『国や社会』を動かすことは、できないで終わる蓋然性が極めて高い。昔の宗教家や文化人が、政治を動かせたのは、それは「そういう時代」であったからで、昔の人が特別に偉かったわけではないのだし、『国や政治』を動かした人が、必ずしも、あるいはしばしば「ぜんぜん偉くない」場合も、今と変わらずあったのだ。
また、昔の「歴史に大きな名前を残さなかった、宗教者や文化人」のなかにも、政治的影響を与えた宗教家や文化人について、本書の著者と同じような批判を加えた人が、必ずやいたことだろう。『最新流行の欧米の概念を使って、その口真似のうまい学者が思想家としてもてはやされた。』と。
しかし、それを妬んでもしかたがない。
現代の私たちが知るべきことは、そうした人たちが個人的に立派だったか否かといったことではなく、何がどのように、日本の政治や文化に影響を与えたのかという事実であり結果であろう。そこが、今の我々にとっても「リアルな問題」となるからである。
つまり、本書著者の末木文美士は、自身の専門(の仏教哲学や仏教史)の範疇にあるものについては、それらをそれぞれに尊重し、真剣に向き合っているのだが、その「専門」から外れたものについては、かなり「安直」で「感情的」な向き合い方しかできていなかったのである。
だが、著者のこうした、「専門外の知」に対する、言わば「身の程知らず」とも呼ぶべき態度は、一体どこから出たものなのであろうか。
私はそれを、著者の「自己の博識と柔軟性に対する増上慢」にある、と考える。
本書『死者と霊性の哲学 ポスト近代を生きぬく仏教と神智学』を読んでもわかるが、著者は「西欧哲学史」的な知識も「ひととおり」は持っていて、カントがどうのハイデガーがどうのと語ってもおり、その理解は、基本的には間違いではない。
しかしながら、その「正しい知識」とは、所詮は「西欧思想史の教科書」や「入門書」を読めば得られる程度のものでしかなく、決して「専門」的な「深さ」を持たない、要は「ひととおり」のものでしかないのだ(カントやハイデガーの専門研究者が読めば、間違いなく、うんざりさせられるだろう)。

無論、著者の「専門」は「仏教哲学」であり「仏教史」なのだから、「西欧哲学」や「西欧哲学史」、あるいは「個々の哲学者の思想」、ましてや「現代思想」にまで通じていなくても、仕方はない。
しかしながら、著者が「専門」を持つ「学者」なのであれば、「専門外」については「よほど慎重でなければならない」ということくらいは、当然、承知していてしかるべきなのだが、著者が知ったかぶって語る「西欧哲学」や「現代思想」の「説明」には、いかにも入門書レベルの「付け焼き刃」感が否めないのだ。
そうした「安直さ」を象徴するものとして紹介すると、例えば、本書著者は「コロナ禍の影響」について、次のように書いている。
『 コロナは従来の価値観を大きく転換させることになった。生身の接触が控えられる中で、インターネットの普及によるバーチャルな人間関係が推進される。「他者」は身体性を失い、画面の中に現れる見せかけの存在に変わる。他者との「絆」は、アプリを消せば消えてしまうはかないものしかない。世界中で国境を越えた交流が断絶するという前代未聞の事態は、観光、ビジネスはもちろん、研究者にとっても大きな試練となった。しばらく前にはSFの中にしかなかった近未来的な状況が、一気に現実のものとなった。』(P26〜27)
これなども、話として大筋で間違ってはいないものの、所詮は「ありきたりに図式的な紋切り型」の域を出ず、さらに悪いことには、見え透いたレトリックによる「恣意的な誘導性」を容易に読み取ることのできるシロモノでしかない。
つまり、「科学」や「合理主義」が嫌いな、わかりやすい「宗教的反近代主義者」が、大衆ウケのする『生身』や『身体性』や『絆』を賞揚する一方で、それに対立するものとして『インターネット』や『バーチャル』や『アプリ』などを、『SF』的な「非人間的」で「冷たいテクノロジー(近代性の象徴)」として、印象付けようとしているのである。
だから、こんな著者が、本書で、嫌いな「近代主義」でもなければ、その反動たる「ポピュリズム的なポスト近代主義」でもない、『第三の道』と称して、「霊性主義」という実質的には単なる「反近代主義」でしかないものを、こと新しげに持ち出すというのは、実にわかりやすく、安直な「子供騙し」でしかないのである。
著者は、本書で、専門の「仏教」に加えて、キリスト教由来の神秘主義思想である「神智学」も持ち出すことで、その「思想的(東西)越境性」と「新しさ」を強調しようとしているが、そんなものは所詮、「時代のリアルとの対決」を避けた、懐古趣味的「アナクロニズム(時代錯誤)」でしかないし、そもそも今どきの日本で語られる「霊性主義」とは、近代的経済発展から明らかに取り残されて落ち目になった現状における、自己慰撫的な「反動的逃避思想(経済がダメなら、心があるさ)」でしかないだろう。

(神智学の創始者・ブラヴァツキー夫人)
著者が、本書「あとがき」で『「横の会」と称して議論を交わしてきた友人たちと、座談会を中心とした『死者と霊性 近代を問い直す』(岩波新書、二〇二一)を編集刊行』と紹介しながら、その名を明記していないこの「友人たち」とは、中島隆博・若松英輔・安藤礼二・中島岳志の4人で、ここには専門の西欧哲学者はおらず、「東洋思想(哲学)」および「保守思想」寄りの人たちばかりである。
末木文美士は、仏教学者としては一流と呼んでいい人のはずだが、しかし、このような偏頗な「横」のつながりで「意気投合」して盛り上がるというのは、いかにも安直だ。

「専門」を持つ学者なればこそ、「専門外の専門分野」に対しての敬意と緊張感を失わず、それと「対決」することで、自身の「専門」性を鍛えるべきなのに、末木に見られるのは「自分は専門バカではない」という思い上がりと自信過剰。それに由来する「専門外の専門分野」に対する安易さ。そして自身の「越境性」を支持してくれる「同類」との安直な「馴れ合い」だけなのである。
専門である「仏教」の範囲内であれば、あれだけ慎重にして「公正誠実」だった人が、どうしてこのような醜態を晒してしまうのだろう?
一一これはもう、「私には、すべてが見えている」という「増上慢」であり、末木の捕らわれている「魔境」の故としか、考えようがない。
多くの祖師が弟子たちを戒めているように、「悟った」と思った瞬間に、人は「悟りへの道」を踏み外している。
その意味で「博識」とは、決して自慢するべきものではない。それは、軽薄な「目移り」や「浮気性」であってはならない。
むしろそれは、自身の「無知」を実感するための、「畏怖すべき外部」でなければならないのだ。
(2022年3月1日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
