
加治伸行 『 論語 ビギナーズ・クラシックス 中国の古典』 : 単なる「理想主義」に非ず
書評:加治伸行『論語 ビギナーズ・クラシックス 中国の古典』(角川ソフィア文庫)
いまさら『論語』である。
と言っても、若い人にはピンと来ないのではないだろうか。『論語』というのは「年寄りが好きそうな、古臭そうな中国哲学」くらいの印象しかなく、実際にどんな「傾向」のものかということまでは知らない。というのも、すでに長らく『論語』について語られることが、めっきり無くなったからである。
私が若い頃は、まだ『論語』を語る人が多少はいた。というのも「日本は儒教文化の国」であり、それが長所でもあれば短所でもあると考えられていたからで、『論語』をありがたがる人もいれば、そこで語られた思想を、時代にそぐわないものとして批判する人も少なくなかったからである。つまり、論議の的(まと)にもなったのだ。
ところが、いまや『論語』的な「社会倫理」がほとんど過去のものとなってしまったから、おのずと『論語』について語られることもなくなったのである。

しかし、では、私自身『論語』について知っているかと言われれば、ほとんど何も知らない。知っていることといえば、「礼節」の重視を説いた孔子の言葉をまとめた書物ということくらい。また、孔子の思想の流れを「儒教」と呼ぶということくらいだろうか。だが、この「孔子・論語・儒教」の三者関係だって、長らく漠然と知っていただけで、自信を持って三者の関係を語れるほどではない。
なにしろ、興味がなかったのである。「日本は儒教文化の国」で、儒教が「礼節」を重視し「上長を敬う」ことを説く「体制側の思想」であり、いかにも「古臭い」となると、それへの興味など、とうてい持てなかったからだ。
なにしろ私は、「全共闘世代」の挫折を経た後の「三無主義・しらけ世代」の人間でありながら、そうした時代の趨勢を越えて、「反抗的」で「下剋上」的な性格に育った、筋金入りの変わり者だからである。
そんな私が、なんでいまさら『論語』に興味を持ったのかというと、ひとつは、私が好きな夏目漱石が「四書五教」の時代の教養人であり、その小気味の良い文体は、「漢文調」のテンポをもったものだと知ったからだ。つまり、漱石のような、適度にペダンチックかつテンポの良い文書を書きたいと思えば、「四書五教」的な教養が必要だと知ったのだ。

こうしたものに惹かれるのは、私が子供の頃、あるいは若い頃というのは、「西欧文化」や「アメリカ文化」が「輸入思想」としては主流であり、憧れの的だったということがあろう。
例えば、「映画」といえばアメリカ映画だし、「思想」といえばフランスだった。そういうものを、最新の流行に乗った知識人の口真似するのが流行っていた。それが「カッコイイ」と思われていた。今の高齢者の多くは、そういう世代である、
だが、私はへそ曲がりなので、そうした流行に、後追いでついていくのは嫌だった。だから、ちょっと違ったもの、変化球のクセ玉で勝負したいと思ったのだ。
だとすれば、流行らなくなって、みんなが口にしなくなったあと、すでにほとんど忘れ去られている「四書五教」的な教養というのは、ほとんど役に立たなかったとしても「反時代的」でカッコいいのではないかと、そう考えた。
そんなことから、何やら意味ぶかげな格言を引っ張ってくることなんかも、流行りではないからこそ、オリジナリティがあってカッコいいのではないかと、そんなことを考えたのである。
さらに「漢文調」がカッコいいと思ったのは、戦前のミステリ作家である小栗虫太郎の影響もあるだろう。
小栗虫太郎の代表作『黒死館殺人事件』などで典型的に示される、小栗虫太郎的「文体」というのは、黒黒とした画数の多い難しい漢字が並んでおり、それにカタカナのルビなんかが振られているという、禍々しくも重厚な「見た目に迫力のある文体」である。

例えば、「亜剌比亜・希臘」には、どのようなルビが振られているであろうか? 正解は「アラブ・ギリシア」である。では「希伯来語」の頭の三文字はどうか「ヘブライ」である。「猶太秘釈義法」はどうか? 「ユダヤカバラ」である。「神秘数理術」はどうか? 「ゲマトリア」である。一一なんとカッコいい!
まあ、このルビが正しいのかどうかはよくわからないのだが、とにかく「カッコいい」というのは大切なことだ。「COOL」と書いて「かっこいい」などとルビを振っても、全然カッコよくないではないか。
そんなわけで、私としては、あくまでも適度にだが、難読漢字だの漢語格言だのを使えるようになりたいものだという気分があったのである。
そして、孔子への興味を決定的なものにしたのは、先ごろ亡くなった、中国伝奇小説の書き手である酒見賢一の『陋巷に在り』を読んだことである。
この小説の主人公は、孔子その人ではなく、孔子に最も愛された弟子の「顔回」である。とにかくこの人は人柄の良かったのだが、若死にをして孔子を大いに嘆かせた人で、その意味では酒見賢一も同じだったのかもしれない。

で、この『陋巷に在り』は、顔回を主人公としながらも、物語は、顔回がつき従う孔子の人生をめぐるものとなっているから、おのずと孔子に関する描写も多く、孔子の思想が多く語られている。
この小説のユニークなところは、リアリズムの「伝記小説」「歴史小説」ではなく、あくまでも「伝奇小説」であるところ。つまり、「妖怪」や「神鬼」や「呪術」などが登場する、一種の「超能力バトルもの」の要素のある小説なのだが、それが今風の「アクション」中心ではなく、一種の「思想闘争」的な性格を持っているところが、重厚で素晴らしい。
本作に近い雰囲気の「伝奇小説」と言えば、日本の近代史を舞台にした、荒俣宏の『帝都物語』以外には思いつかない。『帝都物語』がカッコいいと思える人なら、『陋巷に在り』は確実に面白い。それに、同じように長大な作品ではあっても、小説としては『陋巷に在り』の方が、圧倒的に面白いのだ。

私は、『帝都物語』のファンでもあるから、あまりこの作品の悪口は言いたくないのだが、しかし比較の問題として言ってしまえば、同作の著者である荒俣宏は、小説家としては、残念ながら二流。小説が下手で、小説としては面白くない。博学な趣味人として、面白い着眼点と豊富なアイデアを盛り込んでくるので、その点では面白いのだが、小説としてはイマイチ盛り上がらない。「こんなに面白い素材を扱っているのに」と、もったいないことこの上ないのだが、小説家としての力量が、それについていっていないのだから、それはそれで諦めるしかないことなのである。
そんなわけで、物語作家としての酒見賢一は、抜群にうまい。その力量は、「第1回日本ファンタジーノベル大賞」を受賞したデビュー作『後宮小説』にして遺憾なく発揮されており、選考委員たちを瞠目させたのだが、思えばこの時の選考委員の一人が、荒俣宏その人でもあった。
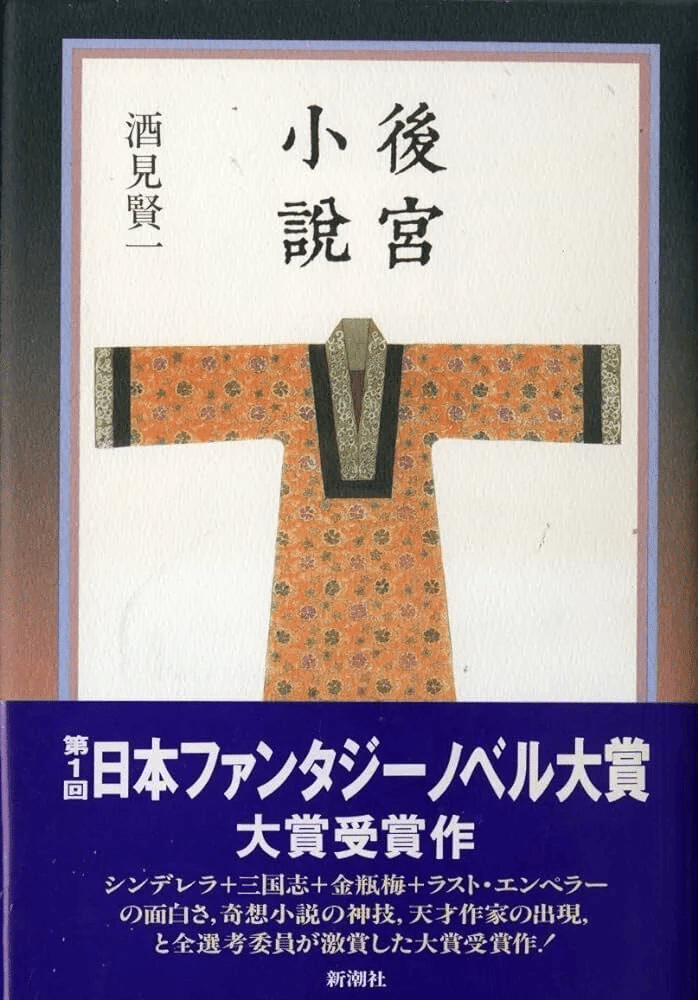
ともあれ、この『陋巷に在り』が抜群に面白かったのと、そこに孔子の人生が描かれていたことから、孔子が単なる「中国古代の偉大な思想家」というだけではなく、「理想を求めて流浪した思想家」として、ドラマチックに立ち上がってきた。人間・孔子が生き生きと描かれていたからこそ、顔回ら多くの弟子たちが尊敬して付き従った孔子その人とその思想に、私は興味を持つことになったのだ。
あと、とても興味深く思ったのは、『陋巷に在り』が「伝奇小説」だから、「妖怪」や「神鬼」や「呪術」などが登場するというだけではなく、孔子その人が、じつは、巫術者(シャーマン)集団に属する女性を母に持つ人であり、孔子の思想にある「親孝行」の思想や「上長を敬う」といった思想の背景には「先祖からの連綿たる繋がりの重視」ということがあるのを知ったからである。要は、孔子は、生きている「自分の親」や「上長」だけではなく、それを通して「過去のすべての人々」との繋がりを見ており、そこを重視していたとも言えるのである。「先祖礼拝(供養)」の思想は、仏教のものではなく、仏教が儒教を取り入れた結果なのだ。

もっとも、孔子自身は「怪力乱神を語らず」という言葉でも知られるとおりで「呪術だの超能力だの、神仏だの妖怪だのといったこと」は語らなかった。
彼はもっぱら「乱世を治めるための政治思想」を説いた人であり、その意味で「リアリズム」の人ではあったのだが、その一方で彼は「為政者は、立派な人間性(人徳)によって民を治めることこそ重要」と考えていた、今で言うところの「理想主義者」であり、決して「力の正義」を語らなかった人である。
もちろん、現実政治を問題にしているのだから、力の問題も語るし、軍事の必要性も語っている。
けれども、孔子の根本にあるのは「優れた人間性」の重要性ということなのだ。それがなくては、いくら力(どんな力や金)があっても、この世の中に平安をもたらすことはできないと、そういう思想だったのである。
こうした思想は、たぶん孔子が、農民の父の子であり、若い頃には肉体労働をして苦労した人だからではないだろうか。庶民の苦労を知っていたからこそ、権力者同士の「力のリアリズム」による争闘では、世に本当の平安をもたらすことができない、庶民まで幸せにすることはできないと、そのように、ある意味ではラディカルに考えたから、「力の思想」を超えたものとしての、理想主義的な「人間の思想」を語ったのではないか。
そして、もうひとつは、前述のとおり、母が巫術者集団に属する人であったため、「現世」や「力のリアリズム」では収まりのつかない「長い射程を持つ」思想としての「人間の思想」を構築しえたのではないだろうか。いくら「理想的にすぎて非現実的」のように見えたとしても、そこまで追求せずに、現実に妥協していては、いつまで経っても、世の平安はおとずれないと、そう考えていたのではないだろうか。
だから、孔子の思想を、「孝行の思想」であり「上長を敬う」ことを求める、「体制護持的な思想」だと考えるのは、間違いなのであろう。たしかに、そのようなかたちで長らく「政治利用」されてきたからこそ、そのような一面的な捉えられ方もされたのだが、孔子の思想そのものは、そんなに薄っぺらなものではなかったはずだ。
実際、孔子は「親を敬い、上長を敬え」と言ったけれど、前述のとおりで、「人の上に立つ者」に対しては、厳格にその「立派な人間性において、民を従わしめよ」と要求したのだ。言い換えれば、「上に立つ者」が立派でないのなら、下の者が彼らを尊重しないのは当然のことであるし、それで世の中が乱れるのも当然のことだと、そう考えていたということにもなろう。孔子は、何も闇雲に「親に従え」「上長に従え」と言っていたのではないのだ。上の立場のある者は、そうした立場に相応しい「立派な人間たれ」と、そう説いていたのである。
だから、儒教思想を取り入れた、利用したと言ってもいいが、ともあれ、儒教を「国教」として採用して、国家の安定を意図した昔の中国の権力者は、実際はともかく、少なくとも人民から見える部分では「立派な人間」としての振る舞いを意識して、無茶無謀なことをしないように自制した。人前であからさまに傲慢な言辞を弄したり、威張り散らしたりはしなかった。そして、その「建前」尊重的な自制において、権力は、大きく間違うことを抑制し得たのである。

そして、これは同じく「儒教」を取り入れた日本でも、長らく同じであった。
為政者(政治家・官僚)というのは、単なる「権力者」ではなく、人民をみちびくための権力を持つに値する人間であろうと、少なくとも表面的にはそのように振る舞った。そのような人間だからこそ、権力を振るえるのだということを、人民に示して見せていたのである。
ところが、今の政治家はどうか? 彼らの中に「人格者」がいるなどと思えるのは、殺された安倍晋三を心から崇拝していた「ネット右翼」のような、ノミの脳みそしか持ち得ない人間だけだろう。
また、今では、いったん権力さえ握ってしまえば、やりたい放題、言いたい放題だと勘違いしているような馬鹿が政治家になっているし、彼らにそのような勘違いをさせることになったのは、「貧すれば鈍する」で、人民の側も、政治家に「人格」を求めて、それに賭けるのではなく、「ひとまずどんなに酷いやつであろうと、国を豊かにしてくれたらそれで良い」などと「小賢しい」ことを考え、そう口にもするようになったからではないだろうか。そうなれば政治家だって「建前なんてどうでも良いんでしょ? 要は、結果オーライなんだから、力が正義だってことですよ」となるのも、当然の結果だったと言えるだろう。

だからこそ、今の日本人は、「政治家」だけではなく、「日本人」全体が、『論語』的な「人間倫理」を、再発見すべき時期に来ているのではないだろうか? 安直な「実績主義」だけでは、すでに世界は立ちいかないところまで来ており、今この世界を救うのは、恥ずることなく「立派な人間」であろうとする思想しかないのではないかと、私にはそう思える。
またこうした考えは、柄谷行人の主張する「統整的理念」というものにもつながってくるのではないだろうか。
○ ○ ○
そんなわけで、「孔子の思想」を語る『論語』だと言っても、今の現実に対するものとしては、全部そのまま字面どおりに受け入れるというわけには、なかなかいかない。
単純な話、「安倍晋三」だの「麻生太郎」だの「森喜朗」だのといった勘違い野郎たちを、尊敬しろと言われても困るし、「後輩にパシリをさせる先輩」とか「子供を虐待する親」とかを、そのまま尊敬することなど、とうてい不可能だし、適切なことだとも思えない。
孔子の思想というのは、あくまでも、その「趣旨」を理解した上で実用に付されないと、長らくそうであったように、それは「権力者による人民統制のための道具」となってしまう。
だが、くり返すが、孔子の思想そのものは、そんな薄っぺらなものではない。孔子が語っているのは「いかに生きるべきか」といった広範な話なのだから、私たちがまだまだ勉強不足で知らない面がいくらでもあるし、そこで「これは素晴らしい」と素直に受け入れられる考えも、いくらでもあるはずだ。
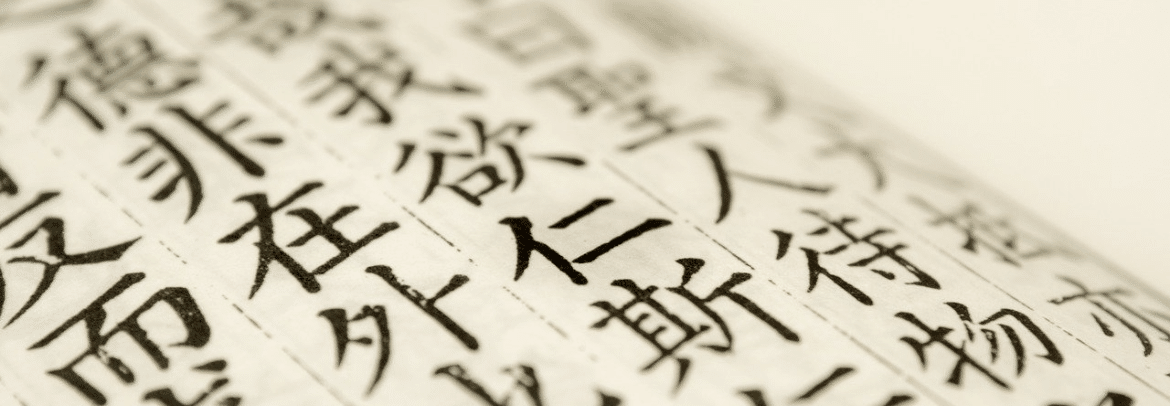
だからここでは、本書で紹介されている中でも、私が特に共感した孔子の言葉について、そのいくつか紹介しておきたいと思う。
なおここでは、書き下し文と、その釈義的現代語訳だけを示した上で、私の感想を付すことにする。
『子曰く、之を道(導)くに政を以てし、之を斉うるに刑を以てすれば、民 免れて恥無し。之を道くに徳を以てし、之を斉うるに礼を以てすれば、恥有りて且格(正)し。
老先生(※ 孔子)の教え。行政を法制のみに依ったり、治安に刑罰のみを用いたりするのでは、民はその法制や刑罰にひっかかりさえしなければ何をしても大丈夫だとして、そのように振る舞ってなんの恥じるところもない。〔しかし、その逆に、〕行政を道徳に基づき、治安に世の規範を第一とすれば、心から不善を恥じて正しくなる。』(P57〜58)
要は「徳政のススメ」である。
ここで注意しなければならないのは、孔子は決して「法制や刑罰」が必要ないと言っているわけではない、という点である。「行政を法制のみに依ったり、治安に刑罰のみを用いたりするのでは」不十分だ、と言っている点を見落としてはならない。
したがって、ここで語られているのは「単なる綺麗事」ではないのである。
『子曰く、古の学ぶ者は己の為にし、今の学ぶ者は人の為にす。
老先生の教え。昔の学徒は、自己を鍛えるために学ぶことに努めていた。今の学徒は、他人から名声を得るために学び努めている。』(P166)
「昔も今も変わらない」ということだろうが、今の方が、その悪しき傾向が「加速」しているということを見落としてはいけない。
『子曰く、由よ、女に之を知るを誨えんか。之を知るは之を知ると為し、知らざるは知らずと為す、是 知るなり。
老先生の講義。「由君よ、君に〈知る〉とは何か、教えよう。知っていることは知っているとし、知らないことは正直に知らないとする。それが真に〈知る〉ということなのだ。』(P167~168)
「知ったかぶりをするな」ということだけではない。それは当然として、より肝心なのは、自分が「何を知らないのか。何を理解していないのか」を知らないと、決して「成長はできない」ということである。
「私は、自分が無知であるということを知っている」という「無知の知」は、ただ「無知であることを知っている」というだけでは、意味がない。それを「知っている」自分に満足してしまうからだ。
しかし、「具体的に、何を知らないのか」まで知っていれば、おのずと現状に満足することなく、学びを続けるはずなのだ。そうしないではいられないはずなのである。
したがって、狭い得意分野や専門分野に自足して満足しているような人は、「無知の知」がない「無知の人」だということなのである。
『子曰く、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず。
老先生の教え。教養人は、和合はするが雷同(自分の意見がなく、人の意見にくっついてゆく)はしない。知識人は、雷同はするが和合はしない。』(P175)
ここで注意すべきは、孔子のいう「君子と小人」を、本書の著者である加地伸行は、単なる「優れた人と愚か者」と解釈するのではなく、「教養人と知識人」だと理解している点である。そして、ここで言うところの「教養人と知識人」とは、「教養人」には「知識だけではなく、人徳もある=リーダーたり得る」けれども、「教養人」には「知識はあっても、人徳がない=リーダーたり得ない」ということだ。つまり、「一流大学を出た頭の良い人」であっても、それに相応の「人徳」が伴っていないのであれば、それは所詮「知識だけの人」であり、人の上に立つべき人ではなく、要は『小人』でしかない、という意味である。
本書著者の加地は、孔子の政治思想から推して、「君子と小人」という言葉は、このように解釈すべきだと考えたわけである。言い換えれば、常識的、あるいは主流の解釈がどうであろうと、加地は「付和雷同はしない」ということだ。
『子曰く、君子は泰にして驕らず。小人は驕りて泰ならず。
老先生の教え。教養人は、堂々としているが驕り高ぶったりしない。知識人は、
驕り高ぶりはするが堂々とはしていない。』(P175〜176)
現代の日本では「驕り高ぶる」ことと「堂々としている」ことの区別がつかない人が、決して少なくないのではないかと心配になる。
『子曰く、剛・毅・木・訥は仁に近し。
老先生の教え。物欲に左右されないこと(剛)、志がくじけないで勇敢であること(毅)、質朴で飾りけのないこと(木)、〔心に思っていることはしっかりしているのだが、うまく言い表わせず〕口下手であること(訥)、〔この四者は〕それぞれ人の道(仁)に近い。』(P176)
私に完全に欠けているのは「訥」だろう。だが、ではその他の3つが完全に備わっているのかといえば、いくらか備わってはいても、とうてい完全とは言い難いのが、厳しいところである。
『子日く、徳有る者は、必ず言有り。言有る者は、必ずしも徳有らず。仁者は必ず勇有り。勇者必ずしも仁有らず。
老先生の教え。人格の立派な人物ならば、そのことばはきっと優れている。しかし、いいことを言う者は、必ずしも人格が立派ではない。人格者は、必ず勇気がある。しかし、勇敢な者は、必ずしも人格者ではない。』(P178~179)
まったくその通りであろう。だがここで問題とすべきは、そうした人たちを見る側に、それだけの読解力や正しい判定能力が、あるのか否か、なのではないだろうか。
「口ばっかり」の輩や「派手なパフォーマンスが売り」の輩が消えることはないし、むしろ、そっちの方が多いからである。
『子曰く、賢なるかな回や、一箪の食、一瓢の飲、陋巷に在り。人は其の憂いに堪えず。回や其の楽しみを改めず。賢なるかな回や。
老先生の評価。聡明である、顔回は。その食物はわずか、飲みものもわずか、そして貧乏な裏町暮らし。ふつうの人ならとてもそのつらさに堪えられない。ところが、顔回は、そこにある楽しみを改めない。〔その楽しみを知るとは〕聡明だな、顔回よ。』(P212)
先に書いた、最愛の弟子である「顔回」を誉めた言葉である。
肖像画などのイメージから、怖そうな人という印象を持たれがちの孔子だが、非常に情愛に満ちた、決して威張ったりはしない人だったというのが、こうした言葉から、よく伝わってくる。
なお、酒見賢一の小説『陋巷に在り』のタイトルは、この言葉から来ている。
陋巷に在りて、質素な生活をしながら、それでもなお叡智を求め、そんな生活に満足できるというような生き方ほど、強いものはないのではないだろうか。
私も少しは、そうなりたいものである。
(2023年12月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
