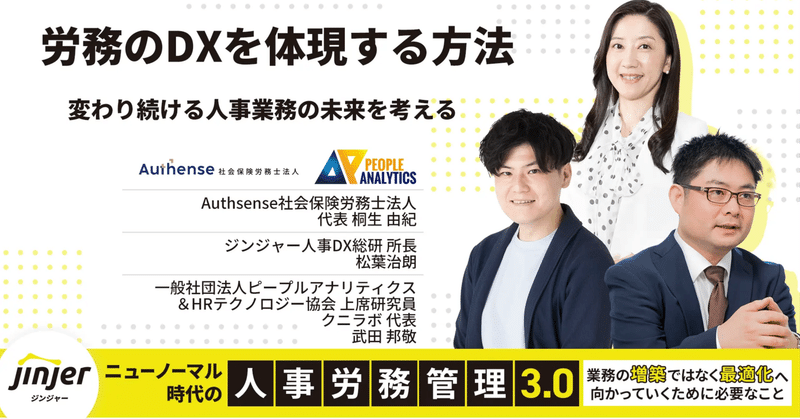新着の記事一覧

なぜ外国人採用が必要なのか?~人口減少の現実と企業の危機~Why do we need to hire foreigners?
日本の人口は減少の一途をたどっており、特に生産年齢人口(15~64歳)の減少は深刻です。このままでは、労働力不足によって経済活動が停滞し、企業の存続すら危ぶまれる可能性があります。 総務省の推計によると、2050年には日本の人口は約1億人まで減少し、生産年齢人口の割合は50%を下回ると予測されています。つまり、2人に1人が高齢者となり、労働力不足がさらに深刻化することが予想されます。 このような状況下で、企業が生き残るためには、新たな労働力の確保が不可欠です。その一つの解

2025年の海外人材ビジネス③これからの日本は外国人に選ばれるのか?
※本動画は2025年1月28日に開催したセミナーのアーカイブ動画となります。 今回は、外国人材活用の専門家である横山仁氏を講師にお迎えし、 現状の海外人材ビジネスについて詳しくお話しいただきます。 動画は3部構成となっていて、第3部となるこの動画では、 外国人材ビジネスの気になる点やこの先に日本が外国人材に選ばれるのかどうかについて、ディスカッションを行っています。 第1部と第2部を見てからこの動画を見ると、より理解が深まるかと思いますので、ぜひ下記からご視聴ください! 01:34 ネパールの方が 中東に行く理由は? 02:18 ドイツへ出稼ぎに 行く人は多い? 04:03 各国の労働者の送り出しスタンス・各国の政策で大きく左右されるフェーズなのか? 10:26 外国人労働者を急に増やした場合、日本の受け入れ体制は大丈夫? 15:25 日本に外国人は 来る?来ない? 18:08 日本の受け入れ体制を整えるために必要なことは? 19:09 民間企業が外国人材ビジネスを やる上で必要なことは? 21:17 ネパール人の出稼ぎ先

【社員インタビュー】元人事が新規事業立ち上げ!「社員の成長を叶える制度設計」を志すコンサルティング事業の裏側に迫る
1.人事のキャリアを積んだ10年、コンサルティング事業の立ち上げの背景とはーこれまでのご経歴を教えてください。 松島:前職は士業法人グループにて営業職としてキャリアをスタートしました。入社当時の社員数は10名程でしたが、翌年に初めて新卒採用を実施する際に採用プロジェクトに抜擢されたことがきっかけで、人事のキャリアがスタートしました。 最終的には、在籍していた5年間で合併等を経て150名程の組織へと成長しました。その過程で全グループの人事・採用・労務・人材開発に携わり、組織開