
蓮實重彦 『映画の神話学』 : 蓮實重彦論
蓮實重彦という人の「本質」をやっと理解できるようになったのは、英米文学研究者である中井亜佐子の著書『エドワード・サイード ある批評家の残響』で引用されていた、フランソワ・キュセの次のような言葉を読んだからだ。
中井の著書から当該言及部分を引用するが、「」で括られた部分が、キュセの著書からの引用である。
『サイードが批判する学問共同体の閉ざされたありかたは、いずれは学問を、共同体の内部においてのみ通用するゲームのようなものへと劣化させていくのだろう。それは、『フレンチ・セオリー』でキュセが皮肉たっぷりに描くことになる、卓越性競争のゲームだ。「こうした戦いに勝つためのただひとつの基本原則は〔……〕独創性を獲得することである」が、独創性の基準はけっして真理の発見でもなければ、公共善でもない。「そのための基準となるのは、ライバルとなる研究者を払いのけ、有名な同僚の主張を時代遅れのものにする能力、今ある研究分野のあり方から逸脱し、その分野においてこれまでほとんど使われてこなかったがゆえに最も効果的な概念を最小限の努力で見つけ出し、それを突きつける能力だけである」。』(P118~121)
ここでキュセの言う、学問共同体内部での『卓越性競争のゲーム』における『戦いに勝つためのただひとつの基本原則は〔……〕独創性を獲得することである」が、独創性の基準はけっして真理の発見でもなければ、公共善でもない。「そのための基準となるのは、ライバルとなる研究者を払いのけ、有名な同僚の主張を時代遅れのものにする能力、今ある研究分野のあり方から逸脱し、その分野においてこれまでほとんど使われてこなかったがゆえに最も効果的な概念を最小限の努力で見つけ出し、それを突きつける能力だけである』というのは、まさに蓮實重彦にピッタリの言葉だった。
「ああ、そうか。蓮實重彦の批評に感じる独特の臭気は、これだったのか」と気づかされたのだ。
蓮實重彦の著書をいくつか読んでみると、わかってくるのだが、蓮實の場合はいつでも、自分の主張を語る前に「他の奴らは、おおよそ全部ダメだ」式の前振りをする。
そして、そうした中から「叩きやすい人物」を何人かピックアップして、それを徹底的に叩いた上で、おもむろに自身の見解を語り、自分が「他と、どれほど違っているか」と、自身の「卓越性」を強調するのだ。
端的に言って、蓮實の「作品読解」そのものは、きわだって「すごい」というほどのものではなく、「そう来たか」という感じの「なかなかユニーク(面白い)」なもの、に止まることが多い。
ちょっと面白い「推理小説(ミステリ)」を読むような感じだ。
だが、自身のその見解を語る前に「これまでの当たり前の批評は、すべて制度的思考にとらわれた、凡庸なものだ」と、レトリックのかぎりを尽くして否定しているから、それらとは「違う」というだけで、蓮實の「ユニークな読解」は、単に「ユニーク」なだけではなく、極めて「例外的」かつ「かくあるべき読解」、のように見えてしまう。
喩えて言えば「名探偵による最終的な推理の前に、ボンクラ警部の推理をいくつも並べておく」ようなものだ。
つまり、蓮實重彦の読解というのは、「中身のユニークさ」そのものとして有難いのではなく、その「希少価値(例外性)」を自らアピールすることによって、特別な「アウラ」が与えられるという、一種の方法的な演出を伴ったものなのだ。
だから、蓮實重彦の批評が「他の人(批評家)たちのものとは違って、唯一正しい批評法によるもの」と言わんばかりの、蓮實自身の「アピール」を外して、それそのものとして見るならば、前述のとおりで、蓮實のそれは「際立ってすごい読解(見解)」ということには、残念ながらならない。
「派手な包装紙を剥がしてみると」というようなことになってしまうのだ。
例えば、『監督 小津安二郎』における蓮實重彦の「読解」とは、よくある「娘の結婚」とか「美しき昭和の記憶」みたいな一般的なものではなく、「不可視の階段」とか「女たちの宙に浮いた二階部屋」とかいった、他の人は思いつかない「ユニークな着眼点」から、作品の本質としての「構造」を取り出す、という形式のものである。
これは、映画作品を論じる場合に、ごく当たり前の「主題論」的な分析もあれば、蓮實ような「構造主義」的な分析もある、というような、言うなれば「多様な見方がある」という立場から見れば、蓮實の「作品分析」は、いろいろな「分析方法」がある中での「ユニークなひとつ」、ということで終わってしまう。

ところが、これも前述のとおりで、蓮實重彦の場合は、「主題論」的な分析なんてものは「制度的思考にとらわれた紋切り型(の一種)」でしかなく、「映像作品としての映画」というものの本質を捉えていないと、そう本質的に否定してしまう。
つまり、「いろんな見方がある」とは、認めておらず、「たいがいのものは、制度にとらわれた見方でしかない」からダメだ、という立場なのだ。
したがって、蓮實の、俗に言う「表層批評」というのは、単なる「一つの立場」ではなく「唯一の正しい立場(からの批評実践)」であるという意味合いが、暗に与えられている。そうと断言まではしないものの、実質的にはそう語っており、そんな印象を読者にハッキリと植えつけるものになっているのだ。
だからこそ、蓮實重彦のやり方だけが、「特別なもの」のように見えて(見せられて)しまう、のである。
で、これは何なのかと言えば、くり返しになるが、所詮はキュセの言った、
『ライバルとなる研究者を払いのけ、有名な同僚の主張を時代遅れのものにする能力、今ある研究分野のあり方から逸脱し、その分野においてこれまでほとんど使われてこなかったがゆえに最も効果的な概念を最小限の努力で見つけ出し、それを突きつける能力』
ということになる。
まさにこれが、蓮實重彦のやり口なのだ。
○ ○ ○
さて、蓮實重彦の「映画論」書としては、1冊目となる本書『映画の神話学』(1979年初刊)も、まさにそうした『ライバルとなる研究者を払いのけ、有名な同僚の主張を時代遅れのものにする能力、今ある研究分野のあり方から逸脱し、その分野においてこれまでほとんど使われてこなかったがゆえに最も効果的な概念を最小限の努力で見つけ出し、それを突きつける能力』を、存分に見せつけた著作となっている。
「栴檀は双葉より芳し」ということなのであろう。

蓮實重彦の初期著書の特徴と言っても良いと思うのだが、本書なども、特に冒頭部分は「殊更に晦渋な文体」で書かれている。
まるで「この本は、頭の悪い奴ではついていけないぞ」と「カマしている」ような書き方なのだ。
だが、心配はご無用。こうした「晦渋な文章」が、1冊丸ごと続くわけではないので、そこを我慢して乗り切れば、あとは比較的「常識的な文章」になっているから、冒頭部分は理解できなくても、後の大半は理解できるようになっているのである。
では、蓮實重彦は、どうしてこんな「面倒くさい」書き方をするのかというと、それは、平たく言えば「鬼面人を脅す」というやつだろう。「私はこんなにすごいんだぞ」というのを、最初に「一発カマしておく」という手法(カウンターパンチ)である。
なぜ、そんなハッタリめいたことをするのかと言えば、それは、これをやっておけば、その後で、どんな「決めつけ」めいたことを書いたところで、冒頭の「難解な文章」の意味を十分に読み取れなかった多くの読者は「きっと蓮實さんは、何か深い根拠に基づいて、こんなふうな断言をしているんだろう」と、そう勝手に「深読み」してくれるからである。
しかし、「深そうな文章」というのは、必ずしも「正しいこと」を正確に語っているものだとは限らない。
例えば、私が趣味で研究している「キリスト教」もそうで、「神学書」なんてものには、一読きわめて「難解」あるいは「意味不明」なものが大半だ。
だが、「神学」というものの意味(本質)を知らない読者だと、それを「何やら深いことが書かれているようだぞ(私には理解できないけど)」と、そういう「誤った深読み」をしてしまいがちである。
だが、それは多くの場合「深いから理解が困難」なのではなく、単に「特殊な前提に立った議論=非常識な前提に立った議論」だから、「常識」では理解できないだけ、なのだ。
この「キリスト教神学」というのは、実は「神の存否」から探究をはじめる「学問(客観的学問)」などではなく、「神は実在する」という「主観(信仰)」を前提として、我が宗派の「ありがたみ」を理屈づけるための、御用学問なのだ(神学・教学というのは、どんな宗教でも、そういうもの)。
だからその意味で客観的に見れば、「クトゥルフの神々は存在する」という前提で語られた、H・P・ラヴクラフトらによる「クトゥルフ神話」と、完全に同等の「フィクション」にすぎない。
しかしながら、それなのにそれを「この世の真理」だと大真面目に語り、また、それを本気で信じこむ信者が大勢いるものだから、そんな「信仰を持たない人にはわからなくて当然の、非合理な決めつけ」が、努力すれば知解可能なものであるかのように誤解させられ、「難しく、さっぱりわからない」という、微妙にズレた理解になってしまう。
「論理的に理解しうるものが、理解できない」というわけではなく、「非論理的なものだから、論理的に理解できるわけがないだけ」のものが、曖昧に混同されてしまうのだ。
「イエス・キリストは、完全なる神であると同時に、完全な人間でもある」などと言われても、そんなもの、「排中律」なんて難しい言葉を持ち出すまでもなく、「非論理的なので理解不能」のひと言で片づくものなのだ(世界のすべてを一瞬に洞察できる人間なんて、人間ではない、ということ)。
要は、それは、合理的には理解不能な、単なる「屁理屈(欺瞞的レトリック)」でしかなく、決して「深いから理解できない」というようなものではないのである。
一一で、蓮實重彦の「特別性=反制度性」というのも、この類いのものなのだ。
本書『映画の神話学』では、文化人類学者の山口昌男が槍玉に挙げられ、「頽廃者」の象徴的な人物として、文字どおりボロクソに貶されているのだが、これもキュセの言う『ライバルとなる研究者を払いのけ、有名な同僚の主張を時代遅れのものにする能力』の、わかりやすい発露に他ならない。
山口昌男の「中心と終焉」理論だとか「道化=トリックスター」理論だとかいうのは、当初は、「目から鱗」の抜群に面白い理論だったし、私も山口がとても好きだったのだが、しかしそれで人気が出て「知識人としての地位」を得てしまうと、もう誰も悪いことは言わなくなったせいなのか、山口は、何を扱っても、みんな「そのパターン」で論じてしまう(切ってしまう)という、好ましくない状態に陥ってしまった。まさに理論が「紋切り型」化してしまい、ファンの私でも「またこれか」という感じになってしまったのだ。
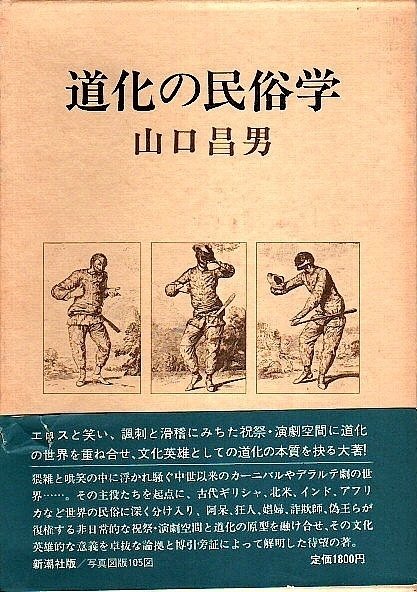
要は、多くの人たちから、本音では飽きられ始めていたのだが、しかし山口昌男という人は、自身「反権威のトリックスター」たらんとしたような、決して威張らない、いかにも「好人物のおじさん」だったから、かえって周囲の人も「もう少し、新しいことを言った方が良い。みんな飽きてますよ」などという注文もつけにくかったのでもあろう。
一一だが、そんな「空気」に目をつけたのが、蓮實重彦だったのだ。
本書で蓮實から批判されているように、たしかに山口昌男の映画『カッコーの巣の上で』論なんかは、まさに「またこれか」であり、それに比べれば、蓮實重彦の「円形と矩形」という着眼点からの分析というのは、「意外性」があって面白い。
小津安二郎を「不可視の階段」から論じたのと同様の「ユニークな着眼点」であり、悪く言えば「奇を衒った議論」でしかなかったのだが、山口昌男のそれがあまりにも凡庸退屈なものだったため、その比較から、蓮實重彦のそれは、実際以上に素晴らしいものに見えてしまうように、本書は出来ているのだ。
実際、山口を批判する前段で語られる、蓮實の『サイコ』(A・ヒッチコック)論における「円形・穴・螺旋」のこれでもかという強調は、客観的に見て、かなり「こじ付け」がましいものだ。

『もはや改めて指摘するまでもあるまい。こうした作品(※ 『めまい』『サイコ』など、ヒッチコックの強迫神経症的な作品)にあって重要なのは、高所恐怖症とかエディプス・コンプレックスといった、いかにもアメリカ文明にふさわしい心理的要因ではなく、円環的主題を介して触知可能となるヒチコックの映画的思考の、その豊かな多義的な統一性である。日常的世界にあってはいかなる類似をも示さない演奏会場と、メリー・ゴーラウンドと、教会の鐘楼と、回転椅子とが、その表情の異質性にもかかわらず同じ一つのイメージに融合しあってしまう現象が殊のほか刺激的なのだ。』(P163)
『もはや改めて指摘するまでもあるまい。』とか『殊のほか刺激的なのだ。』といった、この「断定」口調が、クセモノである。
読者が皆そう思っているとは限らないのに、こう確信ありげに「断定」することで、「そうでしょうか?」といった異論を挟みにくくさせるという、詐欺によくある手口と同じなのだ。
「大丈夫ですよ。私に任せてください!」「そうに決まってますよ。他に何があると言うんです」一一こんな言葉にまんまと乗せられたあげく、裏切られる人が山ほどいるのである。
『このとき、円環の主題があからさまに顕在化する。事実、床に倒れた女の足もとでは、第七の穴にほかならぬ丸い排水孔に渦巻いている水が次第に血に染まってゆくのである。螺旋の主題と穴の主題との結合が、ここでヒチコック的曲線の至上形態に達していることは誰の目にも明らかだからである。接近するカメラは排水孔を大写しで捉え、もはや水の流れを止めうる存在がこの空間に見出しえないことを、黒みを帯びた排水の渦巻きによって強調する。次のショットは、実際、眼を開いたまま死んだ女の顔の、その開かれた瞳孔のクローズ・アップである。死体は算をタイルにおしつけて倒れているので、カメラが後退して顔全体を視界におさめても、人が目にするのは片方の眼球が焦点も結ばぬ視線をむなしく漂わせている光景ばかりである。鼻孔も、耳の穴も、片側しか見えてはいない。すべては、対をなすべきいま一つの穴を奪われたまま、孤独にその黒い窪みを視線にさらしている。つまりは瞳孔と、鼻と、耳とで合計十個の穴が、ここに姿を見せているということになる。これが、円環の氾濫でなくて何であろう。つまりこの場面は、流れる血が螺旋状の運動を描き、瞳はもはや節穴にすぎず、開かれたままの唇からもはや声が洩れることのなくなった瞬間に終りをつげる円環のエロチスムの戯れなのである。円環的思考に触発されぬかぎり、ここにはいかなる映画的な事件も起りはしなかったわけだ。』(P166〜167)
『円環の主題があからさまに顕在化する。』とか『ここでヒチコック的曲線の至上形態に達していることは誰の目にも明らか』とか言うけれども、一一「そうかねえ? そこまで断定できることですかねえ?」と、そう、一歩退いて疑ってみることこそ、批評的精神であろう。
これは、シャワールームで女性がナイフで殺害されるという『サイコ』の有名なシーンについての「解釈」なのだが、この映画に限らず、シャワールームでの裸の女性が写されているのなら、「円形」や「円環」的なものがたくさん映るのは、当然のことなのではないだろうか。
だが見てのとおり、そんなありふれたことでも、蓮實重彦のレトリックにかかれば、何やら、すごい「大発見」のように思わされてしまうのだから、それはまあ大したものである。
だが一方、こうした「ヒッチコック」論に無理があるのは、蓮實自身も気づいているから、そちらへの手当ても、抜かりはない。
『ここ(※ ヒッチコックの『裏窓』)には、円環の主題は豊かに氾濫してはいない。唯一無二の特権的円環たる望遠レンズがあるばかりだ。逆に、横長の矩形は、向いの壁の無数の窓として壁の表層を埋めつくしている。』(P 173)
つまり、ヒッチコックのすべての作品で「円形・円環の主題」が明らかなわけではなく、『裏窓』のように「矩形」が主体である場合だってあるというのは認めるのだが、その中に「カメラのレンズ」の「円形」を見出し、そこを強調することで「この作品も」そうだと、強弁するのだ。
しかし、「円形(円環)」と「矩形」のどちらかが見つかる(頻出する)というのなら、都会を舞台にした作品なら、ヒッチコックの作品ではなくとも、いくらだって見つかるというのは自明な事実であろう。
また、こういう蓮實重彦的な「着眼点の面白さ」とは、じつのところ、その「例外」を意図的に隠蔽したところでの、大胆不敵な「断定的強調」にすぎない。
例えば前述の「小津安二郎論」における「不可視の階段」だって、ちゃんと真正面から階段の写っている作品もいくつかあるし、その二階も女たちの部屋になっているから、「女たちの宙に浮いた二階部屋」ということにはならない。階段が写ってないからこそ、ニ階は、階下とは切断されて、まるで「宙に浮いている」とようだという、蓮實流の「面白い」話にもなるのだが、「例外」の合理的な説明が為されてはいない。
これは。都合の良い事例しか語らないという、いかにも胡散臭いレトリックなのである。
つまり、「主題論」的な批評を「制度的で凡庸」だとあらかじめ否定し、その上で「見逃されている」のは、「事物」だの「形態」だの「運動」だのだと強調した後で、「円形と矩形」などという、普通はあまり注目されないところを指摘するから、殊更に「凄そうに聞こえる」だけなのだ。
要は「他を貶すことで、相対的に自分を立派に見せる」という、一種の「(裏返された)自画自賛」なのである。
そして、そんなやり方で、「映画はこのように見なければならない」と暗に主張し、それが出来ない人は「制度的な思考」にとらわれ、それに安住している『頽廃者』だと否定してみせる。もちろん、蓮實重彦自身は「頽廃」に抗っている少数例外者、というわけだ(これも自画自賛)。
そんなわけで、蓮實が評価したくない『カッコーの巣の上で』に、感動したり、面白かったと評価した人は「頽廃者」であり、その代表が、あのダメダメな山口昌男だと、そうくるわけだ。「あなたも、山口昌男と同様の、知的頽廃者じゃないですか?」と、暗に「脅迫」しているのである。
「そう思われたくなければ、私の批評方法を支持しなさい」と。

『これはごくあたり前なことだが、われわれは、映画について何でも語ることができる。その政治的な側面、社会学的な側面、神話学的な側面、美学的な側面など、これまでいやというほど語られてきたし、その記号学的な側面とやらも、いまや理論的言説の対象たりはじめてさえいる。それはそれで結構なことだと思うし、映画自身のために、またわれわれ自身のために、もっと盛んであったらいいとさえ感じられる。だが、そうした諸々の言説の担い手たちは、みずからの発語がいかにして可能であったかについてはいたって無頓着である。どんな種類の体験に操作されつつ自分が筆を執るのか。そしてその筆から滑りでる言葉が、何を反芻しているのか。そうした点に誰も心を向けようとはしない。むつかしい話はやめようではないか。はじめに感動があったのだから、自分はそれにどこまでも固執する、とある人はいう。わかり切った話はやめようではないか。われわれが捉われているブルジョワ的資本主義体制の生産と消費の必然的な関係の中で、フィルムとの遭遇があったにすぎないと、またある人はいう。それはそれでいいかも知れない。感動から始めることは決して悪いことではないし、映画の制度的側面に触れることも決して悪いことではなかろう。だが、感動だ感動だと口にしながら、その感動そのものがきわめて制度的に操作され、制度によって深く汚染され、結局のところはあの感動もこの感動も似たりよったりの言葉しか生み落さなくなっているのに無感覚だという点で、感動から綴られる映画的言説はいささかも現実的ではない。また、制度を口にしながら、その制度が、映画から視線が蒙る刺激に無傷であり続け、フィルムとの遭遇が制度を変容する契機をいささかもはらんではいないと高を括っているという意味で、制度的必然から出発する映画的言説もまた現実的ではない。つまりは、感動が大いなる自由を可能にすると信ずることは、制度がすべてを不自由にすると信ずることと同様に、抽象的思考を露呈するほかはないということだ。実はここで改めて指摘するまでもなくその事実の抽象性など誰もが知っているのだから、今日あたりに氾濫している映画的言説のほとんどは、感動と制度に引き裂かれたまま事態を曖味にやりすごすための自己の醜悪な正当化にすぎなくなっている。いや、それが自分自身を躍起になって正当化せんと試みているならともかく、大部分の映画的言説はいとも無邪気で善意にみちた身振りによって無償の饒舌を煽りたて、ただただあっけらかんとしたやり方で醜悪さから目をそらそうとする。その無意識の隠蔽作業が、あたりに頽廃の渦を捲きたててゆく。そして奇妙なことに、感動も制度も、ともにこの頽廃者たちの言説によって支えられているのだ。彼らは、見えてはいないはずの領域を見えたと思い、記憶されてはいないはずの体験を思い出しつつあると信じ込みうる資質をそなえており、その便利な資質に授けられて、感動と制度のあいだにいかにもそれらしい橋を架ける。頽廃者たちが捏造するこの架橋するこの虚構の橋こそが、今日的な映画をめぐる言説の真の姿にほかならない。抽象を最も貴重な具体性ととり違えるこの感動的にして制度的な身振りはどうであろうか。彼らにとっては、われわれの日常的なフィルム体験などは、ことによったら回避しえたかもしれぬ錯誤として虚構化され、円環と矩形との葛藤などは、途方もない抽象だとして捨象さるべきものであるに違いない。プロジェクターのランプの球体性も、スクリーンの長方形の壁面性も、おそらくは技術的な要請にほかならぬとして廃棄さるべき偶然にすぎないのだろう。そして映画が、しばしばそのいかにも神経過敏な表層に、自分自身を成立せしめる生の条件を痛々しく刻みつけようとする試みを、たんなる修辞学的な虚飾として遠ざけてしまうに違いない。かくして、アルフレッド・ヒチコックが、倫理もなく、思想もなく、心情もなく、ただ説話技法にたけただけのサスペンス・フィルム作家におとしめられる条件がそろったというわけだ。』(P175〜177)
『それはそれで結構なことだと思うし、映画自身のために、またわれわれ自身のために、もっと盛んであったらいいとさえ感じられる。だが』
『映画の制度的側面に触れることも決して悪いことではなかろう。だが』
一一この「持ち上げてから落とす」というのは、悪口の基本である。
『これはごくあたり前なことだが、われわれは、映画について何でも語ることができる。その政治的な側面、社会学的な側面、神話学的な側面、美学的な側面など、これまでいやというほど語られてきたし、その記号学的な側面とやらも』大いに結構だろう。
けれども、それは『いとも無邪気で善意にみちた身振りによって無償の饒舌を煽りたて、ただただあっけらかんとしたやり方で醜悪さから目をそらそうとする。その(※ 頽廃者による)無意識の隠蔽作業が、あたりに頽廃の渦を捲きたててゆく』作業でしかないと、そう言っているのだ。
一一つまり、私のやり方以外は、みんな「制度にとらわれた頽廃者のものでしかない」と言っているのである。
『感動と制度に引き裂かれた無邪気な頽廃者たちにとって(※ 『カッコーの巣の上で』)は、抗いがたい魅力にみちた作品だといえるであろう。つまるところ、それが恥しいまでに、現在に酷似している故に肯定されてしまう現在として、あまたの頽廃者たちに記号と意味との調和ある共存を保証し、世界に向かって開かれるべき瞳を甘美な休憩へと導くにふさわしい作品がここにあるのだ。』(P180)
『カッコー』に感動する人は「頽廃者」であり、当然、蓮實重彦自身は「そうではない」ということである。
他にも、こんな「貶し方」もある。
『映画なるものが語のあらゆる意味あいで積極的ないかがわしさを身にまとうとしたら、「作品」と呼ばれるフィルム断片は、そのいかがわさを全的に肯定する荒唐無稽な反記号にほかならない。ところで、山口昌男がその深い愛情を隠そうとはしないロシアのアヴァンギャルドやチェコの構造論的美学者たちは、少なくとも「作品」の荒唐無稽ぶりに改めて驚いてみせる生真面目さを持っていたという意味で鋭い感性をそなえてはいたが、その驚きを、再び形而上学的=神学的な思考で解消し、差異と同一性を操作しつつ荒唐無稽を馴致しうると確信したが故に、また滑稽な身振りを演じてしまいもした連中であろう。「作品」に対しての卑小な知的頽廃の敗北を認め、彼らは壮大な知的頽廃、つまりは科学の確立を目指したのである。この生真面目な滑稽さはわれわれにとってきわめて貴重である。現代フランスの大かたの記号論者や、その日本的追従者が絶望的に貧しいのは、彼らがこの生真面目な滑稽さと無縁の地点で、あの卑小なる知的頽廃に加担しながらその事実に無自覚だからにほかならぬ。山口昌男がフォルマリストや構造論的美学者から継承したのが、ほかならぬ生真面目な滑稽さであった点は、われわれをほっとさせてくれる数いたと救いだといえる。』(P203)
ここでは『抽象的』あるいは『形而上学的=神学的な思考』が、否定的なものとして語られているが、どういう意味かと言うと、一般的な「制度的思考」というのは、「現実を見ていない」と、そう言っているのだ。言い換えれば、蓮實自身の対象の見方は「具体的」であり「現実的」であり「非制度的」だという、「自己申告」である。
要は、自分は、映画でも文学でも、その「表層」をしっかりも直視して評価しており、「意味」という思考の制度にとらわれたりはしていないと、そう言いたいのだ。
一一だが、この自己申告を、どれだけの人が素直に呑み込めるだろうか?
つまり、普通に読んで「不必要に抽象的」であったり「思わせぶりに難解」であったりするのは、むしろ蓮實重彦の文章の方だと感じられるのではないだろうか。
したがって、真に「いかがわしい」のは、映画ではなくて、映画を「いかがわしい」ものにしておきたい、蓮實重彦ご当人の方なのである。
例えば上の引用部分では、山口昌男に絡めて、山口が影響を受けた学者たちも、ひとまとめに「なで斬り」である。
だが、この雑な批判は、いかにも自己喧伝的なパフォーマンスにすぎなかろう。
いったい、蓮實重彦は、自分がどれほど「世界的に偉大な批評家」だと思っているのだろうか?
『「作品」を、その自己同一性から解放しているかに見えるからである。作家と呼ばれる主観的個体ではなく、任意の匿名的個体が投影されうる場としての「作品」とは、いわば「作品の芸術的構造全体が集約される点」、「構造がそこへと向って整えられる点」を前提とせざるをえない、とムカジョフスキーはいう。だが問題は、まさにこの構造的集約点という概念によって、新たな排除と選別の身振りが、より高次の水準で誇らしげに介入せぎるをえないという点である。』(P204)
要は、ムカジョフスキーが『「作品」を、その自己同一性から解放しているかに見える』けれども、結局はその『構造的集約点という概念』によって、『新たな排除と選別』をやらかしてしまっている。だから、そういう理論化は、新たな、よりタチの悪い「制度」の産出でしかない、と言っているのだ。
で、ここまで周囲を、大雑把になで斬りにしておきながら『思考の卑小な頽廃ぶりの実態を暴露することに貢したとはいえ、費された知的=感性的な緊張のわりにはあまりに酬われることの少なかった試みの徒労感、不条理な痛みの感覚ばかり』だなどと、わざとらしく嘆いて、己の「自己犠牲」ぶりを大袈裟にアピールし、その後、それでも、やるべきことをやったのだと、次のとおり、またもや自賛するのである。
『いずれにせよ、いまわれわれの内部に沈殿してゆくものは、それで思考の卑小な退廃ぶりの実態を暴露することに貢したとはいえ、費された知的=感性的な緊張のわりにはあまりに酬われることの少なかった試みの徒労感、不条理な痛みの感覚ばかりである。まるで、自分自身を徐々に失ってゆくかのごときその崩壊感は、できればユングやプーレやパノフスキー、あるいはその他諸々の知的ディスクールが棲まうあの形而上学的=神学的時空へと逃れ、フィルム体験があったことなど錯覚にすぎぬと自分にいい聞かせながら、円環や球体や矩形や立方体の口から洩れるとめどのない饒舌を、差異と同一性による思考に従属させえたならばどんなによかったろうとさえ思う。あの晴れやかな知の視線空間に参列し、一瞬見失なわれたかにみえる自分自身をより確かなものに鍛えあげる遊戯に身をゆだねておけば、肉体の酷使が、むなしい徒労感とは別の、すぐれて教育的な努力として正当化されもするだろう。かくして人は、疲労感と崩壊意識とを、生命の犯す一時的な、だが有効な錯誤として忘却しうる権利を獲得するだろう。
だが、生は、疲労感や崩壊意識を排除せんとするその種の正当化作業を、抽象のみに可能な遊戯だとして認めようとはしまい。重要なのは、この疲労と崩壊とがもたらす存在の希薄化を、まごうことなき現実として肯定することの中に生がその基盤をさぐりあてるという事実である。疲労したが故に存在が口にしてしまう嘘言、崩壊が存在を陥れる自家撞着、そうしたものが存在とは似ても似つかぬ仮面を次から次へと捏造しはじめ、無限に捏造された仮面の多様な表情に対応しきれなくなった存在が、その自己同一性を放棄して、瀕死の自分のいかがわしさをいかがわしさとしてうけいれざるをえなくなった瞬間に、その存在の希薄さに見あった映画のいかがわしさが、もはや自分自身もなく、また認識すべき対象の影も薄れ、確かなものは球体と四角の壁面しか残ってはいない空間に、仮死の祭典を準備することになるのだ。』(P219〜220)
これが、例の『ライバルとなる研究者を払いのけ、有名な同僚の主張を時代遅れのものにする能力、今ある研究分野のあり方から逸脱し、その分野においてこれまでほとんど使われてこなかったがゆえに最も効果的な概念を最小限の努力で見つけ出し、それを突きつける能力』なのだ。
「私だけが体を張って抵抗しています」という自家宣伝である。
ここまで具体的な説明すれば、蓮實重彦の「やり口」が、はっきりと見えてきたはずだ。
しかしながら、真の問題は、蓮實重彦の、いわゆる「表層批評」もまた、蓮實自身が批判した、「より巧妙な制度」の一種でしかない、という事実なのだ。
文学作品であれ映画であれ、「意味論」的な批評などではなく、作品の表面に(現に)見えている部分に真摯に向き合うべきだと、蓮實が主張するのは、「意味論」的な読み方というのは、古い文学的な「思考の制度」のよるものだから「そんなもんではダメだ」ということなのだが、問題は、だからと言って、そういう読みの立場(制度)が、否定廃棄してしまえるものなのか、という問題である。
この点については、別のレビューに書いているので、ここではそれを引用して済ませよう。
『しかしながら、本当の問題は、「通俗で何が悪い」ということなのだ。
だが、「通俗映画の良し悪し」がわからない「映画マニア」もまた、決して少なくはないのである。
前述の「偽伯爵」蓮實重彦も、決して「通俗映画」を否定しているわけではない。
というか、蓮實重彦という人の映画に対する評価の基準は、世間一般が考えるような「通俗性(娯楽性)」の有無といったところには無くて、いかにも「フランス現代思想」の影響を受けた「構造主義」者らしく、映画作品を、その「映像」に表れたところから構造分析して、それがいかに「ありきたりなもの(制度的なもの)ではないか=制度的な思考に捉われていないか」という点で評価する。
だから、所詮は「交換可能な表看板」にすぎない「物語」や「テーマ」など、重視しない。つまり、「物語」的に「通俗的か否か」などということは、問題にはならないのである(例えば、小津安二郎の作品を、「娘の結婚」とか「昭和」といった制度化された観点から評価するのではなく、「不可視の階段」「女たちの宙に浮いた二階部屋」とかいった独自な着眼点から、その作品構造を取り出してみせる)。
で、キャプラの場合、この「映像」面では特に見るべきものがなく、「スクリューボール・コメディ」という評言からも分かるとおりで、彼の売りは「セリフ(のやりとりの面白さ)」であり「ストーリー展開(の面白さ)」なのだ。
だから、蓮實重彦に言わせれば、彼の作風は、どっぷりと制度的な思考(物語という制度)に浸りきった、映画本来の魅力を知らない、通俗(制度的な)映画だということになるのである。
蓮實重彦に言われるまでもなく、「制度」的であるのは、たしかに「つまらない」ことだ。だから、「制度」的思考にベッタリと安住したような作品は、パターンで映画を見ることしかできない者以外には、退屈極まりない作品だとは言えるだろう。
一一けれども、そもそも人間は、「制度」から完全に逃れることはできないのだという事実も、決して忘れてはならない。
例えば、「制度に捉われてはいけない」という発想もまた、ある種の「制度」なのだ。「反制度」としての「制度(化された物語)」であるからこそ、その主張は、人を惹きつけもするのである(また、人間の思考とは、そもそも、人間中心主義の制度に他ならない)。
だから、私たちに必要なのは、拒絶し切れない「制度」を自覚しつつ、それに完全に絡め取られることなく、適度に「制度」を楽しむ(泳ぐ)、という「見極めの聡明さ」なのである。
例えば、私たちは普通、「生物という制度」の中にあって「種の保存」という「制度としての本能」に捉われている。
つまり、好むと好まざるとにかかわりなく「性欲」を持っているし、そのために発情(恋愛)もすれば結婚もし、ほとんど勢いだけで子供を作ってしまう者も、決して少なくはない。
無論、「偽伯爵」だって、そんな「ご身分」には関わりなく、当たり前の人として発情し、子供をなしているのだが、しかし私は、それを「制度の奴隷」だなどと、非難したりはしない。
なぜなら、それは、生物として必要な制度に、必要なだけ従っているにすぎないからだ。
道行く男女を、相手かまわずに強姦してまわるのとは、わけが違うのである。
だから、「通俗娯楽映画」も、それがそれだとわかった上で、節度をもって楽しむ分には何も問題はないし、それこそが正しい娯楽作品の鑑賞法なのである。
むしろ「映画は、通俗娯楽ではない」という「芸術至上主義」に捉われることこそ、「芸術至上主義」という「制度」、つまり「エリート指向」という「猿山の親分になりたがる」という「生物学的な制度」に、無自覚に捉われているにすぎない、とも言えるのだ。
だから、キャプラのヒューマニズムの限界を理解しつつ、しかし彼のヒューマニズムの「肯定的」側面を肯定して、それを楽しみ、そこから学ぶのは、決して悪いことではない。
すべての人に対し「漫画なんか読まずに、ドストエフスキーを読め」と言うような人は、端的に言って馬鹿である。
ある時は漫画を楽しみ、別のある時はドストエフスキーも楽しめると言うのが、真に知的なのだ。知性に相応の「幅と余裕がある」ということだからである。
だから、「通俗娯楽」という、ごく当たり前の「制度」に対する受け入れを、自意識過剰なまでに拒否して、それで自分が「非凡人」にでもなったつもりの「勘違い=制度」に捉われると、蓮實重彦のような、賢いけれども、人間として歪んだ、偏頗な人間になってしまう。「伯爵」と呼ぶには、あまりに下卑ているから、「偽伯爵」と名乗らざるを得ないのだ。
したがって、この自称は、謙遜などではなく、さすがは蓮實重彦、自分の「いかがわしさ」くらいは自覚して、それに太々しく開き直ってみせている、ということになるのである。』
つまり、蓮實重彦は、人のやり方を「制度」にとらわれたものであり、そんなのではダメだと否定し、「制度」化を避けるものとして、「仮死の祭典」としての映画・批評こそが必要なのだと、そんなわかったようなわからないようなことを言っているが、これこそが、典型的に「神学」的な物言いなのである。
いかにも「何やら凄そうなことを言ってる」みたいな、レトリックなのだが、だからこそ蓮實は、この肝心かなめの部分は、決して「平易に語る」ことはできない。
なぜなら、簡単に説明してしまったら、それはごく当たり前のつまらない話でしかなく、「そういう考え方もありますよね」と、あっさり身をかわされてしまうのは、目に見えているからなのだ。
「神学者」に対し「理屈は良いから、神がいると言うのなら、ここへ呼んでくださいよ。お会いさせてください」と要求しても、決して会わせてはくれないように、蓮實重彦に「映画だが映画批評だかが、仮死の祭典だとかおっしゃいますけど、それは単なる、洒落た比喩ですよね。そうじゃないのなら、もっと具体的に説明してください」と要求しても、そもそも大して具体性なんて無い「枯れ尾花」なんだから、これですといって、見せるわけにはいかないのである。
で、どうして私が、こんな身も蓋もない断言をできるのかと言えば、それは、「制度」的な思考がけしからんだの、「排除と選別」がけしからんだのと、いかにもご立派なことを言っていた人の成れの果てが、かの「三島由紀夫賞授賞式での、迷惑スピーチ」に示された、隠しようもない「蓮實重彦自身の並外れた頽廃ぶり」だったのであり、そんな「動かぬ証拠」があったからである。

この「迷惑スピーチ」の問題についても、すでに前のレビューに書いているので、それを引用させてもらう。
『(※ フランク・キャプラの映画に代表される)「通俗娯楽」という、ごく当たり前の「制度」に対する受け入れを、自意識過剰なまでに拒否して、それで自分が「非凡人」にでもなったつもりの「勘違い=制度」に捉われると、蓮實重彦のような、賢いけれども、人間として歪んだ、偏頗な人間になってしまう。「伯爵」と呼ぶには、あまりに下卑ているから、「偽伯爵」と名乗らざるを得ないのだ。
したがって、この自称は、謙遜などではなく、さすがは蓮實重彦、自分の「いかがわしさ」くらいは自覚して、それに太々しく開き直ってみせている、ということになるのである。
そして、そうした「太々しい開き直り」からくる行動の、象徴的かつ代表的な事例が、彼の小説『伯爵夫人』が「三島由紀夫賞」を受賞した際の、授賞式での「こんな賞など迷惑だ」という、いちぶに物議を醸した、あのスピーチである。
この「迷惑」スピーチの問題点は「迷惑なら、賞を受けなければよかっただけ(なのに、なぜ、わざわざ受けたのか)」という「事実の不整合(自己矛盾)」性にある。
と言うのも、この手の文学賞というのは、否応なく一方的に与えられる(押しつけられる)ものではなく、事前に「候補者」に対して「受賞者に選ばれたら、賞を受けていただけますか?」という打診があり、それにOKした者だけが、受賞するものなのである。
なにしろ、賞を与えると公表してから、その相手を断られたのでは、賞の沽券にかかわるし、それまでの受賞者のメンツにも関わるからだ。
したがって、公式の受賞者というのは、実は「二番手三番手の候補だった」という可能性だって、ないわけではない。まあ、今は、賞コジキ・勲章コジキばかりだから、そうした事態は想定しにくいが、かつては、現に賞を拒否(固辞)した人も、少数ではあれ、いるにはいたのだ。だからこそ、「事前の打診」が必ずなされるようにもなったのである。
したがって、蓮實重彦の場合も、必ず事前の打診があって、その際には「賞を受ける」と回答していたはずなのに、いざ授賞式に出てくると「迷惑だ」とスピーチした、ということになる。
したがってこれが、「賞の勧進元」に対する「仁義を欠く、裏切りによる騙し討ち」だというのは、論を待たない事実なのである。
では、蓮實重彦なぜ、こんなことをしたのかと言えば、それはたぶん「賞」という「制度」の権威を失墜させるためだ。
「賞なんてものは、業界を盛り上げるための、お手盛りのイベントにすぎない」と、そう批判するために「俺はこんなものをありがたがるほど、田舎者じゃないよ」と、そうアピールしたのである。
実際、蓮實は、映画の方で、アカデミー賞をはじめとした各種の映画賞を、何度も嘲って見せている。当然、文学賞だって、基本的には同じことなのだ。
で、私自身も、「賞なんてものは、作品鑑賞能力のない一般人向けの、業界あげての販促活動にすぎない」と思っている。
事実「芥川賞や直木賞受賞作をありがたがるような奴は、読書の素人である」と、何度も公言している。
だから、「賞」を批判するのは大いにけっこうなのだが、問題は、蓮實重彦の「やりくち」なのだ。
いくら「正しい目的のため」とは言え、蓮實のやりくちは、明らかに、人としての仁義を欠いて、非倫理的なものだ。
やはり、批判するにしても、やり方というものがあろう。
ではなぜ、蓮實重彦ほどの大の大人が、こんな、一種の「テロ」行為に走ったのかいえば、それは「賞」という堅牢な「制度」に痛打を与えるには、外からいくら批判しても効果がないと、それがよくわかっていたからである。
つまり、私みたいに、初めから「賞なんてくだらない」と言っていると、当然のことながら「賞」の対象にはならない。仮に、何か立派なものを書けたとしても、だ。
で、そんな、「賞」に縁もゆかりもない者が「賞なんてくだらない」と言ったところで、普通は「負け惜しみ」だとしか思われないから、その批判は、まったく効力を持たないのである。
だから、蓮實重彦は、「賞」などくだらないと考えてはいても、「賞」を受けることで自分に「箔」がついて、同じことを言っても「説得力」を持つようになるという事実は承知していたから、これまでは、ありがたく、いくつも「賞」を受けてきたのである。
そして、その結果として「東大総長」にまで成り上がり、彼の本を読んだことのない人でも、「それはそれは」と感心してもらえる立場に立ち得たのだ。この上ない「箔が付いた」のである。
だから、蓮實重彦の場合は、もう「賞」なんて、いらなくなったのだ。
いらなくなったからこそ、今度は「賞なんてくだらない」と、人が言えないことを言うことで、さらに自分に「箔」をつけようと考えたのである。人より「もう一段上の箔付け」というわけだ(メタレベルの「箔」というわけである)。
だがそれでも、「賞」の外部から「賞」を批判したところで、「これまでさんざ、ありがたく賞をもらってきたくせに、いまさら何を言ってるんだ」と言われておしまいなのは、目に見えている。
だから、あえて「仁義を欠いて」でも、受賞者となって、そのど真ん中に立って、そこから「賞」を否定してみせるという「掟破りのパフォーマンス」を演じて見せたのだ。
「こんなことをした者など、前例がないだろう?(笑)」というわけだったのである。
たしかにそれで、目立つことはできただろう。
だが、「賞」というものが、どのように運営されているのかを知らない「ど素人」ならば、それで「すごい!」と素直に感心させることは出来ても、文学界であれ映画界であれ、どんな業界であれ、「賞」というものの「本質」を知っている「業界人」にとっては、蓮實の行動は、所詮、単なる「掟破りのスタンドプレー」であり「自分さえ良ければいいという、無責任なパフォーマンス」でしかない。
しかしまた、業界人がそう思うであろうことくらいはわかっているはずの蓮實重彦が、なのになぜ、あえてその「見え透いたこと」をやったのだろうか?
一一それは、蓮實の業界内における権威が、すでに揺るぎないものになっており、誰も真正面から批判しないのがわかっていたからである。
自分にメリットはあっても、ほとんどデメリットがないと、周到な見極めた上での、あれは「無難なテロ」だったのだ。
無論、東浩紀のように「あれは、あの人の芸風ですよ」と、皮肉を言う程度のことはできよう。
だが、蓮實の行動を本格的に批判するには、自分も受けている「賞」というものの本質(的な虚さ)に触れなくてはならないから、そこまでやることは、何より自分のためにもならないので、だからやらない。
また、蓮實は、そこまで事前に読み切った上で「掟破りをしても大丈夫。そのリスクよりもメリットのほうが大きい」と判断して、抜け抜けと「掟破りのパフォーマンス」を演じて見せた、ということなのだ。
以上で、蓮實重彦の「授賞は迷惑」コメントに関する「欲得打算の合理性」については、説明がついたと思う。
だがそれでも、より本質的な「倫理的には、どうなるのか(どうして、そのようなことが出来たのか?)」という問題が残る。
この点こそが、常識人には理解しにくいところで、私も長らく、その点で判断に迷ったのだが、最近、蓮實の本を何冊かまとめて読んだので、蓮實の「思考様式」がおおよそ理解できるようになった。
その、私の「蓮實重彦理解」からするならば、蓮實の「掟破りのパフォーマンス」とは、次のようなものだ。
すなわち、「業界の掟」とは「凡庸な人たちを縛る制度」だと、批判的に捉える。だから、それは、「非凡な私」(蓮實重彦)によって、批判されねばならないし、それができるのは自分だけだ、と考える。
しかし、「いくら正しい目的でも、やり方というものがある」という批判が出てくることは当然想定されるのだが、それに対しては、「常識的な倫理観もまた、体制に都合の良い、反体制を骨抜きにするための、倫理的な欺瞞」でしかなく、それもまた「悪しき制度」だ、と考える。
そして蓮實は、自身を「制度から徹底的に自由な人間(例外的に優秀な人間)」であり、そうした「俗流倫理から自由な人間」なのだと自己規定することで、自身の行動を「観念的に、正当化した」のである。
つまりこれは、ニーチェの「畜群に対する、超人の論理」と同型のものなのだ。自分は「畜群の倫理」になど縛られず、それを嘲ってやられると、そう考えたから、喜んで「(畜群の)仁義を欠いた行動」も採れたのである。』
つまり、蓮實重彦というのは、こういう「得意のレトリックで、巧みにライバル学者をこき下ろし、その評判に傷をつけることで、成り上がった人」だった、ということなのだ。

この人の「批評」文とは、そのために「武器」であり、蓮實重彦が褒める映画作家とは、自分のやり方が生きる(映える)タイプの作家で、誰でも語れるような「テーマ性」や「感動」が売りの作家や作品は、「そんなものは下らない(制度に捉われて頽廃した目を持つ者しか喜ばない)」と、レトリックのかぎりを尽くして貶され腐されることになる。
もちろん、こういう悪どい人間であっても、決して馬鹿ではないし、伊達に映画をたくさん見ているわけではないから、その著書の中には、なるほどと感心させられる知見が少なからず存在する。
しかしそれは、プロの映画評論家ならば、言わば「当たり前」のことで、私は何も、蓮實重彦という人を全否定したいわけではないのだ。
私がしたいのは、蓮實重彦の才能を認めつつ、その生き方の「汚さ」であり、その証拠が、かの「三島由紀夫の授賞式での迷惑スピーチ」だと、蓮實重彦の理屈や主張の「結果」が、あの「スピーチ」にあられもなく露わになっていたのだと、そう指摘しているだけなのである。
だから、蓮實重彦の本も「ま、そういう意見もありますよね」と思って、楽しく読めばいい。
蓮實重彦式でないと「頽廃した人間(鑑賞者)」認定されてしまうなどと、殊更に恐れる必要など、かけらもないということなのだ。
要は「たかが、日本の映画評論家のひとりではないか」ということである。
(2024年8月28日)
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
