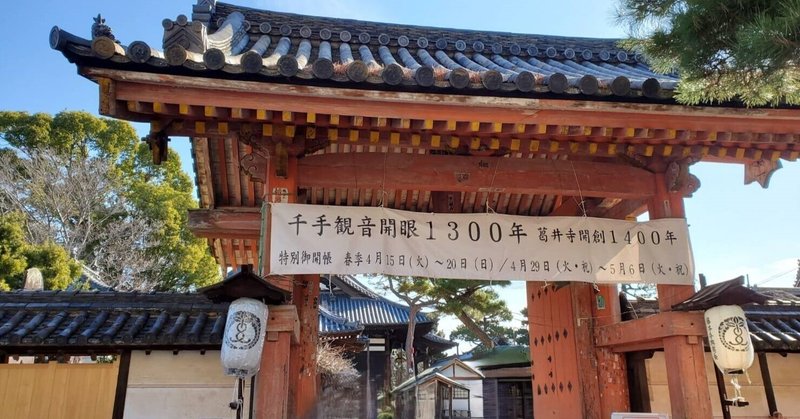新着の記事一覧

【日本史10】大正史備忘録8(シーメンス事件・沢崎寛猛・藤井光五郎・ヴィッカース・岩原謙三・松本和・第1次山本内閣総辞職)
大正時代の学習を深めていきます。 ①山本内閣は政友会と協調性を維持して概ね安定していた。1914年(大正3年)1月22日にイギリスのロイター通信がドイツの重工業メーカーのシーメンスが日本海軍から軍艦受注するために日本の海軍関係者に賄賂を贈った。 ②社員がこの秘密を暴露すると言い会社から金をゆすり取ろうとして逮捕されたという内容であった。この海軍贈収賄事件はシーメンス事件である。この不正な取引は1910年(明治43年)のことなので山本権兵衛とは無関係であった。 ③海軍と薩
スキ
14

【日本史10】大正史備忘録7(中華民国との関係・辛亥革命・第一革命・第ニ革命・孫文・袁世凱・1913年南京事件)
大正時代の学習を深めていきます。 ①中華民国は1912年(明治45年)に成立したが外交関係は課題となっていた。②明治後期には革命家の孫文や宋教仁や黄興たちは日本の明治維新を革命モデルとして度々日本を訪問していた。 ③一部の政治家や活動家は清から来た留学生をサポートしていたが日本政府は清政府から公式に保証されていた清国内の日本の経済活動の自由や日本軍人の駐留の利権を維持するために革命勢力とは直接関わらなかった。 ④1900年(明治33年)に清で義和団事件(北進事変)が起こ
スキ
11

国を、民を守るために、武田信玄は独裁者を目指す 【武田信玄、辞世の句が教えてくれること(大罪人の娘・前編、第参章を終えて)】
武田信玄、辞世の句。 「大ていは 地に任せて 肌骨好し 紅粉を塗らず 自ら風流」 これは、以下のような意味である。 「大抵は世相[世の中の状況]に合わせて生きていくしかないが…… だからといって人目を気にして上辺だけ取り繕う[表面だけ良く見せる]ような生き方をしてはならない。 自分にとって本当の正しい生き方を、『自ら』動いて探し続けよ」 と。 ◇ 「大抵は世の中の状況に合わせて生きていくしかないが……」 まずは、この前半部分。 正直。 あの戦国最強の大名とも謳われた
スキ
1