
大澤真幸、 稲垣久和 『キリスト教と 近代の迷宮』 : 〈馴れ合いなき対談〉 の奇跡
書評:大澤真幸、稲垣久和『キリスト教と近代の迷宮』(春秋社)
博識の社会学者で「無神論者」だとあえて明言する大澤真幸と、キリスト教プロテスタントの信者で、物理学をおさめてから哲学に転じ、今は「公共哲学」というものの必要性を訴えた著書を持つ稲垣久和の対談集である。
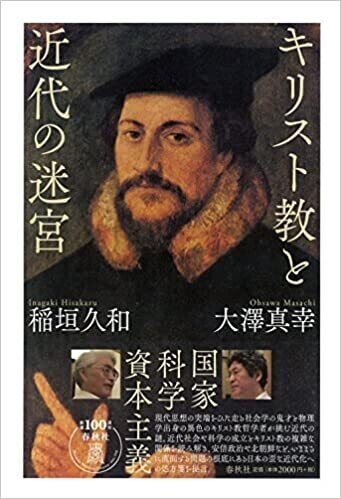
本書は、宗教書を多数刊行している春秋社の企画によって実現した、三度の対談をまとめたもので、3回の内容とは、おおよそ次のようなものである。
(1)近代の成立とキリスト教の関係(特に、カルヴァン派との関係)
(2)近代主義の限界に対し、哲学に何ができるか?
(3)現代日本の諸問題とその本質
これは、私による要約だが、本書の目次における「章題」だと、こうなる。
第1章 キリスト教と近代の迷宮
第2章 近代科学の魔力と哲学の逆襲
第3章 近代の呪縛と現代日本の責任
この章題を見て、察しの良い読者なら、本書がどのような「意図(狙い)」を持って企画されたものがが、容易に見抜けよう。
ひとことで言えば、本書の狙いとは、「反近代主義」に発する「キリスト教哲学の復権」である。
本書の刊行は4年前の2018年4月。
アメリカではトランプ大統領(在任:2017年1月20日〜2021年1月20日)が誕生して派手な動きを見せ「この先アメリカはどうなってしまうのだろう?」という不安が広がり、日本では、安倍晋三政権が「森友・加計学園問題」など様々な問題を起こして話題を提供しながらも、安定した長期政権の記録をどんどん伸ばしていた頃である。
一一つまり、日本でも世界でも「ポピュリズム政治」だ「反知性主義」だと、知的な階層において、危機感が非常に高まっていた時期である。

で、こうした「近代の行き詰まり(としての現代の問題)」が表面化してくると、必ず登場してくるのが「近代の超克」論である。平たく言えば「精神主義(=心主義=霊性主義)」の再評価である。
つまり、本書のねらいは、プロテスタントである稲垣久和の唱える「公共哲学」の必要性・重要性を訴えるところにあり、それに対し、「一般知識人」の代表として「お墨付きを与える」ことを期待されたのが、博識の「人気」社会学者である大澤真幸であった。
稲垣の語る「公共哲学」とは、大正・昭和期のプロテスタントの社会運動家・社会改良家であった賀川豊彦のそれをモデルとしたものであり、いかにもプロテスタントらしい「世俗主義的理想主義」あるいは「人道主義」が、ハッキリと刻印されたものである。
だから、稲垣の「公共哲学」は、きわめて「お説ごもっともな正論」なのだが、問題は「きれいごと」の域を出ず、いかにも「絵に描いた餅」でしかない、という点にある。

しかし、リベラルで「お説ごもっともな正論」だからこそ、リベラルな大澤真幸も、大筋では追認するだろうという「読み」で企画されたこの対談だったのだが、結果としては「そうは問屋が卸さ」なかった。
一一この対談での、大澤の基本的な立場は「話としてはわかりますが、しかし、それは無理だと思います。というのも…」という「注文」を、学術的裏付けを持って付けていく、ということであったと言えるだろう。
本書では、「まえがき」を大澤真幸が、「あとがき」を稲垣久和が担当しているが、大澤の「まえがき」は、こんな調子である。
『 第2章のテーマは、近代科学のパラダイムの乗り越えはいかにして可能か、である。宗教改革の時代と科学革命の時代は半ば重なり、そして隣接している。科学革命を経て生まれた近代科学の世界観は、今日承認されているほとんど唯一の真理のシステムとなっている。近代科学の物の見方のどこに限界や問題があるのか。それをどのような方針で超克すればよいのか。
実は、この章の対談では、私と稲垣氏の見解がかなり異なっていることが示される。というか、本書全体として、文字通り対談、対論であって、二人の意見の一致よりも、両者の間の差異や対立の方を多く提示している。私たちは、差異や対立を大いに楽しんだ。読者も、私たちの間の隔たりにおもしろさを感じる(※ ママ)違いない。そして、稲垣氏と私の対立がもっとも顕著なのが、この第2章である。複雑系やカオスの理論をどう評価し、それが科学のパラダイムに対してどのようなインパクトをもちうるのか。脳のような物質と心や社会との間の関係をどのような構図の中で理解すべきのか。科学の中では排除されている「目的」という現象をどのように位置づけるべきか。こうした論点のすべてにおいて、稲垣と私はするどく対立している。
第3章では、一転して現代日本の具体的な政治状況に関係したアクチュアルな問題が次々と論じられている。』
(大澤真幸「まえがき」より)
一方、稲垣久和による「あとがき」は、こんな調子だ。
『 二〇一七年一〇月、安倍政権は野党共闘の裂け目に乗じていきなり衆議院を解散した。結果は自民党の圧勝となった。決して内閣支持率の高くないこの政権が、なぜ長期政権の座にあるのだろうか。
革新ないしはリベラル勢力と称されたグループの退潮は、この二〇年ほどで急速に進行した。リベラルと呼ばれることをよく思わず保守と名乗る論者やグループが多い。ただ、名称はともかく、正義感が人一倍強い人々の集まりであっても、政治や経済、社会のありかたを描く哲学については一部を除いてほとんど議論されてこなかったのではないか。
だから、この対談がその哲学について考えたいと思う人々、特に若い世代に少しでも参考になれば大そう嬉しい。幸い、大澤真幸氏という独創的な社会学者を得て、その哲学がわかりやすく語られたのではないかと思う。また筆者自身の批判的実在論(四世界と四セクター論)と称した認識論の詳細については『実践の公共哲学』(春秋社、二〇一三年)を参照されたい。
大澤氏は歴史の意味についてうまく説明できる人だ。後世に重大な影響を及ぼした歴史的出来事について、その論理構造を抽出することに長けている。キリスト教の神概念からヒントを得た「第三の審級」など実に興味深い。また西洋近代化論の、特に、産業資本主義勃興の説明であるマックス・ウエーバーにおける「予定説」などの一般化もそのうちに入る。本書の中にもそれについての議論が出てきている。筆者も西洋近代が生み出した〝普遍性〟が、宗教改革という出来事と密接に関係しているという認識について一致する。一六〜一七世紀のヨーロッパは近代科学、基本的人権、資本主義といったグローバルに通用する人類史的な〝普遍的〟出来事を生みだした。
しかし資本主義の起源のエートスはウエーバーの説く「予定説」ではない、これが筆者の考えだ。予定説というのは、もともとカルヴァン派のみならず一般のキリスト教神学の「救済の教理」のひとつであり、社会学者が関心を持っているものとはその内容が異なる。』
(P323〜324、稲垣久和「あとがき」より)
大澤真幸が「まえがき」に書いているように、第2章は、両者の「対立」が火花を散らしており、近来まれに見る「スリリングな対論」となっている。
要は、稲垣が、「公共哲学」の名において「(霊性主義的な)キリスト教哲学」の復権を図ろうとしているのに対し、大澤は、これを「甘い」と否定しているのだ。
もちろん、言葉は丁寧だが、大澤は、内容的に「そこまで言うか」というくらいに、仮借なく稲垣を攻め立てていて、稲垣は、ほとんど防戦一方になっている。
したがって、大澤が「まえがき」で言う『私たちは、差異や対立を大いに楽しんだ。』というのは「タテマエ」であって、実際には、大澤は大いに楽しんだであろうが、稲垣の方は、この十も年下の学者の呵責なき批判に、必ずや苛立ったことであろう。

稲垣が「世間並みの理想論」を語ると、それに対して大澤は、それが現実には通用せず、もっとラディカルなところから考えなければならないと、稲垣の「公共哲学」の非現実性に、鋭く注文を付ける。
すると、稲垣は、専門の哲学や物理学の最先端的な知見を持ち出してきて、その「権威主義的ペダントリー(衒学)」で、大澤を煙に巻こうとするのだが、大澤の方は、本当によく勉強していて、そうしたハッタリに臆することなく、むしろ、その「最先端的な知見についての、稲垣の解釈」が「(御都合主義的に)一面的」であることを、わかりやすく「解説」してしまうので、この第2章では、ほとんど稲垣は、なぶり殺しにあっているような感じなのである。

だから、キリスト教の社会運動家によくいる「きれいごとを語る、キリスト教宣伝者」の「博学的偽善」の化けの皮を剥ぐという意味で、大澤としては楽しかったろうが、稲垣の方は、乗りかかった船で後には退けないとはいえ、相当、苛立たされたであろうことは、「人間心理」の問題として、容易に推察できたのである。
ちなみに、大澤が「まえがき」で言う『科学の中では排除されている「目的」という現象をどのように位置づけるべきか。』の部分の「目的」とは、要は「神の目的(意志)」ということである。
クリスチャンである稲垣は、現代の閉塞状況の原因は「目的(的意味)を排除した近代主義のニヒリズムにある」から、そうした「目的」を取り戻さなければならない、と主張する。
これは「人間は誰でも、それなりに目的を掲げるし、その方がより良く生きられるでしょう。それと同じことですよ。だから、目的を見失って、ただ無意味にこの世界が存在するという認識を根底に持つ近代主義や科学は、まず生きることの目的を回復しなければならない」といった議論をするわけだが、無論、大澤はこれが「糊塗されたキリスト教再評価論」でしかなく、「目的」というのは「神」の別名でしかないことを察知して、稲垣の哲学の「御都合主義」に、鋭く注文をつけたのである。
したがって、稲垣による「あとがき」には、こうした大澤に対する「立腹」が隠されている。
この「あとがき」で語られていることを、身も蓋もないかたちに言い換えると、こうなる。
「 二〇一七年一〇月の衆院選で、安倍自民党の圧勝したのは、革新ないしはリベラル勢力と称されたグループに、政治や経済、社会のありかたを描く哲学が無かったからだ。
だから、私はこの対談で、行動のための根本哲学を提供したい。
幸い、この対談では、大澤真幸氏という独創的な社会学者を対談相手に得て、筆者の哲学をわかりやすく「解説」してもらえたのではないかと思う。だが、それは所詮、表面的な「解説」でしかないから、できれば筆者の著書『実践の公共哲学』を読み、正しく理解を深めてほしい。
大澤氏は、歴史におけるキリスト教的出来事の特権性の意味について、うまく説明できる「解説の達人」だ。哲学的なオリジナリティーは無いものの、後世に重大な影響を及ぼした歴史的(なキリスト教的)出来事について、その論理構造を抽出することなどには長けている。キリスト教の神概念からヒントを得た彼のキーワード「第三の審級」などは、実に興味深くユニークな仕事だと評価する。また西洋近代化論の、特に、産業資本主義勃興の説明であるマックス・ウエーバーにおける「予定説」理論の「一般化」も、そうした仕事のうちに入る。本書の中にも、大澤氏が理解するところのウエーバー的「予定説」についての議論が出てきている。筆者も西洋近代が生み出した〝普遍性〟が、宗教改革というキリスト教的な出来事と密接に関係しているという認識については、大澤氏と意見が一致する。キリスト教は、一六〜一七世紀のヨーロッパは近代科学、基本的人権、資本主義といったグローバルに通用する人類史的な〝普遍的〟出来事を生みだしたのだ。
しかし、行き詰まりを見せている資本主義の起源のエートスは、ウエーバーが言うところのカルヴァン派的「予定説」ではない、これが筆者の考えだ。予定説というのは、もともとカルヴァン派のみならず一般のキリスト教神学の「救済の教理」のひとつであり、社会学者が関心を持っているものとは、その内容が異なる。ウエーバーや、それに学んだ社会学者は、予定説を読み違えており、それは大澤氏も同様である。」
つまり「なるほど、大澤氏は博識かつ器用な人ではあるが、本質的な哲学を持たない学者だ」ということだ。

そんなわけで、本書の「第2章」における「キリスト教哲学と無神論哲学との対決」は、抜群に面白い。
だが、キリスト教徒には、これは面白くない内容であろう。
そもそも「近代主義の行き詰まりへの処方箋としての、キリスト教哲学」の価値を保証する役どころであったはずの大澤真幸が、その役目を平気で無視して、忌憚なく突っ込みを入れまくった結果、いろいろと不都合な部分のある対談になってしまったからだ。
「対談」本というのは、現場で語られたことそのままではなく、録音を文字起こししたものに、後で両者が筆を加えるものなのだが、それでも相手のいることなので、完全に書き換えてしまうことはできず、おのずと「不都合な部分」も残ってしまうのである。
だから、本来、主にクリスチャンを読者に当て込んだ本書は、あまり評判が良くなかったようだ。
2022年9月1日現在、Amazonの本書紹介ページには、3つの「評価」が投じられており、5点満点で、4点が2つ。1点が1つ。レビューは、4点の人の一方による「内容紹介」的なものだ。
つまり、本書を、正しく読んだクリスチャン読者は、むしろ「1点をつけた人」の方だったのである。
(2022年9月1日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
