
淀川長治 『映画とともにいつまでも』 : 愛を語る者は、 愛を否定する者をも愛せるか?
書評:淀川長治『映画とともにいつまでも』(新日本出版社)
本書は、1992年に刊行されたもので、収録されているのは、「講演」記録と、映画評論家・山田和夫との対談である。
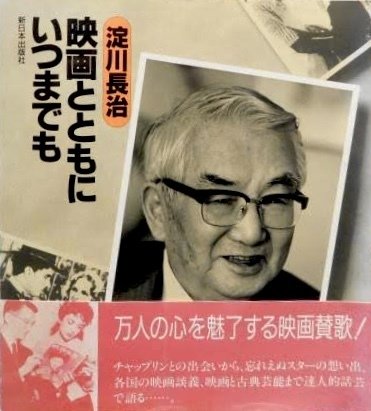
私も古本で買ったあとに気づいたことなのだが、政治に興味のある読書家なら、「新日本出版社」が「日本共産党」系であることをご承知だろう。
日本共産党の下部組織・団体には、「新日本」を冠しているものが多く、「新日本婦人の会」などもその一例で、「新日本出版社」は、そうしたもの中で最も有名かつ、わかりやすい例だと言えるだろう。
こうしたことは、戦後の日本共産党が、「共産主義の理解と浸透」を図るために各種の「文化事業団体」を設立した際、それらの名称として「新日本」を冠したためで、「新日本スポーツ連盟」(旧称・新日本体育連盟)などもそのひとつはずだ(アントニオ猪木が設立した「新日本プロレス」は、気持ちの上でどうかまでは定かではないとしても、共産党とは無関係で、組織的なつながりは無い)。
こうした「文化事業団体」というのは、例えば、創価学会が「民音(民主音楽協会)」などを通じて芸能界に対し、長らく大きな影響力を持ったように、戦後の「文化・芸術」の普及に、絶大な影響力を持った。
今ではインターネットがあるから、個人でも広く販路を確保できるが、それ以前は、各種スポーツ競技にしろ、映画にしろ、音楽コンサートにしろ、そのチケットを売り捌くためには、全国規模の、組織だった販路が必要だったのである。
そんな予備知識が私にはあったので、「新日本出版社から出した本か。どんな内容だろう?」と思って読み始めたのだが、本書の大半を占める講演記録は、淀川長治的に「いつもどおりの内容」で、非政治的なものであった。
まあ、淀川長治がことさらに政治演説をするわけもなく、語られているのは「映画の話」であり、主に「映画の見方」といったことだったのだ。
淀川の著書は、先日読んだ『淀川長治 映画ベスト100&ベストテン』(河出文庫)に続く2冊目だが、映画紹介読み物としては、何も目新しいところがない。
むしろ映画マニアを読者に想定していない、いかにも一般人向け「映画入門」的な内容であったために、私としては、やや食い足りなさが残った。

だが、そうした「映画入門」的な内容であったからこそ、淀川長治の映画に対する「基本的なスタンス」が 、よく表れてもいた。
どういうものかと言うと、
「映画は人生の教科書。人が生きる上で大切なこと、例えば、愛や優しさや思いやりの重要さや美しさといったことを教えてくれる。もちろん、読書も必要だし、優れた古典文化に接することも重要だが、しかし、映画は誰にでも接しやすいという点において、最も優れた文化だと言える」
と、大筋でこのようにまとめられるものだった。
そして、こうした「基本スタンス」から出てくる言葉として、私が特に興味深かったのは、次の言葉だ。
『 映画の見方はそこだと思います。このカメラアングルはいいぞ、このオーバーラップは最高だ、そういう見方もいいでしょう。少年時代の私もそうでした。しかし、それだけが映画の見方ではありません。』(P7)
ここには、現在「映画マニア」の間で主流の「映像論」的な映画の見方に対する、淀川の懐疑や不満が表明されていると、そう見て良いだろう。
無論、そうした見方が「間違っている」とまでは言わない。むしろそういう見方が「必要」だというのは明らかなことなのだが、しかし、そういう見方だけで良いのか、という淀川の疑義が、ここで語られているのである。
これは、淀川が「映画は、人生の教科書」的な見方をする人であるならば、ごく自然なことあろう。
「映画のテクニック的側面=映像的な見せ方の技巧的側面」をいくら学んだところで、「人の騙し方」を学ぶには良いだろうが、映画から「愛や優しさや思いやり」を学ぶことはできないからである。
つまり、淀川長治自身が「映画マニア」である以上、好むと好まざるとに関わりなく、映画の「技巧的な側面」も目に入ってはくるし、気にもなる。「良いテーマを掲げた作品」がすなわち「良い映画」になるわけではないというのは、そうした凡作愚作も山ほど見てきたであろう淀川には、自明の話だっただろう。だから「どう見せるか」という技巧面は、どうしたって無視はできないのだ。映画は、「映像付き演説」ではなく「映像芸術」だからで、「芸術」に技巧は、どうしたって必要なものなのである。
だがそれでも、長年映画を見てきた淀川からすれば、映画マニア的な「技巧論」は、いささか「小賢しい」ものとして、鼻についた、ということなのであろう。
まして、淀川の好みは「愛や優しさや思いやり」を教えてくれるヒューマニズム映画に偏っているし、さらに言えば、それだけではなく、対談のなかで語っているように「女のいやらしさを巧みに描いている」といった「女」を見事に描いた映画を好むように、多少の偏りはあるけれども、要は「人間を描いた映画」が好きなのだ。だから、「技巧」はそうした人間描写に資するものというのが、淀川の基本的なスタンスなのである。そのあたりで「本末転倒であってはならない」という気持ちが、淀川にはあったのであろう。
ともあれ、淀川長治は、基本的に「愛や優しさや思いやり」を重視する映画評論家なのだから、この人を「悪く言う」映画関係者は、映画ファンを含めてほとんどいない。
『淀川長治 映画ベスト100&ベストテン』のレビューで紹介したように、かの皮肉屋の蓮實重彦でさえ、この大先輩を丁重に持ち上げたいたほどなのだから、それ以外の映画関係者が、率直に「淀長さんは、甘い!」と、そんな「本音」を、公の場で語ることは、まずなかっただろう。
だが、実際のところ、そう思っていた映画関係者は、少なくなかったはずだ。
ではなぜ、淀川長治は、表立って批判されなかったのかと言えば、それはまず、彼が映画の「生き字引」であったからだ。つまり、映画をその最初期から同時代に見てきた人であり、今ではフィルムの残っていない映画についての記憶さえ持っている。だから、そうした「知識」の保持者という事実において、「映画大事」の映画関係者としては、そこに敬意を表さないわけにはいかない。
言い換えれば、「映画を山ほど見てきたからって、それがどれほどのことだと言うのだ」とは言えない。映画を「たくさん見て、たくさん知っていること」の重要性それ自体と否定すれば、それは「映画」自体の価値を否定したも同然であり、自分たちの拠って立つ「権威」を否定することになるからである。
したがって、その「映画観」が少々甘くても、ひとまず「映画の大先輩」ということで、淀川に敬意を表さざるを得ないのだが、言い換えれば「映画批評」とは、所詮、その程度のものだ、とも言えるだろう。
要は、「映画の価値そのものを問う」ということはしないし、できないのだ。
「映画は素晴らしいものだ」というのを、無条件の大前提とした上で、すべての議論は組み立てられるのだから、これは「神は存在する」し「神は絶対の正義だ」という前提で組み立てられた「神学」と基本的には同型の、非科学的(非客観的・手前味噌)な馴れ合いの、批評を装った「党派イデオロギー」でしかないのである。
言い換えれば、映画そのものの価値を「根源的に問う」などといったことをする者は、映画界からは「お座敷が掛からない(お呼びではない)」ということにもなろう。
だが、そんなものは批評ではないし、間違いなく「学問」ではないだろう。なぜならそれは「我が仏は尊し」という、「映画イデオロギー」に資するものでしかないからである。
しかしながら、そうした「映画イデオロギー」によって守られていた、淀川長治の「愛や優しさや思いやり」の映画評論もまた、おのずと、一種のイデオロギーでしかなかったのは、理の当然である。
例えば、淀川の映画観からすると、映画は「人間に資するもの」で「なければならない」ということになり、言い換えれば、淀川の価値観からして、「人間のためにならないもの」、例えば「人間は滅ぶべき、醜い生き物である」といった思想を語る作品を、淀川は認めなかったであろう。
また、それと似たこととして、例えば、人間がバラバラに引き裂かれるようなショッキングなシーンが売り物の「スプラッタ・ホラー」などを、淀川が認めていなかったであろうことは、容易に推測できる。
しかし、「芸術」というものは、必ずしも「人間に資するものでなければならない」とは考えられておらず、「美の創造」が目的とされることが多いから、おのずとその「美」の中には「人間否定の美学」も「醜悪の美学」も「悪魔の美学」といったものも含まれよう。
そして、そうした「芸術至上主義」の立場からすれば、淀川の「人間主義映画観」というのは、いかにも「古臭くて偏狭なイデオロギー」にすぎない、ということにもなるのである。
まただからこそ、淀川は、デビュー当時のジャン=リュック・ゴダールを「悪魔」と呼びさえしたのだ。
それは、彼の作品が、それまでの淀川長治的な「人間主義映画観」には収まりきらず、むしろその「枠」の破壊を意図したものだと、淀川が正しく見てとったからなのだ。

ともあれ、あれこれ考えつつ本書を読み進めていくと、最後の山田和夫との対談で、徐々に「政治的な臭気」が漂いはじめ、その最後の最後で、『〝映画は心の共産主義〟』という、なかなか露骨な見出しが、いきなり目に飛び込んでくる。
ここでは、その見出しの、ひとつ前の見出し『〝戦前の文化新聞に寄稿〟』の部分から紹介しておこう。
『〝戦前の文化新聞に寄稿〟
山田 きょうは、先生は恐らく覚えていらっしゃらないだろうと思うものをもってきたんです。「土曜日」という戦前京都で発行されていた新聞です。これ復刻版ですけど。
淀川 あら、知らない、それ忘れとった。
山田 哲学者の久野収さんや中井正一さん、それに京都の映画評論家清水光さんといった人たちが京都で出していた。
淀川 ほお。清水光さんなんかもね。
山田 清水光さんらがやっていて、南部圭之助さんも書かれている。軍国主義がひどくなってきた時に、文化人たちがせめてリベラルな自由な文化的な新聞を出そうということで発行したもので、これを見るとアメリカ映画についても書かれているし、淀川先生はフランク・キャプラの「失われた地平線」についてお書きになっているんですね。
淀川 へえ。何年頃。
山田 一九三七年、昭和十二年。これは大変貴重なものなんですよ。五十五年くらい前になりますね。
淀川 その頃からこんなん書かせてもらってたのね。へえ。
山田 その頃、フランスの人民戦線が文化週刊紙「ヴァンドルディ(金曜日)」を出していたんですね。京都の文化人たちがそれに倣って、それに映画評論家の清水光さんが入っていて、南部さんや淀川さんに声をかけたんですね。だからアメリカ映画やフランス映画の資料が多いんですよ。その当時、そういうのがだんだんだんだんやれなくなったとき……。
淀川 京都は割りにインテリが多かったからね。勉強家がな。
山田 ええ。これは結局潰されるんですけどね。淀川さんの非常にリベラルな気持ちがちゃんとこういうふうに残っているんです。
淀川 凄いね。怖いね。証拠だね。僕なんか、赤狩りなったらいっぺんにやられるね。今度はあっちこっちに証拠があるから、ハハハ(笑い)。
山田 哲学者の久野収さんが、「文化新聞『土曜日』の復刻によせて」という文章を書かれているんです。「土曜日」は、もともとは京都の撮影所の「京都スタヂオ通」から出発したんです。ここに衣笠貞之助、犬塚稔、伊藤大輔、内田吐夢、みんな名前が出てましてね。それが発展してこの「土曜日」になったんです。久野さんが「『土曜日』にはまた若き日の淀川長治が、映画『失われた地平線』の紹介的批評を署名入りで執筆している」と書かれているんです。戦前のもうみんなびくびくしていた頃に書かれたんだからたいへんなもんですよ。
*「土曜日」は、一九三六年七月四日創刊号(「京都スタヂオ通信」からの通算第十二号)から三七年十一月五日の第三十三号(通算第四十四号)まで、月二回発行されたが、『世界文化』「土曜日」グループの引き続く総検挙によって、強制廃刊に追い込まれた(編集部)。
淀川 僕が映画を好きなのは、みんな同じものを観ているからなのね。本を読むのもみんな一緒に読むけれども、やっぱり映画は広いもんなあ。あんたもご覧になってるし、あんたのお父さんがご覧なってもいいし、妹さんもご覧なっていいし、僕が観てもいいし、隣のうどん屋のお兄さんが観てもいいし、皆が観るからな。いっしょに一つのものを暗い中で観る。あれが好きなの、僕。皆がいっしょに観ていることがな。一人だけ観ているんじゃなくてね。歌舞伎もみんなが観るけど、映画は一人で入ってもいいし、歌舞伎と違ってあらゆる人が観るからね。歌舞伎や文楽はどっちかといったらやっぱり知識階級の人が観るのね。映画はもうどんな人が観てもいい。労働者が観てもいいし、それから学校の校長さんが観てもいいしな。
〝映画は心の共産主義〟
山田 しかもその同じ映画を世界中で観られますからね。世界中の人が。去年ですか、『サンサーラ』という雑誌で作家の落合信彦さんと対談されましたでしょう。あの中で同じようなことをおっしゃっておられて、「映画は頭脳の共産主義だ」なんておっしゃっていますね。
淀川 そうそう。頭の共産主義、心の共産主義、映画こそがいちばん共産主義よ。みんな一緒に観るからね。みんな一緒に楽しむからね。それで国の垣根をとるからね。』(P159〜162)

最後の最後で「イデオロギー」的な話に持ってくるところが、それを知らずに読んだ読者には、なんとも鼻白まされるところだろう。曰く「ハメられた」(Amazonに、カスタマーレビューが1本もないのも、そのせいかも知れない)。
淀川自身は、特に共産主義イデオロギー的な話をしているわけではないが、しかし、ここで語られているのは、ある種の「社会主義革命論」つまり「世界同時革命論」(反・一国社会主義論)的な考え方だとも言えるだろう。
淀川は、その「人間主義」において、世界中のあらゆる人々とつながれうると、そう信じているのである。
だが、ことがそう簡単なものでないことは、すでに「映画」において証明されている。
つまり、淀川が考えるような「人間主義的な映画」というのは、映画のすべてではなく、そのような「過度に倫理主義的な縛り」から「自由」になりたいと考える者も当然出てくるわけで、そのひとりが、他ならぬジャン=リュック・ゴダールだった、とも言えるのだ。「映画に物語など要らぬ」とは、「映画的な人間主義表現」への攻撃でもあったのである。
そして、そんなゴダールを、人間主義者である淀川長治は、なんと呼んだか?
一一「悪魔」である。
淀川の持つ、愛と優しさと思いやりの「人間主義イデオロギー」のゆえに、そこからはみ出していこうとするゴダールという人間は、おのずと「悪魔」化されたのだ。
幸いゴダールは、その後、世界的な評価を受けるに至り、日本でも蓮實重彦のような強力な擁護者まで現れたから、いかに「伝説的な映画マニア」である淀川長治の「権威」を持ってしても、ゴダールを「同じ人間」扱いにしないわけにはいかなくなった。
だが、もしも、ゴダールがそのような世界的な評価を受けていなかったら、淀川はきっと、その「悪魔」という評価を改めはしなかっただろう。
「愛と優しさと思いやりの映画評論家」だから、ゴダールに対する「悪魔」という否定的評価を、意図して広めるような積極的な攻撃まではしなかっただろうが、淀川が「嫌いな映画は語らない」という「いつものやり方で、黙殺した」だろうとは容易に推察できるし、人から尋ねられれば、自身の否定的評価を隠しはしなかっただろう。
だが、映画界における「政治的な情勢」としては、そうはならなかったので、淀川は、イヤイヤながらも評価を「一部修正」しなければならなかったのである。まるで「ソ連崩壊」後の「共産主義イデオロギー」のように。

つまり、私が言いたいのは、「愛と優しさと思いやり」を語って、「感じが良いだけの批評」ではダメだ、ということなのである。
ダメなだけではなく、そんなものは、批評の名に値しないのだし、そんな「手前味噌」で「ナルシスティック」な目しか持っていないからこそ、自分でも気づかないうちに「お山の大将」になって、自身の「主義主張」を振り回すようにもなってしまう。
「スターリン万歳」「金日成万歳」「映画万歳」という罠にも、簡単にハマるのだ。
「共産主義」というのは、柄谷行人が言うところの「統整的理念」としては、とても素晴らしいものだ。それは、「理想」として目指されて然るべきものである。
ただし、人間というのは「ひといろ」ではないから、どんなに素晴らしい「理想」、あるいは「最大公約数的な理想」であっても、それが「嫌だ」という者は、必ず現れてくる。
問題は、その場合に、そういう「例外的存在」を、どう処遇するのか、なのだ。
現実の「共産主義国家」が間違えたのもそこで、「理想」の実現のためには「理想に反する存在」としての「少数例外」は、全体のために、否定・排除されなければならない。「それが正義である」一一と、そう考えた結果、そうした「例外的な人間」は「人間社会における悪魔」化され、シベリア送りにされて、社会から抹殺されていったのだ。
つまり、「理想」というのは「目指すべきもの」ではあるけれども、「実現すべきもの」ではないのだ。
なぜならば、それは「実現できないもの」だからであり、そうであるからこそ「理想」なのである。
そして、人間という存在は、「理想」そのものではあり得ず、「現実」存在であるからこそ、そんな「人間」存在に、現実的に「理想」を強いるならば、「理想は、理想ではない何か」に変質してしまう、ということなのである。
私たちは、淀川長治という、皆から愛される「愛の評論家」もまた、人間的な限界を持っていたという事実を直視し、その問題点を率直に批判しなければならない。
どんなに立派そうに見えても「理想どおりの人間」などというものは、存在しないのだ。それは、私が冗談半分ながら「私だって完璧ではない」と、そう自戒するとおりなのである。
ちなみに、本書に収められた、淀川長治の講演を主催した「映画鑑賞団体全国連絡会議」は、今どきのことだから、一見したところ政治色は見られず、政治的背景の有無は不明。だが、旧称が「全国勤労者映画協議会(全国労映)」だそうだから、社会党系か共産党系かは不明だが、政治思想がゼロだということではなさそうである。そして、「社会党系」だった場合、本書に協力するか、そもそも淀川長治を講演に呼ぶか、といった疑問もある。
なぜなら、「Wikipedia」にも紹介されているとおり、淀川長治は1973年当時、「特殊な部落」発言で、「部落解放同盟」から厳しく糾弾された経験があり、かつ本書では、映画『奇跡の人』における、ヘレン・ケラーに対するサリバン先生の、ビンタも含めた「愛のある厳しい指導」を絶賛して「心ある言葉が大切だ」という趣旨のことを語ってもいるからだ(P112〜121)。
なお、その部落解放同盟は現在、(旧)社会党支持である。これは昔(1965年当時)、解放同盟内部で両党派の政治路線抗争があって、共産党系が排除されたためで、以降、解放同盟と共産党は、犬猿の仲なのだ。
また、淀川の対談相手である山田和夫は、共産党員である。
『山田 和夫(やまだ かずお、1928年1月28日 - 2012年8月11日)は、日本の映画評論家、映画史家、映画運動家。
来歴
大阪府大阪市出身。高知高等学校卒業、東京大学経済学部卒業。
東京大学在学中に同学に自由映画研究会を堤清二、富本壮吉などと設立。
1951年に映画業界紙の合同通信社に入社。記者として人脈等を深め、1962年よりフリーとして活動する。
エイゼンシュテイン・シネクラブ(日本)代表。『戦艦ポチョムキン』の自主上映運動などで名を馳せる。
映画提供会社の国際シネマ・ライブラリーの運営に関与し、同社を通じて、ロシア・ソビエト連邦、ラテンアメリカ諸国、ベトナムなどの映画の紹介に尽力。
日本及び、世界の映画史、映画産業を研究。モスクワ国際映画祭、ハバナ国際映画祭へ参加などを通じて、ロシア・ソビエト、ラテンアメリカ諸国の映画に精通し、両国(地域)の映画文化を紹介する。ベトナム社会主義共和国より友好勲章、キューバ共和国より文化功労章などを受章している。また、映画業界紙記者の経験もあり、映画を産業的側面からも論じられる数少ない映画評論家。
1954年に日本共産党に入党。同党映画後援会代表を務めた他、「しんぶん赤旗」の常連執筆者であった。
「九条の会」傘下の「マスコミ九条の会」呼びかけ人を務めていた。日本映画復興会議の代表委員をつとめた。第二次世界大戦での日本を肯定的に描いた『プライド 運命の瞬間』、『ムルデカ17805』などの映画を痛烈に批判した。
2012年8月11日、肺炎のため死去。』
(Wikipedia「山田和夫」)
また、淀川自身も、
『凄いね。怖いね。証拠だね。僕なんか、赤狩りなったらいっぺんにやられるね。今度はあっちこっちに証拠があるから、ハハハ(笑い)。』
と言っているくらいだから、共産党員なのかも知れない。
無論、「共産主義」や「共産党」が、悪いというのではない。
むしろ私は、それを擁護する立場を採ることの方が多い人間なのだが、しかし、「自分の政治的立場を隠した上でのプロパガンダ」というのは、「理想に反する現実主義」として、どうにも好きにはなれない。
私はそんな、「自由な個人主義」者という「悪魔」なのである。
(2024年8月8日)
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
