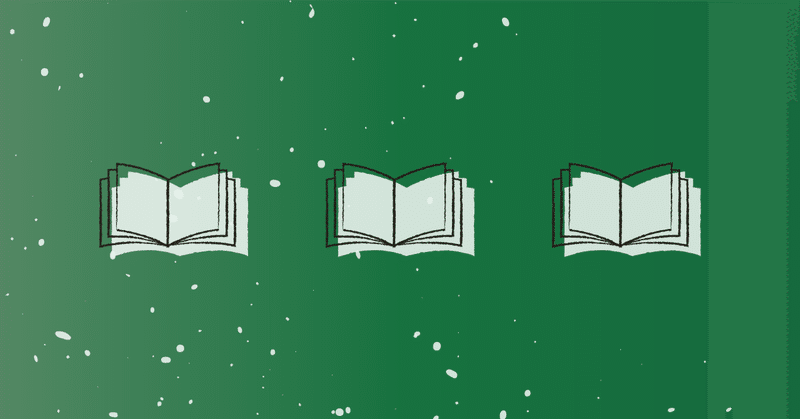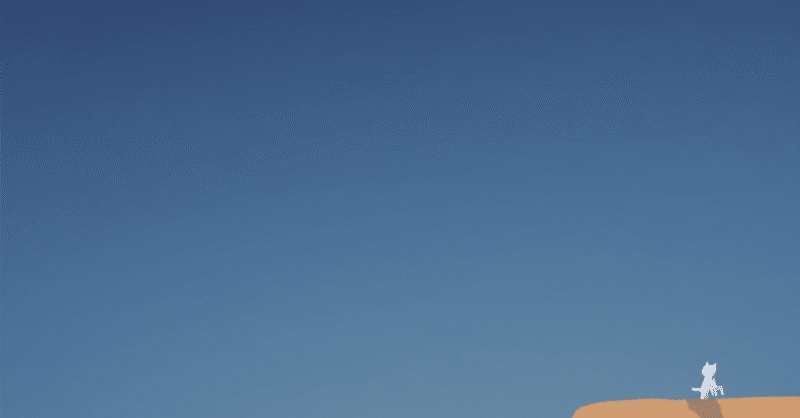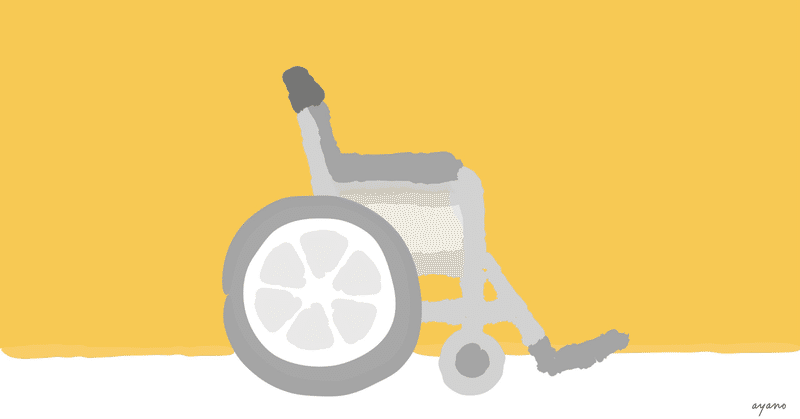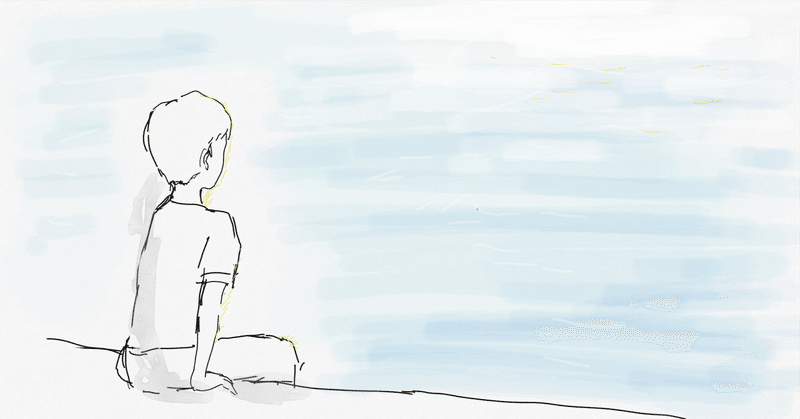全体ビュー(全期間)でアクセスの少ない記事を集めました。アカウントを開設した初期の記事が多いのですが、意外と面白いかもしれませんよ。下へ行くほどアクセスが少なくなっています。
- 運営しているクリエイター
#日本語
多層的で多元的なもの同士が、ある一点で一瞬だけつながる世界
「春」を感じるたびに連想するのは「張る」です。辞書の語源の説明には諸説が紹介してありますが、私は「張る」派です。
春になると、いろいろなものが張ります。木々や草花の芽やつぼみが膨らむのは張っているからでしょう。
山の奥でも雪解けが進み、川面が膨らんで見えます。道を歩く人たちの頬も上気したかのように見えます。細い血管が膨らんでいるようです。
山川草木、そして人が膨らみ張って見えます。膨張
音読・黙読・速読(その3)
シリーズ「音読・黙読・速読」の最終回です。
・「音読・黙読・速読(その1)」
・「音読・黙読・速読(その2)」
◆センテンスが長くて読みにくくて音読しにくいけど素晴らしい文章
まず、前回に取りあげた文章を再び引用します。なお、あえてお読みになるには及びません。ざっと目をとおすだけでかまいません。
(Ⅰ)
(Ⅱ)
*節のある竹のような文章
上で見た、井上究一郎訳によるマルセル・プル