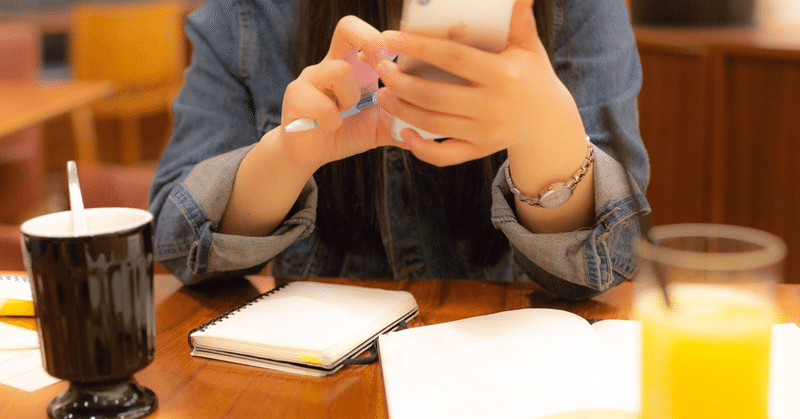記事一覧
言語を生み出す本能 | Steven Pinker
「生成文法」というと創始者のノアム・チョムスキーが有名ですね。言語学者ですが、政治的な著書も多いことでも知られています。
また、さまざまな分野の学術的な論文にも引用されることが多いです。
チョムスキーの次に有名な生成文法学者というとスティーブン・ピンカー。
「言語を生み出す本能」という本は、言語学に関する本の中では、幅広い人々に読まれた書物です。とか言って、私は読んでいないのですが。
一語の宇宙 | 法律・立法 | legislation
「legislation」。
「法律」と「立法」という2つの意味があるので、翻訳するときには注意する必要がある。
私の手元にある英英辞典には、次のように書かれている。
legislation
n [U]
(a) action of making laws: Legislation will be difficult and take time.
(b) the laws made: N
英文法 | 連鎖動詞句
I like to read in bed.
という文の「to read」は、規範文法(学校文法)では「不定詞の名詞(的)用法」だと説明される。名詞(的)用法というのは「~すること」という名詞のような意味を帯びているからである。
すなわち、
I like (to read in bed).のように、
「to read in bed」(ベッドで本を読むこと)を1つの名詞として扱うということである
Groundless Slanders
Like in our daily life, there are people and people on social media including "note." In general, in most cases when you write your article, it is written for the sake of you yourself, not for the sak
もっとみるアイデア整理のための5つのステップ
今日は、私が実践している「アイデア整理のための5つのステップ」をご紹介します。
プロジェクトが始まると、多くの情報や課題が頭の中を飛び交い、思考が整理しきれなくなることがありますよね。ごちゃごちゃとゴミと大事なものが散らかっている状態になります。
そんなとき、私は頭の中をスッキリさせ、新しいアイデアが生まれてくるように、アイデアを整理することを心がけています
1)書き出すまずは、とにかく頭の中に
白衣を着て、母をみる。
因果を思う。
私と実母の相性は悪く、幼少期の傷も相俟って出来るだけ会いたくないし、会う用事は短時間で済ませたい。母は私を溺愛してきたし、過保護で過干渉な母親の成立には、彼女自身の両親が共に毒であった過酷な生育環境に加えて、私が生まれながらに虚弱体質であったために、乳児期から幾度か死の淵を彷徨った事実が、彼女の庇護欲を決定的なものにしたのかもしれない。
私が医師を志した動機は自身の体験によ
一語の宇宙 | someとanyの使い分け
中学生で英語を学ぶとき、「some」も「any」も、「いくつかの」という意味で教えられることが多い。そして、「some」は肯定文で、「any」は疑問文・否定文で使いましょう、と。
そのような「縛り」があるせいか、中学生の問題集をたまに眺めると、本来は「some」のほうがよいと思われる文脈でも、「any(この場合はsomeでもよい)」という解説があったりする。
また、「いくつかの」という日
今だからニーチェを読もう!と思った話
久しぶりに書店に立ち寄った。
「これまでに読んだことのない著者の本を読もう」
まず岩波文庫のコーナーに行くと、私の居住区の書店には残念ながら「誰も買わなくて残ってしまったかのような見た目も古そうな本」しか棚になかった。作戦変更!他の本で探してみる。書店の棚で目を引いたコーナーがあった。「哲学書」なのか「自己啓発本」なのか分類に迷う本だ。ページをめくって中を覗いてみると「すっと心に入ってくる言葉」が