
北村紗衣 『批評の教室』 : 作品批評【実践編】(第2回)
書評:北村紗衣『批評の教室 チョウのように読み、ハチのように書く』(ちくま新書)
さて、想定外の「連載」になってしまった、北村紗衣著『批評の教室 チョウのように読み、ハチのように書く』(以降『批評の教室』と記す)のレビューなのですが、前回「ツッコミどころが多すぎて、どこを取り上げどこを捨てるのかを考えるのが面倒なので、目次に沿って、頭から順に論評していく」という方針を示しはしたものの、そんなやり方で、いったい何回で終われるものなのか、そんな見当など皆目つかず、私自身いささか困惑しています。
そもそも、レビューを書く際も「書きたいだけ書く」「書き終わったところで、そこがおしまい」などという自由気ままでやったきたため、あらかじめの枚数予想などつかないのだから、我ながら困ったものです。
で、この「第2回」からは、本書『批評の教室』に合わせて、「ですます体」で書くことにしました。
これは『批評の教室』の一種の「パロディ」だと思っていただければ良いでしょう。
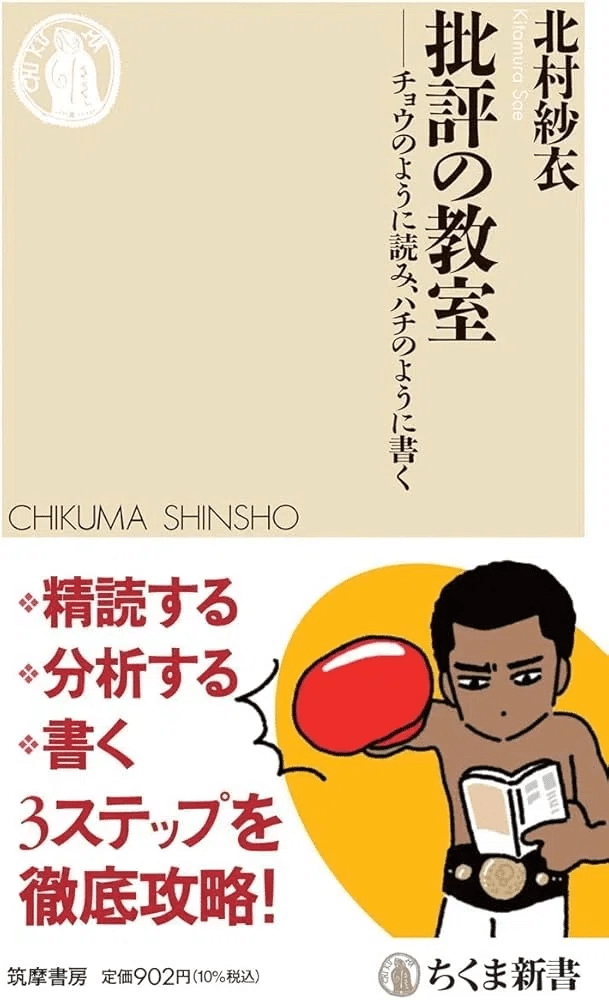
しかし、「パロディ」というのは、単なる「おふざけ」「お遊び」なのではありません。「パロディ」とはしばしば、一種の「批評」でもあるのです。
そこでは、元になった作品の「構造」を浮かび上がらせるための、ある種の「誇張」がなされるからです。
下のレビューも、そうした「おふざけに見せかけた、一種の批評文」です。
そのことに気づいた読者は多くないでしょうが、言い換えれはそれだけ「難解」な(読者に甘くない)批評文だとも言えるものなのです。
私の場合、レビューを書く際には、通常は「である体」で書きます。文末が「である。」「だ。」などで終わる形式の「文体」のことです。
これは、主に「論文」などの「硬い文章」で使われる文体ですが、「小説」の多くも「である体」が使われ、その意味では、最もベーシックな文体だと言っても良いでしょう。
一方「ですます体」というのは「手紙(私信)」などで使われることからも分かるとおり、読む人に対して「丁寧に接している」という印象を与えるものです。言い換えれば、「読者である貴方を尊重してますよ」という「印象」を「与えたい」場合に採用される文体です。
ですがもちろん、この「ですます体」が採用されているからといって、その文章の書き手が、心の底から読み手を尊重しているとは限りません。
詐欺師や誘拐犯が「丁寧で優しく親切そう」な人を装うのと同じで、「ですます体」で書かれているからと言って、書き手が読者に「丁寧で優しく親切」だとは限らないのです(見かけがふざけているからといって、本質までふざけているとは限らないというのと、逆対応しています)。
つまり、こうした「見かけ(形式)としての文体」だけで、著者の「人柄」やその文章における著者の「狙い(意図)」を判断してはいけない、ということです。
それだけで、「著者は、読者に優しそうだ」とか「読みやすようだ」なんて思ってはダメだ、ということですね。
一見したところは「ですます体」で書かれているものの方が、読者に優しそうなんですが、しかし、内容的には「である体」で書かれているものの方が、「わざとらしく読者に媚びてはいない」分、じつは「読者に誠実」な場合だって、多々あるのです。
つまり、子供じゃないんだから、「見かけだけで判断してはいけない」ということです。
これは、本の「装丁」などでも同じことです。
わかりやすく言うと、本の表紙が「きれい」だとか「かっこいい」とか「かわいい」からといって、本の「内容が優れているとは限らない」ということです。
かつての私もそうでしたが、読書経験に乏しい若い人は、ついつい「表紙」や「帯の惹句」などに釣られて本を買ってしまったりしがちです。でも、読書において肝心なのは、本の表紙や宣伝文句などではなく、やはり「中身」なのですから、表紙や惹句、そして「タイトル」を見て飛びつくのではなく、少しは「中身」を確認してから買うようにすべきでしょう。
もちろん、ちょっとページをめくってみたくらいでは「中身の良し悪し」がわかりません。
ですから、読んだことのない著者の本を買う場合には、あらかじめ、「著者」の「実績や評判」を確認するのが良いでしょう。
要は、「優れた著者」は「優れた本」を書く蓋然性が高く、そうでない著者は、そうでない本しか書くことができない、ということです。
今どきは、ちょっとネット検索するだけで、著者の「良い評判」も「悪い評判」も目にすることができるのですから、その「両方を確認した上で、どっちの意見に説得力のあるか」を「自分で判断」しましょう。
その際に大切なのは、どっちの意見が「多数派か」ではなく、あくまでもどっちの意見に「説得力があるか(具体的な説明がなされているか)」です。
この世の中、残念ながら「有力者」や「人気者」に媚びることで、その「おこぼれに与ろう」とする人が少なくありません。
そして、そんな人は、本音では「大したことない」「つまらない」と思っていても、「素晴らしい」とか「面白い」なんて、無責任な「嘘」を平気でつくものなのです。そうした「嘘」をついて、「有力者」に媚びておけば、あとで「解説」や「対談」なんかの「おこぼれ」に与かれる可能性が高まるからです。
それに、こういう「心にもないことを書くライター」というのは、そうした「書評」などの掲載媒体にとっても、使い勝手が良い。
作品を選ばず、なんでも「テキトーに褒めてくれる」からです。
掲載メディアとしても「この本はくだらないから、絶対に買うな」などという「本音のレビュー」なんかは、掲載したくないのです。
そんなものを掲載すると、「有力者」や「人気者」との関係が悪化して、損をする蓋然性が高いからです。
実際、皆さんは、こうした掲載メディアに「この本はくだらないから、絶対に買うな」なんて書評が載っているのを見たことがありますか?
ないはずです。
でも、そんな「クズ本」は、山ほどあるというのが、いつわらざる現実なのです。
「SFの9割はクズである。ただし、あらゆるものの9割もクズである。」
(シオドア・スタージョン)

でも、「二流の書き手(ライター)」というのは、「クズ本の中にもある、たった1パーセント魅力」を、まるでそれがその本の「100パーセント」でもあるかのように書く、という「99パーセントの嘘」つくのです。
そして、それを自分の力量だとさえ勘違いしている。「詐欺師としての力量」であっても自慢できると、勘違いしているのです。倫理観が麻痺しているんですね。「私は、嘘をつくのが上手い」なんて、本気で思っている。
例えば、「この人は美人だ」と書いていても、じつは「この家族の中では最も」という「限定条件」を故意に書き落とすというインチキをする。
この手を使えば、たいがいの本は「面白い」ということになるわけですが、私たち読者が求めているのは、そんな本ではないはずです。
本格ミステリ小説の世界で、「読者への挑戦状」を意図したものとして、「読者よ、欺かれることなかれ」という言葉があります。
つまり、書き手はしばしば、読者を騙そうとするものなのです。だから、読者の方も、そういうつもりで本を読まなくてはいけませんよ、という意味です。
昔の「読書術」の本に、必ずと言って良いほど書かれていたのが「批判的読書」ということですが、これは、「著者の言っていることを鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考えながら読め」ということです。
そうすれば、「読解力」や「批評力」がつくからです。
例えば、このレビューで扱っている、北村紗衣先生の、来月刊行予定の新刊『女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選』(書肆侃侃房)は、どうでしょうか?

「カワイイ表紙」だし、長いけれど、なんとなく「面白そうなタイトル」ですよね。
でも、それだけで飛びついてはいけません。「カワイイ表紙」なのは、主に「装画家と装丁家」の功績であり、著者の功績ではないからですし、タイトルの良さは、必ずしも「中身」の良さを保証しません。
昔から「看板に偽りあり」という言葉がありますが、看板だけ見てると「面白そう」「美味しそう」なのに、実際に読んでみると(食べてみると)、ぜんぜん「面白くない」「まずい」なんてことは、よくある話です。
ですから、「看板」としての「表紙(装丁)」や「タイトル」だけで判断するのではなく、「中身」で判断しなければならないし、それが簡単ではないのだとしたら、「著者の評判」で判断すれば良い、ということになるわけなのです。
例えば、このレビューが扱っている、北村紗衣の『批評の教室』一一と書くと、「あれっ?」と思った人もいるでしょう。「さっきは、北村紗衣先生と書いていたのに、今度は〝先生〟抜きなのか」と。
そうです。なぜ、こんな書き方をしたのかと言うと、一般的には「先生」が付けてあると「立派そうに見える」ということに注目して欲しかったからです。
でも「先生」がついているからといって、その人が「立派な人」だとか「力量のある人」だという保証など、どこにもないというのは、皆さん自身が、「学校」で学んできたことだと思います。
当然のことながら、「先生」と呼ばれる人にも、ピンからキリまでいて、キリの方には「汚職政治家」や「大物詐欺師」なんてのもいるのです。だから、こんな「敬称」という「看板」に騙されてはいけません。

むしろ、「批評対象」である作家や作品を語る際に「先生」を使うような評者は、(それが〝皮肉〟ではないのあれば)「ゴマすりの嘘つき」だと考えた方が無難でしょう。
こうした人は、「読者」の方を向いて「真実を伝えよう」としているのではなく、「著者」の方を向いて「気に入られよう」として、ゴマを擦っているだけである公算が高いのです。要は「心にもないお世辞」を書いている。
だから、そんな文章を鵜呑みにしてはならないのです。
(※ ちなみに、編集者などは、作家を馬鹿にしていても、一応は「先生」と呼んだりします。作家のありがたみを演出するためです)
例えば、このレビューが扱っている、北村紗衣の『批評の教室』(一一と元に戻って)については、次のような「書評」があります。
これは、日本文学の研究者である小谷野敦が、Amazonのカスタマーレビューとして書いたものを、自身のブログに転載したものです。一一つまり「無償で、好きなように書いた書評」です(※ すでに削除されています。管理者に削除されたのかも知れなせん)。
だから、次のようなものになっています。
『北村紗衣「批評の教室 ――チョウのように読み、ハチのように書く (ちくま新書) アマゾンレビュー
誰でも批評が書けるわけではない(星2つ)
2021/10/14
174pまで読んだら「初心者向けの本」とあり、私はどう考えても初心者ではないので、読むのが間違いであったと気づいた。佐藤亜紀の『小説のストラテジー』に比べたら驚くほどつまらないが、それではしょうがない。また、特別な才能がない人向けとも書いてあるが、批評というのは特別な才能がなければ書けないもので、佐藤亜紀のように読者が書けるかどうかなど無視して進んだほうがいい本が書ける。
「精読」と言いつつ映画の話が多いが、映画はどう「精読」するのか、もうちょっと実例を含めて説明してほしかった。
著者自身の作品へのコメントが面白くない。「アンソニーとクレオパトラ」や「ミッドサマー」についての部分など、「どこがオチ?」とか思ってしまう。渾身の作であるらしい「ごん狐」におけるうなぎの話もさほど面白くない。
日本の作品が少なすぎる。シェイクスピアと英文学少し、あとは最近の映画ズラーってのは若い読者にはいいのかしれんが。なお(※ 志賀直哉の小説)「クローディアスの日記」におけるおかしな点は、榊敦子が論文に書いていたので先行研究をあげておくべきだったろう。「リア王」については、シェイクスピア以外の「リア王」はみなハッピーエンドだ、というのを書いておくべきだったろう。「アナと雪の女王」について「フェミニズム映画」と一言で済ますのはいけない。ちゃんと説明しなければ。
ウィキペディアに代表者はいない(171p)とあるが、日本ではいないが他国ではいる。
いいところは、性欲に触れたところ、性欲が批評に及ぼす影響など。
売れているようで重畳です。
なお誰でもボクシングに興味があるわけではないので、題名になっている言葉も私は知らなかった。』
「つまらない」「面白くない」と、身も蓋もない感想ですが、これは小谷野の「本音」でしょう。
しかし、ここで私は、北村紗衣のために、少し擁護的に書いておきますと、この小谷野敦という人は、プロの文筆家であり、北村紗衣などよりも、はるかにたくさんの著作があって、その中には「サントリー学芸大賞」という有名な賞をもらったものもあるくらいの人なのに、わざわざ「無償の(原稿料が出ない)書評を書く」ということ(奇行・稀行)からもわかるとおり、かなり「変わった人」です。

小谷野敦としては「つまらない本が、持て囃されているのが我慢ならない」ということなのか、こうした「無償の書評」では、もっぱら「貶す」ことに専念しているのですが、そこまで「貶したい」と思える「執念(ルサンチマン)」が、並大抵のものではないのですね。
かなり、辛口で知られる私ですら、ときどき「褒めレビュー」を書くのですから、小谷野敦的な偏執は尋常ではない。
だから、上の書評など、まだまだ甘い方なのです。
たしかに「本音を表明する」というのは、とても大切なことなのですが、しかし、この人の「本音主義」は、しばしば「差別発言」として表明されたりします。
具体的に言えば、フェミニストや同性愛者を、ことさらに馬鹿にしたり、「気持ち悪い」などと蔑んだりするのです。
もちろん、そんなものが商業メディアに掲載されることなどありませんから、わざわざアマチュアと同列に「無償で書いたりする」のが、この小谷野敦という、悪趣味な人なのです。
また、そんな人なので、以前に私と接触があった(小谷野から接触してきた)際には、私は、この小谷野敦を厳しく批判しました。
なぜ批判したのかと言うと、この人は「本音で他人を批判する」のは良いのですが、うるさい相手から批判されると、途端にブロックした上で「陰口」をするなどという、卑怯なことを平気でする人だったからです。
で、私は最近、北村紗衣のことを「女性版・小谷野敦」と呼んだりもしました。
なぜなら、両者は、表面的には真逆に見えながら、その実「裏表があって、卑怯」という点では「同類」だと、そう判断したからです。
「本音を隠して、きれいごとで読者をたぶらかす北村紗衣」と「本音を語るが、そのわりにはフェアプレイ精神のカケラもない卑怯者である小谷野敦」の、どっちがマシか、などと問うても意味はありません。
どっちも「ダメ」な書き手だという点では同じことだからです。
だから、読者は「見かけ上の丁寧さや本音主義」などに騙されることなく、その書き手の「本質」を読み取れるようにならなくてはなりません。
なぜなら、それが「読解力」であり「批評能力」というものだからです。
「読み取る能力」のない人が、「優れた批評」など書けるわけがありません。実力が無ければ、良いものは書けない。
「良いものを書いているフリ」が通用するのは、読者に読解力が無い場合に限られるのです。
例えば、北村紗衣の著書は、なぜ「若者向け」の「入門書」ばかりなのでしょうか?
一一それを考えなくてはいけません。
要は、経験と知識の豊富な年配者は騙しにくいけれど、経験と知識に乏しい若者は、騙しやすく、「カモ」にしやすいからなのです。
だから、「見せかけ」に騙されてはいけません。
私のこの連載も、せいぜい疑ってかかって読んでください。
それができるような人なら、決して、北村紗衣の本を読もうなどとは、思わないはずだからです。
○ ○ ○
結局、今回は、『批評の教室』の中身に、具体的に触れることができませんでした。
この調子で書いていたら、いったい、いつ連載を終えることができるのでしょう。
しかしながら、北村紗衣の『批評の教室』が、「批評の入門編」だとすれば、私がここに書いているのは、「批評の実践編」であり「応用編」です。
だからこそ、「こうしたら批評が書ける」なんていう「嘘」は書かずに、「こうしないと、まともな批評は書けない」といった「難しい課題」を課すことになりますが、これは、小谷野敦でさえ言うとおり、『批評というのは特別な才能がなければ書けないもの』だからなのです。
しかし、それでも、単なる自己満足ではなく、「人から関心してもらえるような、人とは一味ちがった批評」が書きたいと思う人は、私が、この連載で課する「困難な課題」に挑んでください。
才能があろうとなかろうと、少なくとも、持っている「才能」を鍛え伸ばさないことには、良いものなど書けるわけがないからです。
「第1回」で書いたことの繰り返しになりますが、小手先の「策や方法」で、良い文章が書けるようになどなりません。「策や方法」が使いこなせるのは、「才能がある人」だけだからです。
だから、本書『批評の教室』で示されているような「基本的な策や方法」を鵜呑みにしてはならないのです。
知っておいて損はしませんが、それを知ったからといって、それで実践できるわけではないという現実をこそを、弁えておくべきなのです。
この連載で私が語るのは、そうした「『批評の教室』についての批評=メタ批評」なのです。だから、おのずとその内容も高度なものとなります。「ですます体」で書かれているから読みやすくはあっても、本当に理解するのは、案外むずかしい、ということなのです。
【第3回に続く】
(2024年10月11日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
