
吉田健一 「饗宴」ほか 「日本幻想文学集成16」 : 朗らかで自由で頑固だった、 酒好き犬好きおじさん
富士川義之編『日本幻想文学集成16 吉田健一 饗宴』(国書刊行会)
吉田健一を初めて読んだ。ずいぶん前から気になっていた作家の一人で、読みたい読みたいと思いながら、その機会を逸し続けてきたのだが、今回やっと読むことが叶ったのは、きっと本書を含む「日本幻想文学集成」(全33巻)を、1冊も読まないまま、蔵書整理のために手放したからであろう。
私は、吉田の英文学者(研究者)としての側面には興味がなく、興味があったのは、もっぱら「幻想小説作家」の面に限られていた。
そんな幻想小説ファンである私は、「日本幻想文学集成」についても、1990年代前半の刊行時に新刊で買い揃えたから、実に30年余にわたって寝かせ、ピカピカの新刊のまま、今回手放したというわけである。
本書を含む「日本幻想文学集成」は、コーティング(PP)のされていない白地カバーのため、カバーは擦れやすいし薄汚れやすいものだった。だから、この叢書に限った話をではないけれど、私は買ってすぐに硫酸紙でカバーをかけたし、日焼けしないように暗所で保管していた。
だから、この1、2年の間に、関西の古本屋から「日本幻想文学集成」の全冊揃いの極美本が出たら、それは私の旧蔵本だと思ってもらっていいだろう。なにしろ、1冊の読んでいないのだから、新刊書店に並んでいた状態(月報や広告の挟み込みなども)そのままで、そういうものはなかなか残っていないと思うのだ。
つい、いつものように話が脱線してしまったが、これは吉田健一の小説の特徴でもあるので、どうかご勘弁いただきたい。
開き直って言うわけではないが、そもそも「文学」というものには、決まった書き方などないのだし、さらに言えば、小説とエッセイと評論とにも、厳密な境界線など引けないのだ。
本書に収められている作品もそうで、いちおうは「小説」に分類されるだろうし、そのように呼ばれてもいるのだが、この「日本幻想文学集成」全33巻を再編集し、全9巻に編み直した「新編・日本幻想文学集成」は、一巻あたり3、4人の、似た傾向の作家がまとめられていて、その第2巻には、吉田健一のほかに、澁澤龍彦、花田清輝、幸田露伴が収められている。そして、その第2巻の帯には『エッセイの小説』と大書されているのだ。
つまり、この巻に収められているのは、「エッセイ形式の(幻想)小説」だということである。

そんなわけで、文学というものは、もともと「自由」なものなのだ。何をどう書いてもかまわない。
結局のところ、面白いものが書ければそれで良いのであって、形式にこだわるのは無意味。こだわるべきは、自分自身の個性としての「スタイル」あるいは「文体」であり、一般的な区分としての「小説」「エッセイ」「評論」といった、形式的分類概念が重要なわけではないのである。
言い換えれば、この「新編」版第2巻に収められている4人というのは、そうした便宜的な形式性から自由だった作家たちだということにもなるのである。
で、話を戻すと、私が吉田健一に興味を持っていたのは、もっぱら「小説家」としてであって、「文学研究者」としてではなかった。だから、「日本幻想文学集成」を買っていた頃には、吉田の小説の代表作である『金沢』や『瓦礫の中』といった作品の初版本を、古書として購入し所蔵してもいた。一一だが、読んではいなかったのである。


今回、初めて吉田を読むことができたのは、「日本幻想文学集成」を手放したからだろうと書いたのは、どういう意味なのかというと、要は、吉田作品の中から最初に読むのであれば、それは吉田の「幻想小説」のなかでも、短編を集めた本巻だと考えていた、それがかえって枷になっていた、ということなのだ。
所蔵する本巻を、積読の山から発掘するのは、かなりの骨だと思えるようになって、すでに久しかったから、それで読めなかったのである。
吉田の代表作は、長編の『金沢』や『瓦礫の中』なのだろうが、長編だと読みはじめて合わなねれば、かなり「しんどそう」だという印象があった。
吉田の文章は個性的で、一般には「読みにくい」とされていることくらいは知っていたから、ましてやその長編となるとと、そんな危惧があったのである。
だから、最初に読むのなら短編集だし、短編集なら、この「日本幻想文学集成」の吉田の巻だとそう考えていたのだが、発掘は困難。かと言って、新たに買う気まではない。そこまで、ぜひ読みたいというほどの気持ちもなかったのである。
そんなわけで、「日本幻想文学集成」を処分して初めて、本巻だけを再購入する気になり、だからこそ、やっと読めたというわけなのだ。我ながら、なかなか微妙な心理の機微があったのだ。
ちなみに、英米文学の研究者であり翻訳者でもあった吉田だが、吉田の翻訳業にも興味はなかった。興味はなかったが、英米文学を多少とも読んでいれば、いやでも吉田の訳業が目に入ってくるし、そのうちの何冊かは、作者や作品への興味で買ったし、そのうちの何冊かは読むこともできた。
読むことだできたものとしては、イヴリン・ウォー『ブライヅヘッドふたたび』があり、いまだに読めていないものとしては、G・K・チェスタトン『木曜の男』などがある。
他にも、吉田による訳本を色々と買っているだろうし、読んだものもあるだろうが、なにしろ訳者にはあまりこだわらない方なので、訳本が何種類か刊行されている作品については、訳者が誰だったかまでは、記憶も記録もしていないのである。

しかしまた、その訳業に興味はなくとも、小説家として、ずっと気になっている吉田健一のことだから、翻訳者名として吉田の名を見かけるたびに「(小説を)読まないとなあ」という思いにさせられて、吉田のことを忘れてしまうことはできなかったのである。
○ ○ ○
さて、本書収録作は、収録順に次のとおりである。
「海坊主」「饗宴」「或る田舎の魅力」「沼」「逃げる話」「邯鄲」「空蟬」「酒の精」「道端」「ホレス・ワルポオル」の短編10篇と、長編『時間』からその「第1章」のみ。
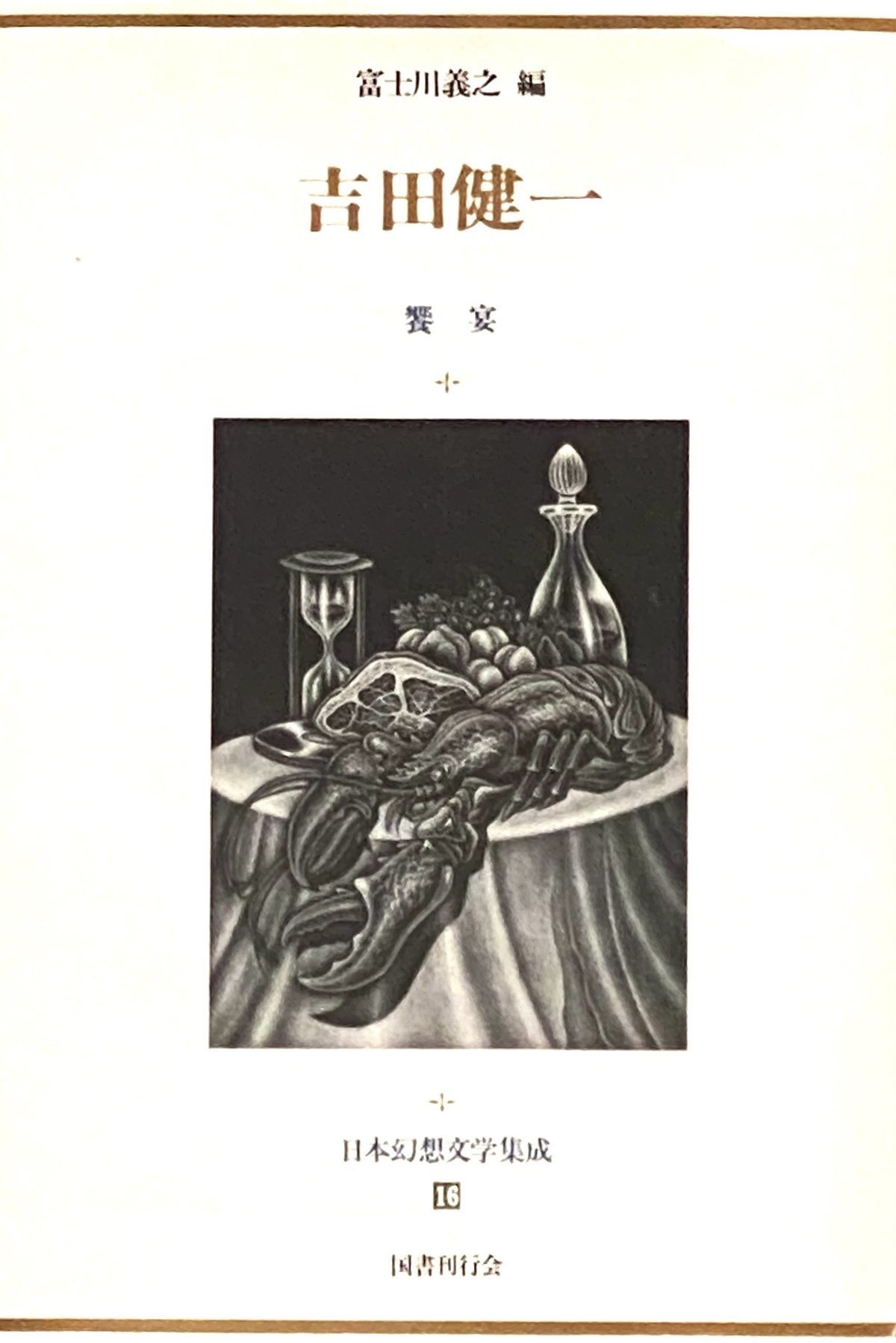
一読してわかるのは「どれも似ている」ということだ。
どう似ているのかというと、エッセイ的な書き方なのだが、話題が連想的かつ脱線的に次々と発展していって、独特の夢幻的な世界へと引きずり出してくれる、という感じの作品ばかりなのだ。
「引きずり込んで」ではなく「引きずり出して」くれる感じ。
ただ、そうした「スタイル」は共通するものの、内容的には、ノンシャランとしたものもあるば、強迫神経症的なものもある。
だがまた、すべての作品に共通しているのは、話題の転換のスピードが極めて早く、次から次へと話題がズレながら移っていくのが、ほとんど「息せき切って」という感じである点だ。こんなタイプな珍しい。
「幻想の世界」へ引きずり込んでくれる幻想小説というのは、たいがいは「徐々に」「ジワジワと」というのが多いのだが、吉田な場合は、その真逆。
そこで語られる話題がどんなものであっても、次から次へと連射的に、話題が「詰め込まれている」という感じのもので、ちょっと例を見ない、ある意味ではペダンチックな作風だとも言えよう。
また、ペダンチックとは、一般に「衒学的」つまり「学をひけらかす(風情)」という意味だが、吉田の場合、ひけらかすのは、「学」に限らず、何でもなのだ。
例えば、食道楽の「妄想」を描いた「饗宴」では、病気療養のために好きなものが食べられないので、代わりに空想の中で「食べたいものを全部、食べたいだけ食べる」という、そんな「妄想」を描いていて、とにかく高級料理から庶民的な料理まで次から次へと出てくるし、登場する店の名前も、実在したものかどうかは私にはわからないが、とにかくかなり具体的にいろいろ出てくる。有名店も、そうではない店も、ということだ。
しかも、「妄想の中なら、いくらでも食べられるから、この際に」と、好きな料理を何度もおかわりして、妄想の中でさえ満足できるほど食べた上で、次に移るといった具合で、「食通(グルメ)」を気取ったところなどは微塵もなく、ひたすら「食道楽」なのである。
つまり、この作品の場合、いろんな料理や料理店に関する情報が、山のようにと言うか、山を成して次々と提供されるのだが、それは決して「衒学(ペダントリー)」といったものではなく、ひたすらな「妄想の(爆発と言うより)暴走」であり、一種の「妄執」の無制限な発露であり、その意味での「狂気」をも漂わせるから、その「妄想」につき合わされながら、読者はあれよあれよと言う間に、「異世界」へと連れ出されることになるのである。
したがって、吉田の文章が「読みにくい」というのも、上のように「次から次へと、話題が切れ間なく展開する」というのが、その「文体」にもハッキリと刻印されているからである。
「Wikipedia」によると、
『後期の谷崎潤一郎の作風に大きな影響を受け、吉田健一の後期の文章に見受けられる句読点が極端に少なく息の長い官能的な文章には、谷崎へのリスペクトの影響がある。』
とあって、吉田の文体も「後期」ほど「うねうねと続く、息の長い、読みにくい文章」になった、ということのようだ。
しかし、そういう文章だと、私の場合は、例えば古井由吉なんかを思い出すのだが、少なくとも本巻に収められた短編を読むかぎりにおいては、そこまで読みにくいという印象はなかった。単に、良い意味で「個性的」という感じだったのである。
ちなみに、吉田健一は、1912年(明治45年)生まれで 1977年(昭和52年)に亡くなっており、作家業としては、
『1935年(昭和10年)6月アテネ・フランセを卒業。同年、ポーの『覚書』の訳を刊行、その後『文學界』への寄稿を始め、当初はフランス文学の翻訳やフランスの時事文化の流行紹介を行う。』
ということだから、著述家としての活躍期間は、戦争を挟んで「1935年(昭和10年)〜1977年(昭和52年)」ということになる。
一方、本巻に収められている小説作品は、昭和29年(1954年)の「饗宴」「或る田舎の魅力」が最も古く、それに続いて昭和30年代(1955年〜1964年)に「海坊主」「沼」「逃げる話」「邯鄲」「空蟬」と昭和37年(1962年)まで続き、そこから10年跳んで、昭和40年代(1965年〜1974年)は同47年(1972年)の「ホレス・ワルポオル」のみであり、「道端」と「時間・第1章」が昭和51年(1976年)、「酒の精」が吉田の没年である昭和52年(1977年)となっている。
つまり、小説家・吉田健一の「後期」とは、たぶん昭和40年代あたりからであり、長編小説に重点が移されてから、ということになるのではないだろうか。
前述のとおり、本巻は、全体としては決して読みにくくはなかったものの、最後の「時間・第1章」だけは、「時間とは」という問題を扱った、哲学的エッセイ風の作品で、そうした思考が、うねうねと連想的に続く文体で書かれているので、第1章だけならまだしも「これを長編でやられたら、かなりしんどいだろうな」いう印象はあった。
小説家というのは、歳をとると、一般に、短編よりも長編を描く傾向があり、文章そのものも、ゆるく長くなる傾向があって、読者としては「無意味に長い」という印象を受けもするのだが、一一しかしそれは、今の私だって同じことなのかも知れない。
そして、そういう立場から「どうして長くなるのか」その理由を考えてみると、要は「書きたいことを書きたいだけ書きたいように書く」ようになるからではないだろうか。
要は「どうせそのうちに死ぬんだから、読者に喜ばれることよりも、自分が書いていて楽しいものを書く」と、そんな具合に開き直るから、という側面もあるのではないか。一一まあ、これは、素人である私個人の話でしかないのかもしれないが。
ともあれ、本巻に収められた作品は、「お話」として「面白い」ものではなかった、と言うか、そもそもエッセイ的な書き方だから、「お話らしいお話は無い」ので、そうした意味での面白さは無くて当然なのだが、その「特異な文体」から生み出される「独自の妄想的世界」は、十分に「楽しいもの」だった。
そしてまさにこれこそが、「文学」の「楽しみ」であり「面白さ」なのだとも言えよう。
それにしてもまあ、いかにもしんどそうな長編『時間』を読む予定はないけれども、代表作である『金沢』(講談社文芸文庫から『金沢・酒宴』として刊行されている)は読む予定だし、それが面白ければ、後期の『瓦礫の中』も読んでみたいと思っている。
なお、最後にいくつか余談的なことを書いておこう。
まず、吉田健一という人は、次のような錚々たる系類を持つ人である。
『吉田 健一(よしだ けんいち、1912年(明治45年)4月1日 - 1977年(昭和52年)8月3日)は、日本の文芸評論家、英文学翻訳家、小説家。父は吉田茂、母・雪子は牧野伸顕(内大臣)の娘で、大久保利通の曾孫にあたる。』
だから、私が大嫌いな政治家・麻生太郎の叔父さんということにもなるわけだが、私としては「甥を憎んで、叔父は憎まず」であるし、さらに「Wikipedia」には、
『1967年秋の吉田茂没後は妹麻生和子(父の私設秘書として常に傍らにいた。元首相麻生太郎の母)とは、余り折り合いは良くなかったようである。』
ともあるから、「よしよし」とも思う。
それに、何よりこの人は、恵まれた環境に育ったからこそ、それをひけらかすのを嫌う「反骨心」のようなものがあったようで、そこが、「七光り」だけで生きている、甥の麻生太郎とは違うところだ。
『戦後復興の時期に首相だった父・吉田茂の実像を最もよく知る人物であるが、父の思い出を語ることは多くなかった。一説には、1941年10月の母・雪子の死後、父が長年関係があった新橋の芸者「こりん」こと坂本喜代(のち喜代子と称する)を、事実上の後妻として迎えたことに健一が反発していたからだと言われている。』
『父の国葬については頑なに反対し続けるが、周囲の説得に押され、家族の中で最後に承諾。1967年10月31日に挙行された際には、喪主をつとめた。喪服を好まず、中村光夫から喪服を借りた。』
といった記述もあるから、当たり前に「親の七光り」的なものを嫌った人なのであろうし、そうした独立した「自由人」たらんとする反骨心は、例えば、一時は親しくつきあった三島由紀夫をめぐる、次のようなエピソードにも見ることができる。
『三島由紀夫とは、1960年代前半に仲違いしている。一説によると、三島が新居に移った時、部屋に置いてある家具の値段を吉田が大声で次々と値踏みしたのがきっかけだったともいう。またジョン・ネイスン『三島由紀夫-ある評伝』(新潮社)によると、「鉢の木会」の月例会の席上、三島の書き下ろし長編『鏡子の家』(1959年9月刊)を、10月7日付けの北海道新聞の書評では「戦後小説に終止符を打つ」と高評価しておきながら、三島の面前で「こんなものしか書けないんだったら、会からは出てもらわなくちゃな」と酷評した事も大きいとされる。最終的に三島が「鉢の木会」を離脱する主因になったのは、1960年11月刊の三島の長編『宴のあと』に関し、翌年に三島が有田八郎(登場人物のモデル)と揉めて裁判になった際、有田と旧知の間柄(有田は父・茂と元同僚)だった吉田が有田側に立った発言をしたため、それが決定打になったとも言われている。』
また、次のような記述もある。
『1951年(昭和26年)5月、チャタレイ裁判の弁護側証人として法廷に立つ。』
『同年(※ 1960年)12月、亀井勝一郎編集『新しいモラルの確立』に「信仰への懐疑と否定」を掲載。』
吉田健一の「笑顔」の写真を見ると、少しも飾ったところのない「面白そうなおじさん」という印象がある反面、どこか頑固そうでもあれば「怒らせたら怖そう」という印象も受けるが、この印象は、大きく外れてはいないのではないだろうか。
また、本巻収録の作品でもわかるとおり、吉田は無類の酒好きであり、食い道楽の酒豪であったようだが、また「愛犬家」という側面もある人で、私の中では、いかにも「昭和のおやじ」という好印象がある。
一一たぶん、この人の場合も、今の私は、「作品」以上に、その「人物」に惹かれているのだろうと思う。
……………………………………………………………………………………
【付記】 梅木英治さんのこと
吉田健一とはまったく無関係な話なのだが、この機会な書いておきたいことがあるので、それを書かせてもらおう。
私は、この「日本幻想文学集成」のカバー絵と装丁を担当した、版画家(メゾチント作家)の梅木英治さんと、かつて面識があったのだ。
梅木さんは、関西在住の方だったのだが、この「日本幻想文学集成」の装画・装丁者に抜擢されて、全33巻の各巻収録作家に合わせた33枚の新作メゾチントを提供することになった。
そしてこの「集成」の刊行中に、同出版社から梅木さん自身の画集『最後の楽園』も刊行され、その展覧会が神戸で開催されたので、私はそちらへ足を運び、メゾチントを何枚かと画集も購入し、それにサインもいただいた。
また、同「集成」の刊行が完了した際には、その表紙画作品による展覧会も開催されたから、梅木さんとは、そうした間に2、3度は顔を合わせ、お話もさせていただいたのだ。

で、この梅木さんは、私からすれば、十以上年上の「中年のおじさん」で、お酒好きであったせいか、すこし酒焼けしたような赤ら顔の、ざっくばらんで朗らかな人、という印象が強かった。
だが、梅木さんの作品については、必ずしも私の「好きなタイプ」なわけではなかった。
私は「硬質重厚」なタイプの絵柄が好きだったのだが、梅木さんの個性は、その逆に近かったからだ。


だから、私が購入したのは、「日本幻想文学集成」の表紙画や、画集『最後の楽園』に収められたカラフルな「南方幻想」的な作品ではなく、梅木さんの作風としては、むしろ異色の部類の作品で、もとは中井英夫の未刊に終わった限定本『光あれ』(だったか?)用に制作された版画ほかの数点ではなかったかと思う。
で、そんなわけだから、「日本幻想文学集成」の刊行が終わってからは、梅木さんの展覧会に行くこともないままだったのだが、関西で開催される好きな作家(画家)の展覧会には、当時はちょくちょく顔を出していたので、同じ関西在住の作家から、たまに梅木さんの話題が出ることもあった。
ところがある時、そうした画家の一人だったか、画廊の主人からだったかはもう失念してしまったが、梅木さんが「自殺した」ということと、「亡くなる前にYouTubeに、お別れの挨拶みたいな内容の動画をアップしていて、それを視た」というような話を聞かされた。
私は、梅木さんのことを「陽気な酒好きおじさん」だとばかり思っていたから、まさか自殺するなんてとショックを受けたし、それでもやはり、その映像を見ないではいられなかったと思う。
「思う」というのは、梅木さんがカメラの方をに向って話している上半身映像のイメージは残っているのだが、その内容はまったく記憶に残っていないからで、もしかするとこれは、聞かされた話からイメージされた「擬似記憶」なのではないかという疑いが捨てきれないからである。
梅木さんの作風からして、作品が一般ウケするということはなかっただろうから、作家一本だけで食っていくのは大変だったはずだし、多くの画家が教職を兼任しているように、梅木さんもそうした兼職を持っていたのかもしれない。
だが、いずれにしろ、あんなに「呑気そう」だった人がと思うと、他人の人生などまったくわからないものだと思うし、自分の人生だって大差ないものだろうというような思いがあった。
私が、生活費だけは堅実に確保しつつも、とにかく好きなことをして生きていこうと考えるようになった一因には、梅木さんの自殺ということも小さくはなかったのではないかと、そう思っているのである。

(2024年7月27日)
● ● ●
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
