
北村紗衣 『批評の教室』 : 作品批評【実践編】(第1回)
書評:北村紗衣『批評の教室 チョウのように読み、ハチのように書く』(ちくま新書)
北村紗衣という人を少しでも知っている読者にとっては、とてもとても「痛い本」である。
どういうことかと言うと、本書に書かれていること、それそのものなら「批評入門」としては、ごく常識的なものであり、可もなく不可もないレベルの、まさに初心者に向けた入門書なのだが、いかにも「痛い」のは、本書に書かれていることを、著者である「武蔵大学教授」で「フェミニスト批評」家を自称している、北村紗衣当人が、まったく実践できていないためである。
だから、読んでいて「痛い」のだし、著者の北村紗衣は、自分が、そうした「当たり前の批評」を実践できていないことを自覚しつつを、本書を書くことで、その事実読者の目から隠蔽できると、そう思っていることが透けて見えてしまうので、その浅はかさがまた、より「痛い」と、否応なく感じられてしまう。
私は、本書を読む以前にすでに、北村紗衣の「映画評」を論じて、次のように書いている。
『たしかに、(※ 映画の見方などについて)基本的な知識を年若い学生に説くくらいのことなら、本を読んで知識さえ蓄えていれば可能であり、特に才能など必要はないが、優れた(面白い)「批評」というのは、センス(鑑賞眼、洞察力)が無くては、できないことなのだ。
基本的な知識を持たない者に基本的な知識を説くだけ、簡単な質問に答えるだけなら、機械にだって出来ることで、インスピレーションをうむ批評的な才能など無くても可能なことでしかないのである。』
これは、北村紗衣教授に関して書いたことなのだ。
本書はまさに「まともな批評を書けない人による、借りものの知識を駆使した、批評の書き方入門」なのである。
だから、本書を読んでも、決して、批評を書けるようにはならない。
「批評の書き方」を知悉しているはずの、本書の著者である北村紗衣自身が、実際には「水準を満たさない批評文」しか書けないのだから、この本を読んだだけで「まともな批評」が書けるようになる道理などないのである。

まあ、こうしたことは、ある程度の年齢に達した「大人」には、常識的な話でしかない。
つまり、『漫画家入門 これで君も漫画が描ける!』とか言ったような本や、『俳優入門 演技の基本』といった本を読んだところで、それで漫画家や俳優になどなれないというのは、人生経験を少しは積んだ「大人」には、わかりきった話でしかない。
では、どうして、「本を読んだだけ」では、漫画家にも俳優にもなれないのだろうか?
それは無論、本を読むだけではなく、それが「実践」できなければならないからなのだが、この「実践」においては、書物から得た知識だけでは、まったく不十分だからである。
例えば、漫画家を目指していくらデッサンを重ねたところで、絵を描く能力には、明らかに「持って生まれた才能」の差という残酷な現実があり、そんな才能をどの程度持っているかで、結果は大きく変わってくる。
つまり、こうしなさいと言われても、それを実践するだけの才能がなく力量の(伸び)ない者は、それを実践したくてもできないのだから、おのずと漫画家にはなれない。
そのため、少なくとも画力以外のところで勝負するしかないが、絵が下手くそな漫画家が、それでも食えるようになるには、別の才能がないかぎりは、とうてい無理。
そして、この「別の才能」というのを持っている人というのも、これまた滅多にはいない。
したがって、いくら『漫画家入門』を読んだところで、実際に漫画家になれる人は、めったにいないのだ。

下手でも何でもいいから、ひとまず漫画が描けるようになれれば良いというレベルでかまわないのなら、わざわざ「入門書」など読まずとも、良い作品をいろいろ読みながら、ひたすら描けば、それはそのレベルになら達することも可能ではあろう。
無論、これは「俳優」についても同じだ。
いくら「入門書」で演技の基本を学んだところで、そもそも「演技のセンス」が無ければ、本で学んだことを実践するのは不可能だ。だから、俳優にはなれない。
ただし、「別の才能」としての「並はずれた美貌」などがあれば、俳優デビューすることは可能であり、また「大根役者」などと陰口をされながらも、演技力など気にしない大衆の支持によって、職業俳優を続けることさえ可能かもしれない。
しかし、その人は「演技以外で、俳優をやっている人」でしかないのである。
北村紗衣などは、まさにこのパターンであろう。だから私は、北村を「大根評論家」とか「タレント教授」などと呼んだのである。単なる悪口、あるいは誹謗中傷などではなく、根拠のある批判なのだ。
なお、北村紗衣の読者は知らないだろうから、いちおう説明しておくと、ここで言う「批判」とは、「否定的な評価」のことではなく、価値中立的な「批評」のことでしかない。つまり、本来の意味での「批判」とは、褒めても貶しても「批判」なのである。
なにしろ「批判」の「批」とは「比べて、よいわるいの品定めをする。是非を言いわける。」という意味なのだから、「批判」とは「比べて、是非を判ずる」ということであり、だから「これは優れた作品だ」という評価を与えることも「批判」のうちなのだ。
そんなわけで、私が北村紗衣を「大根評論家」とか「タレント教授」などと呼ぶのは、単なる悪口、あるいは誹謗中傷などではなく、根拠のある「批判」なのである。
実際、北村紗衣の魅力に当てられて、支持者になったと公言している人もいる。
北村紗衣を誹謗中傷をしたとのことでスラップ裁判にかけられ、のちに敗訴して慰謝料200万円他をむしり取られ、さらには大学講師の職を追われた、かの山内雁琳に対して、次のようなことをすすめるほど、北村紗衣推しを公言する御仁である。
植村恒一郎@charis1756
雁琳さんは北村さんに会ってないよね。彼女は僕には観劇の知人ですが、十年近く前、三軒茶屋の劇場トラムで初めて見かけた彼女は、深紅のジャケットに純白のベレー帽で、それはそれは可愛いお嬢さんでした。僕と議論すると尖がった表情になり、凄く知的です。雁琳さんも彼女に会えば惚れますよ
(^^) twitter.com/ganrim_/status...
2023-04-26 21:32:43
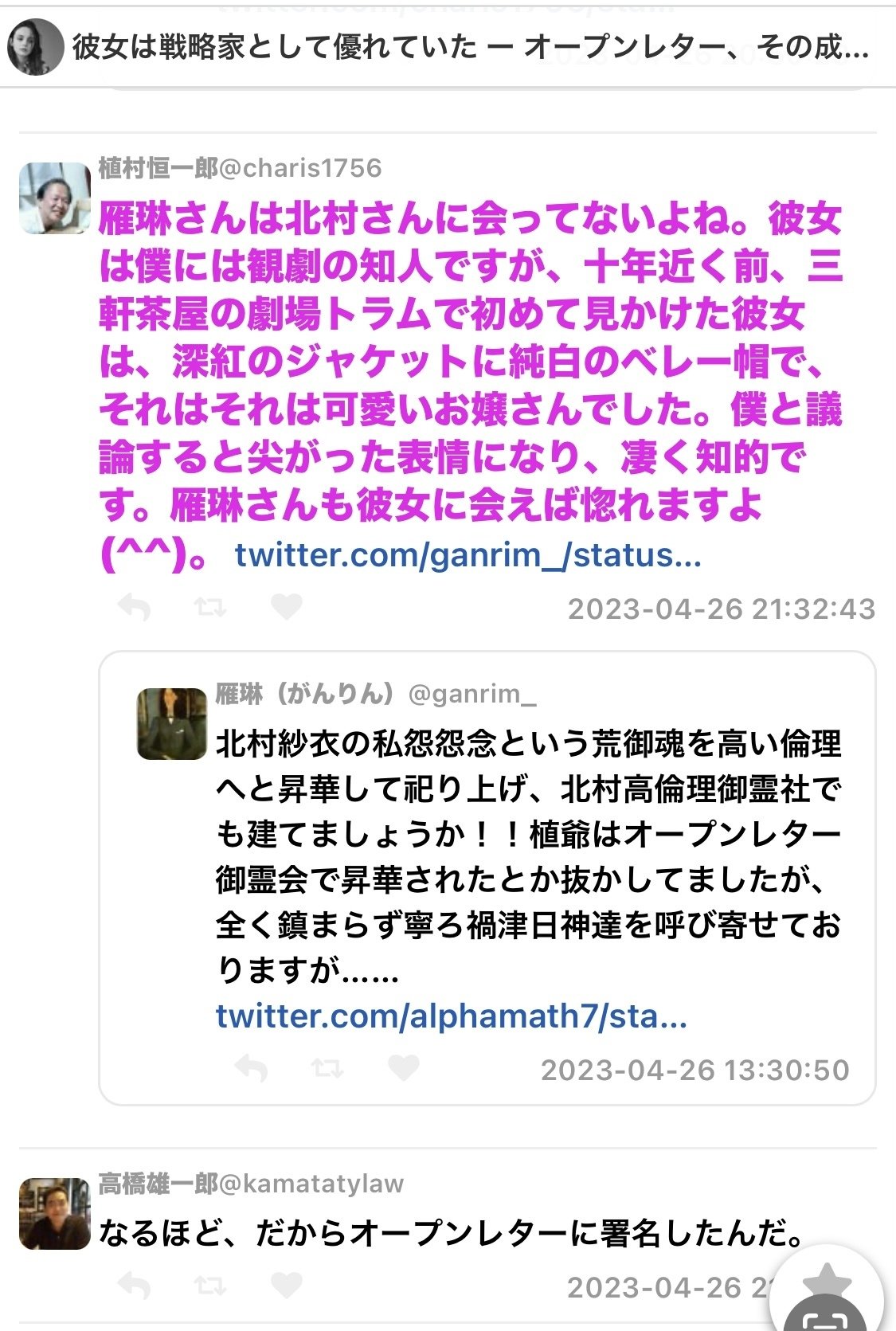
この人は、カント哲学をやっている哲学教授で、かの「オープンレター」にも署名した、当事者の一人である。
すでに大学は退いているようだが、どういう目で、北村紗衣を見ていたかはハッキリとしていよう。
また、北村紗衣自身も、女だから女を売りにする気はあったようで、自著『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』 の帯の惹句にある『(※ 女)「らしさ」の檻を解き放ち、空を飛』ぶ気は、ほとんど無かったようである。

もちろん、「男性社会であるアカデミズム」の中で、成り上がるために、ことさらに年配の男性教授に媚びたというわけでもないだろうが、「ツン」は「ツン」で、この植村恒一郎のように「たまらん」という趣味の人も少なくないし、勝手に鼻の下をのばした男性教授もいただろう。またそれで、あとで「アカハラ」呼ばわりされるのを怖れ、下僕同然の立場になったとしても、もしかすると、それはそれで喜んでいるのかもしれない。マゾとは、そういうものなのである。
また、北村紗衣の文章ではなく、北村紗衣の女としての魅力にやられた人が少なくないという事実は、他にもある。
例えば、常識的に言って、すでに若くはない北村紗衣を、いまだ自称どおりに「さえぼう」と呼んで、子供でも「愛でる」ようにしている、屈折したロリコンじみた酔狂な人たちも、何万人だか実在するのだから、北村紗衣が、自身のそんな特殊な魅力に、無自覚でなどあろうはずがない。
そうでなければ、『深紅のジャケットに純白のベレー帽』なんていでたちをするわけもないのだ。
私もまた、植村恒一郎の例のような、こんなにわかりやすい「当事者証言」を知る前から、『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』のレビューで、同書所収のエッセイ、
・愛の理想郷における、ブス 一一夢見るためのバズ・ラーマン論
を論じて、次のように指摘していた。
すなわち、
北村紗衣がバズ・ラーマンを論じたのは、普通では使えない「ブス」という言葉を、心置きなく使うためであった。
北村は、このエッセイのなかで「自分もブスのうち」のように語っているが、それは「ブス」という言葉を公然と使うための手形を得るためのアリバイ工作でしかなく、無論ホンネとしては「私はブスではない」と思いながら、「ブス」を自称することで、「ブス」という言葉を使えるのを痛快だと感じている。そんな自身の本音を隠して、このエッセイを書いていたのだ。一一と。
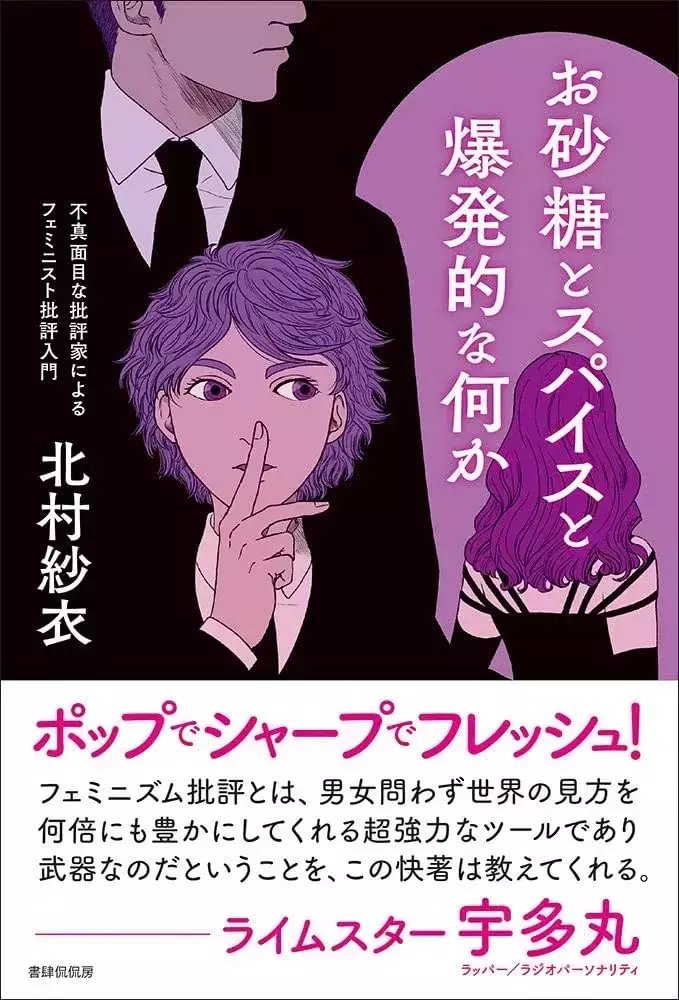
つまり、批評家としての才能が無いのに、曲がりなりにも批評家になれたのは、当然、北村紗衣には「別の才能」があった、ということである。
『深紅のジャケットに純白のベレー帽』など、似合わないと思っていれば着はしないだろうし、ならば、ダテや酔狂で着たわけではないのである。
ともあれこのように、漫画家であれ、俳優であれ、あるいはアスリートであれ、小説家であれ、批評家であれ大学教授であれ、多くの人が憧れる職業というのは、間違いなく、「入門書」を読んだくらいでなれるようなものではない。
なぜなら、なりたい人が多いということは、競争率が高いということであり、競争率が高いということは、求められる水準もおのずと高くなるため、「なんらかの才能」がなければ、そのなかを勝ち抜くことはできないからである。
もちろん、俳優を含めた「タレント」の世界では、「タレント」としての才能は無くても、「別の才能」として、「親の七光り」だとか「枕営業」といったことで、タレントになりおうせる人もいるだろう。
つまり、手段を選ばなければ、なれないこともないのだが、しかしそれを実践するためには、もちろん「有力者である家族親族の存在」だとか、「人の性的欲望をそそる身体」だとかいった、一種の「持って生まれたもの」が無ければ、それとて叶わない。
ただし、そもそも「そんな恥ずかしいことはできない」という「羞恥心」なり「倫理観」のある人には、その条件を備えていてすら、そんなことはできないのだ。
言い換えれば、「羞恥心が無い」とか「倫理観に欠けている」といった、特別な「負の才能」を持っていないかぎり、たとえ親族に有力者がいようと、セクシーな肉体の持ち主であろうと、それを使うことで目的を達するようなことは、できない。
「取り巻きを上手に利用する、ファンネル・オフェンス」なんてことも、恥ずかしくてやれるわけがない。

そして、これは「批評」あるいは「批評家」とて、同じことなのである。
無論、アマチュアとして、漫画を描くとか、演劇をやるとか、スポーツをやるのと同じ意味で、批評をやるのなら、「才能」などは不用だ。
要は、下手くそでも、読めたものではなくても、本人がそれで楽しくやれるのであれば、それはそれで「良い趣味」なのである。
しかしながら、アマチュアでやるとしても、やはり人は「できれば良いものを書きたい」と願うものだ。
プロにはなれないとしても、少なくとも、読んだ人が感心してくれるようなものが書きたい。場合によっては「下手なプロよりよっぽど良い」と言ってもらえるようなものを書きたいと、そう願うのが人情というものである。
だから、本書『批評の教室』の読者の多くも、プロの批評家になりたいとまでは思わなくても、せめて、読んだ人が感心するような批評を書けるようになりたいと、そう願って、本書を手に取ったのではないだろうか。
しかし、そんな夢をぶち壊すようで恐縮だが、本書を読んだところで、「まともな批評文」が書けるようには、決してならない。
それは、誰よりも、本書の著者である北村紗衣が、その身をもって「実証」している、残酷な現実なのである。
「チョウのように読み、ハチのように書く」ようには、なれない。ご当人が、そうはなっていないのだ。
それは、本書で語られるようにして書かれたはずの、先の2著にも明らかだということを、私は、批判者としての筋を通して、具体的に実証しておいた。
そもそも、文学派の私から言わせると、このサブタイトルも、モハメッド・アリの名言「蝶のように舞い、蜂のように刺す」を踏まえているというだけで、北村紗衣によるそれは、じつに語呂が悪いし、その意味で、北村紗衣は文章センスもないのである。
いかにも、勉強ができる人らしく、無難な文章ではあるとしても、文体が無いのだ。
そんなわけで、本書の読者は、決して本書に過大な期待をしてはならない。
繰り返すが、「知識を得ること」と、それを「実践すること」の間には、乗り越えがたい逕庭が、厳然と存在しているのだ。
そのことは、将来を誤らない為にも、是非とも心得ておくべきだ。
当然のことながら、商業出版された書物の場合、保証もできない夢を煽るような書き方のなされていることなど珍しくはなく、当然それは「本を売るため」、夢見るカモを捕えるためなのだと、心得ておくべきであろう。
まして、提灯書評など真に受けるのは、いかにも愚かである。
「この本を読めば、優れた批評文が書けるようになるかも」という期待は、残念ながら、非現実的であり、「過剰な期待」なのだ。
無論、批評文を「読む」上での知識として、本書に書かれているような「批評の基本」を知っておくことは、あながち無駄ではないだろう。
だが、そもそも「作品」をより深く鑑賞するために批評文を読んでいるはずなのに、その批評文をより深く読むために「批評入門」や「批評理論の本」を読むというのは、冷静に考えれば、いかにも迂遠な「本末転倒」でもあろう。
そんなことをしている暇があれば、いろんな名作をたくさん鑑賞し、その目を養った方が良いに決まっている。
良い作品を知らない者が、モノの良し悪しを見分けられるわけもないからである。
だから、安直に「なれる」系の入門書など読むのではなく、良い小説、良い映画を見ることで、まずは自分の目を養うべきなのだ。
その上で、良い批評・評論が書けるようになりたいのであれば、「一流の評論」を読めば良い。
それを読んで、その着眼点やロジックの素晴らしさを堪能して、心から面白いと思えば、借り物の批評理論になど頼ることなく、「自分の目で見たことを自分の言葉で語る」ということの重要さと素晴らしさを知ることになるだろう。
「優れたものに数多く触れる」という実践の中で、その人なりの読解力も批評眼も、養われるのである。
そして、そうした正攻法に比べれば、昔の作品をつかまえて、やれ「男性中心主義」だの「ヨーロッパ中心主義」だのと指摘してみせたところで、それは所詮「猿回しの猿」の芸にすぎない。
そこには、批評における「主体性」が無いからだ。
ではなぜ、本書のようなつまらない本を読んで、「王道」を進もうとはしないのかと言えば、それは「才能のない人ほど、楽をして結果を出そうとしがち」だからである。
つまり、「近道」や「抜け駆け」をしたい、楽に結果を出したいという思いがあるから、そういう「策に走ってしまう」のだが、もともと「才能の無い人」が、そんな「小手先の策」で、まともな結果など出せるわけがない。
だいたい、楽をして金儲けしようとする人が、投資詐欺に引っかかるのであり、それと同じことなのだ。
特別な才能もないくせに、「額に汗して働く」ことを軽んずるような馬鹿者が、こんな本を読んで、あっさり騙されては喜んでいるのである。

まあ、こんなものを読んで、それでも何らかの結果を出せたとすれば、それはそもそも、その人に才能があったからで、その「策」をもうまく利用できたにすぎないのである。その人は、もともと「才能」があったのだ。
だから、本書を読んで、それで「面白い批評が書けそうだ」と、そう思った人は、それは「幻想」にすぎないと、自身を戒めるべきであろう。
繰り返すが、「知識だけでは、どうにもならない」という「現実」は、誰よりも、本書著者である北村紗衣が、その身をもって実証してくれているのだ。
そして、「読める読者」とは、そのことに気づける読者であり、「読めない読者」とは、本書の字づらに惑わされて、書けるような気になってしまった読者である。
催眠商法の会場などへ誘われて行き、うっかりその場の空気に乗せられて、高い買い物をしてしまうようなタイプなのである。
○ ○ ○
さて、以降は、本書著者の北村紗衣が、批評家ではあっても、「三流の批評家」でしかないという現実を、具体的かつ実証的に説明していこう。
なお、タイトルにもあるとおり、今回は、北村紗衣の著書『批評の教室』を分析的に論じる本稿「アンジノソトニデロ…」の「第1回」とした。
普通であれば、書評の「連載」などいう間抜けなことはやらないのだが、本書『批評の教室』の場合は、あまりにも「ツッコミどころ満載」であったため、それを一本のレビューにまとめるには、どうしても何を拾って何を捨てるかと取捨選択が必要となる。
だが、そんなことの頭を使うのは、本書を論じることよりも、よほど面倒なので、それでは「頭から順に」論じていこう、ということになったのだ。
もっとも、構成の都合上、話題は前後することになるだろうが、基本的には、本書『批評の教室』の目次に沿うかたちで進める予定である。
したがって、「第1回」となる今回は、連載における「基本線」を示した「序章」だと理解してもらって良い。
あとは、以上で書いたことを、個別実証的に論じていくだけだとも言えよう。
言い換えれば、ここまでの「序章」部分に深く納得した結果、
「北村紗衣って、今は人気があるのかもしれないけど、結局は、どうしようもない、ポンコツ評論家なんだな。宣伝に乗せられて北村紗衣を読むなんてことは辞めておこう。時間とお金の無駄だからな」
と、そう思った人は、以降を読む必要はないだろう。
読む必要があるのは、
「そうは言っても、あれだけ人気もあれば、大学教授でもある人なんだから、そんなに酷くはないんじゃないかな?」
と、そう思っている人である。
私は、そういう「半信者」や「信者」たちの「洗脳はずし」のために、以降を書いていくのだ。
というわけである。

「あなた方が、いかに信じたかろうとも、麻原彰晃や大川隆法や池田大作が〝にせ・覚者(ブッダ)〟であったように、北村紗衣もまた、その肩書とは別に、その実質としては、偽物なのだ。だから、目を覚ませ」
と、そのように私は、教え促したいのだ。
(2024年10月5日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
