
フランソワ・トリュフォー監督 『華氏451』 : 映画ファンは何を見ているのか?
映画評:フランソワ・トリュフォー監督『華氏451』(1966年・イギリス映画)
アメリカのSF作家レイ・ブラッドベリの名作『華氏451度』の映画化作品。フランス映画界「ヌーヴェルヴァーグ」の旗手として知られるフランソワ・トリュフォーが、初めて英語で撮った作品だが、その評判は良くない。

「ヌーベルヴァーグ」は、もともとは旧来の「撮影所システム」には乗らない「低予算」制作のゆえに、若い作家でも映画が撮れ、その新鮮な感覚を活かせるという特性があった。
だから、トリュフォーと同じく、「ヌーヴェルヴァーグ」の代表選手であるジャン=リュック・ゴダールは、人気作家になった後も、ハリウッド的な大資本映画には抵抗し続けた。大資本のゆえに、映画作家は大衆ウケするエンタメ作品ばかりを要求され、本来の自由な表現が制限されて、映画本来の可能性がせばめられていると考えていたからである。
トリュフォーとゴダールは、「ヌーヴェルヴァーグ」の2大スターとして、大資本による映画製作体制には反対の立場だったのだが、トリュフォーの場合は、人気作家となってしまうと、ハリウッドへの進出を窺うようになった。そのため、ゴダールはこれに反発して、二人の仲は永遠に決裂することになる。
本作は、イギリス映画になっているが、これも本来は、ハリウッドでの制作を目指して企画されたものがうまくいかず、結果としてイギリス資本による製作となったもの。本作の背景には、そうした事情もあるのだ。
さて、前述のとおり本作は、トリュフォー作品の中では、評判のよろしくない作品である。
実際、私が見てみても、パッとしない作品だとしか評し得ない。
「Wikipedia」にもあるとおり、
『読書好きのトリュフォーらしく、書物への愛に満ちている。トリュフォーは「『宇宙もの』とか機械やロボットの出てくるものには生理的な嫌悪感をおぼえる」と公言するほどのSF嫌いであるため、この映画からもいわゆる「SF的な」要素や演出はなるべく排除され、人間ドラマにスポットが当てられている。』
(Wikipedia「華氏451」)
とあるとおりで、トリュフォーは、SFSFした作品が好きではなかった。
しかし、ここで勘違いしてはならないのは、トリュフォーのこうしたイメージは、彼が翻訳で読んだ「アメリカSF」は1950年代のごく初期のSF小説であって、「宇宙船と美女とBEM(bug-eyed monster)」といったパルプマガジン的なイメージが強かったからで、現代のSFを知らない段階での認識だったのだ。つまり、いくらトリュフォーが読書家だったと言っても、その読書は、生年や年齢や使用言語に限界づけられていたという事実を見落として彼を責めたのでは、それもフェアな評価とは言えないだろう。

ともあれ、そんなトリュフォーが撮った映画なので、今の私たちすると、かなり「野暮ったい」という印象をまぬがれ得ない。
これがフランス人のセンスだと言ってしまえばそれまでなのだが、アメリカSF的な美学を拒絶するのであれば、それに抵抗するだけの別のもの(美学)を打ち出す必要もあったのだろう。例えば、変則的ながら『バーバレラ』(1964年、ロジェ・ヴァディム監督)のようにだ。
だが、残念ながらそこまでのものは、トリュフォーにはなかったということだったのであろう。
しかし、本作の最大の弱点は、そこではない。
ビジュアル面は仕方がないとしても、肝心の「人間ドラマ」が説得力を欠いているのだ。これでは評価のしようもないのである。
どういうことかと言うと、要は、主人公である「ファイアマン(消防士)」のモンターグが、国家によって所有さえ感じられた「書物」というものに惹かれていく心理過程の描写に説得力がなく、「普通はそんなことはしないだろう」というほど、安易に書物に接近していくのだ。

書物を見つけて焼却処分にするのが仕事である「ファイアマン」のモンターグなればこそ、「書物」が政治権力からどれほど危険視されており、それに惹かれる者を「反社会勢力」として、社会から排除しようとしているのも重々承知しているはずなのに、書物を愛する謎の女性クラリスと出会い、「あなたは、書物なんてくだらないと言うけれど、その書物を読んだことはあるの?」と問われて、初めて「読んだことがなかった」ことに思い至って「否定するからには読んでみよう」と思い立ったという経緯は、いくら何でもナイーブすぎる。

彼が、そんなことを真面目に考えるような人なのなら、他人から指摘されるでもなく、自分一人で「どうして、書物はここまで禁じられるのだろうか? 書物とは、本当にそんなに悪いものなのか?」という程度のことには、十代のうちに考えたはずだし、自分でそうした疑問を持てないような「社会倫理の盲信者」なのであれば、美女から問われた程度のことで、そんな気持ちにはならないだろう。彼女の気を惹くために本を読んでみたという方が、よほど説得力もあろうというものなのだ。
言うなれば、この映画のモンターグは、美女が「貴方は、麻薬をやったこともないくせに、それが悪だと言うの?」と言われて、そりゃそうだと覚醒剤を試してみる、警察官みたいなものなのである。


そんなわけで、本作は、肝心要の「人間描写」のところで「雑」なのだ。映画の「尺の問題」はあるにしても、あまりにも「雑」な部分が多い。
例えば、モンターグが、夜中に妻とのベッドから抜け出して、手に入れた本を居間で読むというのも、所詮は「頭隠して尻隠さず」。
いずれ妻が気づいて大騒ぎになるのは分かりきった話なのに、モンターグは、まるで子供のように無防備にも読書に耽溺し、きっちり妻に見つかって口論となり、最後は密告されることにもなるのである。
この他にも、書物を秘蔵していた人の家へとファイアーマンとして出動し、家宅捜索に入った際、燃やされる書物の中から、こっそりと1冊の本を、自分のカバンに詰め込んで持ち帰るとかいうのも、いくら本を救うためとは言え、そのやり口が「制服警官が、盗難現場の臨検に入って、物を盗む」ような、お粗末さなのである。
これでは、モンターグの「犯罪」が発覚するのは、どうみても時間の問題でしかなく、忌憚なく言えば、モンターグは馬鹿にしか見えないのだ。
したがって、この映画は、「SF映画」として失敗している以前に、「人間ドラマ」として失敗しているから、見るべきところのない作品になってしまっているのである。
ちなみに、本作の「ストーリー」は、次のとおり。
『徹底した思想管理体制のもと、書物を読むことが禁じられた社会。禁止されている書物の捜索と焼却を任務とする「ファイアマン」のモンターグ(オスカー・ウェルナー)は、偶然出会った可憐な女性クラリス(ジュリー・クリスティ)の影響で、本の存在を意識し始める。テレビのままに動く無気力な妻リンダの空虚な生活と違い、クラリスは本に熱意を持っていた。チャールズ・ディケンズの『デイヴィッド・コパフィールド』から読み始め、活字の持つ魔力の虜となったモンターグ。だが、彼を待っていたのは、リンダ(クリスティ2役)の冷酷な裏切りと、管理体制からの粛清だった。モンターグはファイアマンを辞職することを申し出たが、そのまま出動。目的地は彼自身の家。モンターグが家そのものまで焼こうとすると、制止して逮捕しようとした隊長にモンターグは火焔放射器を向けて殺害。殺人犯として追われ、淋しい空地にたどりつく。そこはクラリスが話していた「本の人々」が住む国だった。人々は全ての本が焼かれても物語を後世に残せるように本を必死に暗記していた。モンターグはエドガー・アラン・ポーの“Tales of Mystery & Imagination”の暗誦を始める。』
(Wikipedia「華氏451」)

○ ○ ○
なお、私が本稿で問題としたいのは、本作が「評判どおりの失敗作」だということではない。
そんなことは、いまさら言うまでもないことだし、また、本作が「禁書(焚書)による思想統制の話」だから「他人事ではない」というような、「型通りの陳腐な感想」を語りたいのでもない。
そうではなく、本作トリュフォー版『華氏451』を見た「映画ファン」が、本作のテーマを、ろくに理解していない点を、問題視したいのだ。
本作は、原作がそのように受け取られてきたから、この映画版も「禁書(焚書)による思想統制の話」だと思い込んで、そうした「型通りの陳腐な感想」で済ませている人が多いようなのだが、本作のテーマは、そういうことではないし、そこに気づいていない点で、「映画ファンは、いったい何を見ているのか」と、そう言いたいのである。
原作の「Wikipedia」には、ハッキリと次のような記述がある。
『愚民政策を題材とした作品として語られることが多いが、ブラッドベリ自身は『この作品で描いたのは国家の検閲ではなく、テレビによる文化の破壊(a story about how television destroys interest in reading literature)』と2007年のインタビューで述べている。』
(Wikipedia「華氏451度」)
つまり、これは「映像文化による大衆の痴呆化を嘆き、それに警告を発した作品」なのだ。
だから、映画ばかり見ている、ほとんど本を読まないような「映画ファン」は、まさに自分が批判されているということに気づかなければならないのだが、本も読まないからこそ、ブラッドベリやトリュフォーの危惧したとおりに、ろくに映画の内容も読み取れない人間になってしまっているのである。
私がこのように言うのは、何もブラッドベリのこのインタビューの存在を知っていたからではない。
本作で最も印象的なのが、そのオープニング・タイトルバックで、家々のテレビアンテナばかりが次々と映し出されるという点だからなのだ。これを見れば、普通は「なんだこれ?」と引っ掛かりを覚えて当然なのである。


活字情報が禁止されているためスタッフロールは無く、ナレーションで紹介されるという演出)
しかも、本編の中でも、当然のことながら本を読まないモンターグの妻は、「テレビ」に依存した生活をしており、およそ物を考えるという習慣のない人間として否定的に描写されており、結婚記念日すら記憶していないとモンターグを嘆かせたりもするのだが、当然このあたりは、「映像文化の問題点」を、批判的に誇張して描いた部分なのだ。

つまり、原作の「Wikipedia」によると、「あらすじ」紹介も次のようになる。
『舞台は、情報が全てテレビやラジオによる画像や音声などの感覚的なものばかりの社会。そこでは漫画以外の本の所持が禁止されており、発見された場合はただちに「ファイアマン」(fireman、焚書官または昇火士)と呼ばれる機関が出動して焼却し、所有者は逮捕されることになっていた。(表向きの)理由は、本によって有害な情報が善良な市民にもたらされ、社会の秩序と安寧が損なわれることを防ぐためだとされていた。密告が奨励され、市民が相互監視する社会が形成され、表面上は穏やかな社会が築かれていた。だがその結果、人々は思考力と記憶力を失い、わずか数年前のできごとさえ曖昧な形でしか覚えることができない愚民になっていた。』
(Wikipedia「華氏451度」)
もちろん、「本を読まなければ、馬鹿になる」とか「映像作品ばかりで満足している人間には、思考力が育たない」などと、いちがいに決めつけることはできない。
また、このトリュフォー版『華氏451』を見て、「禁書(焚書)による思想統制の話」だと、よそで聞き齧ったことを、まるで自分の意見ででもあるかのように語ってしまうような、頭の働かなくなった「映画ファン」が少なからずいたとしても、それは「世間の平均的知能」が低下したということではなく、社会の中では「少数派だった読書家」と、今の「映像文化における大衆」とでは、その人口(分母)が桁違いであることから、おのずと「平均値」が下がったということでしかなく、また、そんな人たちでも、得々と「聞き齧りでしかない持論を語るようになった」という、「SNS」文化のせいでしかないのかもしれない。
しかし、少なくとも表面的に見れば、ブラッドベリやトリュフォーが指摘したように「本も読まないような人間が増え、馬鹿が増えた(のではないか)」という批判には、「映画ファン」ならば、真面目に考えなければならない問題提起が含まれていよう。
本当に、映画ばかり見ていて、ろくに(活字の)本も読まないような人に、人が感心するような知性を持った人がいるのか? いるとしても、それは1,000人に1人なのか? それとも数万人1人なのだろうか?
映画ファンとして、映画を辱めたくないのであれば、せめて多少は活字の本を読んで、自身の知能を鍛える努力の必要も認めるはずだ。

なぜ、「映画オタク」であるトリュフォーが、「映像文化の広がりを危惧」する本作の原作、ブラッドベリの『華氏451度』に共感したのかと言えば、やはり、トリュフォーとしても「本を読む」というのは、知的成長のためには「必要不可欠」だという認識があったからだろう。
「映画」を含む「映像文化」は素晴らしいものなのだけれど、「それだけではダメだ」という危機意識が、「映画愛」とは矛盾しないかたちで併存していたということである。
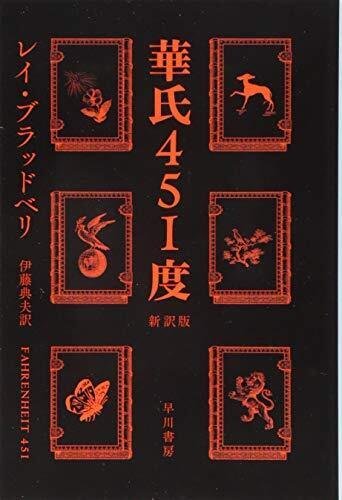
もちろん、稀には、本も読まないで、素晴らしい映画を撮るような作家もいようし、これからも生まれてこよう。
だが、それは「ごく少数の天才」の話であって、「映画ファン」一般の話ではないのである。
だから、その程度のことにも気づかないで「本なんか読まなくたって」などと言っているような「正真正銘の馬鹿」は、難しくはあろうが、映画の名誉のためにも、しっかり反省するべきなのだ。
本編の中で焼かれる数多くの書物の中には、トリュフォーやゴダールが映画作家としてデビューするきっかけを作った、映画評論誌『カイエ・デュ・シネマ』もチラっと映っていたが、映画評論さえも読まないような者が、映画評を書くこと自体、「蛮勇」でしかないことにも気づかないようでは、話にならない。
もしかすると、「蛮勇」という言葉の意味すら知らないのではないかと危惧したくもなってくるのである。
一一これは、「検索すればわかる」という問題ではないのだが、しかし、もしかするとそれすら、わからなくなっているのかも知れない。

(2025年1月7日)
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
