
ゴダールの骸を抱いて セーヌは流れる
評論:ゴダール『勝手にしやがれ』『気狂いピエロ』
大隅正秋『ルパン三世』(テレビ1stシリーズ前半)
出崎統『ベルサイユのばら』(テレビアニメ後半)
「ヌーベルバーグの巨匠」と言われる、ジャン=リュック・ゴダール監督の代表作と目される映画『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』を観てきた。

『勝手にしやがれ』(1959年)は、同監督のデビュー作、『気狂いピエロ』(1965年)は(主な長編作品としては)10作目にあたるようだ。ゴダールが、本年(2022年)9月13日に91歳で亡くなったので、
『今回、2020年の公開60周年を記念して作られた『勝手にしやがれ』4Kレストア版(日本初公開)と、2015年のレストアで明快な色彩が蘇った『気狂いピエロ』2Kレストア版を、ベルモンドへの哀悼を込めて同時公開!』
ということだったらしい。
「だったらしい」というのは、この2本を観てから、パンフレットを読んで、初めて知ったことだからである。
そんな調子なので、有名なゴダールの作品を観たのは、今回が初めてである。
私は基本的に「活字」人間なので、映画にはこだわりはなく、これまで観てきた映画は、主に劇場用長編アニメとハリウッドの娯楽大作映画だ。
子供の頃からアニメを見て育ち、『宇宙戦艦ヤマト』以降は自覚的な「アニメファン」としてアニメ作品を視てきたので、劇場用アニメを観るのも、そうした「こだわり」の延長線上でのことだが、その他の映画については、あくまでも「息抜きの娯楽」でしかない。
私の本領は、あくまでも「活字」である。だから、小難しい本を読むのは嫌いではないが、映画の方は、小難しいものや、マニアックなものを観ようとはあまり思わず、これまでほとんど観てこなかった。
しかし、還暦を迎えて、実質的に定年退職したも同然の今は、すでにほとんど完全な「自由の身」であり、本も読み放題だし、これまでは読書を優先するためにひかえていた映画も、この数ヶ月はどんどん観ている。
今の私の生活は、本を読んでいるか、映画を見ているか、文章を書いているかで、それ以外は、寝てるか食っているか、毎日ではないが、午前中に約1時間のウオーキングをするくらいである。なお、食料の買い出しは、ウオーキングのついでに済ませるようにしているので、それ以外で家を出るのは映画館へ行く時くらい。週に一度くらいしか家を出ないような、優雅な生活をしている。
ずいぶん前から自称していたことだが、いよいよ本格的に「初期澁澤龍彦」型の書斎生活に入ったのだ。
そんなわけで、今回のゴダールの代表作2本についても、最初は、さほど興味はなかった。観たい2本の映画の間の、時間つぶし半分で観ることにしたのである。「あんまり興味はないけど、有名なゴダールの代表作の1本くらい、観ておいてもいいだろう」と、そういう気持ちだったのである。
だから、先に観たのは『気狂いピエロ』の方だった。隔日で『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』を交互に上映していたためだ。最初からその気があって観たのなら、デビュー作である『勝手にしやがれ』の方から順に観たのだが、他の映画の日程を優先した結果である。
で、その『気狂いピエロ』が、どうであったかというと、とにかく「絵として美しい」作品であり、さすがは「巨匠」と言われる人の作品だと、一応は感心した。

しかし、お話には「中身らしい中身」はない。
何かを夢見て、それを追うように生きている、いまひとつつかみどころのない美女と、彼女に引きずられるようにして、それまでの堅実な生活を捨て、彼女との、あてどもない旅に出る男。
お話自体は、ロマンチックな寓話のようなものであり、現実味はない。ただ、つかもうとしてつかみきれない夢を追っているような「切なさ」に満ちた叙情性はあり、最後は二人とも死んでしまう。
一一で、この作品を観た、私の最初の感想は「絵は素晴らしいけれど、内容的には、夢見ることのできた時代の気分が描かれているだけで、今となっては、何も読み取るべき中身がない」と、そんな感じだった。
基本的には「巨匠の代表作にしては、こんなものか」という厳しい評価だったわけだが、友人にLAINで「ゴダールを観てきた」と報告し、『気狂いピエロ』についての上にような感想を送ったところ、友人は「昔、観たきりだが、『勝手にしやがれ』が面白かった」と返信してきた。
たしかに、子供の頃のヒット曲である、沢田研二の「勝手にしやがれ」(作詞・阿久悠)のせいも大きいのだろうが、『気狂いピエロ』よりもデビュー作である『勝手にしやがれ』の方が有名なようにも思えたし、小説においてもしばしばそうであるように、作家の個性はデビュー作に象徴的に現れる場合も少なくないので、やはり『勝手にしやがれ』の方も観ておくことにした。
こちらも観て、やっぱり「合わない」と思えば、私のとってゴダールは「縁なき人」だったと思えばいいと、そう考えたのだ。
そして、一昨日『勝手にしやがれ』を観てきた。
『勝手にしやがれ』は、モノクロ映画であった。知らなかったのだ。
『気狂いピエロ』がカラー作品の、きわめて「絵画的な作品」だったので、その点では少し期待外れだったが、それでも、モノクロ映画として、やはり素晴らしい「絵」を見せてくれる作品で、その点では、やっぱりゴダールはすごい監督なのだと思った。

しかし、『勝手にしやがれ』を観ているあいだ中、ほとんどずっと「いつになったら、面白くなるんだろう」と感じていた。
ジャン=ポール・ベルモンド演ずる主人公は、自動車泥棒の常習犯で、警察に捕まりそうになって警官を殺してしまうが、惚れた女に会いたくてパリに舞い戻ってくる。だが、司直の手は、すぐにパリの主人公の身辺にまで迫ってくる。
一方、主人公が惚れている、ジーン・セバーグ演ずるところのジャーナリスト志望のアメリカ人娘は、主人公のことが好きなのかそうでもないのか、そのあたりがどうにもハッキリしない、いまひとつ何を考えているのかよくわからない、つかみどころのない女である。ただし、ボーイッシュでスレンダーなその容姿は、最高に魅力的だ。当時、大変な人気を誇った女優だそうだが、それとは関係なく、「私の好み」でもあった。

ともあれ、主人公の男がこの女に惚れているのは間違いないが、女の方の態度がいまひとつハッキリしないまま、二人でパリに止まっていたところ、司直の手はついに二人の身辺に及び、最後は女が男の居場所を通報し、逃げようとした男は警察に射殺されて死ぬという、いささかレトロなかたちで幕を閉じる。
主人公のベルモンドがカッコよすぎてわかりにくいが、結局のところ、女にベタ惚れしていて離れられなかったというのは理解できるし、女の方も男に惹かれているというのは確かだったが、しかし、男に身をまかせる気があるのかないのか、いまひとつハッキリしないまま、物語は、あっけない最後を迎えるのだ。
だから、映画を観終わった直後の私の感想は「こいつら、何を考えてるの? 何も考えてないの?」という感じだった。
男の方については、すこし考えれば、女にいつまでもぐずぐずとかかずらわっていては、警察に捕まるのは目に見えているのだから、女を諦めて一旦は逃亡するか、さもなければ女の攫っていくくらいのことをしなければならないはずだし、女の方も、わりと早い時期に、男が警官殺しで警察に追われており、逮捕は時間の問題だと気づいていたのだから、男が好きなら、逃すか自首を勧めるべきだし、そこまで好きではないのならば、さっさと縁を切るべきであろう。ところが、女は女で、男の気を惹く半端な関係をぐずぐずと続けた後、最後は男を警察に売り、言うに事欠いて「自分の気持ちが、よくわからなかったの」みたいなことを言うのである。
だから、私としては「なんだこいつら。まったく、何も考えてないし、成り行きまかせじゃないか。こんな奴らに共感なんて、到底しようがない」と、なかば腹立たしくさえ感じられたのだ。
で、この『気狂いピエロ』を観終わった後も、前述の友人にLAINで、次のような趣旨の感想を送った。
「ぜんぜん合わなかった。主人公たちが、何を考えているのか、さっぱりわからないし、内容らしい内容もなかった。単なる、阿呆な男女の話としか思えなかった。たしかに、こちらも絵的には素晴らしかったし、主演女優は文句なしに魅力的だった。また、映画の冒頭近くで、車に一人で乗っているはずの主人公の男が、カメラ目線で観客に向かって話しかけるというのは、この当時としては実験的で新しかったのかもしれないが、今となっては、どうということはないし、総じて、この映画が、そんなに素晴らしい傑作だとは思えなかった」
これに対する友人の反応は「昔観たきりだから、よく憶えてないけど、主人公の二人がカッコイイなという感じだったんじゃないかな。ヌーベルバーグというのも、映像表現の新しさということで、中身がどうとかいう話じゃなかったんじゃないかな」というようなものであった。
そもそも私は、この友人以上に映画ファンではなかったから、ゴダールの名前も、ヌーベルバーグという言葉も聞いたことはあるけれど、中身はまったく知らなかった。まあ、映画に関する「新しい表現運動」なんだし、「ヌーベルバーグ」というのは「ニュー(new)」に関連する言葉だろう、くらいの印象しかなかったのだ。
で、もしかすると「ヌーベルバーグ」とは、映画における、主に「映像表現」の新しさを目指した運動なのではないかとあたりをつけて、「Wikipedia」を確認してみたところ、
『広義には、撮影所(映画制作会社)における助監督等の下積み経験なしにデビューした若い監督たちによる、ロケ撮影中心、同時録音、即興演出などの手法的な共通性を持った一連の作品を指す(単純に1950年代末から1960年代中盤に制作された若い作家の作品を指すこともあり、さらに広い範囲の定義もある)。
狭義には、映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』の主宰者であったアンドレ・バザンの薫陶を受け、同誌で映画批評家として活躍していた若い作家たち(カイエ派もしくは右岸派)およびその作品を指す。具体的には、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、ジャック・リヴェット、エリック・ロメール、ピエール・カスト、ジャック・ドニオル=ヴァルクローズ、アレクサンドル・アストリュック、リュック・ムレ、ジャン・ドゥーシェなど。また、モンパルナス界隈で集っていたアラン・レネ、ジャック・ドゥミ、アニエス・ヴァルダ、クリス・マルケル、ジャン・ルーシュなど、主にドキュメンタリー(記録映画)を出自とする面々のことを左岸派と呼び、一般的にはこの両派を合わせてヌーヴェルヴァーグと総称することが多い。』
つまり、映画の制作手法において『ロケ撮影中心、同時録音、即興演出などの手法』といったことを特徴とする、ということであり、そんな若手監督たちを指して言った総称だということだ。
そして、この特徴を裏返して言えば、それまでの映画制作では「スタジオ撮影中心」「映像と音声は別取り」「設計的な演出(例えば、シナリオに忠実な撮影、あるいは、事前に絵コンテを作るなど)」だった、ということであろう。
そう言われてみれば、モノクロ時代のハリウッド映画などを見ると、一部の屋外シーンを除くと、屋外のシーンさえもスタジオで撮っているケースが多かったように思う。多分、カメラやフィルムの性能の問題もあり、ライティングの問題などがあったからだろうが「こんなシーンまで、スタジオ撮りか」と驚かされることが多かった。例えば、乗り物の車内シーンなどが、そうしたものの典型的なのかもしれない。
そしてこれは、ハリウッドに限った話ではなく、日本の映画だって基本的には同じだっただろうし、そもそも映画というのは「小屋芝居」の発展したものだろうから、屋内に屋外風景を作って、そこを屋外として演じるというのは、むしろ当たり前でしかなかったのだろう。
音声にしても、同時録音では、よほど高性能な指向性マイクがないと、雑音を拾ってしまうから、同時録音しないというのは、ごく自然なことだ。
また、「即興」と言えば聞こえが良いが、要は「出たとこ勝負」とか「行き当たりばったり」だとも言えるので、失敗の方が多くなりそうだ。それなら、初めから、きちんと「絵ヅラ」を設計しておいて、そのとおりに撮ったものをつないだ方が、確実な映像になるというのは、間違いのないところだろう。
そんなわけで、それまでの映画制作は、そんな具合でやってきたわけだが、「Wikipedia」にもあるとおり、ゴダールをはじめとした「映画批評家」から映像作家に転じた若者たちなら、そういう「伝統芸能」的な映画づくりには飽き足らず、映画に「現場の生々しさ」を持ち込もうとした、というのは、むしろわかりやすい発想だと言えるだろう。要は「無難に手堅く」作るのではなく、「即興性」や「ハプニング」的な要素の自覚的な導入によって、それまでになかった、生き生きとしたリアリズム表現を生み出そうとした、ということなのだろう。よくは知らないが、それが「ヌーベルバーグ」と呼ばれたものの、大筋だったのではないだろうか。
しかし、こう考えてくると、「ヌーベルバーグ」というのは、「映像」や「演技」あるいは「音声」といった「具象」の部分での新しさを模索した運動であって、「文学」のように「思想」や「哲学」といった「内面の新しさ」そのものを目指すものではなかった、と考えていいのかもしれない。
つまり、そこで求められたのは、「視覚」や「聴覚」に訴えかける部分での新しさであって、必ずしも「語られる内容の新しさ」を目指したものではなかったのだろうし、ましてや「多くの若手監督たちに共通する、新しい表現の総称」となれば、「語られる内容」の部分では「人それぞれ」であるのは、むしろ当然だったのであろう。
だが、映画ファンではない私にとっては、映画表現における「新しさ」の「歴史的な意義」、というのは、あまり意味がない。
と言うのも、そういうものは、今や「当たり前(の手法)」になってしまっているのだから、今の私が見ても、それを「新しい」とは思わないし、その意味で、その「斬新さ」や「革新性」の快楽を得ることができないからである。
したがって、私個人が、ゴダールの映画に価値を見出せるとすれば、それは「ヌーベルバーグ」運動における「新しさ」ではなく、単純に、ゴダール個人の「個性」であり「特異な感性」に基づく、「個性的な映像表現」や「個性的な内容」だということになるだろう。

そうした観点から見ていくと、映像的には、明らかに『気狂いピエロ』の方が面白い。カラー作品ということもあって、ゴダール固有の「映像的美」が遺憾なく発揮されていて、いま見ても斬新だし、今では撮れない、真似のしようのない映像ではないかと思う。
そして、それに比べ、『勝手にしやがれ』の方は、そこまでの「独特の映像美」は感じられない。
無論、言われてみれば、この映画は「ロケ撮影中心」であり、セットというのは、ほとんど無いようだし、カメラも屋外を自在に動き回っていて、「Wikipedia」にもあるとおり、言うなれば「ドキュメンタリー映画」的な「リアルな映像づくり」がなされているのがわかる。
だが、前述のとおり、そうした「新しさ」は、今の私には、ほとんど意味のないものなのだ。
したがって、ゴダールの初期の傑作で、代表作でもある『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の2本を観た段階での私の評価は、『気狂いピエロ』の方は「映像表現において、今でも評価できる」のだが、両作ともに「中身」的には「ぜんぜん物足りない」というのが、正直なところだった。
○ ○ ○
ところが、パンフレットに収録されている、3本ほどのエッセイを読んでみて、ハッと気づかされる点がいくつかあった。
たとえば、両作で主演をしたジャン=ポール・ベルモンドの熱心なファンであるらしい、映画評論家・江戸木純の「〈ベルモンド・ユニバース〉という宇宙」では、
『「ルパン三世」のアニメの第1シーズンがベルモンド映画に似ていることなんて、当時の小中学生は常識として会話していた。』
『改めて感じたのは、『勝手にしやがれ』に始まるジャン=ポール・ベルモンドの主演作の多くは、ベルモンドという活劇性の高い肉体が繋ぐ糸によって互いに関連し、影響し合って、巨大な宇宙=〈ベルモンド・ユニバース〉を構成しているという事実だ。
まず、『勝手にしやがれ』と『気違いピエロ』の主人公の持つ、①泥棒、②嘘つき、③無責任、④身軽さ、⑤疾走、暴走、⑥プレイボーイというより、女たらしという特徴は、多かれ少なかれ多くのベルモンド映画に共通するものだ。
『大盗賊』、『パリの大泥棒』、『オー!』、『大頭脳』、『華麗なる大泥棒』といった泥棒&強盗映画はもちろん、一見疑獄サスペンスの『薔薇のスタビスキー』さえ、実はスケールの大きな実在の無責任詐欺師の話だし、『ベルモンドの怪盗二十面相』や『道化師/ドロボーピエロ』も詐欺と泥棒の天才を主人公にした『勝手にしやがれ』の直系の子孫だ。『恐怖に襲われた街』、『警部』、『パリ警視J』のポリス・アクションの主人公は、職業こそ警察官だが、やっていることはほぼ犯罪すれすれの暴走刑事で、捜査と同時に女性との付き合いも欠かさない凄腕。ジョゼ・ジョヴァンニの同じ原作を映画化した『勝負をつけろ』と『ラ・スクムーン』の主人公のストイックの欠片もない短気な早撃ちぶりなどなど、ベルモンド映画の主人公の多くは、『勝手にしやがれ』のミシェルや『気狂いピエロ』のフェルディナンが生まれ変わって演じているかのようなキャラクターばかりだ。』
ここでゴダールは、私の守備範囲である「アニメ」とつながってきた。あとは、一気呵成である。
見てのとおり、江戸木は『「ルパン三世」のアニメの第1シーズンがベルモンド映画に似ていることなんて、当時の小中学生は常識として会話していた。』と書いているが、これはいささか大袈裟な表現である。
というのも、私が、小中学生の頃、そんな「常識」など無かったからで、もしかすると江戸木は年上なのかと「Wikipedia」を確認してみると、なんと1962年の同年生まれだった。

無論、大の「テレビっ子」であった私が、映画やアニメについて、特に無知であったということではないと自負するから、江戸木の話は、自分の周辺の「常識」を、やや安易に普遍化したものではないかと考えられる。
しかしまた、江戸木個人が「常識」と思っていて、私には「常識」ではなかった理由の一端とも思える事実が、先の引用部分の前に書かれてもいる。
『 私はまだ小学生だった。当時の教室での人気は、もちろん例外はあったものの、女子が(※ アラン・)ドロン派、男子がベルモンド派と完全に分かれていた。ドロンとベルモンドが共演した『ボルサリーノ』が放映された翌日など、「どちらがカッコいいか」に対して男子対女子の言い合いが全国各地で、本当に繰り広げられていた。映画ファンといえるほどでもない普通の生徒や学生も含め、ちょっと大袈裟に言えば、当時テレビで外国映画を見ていたほぼすべての男子はベルモンド・ファンだったと言っても過言ではないだろう。「ルパン三世」のアニメ第一シリーズが…(以下、先の引用部分)』
私のクラスでは、こんな男女の言い争いは無かった。そもそも『全国各地で、本当に繰り広げられていた。』って、どうしてわかるんだよ、ということで、この人は、ちょっと「話を盛る」傾向のある評論家さんのようだが、ポイントはそこではない。一一私は、江戸木が言うところの『例外』にあたる「ドロン派」だったのだ。
きっと「類は友呼ぶ」ということだったのであろう(笑)。私は、男だって「美形」の方が好きだったのである。

無論、ベルモンドが嫌いだったわけでもないし、カッコよくないと思っていたわけでもないが、印象としては、ドロンの方が、ずいぶんカッコよく見えた。
実際、その当時、吹き替えを担当していた声優は、ドロンが野沢那智だったというのはハッキリしているが、ベルモンドの声を当てていたのが誰だったかは、ハッキリした記憶がない。たぶん、顔の造りからして、山田康夫ではなかったかと思うのだが、自信は無い。で、調べてみたら、やっぱり山田康夫であった。

山田康夫は、クリント・イーストウッドの吹き替えが有名だから、二枚目も多くやっていたわけだが、ルパン三世をやっていたせいもあって、私の印象では「三枚目の声」という印象も強かったのだ。

で、そんな「ドロン派」の私でも、『ルパン三世』というアニメに関しては、山田康夫つながりということで、ルパンとベルモンドが「似ている」という印象は、たしかにあったのを思い出した。
特にベルモンドファンというわけではなかったが、「マカロニ・ウエスタン」を中心に、ベルモンド映画も視ていたのである。
そして、今回、ゴダールの『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の両作を観て、『ルパン三世』(第1シリーズ前半の、大隅正秋監督担当部分。以下『ルパン三世』と記す)に、ハッキリとゴダールの影響を見ることができた。
簡単に言えば、「女たらしの泥棒と、そのファム・ファタル(運命の女)」という構図であり、「ルパンと峰不二子」は、『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』における主人公男女の関係を、ハッキリと下敷きにしたものだったのである。

ちなみに、こうした「影響関係」は、アニメ以前の、モンキー・パンチによる原作漫画にもともとあったものだ、というのは当然のことである。したがって、アニメ版は、あくまでもそれを踏まえたものなのだろうが、しかし、私自身は、アニメが先であり、しかもモンキーパンチの絵柄が好みではなかったせいで、いまだに原作漫画は読んでおらず、そのあたりについては、区別して論じることができないので、ここでは大雑把に「アニメ『ルパン三世』は、ゴダールの『勝手にしやがれ』や『気狂いピエロ』などの影響を受けている」ということで話を進めたい。

さて、私はここで、「ファム・ファタル(運命の女)」という言葉を使ったが、たしかに『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の2作を観た段階で、その女性造形について、ぼんやりとながら「ファム・ファタル(運命の女)」という言葉が浮かんできたので、あらためてその言葉の意味を確認してみたのだが、やはり、この連想は間違いではなかった。
『ファム・ファタール(仏: femme fatale)(或いはファム・ファタル)は、男にとっての「運命の女」(運命的な恋愛の相手、もしくは赤い糸で結ばれた相手)というのが元々の意味であるが、同時に「男を破滅させる魔性の女」のことを指す場合が多い。
相手が魅惑的であることを示す言葉に英語では「チャーミング (英語: charming)」という言い回しがあるが、ここには魔法や呪いに通じる意味合いがある。日本語においても「魅」の漢字は「魑魅魍魎」といった怪物の意味合いでも用いられている。フランス語であるファム・ファタールも同様に両義性が含まれている。
代表的なファム・ファタールとしては、サロメや妲己、褒姒などが挙げられる。』
(Wikipedia「ファム・ファタール」)
こう書かれてあり、さらに、「ファム・ファタールの一例」の項目の「映画」の項には、しっかり、
・ジーン・セバーグ 『勝手にしやがれ』
とあった。
つまり、峰不二子という女が、ルパンに気があるのかないのかハッキリせず、思わせぶりな態度を見せはするけれど、いざという時は、いつもその腕の中からスルリと逃げ出すし、ルパンを騙したり、しばしば裏切ったりもするという「わかりにくい性格=謎めいた性格」設定は、峰不二子が、ゴダール的な「ファム・ファタルの、正統な伝統に連なる女として、意識的に造形されていた」からだというのが、ハッキリわかる。
また、ルパンが、そんな不二子に惚れて、振り回される「女たらし」だという設定も、ゴダールのジャン=ポール・ベルモンドを意識したものだったというのも、もはや明らかだろう。ベルモンドとルパンの両方に、山田康夫が声を当てていたというのは、決して偶然ではなかったのである。
しかしながら、こうしたことは、私の小中学生時代において、決して「常識」ではなかったと思う。
たしかに「似ている」とは感じていたが、たぶん、それとこれとは「別物」として見ていたように思うのだ。
私がまだ『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の2作を観ていなかったからということもあるだろうが、仮に観ていたとしても、なんとなく「ルパンとベルモンドが似ている」とは感じても、それで『ルパン三世』というアニメが『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の影響を受けた作品だとまでは考えなかったろう、ということである。
子供は、普通、そんなことは考えないのであって、「例外」的にそこまで考える「ませた子供」もいたかもしれないが、それが「常識」だったというのは、江戸木の「後年の理解」が過去に繰り込まれた「記憶改変」のなのではないかと、私は斯様に考えるのである。


(ベルモンドは、アニメ化もされた『コブラ』(寺沢武一)のモデルとしても有名。アニメの映画版では松崎しげる、テレビ版では野沢那智が声を当てた)
○ ○ ○
ともあれ、ゴダールの『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』を「ファム・ファタルへの恋に狂った男の物語」だと理解できれば、これらの映画が描いたものが何かは、比較的分かりやすい。
簡単に言えば、それは「決して手に入らない夢を追って、その身を滅ぼす男の、恍惚と死」とでも言えるだろう(だから彼らは、常習的「泥棒」なのだ)。
この2作において、ヒロインの「ファム・ファタル」性が、より分かりやすく出ているのは『気狂いピエロ』の方である。それは、この物語が「寓話」的に「誇張された物語」だからで、それに比べると『勝手にしやがれ』の方は、そもそも「実話」がベースであり、しかもそれを「ドキュメンタリー」風の映像で、リアルに表現したから、こちらのヒロインは、リアルな「何を考えているのか、よくわからない女」になったのであろう。
だが、いずれにしろ、これらの作品は、ゴダール自身の化身である男性主人公の視点から描かれた物語であり、ハッキリ言えば、ヒロインの方は「生身の人間」ではない。
前述のとおり、『勝手にしやがれ』の方のヒロインは、たしかに『リアルな「何を考えているのか、よくわからない女」』にはなっているのだけれども、それが単なる「バカ女」ではなく「謎めいた女」になり得ているのは、ゴダールが彼女を「ファム・ファタル」として描いたからであろうことは疑い得ない。
実際、『勝手にしやがれ』のヒロインは、当初、後にゴダールの妻となり、『気狂いピエロ』ではヒロインを演じた、ゴダールの「ミューズ」たる、アンナ・カリーナを予定していた。

だが、当時すでに人気女優であったアンナが、新人監督のデビュー作のヒロイン役を断ったため、『聖女ジャンヌ・ダーク』で主役に抜擢され、続くフランソワ・サガン原作の映画『悲しみよ、こんにちわ』を大ヒットさせて注目を集めていた、若手人気女優のジーン・セバーグが、代わりにヒロインを演ずることになったのである。
ここで、私は、アンナ・カリーナを、ゴダールの「ミューズ」と表現したが、「ミューズ」とは『ギリシャ神話で、文芸・学術・音楽・舞踏などをつかさどる女神ムーサの英語名。』(「weblio辞書」)であり、一般的には「男性芸術家に、創作へのインスピレーションを与えてくれる女性」だとでも言えるだろう。
つまり、ゴダールは当時、アンナ・カリーナに、公私ともにベタ惚れしており、彼女を撮りたい、彼女なら素晴らしい映画が撮れると、そう入れ込んでいたのである。

そんなわけで、ゴダールにとっては、アンナは「ミューズ」であり、作品世界においては「ファム・ファタル(運命の女)」であったから、彼の当時の作品のヒロインの多くは、おのずと「最後は男を滅ぼす、ファム・ファタル」とならざるを得なかった。
ゴダール自身が現実に身を滅ぼすのは不都合だろうが、映画の中では、行くところまで行かなければならないから、「ファム・ファタルへの恋」は、最後に「死」が待っていなければならず、『勝手にしやがれ』では、男性主人公は、女に裏切られて死に、女は生き残る。『気狂いピエロ』では、女が先に死んで、男は後追い自殺をして死ぬことになる。
したがって、『ルパン三世』という作品において、「ルパンと峰不二子」の関係が、いつでも「結論先送り」で、不二子がルパンの腕の中からスルリと抜け出してしまうのは、「最後の死」を避けるための、必然的な仕掛けだったと言えよう。
「ルパンと峰不二子の恋」において、その成就は、二人またはどちらか、多くの場合、男の方の死を結果せざるを得ず、それを本能的に察知しているからこそ、不二子は、決して「ルパンの腕の中」に収まることをしなかったのであろう。
実際『ルパン三世』(第1シリーズ)のエンディングテーマ曲である「ルパン三世〜その2」の歌詞(東京ムービー企画部)は、次のようなものだった。
『足元にからみつく
赤い波をけって
マシンが叫ぶ
狂った朝の光にも似た
ワルサーP38
この手の中に
だかれたものは
すべて消えゆく
さだめなのさ ルパン三世
にくしみの まなざしを
背中にうけて
今日をすてる
女の胸に残してきた
燃える血のバラ
この手の中に
だかれたものは
すべて消えゆく
さだめなのさ ルパン三世
海の底から 聞こえるような
殺しの歌を
マシンがうたう
ふるえるような かすかな といき
ワルサーP38
この手の中に
だかれたものは
すべて消えゆく
さだめなのさ ルパン三世
ルパン三世 』
つまり、主人公であるルパンを死なせられないのだとしたら、ルパンが本気で愛し、その愛に応えた女の方が「死」ななければならない、という「運命」にあるということを、この歌詞は意味しているのである。

だが、いずれにしろ、ファム・ファタルたる峰不二子にとっても、やはり「愛するルパン」を死なせたくはなかった、ということなのであろう。
このように、『ルパン三世』という作品には、ゴダールの影響があるというに止まらず、そのゴダール自身がとり憑かれた「ファム・ファタルとの、死に至る運命の恋」という「フランス(文学・映画)の伝統」が、流れ込んでいた。
それは、原案に当たる、モーリス・ルブランの『怪盗ルパン』シリーズが「フランスの小説」だったから、『ルパン三世』でも「時に、フランスを舞台にする場合がある」というに止まらない、「フランス的なもの(精神)」の流れ込んでいる作品だと言えるのだ。

○ ○ ○
それにしても、ゴダールのとり憑かれた「ファム・ファタルとの恋」とは、いったい何だったのであろうか?
私が思うに、それは先にも少し書いたとおり「決して手に入らない夢を追う」という無謀な行為の、ロマンティックな「象徴」なのではないだろうか。
つまり、「ファム・ファタル(運命の女)」とは、「(生身の)人間」ではなく、「究極の存在」であり「超越的世界の象徴」であって、人(この場合は、男)が夢見る「人間の限界を超えること」なのではないだろうか。
言い換えれば、完全に「男のものになってしまう女」は、「ファム・ファタル」ではない。そうではあり得ない。
「男のものになってしまった女」は、その瞬間から「人間の女」になってしまって、いずれ「男の恋」は醒めてしまい、その男が、それでも「究極の存在」であり「超越的世界の象徴」を求めることを止めないようなら、その女は捨てられることになるだろう。
「女たらし」の象徴たる「ドン・ファン」とは、これも「Wikipedia」によると、
『ドン・ファン(スペイン語: Don Juan)は、17世紀スペインの伝説上人物。ティルソ・デ・モリーナの戯曲「セビリアの色事師と石の客」が原型。好色放蕩な美男として多くの文学作品に描写されている。プレイボーイ、女たらしの代名詞としても使われる。』
ということになるのだが、この虚構の人物を、実在した同種の人物とみられている『カサノヴァ回想録』の著者ジャコモ・カサノバと比較して、「ドン・ファン」的なるものを、精神分析的に見てみると、次のようにも解釈できる。
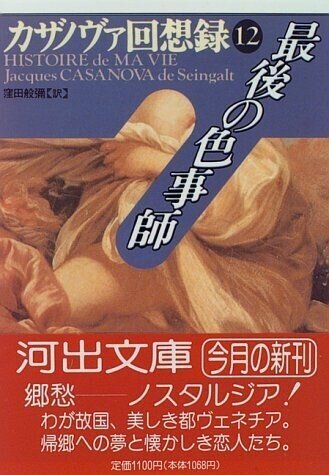
『いずれも、精神医学的には「異常」なのですが、強いて差異を述べるならば「ドンファン」はあまりにも高い理想を追い求める「自己愛性パーソナリティ障害」に相当するでしょうか。「カサノバ」は他人の注目を浴びることで満足を覚える「演技性パーソナリティ障害」に相当するでしょうか。』
(茅野分「「ドンファン症候群」「カサノバ症候群」とは」)
つまり、実のところ「ドン・ファン」は、個々の女を愛してはいない、のである。
彼にとって美しい女は、「究極の存在の化身」であり「超越的世界の象徴」であるから、原理的には「手に入らないもの」であり「手に入るようなものは、偽物」でしかないから、手に入った女には興味を失って、次々と「未知の女」へ移っていくことになるのだ。
だから、峰不二子からすれば、もしも自分がルパンに本気になってしまったら、きっとルパンは自分を捨てるだろうと思っているし、もしもそれが許せないのであれば、ルパンを殺すか、自分が死ぬしかないとも感じているのではないだろうか。そうした意味で、自分はルパンにとっての「ファム・ファタル」に止まるしかなく、絶対に「可愛い奥さん」にはなれない存在だと、自身、賢明にも察していたのではないかと私は思う。
ともあれ、ゴダールの『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』に関していえば、ヒロインは「ファム・ファタル」であって「人間」ではない。「人間」であってはならない。
まことに、典型的な「男性中心主義」の「幻想」であり、今の「フェミニズム」的な観点からすれば、許しがたい「女性の道具化されたイメージ」だったと言えるのかもしれない。だが、そういう時代であったのだ。
さて、ゴダールの『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』は無論、日本のアニメ『ルパン三世』にさえ流れ込んでいた「フランス的なるもの」を、「究極的な存在への渇望」だとか「超越的世界への欲望」というふうに理解するなら、『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の2作において、明らかに「哲学趣味」が見られるというのも、当然のことだと言えよう。
それは、ゴダール個人に「哲学趣味」があるというに止まらず、フランス(人)には、「キリスト教(カトリック)」とはまた別の「究極的な存在への渇望」だとか「超越的世界への欲望」といった「伝統的な体質」があったからこそ、長らく「哲学」の世界をリードする国たり得たのではないだろうか。
そして、近年の世界的な「フランス現代思想ブーム」(1970年代)というのが、「革命」幻想の潰えた時代における、もうひとつの「究極的な存在への渇望」だとか「超越的世界への欲望」の発露だったとは考えられないだろうか。
実際、ゴダールを含む「ヌーベルバーグ」世代も、おおよそ同時代なのである。
そして、「フランス現代思想」としての「ポストモダン思想」が、きわめて「文学的」であり「詩的」な比喩表現を用い、それゆえの「難解さ」を抱えてしまうのは、この国の根底に「究極的な存在への渇望」だとか「超越的世界への欲望」があるからではないか。
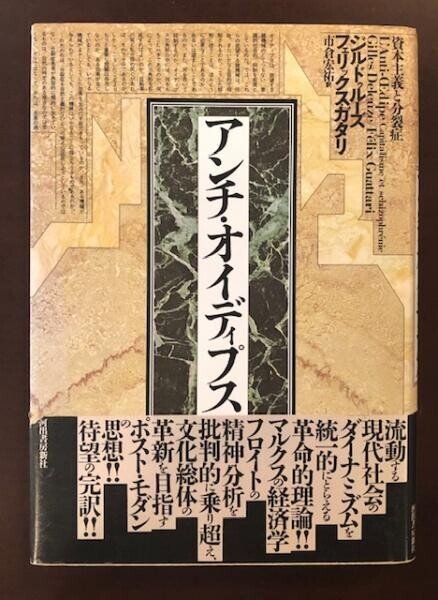
つまり「わかってしまったら、それは偽物」であり「真理は、常に、人間の思惟の網をすり抜けていくものだ」という思いが、どこかにあるのではないか。言い換えれば、「哲学」の世界においてさえ「究極のもの」とは、「ファム・ファタル」のような「捕まえきれな存在」なのである。
まただからこそ、「わかりやすい哲学」「実生活に役立つ哲学」などという、今の日本人読者がありがたがるような「哲学」とは、「哲学」の名に値しない、唾棄すべき「偽物」だということなのではないだろうか。
○ ○ ○
ともあれ、このように「フランス的なもの(精神)」とは、「究極的な存在への渇望」とか「超越的世界への欲望」といったものを根深く抱えており、それゆえにこそ「人間は、真理への途上で死んでいくものであり、決して真理に達することはできないし、それこそが正しい」と感じている部分があるのではないだろうか。
「究極的な存在」や「超越的世界」の前には、人間など、所詮は「卑小な存在でしかない」と思っている。
つまり、男(=人間)は「ファム・ファタル」の前に、最後はひざまづいて死ぬしかない存在である、そんなふうに感じられているのである。
それにそもそも、「絶対に手に入らないもの」の代表とは、「死」そのものであろう。
ハイデガーも語るとおり、人間は決して「死」を所有することできない。死んでしまえば、人は「死」を所有するべき主体を失ってしまうからである。その意味でも「ファム・ファタル」を求める者は、「死」を持って最期を迎えるしかない、とも言えるのである。
それにしても、このような「ロマンティックな、しかし暗い死」というイメージは、やはり「フランス的なもの」なのかもしれない。
「ロマンス」が、どこか「暗さ」と結びつく感性というと、私は、有名なシャンソン(フランスの歌謡曲)の名曲「パリの空の下」の、どこか物悲しいロマンティシズムを連想させる。
この歌の「和訳歌詞」は、こうなる・
『パリの空の下
鼻歌が聞こえる
フム ム
それは今日少年の心に芽生えたもの
パリの空の下
恋人たちは散歩する
彼らが感じている幸せを
確かめているかのよう
ベルシー橋の下では
哲学者が座っていて
2人の音楽家と何人かの見物人
その後に続く何千人の人々
パリの空の下
夜まで歌が流れる
国歌を愛する人々
旧市街地から
ノートルダム大聖堂の近く
時には浮かないドラマ
そう、でも物語は
みんな変えられてゆくもの
夏の空の光線
船乗りのアコーディオン
希望の花咲く
パリの空
パリの空の下
喜びの川が流れる
それは、夜でおしまい
路上生活者や物乞い
パリの空の下
幸運の神様の鳥たちが
世界中からやってきて
ささやき始める
パリの空
彼のために秘密にしてること
20世紀から愛している
私たちのサンルイ島から
島が微笑むと
空は青くなって
パリに雨が降るとき
それは悲しいとき
ときにはやきもちを焼いて
何百万の恋人たちに
叱っているよう
明るい雷を光らせて
でも、パリの空は長いいじわるはしないの…
償いには、虹を架けてくれるの』
ジュリエット・グレコの歌う、この「パリの空の下」(Sous Le Ciel De Paris)は、元々は同名の映画、邦題は『巴里の空の下セーヌは流れる』(1951/仏) の主題歌であった。
映画の内容は『パリに住む人たちの日常のスケッチ・点描といったもの』だそうで『どこの都市にでもあるようなエピソードと悲喜劇に、観客は自分自身を投影して現実的な考えを巡らせるというリアリズムの映画』なのだそうだ。(歌詞和訳「パリの空の下」)

したがって、この歌詞自体は、決して「究極」や「超越」あるいは「死」を思わせるところは無く、むしろその真逆である「庶民の小さな幸福」を歌っているとも言えるのだが、しかし、ここで映画のタイトル『巴里の空の下セーヌは流れる』の方に注目すると、ここに登場する、フランスを象徴する「セーヌ川」は、そうした人々の生活を貫いて流れる「永遠の象徴」のように、私には思える。
「母なるセーヌは、やがて去りゆく人々の暮らしとその歴史を、時間を貫いて、黙って見守ってきた」というイメージだ。それがあるからこそ、この歌は、どこか「物悲しいロマンティシズム」を湛えているのだとは言えまいか。
そして、ここで私の連想は、さらに、アニメ監督・出崎統によってテレビアニメ化された『ベルサイユのばら』(原作・池田理代子)の終盤に登場する、アニメのオリジナルキャラクターである「名もなき吟遊詩人」へとつながる。
彼は、セーヌ河岸の橋の下で、革命へと流れ込む人々の思いを、誰に聞かせるともなく、アコーデオンを弾きながら語る。そんな彼の姿は、「うつりゆく時代の運命」の「陰の部分」を象徴するかのようである。

彼の「語り」とは、例えば、こんな具合だ。
『セーヌの流れは止まりゃあしねえ…。
それでもいつもセーヌは流れる…。
悲しいこと、辛いこと、すべてを呑み込みセーヌは流れる…。
ずっとずっと夜は続くが…やがて陽が昇り、明るい朝の中…涙した人はドアを開く…
するとそこに、いつものようにセーヌが…滔々と優しく流れている。』
この吟遊詩人は、結局のところ、革命の成就を見届けることなく、その貧しさのゆえに死んでゆき、その息子が、父の遺言どおりに、その骸をセーヌへ流し、父の跡を継ぐようにして、アコーデオンを弾きながら、父の骸が流れていくのを見送る。


この吟遊詩人のエピソードは、「究極的な存在への渇望」とか「超越的世界への欲望」の象徴たる「ファム・ファタルとの恋」を夢想する「恵まれた芸術家」たちの対極にある、貧しい「庶民」の姿だと、そう考えても間違いではない。
しかしながら、対極にありながらも、両者に共通するのは、やはり「究極的な存在への渇望」とか「超越的世界への欲望」であろう。
なぜなら、この吟遊詩人の「語り」の中心的な象徴とは、「庶民」ではなく、むしろ、それを黙って見守る「永遠なる川セーヌ」の方にこそあるからだ。
実際、ゴダールも、決して単なる「恵まれた芸術家」ではなかった。
彼は、それまでの「映画芸術」に「革新」をもたらそうとした、新時代の表現者であったし、功成り名遂げた後も、「革命を希求する時代の声」に呼応しようとした。
『1968年5月、五月革命のさなかの第21回カンヌ国際映画祭に、映画監督フランソワ・トリュフォー、クロード・ルルーシュ、ルイ・マルらとともに乗りこみ各賞選出を中止に追い込む。同年、ジャン=ピエール・ゴランらと「ジガ・ヴェルトフ集団」を結成( - 1972年解散)、匿名性のもとに映画の集団製作を行う。』
つまり、彼は「映画賞」というものに抵抗しようとした。それが「エリート主義的な選別システム」であると考え、もっと民主的な形式があるのではないかと「夢想」したのであろう。
このとき彼が『匿名性』を選んだのは、選ばれて得た「名前=名声」の特権性を、作品に与えたくないと考えたからであろう。
しかし、こうしたゴダールの理想は、やがて捨てられ、彼は「商業映画」へと帰っていく。
彼は、このようにして「夢」に破れ、そのことで「死」に、そして、91歳のその「死」まで、「この世」に永らえることになる。
彼の商業映画復帰後の作品は『トリュフォーをして「彼こそが本物の天才だ」と言わしめた初期の大胆な撮影・編集手法は、しだいに影をひそめるようになった。』そうだ。
きっと、彼はもう「ファム・ファタル」を熱望することができなくなっていたのであろう。
若き「究極的な存在への渇望」「超越的世界への欲望」を失って、彼は「平凡な日常」に生きる「人間」の仲間入りをしたのだ。
それでも、セーヌは、そんな悲喜こもごもを黙って見守りながら、今も流れ続けている。
「超越を夢見た者」の骸も「夢破れて日常に埋没した者」の骸も、分け隔てなく、その内懐に受け入れて、セーヌは永遠の時を流れ行く。
「フランス的なもの」としての「ロマンティシズム」は、こうしたものだからこそ、どこか物悲しさを湛えているのではないだろうか。

(2022年10月16日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
