
酒見賢一 『中国雑話 中国的思想』 : 中国人的思考と日本人的思考
書評:酒見賢一『中国雑話 中国的思想』(文春新書・2007年)
酒見賢一が若くして急逝したのは、一昨年2023年の11月7日。59歳の若さであった。
酒見は、私の一つ年下で、私がちょうど還暦を迎えた年だったので、余計に感じるところもあった。人の寿命など、本当にわからない。
酒見賢一は、その作家デビュー当時から知っている。1989年に刊行された「第1回 日本ファンタジーノベル大賞」受賞作として、そのデビュー作『後宮小説』を読み、心から感心した。
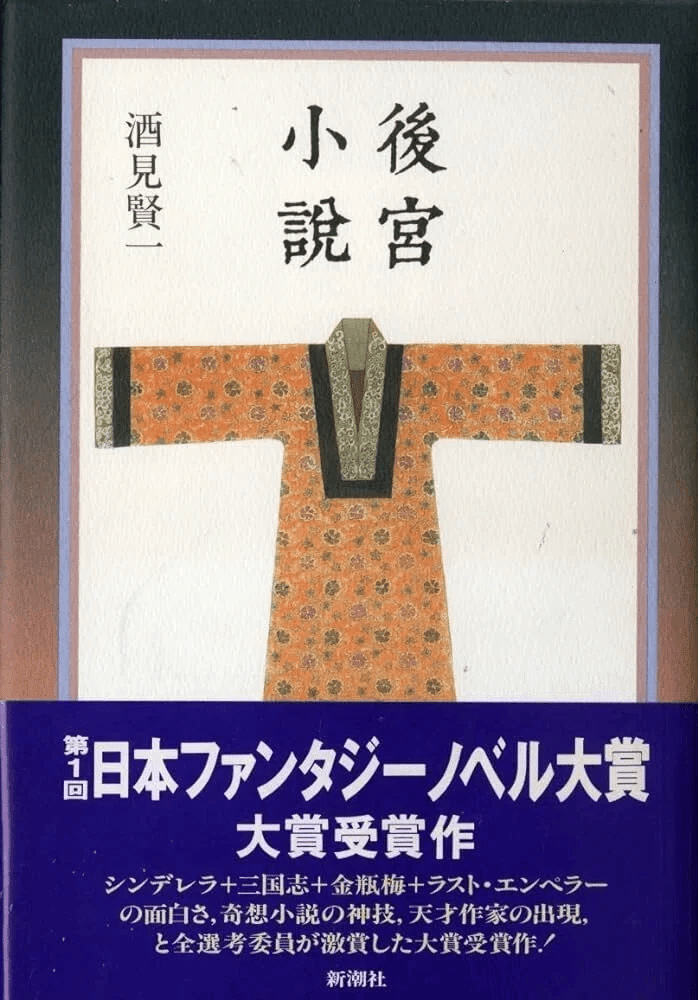
その後の経緯については、酒見の訃報が公けに報じられたその翌日に書いた、下の追悼文に詳しいから、ここでは繰り返さない。
とにかく、酒見賢一が亡くなった段階で、未読だったその著作とは、最後の長編小説である『泣き虫弱虫諸葛孔明』(全5巻)と、本書『中国雑話 中国的思想』だけになっていたのである。
『泣き虫弱虫諸葛孔明』は、単行本を買い揃え、分厚い全5巻本は、通勤で読むには不向きだと読めず、それで全5巻が文庫に落ちるのを待って買い揃えても、まだ読めなかった。
他にも読みたい本が次から次へと出てきてしまう私としては、大長編小説を読むというのは、よくよくの覚悟が必要だったため、ついつい後回しにして、今日に至っている。
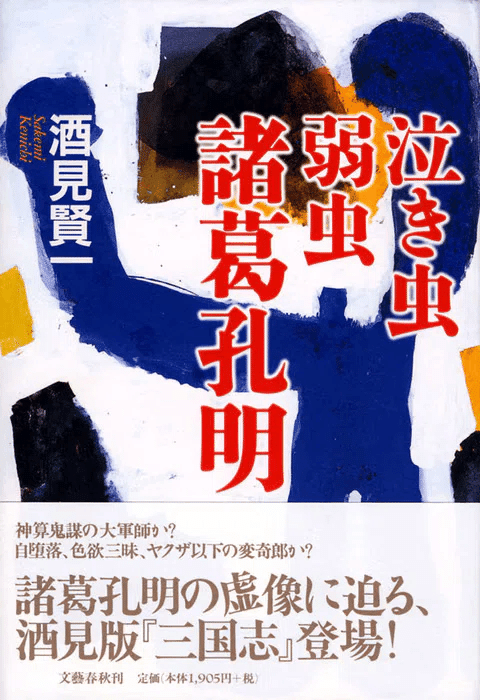
もう一方の未読本であった本書『中国雑話 中国的思想』の方は、私が酒見賢一の「小説」のファンであるため、そう一生懸命探してはいなかったせいもあって、単純に手に入らなかったから読めなかっただけである。
ともあれ、酒見賢一が亡くなっていよいよ、残された作品を読まなくてはという思いが強まった。そこで、ひとまず1巻本である本書『中国雑話 中国的思想』を片づけてから、最後の大作『泣き虫弱虫諸葛孔明』をじっくり味わおうと、そんな計画を立てた。
そして、昨年末ごろ、ついに本書を入手し、『後宮小説』のアニメ化作品『雲のように風のように』を見たのを契機に、本書を読んだのである。
○ ○ ○
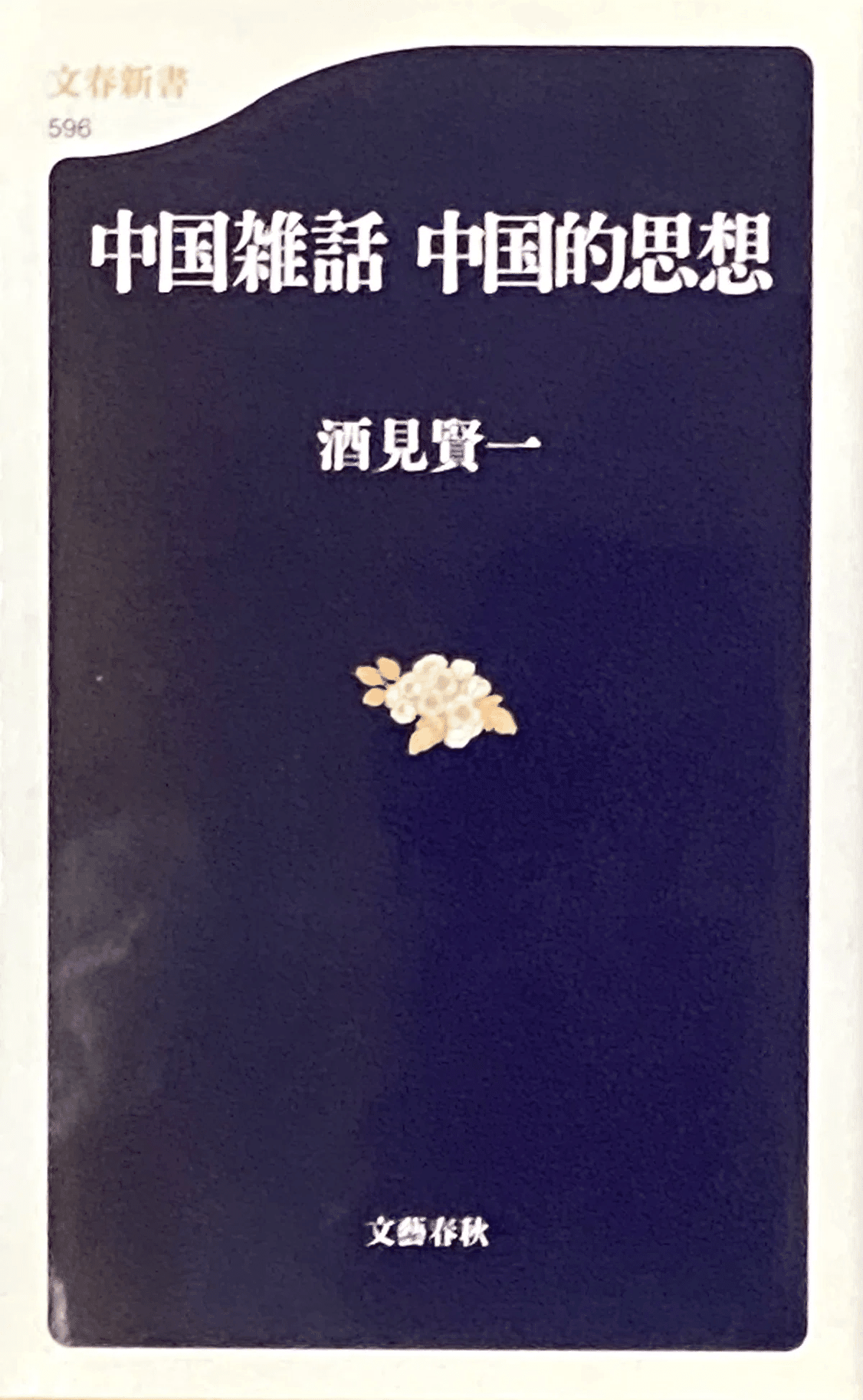
本書は、「NHKラジオ 中国語講座」に連載されたエッセイをまとめたものだ。酒見自身が「あとがき」に書いているとおり、この読み切り連載エッセイは、編集者の思惑では「中国歴史人物列伝」的なものだったようなのだが、意思疎通が十分ではなかったのか、酒見の方は「中国に関することなら何でもあり」だと思っていたので、「人物」には限らない内容になってしまった。一一たぶん「中国語講座」テキストも「おまけ」的な読み物だったので、編集者も、あまり細かい説明はせずに「お好きに書いてください」みたいな言い方をしたのではないだろうか。
そんなわけで、本エッセイ集で扱われているのは、次の8項目である。
一、 劉備
二、 仙人
三、 関羽
四、 易的世界
五、 孫子
六、 李衛公問対
七、 中国拳法
八、 王向斎
見てのとおりで、人物も扱ってはいるが、そうではなく「中国文化」を扱っているものもある。酒見も言うとおり、「人物伝」ではなく「事物伝」になっているのだ。
しかし、ここで気をつけなくてはならないのは、各章の枚数がバラバラで、その落差がけっこう激しいという点である。
単行本収録時に加筆修正がなされたのは間違いないが、やはり連載時から、枚数にバラつきがあったのかもしれない。そのあたりも、もしかすると編集側の注文が緩かったのではないだろうか(親方日の丸のNHKだし)。
大半は20ページ前後の長さなのだが、「中国拳法」の章だけは64ページもあって、他の章の3倍近い長さになっている。
これは、中国拳法そのものの歴史は古くても、もともと古い文書資料が少ないところに、文化大革命時に迫害を受けたため失われた伝統もあり、結果としてその研究資料が現代に書かれたものが多い。したがって、一般的な歴史の本とはまったく別に、そうした現代の専門資料を当たらなければならなかったせいで、手間暇かかって長くなったか、あるいは、連載時の調査不足を、単行本収録時に補足したからかで、余計に長くなったのかもしれない。
いくら中国の歴史に詳しくても、「中国拳法」の歴史となると、やはり、そちらの専門書に当たらないことには、その大筋さえ語れないといった事情があったようだ。
ともあれ、このように見ていくと、本書は、一見したところ「まとまりがない」という印象を与えるし、また、中国史マニア、あるいは、もっと平たく言うと「三国志」マニアなんかが期待するような内容には、あまりなっていない。劉備、関羽といった人物を扱ってはいるものの、その枚数は決して多くはないのだ。
なぜそうなったのかといえば、酒見賢一としては、いまさら「通説」を語る気はなく、枚数的にも、そこから外れる話題に限定したからであろう。
そのため、そのあたりの有名人物について、まともに語ってほしかった読者は、たぶん肩透かしに近い感じを受けたのではないだろうか。しかも、最後は、さほど興味もない「中国拳法」の、現代に近いあたりの話になっているのだから、なんだかなあという感じだったのではないかと推察される(最終章の「王向斎」は、現代の拳法家)。
また、だからこそ、Amazonカスタマーレビューの点数も、少々低目になってしまったのではないだろうか。
しかし、酒見を擁護するわけではないが、本書は『中国雑話 中国的思想』と題されているとおりで、たしかにまとまりのない話、つまり「雑話」なのだが、酒見がこの「雑話」で何を語ろうとしたのかは、後の「中国的思考」というのに明らかだろう。
つまり酒見としては、「個別の話題」を掘り下げるのではなく、それらをざっと紹介する中で、それらの中にひそむ共通点たる「中国的な思考パターン」というのを探り、それを書こうとしたのではないか。
良かれ悪しかれ、私たち日本人とは違う思考パターン。また、現代中国において大きく様変わりしてしまったようでいて、実はあまり変わっていない「中国的な思考」というものの意味を考えてもらいたいと、酒見は、これら一見バラバラに見える話題を、あえてチョイスしたのではないだろうか。
例えば、第三章の「関羽」だが、この章で描かれる関羽は、歴史上の人物である関羽でもなければ、物語化された『三国志演義』における関羽でもない。
この章では、神に祭り上げられた、死後の関羽を描いており、しかも、史実であれフィクションであれ、生前はそこまでの大人物ではなかった関羽が、死後は、孔子にも並ぶほどの偉大な神に祭り上げられていったその軌跡を追うことで、「中国人的思考」というものを浮かび上がらせていく。
要は、生前の功績に従って、死後も相応に祭り上げられるというのではなく、自分たちに都合が良い(性格を持つ)と思える人物を、殊更に神格化してどんどん持ち上げていく、といった実利的でマイペースところが、「中国人気質」なのではないかと、酒見はそう見ているようなのだ。
そんな具合で、他の章でいろんなことを扱っているが、「中国人気質に由来する、その特異な思考パターン」を描こうとしている点で、すべての章は、ゆるく一貫している。そして、そこに気づかなければ「なんだか話題が散漫な、ゆるい本だな」という印象を受けてしまうのである。
したがって、本書で味読すべきは、私たち日本人とは、似て非なるものである「中国人的思考」の特質であり、それを楽しむことなのであろう。
それを、殊更に肯定する必要も否定する必要もないが、やはりどこか違っているということを感じ取っておくことは、私たち自身が「日本人的思考」の「くせ」を自覚しなければならない際に、きっと役立つものだからである。
○ ○ ○
さて、以上のような意味で、噛めば噛むほど味の出るエッセイ集だとはいうものの、以下では、比較的わかりやすく面白い部分を紹介しておこう。一一第五章「孫子」。あの「孫子の兵法」に関わるエッセイである。
『戦わずして勝つのが最善
(※ 著者が誰であるにしろ、著作としての)『孫子』の基調をなすものは、戦争はなるべくすべきではないという考えである。本来そのすべきではないものを、当時、春秋戦国期の列国は、とにかくしきりに行うのであり、兵家(※ 兵法の研究家)はこの現象を如何にすべきかを目をそらすことなく積極的に考えた諸子であった。
戦争を行う君主に道徳を説いてもあまり意味はない。呉越の争いのように意地や憎悪が動機である戦争もあるが、たいがいは欲得ずくで利益を見込んでするものである。
『日に千金を費やして、然る後に十万の師挙がる』(作戦篇)
と孫子は説く。戦争には莫大な費用がかかる。十万の軍を起こすとして、兵員のみならず戦車、輸送車、馬匹、食糧補給、外交費用など、一日ごとに千金(膨大なお金)が煙のように消えることを覚悟しなければならない。戦争に勝って、賠償金を分捕り、あるいは相手国を併呑したとしても、大赤字になる恐れがある。これが戦争を避けるべき重大な理由の一つとなる。君主が日々食べていたご馳走が、戦争をしたせいで一汁一菜メザシー匹にもこと欠くようになってもいいのか。戦争赤字のために国家が衰退しては元も子もないわけで、利益目的の君主にはこう言ってやったほうが効くであろう。
それでもやるというのなら、勝敗の見通しがつかないような戦争は不可であり、一〇〇パーセント勝てる戦争しかやるべきではない(そんな戦争はまずないのだが)。だから、戦費に次いで大事なことは、必ず短期間で終わらせることである。
『故に兵は拙速なるを聞くも、いまだ功の久しきを暗ざるなり。それ兵久しくして国の利するは、いまだこれあらざるなり』(同前)
と孫子は説く。戦争はたとえ作戦が拙劣であっても、速やかにやったおかげで成功した例は聞くが、長期戦をうまくやって成功したなどという例は聞いたことがない。二年も三年もかかるような長期戦が国家に利益をもたらすことはない。速戦即決の戦略が立てられないような戦争は不可である。長引くほどに敵も味方もひたすら消耗してボロボロになり、なんとか勝てたとしても、目を覆うような惨状を呈しているであろう。生産力はがた落ちとなり、回復するのに二十年、三十年もかかるとすれば、利益目的の戦争は成立しない。
孫子は速戦即決の短期戦が、結局は敵味方の区別なく、損害最小にして民のためにもなると考えたろう。また第三国が漁夫の利を得ようと、頃合いを見計らって侵攻してくるおそれがあり、その隙を与えてはならない。事前の外交で中立条約を結んでいようが、弱肉強食の連中を容易に信用すべきではなく、もし急襲を受けても迎撃できるだけの余裕を持っていることが望ましい。
『およそ用兵の法は国を全うするを上となし、国を破るはこれに次ぐ』(謀攻備)
兵の用いかたは、敵国を無傷のまま降伏させることが上策で、戦って破るのはその次の策である。
こうした孫子の原則が、後世に普遍の金言といわれる名言をいくつも出すことになる。
『百戦百勝は善の善なるものに非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり』(同前)
すなわち「戦争をせずに勝て」の原理である。孫子は説く。百回戦って百回勝つことは最善とは言えない。不戦屈敵こそベストである。『孫子』の三分の二は百戦百勝のための具体的な戦略戦術論が述べられているが、それはあくまでやむをえず戦争となったときの次善の策である。「孫子』の本領は残りの三分の一、戦わずして勝つの最善策にある。
孫子の認識はクラウゼヴィッツの戦争論に通じるところがあるが、大きな相違点はこの部分で、クラウゼヴィッツは、
「戦争とは相手にわが意志を強要するために行う力の行使である。この目的を確実に達成するためにわれわれは力をもって敵を無力にせねばならない。また、これが軍事行動の本来の目標である」
としており、あくまで戦闘により敵を完全屈服させることがベストであるとする。常に百戦百勝することが最善なのであり、孫子とは逆で、「戦ってほぼ完璧なまでに勝つ」ために戦争をする。戦わないで勝つというのは、戦争をしないと言うのと変わらないのである。近代ヨーロッパの事情ではそうなるのだろう。
戦わずして勝つ、は、日本人にはなんとなく納得できる理屈ではあるが、果たして実現可能なものなのか。日本の戦国時代の戦例の中に近いものはある。豊臣秀吉は合戦をすることなく、敵を下す外交交渉術に長けていたが、織田軍団の血なまぐさい後ろ盾があればこそ出来た離れ業がすくなくなかった。
『故に上兵は謀を伐つ。その次は交を伐つ。その次は兵を伐つ。その下は城を攻む』(同前)
と孫子は説く。最上の戦いとは、敵方の謀略を見抜いて潰すことである。その次は、敵方の外交関係を破壊することである。この二つは一切の兵を使わずに行える外交、謀略の政治の戦いである。その次が、普通の軍事衝突で勝つことである。最もまずいのは攻城戦を行うことである(※ 守りを固めた敵を、攻め落とそうとすること)。』
(P100〜103、※ は引用者註)
ここを読めば、多くの人は、現在も進行中の「ロシア・ウクライナ戦争」のことを思い出すことであろう。
そして、いくら「ロシアが悪い」と言ったところで、孫子の『二年も三年もかかるような長期戦が国家に利益をもたらすことはない。』という言葉は、戦争当事国の双方に痛感されて、千金の重みを感ぜずにはいられないはずだと、そう気づけもしよう。
たしかに「ロシアが悪い」から「ロシアに勝たせるわけにはいかない」、だから「安易な停戦合意はできない」というのは、当事国は無論、支援国であってもそう考えざるを得ないところなのだが、しかし、ならば、どちらかが決定的敗れるまで、この「消耗戦」を続けるべきなのか。
ひとつ言えることは、「国家」としては絶対に負けるわけにはいかないのだけれども、国民としては、家族を殺されるくらいなら、敵国の占領下に入った方が、たぶんマシだろうということだ。
たしかに敗戦国民の生活は、楽しいものではないだろう。だが、敗戦国民が、全員殺されるというわけではないのだから、降伏すべき時には降伏した方が、個人としては正しい判断だと言えるのではないだろうか。
寺山修司が歌っているとおりで、所詮、自分あってこそ、家族や友人が生きていてこその「お国」なのだ。
マッチ擦する つかのま海に 霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや
無論、そんな「最後の選択」をしないで済むためにこそ、「平時の備え」は重要である。
だから、「平和主義」とは「平和のために死ぬ」ことではなく、「死なないでいいように、平和を保つ手立てを凝らす」ということなのではないだろうか。
『孫子』の兵法は、徹底した「リアリズム」に支えられた「兵法」である。だから、「戦わない工夫を最大限にする。そのためには手段を選ばない」といったようなことだろう。
「手段を選ばない」というのが「即暴力(武装)」と考えてしまうところが、日本人の「夢想主義」ということにならないようにしなくてはいけない。最後は、誰も責任なんか取ってはくれないのだから。
(2025年1月6日)
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
