
施川ユウキ 『バーナード嬢曰く。 6』 : 〈承認と否認〉をめぐる 葛藤の果てに…
書評:施川ユウキ『バーナード嬢曰く。』第6巻(REX COMICS・一迅社)
施川ユウキの作品はほとんど読んでいるはずだが、その作品傾向を大別すると、内面性を強く反映した「叙情的な作品」と、生活的リアリズムをベースにした「自虐的ギャグ作品」の二つに分けられるように思う。
前者の代表作が『サナギさん』『ヨルとネル』『銀河の死なない子供たちへ』といった作品だとすれば、後者は『鬱ごはん』『がんばれ酢めし疑獄!!』そして、本作『バーナード嬢曰く。』もそうだろう。


もちろん、完全に二分されるというわけではなく、それぞれの作品が、どちらの性格を基調にしているかということであって、その割合こそ違っているものの、どちらの要素も含まれるのは、同じ作者の作品として、むしろ当然である。
例えば、本作『バーナード嬢曰く。』は「読書好きの、あるあるギャグ漫画」というのが基本ラインだが、その中で、バーナード嬢こと町田さわ子と、読書友だちである神林しおりとの「友情物語」という側面もあり、日頃は大ボケのさわ子は、時に、極めて繊細な心遣いと洞察によって、その「優しさ」を示し、神林の「孤独」を癒しもする。
このギャップが「グッとくる」ところでもあれば、「百合」だなどと言われたりもする部分なのだが、施川作品の通奏低音として流れるのは「孤独」であると考える私は、施川ユウキの描く「友情物語」に「恋愛」的な要素はほとんどなく、それはもっと根源的な「人間の本質的孤独からの救済願望」とでも呼ぶべきものの、洗練されたかたちなのではないかと考える。
だからこそ、神林を思いやる時のさわ子は、日頃のボケっぷりが演技なのかと思えるほどの「女神」のごとき「優しさ」で、神林を救うのだ。

そして本巻では、そうした側面がかなり強く出ているように思う。
これが何を意味するのか、無論、正確なところはわからないのだが、施川が「あとがき」で、次のように「コロナ禍」に言及しているところを見ると、その影響ということも考えられよう。
『 (※ 前巻)第5巻のあとがきを今読み返すと、切迫感あふれる筆致で新型コロナの話を綴っている。コロナ禍で一番混乱していた時期のようだ。一年半前、ずいぶん昔のような気もするし、つい最近のような気もする。』(P157)
つまり、前巻が刊行された頃は『コロナ禍で一番混乱していた時期』で、その切迫感に支配されていたが、コロナ禍の長期化で、その切迫感がだんだんと薄れていった時期に描かれたのが、この第6巻所収の作品で、徐々に緊張感が薄れきた時期だからこそ、それまでリアルな困難において押さえ込まれていた「人恋しさ」が、意識の表面に浮上してきたのではないか、という推測である。
○ ○ ○
本巻で、私が特に面白く感じたエピソード、二つについて書いておこう。神林との「友情物語」の部分ではない。
一つは、第98話(98冊目)「山月記」の回。テーマは「自意識」である。
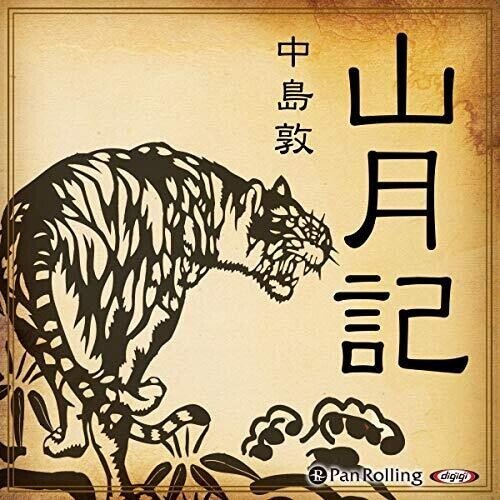
さわ子と神林は、読んだ本に「点数をつける」という行為について、次のような議論を交わす(P107〜109)。
さわ子「ふーっ なかなか面白かったよ」
神林 「そっか 貸してよかった」
さわ子「星3.8」(きっぱりと)
(それを聞いた神林は、少し退いた感じ)
「あれ低かった?」
神林 「というか 点数つけるなよ」
さわ子「神林は つけない派かー」
神林 「いやまぁ 読んだ人間の自由だからいいけど」
「作品の良し悪しを数値化するなんて 自分にはできないな」
「そもそも 未熟な私がプロの作品を採点するとか… 傲慢じゃないか」
(そう言った、神林の肩を、さわ子はポンと軽く叩いて、諭すように言う)
さわ子「神林 未熟な私たちには 傲慢になるチャンスが与えられている…!」
「若さ故の万能感から 傲慢に振る舞い やがて己の未熟さに気づいて自己嫌悪に陥る」
「それが青春!」
「傲慢を恐れていたら 成長するきっかけすら失っちゃうよ!」
神林 「屁理屈にしか聞こえないが 堂々と言われると一理ある気がしてきた…」
中島敦の名作短編「山月記」が、言わば「潔癖な自意識過剰」を描いているという点で、ここでは神林の「潔癖な自意識過剰」と対応している。
そして、「山月記」の語り手主人公が、その「潔癖な自意識過剰」の故に「虎(人外)」となってしまう不幸に対し、神林の場合は、その「潔癖な自意識過剰」を、日頃いい加減なさわ子が相対化し「中和」して、結果として神林を救済することになる。要は「人間、失敗してナンボだから、気にするな」という楽天主義である。
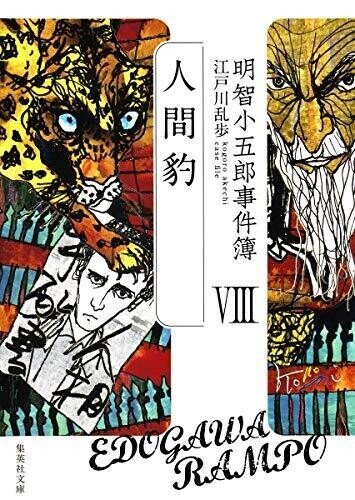

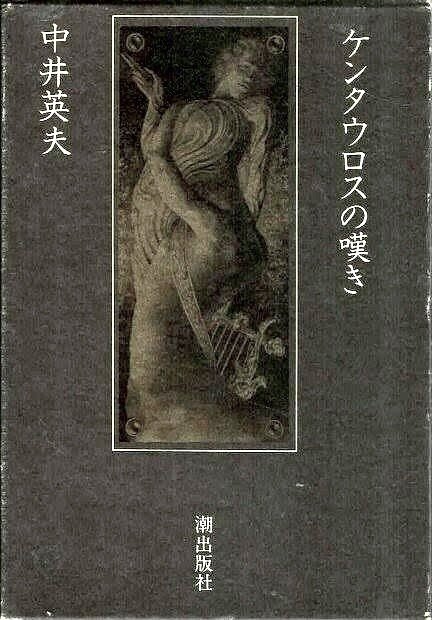
さわ子の楽天主義的な意見に、神林は完全に納得したわけではない。当然である。
さわ子は「間違った評価表明は、人を傷つける」という側面を見落としており、あくまでも「自分」の問題としか考えていないからだ。
しかし、問題は、神林が感じているような「間違ったことを言ってはいけない」「それで他人を傷つけてはいけない」というのは、「原則」として正しい「人間倫理」だとは言えるのだけれど、しかし「現実」としては、人間は神様ではなく「完璧」ではあり得ないから、必ず「間違い」をしでかす存在なのだ。
言い換えれば、さわ子も言うとおり、人間は最初から「完璧なかたちで生まれてくる」のではなく、未熟不完全なかたちで生まれてきたものが「試行錯誤の経験」を重ねることで、徐々に「完成」を目指していく存在である(でしかない)というのが「事実」。
したがって、この場合、さわ子と神林の、どちらか一方が「完全に正しい」ということではなく、正解は、その「兼ね合い」の中にしかない、ということなのである。
だから、あえて「正解」風にまとめてみるならば「人は生涯、成熟を目指して、できるかぎりの最善を尽くしつつ、しかし失敗を恐れることなく、経験を積み重ねていくべきものである」ということにでもなろう。
そんなわけで、厳密に言うならば、人は「傲慢であって良い」のではなく「傲慢に見えるくらいで、ちょうど良い」ということになる。
と言うのも、本当に「傲慢」な場合は、自身の「未熟性」に無自覚なのであり、そのために「失敗を失敗と認めない」から、それが成長の妨げになってしまう。
しかし人間が成長するためには、失敗の経験が是非とも必要であり、同時に、その失敗を失敗だと認め得る「謙虚さ」も必要となって、ここで初めて、神林の意識する「謙虚さ」が重要となってくるのだ。
つまり、「謙虚さ」というものは、「保身」のためにあるのではない、ということである。
そうではなく、「謙虚さ」とは、自分が「未熟」であることを認めて、「成長のための努力」の必要性を認めるためのものでなくてはいけない。
ところが、神林の「謙虚さ」は「潔癖な自意識過剰」に由来するものであり、「潔癖な自意識過剰」というのは、言うなれば「自分は完璧であり得る」と考える、ある種の「傲慢」でもあって、その「過剰な自意識」を傷つけないための「防衛意識」でもあるのだ。だからこそ、神林は、しばしばそんな自分に気づいて「顔を赤らめる」て恥じるし、自己嫌悪にもなる。
言い換えれば、無意識的にではあるが、すでに「完璧な自分」に、少しでも傷がつかないようにと、ビクビクしているというのが、神林の「謙虚さ」における「過剰さ」の正体なのである。

したがって、さわ子の「抜けっぷり」が、神林に示すのは「私たちは未熟だし、もともと傷(欠点)だらけの未完成品なんだよ」ということであり「だから、他人との接触の中で、切磋琢磨して、自分を磨かなきゃならないんだ」ということなのである。そしてこれを言い換えるならば「摩擦を恐れるな」ということであり、声高に「傷つけられた」とアピールしたがる人の目立つ昨今の日本人には、殊のほか重要な認識なのだと言えるだろう。

(上の2枚は、第3巻より)
さて、次の興味深かったエピソードは、第101話(101冊目)の「レコメンド」。
「レコメンド」とは、要は「おすすめ」のことであり、例えば「おすすめ本」なんかもそうである。
この話題で思い出すのは、またしても先日の「書評家・豊崎由美による、TikTokerけんご批判」である。
けんごは、豊崎由美に「まともな書評が書けるのか」と言われて、
『書けません。僕はただの読書好きです。
書けないですが、多くの方にこの素敵な一冊を知ってもらいたいという気持ちは誰にも負けないくらい強いです。
読書をしたことがない方が僕の紹介を観て「この作品、最高でした」「小説って面白いですね」と言ってくれることがどれだけ幸せなことか知ってますか?』

と、このように、読解力のない一般読者向けの「泣き落とし」を綴っているが、本の「おすすめ」をして喜ばれた時の喜びなど、読書家なら誰でも知っているに決まっている。なぜなら、それは「相手を喜ばせる」のと同時に「自分の価値観が追認される」ことでもあるからだ。
平たく言えば、「共感」されて「幸せ」な気分にならない人間など存在せず、それは豊崎由美でも私でも当然同じであり、『どれだけ幸せなことか知ってますか?』なんて問いは、「愚問」である以上に「自分だけは、よく知っている」という「傲慢(エリート意識)」の証でしかないのである。
まあ、このような「読み」は、それなりの「文学読み」には容易なことでしかないが、けんごの上のツイートの、「成心」丸出しの露骨な「お涙頂戴の意図」すら読み取れないような未熟な読者が、けんごのリコメンドを喜ぶのは「身の丈にあった選択」として、仕方のないことなのではあろう。
しかし、第98話(98冊目)「山月記」の回の感想として書いたように、「自分の未熟さを反省できない」人間は、成長できない。
未熟さを、未熟だと指摘されて、それをいつまでも認められないような人間は、いくら歳をとっても未熟なままで終わるのだ。決して「時間の経過とともに、自然に成長」したりはしない。
某氏が『認めたくないものだな……自分自身の、若さ故の過ちというものを』と語って、「反省」の必要性を認めていたとおりで、人間は「反省」が無いままでも、歳をとれば、おのずと相応に「読解力」がつく、なんてことはないのである。
したがって、私としては、町田さわ子が語ったように、けんごとそのファンには、「若さ故の万能感から 傲慢に振る舞い やがて己の未熟さに気づいて自己嫌悪に陥る」という「反省経験」を、いつかはして欲しいと願わずにはいられない。しかし、そのためには「失敗を失敗、未熟を未熟だと教えてくれる、大人の存在」が、是非とも必要なのである。
ともあれ、この第101話(101冊目)「レコメンド」は、単純に「とにかく承認されれば良い」という内容ではないことを、多くの読者に読み取ってもらいたいところである。
若者よ、承認コジキにだけはなるな。
未熟だが、成長を目指し続ける者こそが、そのままで、真に素晴らしい人間なのだから。
(2021年12月25日)
○ ○ ○
○ ○ ○
