
小川哲 『君のクイズ』 : 理想と現実の狭間で
書評:小川哲『君のクイズ』(朝日新聞出版)
小川哲にしては薄目の本であり、いわゆる「鳴り物入り」の刊行ではなかったせいか、刊行されているのに気づくのが遅れてしまった。
例によって、帯には4つもの「推薦文」がにぎやかに並んでいるのだが、しかし、伊坂幸太郎以外は、知らない名前である。
「肩書き」が無いから、いわゆる「カリスマ書店員」ではなさそうだし、何者だろうと思いながらも、そのまま本編を読んだのだが、読了した今は「きっと、テレビで有名な、クイズ王たちなんだろうな」と思い、検索してみた。一一結果は、読み筋としては悪くはなかったが、正答ではなかった。


人気ミステリー作家である「伊坂幸太郎」は別にして、帯の推薦文が、伊坂と同じく「赤文字」で刷られている新川帆立は『日本のミステリー作家、弁護士。元プロ雀士』だそうで、2020年に『元彼の遺言状』で第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した、若手ミステリ作家のようだ。
一方、帯に「青文字」で推薦文の刷られている、佐久間宣行は『日本のテレビプロデューサー、演出家、作家、ラジオパーソナリティ、YouTuber、司会者』で、要は、本作中でも重要な役どころである、プロデューサーという「テレビ番組」を作る側の人物。
そして、最後の山上大喜は、「東京大学」の学生で「クイズライター」だった。
それぞれの「推薦文」(帯に刷られた推薦文)は、次のとおり。
『面白すぎ!!こんなに興奮する
謎に出会ったのは久しぶりで
ミステリーとしても最高。
小川哲さん、ほんとすごいな。
一一伊坂幸太郎 』
『一度本を開いたら
もう終わり。
面白すぎてそのまま読み切ってしまった。
ミステリー?バトルもの?人生ドラマ?
ジャンルは、たぶん「面白い小説」だ。
一一佐久間宣行 』
『読了後、世界のすべてが
クイズに見える。
妙にクセになる中毒性を
味わってほしい。
一一新川帆立 』
『物語の謎に入り込む。
クイズのリアル。
こんな片隅までよくぞ、
描いてくださいました!
一一山上大喜 』
「肩書き」を知った上で読めば、伊坂と佐久間の推薦文は、いかにも「世慣れ」した感じだし、新川と山上は若手らしく「ハッタリ」めいた書き方ではない。
特に、本作の主人公と同じく、自らもクイズを嗜むのであろう山上のそれは、推薦文ではなく、「クイズ業界を描いてくれた」作者への感謝のメッセージと言った方が正確なものであり、初々しささえ感じさせて、なるほどという感じであった。
本作は、「対戦型クイズ競技」の世界を扱った作品である。テレビでよく見かける「クイズ王なんたら」とかいった感じのアレである。
私も若い頃は、人並みに『クイズ タイムショック』『アップダウンクイズ』『クイズダービー』『パネルクイズ アタック25』あるいは『ダイビングクイズ』なんていうテレビ番組を視たものだが、成人してからは、ああいう番組は視なくなった。
読書家になってからは、ああした「断片的な知識の量」を競うようなものには、つまらなさを感じるようになったからであろう(別に、それが「悪い」というのではない。駆けっこなどの各種運動競技に興味がない、というのと同じ話である)。




それにしても、今の若い人は『ダイビングクイズ』なんて番組は、聞いたこともないはずだ。
回答者は、スタジオに設置された「すべり台」の上で回答をし、誤答すると、すべり台の角度が急になっていき、すべり落ちてしまったところでゲーム終了、という番組だったが、私も、すべり台の印象こそ強く残ってはいたものの、番組名は、検索して知った後でも思い出せなかった。
1964年から1974年まで放映された長寿番組で、私は1962年生まれだから、主に後半を記憶しているのだろうが、おじいちゃんが番組名を思い出せなくても、孫の世代の「クイズ王」たちなら、きっと番組名を即答できるのだろう。あの番組の面白さを、知らなかったとしても、だ。

○ ○ ○
本作の「ストーリー」と「煽り文」は、次のとおり。
『生放送のTV番組『Q-1グランプリ』決勝戦に出場したクイズプレーヤーの三島玲央は、対戦相手・本庄絆が、まだ一文字も問題が読まれぬうちに回答し正解し、優勝を果たすという不可解な事態をいぶかしむ。いったい彼はなぜ、正答できたのか? 真相を解明しようと彼について調べ、決勝戦を1問ずつ振り返る三島はやがて、自らの記憶も掘り起こしていくことになり――。
読めば、クイズプレーヤーの思考とその世界がまるごと体験できる。人生のある瞬間が鮮やかによみがえる。そして読後、あなたの「知る」は更新される!
「不可能犯罪」を解く一気読み必至の卓抜したミステリーにして、エモーショナルなのに知的興奮に満ちた超エンターテインメント!』
このように、本作は「対戦型クイズ競技」(以下「クイズ」と記す)の世界を描いた作品だが、物語を駆動する謎は『まだ一文字も問題が読まれぬうちに回答し正解し、優勝を果たすという不可解な事態』である。一一はたして、この真相は「ヤラセ」か「超能力の類」か、あるいは「何らかの合理的な方法」によるものか、という「謎」を、当該クイズ番組の決勝戦で敗れた、本編の主人公である「三島玲央」が追っていく、というお話だ。
だが、本作は、いわゆる「本格ミステリ」ではない。
すぐれた「ミステリー」作品だと書いている推薦者がいるし、本作の謎は、一種の「不可能犯罪」的な謎なので、Amazonカスタマーレビューなどを見てみると、「本格ミステリ」を期待してしまった(そして、腹を立てた)読者も少なくなかったようだが、本作は、いわゆる「ミステリー作品」であって「本格ミステリ」ではない。末尾に「ー(長音符)」の付いた「ミステリー」なのだから、「騙された」と言うのは、少々「筋違い」だ。
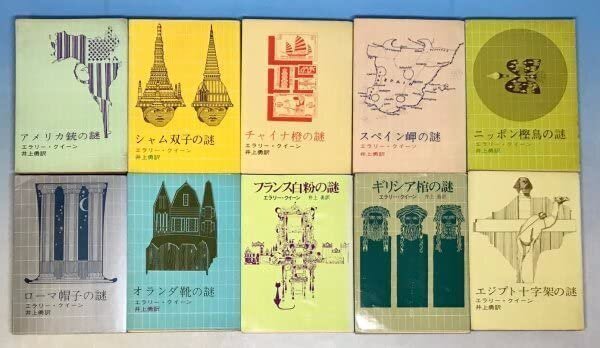
もともと、伊坂幸太郎は「本格ミステリ」の人ではないし、佐久間宣行はテレビ・ディレクターでしかない。まして、記名のない「煽り文」は、編集者あたりが書いたものだろうから、「本格ミステリ」と「ミステリー」の厳密な使い分けを期待するほうが間違っている。
逆に、「本格ミステリ」マニアなら、そこを一緒くたにして「誤解」した、自身の迂闊さを反省すべきであろう。
一一で、本作は、こういう「マニアの美意識」に関する物語、だと見るべきであろう。
「本格ミステリマニアならば、論理的に厳密であるべきであり、明らかな語句の違いを見落としてしていたのなら、それは自身の過失であって、出題者を責めるべきではない」といった「美意識」と同様、本作の主人公である「三島玲央」も、「クイズとは、かくあるべき」という「美意識」を持った、ある種の完璧主義者であり、だからこそ「ゼロ文字正答」が「クイズとして、ありえないもの」と考える。
つまり、単純に「問題が、ひとことも読まれていない段階では、問題の中身を論理的に推測することは不可能であり、それでは問題を解いたことにはならない」という考え方であり、要は「ヤラセ」のインチキは論外として、「超能力」や「まぐれ当たり(あてずっぽう)」の類いで「正答」したとしても、それは「クイズ」の回答としては(「解答」ではないから)「邪道」でしかないと、三島は考えるのだ。
しかし、三島自身も、「本庄絆のゼロ文字正答」の「真相」がわからなかったので、完璧主義者である彼は、その真相の「謎解き」を試みる。
だが、世間の単なるクイズファンはおろか、他の常連クイズプレイヤーたちでさえ、「本庄絆のゼロ文字正答」を、自分の「常識」や「世界観」に従って、「奇跡的な能力」か「ヤラセ(インチキ)」のいずれかとしか考えず、それを持って、肯定したり否定したりするだけで、「真相を究明しよう」とはしなかった。
だが、三島にとっては、「ヤラセ(インチキ)」であれ「奇跡的な能力」であれ、いずれにしろどちらも、「クイズ」の範疇にあるべきものではない。
とは言え、やはり両者はまったく「質の違ったもの」なのだから、そのあたりを曖昧にしたまま、本庄を責めることなどできない、とそう考えたのだ。
○ ○ ○
【※ 本作における「ゼロ文字正答」のネタを割りますので、未読の方はご注意ください】
「ゼロ文字正答」は、いかにして為されたのか?

その答は、「ヤラセ(インチキ)」でもなければ、「奇跡的な能力」によるものでもなかった。
あえて言うなら、その「中間」だった、というのが、本編での「真相」であった。
つまり、本庄は、最後の出題となった問題について、ある程度の「予測」を立てることが可能な立場(特別な立場)にあった。しかし、その「不確定であり、その意味で幅を持つ、予測」を「正答」にしたのは、やはり彼の「非凡な才能と努力」があったからに他ならなかった。
だから、この「正答」は、完全な「ヤラセ(インチキ)」でもなければ、「奇跡的な能力=超能力」だけによるものでもなかったけれども、三島の考える「クイズ」の「理想」からすれば、それは「半分はインチキで、半分は努力によってつちかわれた非凡な実力によるもの」だった、ということになるのである。
で、この「解答」を、「本格ミステリ」を期待した読者が受け入れられなかったのは、冒頭の「ゼロ文字正答」のシーンにおいて「正答に至ることを可能とするための、すべてのヒント」が出されていたわけではなく、三島が謎を追っていく過程で、正答に必要なヒントが「小出し」にされたからである。
つまり、冒頭の「本庄絆のゼロ文字正答」のシーンだけでは、その「謎」を論理的に解くことは不可能であり、本格ミステリにおける「問題篇」としては不完全だった、ということだ。
だが、狭義の「本格ミステリ」ならばともかく、広義の「ミステリー小説」の場合、最初から「合理的な推理を可能にするだけのヒント」が「すべて与えられている」必要など、ない。いわゆる「本格ミステリ」に分類されている小説であっても、主人公である「名探偵」や「刑事」が、謎を追っていくうちに「ヒント」を見つけるといったことは普通にあることなのだから、本作が「ガチガチの(読者挑戦型)本格ミステリ」ではなかったと責めるのは、明らかに行き過ぎであり、あまり「本格ミステリ」を読んでいない、未熟な「本格ミステリ」読者の勇み足、だと評するべきなのである。
○ ○ ○
では、本作の「読みどころ」は、奈辺のあるのだろうか?
それは、人の「こだわり」や「理想」や「美意識」といった問題であり、そしてそうしたものが「一般大衆には無い」という「諦観」である。
一一つまり、小川哲という作家の、最大の特徴と言っても良い「諦観」が、本作でもまた描かれているのだが、薄っぺらで表面的な「推薦文」や「紹介文」においては、誰もそこまで指摘できていないから、それらを鵜呑みにするだけの、思考の停止した読者には、本作は「誤読」されがちな作品となっているのである。
最後まで読めばわかることだが、本作は明らかに「こだわり」や「理想」や「美意識」の物語であり、しかし、それが多くの場合、他者とは共有されないものである、という「残念な現実」を描いている。
同じように「クイズ」をやっている仲間であっても、「クイズ」にかける情熱やこだわりは、所詮、ひとそれぞれでしかなく、損をしてでも「クイズの美学」を貫きたいという主人公の三島のようなストイックな人間もいれば、三島が、同じような理想の持ち主であることを期待した、ライバルの本庄は、その期待どおりの人物ではなかった(つまり、実利優先のリアリストだった)。
本作は、世間ではあまり知られていない「クイズの世界」を描き、「クイズプレイヤーの内面」を描いているという、言うなれば、読者の「覗き見趣味」を満たすところで話題になってはいるものの、その本質は、もっと「普遍的なもの」であると言っていい。
例えば、本作における「クイズ」とは、「小説」の寓喩であると、読書家ならば、そう「考えるべき」なのだ。なぜなら、それが「読書家の美学」だからである。
本作における「クイズ」が「小説(書き)」の寓喩である、とはどういうことなのか?
「小説書き=文学」とは、「人間を描かなければならない」とか「人間の心理や実存を描かなければならない」とか「通俗的なウケに走ってはならない」とか「派手な惹句や推薦文を並べるといったことで、読者を欺こうとしてはならない」「結局は売れるが勝ち、なのではない=小説は、その内容的な深さと完成度において、価値評価がなされるべきである」といった考え方は、「小説書き」における、一種の「こだわり」や「理想」や「美意識」の問題だと言えるだろう。
だが、周知のとおり、現在の出版界では、こうした「こだわり」や「理想」や「美意識」が、ほとんど顧みられない状態にあると言っていい。
作家であれ編集者であれ「結局は、売れてナンボでしょ」と思っている者は少なくないし、それを口に出す者さえ少なくないだろうというのが、昨今の状況である。
無論、これは「小説書き」に止まる話ではない。
なによりも「読者」の方、つまり「小説読み」の方が、「深遠な文学とか、いらない」とか「(類型的な作品でも)面白ければ良い」とか「ミステリーは、ビックリさせてくれればいい=伏線の妙とか厳密なロジックとかまで読み込むほど、暇ではない」ということになってしまっており、言い換えれば、「小説読み」としての「こだわり」や「理想」や「美意識」を失って、「新自由主義的な消費者」に頽落してしまっているからこそ、「小説家(小説書き)」の方も、「こだわり」や「理想」や「美意識」にこだわって書いていたのでは、プロとして「上がったり」になってしまうので、ほとんどの作家は、本作の主人公である「三島玲央的な生き方」ではなく、三浦の期待を最後は裏切る「本庄絆的な生き方」を選ぶことになるのである。
つまり、本作は、小川哲という作家の内面を、かなりハッキリと描いた作品だと言えるだろう。

小川哲は、本当なら「文学的な作品=重厚な作品」を書きたいのである。
しかし、自身のそうした「こだわり」や「理想」や「美意識」を全開にしてしまったら、プロの作家として「食っていく」ことはできないと悟っており、そうした「諦観」の上に立って、戦略的に自身の「作家としての確固たる地位=好きなように書いても売れる立場」を築こうとしているのだ。
そのためには、ひとまず、馬鹿にも「ウケる小説」「売れる小説」を書かなければならない。
もちろん、自分の個性を最大に発揮できるジャンルにおいて、それをやらなければ、馬鹿にも「ウケる小説」「売れる小説」というのだって、狙って書けるわけではない。
また、実際問題として、「小説」というのは、「中身が良ければ売れる」というものでもない。
だから、何よりも、今の市場に必要なのは「宣伝」である。
では、どうすれば効率的な宣伝が可能なのか。
そのひとつは「インタビュー」や「対談」などを積極的に行って、可能なかぎりメディアに露出し、自分が「売れっ子」であると世間にアピールして人々の興味を惹きつけ、「この作家が流行っている」という「印象」を植え付けることだ。
小説の中身が読めない読者ほど、そうした「宣伝」による「イメージ」に弱いものだし、「インタビュー」なら、作品の意図や狙いを語ることで、それが「作品からは読み取れない読者」に、興味と安心感を持たせることができる。なぜなら、多くの凡庸な読者は、その作品を読んだ後は、作者が「インタビュー」などで語ったことを、そのまま「受け売り」で語っておけば、「読める読者」に見えると、半ば無自覚に考えるからだ。
また「対談」であれば、相互の「褒め合い」によって、お互いに「権威づけ」をすることができる。凡庸な読者は、こういうのにも弱い。
また、「対談」で人脈を築いておけば、「文学賞レース」においても有利に働くのは、疑い得ない事実である。「文壇」とは、昔から、そういう(党派政治的な)ものなのだ。
そして、そのような「地道な努力」の果てに首尾よく「文学賞」作家になれれば、それで「プロの地位」が、一定のところは保証される。
言い換えれば、「文学賞」であれば何でも良いということではなく、一般世間が興味を持つ「有名な賞」の受賞者でなければならないない。例えば、「芥川賞・直木賞」とか「本屋大賞」とか。


しかし、「芥川賞」は純文学を対象とした賞だから、そうしたものが書けるとしても、自分のこれまでの経歴からすると、読者にわかりにくいものになるので、取るのなら「直木賞」だろう。「本屋大賞」は、受賞すれば、その本は売れるだろうが、作家の「肩書き(権威保証)」としては弱いので、それは目標となるようなものではない。同様に、例えば「泉鏡花賞」や「ドゥマゴ文学賞」とかいったマニアックな賞は、くれるものなら、もちろんもらいはするが、一般人の知らない賞なので、永続的な「売上げ」につながる「肩書き」とはならない。したがって、それらはあくまでも、「ステップ」であり「おまけ」であると考えるべきである。
一一と、このような「生き残り戦略」を優先して、それに「クイズ」をも従属させたのが、本庄絆という人物だったのである。

つまり、本作は、三島玲央と本庄絆という二人の「優秀なクイズプレイヤー」のそれぞれに、自身の「内面の理想」と「外的な現実」を投影して描いた作品だと、そう言って良いのではないかと思う。
三島玲央のような「こだわり」や「理想」や「美意識」を、自分だって持っている。
しかし、それをそのまま実行動に反映してしまったら、自分は「実在の人間」として、「プロの作家」として生き残っていくことが困難になろう。
だから、なかば「忸怩たる思い」を抱えながらも、本庄絆のように生きることを、自分は否定できないだけではなく、そちらの生き方を、「方便」的に選ばないではいられないのだ。太宰治だって、芥川賞が欲しくて、選考委員の佐藤春夫に「受賞嘆願の手紙」を送ったほどなのだから…。
本作は、そういう、やるせない「著者の諦観」を込めて、「人間を描いた」作品である。
一一そう言って良いのではないだろうか?
(2022年12月4日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
