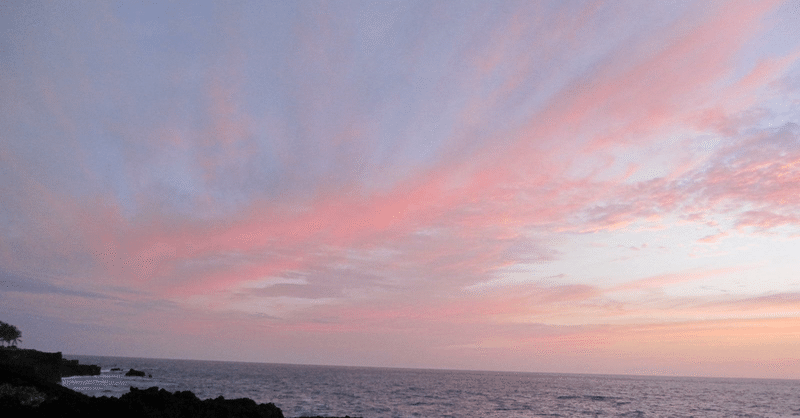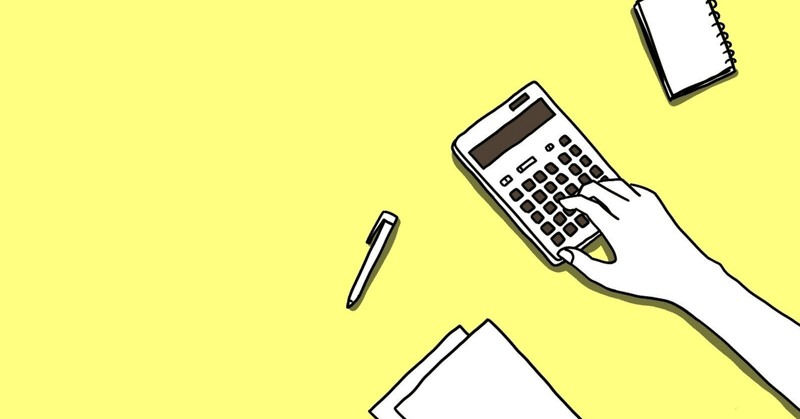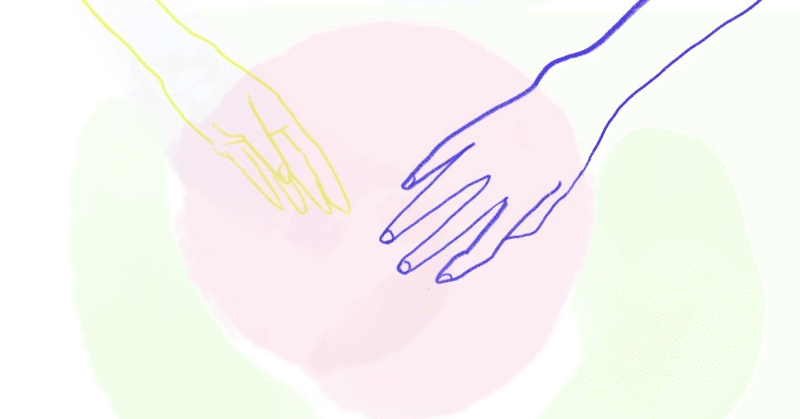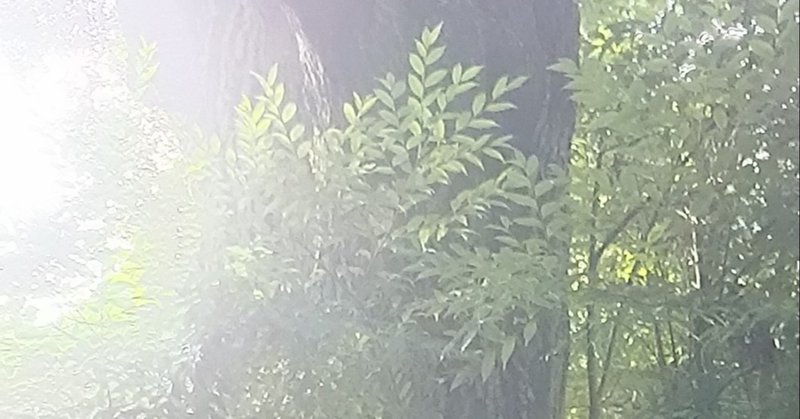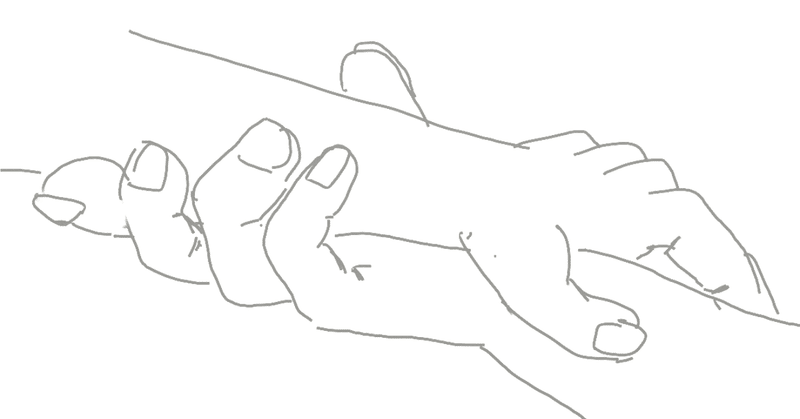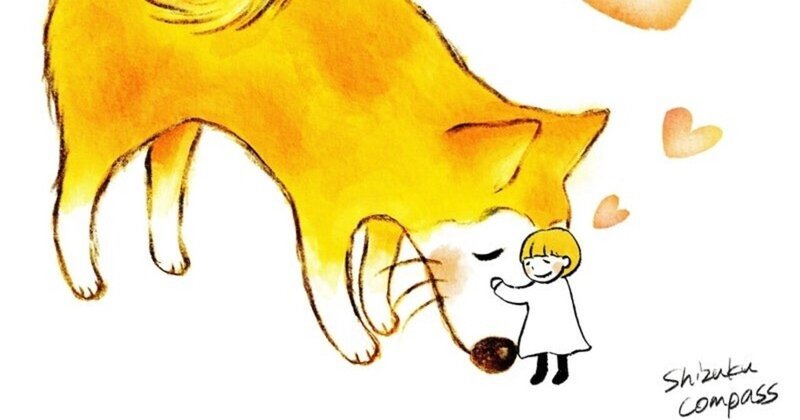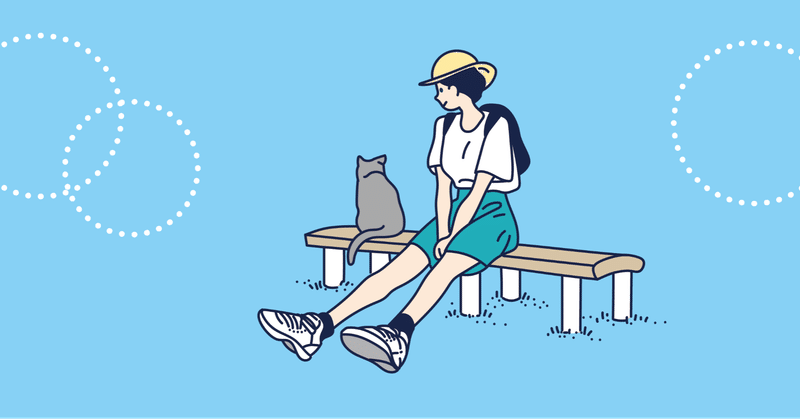記事一覧
認知症とアロマテラピー 鼻のもつ力とこころの力を信じてみるならば
こんにちは
毎日暑いですが、みなさまお元気ですか。
セミも元気に鳴いていますが、ツクツクボウシも鳴きはじめました。
そして今日は長崎平和祈念の日ですね。
さて、本日は
認知症とアロマテラピーについて書いてみたいと思います。
というのも、立て続けに認知症について、アロマでできるはことないかとのお問い合わせをいただいたからです。
せっかくのなので、今回は
一般的なアロマテラピーでの認知症の予
不安をやわらげ力を与える「多感覚コミュニケーション」の話
心理的に不安を抱えている人に対して、目を見て、触れながら話をする「多感覚コミュニケーション」を積み重ねることで、相手に活力を与えることができる、という話を書きます。
たとえば「握手をしながら目を見て話す」といったように、複数の感覚を用いたコミュニケーションを「多感覚コミュニケーション」といいます。このような方法は、赤ちゃんや子どもと関わるときにとても役に立ちます。
ユマニチュードの思想と技法今
タッチケア(触るケア)で、幸せホルモンのオキシトシンが分泌され、痛みの緩和、認知症の人の乱暴な言動が減るなどの効果。声を聞くだけでも分泌
「幸せホルモン」と呼ばれる「オキシトシン」。
例えば、実験によると、5分間、人と抱き合う(ハグする)と、カップル同士ではなく友人同士などでも、オキシトシンが増えて(ホルモンの量は唾液を採取して調査)、幸せな気持ちになる。
そのオキシトシンが、「タッチケア(触るケア)」によって増加するということが注目されている。
スウェーデンでは、医療の現場や保育所、小学校でもタッチケアが行われ、痛みの改善・
『介護力 = 人間力』 介護すると身につくスキル~思いやり~
介護をする人は思いやりがある。
多くの人は漠然とそう思っている。
介護職を選んだだけで「優しそうだものね」と声を掛けられるし、大変な仕事を頑張っている人というイメージがつきまとう。
それはそれでありがたい話しですが、ある意味洗脳となり自分を見失ってしまう人も少なからずいる。
元々自分が持っている『人を思いやる気持ち』と、スキルとして身についていく『思いやり』では種類が異なるように感じます。
介護で『幸せホルモン』を分泌させる~セロトニン♪
『幸せホルモン』と言われているセロトニン。
セロトニンが分泌されると精神の安定・安心感、自律神経が整う、脳の活性化、記憶力低下の予防などの効果が期待できます。
分泌される場面としては、
日光を浴びる、食事でトリフトファンを摂取する、涙を流す、腹式呼吸、リズム運動などが上げられます。
介護において、セロトニンが分泌され幸せを感じられるとは、どういった場面なのか?ご紹介いたします。
リズム運動
介護で『幸せホルモン』を分泌させる方法~自分編~
介護をしていると『幸せホルモン』と呼ばれる
・ セロトニン
・ オキシトシン
このホルモンを相手に分泌させているのでは?と過去記事で説明してきました。
今回は介護をしている自分も『幸せホルモン』が分泌されているんじゃないかと思い、記事にしてみます。
肌に触れると愛情を感じる介護の場面では肌に触れることが多くあります。
相手に触れることで介助方法や力の加減、身体の調子を微妙に感じとることが