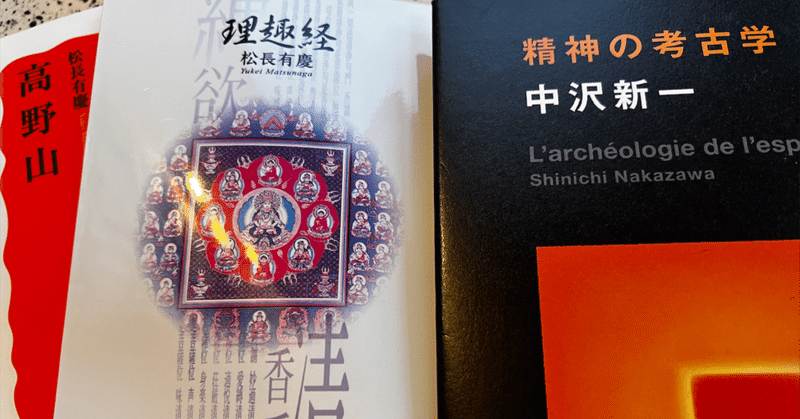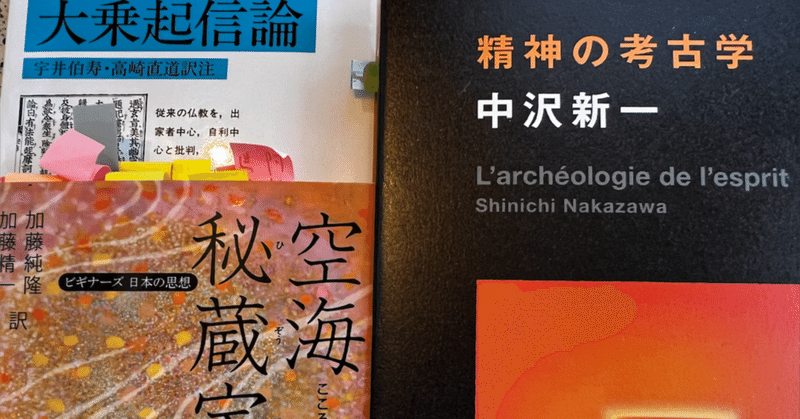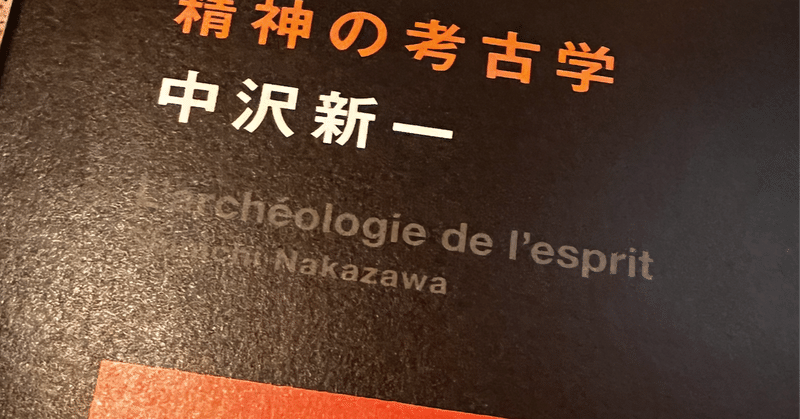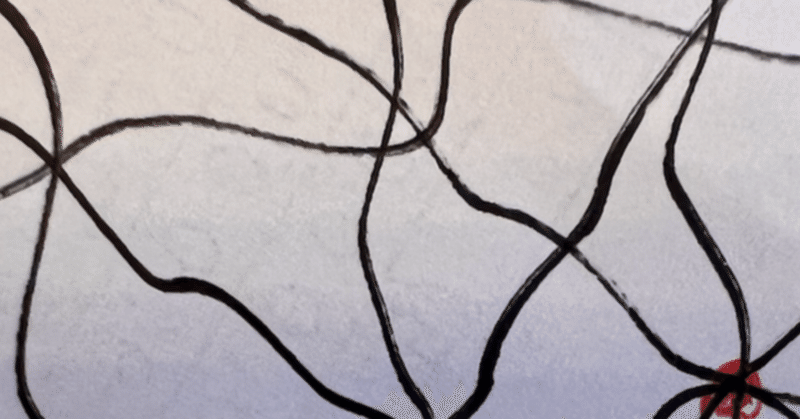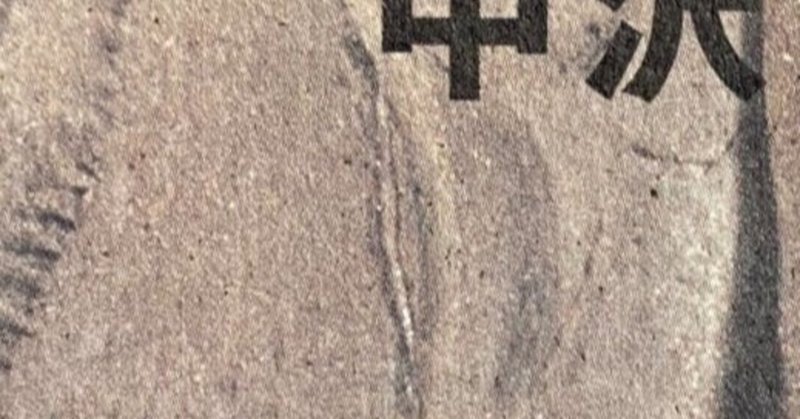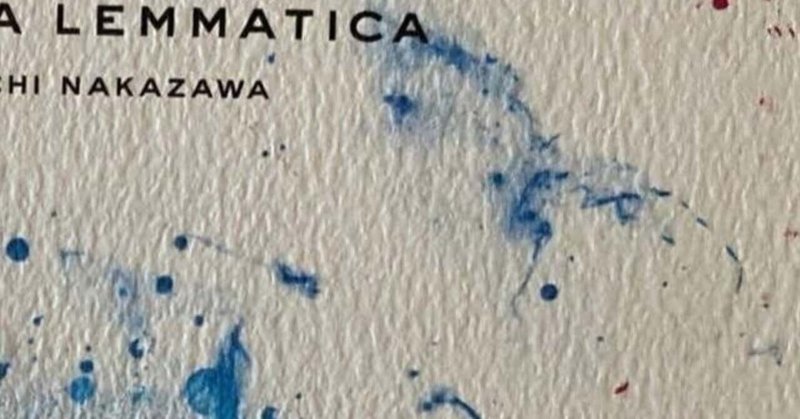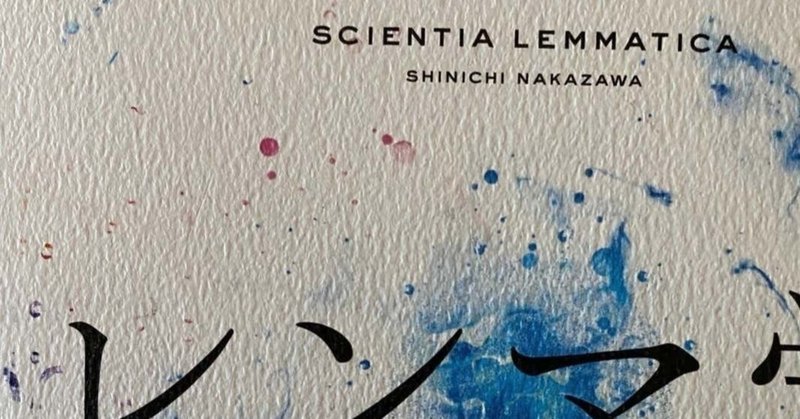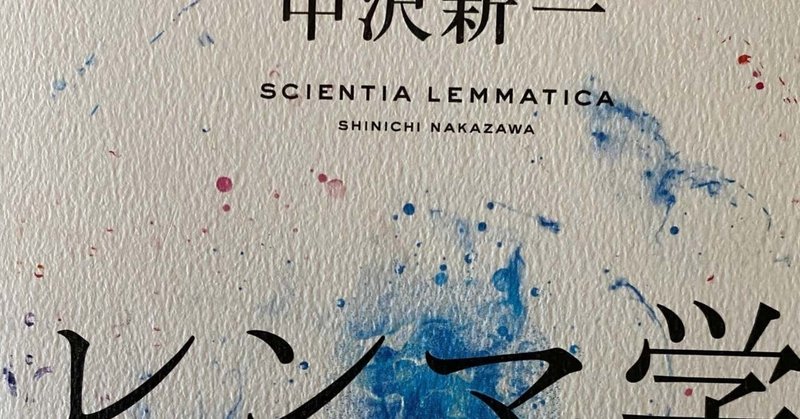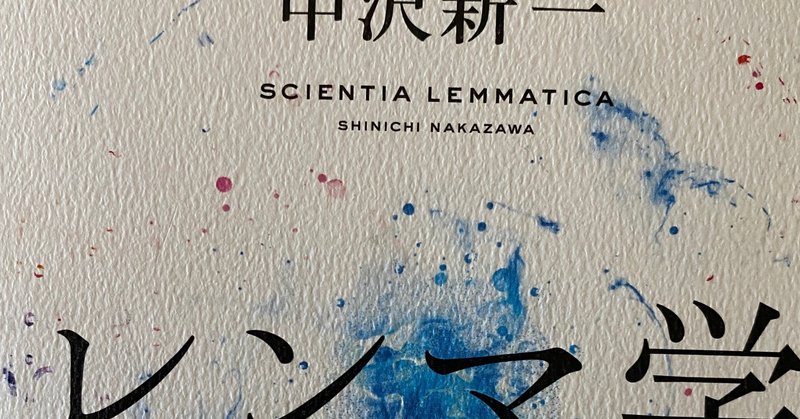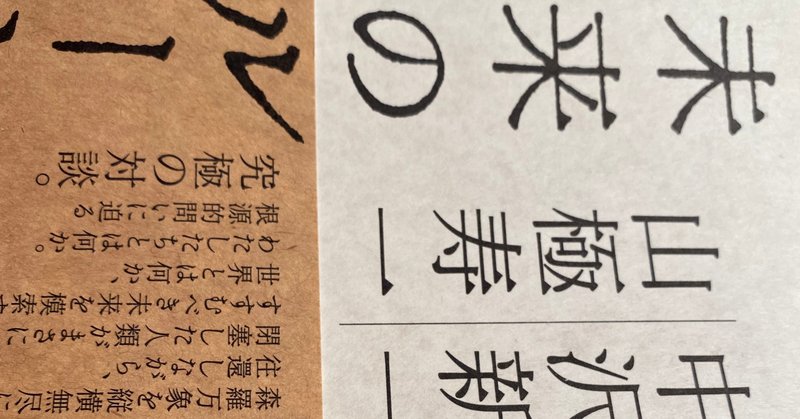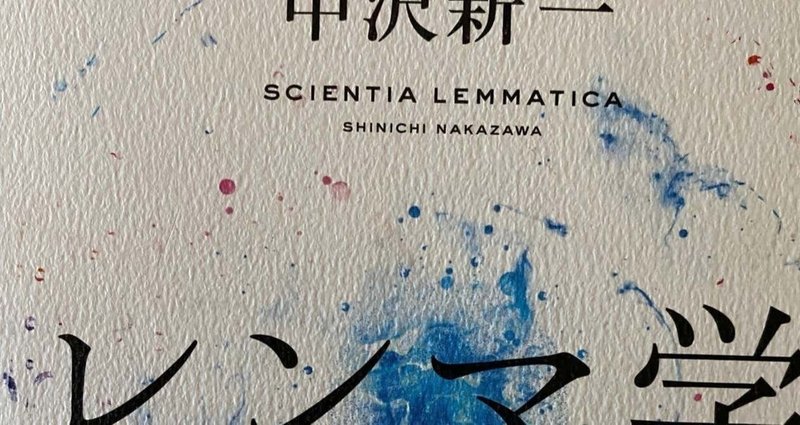
- 運営しているクリエイター
#読書
ユング、マンダラ、共時性:ユングの論文「共時性:非因果的連関の原理」を読むーーユングとパウリの共著 『自然現象と心の構造』より
深層心理学で知られるカール・グスタフ・ユングと、「パウリの排他律」で知られる物理学者ヴォルフガング・パウリとの共著『自然現象と心の構造』を読む。
パウリの手による論文「元型的観念がケプラーの科学理論に与えた影響」については下記の記事で論じたので、今回はユングの手による「共時性:非因果的連関の原理」を読んでみよう。
「偶然」の世界・・偶然?必然?「共時性:非因果的連関の原理」の冒頭、ユングは次の
超-明るい部屋へ/埋蔵経典を”発掘”する神話的思考 -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(7)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。
精神の考古学。
私たちの「心」は、いったいどうしてこのようであるのか?
私たちが日常的感覚的に経験している分別心(例えば、好き/嫌いを分別したり、自/他を分別したりすることは当たり前だと思っている心)が、発生してくる深みへと発掘を進める中沢氏の「精神の考古学」。
いよいよ第八部「暗闇の部屋」を読んでみようと思う。
ここで中沢氏は、「まったく光の
分別する眼と無分別の眼を共鳴させる -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(4)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。今回は、第五部「跳躍(トゥガル)」を読んでみよう。「トゥガル(跳躍)」とは、「青空と太陽を見つめる光のヨーガ」である(p.175)。
「光」を「みる」、視覚のモデルこのヨーガを修することで、あるとても不思議な「光」を「みる」ことができるようになるという。
*
通常、「見る」といえば、感覚器官である「眼」に「外界」からの「光」が「刺激」として入力され
”心”の表層を剥がしていくと -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(2)
ひきつづき中沢新一氏の『精神の考古学』を読みつつ、ふと、松長有慶氏による『理趣経』(中公文庫)を手に取ってみる。かの理趣経、大楽金剛不空真実三摩耶経を、かの松長有慶氏が解説してくださる一冊である。
はじめの方にある松長氏の言葉が印象深い。
苦/楽
大/小
何気なく言葉を発したり思ったりする時、「その」言葉の反対、逆、その言葉”ではない”ことを、一体全体他のどの言葉に置き換えることができるのか
詩的言語/サンサーラの言葉とニルヴァーナのコトバの二辺を離れる -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む
しばらく前のことである。
「人間は、死ぬと、どうなるの?」
小学三年生になった上の子が不意に問うてきた。
おお、そういうことを考える年齢になってきたのね〜。と思いつつ。
咄嗟に、すかさず、大真面目に応えてしまう。
生と死の二項対立を四句分別する。
念頭にあるのはもちろん空海の「生まれ生まれ生まれて、生のはじめに暗く
、死に死に死に死んで、死のおわりに冥し」である。
こういうのは子どもに
中沢新一氏の新著『精神の考古学』を読み始める
中沢新一氏の新著『精神の考古学』を読んでいる。
私が高専から大学に編入したばかりの頃、学部の卒研の指導教官からなにかの話のついでに中沢氏の『森のバロック』を教えていただき、それ以来中沢氏の書かれたもののファンである。また、後に大学院でお世話になった先生は中沢氏との共訳書を出版されたこともある方だったので、勝手に親近感をもっていたりする。
中沢氏の書かれるものには、いつも「ここに何かがある」と思
意味分節理論とは(10) 分節と無分節を分節する ー意味分節理論・深層意味論のエッセンス 〜人類学/神話論理/理論物理学/人間が記述をするということを記述する
noteのシステムから当アカウントが「スキ」を7000回いただいているとの通知がありました。みなさま、ありがとうございます!
いったいどの記事が一番「スキ」をいただいているのだろうかと調べてみると下記の「難しい本を読む方法」がスキの数一位でした。
二年ほど前に書いた記事ですが、改めて読むとこの記事自体が難しいような気がしないでもないです。
* *
この記事の趣旨を煎じ詰めれば「分かる」とい
"現実”の深層へ -中沢新一著『精霊の王』(と『アースダイバー 神社編』)を精読する(7-1)
(このnoteは有料に設定していますが、最後まで無料でお読み頂けます)
中沢新一氏の著書『精霊の王』を精読する連続note、その7回目である。
(前回はこちらですが、前回を読んでいなくても、今回の話だけでお楽しみいただけます。)
※
今回は第8章から最後までを一気に読んでみよう。・・・と思っていた所、2021年4月20日に中沢新一氏の新刊が発売されました。その名も『アースダイバー 神社編』
区別・分節作用それ自体の象徴としての"精霊"へ -中沢新一著『精霊の王』を精読する(4)
中沢新一氏の著書『精霊の王』を精読する連続note。その第四章「ユーラシア的精霊」と第五章「縁したたる金春禅竹」を読む。
(前回はこちらですが、前回を読んでいなくても大丈夫です)
精霊の王というのはその名の通り「精霊」の「王」である。
精霊には古今東西色々なものが居り、人類によってさまざまな名で呼ばれてきた。精霊は多種多様でさまざまな名を持っている。
しかし、そうした精霊たちの間には、違い
中沢新一著『レンマ学』を精読する(2)ー「縁起の論理」より、私は他者であり、他者は私である
中沢新一氏の『レンマ学』を読む。
互いにはっきりと区別された物事を、並べて積み上げたものとして世界を理解するのが「ロゴス」的な知性である。通常「知性」というと、明確に定義され互いにはっきりと区別された言葉を理路整然と積み重ねていくことのように思われているが、ロゴスはまさにそうした知性のあり方である。
◎私は私であって他の誰でもないし、他の誰かは私ではない。
◎私と他者は最初から、完全に分かれて
反復するリズムが増殖する"過剰な意味"を"日常の意味"へと媒介する −読書メモ:中沢新一 山極寿一著『未来のルーシー』
『レンマ学』の中沢新一氏と山極寿一氏の対談共著である『未来のルーシー』。300万年前の人類の祖先の化石に付けられた「ルーシー」という名前を媒介に、次々と話題が絡み合っていく。
地球の生命のひとつとしての人類について、生命の歴史の中で今日の姿に「なった」人類について、人類が他の生命から飛び抜けた力を持ててしまったことについて、縦横無尽にヒントがつながっていく一冊である。
その二回目の読書メモであ