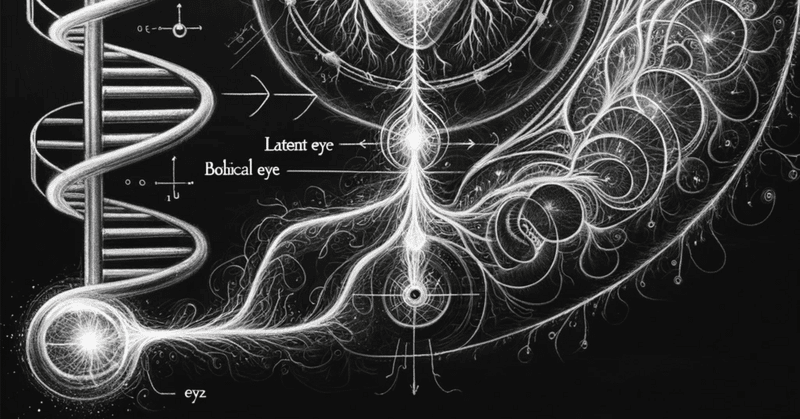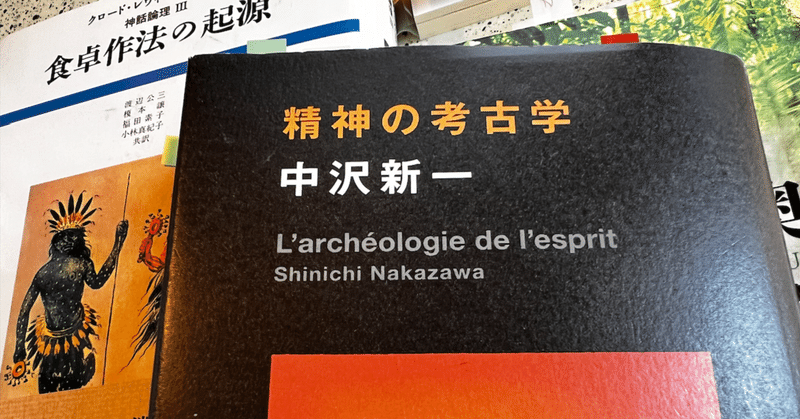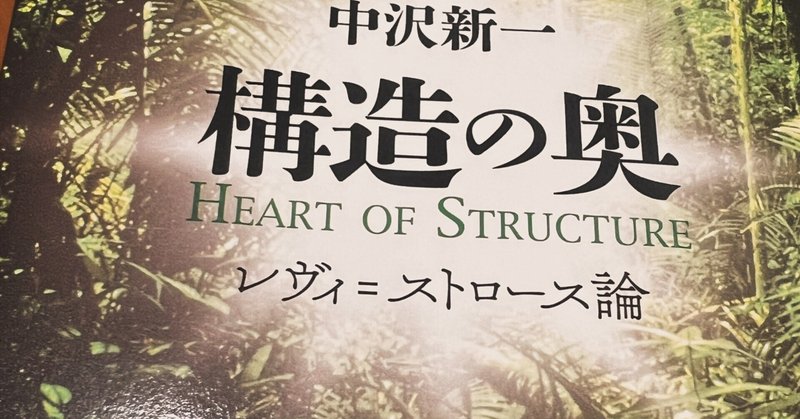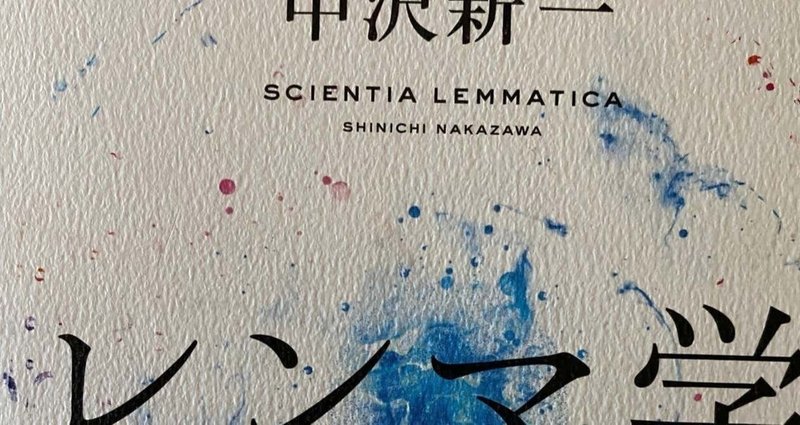
- 運営しているクリエイター
記事一覧
深層意味論的夢分析のケース・スタディ:ユングによるパウリの「マンダラ夢」分析をたどる(パウリのマンダラ夢1〜16)
C.G.ユングは『心理学と錬金術1』の147ページにおいて、「夢に現れるマンダラ」として次の例を挙げている。
ぐるりと円を描く蛇。
青い花。
手のひらの上の金貨。
サーカス小屋?
赤い球。
球体。
「蛇」、「花」、「金貨」。ずいぶんと具体的なもののイメージが並んでいる。
具体物の向こうに述語的様相の脈動としてのマンダラを幻視するこういう具体的なものには注意が必要である、というのはレヴィ=スト
無意識はマンダラ状の形態を意識の表層の一番底に映し出す ー C.G.ユング著『個性化とマンダラ』を読む
ここ最近、ふとしたことからユングの著書を読んでいる。
ユングの著作に最初にふれたのは、随分むかしのことである。
まだ中学生の頃、とあるところから「読むべし」とアドバイスを受け、読み始めたものである。
読み始めた、といっても当時は「文字がならんでいるなあ」以上のことは理解できておらず、どうにもならなかったのであるが、それでも1ページ1ページ、一文字一文字、言葉の透明な流れに手を突っ込むように、
ユング、マンダラ、共時性:ユングの論文「共時性:非因果的連関の原理」を読むーーユングとパウリの共著 『自然現象と心の構造』より
深層心理学で知られるカール・グスタフ・ユングと、「パウリの排他律」で知られる物理学者ヴォルフガング・パウリとの共著『自然現象と心の構造』を読む。
パウリの手による論文「元型的観念がケプラーの科学理論に与えた影響」については下記の記事で論じたので、今回はユングの手による「共時性:非因果的連関の原理」を読んでみよう。
「偶然」の世界・・偶然?必然?「共時性:非因果的連関の原理」の冒頭、ユングは次の
心の深層に浮かび上がる”四”について、ユングの夢、空海の曼荼羅、レヴィ=ストロースの神話論理から考える
かのC.G.ユングがノーベル賞物理学者であるヴォルフガング・パウリの「夢」を分析したセミナーの記録である『C・G・ユングのセミナー パウリの夢』を読む。
パウリの夢の分析はユングの著書『心理学と錬金術』でも整理されているが、この『パウリの夢』をつうじて、ユング自身が『心理学と錬金術』の内容をレクチャーしてくれているかのようなライブ感を楽しむことができる。
全編を通じておもしろいのであるが、特に
W・パウリ「元型的観念がケプラーの科学理論に与えた影響」における四数性と、思考の根源を思考すること ーーユングとパウリの共著 『自然現象と心の構造』より
深層心理学で知られるカール・グスタフ・ユングと、「パウリの排他律」で知られる物理学者ヴォルフガング・パウリとの共著『自然現象と心の構造』という本がある。
この本の終盤、「付録III」、236ページに次のような図が掲載されている(図3 スコトゥス・エリウゲナの『自然の分類について』において考えられた四元性)。
ここでは、
1: 造る(能動)/造られる(受動)
2: する/しない
この二つの二
法界と共鳴しつつ生きていることを知る -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(9)
中沢新一氏の『精神の考古学』を読む。
+ +
私たちの「心」は、普段、あれこれの物事を、
好き/嫌い
損/得
うまい/まずい
良い/悪い
ある/ない
うち/そと
容器/中身
などと分けては、
「あちらではなく、こちらを、絶対に選ばなければならない」
という具合に働いている。
「好きなものだけを選びたい、嫌いなものは選びたくない」、「安くてもまずいものは食べたくないが、高くて美味いものも食べ
暗黒瞑想 宇宙/非宇宙分節以前の”法界の根源的脈動”と微かに共振するアンテナとしての”わたし”へ -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(8)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。
松岡正剛氏が『空海の夢』で「仏教の要訣は、せんじつめれば意識をいかにコントロールできるかという点にかかっている」と書いている(松岡正剛『空海の夢』p.23)。
意識をコントロールする例えば、私たちが迷い苦しむのは、自/他、生/死、清/濁、光/闇、などと二つに分けて、そのどちらか一方だけを自分ものにしようとこだわり、他方を遠ざけておこうこだわるから、
超-明るい部屋へ/埋蔵経典を”発掘”する神話的思考 -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(7)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。
精神の考古学。
私たちの「心」は、いったいどうしてこのようであるのか?
私たちが日常的感覚的に経験している分別心(例えば、好き/嫌いを分別したり、自/他を分別したりすることは当たり前だと思っている心)が、発生してくる深みへと発掘を進める中沢氏の「精神の考古学」。
いよいよ第八部「暗闇の部屋」を読んでみようと思う。
ここで中沢氏は、「まったく光の
如来蔵・曼荼羅・色即是空空即是色 -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(6)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。
精神の考古学。
私たちの「心」は、いったいどうしてこのようであるのか?
心の動きの全貌を観察するために、表層の分別心だけに依るのではなく、「セム(分別心)を包摂する(深層の)無分別のセムニー」でもって、目の前に浮かぶあれこれの事柄(諸法)を見て、その「意味」をコトバでもって説く。
+ +
表層の分別心の道具としての言葉は「あちらか、こちらか」「
潜在眼で心の深層を「見る」/卵の殻としての言語 -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(5)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。
精神の考古学。
私たちの「心」は、いったいどうしてこのようであるのか。
私たちが日常的に経験している「心」は、よい/わるい、好き/嫌い、ある/ない、真/偽、結合している/分離している、同じ/異なる、自/他、といった二項対立を分別するようにうごいている。通常「心」というと、こういう識別、判別、判断を行うことが、その役割であるかように思われている。
分別する眼と無分別の眼を共鳴させる -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(4)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。今回は、第五部「跳躍(トゥガル)」を読んでみよう。「トゥガル(跳躍)」とは、「青空と太陽を見つめる光のヨーガ」である(p.175)。
「光」を「みる」、視覚のモデルこのヨーガを修することで、あるとても不思議な「光」を「みる」ことができるようになるという。
*
通常、「見る」といえば、感覚器官である「眼」に「外界」からの「光」が「刺激」として入力され
執着の源である”言語”を「心の解放」のために転用する -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(3)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。
『精神の考古学』 第五部「跳躍(トゥガル)」の冒頭、中沢氏は師匠から授けられた言葉を紹介する。
ベスコープというのは映画のことである。映画を見るのはとても楽しい体験である。感情を喚起され、いろいろなことを考えさせられる貴重な機会である。
中沢氏がネパールでチベット人の先生のもとで取り組んだ修行にも、「光の運動をみる」ヨーガが含まれている。このヨー
鶴の恩返し?!「神話」から神話の外へ -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(62_『神話論理3 食卓作法の起源』-13)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第62回目です。これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
鶴の恩返しの八項関係一年生になったばかりの下の子が、学校で「鶴の恩返し」のお話しを聞いてきたという。
そして次のように尋ねてきた。
ん? わたしに聞くと、ちょっと、話、長くなる
中沢新一著『構造の奥』を読む・・・構造主義と仏教/二元論の超克/二辺を離れる
(本記事は無料で全文立ち読みできます)
中沢新一氏の2024年の新著『構造の奥 レヴィ=ストロース論』を読む。
ところで。
しばらく前からちょうど同じ中沢氏の『精神の考古学』を読んでいる途中であった。
さらにこの2年ほど取り組んでいるレヴィ=ストロース氏の『神話論理』を深層意味論で読むのも途中である。
あれこれ途中でありますが、ぜんぶ同じところに向かって、というか、向かっているわけではなく