
野間宏 『青年の環』と 戦後文学 : 文学がまだ〈文学〉であった時代
書評:埴谷雄高編『『青年の環』論集』(河出書房新社)
過日、年来の課題だった、野間宏の『青年の環』(全5巻)を読むことができ、レビューをアップした。
なにしろ、各巻が500頁前後の分厚さだし、野間宏の文体というのは、粘り気のある執拗なものなので、その読みにくさといったらなかった。特に、最初の方がその最たるものだったから、量的にも内容的にも、かなりの難物だったのである。
で、読んでみてどうだったかというと、正直言って、とうてい理解できたとは言い難い。
別に難しいことが書いてあるわけではないのだが、作者が「何を描きたかったのか」が判然とぜず、とにかく執拗な主観描写と、延々と続く会話が、交互に出てくるような、現代の感覚から言えば、退屈を通り越して、苦痛極まりない、およそ、エンターティンメント性の「エ」の字もないような、「純文学の中の純文学」であったと言えるだろう。
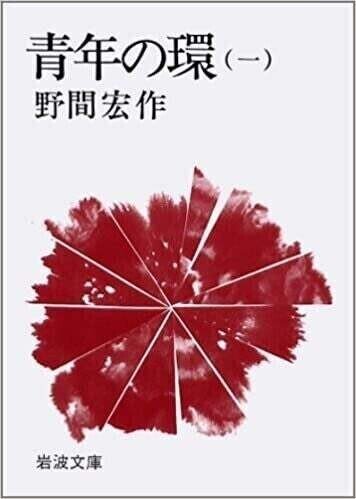
私は、前期レビューの中で、同作を次のように評している。
『私がこの作品に感じた「しんどさ」「合わなさ」は、主にその「鈍重さ」にあったと言えるだろう。
例えば、この二人の主人公だが、どちらも「察しが悪く、独り合点」である。つまり、端的に言って「あまり頭が良くない」のだ。
「本格ミステリ」ファンである私としては、「名犯人と名探偵」「欺く作家と看破する読者」的な、頭の良い者どうしが丁々発止でギリギリのやり取りをするような小説が読みたいのだが、残念ながら本作『青年の環』の二人の主人公は、二人ともそういう「主人公らしい主人公」ではなく、わざわざ物語を停滞させるような独りよがりに嵌まり込みがちだし、繰り返しの多い、くどい議論を執拗に繰り返してくれる。
それで、読まされるこちらは心底うんざりさせられるわけだが、しかし、そこには、今の「エンタメ小説」は無論、「今の純文学」にも存在しないような、「手段を選ばないリアリズムの追求」を見ることができる、のではないだろうか。
たしかに、「察しが悪く、独り合点」な「面倒くさい主人公たち」であり、その意味でおのずと「しんどい」「合わない」小説なのだが、しかし「こういうことって、よくあるよな」とも思うし「人間、だいたいこんなものだよね」とも思う。本作は、そういう「思い当たる節」を仮借なく突きつけてくるからこそ、読者を、少なくとも私を「うんざり」させるのではないだろうか。「そんなのは、現実の方で間に合っているから、小説でまで読みたくはない」と思わせるのではないか。』
そう、私は、この作品をお世辞にも「楽しめた」とは言えないが、しかし、ここに何か「滅多にないもの」があるというのには気づいた。
今の作家が、決して書こうとはしない非効率的な何か、野間宏がその執拗さを持って、20年の歳月のかけてでも追求した何かが、この作品には描かれているのだ。
それが、成功したかどうかは、よくわからないが、とにかく野間が何かを、今どきは、決してお目にかかれないであろう何かを、必死に描こうとしたことだけは感じ取れたのである。
だから、この「何か」を、ぼんやりとよくわからないままにして、『青年の環』を読了したことだけで満足するというのは、いかにも勿体ないことだし、そこで済ませては、どこか落ち着かないとも思った。
そこで、すでに購入してあった、埴谷雄高編の『『青年の環』論集』を読むことにした。少しは何かが得られるだろうと思ったのである。
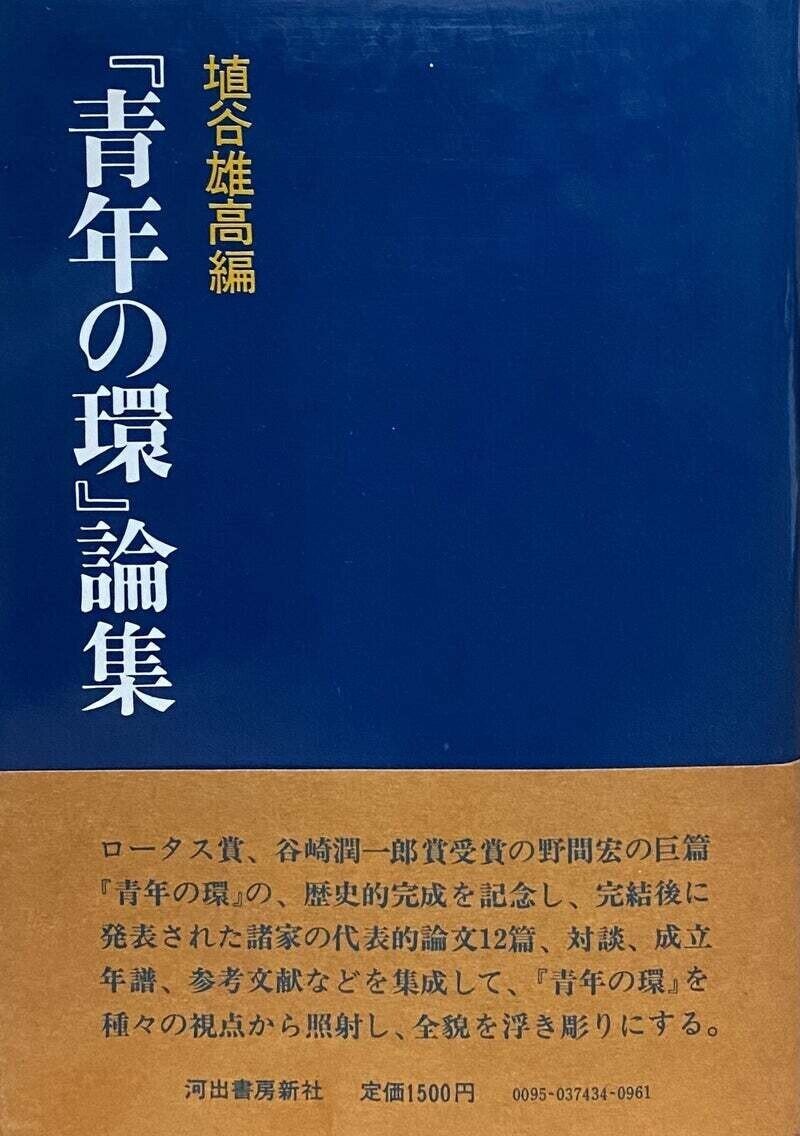
ところが、この本もまた、なかなかの難物であった。
刊行されたの1974年(昭和49年)で、上下二段組340頁余の本であり、そこに、ほとんど改行のない当時の論文が、びっしり収録されているのだから、これも、それなりの覚悟がないと読めない本だ。
ちなみに、半世紀近く前の本なのに、定価が1500円とは、かなりのもので、今なら5000円を下らない本だろう。と言うか、出版不況で、純文学などさっぱり売れない現在なら、こんな本は出せなかったであろう。
この当時は、『青年の環』が20年をかけて完結したというのを、一般の新聞紙が記事にしたような時代であり、全5巻で完結した単行本は、かなり売れたというのだから、良い時代であったのだろう。
買った人の半分ほども読了できたかどうか、かなり疑わしいとは言え、当時の日本人は、「娯楽作品」ではない、「文学作品」に挑む気概は持っていたのである。
○ ○ ○
さて、本論集を読んで教えられたのは、野間宏は本作『青年の環』をもって、日本で初めての「全体小説」を書こうとした、それに挑んだのだ、ということである。
「全体小説」と言っても、何のことだか、多くの人はわからないだろう。今時の文芸評論家にもわからないだろうし、私もわからなかった。
しごく大雑把に言えば、「全体小説」とは、日本のそれまでの純文学の主流だった「人生の一断面を切り出す」ような作品の対極にある、「世界」を丸ごと描こうとするような小説、だと言えるだろう。
もっとも、世界を丸ごと描くなどということは、物理的に不可能なのだから、あくまでも意図として「世界を丸ごと、映し出した作品」ということであり、そこに描かれるのは、それまでの日本の文学にもあった「心理・心境」といったことだけではなく、「肉体」とか「生理」といった身体性の問題、さらに「歴史」や「社会」や「文化」や「思想」といったことまでを広く含み込んだ「総合的な小説」ということになる。
そして、そうしたものは、西欧の大長編小説の傑作、ロジェ・マルタン・デュ・ガール『チボー家の人々』とかトルストイ『アンナ・カレーニナ』といった作品でイメージされ、単に「心理・心境」とは違った小説、「物語性」の強い大きな小説として「ロマン」と呼ばれた。
日本には、そうした「ロマン」が書かれたことがなく、「文学」は小さくまとまる傾向があったのだが、文学が真に「世界」と向き合うためには、日本でも「ロマン」が書かれねばならず、その先に「文学」の未来がある、という風の考えられたようである。
しかし、「ロマン」と言っても、「全体小説」と言っても、定義があるわけではなく、それぞれの作家の「理想」や「目指すところの違い」によって、自ずとそれは、それぞれに「似て非なるもの」にならざるを得ない。
野間宏が『青年の環』で目指したのは、サルトルが『自由への道』で「全体小説」の達成に挑み、ついに挫折したものを乗り越える、「全体小説」であった。


野間宏が、サルトルの「全体小説論」として評価したのは、「神の視点を排除する」ということだった。
娯楽作品なら、それでも良いだろうが、「世界」をありのままに描こうとする場合、「神の視点」を持ち込むのは、どう考えても「ズル」でしかない。なぜなら、この世の中に「神の視点」に立ち得ている人間など一人もおらず、それぞれの視点から、せいぜい客観視しようと努力しているに過ぎないからだ。
だから、野間は、この点ではサルトルの考えを引き継いだ。しかし、サルトルの失敗にも、相応の原因があったと考えた。
それは、サルトルの影響を受けたヌーベルバーグの作家たちの作品がそうであるように、特権的な視点を失った途端に、それはバラバラに並立する視点の寄せ集めとなり、なんとも捉えどころのない世界を描くものとなったしまったのだ。
無論、それはそれで「表現」としては面白いのだが、やはり「この世界」の一部としての「人間のリアル」からは遊離して、作家的な美意識の産物に堕していると、野間には、そう感じられたのではないか。
したがって、ただ「神の視点」を拒否するだけでは、不十分であり、人間は人間の視点において、「他者」を見、「世界」を見て、その関係性の網目の中で「他者」であり「世界」をそれなりに構築しているのだから、文学が「世界」を描くことを目指すのであれば、そうした方法を探らなければならないと考えて、その試行錯誤を『青年の環』において行った、と大筋、このようなことだったのであろう。
野間の次の言葉は、そうしたことを語っているのだと、私は解した。
『 サルトルの「フランソワ・モーリアック氏と自由」のなかには神の目を排し、しりぞけるという提言があるが、作中人物の自由をたもつために、作家は神の目をもって作中人物を自由自在に動かしてはならないということと要約してよいだろう。これは非常に重要なものをふくんでいる言葉であり、作中人物が作品のなかで自分自身の自由を自分自身によって選び、発展をとげるため、その保証として出されている言葉といってよい。
私はこのサルトルの言葉を重要な言葉として受取ったが、私は神の視点を排するというこのサルトルの言葉を自身に受けとるとともに、それに大きな疑問をいだき作中人物を見る目を、作中人物の主人公、その他作中人物の(※ 個々の)目とはせず、作中人物の主人公、その他作中人物の目よりも、一まわり大きい目を見出す必要があると考え、「青年の環」にあっては、それを実行に移したのである。もちろん理論の実行と作品の結晶作業とはまた、まったく別のもので、私は出来るならば、多くの批評がこの作品にたいして、生まれでてくることを、心から期待している。〟
(小説の全体とは何か一一「青年の環」の完成まで・朝日新聞 昭和45年11月26日、29日)』
(本書P291)
こうした、いかにも野間らしい「それかこれか」では済まさないという個性に由来する方法論を、小田実は、野間の魅力を語って、実に的確に指摘している。

『 しかし、より根本的には、私は彼の作品のなかにある、もどかしさにひかれるのだろう。ダラダラとつづく、くねくねと曲がる彼の文体にもよくあらわれていることだが、彼の作品は何かもどかしいのだ。歯切れのわるいところがある。スパッといかないところがある。裏がある、いや、裏のまた裏がある。そうしたものが私をひきつける。いや、ほんとうに、そうしたものが彼の文学の最大の魅力をかたちづくっているのではないか。
そのもどかしさは、野間宏にすべてが判っていないということだろう。すべて見通しでないということだろう。手もとに本がないので正確に引用できないが、彼の文学論のなかにそんなことを書いたくだりがあった。一人のお婆さんがいて、そのお婆さんを書こうと思っても、自分には、どうしても、彼女の歩き方、立ち方が判らない。歩き方、立ち方の背後にあるもろもろがつかめない。いろんな手れん手くだを使ってみるのだが、どうしても判らないところが残る一一あらまし、そんなふうなことを、そのこともまたもどかしげな文体で長々と書いていたのだが、私は、彼のこうしたことばが判らないかぎり、野間宏の作品は判らないのだと思う。手れん手くだのなかにはもちろんマルクシズムも入っているのだが、さて、こうなると、方法は一つしかない。野間宏自身が坂口安吾のことばを引用して述べていたことだが、世界をまるごと、一枚の紙でおおうようにしてとらえるよりほかにはない。といっても、野間宏自身も世界のなかにいるので、それをとりもなおさず、内と外から世界をおおうという奇妙でまったく困難なことになるのだが、野間宏の言う「全体小説」とはまさにそんなふうなものであり、『青年の環』は、そのみごとな一つの例なのだろう。
(昭和43年10月『青年の環』月報Ⅳ)』
(本書P319)
そして、石川淳は、野間宏とは真逆に、無駄を削ぎ落とした言葉で、てきぱきと野間の個性を語る。
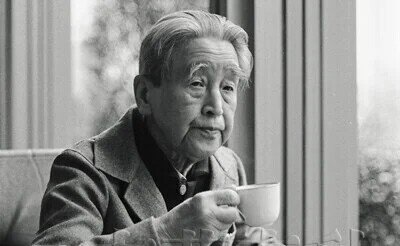
『 たしかに、人間の言動はいつも簡潔にてきぱきはこぶとはかぎらないのだから、また精神が俗に入って運動するために小説という形式があるのだから、ときに冗長と見えるような記述は表現上の必然であって、その長丁場が意外な発明をうながす仕掛でもありうる。野間君の表現力はこの仕掛に乗って、いわば十九世紀風に似た手段を使うと見せながら、よくこれをあたらしい技法に切りかえている。
すなわち、そこに表現されているものはかならずしも市井の雑事とか人間の心理とかではなくて、雑事を通しておのずから人間の生活と時間との関係を語っているにひとしい。あっけらかんと間のびしたような、そのくせ足もとからじりじりせき立てて来るような時間というもの。その時間の外にはずれたところでは、のんびりにしても、あくせくにしても、生きることができない人間というもの。この執念ぶかい関係をあらわすには、タオルのビールのと、これだけ記述に手間をかけなくてはならぬのだろう。』(本書P333)
事ここに至って、私がなぜ野間宏を楽しめなかったのは明らかだろう。要は、私が「小説」に求めていたものとは真逆のものを、野間は手探りで探求していたのである。
自分で言うのもなんだが、私は「娯楽作品ではない文学=純文学」というものの「意義」や、その「面白さ」をそれなりに理解して、最後までしんどい作品にも、それだけの価値を有する作品の在ることを認めている人間なのだが、しかし、私自身が「娯楽の時代」に生まれた人間であるという事実は否定しえず、「耐えて読む」ということが、決して「当たり前」ではない時代状況の中で、頑張って、読んできた人間なのだ。だから、おのずとその「限界もあった」ということなのであろう。
そしてまた何よりも、私個人の個性として、野間宏的な、その粘着質で世界を絡め取るというようなやり方ではなく、石川がいうところの『簡潔にてきぱき』とやるのが「好み」だったのである。
わかりやすく言えば、論理的にスパッスパッと切っていき、分解して説明するような「明晰さ」が好きであり、だからこそ前掲の『青年の環』のレビューで、私は、
『私がこの作品に感じた「しんどさ」「合わなさ」は、主にその「鈍重さ」にあったと言えるだろう。
例えば、この二人の主人公だが、どちらも「察しが悪く、独り合点」である。つまり、端的に言って「あまり頭が良くない」のだ。
「本格ミステリ」ファンである私としては、「名犯人と名探偵」「欺く作家と看破する読者」的な、頭の良い者どうしが丁々発止でギリギリのやり取りをするような小説が読みたいのだが、残念ながら本作『青年の環』の二人の主人公は、二人ともそういう「主人公らしい主人公」ではなく、わざわざ物語を停滞させるような独りよがりに嵌まり込みがちだし、繰り返しの多い、くどい議論を執拗に繰り返してくれる。』
と書いていたのだ。
つまり、私の好みとは、「神のごとき名探偵」的な「明晰で決定的な洞察」が描かれた作品であり、ぬかるんだ塹壕の中を必死で這い回る兵隊のような「執念」ではなかった、ということなのだ。
そして、そうした意味で私自身もまた、安易に「神の視点」という「虚構」に甘やかされていた、「消費社会の毒におかされた人間」の一人だったのである。
小田実が言うように、野間宏が『青年の環』において目指した「全体小説」とは『世界をまるごと、一枚の紙でおおうようにしてとらえるよりほかにはない。といっても、野間宏自身も世界のなかにいるので、それをとりもなおさず、内と外から世界をおおうという奇妙でまったく困難なこと』であり、論理的に言えば、明らかに「不可能な企て」だったと言えるだろう。

だが、それを「冷笑」して見せるしかないのが、現代の「娯楽小説」読者であってみれば、私は、野間宏をはじめとする、高みに手を伸ばそうとしていた「純文学」作家たちの側につきたいと思う。
結果や成果が問題ではないのだ。何を望み、何を目指し、どのようにして書いたのかが、真の問題なのである。
なぜならば、それこそが「書き手の生」であり、それが「私という作品」だからである。
(2022年6月31日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
