
小松和彦 『聖地と日本人』 : 〈怖さ〉を知らない 「楽しい学問」
書評:小松和彦『聖地と日本人』(角川ソフィア文庫)
日本において「聖地」と考えられている「宗教的トポス」と「能楽」に関する教養が身につく一冊ではあるものの、他の方も書いているとおり、個々の文章が短いせいもあり、食い足りない印象は否めない。一一しかし、それだけでもないように思う。
小松和彦を読むのは、実にひさしぶりだ。
最初に読んだのは、1991年に『新編・鬼の玉手箱』で、それから3年後の1994年から数年で『憑霊信仰論』など5冊ほどを読んでいる。
1991年に『新編・鬼の玉手箱』を読んだのは、その3年ほど前に馬場あき子の『鬼の研究』を読んでいるから、その頃すでに、鬼には興味を持っていたのだろう。
1994年以降にまとめて読んだのは、御多分に洩れず、京極夏彦のデビューを受けてのことであった。この時期に刊行された小松の初期著書はほとんど全て購入しているはずだし、第一著作である『憑霊信仰論』の初版である「伝統と現代社」版(1982年)まで、古本屋で手に入れたりしていた。
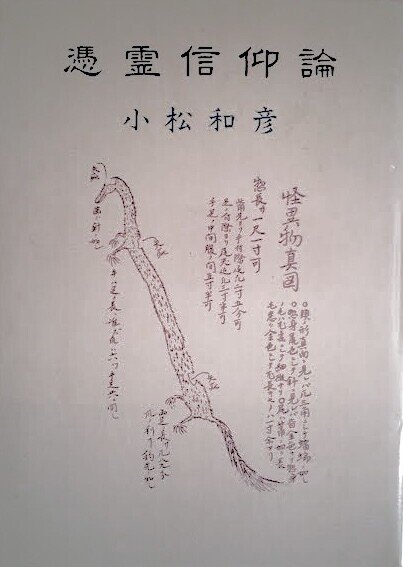
今回、たまたま『聖地と日本人』(旧題『誰も知らない京都聖地案内 京都人が能楽に込めた秘密とは』)を手に取ったのは、「聖地」という言葉に惹かれたからで、これは最近、佐藤弘夫『日本人と神』、岡本亮輔『宗教と日本人 葬式仏教からスピリチュアル文化まで』といった「宗教学」書を読んで、日本における「聖地」というものに、少し興味を持ったからである。

最初に、小松和彦を読んだ頃には、たぶん私は「鬼」や「妖怪」や「幽霊」といったものに、子供の頃と同様の興味を持っており、それでいて「ちょっと学術書めいたものを読んでみよう」くらいの気持ちだったのだろうし、二度目に読んだときは、京極夏彦の影響と「民俗学」というものへの興味があったのだと思う。この頃には、柳田國男や南方熊楠も読んでいる。
そして、今回ひさしぶりに小松を読むまでの間に、私は「宗教」というものを、素人なりにかなり勉強して、筋金入りの「無神論者」になっていた。その上での、小松との再会だったのである。
今なら、小松よりも私の方が、少なくともキリスト教に関しては知識があるはずだ。私は「宗教」を批判的に研究するために、まず手始めとして「キリスト教」を選び、その素人研究が一段落して、今は「日本の宗教」に回帰してきたところだったのである。
で、こうした観点からすると、少なくとも今回読んだ『聖地と日本人』は、まったく物足りない。
小松は、本書のプロローグで、今の日本には「陰影」がない、「異界」に通ずる「奥」行きがなく、しらじらと平板である、といった趣旨のこと語っているが、私はこの言葉に「谷崎の『陰翳礼讃』の焼き直しか」と、思わず鼻で嗤ってしまった。

いや、谷崎の場合は、「日常生活における文化的陰影」の話だから、まあそういう面はあるよねくらいの共感を覚えることはできる。
しかし「宗教」「信仰」といった問題の「現実的重さ(暗さ)」を知った今となっては、そうしたものに関して「陰影が足りない」などと言うのは、いかにも呑気な趣味的学問だ、としか思えなかったのだ。「それでは日本でも、異端審問や魔女狩りの拷問でもやれば、さぞや闇の奥行きも広がることだろう」とか、「オウム真理教事件は、日本の日常に陰影をもたらしたよな」などと、そんな皮肉な実感があったからである。

だから、本書が「物足りない」のは、単に、個々の文章が短いからとか、小松がそれほどの「能楽」ファンではなかったから、といったことではなく、そもそも、小松の「宗教」や「信仰」への向き合い方が、「オタク」的なものだったからなのではないかと疑うのだ。
もちろん、小松は、学者であって、単なる「オタク」ではないのだけれども、その根っこにあるのが、どうにも無邪気な「好き」に止まっている気味があって、「宗教/信仰」問題の「闇」や「奥」と向き合ってきた者の端くれとしては、なんとも「軽い」し「薄味」なのだ。むしろ、「明るく健康的に過ぎる」のである。
小松とて「オウム真理教事件」を通過してきたはずなのに、それが小松に影を落とした形跡が感じられない。そもそも、この人なら「あれはちょっと、別ジャンル」だと済ませてしまいそうな印象すらある。またそれくらい、以前に読んだ小松の本は、勉強にはなったけれども、印象は薄いのである。
小松の読者の大半は『怪』とか『幽』とかを読んでいた、妖怪マニアたちなのではないか。と言うのも、そもそも民俗学マニアというのは、ごく少ないし、コアな民俗学マニアは、ことさらに「妖怪」や「幽霊」にこだわらないだろうと、容易に推察できるからだ。
無論、妖怪マニアが悪いというのではない。オタクがいけないというのではないが、そうした人たちの「闇」や「奥」との向き合い方に、私は「危うさ」を感じないではいられない。オウム真理教信者がそうであったように、自身が「リアルとフィクション」の区別を容易につけられると思っているだろう部分にこそ、「宗教/信仰」がらみの問題を扱う際の、不用意さを感じるのだ。

数年前、ひさしぶりに京極夏彦の新刊『虚実妖怪百物語』を読んだのだが、同作中で京極が「幽霊」だの「呪い」だのを本気で信じている人たちに対し、苦々しい思いを持っているらしいことを知って、共感した。
この作品は「小説家業界実名フィクション」だから、作中の京極夏彦の考えが、そのまま作者・京極夏彦の考えだとは決めつけられないだろうが、おおよそ同じようなものであろうことは、容易に看取できる。

つまり、そこでの京極夏彦の苦々しさとは、たぶん「フィクションを楽しんでいたはずの人が、フィクションに憑かれた」醜態への苦々しさなのではないか。それは、京極夏彦が長編エッセイ『地獄の楽しみ方』で、スポーツを楽しんでいたはずの人たちが、いつの間にか「オリンピック」だの「金メダル」だのという妖怪に憑かれているのを揶揄していたのと、同じようなことではないのか。

人々は、あまりにも「憑き物」に対して不用意であり、それは小松和彦の「学問」にすら感じられるのである。
初出:2021年5月13日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
再録:2021年5月23日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
○ ○ ○
○ ○ ○
