
1984年以前レベルの、北村紗衣のフェミニズム : 『ベル・フックスの「フェミニズム理論」 周辺から中心へ』
書評:ベル・フックス『ベル・フックスの「フェミニズム理論」 周辺から中心へ』(あけび書房)
本書は、1984年の初刊以来、今も販を重ねて読まれ続けている、「フェミニズム」理論の基本書である。
私が、本書の存在を知ったのは、「アナーカ・フェミニスト」を名乗る高島鈴のエッセイ集『布団の中から蜂起せよ アナーカ・フェミニズムのための断章』(「紀伊國屋じんぶん大賞2023」第1位)の中の「フェミニズム関連推薦図書」で本書が紹介されており、その推薦文が、次のとおりだったからである。
『 フックスは八〇年代、従来の白人中心主義フェミニズムを批判する形で、論壇に登場したブラック・フェミニスト。本書は、同質性や被害者性で馴れ合うフェミニズムを痛烈に批判し、問題意識によってのみつながるシスターフッドを提唱したフックスの代表作だ。』(P84)
私は、これまで「ブラック・フェミニスト」の書いた本を読んだことがなかったし、『同質性や被害者性で馴れ合うフェミニズムを痛烈に批判』という点にはまったく同感で、そんなフックスの「代表作」だというのだから、これは読まねばなるまいと思ったのだ。
なお、本書『ベル・フックスの「フェミニズム理論」 周辺から中心へ』の「訳者まえがき」で、本書共訳者の野﨑佐和は、本書を次のように紹介している。
『 本書は2015年に出版された『フェミニズム理論 周辺から中心へ』3版を翻訳したものです。初版は1984年ですから、上梓されてから33年ということになります。
著名なフェミニストというだけではなく、教師であり、アメリカ代表する思想家であり、文明批評家としての多彩な顔を持つベル・フックスの30冊を超える著作の中でも、本書は彼女の代表作とされています。』(P1)
つまり、本書は、従来「白人女性中心」で発展してきた「フェミニズム」の抱える問題を、「アメリカ黒人女性」の視点から批判した本であり、今や古典となって「フェミニズムの教科書」的に読まれている本だということである。
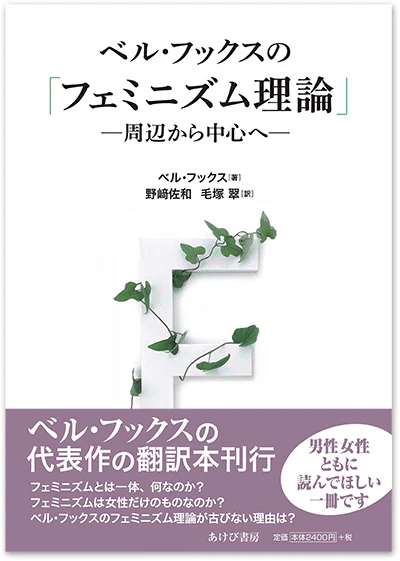
無論、フックスの立場が、「フェミニズム」のすべてを代表するわけではない。当然のことだが、フックスに批判された「白人女性中心主義」的なフェミニズムの立場に立つフェミニストは、フックスの見方に必ずしも肯定的ではないだろう。
では、フックスの立場がどういうものなのかというと、簡単に言えば、それまでの「白人中心主義的フェミニズム」というのは、当然のことながら、黒人を含む「有色人種」の視点が欠いたものであり、決して「女性」全体を代表するものでもなければ、「女性」全体の利益を考えたものでもなかった、ということである。
言い換えれば、上流または中流の、比較的恵まれた環境にある「白人女性」の、さらなる解放を意図したものではあっても、「有色人」女性や、低所得者階級の女性のことなど、考えてはいなかった。
また、それにもかかわらず、まるで全「女性」の利害を代表しているように思い込んで、結局のところは、自分たちの「人種的・階級的に限定された、女性の党派利益」しか求めていなかったのだ。
いくら、有色人女性や低所得者層女性の「フェミニズム」運動への参加を呼びかけたところで、それは結局のところ、自分たちの利益を実現するための「私兵集め」に過ぎなかった、という批判である。
そして、初期フェミニズムのそうした性格は、「フェミニズム」運動の発端が、女性が家父長制的男性支配の下において、家庭に縛りつけられていたことへの反発から始まった、という点に明らかだろう。
男は外に働きに出て、社会の中でそれぞれに責任を担って生きているが、その男性に食わせてもらっている女性は、家庭を守るのが仕事だ、という考え方に対する反発から、フェミニズムは「女性解放運動」として始まった。つまり、何からの「解放」かと言えば、「家庭」からの解放であり、「男性支配」からの解放だ。
「女性だって、外に働きに出て自立したいし、自立できるのだ。家庭に束縛されることなく、男性と同じように、社会の中で自己実現できるし、それを求めるのは、同じ人間として当然のことである」というようなことだ。
そして、そうした時代の意識を象徴するのが、イプセンの戯曲『人形の家』の主人公ノラである。彼女は、
『夫にとってかわいい人形にすぎない妻の地位を捨て、夫や子供とも別れて家出する。近代的自我に目覚めて自立を望む新しい女性の典型とされる。』
(goo辞書「ノラ」)
ということになる。
しかしだ、これは、フックスのような黒人女性の視点からすれば、「いい気なもんだ」ということにしかならない。
というのも、『夫にとってかわいい人形にすぎない妻の地位』とは、要するにノラは、「人形」のようなお飾りであればそれで十分なほど「恵まれた経済環境」にあった、ということだからである。
私は、『人形の家』を読んでいないので詳しいことは知らないが、しかし、ここで言えるのは、ノラは「家庭の中でさえ、家事にあくせくと働く必要のなかった=人形でいられた」身分だった、ということである。
では、ノラの家庭では、誰が「家事」をしていたのだろうか? 一一それは無論、下女だの召使いだの(あるいは、奴隷)といった人たちであろう。そういう人たちがいたから、ノラはそれを監督しているだけで済む「女主人」として、暇を持て余すこともでき、その退屈さに不満を覚えることもできたのだ。
しかし、ノラのそうした「人形の生活」を支えた「下女だの召使いだのといった人たち」は決して、ノラのように好きで「家を出たかった」わけではない。
彼(女)たちは、できれば、夫や妻や子のいる家庭で過ごす時間が欲しかったのだが、その貧しさゆえに、下女だの召使いだのといったその「身分」において、否応なく、家を出て稼がなければならなかったのだ。
つまり、初期の「フェミニズム」である「女性解放運動」というのは、基本的に「裕福な(中流以上の)白人女性中心」であり、大半の「貧しい有色人女性」はもとより、「貧しい白人女性」のことすら、視野に入ってはいなかった。
彼女ら、教育もあれば社会的な地位もある「白人女性フェミニスト」たちは、自分たちが「家庭におけるお飾りの人形」でしかなかったことに反発して、そこからの「解放」を求めて始めたのが、「女性解放運動」であり「フェミニズム」なのだから、こうしたフェミニストたちに「貧しい人たち」への理解が欠けており、おのずとその目指すところも、ごく限定された白人女性のためのものでしかなかったというのは、もはや明らかなのだ。
(D・W・グリフィス監督『イントレランス』に描かれた、矯風会の女性運動家たちの意識も参考になるかもしれない)
フックスがそのことに気づき得たのは、彼女が「黒人女性」であり、それまでのフェミニズムの「問題設定」が、あまりにも自分たち黒人の現実からかけ離れたものであることに気づいたからである。
だから、そんなものは「女性解放運動」ではなく「中・上流白人女性解放運動」でしかなく、黒人女性が協力する価値のあるものではないと、そう批判したのだ。
そして「フェミニズム」が真に「女性解放運動」たらんとするのであれば、単に「恵まれた白人女性」のための「白人中心社会の中での女性解放」ではなく、そこに「人種」や「社会階級(階層)」の問題が同等に並置され統合されたものでなければならないと、そう主張した。
言い換えれば「女性は、男性中心主義から解放されなければならない」だけではなく、「人種差別主義」や「階級差別」からも解放されなければならない。それらの解放なくして「女性解放」はあり得ない。
なぜなら、それらは資本主義社会において、密接に「連動」したものだからだと、そう主張したのである。
つまり、ここで重要なことは、従来のフェミニズムが「女性の男性からの解放」のみを強調し、「男性中心社会さえ打倒すれば、女性による優しい理想社会が実現できる」という単細胞な「男は敵だ」理論を唱えがちだったのに対し、フックスは「そんな簡単な話ではない」と主張したのだ。
単に「男を敵視して」事足りるなどと考えるのは、「人種差別」や「階級差別」の現実を無視し、恵まれた白人たちの間での「男女間紛争」しか問題にしていないからであり、それが「経済的に恵まれた白人女性」たちにとっての問題でしかなかったからにすぎない。
彼女たちは、その恵まれた階級の中で、男性同様の、あるいは男性以上の「社会的地位」を得られればそれでよく、「有色人女性」や「低所得者階級女性」のことなど、どうでも良かった。少なくとも「後回しにして良い」と考えて、単純に「男は敵」だと言って、男性を攻撃することで、自分たちの権益を拡張しようとしていただけなのである。
だから、「フェミニズム」が「すべての女性の、男性中心社会からの解放」を訴えるのであれば、当然のことながら「人種差別」や「階級差別」の問題を一体的に考えなければならない。
「恵まれた白人女性ファミニスト」たちは、これまでの、自分たちの「視野の狭さ」とその「自己中心主義」を反省しなければならない。自分たち「恵まれた白人女性」の権益確保ばかりを考えて、貧しい人たちのことを視野から除外し、差別してきたことを反省しなければならない、ということになる。
そして、これは「アメリカ黒人の公民権運動」以後の世界の「常識」であるからこそ、現在のフェミニズムにおいては、「性差別(男女差別)」だけではなく、「人種差別」や「階級差別」をも合わせて考えなければならないというのが、もはや常識となっており、これを「フェミニズム」用語で「交差性(インターセクショナリティ)」と呼ぶようになった。
「性別」と「人種」や「社会階級」が複雑に交差するところで、「女性の解放」ということを考えなければならない、ということになったのである。

無論、ここで言う「交差性」とは、「性差別(男女差別)」「人種差別」「階級差別」の3つだけ、を考えれば良いということではない。
「差別」には、さまざまなものがあって、わかりやすいものとしては「宗教差別」という重大な問題があるし、世界の各地で、その地域固有の差別が多数存在する。
例えば、「聖書」の時代には「サマリア人差別」があった。だからこそ、聖書には「善きサマリア人の喩え」などというものもある。「蔑視されているサマリア人でさえこうするのに、あなた方は恥ずかしくないのか」というイエスの訓話だ。
もちろん現在でも、インドにはまだ「不可触民」差別が生きているし、トルコやシリアなどでは「クルド人差別」などがあって、それはすでに、我が国にまで波及している。
また、そんな「外国の話」ばかりではなく、我が日本においても、「部落差別」問題や「在日朝鮮人差別」問題、あるいは「沖縄米軍基地問題」(米軍基地の沖縄への押しつけ問題)といったものがある。
つまり、当然のことながら、「部落(同和地区)」と呼ばれた地域にも「女性」は住んでいるし差別も受けている。「在日朝鮮人女性」もいれば「沖縄の女性」もいて、そうした女性たちへの社会的な差別や抑圧に対し、「女性解放運動」たる「フェミニズム」が関わるのは、当然のことなのだ。
アメリカのフェミニズムでは、「性差別」の他に、主に「人種差別」や「階級差別」が問題とされるが、だからといって、世界のどこでも、そのパターンを真似していれば良いというものではない。その3つだけで済まないのは、当然のことなのである。
ところが、現実にはそうではない。
現在メディア上で活躍中の「日本のフェミニスト」の多くは、「部落差別」問題や「在日朝鮮人差別」問題、あるいは「沖縄米軍基地問題」には、積極的に関わろうとはしないばかりか、言及しようともしない。
彼(女)らは、もっぱら「性差別」だけを問題とし、せいぜい「男女」に限らない「多様な性」としての「セクシャリティ」の問題を語るばかりなのだ。
かつて、上野千鶴子は「従軍慰安婦」問題について積極的に語ったけれど、今どきの「大学フェミニスト」たちは、そうした「具体的な案件」、「日本人として責任を共有すべき差別問題」についてはむしろ敬遠して、まるで「フェミニズムの本場」であるアメリカやフランスの真似をして「国際派」を気取るかのように、「人種」の問題(例えば「黒人」だとか「ブラック・ライブズ・マター」)に触れるのがせいぜい。「経済格差」が問題になってすでにひさしい我が国の、具体的な「社会階級(貧富格差)」問題などには、触れようとしない。一一それはなぜか?
無論それは、現在活躍中の大学フェミニストの多くが「恵まれた白人女性フェミニスト」の末裔だからに他ならない。
エリート階級に属する自分たちの権益確保を目的として「フェミニズム」を語っているだけだから、話題を「男女差別」だけに限定し、他の多くの「差別」については、意図的に無視しているのだ。
そして、そうした「えせフェミニスト」の代表と言えるのが、「武蔵大学の教授」であり、自称フェミニストの北村紗衣であり、彼女の盟友である東京大学の教授・清水晶子(あるいは、「呉座勇一に対するオープンレター」署名者たち)などであろう。
彼女らの語る「フェミニズム」は、極めて限定的なものであり、たまに「黒人」に言及することはあっても、それ以外は、もっぱら「性差別」問題に終始するのは、彼女らがもともと恵まれた「リーン・イン・フェミニスト」だからに他ならないのだ。
私はこれまで、北村紗衣を批判するのに、「すべての差別に反対するはずのフェミニストが、どうして「部落差別」問題や「在日朝鮮人差別」問題、あるいは「沖縄米軍基地問題」については、一言半句、触れようともしないのか。それは結局のところ、自分たち女性の党派利益しか考えておらず、それ以外の人たちが差別されることなど、気にしていないからではないのか? しかし、だとすればそれは、そうした差別を追認していることになるのだが、そうではないという申し開きができるのか?」と問うてきたが、この問いに対する回答は、北村紗衣や清水晶子はもとより、その周辺からも、まったく返ってはこなかった。彼女らの「勝手ツンボ」は、有名な話である。
私が、彼女ら「日本の女性フェミニスト」たちに対し、このような説明を求めるのも、それは私がまだ、フェミニズムについてはまったくの無知だったから、私が想像できないような根拠が、「性差別問題優先主義」者たちの側にあるのかもしれないと、そう考えたからだ。
「他の差別」はすべて後回しにしてでも「性差別(男女差別)」だけを強調し、「男が悪い」と主張して「男性中心主義社会」を攻撃することが「喫緊の課題」であると主張する、何らかの理由や理論があるのかもしれない。あるのなら、それを聞かせてもらい、それで納得できるのであれば、喜んで「彼女たちのフェミニズム」に賛同し、協力もしようと、そう考えたのだ。
一一無論、そんな「理由」など、簡単に提出できはしないだろうという予測はあったにしろだ。
だが、結局のところ、彼女らからの「回答」は無かった。なぜ「性差別問題優先主義」なのかの理由説明は、得られなかったのである。
そんな、当事者説明の得られなかった、「性差別問題優先主義」というものを考える上で、説得力のある説明を与えてくれたのが、すでに紹介した、シンジア・アルッザ、ティティ・バタチャーリャ、ナンシー・フレイザーの共著『99%のためのフェミニズム宣言』であった。
彼女たちは、この著書の中で、「資本主義の侍女」でしかない「リベラル・フェミニスト」や「ラディカル・フェミニスト」といった、「リーン・イン・フェミニスト」の存在を、次のように紹介していた。
『 二〇一八年春、フェイスブック社の最高執行責任者(COO)であるシェリル・サンドバーグは世界に向けてこう発言した。「すべての国と企業のうち半数が女性によって運営され、すべての家庭のうち半数が男性によって切り盛りされれば、状況はずっとよくなるでしょう」。そして「その目標を達成するまで、私たちは決して満足してはいけないのです」。企業フェミニズムの主唱者として、サンドバーグはそのときすでに女性経営者らが役員会の「内側に入りこむ(リーン・イン)」よう促すことで名声(かつ財力)を得ていた。アメリカの財務長官ラリー・サマーズ一一ウォール街の規制を緩和した男性一一の元首席補佐官であった彼女は、ビジネス界の荒波をくぐり抜けて勝ち取る成功こそがジェンダーの平等へとつづく王道なのだ、とすこしの懸念もなく力説した。
同じ年の春、闘争的なフェミニスト・ストライキがスペインを機能不全に追いこんだ。五〇〇万人を超える参加者に支えられ、二四時間にわたるストライキを組織したウエルガ・フェッニスタ(フェミニスト・ストライキ)の主導者たちが呼びかけたのは、「性差別的抑圧、搾取、暴力から解放された社会の実現」であり、「私たちに従順であること、服従すること、沈黙することを要求する家父長制と資本主義の協力体制に抵抗し、闘いを挑む」ことだった。マドリードとバルセロナの上に太陽が沈んだとき、フェミニスト・ストライキの参加者たちは世界にこう表明したのである一一「この三月八日、我々は断固として、すべての生産活動、また再生産活動を停止させる」。そして今後、「同じ労働に従事する男性よりも劣る労働条件や賃金を決して認めない」と。
これら二つの声は、フェミニストの運動においてまったく逆の方向を示している。他方、サンドバーグや彼女と同階級に属する人々は、フェミニズムを資本主義の侍女であるとみなして(※ それを肯定して)いる。彼(女)らが望むのは、職場での搾取と社会全体における抑圧を司る仕事が、支配階級の男女によって等しく分担される世界である。これは支配の機会均等という特筆すべき展望であり、つまりは普通の人々に対し、フェミニズムの名の下にこう求めるのだ一一あなたがたの労働組合を破壊し、あなたがたの親を殺すようドローンに命じ、あなたがたの子どもたちを国境沿いの檻のなかに閉じこめるのが、男性ではなく女性であることをありがたく思いなさい(※ それをするのが女性であるならば、それは悪ではないのだ)。こうしたサンドバーグのリベラル・フェミニズムとはまったく対照的に、ウエルガ・フェミニスタの主導者たちは「資本主義に終焉をもたらす」ことを主張している。つまり、上司(ボス)というものを生み出し、国境を設け、それらを警備するためにドローンを生産する(※ 資本主義)システムの終焉である。
フェミニズムのこの二つのヴィジョンを前にして、私たちは一つの分岐点に立っていることがわかる。そして、私たちの選択は人類全体に誰も予想のできなかったような結果をもたらすことになる。一方の道は、人間の暮らしが存続可能なのかわからないほど悲惨なものになってしまう焼け焦げた地球へとつづいている。もう一方の道は、人間が見うるかぎりもっとも崇高な夢のなかで語られてきたような世界へと向かっていく。すなわち、富と天然資源がすべての人によって共有された世界、平等と自由がもはや渇望の対象ではなく、前提となった公正な世界へと。』
(P9〜12、傍点はゴシックに変えた。※ は、引用者註または補足説明)
つまり、「性差別」しか問題にしたがらず、「それ以外」については語ろうとはしない「フェミニスト」というのは、結局のところ、フェミニズムを利用して自らが「上位1%」の仲間入りをしようとしている、あるいは、仲間入りした「リーン・イン・フェミニスト」に他ならない、ということなのだ。
自身の「立身出世」のために、大学でお勉強したフェミニズムの「知識」を利用しているだけの人たちであり、だからこそ、「貧乏人」には興味がないし、「部落差別」問題や「在日朝鮮人差別」問題、あるいは「沖縄米軍基地問題」といった、「資本主義体制における犠牲者」たちにも興味がない。
一一と言うか、そのような「犠牲者」がいてくれないことには、彼女たちは、この「資本主義社会における上位1%」になることも不可能なのである。みんなが「平等」であっては困るのだ。
したがって、彼女たちが「男性を敵視」するのは、今の社会では、その「1パーセント」を男性が占めているからで、要は、その半分(以上)の席をこちらに寄越せ、そうでないと「差別」だろう、という話でしかないのだ。
そもそも、「差別された人々」や「虐げられた人々」になど興味がないから、もっぱら「大学教授に女性の占める割合」だとか「会社役員に女性が占める割合」などといった、「恵まれた上位階層」の中での問題しか、話題にしないのである。
彼女らは、自分自身が「恵まれた階級」の人間だとは決して口にしないし、そう指摘されたくもないのである。
そんなわけで、「日本の大学フェミニスト(エリート・フェミニスト)」たちは、どうして「性差別」の問題しか口にしないのかという理由は、これで明らかにできたし、私の問いに答えない理由も分かった。
彼女たちは「今の社会を変えたくない」のである。
今の「階級社会」を温存したままで、自分だけは上流階級にリーン・インしたいだけなのだ。だから、貧乏人などどうでもいい。ただ、自分個人が「女性」として、「男性」と同等扱いにされないのが、不満なだけなのである。
したがって、くり返すが、具体的な差別問題を敬遠する「日本の大学フェミニスト(エリート・フェミニスト)」たちは、かつての「恵まれた白人女性フェミニスト」の末裔であり、その「日本人版」にすぎない。
彼女たちのフェミニズムは、「黒人女性」からの批判によって修正深化された後のフェミニズムではなく、むしろ、日本という、アメリカほどには「人種」が問題にならない国において、特殊に「先祖返りし退化したフェミニズム」なのだ。
自分たち「恵まれた女性」のことしか考えない、「えせフェミニズム」なのである。
○ ○ ○
そんなわけで本書『ベル・フックスの「フェミニズム理論」 周辺から中心へ』を読むと、詳しくはないなりに私が北村紗衣らに対して呈していた疑問の数々は、私のフェミニズムについての無知ゆえの的外れな疑問だったのではなく、むしろ、まともなフェミニズムと同じ立場に立っての、当然の疑問・疑義だったということが、ハッキリした。
本書を読んでみると、私がこれまで「北村紗衣批判」として発してきた批判とそっくりな言葉が、次から次へと出てきて、私の正しさが、あるいは、北村紗衣のフェミニズムのデタラメさが、明白になったのである。
だからここからは、そうした「私の主張」とそっくりそのままのベル・フックスの言葉(と彼女が引用した言葉)を、本書からいくつか引用紹介し、私がそれに短く解説を加えるというかたちにしたい。
本書に書かれているのは、具体的にはこのようなものだと、ここからはその実例をもってご紹介しよう。
(1)『 人種と階級のアイデンティティが、女性が分かち合っているとされている共通の体験をしのぐほどの、生活や社会的な地位やライフスタイルの質における差をつくりだしているという現実を実証する証拠はたくさんある。そして、そうした差異は、めったに乗り越えられることはない。物質的に恵まれ、高等教育を受け、さまざまなキャリアやライフスタイルを選択することができる(※ 恵まれた)白人女性が「苦悩というものは測ることはできない(※ したがって、他の人のそれと比較考量することはできない)」と(※ 他のそれと比較して、自らの苦悩の重みを殊更に)主張(※ し、擁護しようと)するとき、その動機は疑われなければならない。
間違いなくフリッツ(※ レア・フリッツ)は、このような(※ 手前味噌で自己正当化的な)発言をした最初の白人フェミニストである。わたしはこれまでこのような発言が、いかなる人種であろうと、貧しい女性によってなされたのを耳にしたことはない(※ 貧しい人は、金持ちと貧乏人の苦悩は、比較できないから同等だなどとは、決して言わない)。ベンジャミン・バーバーが著した女性運動に対する評論「フェミニズムの解放」(1975年)には異議を唱えるべきところもたくさんある。しかし、次のような彼の主張には同意できる。
〈苦悩とは必ずしも、ひとつのものさしで測ることができるような固定した普遍的な体験ではない。なぜなら、それにはその人間の状況やニーズや切望が関係しているからである。しかし、この言葉を用いる際には、社会における優先順位が決定されるための、また苦悩のさまざまな形態や程度がもっとも注目されるための、いくつかの歴史的かつ社会的パラメーター、すなわちその物ごとの本質がよく分かるように数値に置き換えられた母数のような客観的な判断基準がなければならない。(※ そうでないと、相対主義の誤魔化しに終わってしまうおそれが少なくない)〉
「共通の抑圧」という概念
現代フェミニズム思想の中心となる教義はこれまでずっと、「すべての女性は(※ 同じように)抑圧されている」という主張だった。それは今でもそうである。こうした主張は、女性は共通の運命を(※ 同じように)分かち合っているということを意味している。また、一人ひとりの女性の生活において、性差別主義が及ぼす抑圧的な力の程度を決定する体験の多様性は階級、人種、宗教、そして性的指向などといった要素によって生じるわけではない(※ それらは、本質的なものではない)ということも意味している(※ そう暗に示唆している)。
(※ しかし)支配システムとしての性差別主義は制度化されているが、この社会のすべての女性の運命を絶対的に(※ 単独で)決定づけてきたわけではない。』
(P23。本文中、一段落としで表現された「引用文」部分は、ここでは〈〉で括った。※は、年間読書人による補足)
見てのとおりである。「差別」というのは「性差別=男女差別」だけではないし、「女性への抑圧」というものも、その原因は「性差別主義」からだけ生まれるものではないという、しごく常識的な考え方だ。
(2)『スーキー・スタンプラーは著書『ウーマンリブ 将来の青写真』(1970年)の導入部分で、(※ 男性を批判することで、一気に世界が変えられるとする)そうした急進的な精神をこう表現している。
〈(※ フェミニズムの)女性運動家は、有名人やスーパースターをつくりあげようとするマスメディアのために、いつもわき道に脱線させられてきた。これはわたしたち(※ フェミニスト)の基本理念に反することである。私たちは、名誉や名声を鼻にかけるような女性たちと関係を結ぶことなどできない。わたしたちは、特定の女性の利益や特定の女性集団のために闘っているわけではない。わたしたちは、すべての女性にかかわる問題に取り組んでいるのである。〉
ブルジョワ的イデオロギー
運動の初期、こうした意見は多くのフェミニストによって支持されていた。しかし、それは長続きしなかった。フェミニズムの文章を書いたり、あるいは労働における平等を要求するフェミニズム運動によって利益を得たりして、名誉や名声や金を手に入れる女性が多くなるにつれて、自分勝手な日和見主義が横行し、集団闘争の訴えの土台は(※ こうした、堕落したフェミニストによって掘り)崩されていった。そして、社会、資本主義、階級差別、そして人種差別に反対する気もない女性たちが、自らを「フェミニスト」と称した。
そうした女性たちの期待はさまざまだった。特権階級の女性は自分たちと同じ階級の男性との社会的平等を望んだ。同じ労働に対して同じだけの賃金を要求する女性もいれば、今とはまったく違った(※ より恵まれた)ライフスタイルを望む者もいた。そして、これらの特権階級の女性にとって正当な要求の多くは、社会を支配する資本主義的な家父長制によって簡単に取り込まれて(※ 彼女らは懐柔されて)しまった。フランスのフェミニスト、アントワネット・フーケは著書『警告』(1980年)のなかで、こう述べている。
〈フェミニスト集団の提案する行動は、著しく挑発的である。しかし、挑発(※ だけ)であぶりだされるのは社会の矛盾の一部分でしかない。挑発では社会のなかの根本的な矛盾を暴くことはできない。フェミニストは、自分たちは(※ 単に)男性との平等を求めているわけではない(※ もっと本質的な変革を求めているのだ)と主張している。しかし、彼女たちの行動は明らかに矛盾している。(※ 実際のところ)フェミニストとは、男女(※ の性別)を逆転させただけの支配的な価値観を持つブルジョワ階級のアバンギャルド、すなわち時代の先頭に立つ革新的な人びと(※ 過激派なの)である。
(※ しかしながら、)価値観を逆転させただけでは何ものも生まれない。改革は(※ 一部のアバンギャルドのためのものではなく)すべての人びとのためでなければならない! (※ そうでなければ)ブルジョワ的な秩序、資本主義、男性中心主義は、必然的に多くのフェミニストを取り込んでしまうことになる。そんな(※ 前衛的な)女性たちが「男性」になるということは結局、男性の数が少し増えるという意味でしかない。性が違うということは、その人間がペニスを持っているかどうかなのではなく、その人間が男根崇拝的(※ 権威主義的)な男社会の経済に取り込まれているかどうかで決まるのである。〉
アメリカ合衆国のフェミニストたちも、こうした矛盾には気づいていた。キャロル・エールリヒは、評論「マルクス主義とフェミニズムの不幸な結婚救うことはできるのか?」(1981年)のなかで、こう指摘している。「ブルジョワ・フェミニズムへ向かうことでフェミニズムの急進的な本質が力を失っていく」につれて「フェミニズムはますます、行き当たりばったりで、安全で、革命とはほど遠い様相を呈してきたように思われる」と。そして、「わたしたちはこんなことをいつまでも続けさせるわけにはいかない」と強調している。
〈フェミニズムは、成功の衣を身にまとうことでも、会社の重役になることでも、選挙によって選ばれることでもない。そのことを女性たちは知っておかなければならない。そして、そのことを見極めることは、ますます難しくなってきている。フェミニズムは、夫婦でキャリアを追いかけることでも、スキー休暇をとって夫や可愛い子ども2人とたくさんの時間を過ごすことでもない。
なぜなら、自分にはそんなことをする時間も金もない家政婦が必要なすべてのことを(※ 奥様の)代わりに引き受けている(※ ために出来ることな)のだから(※ そのことに差別を感じないような人間は、フェミニストを名乗る資格はない)。フェミニズムは、女性のための銀行を開くことでも、どうしたら積極的に(攻撃的に、ではなく)なれるのかを伝授してくれる金のかかる(※ ばかりの贅沢な)ワークショップに参加して週末(※ の暇)を(※ 潰して)過ごすことでもない。そして何より、刑事やCIAの諜報員や海軍の将校にな(※ って、社会を支配する側の人間にな)ることでは絶対にない。
しかし、こうした(※ 資本主義な男性中心主義によって)歪められたフェミニズムのイメージが、わたしたちが思っているより現実(※ のフェミニズム)に近いとしたら、わたしたち(※ そうしたものに反対するフェミニスト)にその責任がまったくないとは言えない。(※ だから)わたしたち(※ 平等な社会を目指すフェミニスト)は、人びとの生活にそくした明確で有意義な、そして新しい分析を提供するように、そして有益かつアクセスしやすい組織として機能している集団、たとえば、集会、NPO、会社などを用意するように、もっともっと努力してくるべきだった。〉』
(P26〜28。ゴシック強調は年間読書人)
これは、アメリカの話であって、日本のフェミニストで「テニュア(終身雇用保証)の大学教授」である、北村紗衣のことを指して、言っているわけではないのだ。
(3)『 大抵の場合、特権階級のフェミニストたちは、女性のさまざまな集団に訴えかけることも、一緒に話し合うことも、そしてその声を代弁することもできなかった。今でも代弁することができないままである。なぜなら、彼女たちは性、人種、そして階級における抑圧の相互関係を十分に理解していないだけでなく、そうした相互関係を真剣に受けとめようともしていないからである。
女性の運命に関するフェミニストたちの分析はもっぱら、ジェンダーに焦点が絞られる傾向があり、フェミニズム理論をつくりあげるための堅固な土台を築くことができないでいる。そうした分析は、女性の現実をごまかすためにジェンダーだけが唯一の女性の運命を左右する決定要素であると主張する西欧の家父長主義的な精神の支配的な傾向を反映している。
たしかに、人種、あるいは階級における抑圧を経験していない女性たちにとっては、これまでも、そして今でもジェンダーにだけ焦点を絞るほうがより簡単だったのだろう。』
(P36〜37。ゴシック強調は年間読書人による)
つまり、あまり教育のない女性たちを扇動するには、「性差別」問題つまり「ジェンダー」問題一本に話を絞った方が、「わかりやすい」とウケが良くて、得策だということである。
本当は、あれこれ考えなくてはならないことがあるのだけれど、ひとまず、大衆を扇動するにためは、小難しいことを言ってダメ。
また、大衆を変に啓蒙して問題意識など持たれたりしたら、自分たちのフェミニズムが、所詮は「リーン・イン・フェミニズム」でしかないことに勘づかれてしまうので、なるべく頭を使わせないで、ただ煽てておけばそれで良い。猿もおだてりゃ木に登るのだからと、えせフェミニストたちは、そのように考えている、ということだ。
(4)『 アメリカ合衆国のほとんどの人々は、フェミニズムを、もっと一般的な言い方をすれば「ウーマンリブ」を、女性が男性と社会的に平等になることを目的とした運動だと考えている。マスコミや運動の主流派(※ リベラル・フェミニズム)によって、一般に広められたこうした大まかな定義によって、問題をはらんだ疑問が生じている。
白人至上主義的で、資本主義的で、そして家父長主養的な階級構造において、男性たち(※ の中にあって)も平等ではないとしたら、女性はどんな男性と平等になりたいと思っているのだろうか? 女性は平等とは何なのかということについてのビジョンを共有しているのだろうか? また、女性解放をこのように(※ 女性が男性と社会的に平等になることだと)単純に定義してしまえば、個人が差別、搾取、そして抑圧される程度を、性差別主義と結びついて決定する人種や階級といった(※ 他の)要因が暗黙のうちに無視されることになる。女性の権利問題に関心を持っているブルジョワ白人女性が単純な定義で満足してきた理由は明らかである。言葉の上で自らを抑圧された女性と同じ社会区分に位置づけることで、(※ 白人女性の)人種や階級における特権に(※ ついて、他の人々からの)注意を呼び起こさないよう望んでいるのである。
下層階級や貧しい女性、なかでもとりわけ非白人の女性であったら、女性解放を女性が男性と社会的に平等になることだとは決して定義してこなかっただろう。なぜなら、非白人の女性たちは、毎日の生活のなかで、すべての女性が同じ社会的地位を共有しているわけではないことを絶えず思い知らされているからである(※ 女主人と家政婦がまったく違うように)。同時に、自分たちと同じ社会集団(※ 例えば、黒人)の多くの男性が搾取され、抑圧されていることも知っている。自分たちと同じ集団の男性が社会的、政治的、そして経済的な権力を持っていないことを知っているために、(※ 黒人などの)非白人の女性はそんな男性たちと同じ(※ 低劣な)社会的地位を共有することが解放だなどとは決して考えない。
非白人(※ 例えば、黒人)の女性は、自分たちのそれぞれの(※ 例えば、黒人などの)集団の男性が自分たち(※ 黒人女性)には認められていない(※ 黒人社会の中だけに限定された、男性としての)特権を持つことを(※ 世の中一般の)性差別主義が可能にしているということに気づいている。しかし一方で、彼ら(※ 黒人男性など)が仲間うちで男性優位主義を大げさに表現する(※ 男らしさをアピールしがちな)のは、全てにおいて特権を持っている社会的地位にある人間としての表現(※ つまり、その自信を示す表現)と言うよりも、むしろ、(※ 白人などの)支配者集団の男性との関係において、(※ 自分たち黒人は)弱くて無力であるということをいつも思い知らされている男としての感覚(※ 情けなさ)に起因しているとみなす傾向が(※ 黒人女性などには)ある(※ だから、黒人男性に同情して、威張ることも許してあげる)。
女性解放運動が始まったそのときから、そうした(※ 強い黒人)女性たちが(※ 男性を攻撃して、女性の権利を言挙げする、白人女性の)フェミニズムを疑わしく思っていたのは、まさにその定義に本来備わっている(※ 弱い立場の男性たちを救えないという)限界に気づいたからである。また、(※ そうしたことから)そうした(※ 黒人を含む、非白人の)女性たちは、男性との社会的平等を目指すものとして定義づけられたフェミニズムは主として、中産階級や上流階級の(※ もとより比較的恵まれた)白人女性の社会的地位に影響及ぼす運動にはなるかもしれないが、労働者階級や貧しい女性の社会的地位にはほとんど影響を与えないだろうということにも気づいていた。』(P40〜41)
私が付箋を貼った部分をすべて引用するわけにはいかないので、ここでは4箇所にとどめておく。
しかし、見てのとおり、以上は、本文全220ページの中の5分の1にも満たない部分からの引用で、全12章の第2章の冒頭部分までからの引用でしかない。
上のようにして紹介したいと思い、付箋を貼った部分が、他に「18箇所」もあるのだ。すべて引用紹介するわけにはいかないと書いたことの意味が、これでご理解いただけよう。
ともあれ、1984年にアメリカで刊行された本書の中で、すでに「フェミニズムの抱える問題点」は、このように的確に指摘されていたのだ。
だが、今の「日本のフェミニズム」がどうなのかといえば、少なくとも、北村紗衣や清水晶子などを見るかぎり、彼女らのフェミニズムは、1984年以前に「先祖返り」し退化しているとしか思えない。
しかし、こうした問題含みの「リーン・イン・フェミニスト」たちが、他のフェミニストたちから公然と批判されないのだとしたら、他のフェミニストも、似たり寄ったりなのか、あるいは、まったく無力なのかの、いずれかであろう。
日本の「フェミニズム界」では、ベル・フックスが本書で行ったような批判による「自浄作用」が機能していないどころか、本書の初刊された時代同様に、「フェミニズム」は、「一部の恵まれた女性」がさらに「上位1%」に「リーン・イン」するための道具になっており、それに踊らされている、一部の愚かな女性たちが、いいように利用され搾取されている、ということになるのである。
実際、本書の第8章は「女性を教育する」と題されているが、アメリカでも日本でも、フェミニズムを口にする女性の大半は、ろくにフェミニズムの本を読んでもいなければ、読む気もない人たち、つまり、北村紗衣の「フェミニスト批評入門」だとか「ジェンダー・フェミニズム批評入門」などというサブタイトルのついた、映画評論を含むエッセイ集を読んだだけで、もうフェミニズムがわかったつもりになっているような人たちなのであろう。
例えば、北村紗衣の『批評の教室』という新書を読んで「批評理論を知るために、ざっと読んだ」というようなことを書いていた人がいたが、この人などはたぶん「批評理論を知れば、批評が書けるようになる」と勘違いしているのだろう。しかも、その批評理論を知るために、批評理論の専門書を読むわけでもなく、北村紗衣のエッセイ集1冊で済ませようとし、さらにそれも「ざっと読む」ことしかしてせず、それがあたかも自慢できることのように語っている。
一一つまり、これが「北村紗衣読者」の「ファスト読書」というものであり、だからこそ、北村紗衣読者の自称フェミニストには、やはり「教育」が、必要なのである。
彼らは、何も知らないで、知っているつもりになっており、そうした人たちが、本来のフェミニズムの足場を切り崩している。
なぜ、日本でもアメリカでも、反フェミが増えたのか?
それは、フェミニストを名乗る者の多くが、他者の苦しみに鈍感な、我利我利亡者(女性の権利亡者)でしかないことが、決して珍しくはないからなのである。
(2025年1月28日)
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
