
『靖国問題』と その〈明晰性〉 : 高橋哲哉 『靖国問題』
書評:高橋哲哉『靖国問題』(ちくま新書)
【旧稿再録:初出「アレクセイの花園」2005年5月31日】
(※ 再録時註:高橋哲哉と加藤典洋による「歴史主体論争」は、一般的には加藤の論を支持する議論が多かったようだが、私は終始一貫して、高橋哲哉支持である。これは明らかに、私の物の考え方が高橋に近いからだろうし、それは自慢できることだろうと思う。加藤典洋の議論は、あまりに「日本人向き」なのである)
先日の、小泉首相の靖国神社参拝問題をめぐって、来日中であった中国の副首相が、小泉首相との会談をキャンセルして急遽帰国するといった事件の矢先であるせいか、本年4月10日に初刷を刊行している本書は、私の確認したところ、現在すでに6刷を重ねており、この種の本にしては珍しく、ベストセラーとなっているもようである。

私に言わせれば、靖国神社を肯定する多くの一般日本人は、靖国の歴史について、ハッキリ「無知」だ。
むろん、私とて人に自慢できるほどのことはなく、数冊の専門書を読み、ひととおりその歴史を学んだ程度ではある。だが、靖国神社を肯定する多くの一般日本人は、そもそも「歴史」や「宗教」や「政治」に関する専門書など「読んだことがない」者が大半で、平たく言えば「何も知らないまま、気分で物を言っているだけ」だと言えよう。
あえて、こう挑発的に言うのも、そういう無知な人ほど、自身の無知が認められないものだからだ。
そういう人たちも、「テレビ」や「雑誌(週刊誌)」などで「それなりに」勉強しているとでも言うのだろうが、要は「その程度(=プロパガンダも考慮できない程度)」のこと(理解)だということだし、そういう人には、そもそも「学ぼう」とか「考えよう」などという積極的な意志など無いのだから、そんな安手な知識など瞬時に流れさり抜け落ちて、後に残るのは「自己肯定的な気分」に過ぎない。

私は現在、先般読了した高橋哲哉の『戦後責任論』(講談社学術文庫)との関係で、今さらながら加藤典洋の『敗戦後論』(講談社)を読んでいる。
1997年に刊行され、賛否両論を巻き起こした話題の書ではあるが、高橋哲哉による同時期の批判(これが『戦後責任論』に収録される)や大西巨人による批判などを通過し、さらに「9.11」や日本の「有事(=戦争)国家化」を目の当たりにした現在にあっては、加藤典洋の『敗戦後論』は、いかにも無惨陳腐なその「じつの姿」を曝していると言えよう。
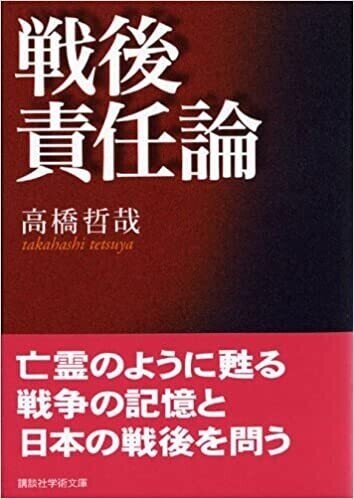
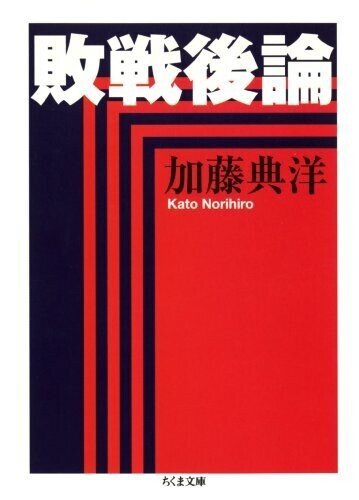
ハッキリ言って、加藤典洋の『敗戦後論』は、戦後の「平和ボケ」によって生み出された、(悪い意味で)文学的な「蒙昧の書」である。
同書の特徴は、『ねじれ』『よごれ』『ジキル氏とハイド氏』『人格分裂』といった、「文学的」あるいは「エセ心理分析的」なキーワードに象徴される、その「気分的=非論理的=呪術的」な語り(レトリック)にある。
高橋哲哉の『戦後責任論』『靖国問題』、大西巨人の『敗戦後論』批判と読み比べれば一目瞭然なのだが、高橋や大西の主張は「明晰な論理」と「現実的な現実認識」に立脚したものである(もちろん、ここで言う「現実的」とは、「現実妥協的」という意味ではなく、「現実をありのままに直視し、それに対峙する」ということにほかならない)。
それに対し、加藤典洋の『敗戦後論』は、まさしく「気分」に訴える態の文章であり、論理を明晰に追い得ない(不明晰な)読者にとっては、いかにも「意味深長」と思える(誤認される)ような「曖昧さ」や「気分」ばかりに満ちているのだ。
加藤典洋の『敗戦後論』の内容的な批判については、高橋哲哉の『戦後責任論』に譲りたいが、私がここで指摘しておきたいのは、一般の日本国民であれ、加藤典洋のような文芸評論家であれ、「日本国家による日本人戦死者の追悼」をもっぱらに主張したり、もっぱらではないにしろ、「日本国家による日本人戦死者の追悼」を「日本軍によって虐殺されたアジア被害者」の先に立てようとするような「自国中心主義=ナショナリズム」な人たちというのは、例外なく「気分的」であり「感情的」、言い換えれば「論理的」ではなく「理性的」ではない。つまり、高橋哲哉や大西巨人的な知性の、対極にある存在であると言えよう。
それを裏づける事実として面白いのが、加藤典洋が自説(『敗戦後論』)を権威づけるために引っ張ってくる文学者というのが、中野重治・大岡昇平・福田恒存といった、一般に「論理的(で倫理的)な作家」だと評価されている人たちだ、ということである。
たしかにこれらの作家は、日本の文学者の水準からすれば、十分に「論理的(で倫理的)な作家」だと言えよう。だが、論理的一貫性をさらに厳格に問う(「厳格主義者」と呼ばれたりする)大西巨人からすれば、いずれも尊敬に値する作家ではあろうけれども、問題が無いというわけではない、ということになる。
例えば、大西巨人は、盟友にして尊敬する先輩でもある中野重治について、戦後の共産党活動を描いた中野の自伝的小説『甲乙丙丁』(講談社文芸文庫)における、作者中野の「曖昧さ」や「腰砕け」を指摘しているし、大岡昇平については、昭和天皇の死去にあたっての「おいたわしい」発言(大岡の死後発表)を「何か思い違いをしている」とし、大岡と自身との差を、大要、次のように説明している。
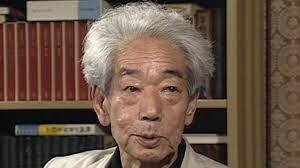
「例えば、戦場で、私と戦友とが、二人で並んで歩いていたとします。そこを狙撃されて、弾が戦友の方に当って彼が死んでしまい、私が生き残ったとします。この場合、私は彼の死を悼み悲しみはするけれども、彼の死に対して責任を感じることはない(私の方が死んだ場合、彼が責任を感じるのが正しいとは思わない)。ところが、大岡の場合は、そこに一種の後ろめたさを感じるんですね。で、その罪滅ぼしのためにも、自分は死んでいった戦友のために、彼らの死の現実を書き残さなければならないという義務感に駆られて、あの『レイテ戦記』を書いたというような節がある。でも、彼の感じた、後ろめたさや負い目というのは、やはり基本的には、筋違いの、勘違いの、お門違いのものだと思う。そのような感じ方をする人だからこそ、いったんは否定した憎悪した昭和天皇に対しても、筋違いの同情を寄せたりしたのではないか」
(NHK制作『『レイテ戦記』を語る』より、大西巨人の言葉要旨)
つまり、水準以上に明晰で論理的な作家たちであったとしても、そこに「気分」的「感情」的な「曖昧」なものが入り込むと、「英霊」や「天皇」といったものを、「曖昧」に「情緒的」に肯定してしまいがちだ、ということなのだ。

だから、加藤典洋が『敗戦後論』で、中野重治・大岡昇平・福田恒存といった「論理的(で倫理的)な作家」を、持論の権威づけに利用していたとしても、それは彼らの「論理性」が加藤典洋の論理を保証しているということではなく、彼らの中の「曖昧さ」や「弱さ」こそが、加藤典洋の「曖昧さ」や「弱さ」と同型をなしている、というに過ぎない。
そんなわけで、是非とも多くの人に、高橋哲哉の『戦後責任論』『靖国問題』と、加藤典洋の『敗戦後論』を読み比べてほしい。そして、さらに言えば、「靖国肯定論者」の本も読んでほしいと思う。
そうすれば、私がここに主張したとおり、「靖国肯定論」等の「自国中心主義」的議論というものが、基本的に「曖昧」で「気分」的な「非論理的論理=エセ論理」でしかなく、決して「論理的」でも「現実的」でもないというのが、その「文体の比較」からも、実感をもってご理解いただけると確信する。
ともあれ、まずは旬の話題作、高橋哲哉の『靖国問題』(ちくま新書)を、ぜひお読みいただきたい。
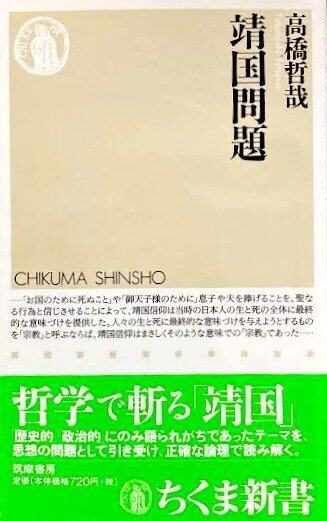
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
