
江藤淳 『成熟と喪失 〝母〟の崩壊』 : 〈我が事〉ゆえの 切実において
書評:江藤淳『成熟と喪失 〝母〟の崩壊』(講談社文芸文庫)
「蟹は甲羅に似せて穴を掘る」という成句があり、それは『《カニは自分の大きさに合わせて穴を掘るところから》人はその身分や力量にふさわしい言動をしたり、望みを持ったりするということのたとえ。』(goo辞書)という意味だそうで、ここで問題とされる「相似性」は、主に「大きさ」であって「形」ではないようなのだが、私はずっと「形」のことを言っているのだと思っていた。
つまり、「それぞれの研究テーマを見ると、本人が抱えている問題だと考えてまず間違いないわ。自分が困っているから、その分野の研究をするのよ。」(米心理学者ウォルター・ミッシェルの言葉、スザンナ・キャラハン『なりすまし』P368)ということである。本人が抱えている「問題」を他人に投影し、それを補助線とすることで、他人が隠し持っている問題に鋭く気づくことができる、というわけだ。
本書『成熟と喪失 〝母〟の崩壊』において、安岡章太郎『海辺の光景』、小島信夫『抱擁家族』、遠藤周作『沈黙』、吉行淳之介『星と月は天の穴』、庄野潤三『夕べの雲』といった小説作品における「母の喪失」の問題を、江藤が非凡に鋭く剔抉し得たのは、じつは彼自身が、深く「母の喪失」に苦しんでいたからであろうし、彼が「愛国的保守主義者」となって、一見「マッチョな保守理論家」の印象を与えながらも、じつのところ、自身の妻に「母の安らぎ」を求めたあげく、妻に先立たれた後は、すっかり気落ちし、その翌年には『自らを「形骸」とし、自宅で自殺した』(Wikipedia「江藤淳」)というのも、他人の内面の問題ゆえに軽々に断定できないとは言え、何より本書を読んだ読者には、いかにも説得的な「江藤淳理解」となってしまうのではないだろうか。

(江藤淳の母、江頭廣子)
私は1962年生まれだから、江藤の三十歳下で、言うなれば江藤の子の世代なのだが、それでも私が若い頃には「母子密着型」という問題が、よく語られた。「専業主婦」が当たり前の時代にあって、「母と子」、特に「母と息子」の密着ぶりが、例えば「教育ママ」などの問題などと関連して語られた。
しかし、私自身は、このタイプでは全くなかった。
私の両親は夫婦で寿司屋を営んでおり、正午すぎまで家で寝ていて、午後3時ごろに隣町の繁華街にある店に出勤し、日付の変わる頃に閉店して、午前2時過ぎに帰宅して就寝する、という生活をしていた。私と一つ下の弟の面倒を見ていたのは、同居していた母方の祖母であったが、この人が、きつい性格の人で、私たち兄弟は、父と母が店に出た後、祖母と三人でいる大半の時間は、いつも祖母の顔色を窺って生活していた。
つまり、両親と、私たち兄弟とでは、生活のサイクルがズレており、朝は両親ともまだ寝ているし、学校から帰宅した時にはすでに両親はおらず、私たちが寝てしまった後に帰宅したのだ。だから、両親に甘えられるのは、店が休みの水曜日だけだったのだが、そのぶん、休みの日には、両親は私たち兄弟を甘やかしてくれた。どういうわけだか、私は父親っこで、弟は母親っ子だった。
そしてそんな私には、父に愛されて育ったという確固たる自信があり、母に対するこだわりは、愛着も含めて、特にない。だから、「母子密着型」というのは理解不能だった。むしろ「みっともない」とか「恥ずかしい」ものだと、ずっと思っていた。私は、授業参観日に誰も来なくても、全然平気だったし、それが自慢でもあった。平気な自分が自慢だったのである。たぶん、親から自立しているという自負があったのだろう。
そして、今もなお私は「マッチョ」タイプであるとの自覚がある。「重厚長大」「硬質」「鋭利」「論理的」なものが好きで、「べったり」とか「ネチョネチョ」とか「甘ったるい」ものが好きではない。
そんなわけで、私は「母子密着型」の作品に興味を持つことがなかった。私が「第三の新人」作家に、興味を持たなかったのは、ほとんど直観的なものだったのかもしれない。読むのなら、教科書に載っているような、明治大正そして戦前からの昭和作家か、あるいは80年代以降の同時代作家にしか興味が持てなかった。「第三の新人」作家たちに興味が持てなかった理由は判然としないが、本書を読むと、少なくともこうした作家たちの抱えた問題を、私が共有できなかったからかも知れない。

(「第三の新人」たち。前列左から、遠藤周作、不詳、不詳、十返肇、不詳、吉岡達夫。後列左から、不詳、安岡章太郎、不詳、小島信夫、庄野潤三、小沼丹、吉行淳之介、進藤純孝)
ともあれ、私が最初に好きになった作家が夏目漱石であり、後年「師と仰ぐ」ほど惚れ込んだ作家が大西巨人だというのは、分かり易すぎるくらいに分かり易い傾向性だと言えるだろう(漱石の方は、「論理的」であると同時に「マザコン」でもあったが)。
私が、江藤淳を読み始めたのは、ごく最近のことで、それは優れた文芸評論家としてではなく、「反戦後民主主義的保守主義者」として、批判的な観点から「無視できない」と考えたからに他ならない。
私は「ネトウヨ」や「エセ保守」が大嫌いだから、彼らの担ぐ江藤淳とはどんな人物かと『閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本』(1989年)を読んでみたのだが、正直「なんだ大したことないじゃないか。これじゃあ、ネトウヨに毛が生えた程度だ」という印象しかなく、文芸評論家としての力量まで眉唾なのではないかと疑ったのである。しかし、ただそれを確認しないままに江藤をつまらない評論家呼ばわりするのでは、無知なまま歴史を語る「ネトウヨ」と大差がないので、私は評判の高い代表作的な文芸評論書として、本書を読むことにしたのだ。
そして、その結果は、最初に書いたとおりで、たしかに本書は素晴らしい文芸評論書であり、評判になるだけのことはあると思った。しかし、その「すごさ」は、本書のテーマが、江藤の抱えた「中心的テーマ」を扱ったものであったからで、江藤が、何にでも鋭いわけではない、ということも、よく理解できたのである。

例えば、「講談社文芸文庫版」の解説者である上野千鶴子が指摘しているとおり、江藤がここで説明の道具として利用しているエリクソンの「フロイト派心理学」や、エリアーデ的な「大地母神」的「母性」理解は、時代の制約があったとは言え、いかにも紋切り型のペダントリーでしかない。こうした説明は、素人読者向けの「虚仮威し」としては有効だけれども、分析としては、やや図式依存にすぎて、安易であると言えよう。
と言うのも、フェミニスト上野千鶴子の指摘を待つまでもなく、「母性」を、「女性における自明な本質」のように考えるのは、歴史的な「憶断」に過ぎないからだ。私たちはしばしば、エリアーデやユング的な「原型論」的理解で「女性とは、本来本質的に、母性を持ったもの=大地母神的な存在である」と考えてしまうが、これは、いかにも男性的な「神話」に過ぎない。「女性=母性」ではないのだ。
「女性」が「母性」を持つのは、進化論的に構造化された「身体的な性別特質」と「文化」の相互作用において、初めて「発生」し「作動」するものであって、「文化」的側面においてその「必要性」が無ければ、「女性」にも「母性」は生まれないし、言い換えれば、「文化」のあり様においては「男性」にも「母性」は生まれ、作動するのである。つまり「母性」とは、「性別」と同様に「二者択一」ではなく、男女の別なく「グラデーション」的に存在するものなのだ。
だから、江藤淳が直面した「母性の喪失」としての「母の崩壊」というのは、「文化の歴史的変容」の結果であって、「女性」の「本質的変化」なのではない。だが、江藤は「母性」というものに執着するからこそ、それが「本来的本質的」なものであると思いたいし、それが失われていく時代への「哀歌」を、声をあげて歌わずにはいられなかったのである。
また、そんな「母子密着型」の江藤淳だからこそ、「国家」という「母像」にしがみつかなければならなかった。それを「父」だと強弁してでも、自身の寄って立つ「大地」を確保しなければならなかったのだが、それは所詮「自立できない息子」の「甘え」でしかなかったし、だからこその「雄々しさに欠けた終幕劇」だったのではないだろうか。
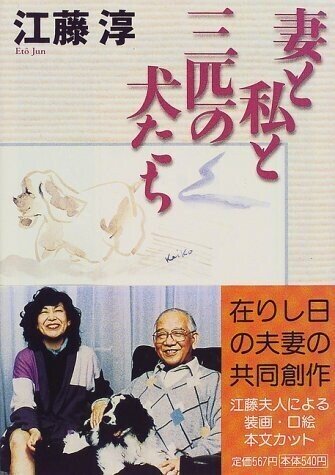
(※ 愛犬に関する議論については、下のレビュー「Don't think! Feel」をご参照ください)
「ネトウヨ」が「フェミニスト」を嫌うのは、要は「甘やかしてくれないから」に他ならない。
「日本の伝統」を口にするわりには、『日本書紀』も『古事記』も読んではおらず、借り物の薄っぺらな理論で満足できるのは、彼らがしたいのは「自立」ではなく「依存」だからだ。「本当のこと」なんか、どうでもいいのである。
たしかに江藤淳は、「他人」の中の「母の影」を、その「共感」ゆえに鋭く見通すことはできた。だが、自分自身の中の「母の影」を直視することはできなかった。つまり彼は、ついに「母」から自立できなかったのである。
初出:2021年5月19日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
再録:2021年5月28日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
