
◆読書日記.《エーリッヒ・フロム『正気の社会』》
<2019年11月11日>
新フロイト派の精神分析学者エーリヒ・フロムの社会心理学論『正気の社会』読み始めました。

この間読んだ山崎雅弘『歴史戦と思想戦』にフロムの『自由からの逃走』について触れた個所があって興味があったんですが、ちょうど手元にあったのが本書だったので、読んでみることにしましたよ♪
翻訳者がお医者さんだったり学者さんだったりするためか、若干翻訳が固くて読みにくい。
まだ入口部分を読んでいるだけですが、本書は「われわれ人間は本当に正気なのか?」という面白い問いから始まっているのが興味深いですね。
確かにフロイト派には人間は多かれ少なかれ神経症を患っているという考えがあります。
というのも人間と言うのは社会に適応するためには自分の元来の欲望を抑えなければならず、幼児期に両親から躾けられる事とはそのように「欲求を抑制する事」だと言っていいでしょう。
他人に暴力をふるってはいけない、静かにすべき場所で騒いではいけない、お腹が空いても決まった時間に食事しなければならない、嫌いな食べ物でも食べなければならない、毎日歯磨きをしなければならない、欲しいものがあっても我慢しなければならない、等々。
人が人となるという事は、動物的な本能を抑制して、ルールに従う事を覚えるという意味がある。つまり「基本的に、人間の欲望は抑圧されている」という事です。
そのためかフロイトやラカン思想には「人間は本能が壊れた生き物だ」という考え方があります。
しばしば呟いてますが、人間の性欲というのはもはや「生殖本能」とは関係のないものになっています。
だからこそ生殖とは全く関係のない身体部位「胸」や「尻」を見て性欲を感じるという事となります。
「食欲」も本来の「栄養補給」という欲求とは乖離しています。
それはしばしば「空腹を満たす」のではなくて「和食が食べたい」や「故郷の料理が食べたい」「流行りのランチに行きたい」になる。
衣服についても「暑さ/寒さを調節する」役割とは関係なく、例えばモテるファッションを着たいと思う様になる。
つまり、「生殖本能」は「ポルノ」に、「食欲」は「グルメ」に、「衣服」は「ファッション」に……と言ったように人間の欲望とは、生存本能や本来の動物的な欲求とは関係のないものになってしまっているのです。
そういう前提のもとに考えてみるわけです。「われわれ人間は本当に正気なのか?」と。
そう考えるとわれわれ「正気」とされている人間とは、イコール「本能の狂った動物」なのかもしれません。
精神病患者は社会の中のマイノリティなのだ……と思っていてその実、われわれマジョリティのほうが本当の意味で精神病を患っており、分裂症患者や神経症患者のほうが、元来の自然的本能を保った「本来の本能を保った生き物」なのではないか?
……このような疑問を解消するためには、まず「では正常な人間とは一体いかなるものか?」という事を考えねばなりません。
社会に生きるということは、著しく本能を滅殺していくという事ですが、では本当に望ましい「精神の健康」とはいかなるものなのか。
そして、われわれの発展型資本主義社会というものは、そのような「人間の精神の健康」にどのような影響を与えているのか。
そして、そのような「人間の精神の健康」を追求できる社会体とは如何なるものなのか――そういった部分が、どうやら本書のテーマになっていくようです。
<2019年11月12日>
エーリッヒ・フロム『正気の社会』読んでます♪
読み始めた当初は翻訳が固くいし実証的な研究ではないし、本当に良い本なのだろうか?と疑問だったのですが、読み進めるうちにどんどん面白くなってきました。
フロムがやっている事は、心理学や精神分析の研究成果を社会学的な分野に当てはめる事なんですね。
◆◆◆
さて、「人間は様々な本能が壊れた動物である」と先日呟いたが、なぜ人間は本能が壊れているのだろうか?
人間には動物に無い「理性」によって、動物的欲求や生理的欲求を捻じ曲げてしまっているからだ。
では、その代わりに現れた「人間的欲求」とは何だろうか?
フロムはそれを「関係づけ、克服および、結びつきを求める欲求、同一感を求める欲求、方向づけや信仰の枠組みを求める欲求」と説明し、「人間の精神の健康」はそれら「人間的で、人間の状況条件から生ずる欲求や情熱の満足にかかっている」と言うのだ。
フロムはフロイトのリビドー説を真っ向から否定するのである。
人間は生理的欲求だけを満足させても決して「精神の健康」は保つことができない。
それは生理的欲求にプラスして「人間的な、人間の状況条件から生ずる欲求」を満足させる必要があるからだ。
こういった人間的な欲求を満足させ、人間の精神の健康を保つための条件と言うのを本書でフロムは提示している。
「精神の健康は次の点で特徴づけられる。即ち愛し創造する能力、氏族や土地への近親愛的な絆から抜け出す事、自分自身が自分の力の主体であり、行為者であるという経験から生ずる同一感、我々の内部の現実と、外部の現実を把握する事、つまり客観性と理性を発達させる事である」
これがフロムの提示する条件である。
これは、一つには西洋的な「成長」の概念に近いような気がする。個としての「自我」を確立させる事が、人間の健全な精神の確立につながる。
だがこの「精神の健康の条件」は、細かい所では所属する社会の文化等の条件によってだいぶ変化する。
では、社会は「人間の精神の健康の条件」にどのような影響を与えるのか。
「精神の健康は、個人の社会への『適応』という意味では定義できない。反対に社会が人間の欲求にどのように適応したか、つまり精神の発達を促進したり、妨害したりする社会の役割によって定義されなければならない。個人が健康であるかどうかは、まず何よりも個人的な事柄ではなくて、その社会構造に依存している」
――という所から、本書の論旨はタイトル通り『正気の社会』とはどのようなものなのかという社会心理学的な考察に移行していく。
ここで興味深いのは、「精神的な健康」は個人が社会にどの程度適応できたかによるのではなく「社会が人間の欲求にどのように適応したか」によるという指摘であろう。
人がどんなに社会に適用しようと生活していても、社会構造の如何によっては人の精神の健康は必ずしも保証されない。
「病的な社会/不健康な社会」があり、「正気の社会/健康的な社会」がある。
では、そのような社会とは一体、どのような社会なのか。
現代の高度資本主義社会というのは、どちらの社会なのだろうか。
フロムは「不健康な社会とは、相互に敵意と不信とを生じさせ、人間を他人が利用し、搾取する道具に変え、他人に服従するか、自動人形にならない限り、人間から自我の感覚を奪ってしまう社会である」と定義する。
フロムによれば、社会は人間の精神的な健康を助長する事もあれば妨害する事もあると指摘しているのだ。
そして、社会にはたいていの場合「不健康な面」と「健康な面」の両方を持っており、問題はそのどちらがどの程度影響しているかという点にある。
我々は、我々の健康のために、我々の所属する社会における「人間の精神の健康を促進する面」を強化していかなければならないのだ。
個人個人が、一生懸命社会に適応しようとしても、限界がある。悲しいかな、それを理解しなければならない。
だからこそ「脱落者」とみられる人たちが増えている社会というものは、個人個人がそれぞれに社会適応するために頑張ってもダメで、社会のほうをどうにか「正気の社会」に近づけていかねばどうしようもない。
日本では個人よりも組織を優先する傾向があるためか、個人が周囲に合わせないといけないという考え方に陥りがちなのではないだろうか。
何かあるごとに引きこもりやホームレスや生活保護を受けている社会的弱者の不備を責めるのは、そういった意味では「不健康」な社会の傾向なのではないかと思うのだ。
そして、我々の所属する社会における「人間の精神の健康を促進する面」を強化し「正気の社会」になるための道を示そうというのが、本書の最終的な結論となっていくようである。
――ところで、フロムが提示した「不健康な社会」像である「相互に敵意と不信とを生じさせ、人間を他人が利用し、搾取する道具に変え、他人に服従するか、自動人形にならない限り、人間から自我の感覚を奪ってしまう社会である」――というのは、我々の知っている「ある現実の社会」にとても似てると思うのは、果たしてぼくだけであろうか?
<2019年11月13日>
エーリッヒ・フロム『正気の社会』読んでますよ♪
フロムの代表作『自由からの逃走』は、フロムがその社会心理学的な視点を持ってナチスドイツをメインとした「全体主義」という「集団の病理」を分析した内容となっている。
全く持って解き放たれた自由な個人というのは孤独や責任というものが付きまとう。
「もし個人が十分な理性と愛情のための能力を持っていないと、自由や個別性の重荷に耐え切れなくなって、帰属と結びつきの感じを与えてくれる人工的な絆に逃げ込もうと試みる。自由から逃れて、国家や民族のような人工的な結びつきに退行する事は今日ではすべての精神病の現れである」
つまりフロムは「愛国心」を持った人間や「国家主義」的なパーソナリティを持つ人を「精神病」と断じているのである。
西洋的な常識では一人前の社会市民となるには自我を確立させねばならないという考えがある。
集団に依存してしまっている人間と言うのは一人前の社会人ではないというわけだ。
だが、日本のユング派心理学者・河合隼雄によれば日本人の自我は集団や共同体と半ば溶け合っていると言う。
つまり、日本人は集団に依存するように求められる傾向にあるというのだ。
「会社の危機なんだ。会社を潰さないためには、少々辛い業務でも我慢してやるべきだ」「クラスが優勝するためには、みんな一致団結して放課後もちゃんと運動会の練習に積極的に参加すべきだ」――改めて考えてみれば日本と言うのは、集団の延命のために個人が自己犠牲を強いられるシーンがしばしばみられるのではないか。
このように個人が集団に依存するよう求められ、個人がそのようなパーソナリティを得る事が多い社会だからこそ河合隼雄はそのような傾向を「日本人の自我は集団や共同体と半ば溶け合っている」と表現しているのだ。
日本型のパーソナリティが「ダメだ」とは言わないが、少なくとも「弱点」は理解しておくべきだろう、という趣旨で書かれたのが河合隼雄の『母系社会日本の病理』だ。
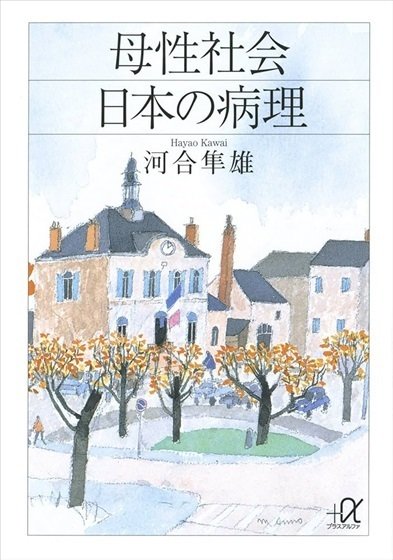
これもフロムの専門分野と同じく社会を心理学的に分析する社会心理学の理論だった。
日本人的パーソナリティである「自我が所属集団と溶け合っている」という性格特性は一長一短ある。
集団を優先するパーソナリティというのは確かに集団の権威と権力は増すだろうが、反面、個人への扱いが冷たくなる傾向がある。
こう書くだけでも、どこかいろいろと心当たりが出て来るのではなかろうか? 日本は「個人主義」を冷たく扱う国なのかもしれない。
因みに、ぼくはネトウヨのパーソナリティについて「現政権とアイデンティティを重ね合わせ、依存する事で自分も権威を得た気分になる」と説明する言説について、今までは理屈が分かるが"感覚"的には分からなかった。
が、最近良い例えを思いついたことでその説明について感覚的に理解できるようになってきた。
「ネトウヨのパーソナリティは"フーリガン"的である」
つまり、政権が正しい事をやっていようがいまいが関係なく、自分の応援している集団が勝つことに快感を感じる。だから、詭弁だろうが強弁だろうが「勝てばいい」と思ってしまう。――だから「ネトウヨは単なるフーリガンである」
<2019年11月14日>
エーリッヒ・フロム『正気の社会』読んでますよ♪
さて、前々回は、人間はなぜ動物が本来備わっているはずの本能がねじ曲がってしまったのかという説明として、人間が「理性」を手にして文化・文明を発展させたことによって、そこに適応するために本来の欲求や本能を捻じ曲げていったからだと呟いた。
人間は生理的欲求だけを満足させても決して「精神の健康」は保つことができない。
それは生理的欲求にプラスして「人間的な、人間の状況条件から生ずる欲求」を満足させる必要があるからだ。
この状況をもう少し詳しく説明しよう。
フロムは、動物は退屈しないと言っている。人間だけが退屈することができる、と。
考えてみれば、人間は「理性」を手に入れてそれを使っていろいろと考えるようになったために様々な「動物にはない問題」を抱えるようになった。
例えば、本日購入した作家であり精神科医のなだいなだ『とりあえず今日を生き、明日もまた今日を生きよう』でも、なださんは「うつは『いろいろと考えられるようになった』人間に起こる」と言っている。
幼児に鬱病は起こらない。
学齢期の子供も稀である。が、ぼちぼちみられるようになる。鬱傾向になるのは「ませた利口な子」なのだと言う。
そして、鬱病は大人になると珍しくなくなり、老人になると多くなる。
だが老人も後期高齢者になると減ってくる。
だから「鬱病は理性的に考える能力を持った時期に集中して起こる病気」とも言えるのだそうだ。
様々な精神病と言うのは理性的な動物である人間だから起こる病気なのかもしれない。
「退屈」というのも、一時的ならば問題なかろうが、一カ月や一年間など長期に渡れば精神に関わって来る。
人間は自然状態から離れる事によって本能を捻じ曲げて来たが、その際に生まれた「歪み」をどうやって慰撫してきたかと言えば、様々な「文化」的な方法によって癒してきたのではなかろうか。
なぜ人間は生きていくのに不必要な「芸術」や「娯楽」を生み出し、今なお生み出し続けているのか?と言う問題は昔から言われてきたことだが、人間はそのように「本来の欲求を抑圧する事で生じた歪み」を癒すために、必然的に娯楽を生み出してきたのではなかろうか。
人間は自然から離れることによって本来持っていた欲望を様々な形で抑圧していかなければならなかったが、その代わりに理性/文明の力によって猛獣に襲われて食われる恐れや病気で若くして亡くなる恐れというものからも離れる事ができてきた。
これをフロムは聖書の楽園追放のエピソードで例えている。
我々人間は知恵の樹から禁断の果実(=理性/知性)を手にしたために、楽園(=自然)を追放されてしまったのだと。
そのために生じてしまった歪みを、我々は文明や文化によって矯正してきたのではないか。
例えば、娯楽にはなぜ多くの場合「カタルシス=浄化作用」が必要になって来るのかという点も説明できそうだ。
娯楽におけるカタルシスが「浄化作用」なのは、それが「抑圧とその解放=ストレスからの解放」であるからこそ、それを見た観客が「気持ちいい」と感じる。
「カタルシス」を得られる娯楽の典型例が例えばドラマ『水戸黄門』などの分かり易いエンタテイメントに見られる。
悪代官や越後屋が汚職をして私腹を肥やし、その陰で一般庶民や農民は苦労を強いられてしまう。
つまり「ストレス」だ。
ラスト、その分かり易い悪役達を黄門一行がバッタバッタとじゅうぶん切り伏してから黄門様が印籠をかざせば、仰天した悪役はすぐさま平伏し「裁きを待て!」と言われてシュンと縮んでしまう。
これが「ストレスからの解放=抑圧からの解放」だ。
王道型のエンタテイメント物語というのは、多かれ少なかれこういった「型」で説明できる。
この手の娯楽は、理性と知性を手にしたかわりに本来的な欲望を抑圧された人間にとって、そういった抑えられた欲望を疑似的に解放してくれる喜びがあるのかもしれない。
だからこそ「カタルシス作用」というのはエンタテイメントの常道となっているし、ひいては人は「癒し」のために太古から現在に至るまで「芸術」や「娯楽」を飽くことなく作り続けているのではなかろうか。
「禁断の果実」を手にして楽園を追放された人間は、その心を癒すことにもまた「禁断の果実」を必要としているのだ。
<2019年11月17日>
自分の人生の中の「幸福」と「不幸」の貸借対照表を作ってみたとしたら、自分の人生は、どれくらい損失が出ているのだろうか。それとも、利益のほうが優っているだろうか。
――こういった疑問に似たような考えを持ったことはないだろうか。
エーリッヒ・フロムはこのような「幸福」と「不幸」の「量」を計るかのような考え方というのは、産業資本主義が盛んになってから出てきた考え方ではないかと『正気の社会』で指摘している。
少々長い引用になるが、該当箇所の文章を以下引用してみよう。
「現代人の心の中に新しい疑問が起こったのであって、その疑問というのは即ち『人生は生きるに値する』かどうか、したがって、人生は『失敗である』かそれとも『成功である』かという感情である。こういう考え方は、人生を利益を生むはずの企業だと考える事に基づいている。失敗とは、損失が利益よりも多い企業の破産のようなものだ。だがこの考えは無意味な考えである。我々は幸福であるし、不幸でもある。ある目的は達成できても、他の目的は達成できない。しかも、人生が生きるに値するかどうかを示しうるような敏感な貸借対照表はない。おそらく、貸借の対照という見地からすれば、人生は全く生きるに値しない。人生は必然的に死をもって終わりをつげる。我々の希望の内の多くのものが裏切られる。人生には苦痛と努力が伴う。即ち貸借の対照という見地から見れば、全然生まれなかったか、幼時に死んだほうが、よほど意味があると思われる。一方、幸福な愛のひと時や、ある晴れた朝に息を吸い込んだり、散歩したり、新鮮な空気をかいだりする喜びが、人生に含まれる全ての苦痛や努力に値しないとは誰にも言えないだろう。人生は、かけがえのない贈物であり、挑戦であって、他のものでは計る事が出来ない。しかも人生は『生きるに値する』かという質問に対しては、わけのわかった解答は何も与えられない。なぜなら、その質問は何ら意味をなさないからである。」
あまりに分かり易く丁寧に説明しているので、ぼくの意見を付け加えると蛇足となりそうだ。
つまり「自分の人生は生きるに値するか否か?」という疑問は「幸福」と「不幸」を「量が計れる"値"」として見ている背理だというわけだ。
「幸福」も「不幸」も、数値化して比較できるものではないのである。
幸福の量が多ければ、不幸を打ち消すことができるわけでもない。
また、それぞれの幸福を「数値」に翻訳する事など不可能だ。
それは、人によって、時期によって、気分によって、感じ方によっても受け取り方によっても全く価値が変わる。
そう考えれば「人生は生きるに値するか否か?」などという疑問は意味がないのだ。
<2019年11月18日>
エーリッヒ・フロム『正気の社会』読んでますよ♪
今までの流れとしては問題設定⇒人間という存在とは⇒人間の精神の健康とは……と来てから、資本主義社会における人間の診断というテーマの所まで読み進めています。
予想通り、資本主義社会における病理と言うとヘーゲルとマルクスの疎外論が出てきましたね~。
◆◆◆
人は自分の意思決定通りに動けない。
社会に適応するという事はそう言う事で、「社会」というのは人間が開発したはずのものなのに、人はその社会の仕組みに操られて生きていかねばならない。
家庭では両親の指示に従い、学校では教師による命令に従い、会社では上司や経営層の指示・命令に従わなければならない。
「会社に従う」という事は「朝、決まった時間に起き、決まった時間に出勤し、決まった時間まで仕事をし、決まった時間に退社して夜になったら寝る」という生活に服従する事を意味している。
「夜のほうが頭が働いて日中は力が発揮できない」という夜型のタイプであっても基本はこのライフサイクルに矯正させられる。
睡眠障害の正体と言うのは、社会(=企業の就業時間)のライフサイクルに自分の体内時計を合わせられない事を意味していて、「資本主義社会で社会に適応する事」とは「朝は遅刻しないように起床する」という生活に適応する事だ。
「社会人」とは社会の決まりに、自らの個性を適応させるという事となる。
資本主義社会にはこのような疎外状況と言うのは様々な形で存在している。
「即ち健康とは人間が社会的機能を果たす事ができ、生産を続け、生殖できるという意味なら、疎外された人間は全く健康なのである」とフロムも言っているように、資本主義的基準では「社会的機能を果たせる事」が健康の定義となってしまう。
この定義の正当性をフロムは、ウェルズの『盲目の国』という小説を引用して説明する。
この小説の主人公は普通の人間なのだが、この男が全員生まれつき目が見えない種族のいる国に居を構えるのだ。
彼はその種族の医者から「彼は脳をやられている」と診断される。
「《眼というおかしなものがあって(~略~)その眼がおかされているために脳がやられているんだ。彼の目は非常に膨らんでおり、睫毛が生えていて、瞼が動くので、彼の頭脳はいつもいらだち気が散っているというわけだ》《へえ?》《まさか》と年をとったヤコブは言った。
《そこで彼を完全に治すために必要な事は、簡単かつ容易な外科手術、即ちこの刺戟物を取り除く事で十分だと、かなりはっきり言えると思う》《そうすれば彼は正気になるでしょうか?》《完全に正気になり、全く立派な市民になりますよ。》《本当に科学のおかげです》」
人間の精神の健康と言う状態は、このように人間の疎外されたパーソナリティをスタンダードなものとして定義される。
個人的な状況ではなく、社会的な状況に合わせられる事が「健康な精神」なのだ。
自分を社会の一部として扱う事がスタンダードであり、より深い状態で個人的動物的欲求を抑え込む事を求められる。
このように自分の生活や仕事の中で「自己決定」による行動が減り、自らの所属する社会のスタンダードに自らをはめ込む事ができずに病んでしまうと、それは「適応障害」という精神病となって現れる。
資本主義社会の健康と病理との関係というのは、そういった人間の疎外状況の中にも見出せるという事だろう。
ちなみに、こういった人間が疎外された状況というのをフロムは批判的に扱っている。
また、こういった「社会的機能を果たせ」「生産を行える人間になれ」という意思が蜘蛛の巣のように社会にいきわたっている状況を「生-権力」論として批判したのがフーコーだった。
<2019年11月22日>
エーリッヒ・フロム『正気の社会』読了!
分量はさほど多くはなかったんですが、面白いのでいろいろと考えを広げている内に読むのに時間がかかっちゃいましたね。
ちなみに、本書のタイトルを「正気の社会」としているのは、今の社会が「正気だ」と肯定しているわけではありません。
逆に、今の社会には正気でない部分があるからこそ、もっと人間の精神に対して健康な社会となるような指針を示して見せようというのがテーマとなっています。
このテーマを考えるためにフロムが出してきた素材は心理学と精神分析のほかに、社会学、経済学、政治学、哲学、歴史……と、かなりの広い範囲に渡っています。
基本線は、本書の出版された1950年代の国家の大きな流れである資本主義社会と共産主義社会とのふたつの社会に関する分析を行ったうえで、今後「人間の精神の健康」が得られる社会とは何かという事を考えるという流れとなります。
フロムが新フロイト派だという事情もあってか、勿論結論は心理学的なものになります。
これまで注目されてきた資本主義的な考え方というのは、経済の活性化が議論の中心となり、そのために個人の人間性を尊重する視点に欠けているのではないか、というのがフロムの主張のひとつとなっているようです。
産業は本来人間のために発展するべきで、現代の労働者は産業の発展のために自らを犠牲にしているのではないか。
ものを作る(産業)のために、人間が苦役を強いられる。
つまり、本来なら人間のためのモノであるはずであるものが、資本主義社会では「モノのために人間が従わされている」という疎外状況が発生している。
資本主義の考え方では、物が充実すれば人間が幸福になるという意識があるのかもしれない。
ですが、そこには個々の人間の心理に対する視点が欠けているというわけです。
この考えは若干マルクス的です。
集団というのは、大きくなればなるほど多くの末端労働者を疎外していきます。
末端の労働者に植え付けられる意識は「自分の代わりなんて掃いて捨てるほどいる」という人間軽視の意識です。
経営者的な「人はお金さえもらって物が充実していれば幸福である」という推測は、末端労働者の心理を理解していないというわけです。
人は、毎日の仕事に意味を感じず、興味を持てず、熱意を持てない場合、その仕事に「不満」を感じます。
こういう不満が何故起こるかと言えば、仕事に対して自己参入感を得られないという事情があります。
自分の仕事に対して自分の意志でやり方を選ぶことが出来、結果に影響を与えることが出来、結果の充実度を確認することが出来る。
それが出来てこそ「仕事に関わっている」という意識が生まれる。
指示・命令に背くことができず、自分の仕事に対して意見することができず、自分の仕事に対する結果がどのようなものだったのか、その成果を確認する事が難しい。
このように、自分の仕事に対して「自分のもの」であるという「参入感覚」が薄れる事で、末端労働者は自分の仕事を「他人の労働をさせられている」と感じ、「毎日の仕事に意味を感じず、興味を持てず、熱意を持てない」という状況に陥る。
こういう熱意をなくした末端労働者を、経営側は「怠けている」と感じるわけです。
そして経営者は労働者が怠けないように監視する仕組みを取り入れる。
経営者にあるのは「基本的に人間は怠けるものだ」という意識です。「性怠説」とでも言いましょうか。
そこでフロムは「怠惰」は精神病的なものだと主張します。
「怠惰は正常どころか精神病理の症状である。事実、精神的苦悩の最悪の形態の一つは、自分自身や、自分の人生について何をしたらいいかが分からない退屈なのである。仮に、金銭上の報酬や、何か他の報酬がなくても、人間は、不活発が生み出す退屈に耐える事ができないために、何か意味のあるやり方で熱心にエネルギーを費やそうとするだろう。
子供達を見てみよう。彼らは決して怠けていない。ほんのちょっとした励ましが与えられたり、それがなくても遊んだり質問したり、物語を作ったりして忙しいのだが、その場合には、活動それ自身の喜び以外には何の奨励もしない。
精神病理学の分野では何をする興味もない人間は重症であり、人間性の正常の状態からはほど遠いことが分かっている。(~略~)それにも関わらず、人間は生まれつき怠惰だという信仰が広まっているのには、正当な理由がある。主な理由は、疎外された労働は退屈であり、不満足だという事実にある。
すなわち、多くの緊張と敵意とが生じ、自分のしている労働やそれに関係のある全てを嫌悪するようになる。その結果、怠惰や「無為」に対する憧れが多くの人々の理想となるのが分かる。こういうわけで、人々は自分たちの怠惰は生活の病的な状態の病状であるよりも、精神の「自然な」状態であり、無意味で疎外された労働の結果だと感ずる」
つまり「仕事に興味が持てない」のは「労働者が怠惰だから」ではなく、労働者が疎外された労働条件を押し付けられているからだ、というのがフロムの主張なわけです。
自分の事を、自分の責任で、自分で決めてやることのできる仕事なら怠けたり興味を持てなかったりするわけがないだろう、というわけです。
こういった労働者のモチベーション的な問題と言うのは本人の自己責任の問題ではないのです。
例えばフロムは、家政婦の仕事と専業主婦の仕事を比較してみせます。
両者はほぼ同一労働であるにも関わらず、そのモチベーションは違います。
専業主婦は自分の家族のために、自分の責任範囲で自分の仕事を決めて労働を行う「自己参入感」を得ていますが、家政婦は雇い主に命じられて決められた労働を決められたとおりに行わなければなりません。
つまり、同一労働であっても、社会的条件が違っていれば疎外は起こるし、モチベーションも違うのです。
日本の民間企業の会社員の社会条件についても同じ事が言えるでしょう。
高度経済成長期の日本の会社員でしたら、働けば働くほど自分の給料は上がっていき、社会インフラは整っていき、テクノロジーは発展していき、経済がどんどん良くなって職場の全員に明るい未来が見えている。
それに対して現代の日本の会社員は、働いても給料は上がらず、長く会社に居座ってもなかなか昇進できず、年を取っても自分の生活は豊かになっていかず、結婚も出産も負担になるばかり。
そのうえ将来に好景気が待っているという保証はない。
行き先が暗いのに高度経済成長期の日本の会社員のようにガムシャラに働いたっていい事が起こるなんて限らない。
高度経済成長期に働いていた会社員と現代の会社員とでは、疎外の度合いが全く違っている。
これでは、高度経済成長期と同じようなガムシャラな働き方(同一労働)を求めるのは無理な話でしょう。自然、そういった世代間の労働観にギャップが出るわけです。
フロムはこういった、労働者に「精神的に不健康」な条件を与えている社会を変えるための条件をいくつか提示します。
巨大企業というのは、労働者から経営方針までの距離が果てしなく遠い。
また、政治についても、投票から政治的決定までの距離が遠い。
有権者の数が多ければ多いほど、国民ひとりひとりの意識が政治に反映する確率は数万分の一、数千万分の一、数億分の一に薄まる。
フロムは、この状況を変えるために地域分権を進め「人間主義的な共同社会主義」を提案します。
ぼくは、このフロムの提案自体はさほど関心はしなかったのですが、重要な部分は今までの「資本」を中心に社会形態を考えるのではなく「個々の人間性」を尊重する事を中心に社会形態を考えるべきだ、という考えには賛同したいと思いました。
現代のウルトラ資本主義社会は、既に個々の労働者の事情を離れ、人間よりも「経済」や「資本」の発展を考える「脱人間中心主義社会」であるという所に、批判すべき根本があるようにも思えます。
