
『ザリガニの鳴くところ』 : はたして彼女は、犯人だったのか?
書評:ディーリア・オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』(早川書房)
【※ 原作小説および映画化作品の、ネタを割りますので、未読未鑑賞の方はご注意ください。】
本書(日本語版)は、2020年3月の刊行で、「2021年本屋大賞 翻訳小説部門 第1位」「2021年版 このミステリーがすごい! 翻訳ミステリ部門第2位」などの結果を残した、きわめて評判がよく、ベストセラーにもなった作品である。
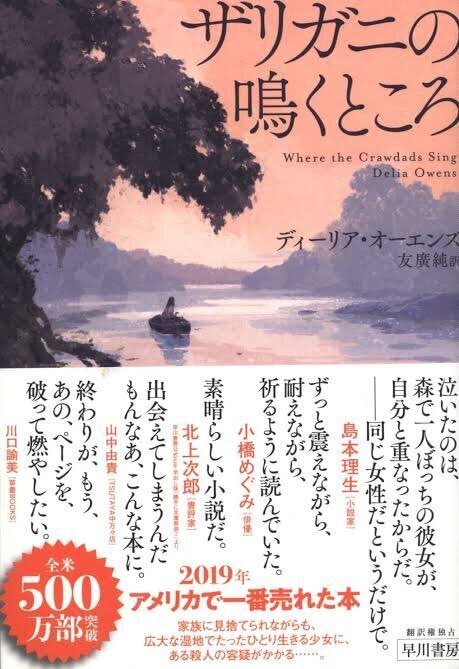
私も刊行当初に、その一風変わったタイトルと、アメリカでベストセラーになっている作品だという惹句に惹かれて、いったんは手に取ったのだが、結局、今日まで購読しなかった。
その理由は、本作が「感動的な作品」であろうことを、帯の推薦文が示唆していたからで、例えば次のようなものだ。
泣いたのは、森で一人ぼっちの彼女が、自分と重なったからだ。一一同じ女性というだけで。 島本理生氏(小説家)
ずっと震えながら、耐えながら、祈るように読んでいた。 小橋めぐみ氏(俳優)
「きっと、可哀想な少女をめぐる、事件がらみの話なんだろうな。だが、そういうのは苦手だ」と思ったのである。
そんな私が、なぜ今頃になって、同作を読もうと思ったのかというと、私が「note」でフォローさせていただいている、映画好きの「佐藤厚志」さんが、先ごろ公開された映画版『ザリガニの鳴くところ』についてのレビューをアップしたからである。
佐藤さんが「高評価をしていたら、映画を観ても良いかな」と思ったのが、きっかけだったのだ。
しかし、このレビューの冒頭部が、次のようになっていたので、後を読むことはやめてしまった。
『昨日『すずめの戸締まり』を見る前に、この映画を見た訳です。その感想です。文中でネタは割ってないと思いますが、もしかしたらカンの良い人だったら「あっ」と察してしまうおそれがあります。しかしミステリの感想やら批評を書くって難しいですね。』
いちおう私は、ミステリをずっと読んできた人間だから、読んだら「察して」しまうおそれがあると思った、と言うか、ここを読んだ段階で「叙述トリックもの、ではないのか?」と思ってしまったのだ。
しかし、だとしても、このまま事実関係をハッキリさせないというのは気持ち悪いし、単に「どう書かれて(描かれて)いるのか」その結果だけを知りたいわけでもない。やはり、作品として、そのあたりの「出来がどうなのか」というのが気になった。
で、私は、映画よりも小説の方にこだわりのあるタイプだから、やはり原作である小説を優先して読むことにし、原作小説を読んだ上で、それでも観る価値がありそうなら、映画も観ても良いと考えたのである。
また一昨日(2022年12月4日)は、佐藤さんがアップしておられた、セルゲイ・ロズニツァ監督の映画『ミスター・ランズベルギス』のレビューのコメント欄に、わざわざ次のようなコメントをしておいた。
ロズニツァ監督も、佐藤さんのレビューでその存在を知り、ハマった監督だったからである
『 年間読書人 2022年12月4日 20:56
まだ、このレビューは拝読しておりません。大阪での公開は、10日からだからです。
気になりますが、映画を観てから読ませていただきます。
なお、現在『ザリガニの鳴くところ』の原作を読み始めたところです。ご報告まで。』
そして、昨夜(本日)、原作小説『ザリガニの鳴くところ』を読み終えたので、さっそく佐藤さんの映画『ザリガニの鳴くところ』についてのレビューを一読し、そのコメント欄に次のようなコメントを書き込み、意見交換をした。
『 年間読書人 2022年12月6日 00:39
いま、原作の方を読み終わりました。
もう、映画の方は観ないでいいかなという感じになってます。
レビューを拝見すると、映画の方は、ミステリ的な仕掛けの方に力点を置いているようで、あの長い小説を映像化するのなら、正しい選択だと思います。
レビューの中で「メタフィクショナル」な作品だと書かれてましたが、その通りですね。ミステリとして見るなら、叙述トリックの作品だと言えます。
ただ、原作の感じからすると、それは著者の動物学的な思想から出た仕掛けで、ミステリ的なものからじゃない。
純粋にミステリとして見れば、やっぱりちょっと弱いと思いました。
近いうちに、原作のレビューを書く予定です。』
『 佐藤厚志 2022年12月6日 05:12
コメントありがとうございます。私は逆に原作読んだことがなくてこれから取り組んでみようかなくらいに考えていました。ミステリとしては弱いか、なるほどねー。
私が映画として評価した点なんですが、少し補足するつもりで書いてたら意外と長くなってしまったので笑、新しく記事に投稿しました。よければご笑覧いただければ幸いです。
https://note.com/atsushisato/n/n0406a29e35b8 』
そこで、上にご紹介していただいた、佐藤さんの「ネタバレあり」の映画『ザリガニの鳴くところ』評を読み、そのコメント欄で、さらに議論をすることになった。
『 年間読書人 2022年12月6日 08:06
レビュー、拝読しました。
まったくご指摘のとおりだと思います。
私はまだ原作を読んだだけで、映画の方は観ておりませんが、原作が主人公の、同情すべき生育状況を丹念に描くことで、主人公が犯人ではあり得ないと、読者に思わせるところを、映画では端的に主人公の見た目で補強したのだと思います。
ただ、私がミステリとして、正確に言えば、本格ミステリとして弱いと思うのは、こうした「叙述トリック」というのは、これが「小説」であり「現実=リアル」そのものではない、という読者とのお約束の上に立ってこそ成立するものだという点なんです。そして、それは映画だって同じで、要は「人間が意図的に作ったフィクション」でしかない、ということです。
だとすれば、こう書けば、こう理解すべき、という約束どおりに読者が読んだ場合、作者がその約束を裏切って「でも、現実はそうだとは限らない」とやるのは、アンフェアなんです。
この点で、この原作は、ラストの驚かせ方が、本格ミステリとしては、少々アンフェアだと感じました。
私も、原作についてレビューを書くつもりですが、もうあまり書くことが無くなりました(笑)。』
『 年間読書人 2022年12月6日 08:22
補足します。
原作の方でも、主人公が犯人である伏線は、張られています。
それが、動物学的な知見として「生きるためならオスを殺すことだってあるし、それは間違いではない」といった描写です。
それに、主人公は、人間社会のお約束に慣れないまま成長したというのもある。
ですが、主人公が実際にあの事件の犯人だとすると、犯行方法は保安官の推理したとおりだということにしかならないと思いますが、そこは、ちょっと主人公が案出したアリバイトリックとしては、偶然に頼りすぎていて、無理があると思います。
変装が行きも帰りも見破られないとか、名クォーターバックだったという若い男を、櫓から首尾よく突き落として、一発で殺すとか。
この物語のラストは、明らかに主人公が犯人だったと(※ 示唆)するものですが、こうした偶然性、あるいは現実のイレギュラー性をすべて認めるのなら、あのラストであっても、主人公が犯人ではなかった蓋然性だって、いくらでも考えられると思います。』
『 年間読書人 2022年12月6日 08:39
もうひとつ、これは例の「決定不可能性」というやつでしょう。
『 Wikipedia「決定可能性」
決定可能(けっていかのう、英: decidable)は、数理論理学または現代論理学において、論理式の集合のメンバーシップの決定をする実効的(effectiveな)方法が存在することを指す。決定可能性(けっていかのうせい、英: decidability)は、そのような属性を指す。命題論理のような形式体系は、論理的に妥当な論理式(または定理)の集合のメンバーシップを実効的に決定できるなら、決定可能である。ある決まった論理体系における理論(論理的帰結で閉じている論理式の集合)は、任意の論理式がその理論に含まれるか否かを決定する実効的方法があれば、決定可能である。』
集合のメンバーを限定しなければ、確定した答は出せない、ということであり、本格ミステリは、「現実的にメンバー(勘案すべき要素)が開かれていない」ことを前提了解としている、するしかないフィクションだと思います。』
『 佐藤厚志 2022年12月6日 09:32
コメントありがとうございます。ミステリしては弱い、と書かれた意味がわかりました。』
『 年間読書人 2022年12月6日 09:53
作者が意図したところは、貴兄のご指摘どおりなんだと思います。
ただ、ラストで主人公が犯人だったと明かして「読者(観客)の偏見」を批判するというのは、「お約束」やぶりで、アンフェアだと思うんですよね。「それは、約束が違う」という意味で。
ですから、ラストは「どちらとも考えられる」という、開かれたかたちにしていたなら、アンフェアではなかった。
でも、それだと「アンチ・ミステリ」というかたちになって、読者・観客には、ややわかりにくいものとなって、インパクトも弱まってしまう。
あのラストは、明らかに「読者・観客への一撃」を意図したものだと思うんですが、そこがちょっと安直で、弱いと感じました。
最近よく書くことなんですが「最後のどんでん返しで、びっくりさせれば良い」というものじゃないぜ、ってことです。
なお、これから書く、原作『ザリガニの鳴くところ』のレビューでは、また、貴兄のレビューや、ここでのやりとりを引用させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ツーと言えばカーと返ってくる議論は楽しいですね(笑)。』
『 佐藤厚志 2022年12月6日 10:16
安直で、弱い、か。これは厳しいですね。年間読書人さんのレビュー楽しみにしております。』
先日アップした、私のレビュー「『すずめの戸締まり』の社会心理学」と同様、本稿においても、佐藤さんとのやり取りの中で、私の考えたことの目ぼしいところは、ほぼ出そろっているのだが、佐藤さんのご指摘にある、私の『厳しい』評価が、どのあたりから出てきているのかということを中心に、以下で、補足的な議論をしたいと思う。
○ ○ ○
佐藤厚志さんの、映画『ザリガニの鳴くところ』に関する2本目のレビューにおいて、「ネタバレあり」で語られた「作者の意図」とは、私たち「原作小説の読者」や「映画の観客」が、無自覚に持っている「偏見」の告発だった、ということになるだろう。
佐藤さんは、そのあたりのことを、次のように指摘している。
『しかし……果たしてそこに偏見が一切無かったと言えるでしょうか? フラットな目線で接していたでしょうか。たとえば、この映画では犯行時間にカイアが何をしていたか、敢えて避けられて描かれません。つまり、カイアにとって都合のいい情報しか提示されていない訳です。カイアの人間性は疑うべくもないのですが、だからと言って、殺人を犯さないという理由にはならないし。検察が提出する状況証拠だけでは彼女の犯罪は立証できないが、彼女の無罪を証明する確実な証拠もまたありません。
逆に街の人々は醜悪で、俗物っぽく描かれてます。差別を行う側を、ある意味テンプレっぽい、古い価値観で凝り固まった人を配置することにも意味があると思っています。これも観客へある種の偏見を植え付けるための仕掛けなんですよね。不自然っちゃ不自然なんですよ。テイトや、あの商店の夫婦以外にもカイアを助けてくれた人はいたかもしれないし。まぁ大半はひどい連中なんでしょうけれどもw それもノースカロライナという保守的な土地を舞台にしているからその不自然さが緩和されていて(これもある意味ひどい偏見ですが…)、よく計算されてるなと思いました。人間って不思議なもので、そういうわかりやすいバカを見てるとつい「俺は断じてこういうバカじゃない、一緒にすんな、おれは公平だ」と無意識のうちに反駁する作用が働くものだと思っているんですが、それも結構おちいりがちな、危険な陥穽だと思ってます。』
原作小説の場合であれば、私たち読者は、主人公カイヤの同情すべき生育経歴を知らされ、それでも健気にも真っ直ぐに育った彼女に同情して、彼女を「善人」だと考えるだろう。そして、彼女を信じるようになる。つまり、基本的には「いくら自分を弄んだ男であっても、だからといって、その男を殺すような女性ではない」と考えてしまう。
映画の場合だと、そうした生育経歴の描写に割ける時間が限られているため、「無垢な善人」に見える役者を使うことで、観客にわかりやすく、彼女の「基本的な性格」を伝えることになったはずだ(それが映画の「お約束」である)。

だから、原作読者や映画鑑賞者が、カイヤを「善人」であり「殺人犯ではない」と考えるのは、「小説」や「映画」という「フィクション作品の構造(お約束)」上、やむを得ないことだと言えよう。
したがって、このままでは、本作は、原作小説にしろ映画版にしろ、鑑賞者との「お約束」を逆手にとった、いささか「アンフェア」な作品だ、ということになる。
いわゆる「本格ミステリ」の形式で書かれた(作られた)作品としては、「アンフェア」だということになってしまうのだ。
しかし、そこは作者の重々承知していて、カイヤが「単なる善人」ではない、「私たちが考えるような、わかりやすい善人ではない」という「描写」をちりばめて、ラストの「どんでん返し」への「伏線」を張っている。
それが、カイヤの「動物学的な世界観=生きるためならオスを殺すことだってあるし、それは間違いではない」である。

彼女のそうした「倫理観」からすれば、彼女をつけねらって暴行を加えようとするであろう男ならば、「誰も私を助けてはくれず、自分一人の力で生きていかねばならない」以上「殺害もやむを得ない」という理屈は、少なくとも彼女の中では、通るのである。
だからカイヤが、彼女をつけ狙う男(チェイス)を殺したのは「合理的な根拠のあること=推理可能なこと」だと言えるのだが、しかし、私が問題だというのは、作中で暗示されている、カイヤによる「アリバイトリック」が、かなり粗雑なものであり、幸運に助けられたからうまくいったものでしかないという点と、それがカイヤらしくない「計画的犯行」だという点である。
まず、カイヤの「事件発生時は、別の街に出かけていた」という「アリバイ=現場不在証明」に対し、検察・保安官側は、彼女がバスで町を出たのは事実だが、実は「変装」をした上でバスで戻ってきて、手際よく「計画殺人」を犯した後、またべつの変装をして、出かけた先の街へバスで戻った、という推理により、疑問に付す。
だが、このいささかご都合主義な「アリバイ破りの仮説」は、その「現実性の弱さと客観的証拠の不足」によって、裁判では採用されず、カイヤは無罪を勝ち取ることになる。

物語のラストでは、「しかし、真相は、保安官が考えたとおりの犯行だった」ということが示唆されるわけだが、だとすると、このラストのどんでん返しは、検察・保安官側の「ご都合主義的な無能さ」の故に成立したものでしかない、ことになってしまう。
そもそも、犯行方法も現実味に欠けて脆弱なら、その真相を突いた推理も客観的な裏付けを欠いた「単なる仮説」でしかなかったからこそ、「ラストのどんでん返し」が可能になった、ということだ。
だから、この「ラストのどんでん返し」は、読者の「心理」的にはショックなものではあっても、ミステリの「どんでん返し」としては、いささか「弱い」のである(例えばそれは、ジェームズ・ワン監督の映画『ソウ』における、冒頭の「死体」のようなものだ。ビックリはさせられるが「それはちょっと無理筋だ」という印象になってしまう)。

また、「恋愛小説」か「詩」か「聖書」か「自然誌や生物学」の本くらいしか読んでいないように描かれ、その意味で「本格ミステリ」とは無縁のように描かれていたはずの自然派のカイヤが、こんな「B級本格ミステリ」みたいな人工的なトリックをひねり出し、しかも実行にうつすというのは、いささか無理があるのではないだろうか。
例えば仮に「ある種の生物は、別の生物に擬態して、その成果を横取りする」といった描写がなされていたとしても、それをそのままカイヤが「人間社会」の中で流用したと考えるのは、カイヤの人柄や知的レベルからして、いささか無理があって、取って付けた感が拭えないのだ。
○ ○ ○
「本格ミステリ」というのは、もともと「自然」としての「現実」からは遠い、「人工的な論理のユートピア」という、特徴的な性格を持っている。ミステリが「読む機械」「読ませる機械」(トマ・ナルスジャック)などと言われるのも、そうした性格からであり、だからこそ「機械のパーツ」というのは、「生物」のようにグニャグニャと「変形変化」してはならない。

熱心な探偵小説ファンとして知られた、詩人のW・H・オーデンが、そのエッセイ「罪の牧師館」で書いたとおり、「(本格)ミステリ」における登場人物というのは、現実の人間とは違って「性格が変わってはいけない」。なぜなら、それでは「本格ミステリ」は、成立しないからである。
例えば、きわめて几帳面な性格である犯人は、その「几帳面な性格」において一貫していなければならない。なぜなら、そうでないと、「合理的な推理」が不可能になってしまうからだ。
それまで、精密機械のような犯行を行なっていた犯人が、ある時、ふと「いい加減な行動」をしたとする(魔が差した)。これは、現実の人間になら当たり前にあることなのだが、「本格ミステリ」の中に、そんな「不規則行動」を持ち込まれてしまうと、合理的に推理する(するしかない)「名探偵」や「読者」は、例えばそれを、「別の犯人の存在可能性」といった具合に、合理的に、誤って解釈してしまうのだ。
つまり、犯人が「行き当たりばったり」で犯行を行っているようなら、「合理的な推理によって真相に至る」なんてことは、原理的に不可能なので、「本格ミステリ」の登場人物たちは、「運命に支配されて行動する、ギリシャ悲劇の登場人物(例えば、オイディプス)」と同様に、一貫した「性格(合理性)」によって行動する存在でなければならず、したがって、現実の人間のように「途中で性格が変わる」などということがあってはならない。

したがって、いくらカイヤが「生き残りのための殺人」を正当化する論理の持ち主であることを示唆する描写(伏線)があったとしても、読者が、彼女から受け取る「全体的な印象」と、そうした「例外的な部分」に違和感や齟齬が生じるようなら、その描写は、「本格ミステリ」の「伏線」としては、「弱い=不十分」と言わざるを得ないのだ。
「本格ミステリ」の「叙述トリック」ものでは、しばしば「一人称の語り手」が犯人だったという作品があるけれど、この場合、犯人の「内面描写」は、おのずと限定的なものとなる。
そして、描写として制限されるのは、単に「思考内容」だけではなく「感性」的な部分も含むと考えるべきだし、だからこうした「一人称の語り手である犯人」というのは、多くの場合「性格のはっきりしない人物」あるいは「フラットな性格の人物」として描かれることが多い。
「口」ではどんなことを言ったとしても、内面描写においては「どうとでも取れる性格」の人物にしておかないと、最後のどんでん返しについて、読者に「彼(彼女)は、そんなことをする性格ではなかっただろう」という印象を持たせてしまう蓋然性が低くないからである。

つまり、少なくとも原作小説『ザリガニの鳴くところ』においては、主人公カイヤの性格描写や内面描写が「なされすぎている」のだ。
彼女が、動物学的な知見から「生きるためならオスを殺すことだってあるし、それは間違いではない」という「思想」を持っていたとしても、だからと言って、それを冷徹に実行に移すことが可能な人物だという印象を与える描写が、十分になされてはいなかった。だから、読者は、まんまと作者の思惑どおりに騙されたとしても、最後に示された真相を「認めたくない(それは違う)」ものだと感じたのである。
また、だからこそそこには、「ああ、まんまと騙されてしまった!」という、本格ミステリ的な「痛快さ」が無かったのだ。
これは、作者の張った「伏線」が、「心理面」においては不十分だったためであり、その意味で本作は、一定の「伏線」が張られていたのは事実だとしても、やはり「本格ミステリ」としては、少々「アンフェア」だった。「真相を、合理的に推理するための伏線が、十分に、張られていなかった」と、そう言えるのである。
○ ○ ○
無論、私も、本作における作者の意図である「差別を憎んでいるつもりの貴方がたにだって、自覚のない差別はあるのですよ」という、いささか「意地悪な指摘」には、むしろ深く共感している。
「何を、心優しい理解者ヅラしてやがる。そんなにご立派な人が、世の中の多くを占めるのなら、この世の中に、これほどの差別偏見が蔓延るなんてことはないんだよ!」と言いたい気持ちは、「無自覚なバカが大嫌い」で、その分「差別感情も強い私」には、とてもとてもよくわかるし、共感できるのだ。
だが、そうした「意地悪な感情」という欲求に身を任せてしまったがために、ラストの「どんでん返し」は、「本格ミステリ」としての「十分な合理性」を持つものではなくなり、結果として、少々「アンフェア」なものになってしまった。
この作品のラストが、「もしかすると、カイヤが犯人だったのかもしれない」という程度に止められ、「多様な解釈に開かれた」ものだったなら、こうした「無理」は生じなかっただろう(事実、多くの人が一度は疑った、ジャンピンが犯人だった可能性も否定できてはいない)。
だが、そうした「読者に思考を委ねる」かたちでのラストでは、「読者にひと泡吹かせてやりたい」という「作者自身の感情」を満足させられないし、それだけではなく、「決定不可能な現実」の「重み」に耐えられず、「わかりやすくショッキングな結末」(あるいは「わかりやすくありがちなハッピーエンド」)を求めるエンタメ読者には、そうした「決定不可能性を孕んだ作品」は、理解されにくくもあれば歓迎されにくいというのを、作者も承知していたために、ミステリ的にわかりやすくて、通俗的にインパクトのある「どんでん返し」を、作者は選択してしまったのではないだろうか。
しかしながら、その結果として本作は、「人間を描いた文学」としても中途半端なら、「本格ミステリ」としても中途半端な作品になってしまった。
私としては、たとえ「一般受け」しなかったとしても、そのどちらかに徹して作品の完成度を高めて欲しかったのだが、現実には、作者は、その「中間あたり」を選ぶことにより、この作品を「ベストセラー」にできたのだ、とも言えるだろう。
「小説」であれ「差別問題」であれ、徹底的に突き詰めてしまうと、多くの人は、ついてこれなくなる。
むしろ、適当に「抜けたところ=抜け道」のある「ゆるい作品」の方が「世間ウケする」という「現実」を、この作品は体現していたのではないだろうか。
だが、作者がそれを、十分自覚的に選択したとは、私は見ていないのである。
(2022年12月6日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
