
北村紗衣vs笠井潔 : 『情況 2022年春号【特集】キャンセルカルチャー』
雑誌評:『情況 2022年春号【特集】キャンセルカルチャー』(情況出版)
この3ヶ月来「北村紗衣批判」を行なっている私なのだが、もともとの専門は「笠井潔批判」であり、「笠井潔葬送派」を名乗って、すでに30年近くになると思う。
「笠井潔葬送派」とは、笠井潔が昔、小阪修平、長崎浩などと「マルクス葬送派」と名乗っていたからだ、と書くと正確ではない。私は長らくそのように誤解していたのだが、正確には笠井らの座談会記事に対して、掲載誌編集部が「マルクスを葬送する」という見出しタイトルを付けただけであって、笠井ら自身が「マルクス葬送派」を名乗ったことはない、ということらしい。
まあ、そのあたりの細かい事情は別にして、笠井らが「マルクス(思想)を葬送する」という目標を掲げていたことは事実だし、笠井潔の盟友であった戸田徹に『マルクス葬送』という著作があったのも事実だから、「他称」としては間違いではない、ということになるだろう。よって笠井潔らを「マルクス葬送派」と呼ぶこと自体は、間違いではないのである。
で、そんな「マルクス葬送派」の一人で、その代表的な理論家である笠井潔を批判するのに、私は皮肉を込めて「笠井潔葬送派」を「自称」したという次第だ。

では、なんで私が笠井潔を「葬送」したいと思うようになったのかというと、それはもともと私が、笠井潔の大ファンだったからだ。可愛さ余って憎さ百倍、というやつである。
私と笠井潔の出会いは、笠井潔の作家デビュー作であるミステリ小説『バイバイ、エンジェル』(1979年)である。一一と言っても、読んだのはその文庫版でであり「1984年」ことだ。
この『バイバイ、エンジェル』は、一生を左右するほどの衝撃を私に与え、その年のうちに、この『バイバイ、エンジェル』を含む「矢吹駆シリーズ」の既刊3冊(『サマー・アポカリプス』『薔薇の女』)を読み、すっかり笠井潔ファンになってしまった。

しかし、私がこの「矢吹駆初期三部作」を読んだ頃、笠井潔はすでに「本格ミステリ」を書かなくなっていた。
その頃の笠井は、『ヴァンパイヤー戦争』や『巨人伝説』『サイキック戦争』といった「コムレ・サーガ」と総称される「伝奇アクション」小説の方に注力していたのだ。
この頃、笠井のデビュー作『バイバイ、エンジェル』の版元である角川書店では、二代目社長・角川春樹の肝入りで、文庫サイズの小説誌『小説王』などが刊行され、そこで荒俣宏の『帝都物語』の連載が始まるなど、「伝奇小説」ブームが巻き起こっていた。
それで、もともとオカルト(神秘主義思想)にも詳しく「伝奇小説」も好きだった笠井潔は、手間がかかる割には売れない「本格ミステリ」の「矢吹駆シリーズ」はいったん横において、『ヴァンパイヤー戦争』などの伝奇アクションの方に注力し、実際、こちら方がよく売れていたのである。
だが、私は「アクションもの」には興味がなかったので、笠井潔の伝奇アクション小説には、当初は手をつけなかった。
殊に「コムレ・サーガ」の中心となる『ヴァンパイヤー戦争』が10巻を超える長編であり、それでなくとも「新本格ミステリ」ブームで、次から次へと気になる本格ミステリの新刊が出ていたから、そっちを読むので精一杯だったためである。
そして、前記の「矢吹駆初期三部作」以降にひさしぶりに読んだ笠井のミステリ小説が、1988年に書き下ろしで刊行された『復讐の白き荒野』であった。
これはたしか、新潮社の書き下ろしミステリレーベルからの刊行で、前年1987年には綾辻行人のデビュー作である『十角館の殺人』が講談社ノベルスから刊行され、それに続いて、同じ講談社ノベルスや東京創元社のレーベル「鮎川哲也と13の謎」などから、続々と新人ミステリ作家が登場して「新本格ミステリ」ブームの熱狂が巻き起こり始めていたためでもあろう。つまり、新潮社はそうしたミステリブームに便乗しようと、すでにデビューしていたミステリの作家をかき集めて、単行本の書き下ろしシリーズを刊行し始めたのだが、この叢書で、笠井潔も、ひさしぶりにミステリ作品を書いたのだ。
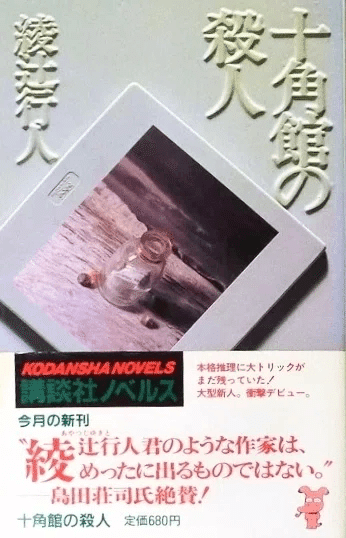
ところが、この『復讐の白き荒野』は、私が期待したような作品ではなかった。「矢吹駆シリーズ」のような「本格ミステリ」ではなく、「右翼思想」を扱った冒険小説だったのである。
私個人は興味がなかったのだが、これはたぶん、当時、「新本格ミステリ」ブームに先んじて、「冒険小説ブーム」が起こっていたためなのであろう。笠井潔はそちらへの展開も視野に入れて、『復讐の白き荒野』を書いたのではないだろうか。
だが、そうした笠井潔の思惑にもかかわらず、私の場合は、冒険小説そのものに興味がなかったので、ミステリ作品として大変な期待を寄せて読んだ同作は、まったくの期待はずれであった。
だがまた、これは「ジャンル違い」というということでもあったから、私としては「矢吹駆シリーズの続きを書いてくれないかな」と、まだまだそんなファンとしての期待を、笠井に寄せていたのである。
さて、すでにその頃の私は、同世代の「新本格ミステリ作家」による「新本格ミステリブーム」に完全に乗って、ミステリファンとしての同人活動を活発に行なっていた(綾辻行人が2つ上、法月綸太郎が2つ下)。
今の執筆ペースからも想像できるだろうが、当時の若い私は、いま以上の馬力があったから、一つの同人サークルの属するだけでは、ぞの執筆意欲を満たすことができず、趣味の合いそうなところには片っ端から頭を突っ込んでいた。
その代表的なところが、「SRの会」「怪の会」「畸人郷」などである。「エラリー・クイーン・ファンクラブ」の会長である飯城勇三氏とは、「SRの会」で知り合っていたのだが、当時はまだクイーンを読んではいなかったので、そちらには入らなかった。
そんなわけで、当時の私は、派手に同人活動をやっていた。
とにかく会誌用の原稿をたくさん書く。しかもそれの多くが、今と同様、論争的なものであり、例えば、「SRの会」の会誌「SRマンスリー」などでは、親ほど年齢の離れた先輩会員たちにも、遠慮なくがんがん噛みついていった。例会などで面識のある先輩会員にだ。
また、「怪の会」の会誌「地下室」では、新本格ミステリに否定的であった中心メンバーの、長谷部史親や縄田一男らに噛みついた。
したがって、今のような「ネット上での、匿名での批判」というようなことではない。
「公務員」という職業柄、何かとうるさい職場には気づかれないように、固定のハンドルネーム(アレクセイ)やペンネーム(田中幸一)を使ってはいたが、批判対象に対しては、私がどこの誰であるかを隠そうという気持ちなど、さらさらなかった。だから、場合によっては、直接対面の場でも批判することを辞さなかったのだ。
だが、今思えば、私は当時から、相手に意見ではなく、その社会的な立場を狙った、「キャンセル」の危険性には、人一倍配意していたということでもあるし、私に批判された面識のある人たちも、私の本名を晒そうなどというようなアンフェアなことは、決してしなかった。やって良いことと悪いことを、人としての恥を、知っていたのである。理論的な対立は、あくまでもその中身において、戦わせるべきだという倫理が守られていたのだ。
そんなわけで、とにかく私は、会誌用原稿を次から次へと量産していたのだが、これがなかなか会誌に掲載されない。
なぜなら、当時の同人会誌は、ページ数が少なく、また良くて「隔月刊」だったからだ。「SRマンスリー」などは「年3回」だったから、私が批判論文を書いて、それが掲載された号が出るのが数ヶ月後。それを読んだ先方が反論を書いて、それが掲載されるのが、早くてさらにその次の号の4ヶ月後。それを読んで、私は数日で再反論原稿を書くのだが、その再反論原稿が掲載されるのは、早くて、さらに約4ヶ月後の次の号といった調子。しかしそれも、特集記事などの都合によって次号回しなどにされると、掲載されるのは、投稿から8ヶ月後なったりするから、それへの相手の反論を読めるのは、早くて1年後というようなペースだったのだ。
このあたりが、書いた瞬間に反論が返ってくる、今のTwitter(現「X」)などとは、良くも悪くも大きく違っていたのである。
そんなわけで当時は、会誌上で論争をするとなると、数年単位を覚悟しなければならなかず、「白ヤギさんと黒ヤギさんの論争」めいたノンビリしたものだった。
だが、もともとせっかちな私は、そんなことでは到底満足できないから、あちこちの同人サークルに入って、原稿を書きまくったのである。しかも、論争的で個性的なものをだ。
また、そうして知り合った友人などの伝手で「関西大学ミステリ連合」略して「関ミス連」の年1回の例大会にも参加するようになり、綾辻行人ら「京都大学ミステリ研究会」出身の新人作家などとも面識ができ、そういう作家には、自分が原稿が載った同人誌を郵送献呈するなどした。一一つまり、当時から私は、目立つミステリファンだったのだ。
で、そんなおり、当時「SRマンスリー」の関東号の編集をしていた、ミステリ研究家の山前譲さんから電話があり「こないだ君が書いた、笠井潔の赤川次郎論についての文章を笠井さんが読んで、よかったら会いたいというような連絡があった」と知らせてくれた。もちろん私は大喜びで、友人数名と共に八ヶ岳の笠井潔に会いに行ったのである。
それが「1989年の8月」のことだから、その時点で読んでいた笠井潔の著作は、「矢吹駆初期三部作」と『復讐の白き荒野』の4冊だけということになる。
この時のインタビューを、翌年(1990年)3月発行の同人誌『群探』(探偵趣味俱楽部)14号に「アンチ・ミステリの巨人 笠井潔さんに聞く」として掲載し、その内容は、もっぱら「矢吹駆シリーズは、今後どうなるのか?」ということだったのだが、それとは別に、憧れの人に直接会うことで、触発される部分は大きかった。

私が笠井潔に会ったこの当時は、まだ笠井潔は「新本格ブーム」の渦中には入ってきていなかったので、若いミステリマニアの間では、笠井潔は「少し前の人」という感じだった。
さすがに、綾辻行人らの「本格ミステリ」マニアにはリスペクトされてはいたものの、多くのミステリファンの間では、まだまだマイナーな存在だったのだ。
だから、後年、東京創元社が主催した公募ミステリ評論賞である「〈創元推理〉評論賞」で、笠井潔、巽昌章、法月綸太郎が選考委員を務めることになり、これに対し私が、その第1回には、当時、笠井潔を中心として盛り上がっていた「ミステリ評論」ブームについての批判論文を投じ、さらに第2回には、もろに「笠井潔批判」を投じた際には、笠井潔は、私の論文を無視したが、法月綸太郎は、その選評で、
『田中幸一「地獄は地獄で洗え…… 一一笠井潔批判」。これを読んだ笠井委員は怒り心頭に発して、破門を言い渡したそうである。むべなるかな。例によって、私も刺身のツマのごとく、批判の俎上に載せられているので、公の選評というには微妙なところだが、作家論としてみれば、あまりにもナイーブで、楽天的にすぎる。太刀筋は決して悪くないのだから、肉を切らせて骨を断つような筆法を身に付けてはどうか。』
(『創元推理 1996秋号』P19)
と書いて、私のことを冷やかした。
つまり、法月綸太郎の言う『笠井委員は怒り心頭に発して、破門を言い渡したそうである。』というのは、私が、法月綸太郎などよりも、ずっと古い笠井潔ファンであることを指して言っているのだが、私にすれば、私は「破門」が可能な「弟子」などではなく、また、後から「笠井潔の子分」になった法月などとも違い、純粋なファンであるという、確固たる意識があった。「ファンであり、期待するからこそ批判もする」という意識があったのだ。
だから、法月のこの皮肉に対しては、以降「私は、笠井潔のファンではあったが、弟子になったことは一度もないし、ましてや法月綸太郎のように子分になどなったことはない」とやり返すことを、常としたのである。
この「第2回〈創元推理〉評論賞」の「選評」が掲載された『創元推理』誌が「1996秋号」ということからもわかるとおり、私が笠井潔と初めて面談した「1989年8月」の段階では、まだ「新本格ブーム」とは繋がっていなかった笠井潔は、その後、急速に「新本格ムーブメント」の中に入ってきて、「本格ミステリ作家」の先輩として、また年長者であり先鋭な理論家として、「新本格ブーム」を主導するようになっていった。
「〈創元推理〉評論賞」が設立されたのも、そもそも笠井潔が、ひとつのムーブメントを確固たるものとしての、文芸ジャンルとその歴史に位置づけるためには、それを支える理論的な枠組みが必要だ、というような、いかにも「全共闘セクトのイデオローグ」だった人らしい主張がなされてのことで、当時の「新本格ミステリムーブメント」を支えていた出版社のひとつ東京創元社に、笠井潔が働きかけてのことであった。

つまり、私が初めて会った当時には、笠井潔は「新本格ムーブメント」とは関わりのない「伝説の人」だったのだが、その後、急速に「新本格ムーブメント」の中に入ってきて、すぐにその「理論的なリーダー」の位置に座ってしまったのである。
ただ、そこまでは良いのだが、私が不満を持つようになったのは、笠井潔の「新本格ミステリ」論が、「新本格ミステリ擁護」を超えて、「新本格ミステリこそが、現代文学の最前線だ」というような、露骨に手前味噌な「権威づけ」の様相を強めていったからである。
これは、この当時、世間的な認知を得るための権威としての直木賞が「冒険小説やハードボイルドでは取れても、人間が書けていないと見当違いの理由で、本格ミステリでは受賞できない」という苛立ちが、本格ミステリ作家たちの側にあったからではあろう。だから、そのあたりで、笠井潔は、理論的に「本格ミステリ」の正当な位置づけを勝ち取ろうと、露骨に党派的な評論を書いたのだが、それが私には不満だった。ケチな身内贔屓としか思えなかったのだ。
しかし、笠井潔の政治思想関係の著作を読んだ今となっては、笠井がこのような業界政治的で「党派(セクト)的な文章」を書くのは、それまでどおりの「いつものこと」でしかなかったとも言えるのだが、当時の私は、まだ笠井の「思想関連書」を読んではいなかったし、なにより「矢吹駆シリーズ」の熱心なファンとして、笠井潔を理想化し、偶像化してさえいたので、笠井の「党派的な言説や振る舞い」は、私を深く失望させ、苛立たせるものだったのだ。
つまり、笠井潔が「新本格ムーブメント」に入ってきた当初は、「矢吹駆シリーズ」の新作が読めるかもしれないと単純に喜んだ私も、その後の笠井による「政治的な動き」には違和感を感じて、徐々に苛立ちを深めるようになっていった。私は、笠井潔に「政治屋の辣腕」ぶりではなく、「フェアプレイ精神の高潔さ」を期待していたのである。
だから、「〈創元推理〉評論賞」第1回では「笠井潔批判」を投じず、笠井の主導した、当時の「ミステリ批評のあり方」に対する批判論文を投じた。「軌道修正して欲しい」というファンとしての未練が、まだ残っていたためだ。
だが、どうやら、そうした間接的な批判ではどうにもならないと覚悟して、第2回には、本丸である笠井潔を直接批判する評論文を投じたのである。そのタイトル「地獄は地獄で洗え」は、吉本隆明に由来するもので、要は、「馴れ合いではダメだ」という趣旨のものであった。
こうした公募評論賞で、その選考委員長とも呼ぶべき人物を直接批判する論文を投じた者など、今も昔も、そうはいないのではないだろうか。
ともあれ、以上のような経緯があって、私は腹を括って「笠井潔葬送派」に転じたのである。
単に「軌道修正を求める批判」では通じないと覚悟して、笠井潔を葬送するつもりで、批判を展開することに決め、そのあとは、批判のための必要性から、笠井潔の理論的著作もほとんど読んできたのである。
私が現在、思想だの哲学だのの本も読んでいるのは、そのきっかけとして、そのあたりの知識がないことには、新左翼セクトの理論家であった笠井潔を批判することは不可能だったからなのだ。
○ ○ ○
だが、そんな笠井潔も、今や76歳で、作家としては第一線からは退いた、半ば「過去の人」と化している。
その後「矢吹駆シリーズ」は当初の予定である全10作の雑誌連載を終えているはずで、あとはそれらに加筆修正を加えて、単行本にするという段取りのはずだが、これが、もはや旬を過ぎた作物として、なかなか刊行されなくなっている。
もともと「矢吹駆シリーズ」は、笠井潔の看板シリーズだったから、雑誌連載をしたあと、単行本化する際には、徹底的に手を加えて、雑誌掲載時の数倍の長さになることも珍しくない。
「矢吹駆初期三部作」のあと、ひさびさの第4作目の『哲学者の密室』が雑誌連載された際、私は大喜びでその雑誌連載を読んだのだが、その出来はイマイチであった。
しかしながら、この『哲学者の密室』が単行本化された際には、なんと3倍の長さになっており、それはそれなりに重厚かつ面白くはなっていたものの、私はこうした書き方が笠井潔のいつもの書き方なのだと知って、以降は、雑誌連載ではいっさい読まなくなった。
ともあれ、「矢吹駆シリーズ」は、雑誌連載を終えても、なかなか単行本化されないというのは、もはや笠井潔読者の常識と化していたので、私は、その、いつで出るのかわからない単行本を気長に待つ、というスタンスに変わっていった。じっくり時間をかけて良い作品を書いてほしいと、そう考えたのだ。
だが、そうした「忘れた頃に刊行される、矢吹駆シリーズの新作」も、何冊か読むうちに「これはもうダメだ」と思うようになった。
たしかに「手が込んでいて凝っている」のはわかるのだけれども、そもそも驚きや新鮮さがない。ただ、手間が掛かり、凝っているだけなのだ。
だからもう、「矢吹駆シリーズ」にさえ見切りをつけた私に残っていたのは、ただ「笠井潔葬送」ということだけだったのである。笠井潔に引導を渡すのは、誰よりも古く、誰よりも熱心なファンだった私以外にはないと、そのように考えるようになっていったのだ。
そして、私の気の長い「笠井潔批判」の影響も多少はあったのかどうか、一時は「新本格ミステリ界」の理論的支柱であり「ラスボス」的な存在にまでなっていた笠井潔が、その驕りから、2005〜2006年の『容疑者Xの献身』(是非)論争(=「本格(ミステリか否か)」論争)の結果として、「本格ミステリ界」から、ほとんど総スカンを喰らうかたちで去ることになった。
そして、それ以降、法月綸太郎などは、ほとんど笠井潔については言及しなくなっている。
要は、ミステリ業界の風向きを見て「親分を見捨てた」のが、笠井潔の元「子分」である法月綸太郎なのだ。
だから、そんな不実な子分に比べれば、私はいつまでも「愛を持って批判する笠井潔ファン」であり続けたのであり、その意味での「笠井潔葬送派」だったのである。
したがって、笠井潔がほとんど「過去の人」となった今では、笠井潔批判も、かつてほど熱心ではなく、たまに笠井潔を論じても「小説はつまらないけど、理論書はやはりスゴイ。どこまで信用できるかは別にして、その白を黒とでも言いくるめてしまえる博識と説得力は並外れており、やはり笠井潔は非凡な理論家だ」というような、褒めているのか腐しているのかわからないような書き方になっていることがわかるだろう。
だから、今回の『情況 2022年春号【特集】キャンセルカルチャー』の巻頭に、笠井潔のインタビューが載っていると知って、「さすがは笠井潔」と思ったし、その内容にも素直に期待したのだが、その期待は、十分に応えられていたのである。
○ ○ ○
さて、ここでやっと「北村紗衣」である。
私が、北村紗衣とかかわりを持つようになったのは、ほんのここ3ヶ月のことに過ぎない。
しかもそれは、私の方から北村紗衣に関わったのではなく、言うなれば、北村紗衣の方から私に難癖をつけてきて「誹謗中傷」をしたので、それへの「お返し」をするというかたちで、関係ができてしまったのである。
それまでは、私は「北村紗衣」なんて小娘は、その存在さえ知らなかったのだ。
だが、「北村紗衣批判」を始めて、北村紗衣の「論争によらず、論敵の存在を排除する」という手法が、「キャンセルカルチャー」なるものに由来するというのを知り、北村紗衣の著作をひと通り読んだあとは、
(1)前嶋和弘『キャンセルカルチャー アメリカ、貶めあう社会』
(2)アレックス・ガーランド監督(映画)『シビル・ウォー アメリカ最後の日』
と「キャンセルカルチャー」の本場であるアメリカに関する本を読み、映画を鑑賞し、さらに、「キャンセルカルチャー」と関連するらしい「トランスジェンダリズム(性自認至上主義)」問題に関わる、
(3)アビゲイル・シュライヤー『トランシジェンダーになりたい少女たち』
(4)斉藤佳苗『LGBT問題を考える 基礎知識から海外情勢まで』
(5)キャスリン・ストック『マテリアル・ガールズ フェミニズムにとって現実とは何か』
(7)女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会編『LGBT異論 キャンセル・カルチャー、トランスジェンダー論争、巨大利権の行方』
と読んできたので、『情況』誌が「2022年」に「キャンセルカルチャー特集」を組んでいたことも知り、しかもそれには笠井潔が登場しているのを知ったので、このバックナンバーを取り寄せて読むことにもなったのである。
○ ○ ○

さて、『情況 2022年春号【特集】キャンセルカルチャー』だが、これには、同誌編集部員による緒言につづく「笠井潔インタビュー」をはじめとして、14本の特集記事が収録されている。
だが、読むに値する水準に達しているのは、「笠井潔インタビュー」と、北村紗衣による民事裁判に敗訴した山内雁琳の、まだ係争中の頃に書かれた記事の、2本だけであると、そう言っても過言ではないだろう。
全体に短い記事が多く、それなりに読めるものも他にないではないが、かなり酷いものもある。
その「酷いもの」とは、主に「キャンセル」を行った側の記事であり、要は、それを批判されて「言い訳」をしている側の文章なのだ。
だから、以下では、「笠井潔インタビュー」を中心に紹介し、残りについては簡単に触れることで済ませたいと思う。
まずは、本号特集記事の「目次」を示しておこう(ヘッドナンバーは、こちらで振った)。
(01)特集への緒言「キャンセル・カルチャー」試論 (塩野谷恭輔)
(02)インタビュー笠井 潔 キャンセルカルチャーをめぐって (笠井潔)
(03)東京音頭の波及力とキャンセル文化 (前田和男)
(04)絓秀実 第四波を犬きする (絓秀実)
(05)キャンセルカルチャーは存在しない (藤崎剛人)
(06)キャンセルカルチャーとは何か一一その現象と本質 (山内雁琳)
(07)「妄想の共同体」としてのネット空間 (嶋理人)
(08)云ってることは新左翼だが、やってることがイジメ (外山恒一)
(09)SNSと、ナラティヴの戦争 (藤田直哉)
(10)加速するジェンダー系炎上とポリティカル・コレクトネスの現在 (柴田英里)
(11)「国体」にキャンセルされた歴史学者たち (高井ホアン)
(12)窮地に立つ「京大的文化」 (ホリィ・セン)
(13)あらかじめキャンセルされた文化 謎の「社員旅行」に迫る (山本華織・松山孝法)
(14)「私たちは清された展2022」潜入ルポ (情況編集部)
まず(01)の、塩野谷恭輔による、特集への緒言「「キャンセル・カルチャー」試論」だが、その主張するところは、次に示す最後の一節に明らかであり、大いに同意のできるところである。
『 念のため最後に付言しておくが、筆者は現在「キャンセル・カルチャー」運動に携わっているすべての論者がこのような退廃に陥っていると考えているわけではない。しかし、このような緊張感を失った主張は、思想性も必要性も欠いた無効な代物にしかなりえない。以上は、筆者を拘束している最低限の倫理である。』(P10〜11)
さて、いよいよ本命である(02)の「インタビュー笠井 潔 キャンセルカルチャーをめぐって」である。
引用文は、編集部の問いに答えた「笠井潔の言葉」だ。
(02−01)『MeToo運動に由来する、不正義であると見做された発言、行為、人物のキャンセルは、「抹消」の意味ですね。もう一つ、Black Lives Matterの中で南軍の将軍やコロンブスの像が破壊される事件がありましたが、これもキャンセルカルチャーだと言われます。この場合のキャンセルは、「解除」だと思います。同じキャンセルという言葉が使われていても、意味、含意が違っている。歴史の解除、正史としての歴史の固定化を解除していくのなら僕は支持すると、前回のインタビューで言いました。しかし発言や行為にとどまらず人物そのものをキャンセル、抹消するということに関しては、具体的な事例に則して判断しなければならない。とりわけインターネットでは、「娯楽としてのキャンセル」や「ルサンチマンの発露としてのキャンセル」と思われるケースもしばしば見受けられますから。
最初にいっておきたいのは、これはPC(※ ポリティカル・コレクトネス)批判の場合も同じですが、抹消としてのキャンセルカルチャーへの批判の前提は、差別や抑圧それ自体への批判です。被害当事者からのセクハラ、パワハラの告発、糾弾は当然のことながら支持する。その上で、差別批判として有効でないから、場合によっては差別の隠蔽や温存に通じる(※ つまり、差別意識の隠蔽のための「大義名分」として利用される場合がある)から、ある種のPCは批判されなければならない。簡単に言うと、前もって差別批判を積極的に行っている者にだけPCを批判する権利がある。差別批判抜きのPC批判の本音は、差別を肯定し固定化すること(※ 自分に都合の良い党派的な価値観を保守し絶対化すること)ですが、抹消としてのキャンセルカルチャー批判についても、同じことがいえます。』
(P12〜13、「※」は引用者補足)
まず、冒頭の整理部分だが、相変わらず明晰な整理である。
「MeToo運動」に由来するキャンセルを「抹消」、「Black Lives Matterの中で南軍の将軍やコロンブスの像が破壊される事件」などを「解除」だとして、同じように「キャンセル」という言葉で語られる事象を区別してみせる。
この点について、私はまったく同感で、私の場合も、北村紗衣による呉座勇一や山内雁琳に対する「抹消」、つまり、地位を奪い、その発言権を奪うという意味での「キャンセル」は認められないと、何度もそのことを論ってきたが、「Black Lives Matterの中で南軍の将軍やコロンブスの像が破壊される事件」などについては、それまでの一面的かつ、その意味での誤りを含んだ「歴史的認識」というものは、当然、修正されなければならないものとし、その上で、その「手法」が「暴力的で一方的なもの」ではなく、「議論による説得」を基本とする漸進的なものでなければならないとした。なぜなら、「新しい認識」もまた誤っている蓋然性は十分にあるからで、優勢な者によって「誤りを誤りにすげ替える」ような「歴史修正」であってはならないと、そう考えたからである。
さて、上の引用文(02−01)で、「北村紗衣」と直接関係するのは、後半部分の、次の言葉だ。
『前もって差別批判を積極的に行っている者にだけPCを批判する権利がある。』
つまり、自身の「属性」に関わる、その属性への差別を批判する者は、それ以前に「それ以外の各種の差別一般」についても、同様に批判していなければならない、ということだ。
例えば、「女性差別(性差別)」に反対する女性は、それ以前に「それ以外の各種の差別一般」を問題視して、そうした別種の差別者をも批判していなければならない。
それをやらないで来て、つまりそうした「差別一般」については「黙認あるいは加担」してきたくせに、自分の「属性」に関わる「差別」についてだけは反対する、というのは、結局のところ、「差別」に反対しているのではなく、自身の「党派的な利益」を守ろうとしているだけだ、ということになるためだ。
それは、「差別反対」という「美名=正義」も下に行われる、「党派的権益」の確保を目指すものでしかない、ということである。
だからこそ私は、北村紗衣の著作『お砂糖とスパイスと爆発的な何か 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門』(書肆侃侃房)のレビューにおいて、次のように書いたのだ。
『ここで考えなくてはならないのは、(※ 北村紗衣が言うところの)世の中の「(思考の)檻」とは、北村紗衣が入れられていたものだけでもなければ、「女性」だけが入れられるものばかりではない、という当たり前の事実である。
例えば、「部落差別問題」「在日差別問題」「米軍基地の集中という沖縄差別問題」などは、(※ 北村紗衣の語る)「フェミニズム」でも「文学」でも、解決解放することはできない。
つまり、北村紗衣が『私を檻から出してくれたのは、フェミニズムと文学でした。』と、いかにももっともらしく屈託なく書けるのは、「女としての被害者である私」のことしか考えていないからに過ぎない。
「差別されている人」「弱者」のことを本気で考えるのなら、問題は「男女の性役割(ジェンダー)の問題」だけで済まないのは、わかりきった話なのだ。
だが、「自分のことしか考えていない」のであれば、手に入れた武器としての「フェミニズム」を振り回してさえいれば良いだけだ。
自分の対決すべき現実を、その武器の射程範囲内に限っておけば、そのかぎりにおいては無敵でもあり得よう。』
したがって、笠井潔の言う『前もって差別批判を積極的に行っている者にだけPCを批判する権利がある。』という観点からすれば、北村紗衣には、「女性差別」者を批判する資格はない、ということである。他ならぬ北村紗衣自身も、別のところでは差別主義者だからだ。
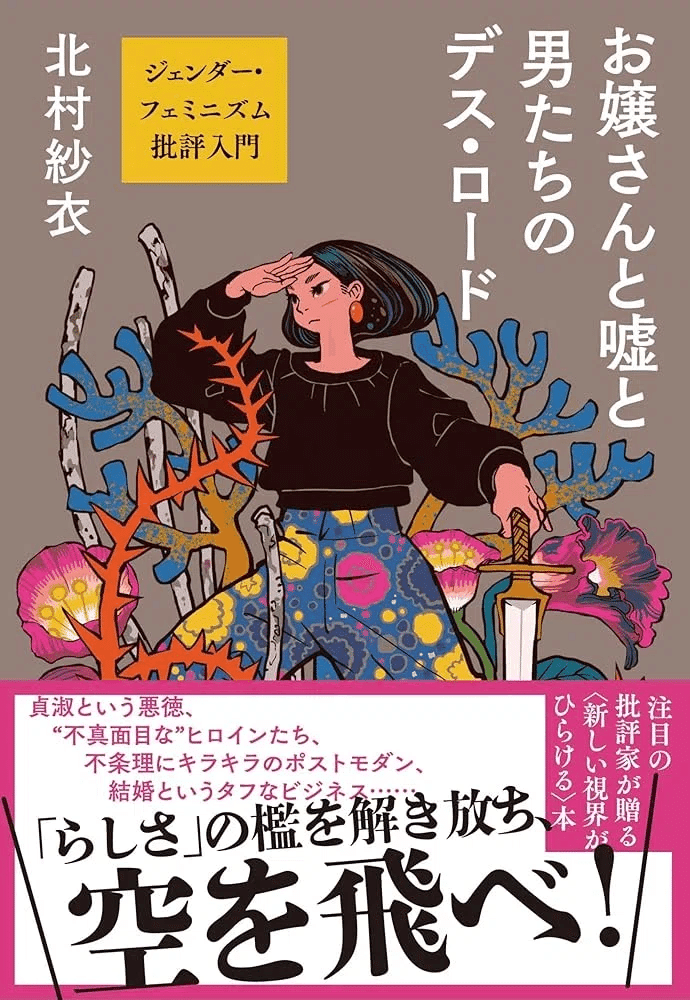
実際、北村紗衣の著作を読めばわかることだが、「フェミニスト」として「被害者である女性の権利」ばかりを主張して、それ以外の「差別」については「完全黙秘」である。
北村紗衣も日本人であり、ましてや「大学教授」なのであれば、日本における「部落差別」や「在日差別」や「沖縄米軍基地問題」くらいは知っているはずなのだ。
なのにどうして、北村紗衣は、それらには一切触れようとはせず、もっぱら「女性差別」問題にしか触れないのかと言えば、それはそれらの他の差別に触れると、「女性差別」問題の重要性が「相対化」されて霞むことになり、それでは「損だ」という計算が働いているからである。
北村紗衣が、正義漢ぶって「女性差別反対」を叫んだところで、「部落差別」や「在日差別」や「沖縄米軍基地問題」について沈黙し、そうした「差別」については実質的に黙認することで「不当な利益」を得ている、ということに広く気づかれてしまうと、いかにも不都合であろう。
つまり、北村紗衣が、いくら「女性差別反対」と声高に主張したところで、当たり前に問題意識のある人から、
「その意見は、至極もっともだ。しかし、そのようにして差別反対を叫んで正義感づらをしているお前自身が、部落差別や在日差別や沖縄差別を、一人の日本人として黙認し、不当な利益を享受しているのだとしたら、そもそもお前には、差別を批判する資格など無いではないか」
と、そう批判されれば、反論に窮するしかないからである。
だから、北村紗衣は、そうした「各種の差別の歴史」に「無知な若者」を、もっぱらターゲットにしている。
そのうえで、話題を「女性差別」あるいは「フェミニズム」に限定することによって、他の「差別問題」に気づかせないようにしているのだ。
年齢相応に「無知な若者」たちは、北村紗衣に「女性差別」についての問題意識だけを植えつけられ、それが「フェミニズム」だと教えられることで、なにやら「意識の高い人間」になったかのような勘違いをする。
実際には、ほとんど何も知らないのに、ひとつの「思想」を教えられると、それで世の中の「すべての問題」が切れる(理解できる)かのように思い込んでしまうのだ。かつての、マルクス主義を信奉した、「左翼学生」たちのように。
だから私は、先のレビューの中で次のように指摘してもいたのだ。
『つまり、北村紗衣は、「フェミニズムと文学」で「女性差別の檻」から出たつもりなのかも知れないが、実は、その「小さな檻」は、「自らのエゴと偏見」というもっと「大きな檻」の中に収まっていたのであり、北村紗衣は、その「大きな檻」からは未だ出ていないどころか、その中にいることにも気づかず、その中に安住したままなのである。
だから、「女性への差別」にはうるさくても、「他の差別」には、とんと興味がない。
というか、他の「差別問題」にまで視野を広げてしまうと、自分の武器である「フェミニスト批評」が役に立たないというのを知っているから、その「既得権益」を手放さないためにも、自分の守備範囲を限定して、その外にいる人たちのことは、見殺しにすることにしたのであろう。
北村紗衣が、本書で語っているのは、いかにも古くさい「紋切り型のフェミニズム批評」だけだと、そう言ってよく、それ以外は、せいぜい「クィア批評」の名が挙がるだけ。
しかも、その「クィア批評」たるや「腐女子的な視点で作品を見れば、男同士のあれこれが読み取れて楽しい」とかいった程度の、素人くさいものでしかない。
だから、こんな北村紗衣が、「男女二分に収まりきらない存在であるが故に、変態(クィア)と呼ばれる人たち」の、「男女」双方から向けられる差別的視線による苦しみを、理解しょうともしていない、というのは明白だ。
そもそも、「女であること(自分は男ではないと言い切れる立場にあること)を自明として、男の専制を責める」という古典的な「党派利益追求型のフェミニズム」を採用しているかぎり、北村紗衣が「男でもなく女でもない人たち」のことを真剣に考えたりはしない、というのは、理の当然なのである。
そして、こうしたことは「フェミニズム」の世界では、もはや自明のことなのだが、それを知らない人たちは、北村紗衣の「フェミニズム」を、オーソドックスなものだと「錯覚」してしまうのだ。』
つまり、北村紗衣が、知ったかぶりで「クィア批評」などという言葉を口にしながら、もっぱら「腐女子」的な論点についてしか語らないのは、「クィア」問題をまともに語ってしまうと、「LGBT問題」つまり「トランスジェンダリズム問題」との関係で、「男女二元論」を自明のこととしては語れなくなってしまうからなのだ。
そうなれば、もっぱら「男が悪い」などという「単純な善悪二元論」が語れなくなって、「女性」としての「党派的利益」を主張しにくくなるためである。
実際、北村紗衣に近い「東大出身のフェミニズム学者」の多く、「呉座勇一に関わるオープンレター:女性差別的な文化を脱するために 研究・教育・言論・メディアに関わるすべての人へ」に、北村紗衣とともに「発起人」として名を連ねた「仲間」のフェミニストたちの多くは、「反差別」という観点から、「トランスジェンダリズム」への支持を表明している。
ところが、北村紗衣に限っては、「クィア批評」については発言しても、当然それと関連してくる「LGBT問題=トランスジェンダリズム問題」については言及しない。
一一それは、なぜなのかと言えば、もともと「男は女性の敵だ」とは言えても、精緻なフェミニズム理論を語るほどの能力のない北村紗衣にとっては、「LGBT問題=トランスジェンダリズム問題」について発言するのは、単に「男女二元論」を揺るがせることにしかならない「鬼門」であり、それにかかわるのは、自分にとっては「損だ」という計算しかないからである。
北村紗衣にとっては、「性別曖昧」なマイノリティへの「差別」問題など、「部落差別」や「在日差別」や「沖縄米軍基地問題」などと同様に、関わるだけ損だから、そのことには触れないという、ある意味では、わかりやすい「我利我利亡者」なのである。
また、だからこそ北村紗衣が「オープンレター問題」に触れて欲しくない、というのも、「呉座勇一をネットリンチした首謀者」だという「恥ずべき過去」を隠したいだけではなく、実は、そこで名前を連ねていた「トランスジェンダリズム支持のフェミニスト学者」の「仲間」だと、知られたくなかったからではないだろうか。
それを知られてしまえば、北村紗衣は、人から、
「女性差別に反対しているフェミニストであるあなたも、当然、トランスジェンダー差別に反対し、トランスジェンダリズム(性自認至上主義)を支持なさるんですよね?
しかし、だとすると、あなたは、『身体は男性だが、心は女だ』と主張する人を、女性と認めるんですよね?
しかしまた、そうなると、あなたは、そうした、身体は男性のままのトランス女性を、女性と認めるわけだから、あなたを批判する身体が男性の人が、仮に『私は、心は女性である』とか『男性でもあれば女性でもある』などと主張した場合に、その相手を、ミソジニーの持ち主である男性なのだと、決めつけることはできなくなりますよね?」
と、そう問われることになりかねないし、そう問われた時には、「そうだ」と認めざるを得なくなって、「身体が男性(生物学的男性)」だからといって、いちがいに「ミソジニーの持ち主」であり「女性差別者」だと気つけるわけには、いかなくなるのである。
そして私は、最初からこうした「フェミニスト北村紗衣の弱点」を見抜いていたからこそ、北村紗衣による「管理者通報」によって、今も「閲覧停止」状態になっている、最初の「北村紗衣批判文」である、
・北村紗衣という「ひと」:「男みたいな女」と言う場合の「女」とは、 フェミニズムが言うところの「女」なのか?
の冒頭において、次のように書いておいたのである。
『ひとまずここでは、私は「男のような女」であり「女のような男」であり、「男らしい男」であり「女らしい女」であり、「男でも女でもない、女であり男」であると、そう言っておこう。またこれは、「自賛でも卑下でもない」。
私とは、なかなか「奇妙で不可解な何か」なのである。一一お分かりだろうか?』
つまり、私が「広義のトランスジェンダー」だと主張すれば、北村紗衣は、私を「男扱い」にすることが出来なくなり、「ミソジニー」だと決めつけることもできなくなる。
しかし、それ一本槍で、他に芸のない、「ワン・トリック・ポニー」の「フェミニスト」である北村紗衣としては、そう主張されるのは、絶対に困るのだ。
もちろん私は、自分のことを「心も体も男」だと思っており、それを疑ったことはないから、一般的な意味においては「普通の生物学的な男性」でしかない。
一一しかしだ、私がこれまでの人生で、一度も「女性であったら良かったかも」と思ったことがないわけでもない、というのもまた事実であれば、私の中には、ごくごく低い比率ではあれ「女性」性が無いとは断じられないのだ。
だから、その意味においては、私は「広義のトランスジェンダー」だと主張したとしても、「トランスジェンダリズム(性自認至上主義)」を認める「フェミニスト」たちには、その主張を否定することはできないのである。
つまり、言い換えれば、「すべての男性」が、ごく「薄く」ではあれ、自分も「トランスジェンダー」だと主張し、その「権利」を主張することも、「トランスジェンダリズム」的には可能であり、しかし、そうなると、北村紗衣のような「生物学的(身体的)女性」たちは、「生物学的(身体的)男性」を、「男」だという理由で、「女性への差別者」だと認定をすることが不可能になってしまうのである。
だから、そのことに薄々勘づいている北村紗衣は、利口にも「トランスジェンダリズム」とは関わろうとはしないし、「呉座勇一に関するオープンレター」に加わっていたという事実、正確には、自分が「発端」であり「首謀者」であったことを隠そうと、必死になるのである。
なぜなら、そのことを知られてしまうと、当然のことながら、呉座勇一に「女性差別的な悪口を言われた被害者」としての北村紗衣を擁護して「オープンレター」に関わった、「トランスジェンダリズム支持者のフェミニスト学者」との密接な関係が取り沙汰されざるをえず、北村紗衣一人だけが「私は、男女二元論者です。生物学的女性の権利は、生物学的男性から守られねばなりません」などと、「トランスジェンダリズム反対派」の女性たちとそっくりなことを、これまでどおりに、主張するわけにはいかなくなるからなのだ。
したがって、笠井潔が先の引用部(02−01)で指摘したことは、北村紗衣の「キャンセル」行動の「問題点=弱点」を、ズバリと突いたものになっていると、高く評価し得るのである。
(02-02)『もう一つ、日本では小山田圭吾の事件などから社会問題として露出してきた、業績の全否定から社会的存在の抹消にまで至りかねないキャンセル運動があります。イジメ加害者や悪質な差別者は自殺まで追い込んでもいい、追い込むべきだというような極端な発言も、ネット上ではしばしば見受けられます。
MeToo運動が反セクハラの女性差別反対運動であるように、第二のキャンセル、抹消としてのキャンセルでは、差別を巡る問題が大きいですね。一九七〇年の華青闘の告発をきっかけに日本の新左翼運動は反差別に集中して取り組みはじめたのですが、そこで糾弾、コールアウトも頻繁に行われ、いろいろな意味で問題になりました。しかし反差別運動は糾弾行動の適切な位置づけに、失敗してきたといわざるをえないところがある。そのこともあって、華青闘告発以来の反差別運動は徐々に力を失っていった。八〇年代を通過して九〇年代になると、社会党から自民党穏健派、リベラル派まで含めた、何となく反差別という雰囲気の中に拡散していく。反差別への強力な反動、バックラッシュが巻き起こっても、それと闘って勝ち抜くだけのパワーを、何となくリベラルな反差別統一戦線は持ち得ませんでした。この辺のことは『例外社会』で書きましたが、どうして新左翼的な差別糾弾が空転していったのかというと、糾弾の運動的・文化的蓄積に無知なまま、外見だけの糾弾を振り回すことがしばしば見られたからです。普遍的な問題である反差別には還元できない個人的な信条の問題、アイデンティティの問題がうまく意識化されないまま混ざり込んでいく、そういう傾向があったともいえます。その最悪の形態が反差別の党派的利用でした。
今でもそうですけど、その頃、それ以前の戦後民主主義的な差別解消の論理に対して、ラディカルな反差別の立場を象徴するものとして、「足を踏まれた痛みは踏まれた人間にしか分からない」という言い方がありました。これは意識的な差別ではない、慣習的あるいは無意識的な差別を問題化するという意味では積極的な効果があった。その意義は否定できないし、運動を進める上でも有効だったのですが、しかし無視できない問題もそこから生じてきました。たとえば踏まれてもいないのに踏まれたと言い張って、相手を攻撃する者が出てきても誰もチェックできません。踏まれた人間にしか踏まれたことは分からないわけだから。本当に踏まれている場合と、詐欺師が言いがかりをつけている場合の区別がつかない。詐欺師はいないという性善説に立った論法でもある。七・七以降に取り組まれた反差別闘争の場合は、金銭目的の詐欺師による差別批判や糾弾の利用というよりも、正義観念の倒錯やアイデンティティの自己目的化や報復感情への埋没といった事例が目に付きました。部落解放運動の場合は戦前の水平社期時代から、社会運動における差別糾弾の意義を明らかにし、そのルール化に努めてきたわけですが、われわれ(※ 左翼の人間)はよく言えば手探りで、あるいは思いつきで差別の告発や糾弾を運動的に進めた結果、さまざまな限界や困難を抱え込むことになった。この辺で積み残された問題が、ネット社会の到来とともにキャンセルカルチャーの問題として、次元を変えながら露出してきた面があるように思います。』(P13〜14)
ここで語られている、かつての「(新)左翼」が関わった、各種の差別に対する「糾弾」活動の失敗ということだが、このことについては、すでにレビューを書いた、『情況 2024年夏号 【特集】トランスジェンダー』 で、笠井潔と同世代の「左翼」である、前田和男と沢辺均が、「[鼎談]子ども向けのLGBT入門絵本から読み解く日本の性的マイノリティ運動の歩み」の付録として書いた「鼎談を終えて」で語たられていたことと同じである。

彼らは「トランスジェンダリズム(性自認至上主義)」運動を支持しつつも、その強引で独善的なやり方には、次のように「警告」を発していたのである。
『戦後(新)左翼運動や全共闘運動は、結局は『ゲバルトの杜』に迷い込み、自滅してしまった。このことの教訓を活かす必要があるのだと思う。』(沢辺均)
『思えば、そもそも私たち自身も同じだった。先達としては、戦後の日本共産党が主導した運動があって、そこでは武装蜂起路線の失敗と挫折から内粉と分裂による大きな痛手をおった。私たち全共闘世代はそれを骨身にしみて理解できたかというと、それができずに同じような内ゲバを起こして自壊した。そうなると、先達たちの失敗は反面教師として教訓化できないということを教訓化しなきゃいけないってことなんだろうか。』(前田和男)
つまり、「トランスジェンダー差別」を無くすために、「差別者」に対しては「キャンセル」も辞さないという「トランスジェンダリズム至上主義者」のやり方は、「過去の教訓」をまったく生かしていない、無知に由来する愚行だ、ということである。たとえその「理想」が、どんなに正しくともだ。
で、こうした「トランスジェンダリズム至上主義者」による「崇高な目的」達成のための「手段としてのキャンセル」の問題点は、そのまま、「女性差別者を含む、論敵をすべてキャンセルする」という、「ノーディベート」な「北村紗衣の暴力的なやり方」にも、そのまま当てはまる。
言うまでもなく、「女性差別」はいけない。「女性を誹謗中傷するような言動」は「差別」であるから、批判され正されて然るべきものである。
一一ただし、だからと言って、そうした「悪口」を言った者が、社会的に「キャンセル」され、「職を追われ(呉座勇一)」「過大な賠償金をとられる(山内雁琳)」といったことは、「過剰報復」として、許されないことなのだ。
かつての、正義の御旗をふりかざしての、暴力的な「糾弾」活動が、そのやりすぎのために、一般からの支持を失ってしまったのと「同じ過ち」を、「トランスジェンダリズム至上主義者」や「北村紗衣」は、そのまま繰り返してしまっているのである。
そして、上の引用文後半の、
『「足を踏まれた痛みは踏まれた人間にしか分からない」という言い方がありました。これは意識的な差別ではない、慣習的あるいは無意識的な差別を問題化するという意味では積極的な効果があった。その意義は否定できないし、運動を進める上でも有効だったのですが、しかし無視できない問題もそこから生じてきました。たとえば踏まれてもいないのに踏まれたと言い張って、相手を攻撃する者が出てきても誰もチェックできません。踏まれた人間にしか踏まれたことは分からないわけだから。本当に踏まれている場合と、詐欺師が言いがかりをつけている場合の区別がつかない。詐欺師はいないという性善説に立った論法でもある。』
という部分が、北村紗衣の、男性に対する、一方的な「ミソジニー」認定と、ぴったり重なる。
要は、北村紗衣のことを「悪く言った男」の側にも、「悪く言うだけの理由」は、多少なりともあったのだが、その「理由」が妥当なものなのか否かの「議論」がなされることもなく、
「結局は、どんな理屈をこねたところで、あなたはミソジニーを持つ女性差別者でしかないのですよ。自身の、そのミソジニーに無自覚なのです」
という「一方的な決めつけ」で、相手を「差別主義者」認定し、その存在を「キャンセル」することも正当化されてしまうのである。
実際、呉座勇一が、ツイッターの「鍵付きアカウント」で、下品な悪口を言ったというのは事実のようだが、それは呉座の認識としては「私的な会話」として「許されるもの」だということだったようである。
つまり、いつでもどこでも、他人の「悪口」や「陰口」をいっさい言わない人間などは、男女を問わず「存在せず」、まして北村紗衣などは、ツイッターにおける公開で「悪口」を書くくらいなのだから、当然、非公開の陰口もしているはずで、それが「いっさい無い」とは言えないはずだ。
ただ、呉座勇一の場合は、「鍵付きアカウント」でも「身内だけ」でならかまわないだろうと思って発した「陰口」がリークされて外に漏れ、当の北村紗衣の知るところとなってしまった。
そして、北村紗衣自身が、その「陰口」を公に晒して、「呉座勇一とは、こんな卑怯な、裏表のある差別主義者だ」と批判し、さらに「私はこんな悪口によって、さんざん傷つけられた」と被害者アピールしたことから、フェミニズムに関わる大学の女性教員や出版関係者を中心に、千人を超える署名者の名を連ねた、件の「オープンレター」が公開されることになる。
そこでは、「呉座のような男」の体現する「女性差別的な文化を脱するため」には「研究・教育・言論・メディアに関わるすべての人たち」は、このような人物と席を同じくすべきか否かを、真剣に考えるべきだと主張して、表面的には「キャンセル」対象を限定しないかたちで、しかし実質的に「呉座勇一を、研究・教育・言論・メディアの世界から排除(キャンセル)せよ」と、呉座個人を狙い撃ちにして「キャンセル」したのである。

ちなみに、北村紗衣が運営に関わる「Wikipedia」では、「オープンレター」で検索しても本件は出てこない。なぜなら、わざわざ「女性差別的な文化を脱するために」というタイトルで、項目が立てられているからだ。しかも、そこでは、加害者はもとより、北村紗衣をはじめとした「発起人」の名前さえ伏せられている。呉座の名前は伏せるとしても、どうして発起人の名前を伏せる必要があるのか。無論、歴史を抹消する(黒塗りにする)ためである。じつに狡猾な「証拠隠滅」的アリバイ工作ではないか)
本気で「差別者」一般のことを問題にしたかったのであれば、そこで「呉座勇一」ひとりを名指しの「実例」として挙げる必要はまったくなかった。
なのに、あえてそれをしたのだから、これは呉座個人に対する「署名者千数百人」による「ネットリンチ」だったと、そう考えるべきなのだ。

また、北村紗衣による「山内雁琳に対する、誹謗中傷にかかわる民事(賠償)裁判」も、与那覇潤が正しく検証したとおりで、長々と交わされたTwitter(現「X」)上でのやり取りの中から、裁判で問われたのは、山内がリツイートした他人のツイートも含む、たった「11個(件)」だけだったという事実から、この裁判の本質も窺えよう。
つまり、長く激しいやりとりの過程で、つい感情的に発せられてしまった、山内雁琳側の「汚い言葉=女性差別的な言葉」や「リツイート(他人のツイート)」を、たったの「11個だけ」を切り取り、そもそもの「やりとりにおける文脈(北村紗衣が何をし、何を言ったか)」はいっさい無視し、北村紗衣の発言は不問に付したまま、その山内雁琳側の「11個の言葉」だけが「名誉を毀損するものか否か」とだけ、一方的に問われたのである。
そして、北村紗衣は、こうした「切り取りのよるフレームアップ」作戦に成功し、味を占めたものだから、それ以降、自分を批判する者の対しては、その「言葉尻だけ」をとらえて攻撃することを、「常習手段」化したのである。
「文脈」はどうあれ「ひとまずその言葉は、誹謗中傷であり、言い訳の余地はない」と責めるという手法を、学習したのだ。
そのため、当時、北村紗衣が批判(反撃)対象としていた「須藤にわか」氏の「note」記事のコメント欄に、私が須藤氏に向けて、
『年間読書人
2024年8月25日 05:14
それを、それこそ『ダーティハリー』すら見てなかった素人が、「アメリカン・ニューシネマ」は「こういうものだ」なんて、知ったかぶりで語るのは、まさに「盲目、蛇に怖ず」ってやつだと思います。
そして、そうした態度の根底にあるのは「差別的な上から目線」。だから、そこで「フェミニストの恥さらし」にもなるわけです。
今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。』
と書いたのを見て、北村紗衣は、その最後の部分である『今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。』に着目し、これを切り取って問題発言化し、「note」管理者に対して、「脅迫された」と「管理者通報」することにしたのである。
そして、その「管理者通報」という強行手段を論敵である須藤氏に伝えることで、須藤氏をも黙らそうと考えて、北村紗衣は、私がコメントしたのと同じ、須藤氏の「note」記事のコメント欄に、次のように書き込んだのである。
『北村紗衣
2024年8月27日09:36
須藤にわかさん、あなたは私が「お姫様 になることが女性の権利向上と考えているフシがある」などと私が思ってもいないことを言って人格攻撃を行いました。それが弁護できることだとでも思っているのでしょうか。フェミニズム観の違いに逃げようとしても無駄です。
年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメントは通報いたしました。』

つまり、私が、
『今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。』
と書いた部分だけを捉え、文脈を故意に無視して、これを、
『年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメント』
だとして「管理者通報」したのだが、一一ここでの北村紗衣は、調子に乗って、やりすぎてしまっていた。
それは、この北村紗衣の言葉は、私の言葉の「切り取り」では済まず、「改変」まで加えてしまっており、「文脈無視」だけではなく、完全に「改ざん」による「言いがかり」になってしまっている点である。
「文脈」的には、私は、北村紗衣の本を「物理的に切り刻む」と言ったのではなく、「その内容を、細かく批判する」と言っているのは明らかだが、仮に、その「文脈」を無視して「切り取る」にしたところで、私が「現に発した(書いた言葉)」は、
『切り刻んでやろうかな』
であって、北村紗衣が「通報」した際に書いたと推認される、
『切り刻む』
とは、まったく意味の違う言葉だ。
要は「切り刻もうかな」と「思う」のは「自由」だし、「そう思った」と書くことも「自由」なのだ。
「切り刻む」という「物理的攻撃」を意味する言葉を、公の場所で、特定他者に向けて書けば、それは一種の「脅迫行為」だと認められるような場合もあろうが、例えば「私は、安倍晋三を殺したいとまで思った」と書くことが「脅迫」行為になるのであれば、「表現の自由」は著しく制限されることになるのは明白である。
したがって、私が書いた『今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。』は、完全に「表現の自由」の範囲内のものであり、北村紗衣の「改ざんによる、事実に基づかない、誹謗中傷」の方が、明らかに、よほど「有罪」なのだ。
それにそもそも、自分の買った本を「切り刻む」と書いて「脅迫」になったのでは、使用済み商品を、「ゴミ出しします」とも書けないことになるのではないだろうか。
なぜならそれは、北村紗衣的には、その商品を「燃やし尽くしてやる」と言って、製造者を脅迫しているも同然だ、ということになるからである。
一一だから、北村紗衣には、今後「ゴミ出し」は「他人の創作物を毀損する行為」として、いっさい謹んでもらわなくてはならないだろう。その義務が、北村紗衣にはあるはずなのだ。(わかったな?)
(02-03)『告発や糾弾は処罰ではないから。もしも差別の被害当事者やその支援者は差別者を勝手に処罰していいとすれば、それは定義からして私刑、リンチの肯定になりますね。その線を越えてしまうと、仕事、業績の否定から存在の否定まで行きかねない。存在の否定まで行くとなると、その意味するところは戦争状態に入るということです。(※ 小山田圭吾へのキャンセル運動とは)小山田を敵と認定して戦争状態に入る。カール・シュミット流に言うと「例外状態」に入る(※ ということを意味してしまう)。社会運動の文脈では、そういうこともあり得ます。しかし小山田の存在自体のキャンセルを要求する者が、物理的抹殺も含め敵を打倒するしかない戦争状態に入るという(※ そこまでのシビアな)認識と、内戦状態だから自分もいつ殺されるか分からないという覚悟があって、そうしているのかどうか。そうとは思えませんね。だけど実際にやろうとしていることは意識的であれ無意識的であれ「敵」の抹殺。にもかかわらず、そのことを自覚していない。呉座勇一の差別事件もそうですが、オープンレターの差出人は正義の側に立って中傷や差別に反対し、その事例として呉座の差別発言に反対し、その事実として、それが呉座から職を奪うことになった。そのような結果を望んだわけではないというのか、当然の結果で反差別闘争の勝利だというのか、(※ オープンレター署名者)それぞれ立場は違うかもしれませんが。しかし、(※ それ以前に、すでに)責任を認めて謝罪している人間を、それでもまだ名前を挙げて叩き続けることが何を意味するのか(※ それは、一人の人間の社会的な抹殺までをも望んでいるというのを意味してしまう、ということ)、それについて無自覚な批判者が多すぎるように思います。これはおかしいんじゃないのか。敵を抹殺することもやむを得ない状況があり得ることについて(※ 自覚的に)考えてきた(※ 私のような)人間からすると、そこの甘さがとても気になる。微温的に、常に正義の側に身を置いていたいと思って(※ いるだけで、自分の行動が、どのようなことを結果するのか)、そのことを疑おうともしない安直な精神の連中こそ、ゴツンとやって(※ 現実の過酷さを)分からせた方がいいんじゃないか(笑)。ただし、差別事件の被害当事者の場合は問題が別ですよ。被差別者、被抑圧者には差別者や抑圧者を敵として打倒する権利があります。謝罪を求めて和解するのか、打倒するまで闘うのかは被害者の判断ですが、もう一点、ここには共同体とその外部の倫理をめぐる問題(※ 共同体の内部の人間同士なら、同じ価値観とルールを共有しているから、話し合いが可能だが、価値観やルールを共有しない外部の者である絶対的な敵とは、話し合いが成立せず、最後は力による制圧しかなくなってしまう、という問題)が絡んできます。』(P16)
笠井潔がここで問題としているのは、「敵をやっつける(殺し合いをする)」という行為に対する「リアリティ」の無さ、という問題である。
笠井潔は「連合赤軍の総括殺人による自滅」の問題を「人間に憑く観念」の問題として考えてきた人だ。最初の理論的な著書『テロルの現象学』のサブタイトルが「観念批判論序説」となっているのも、「(思想や理想などの)観念が、人をテロルへと走らせる倒錯」という問題を、批判的に考えた著作だからこそ、「観念批判論」なのである。
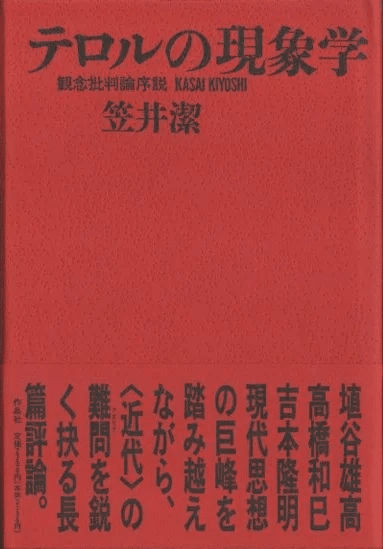
で、そうした「極限的な観念の犯罪=理想を求めて、殺人者に堕ちる」という極限的な問題を考えてきた者にとっては、他人を「キャンセル」して「勝った勝った、正義が勝った」などと喜んでいるような輩、つまり「北村紗衣をはじめとしたオープンレター署名者たち」は、「人を追いつめて殺す」という行為についての「想像力」が、あまりにも乏しすぎると、そんな不満とも呆れともつかない感情しか持てないと、笠井ここで、そう言っているのだ。
言い換えれば、「殺すのなら、殺すのだという自覚と覚悟を持って、その責任を引き受けた上でやれ」ということである。
これにはまったく同感で、私がネトウヨと喧嘩した際などがそうだが、私はそのネトウヨの「人格を否定するようなこと」を自覚的に繰り返して突きつけてやる。
匿名の陰でしか悪口も言えないようなヘタレの卑怯者は、私によって徹底的に、人としてのプライドを傷つけられて当然だし、そのことが原因で、自殺して「死んでもらってもかまわない」と思いながら、私はやってきた。また、そう公言してもきたのだ。
つまり、私のネトウヨ批判は、単なる「善と悪との戦い」などではなく、「善を異にする、相容れない者同士の、言葉での殺し合い」だというそんな自覚が、私にはあったのである。
だから仮に、私が徹底批判した相手が「あいつがこんなことを書いたので、私は傷ついてしまい、自殺することにした」という遺書を残して死んだとしても、その時になって、途端に慌てて「そんなつもりはなかった」などといった間抜けな言い訳など、私は金輪際しないと、そこまで考え、そう公言してやってきたのである。
だから、私は「数の力」で北村紗衣を「キャンセル」するつもりはないけれど、私の言葉が北村紗衣を「精神的にどこまでも追い詰める」ことなら、自分に許している。
「言うべきことは言ったから、これでもういい」などという「ヌルいこと」は考えておらず、あくまでも北村紗衣と、言論による内戦状態を闘っている、私はゲリラなのだ。
で、当然、笠井潔も、そういうスタンスでやってきた人だから、「子供が刃物を振り回している」も同然である「北村紗衣らオープンレターの面々」については「ゴツン」とやった方が、当人と社会のためだとそう考えている。
また、与那覇潤が、「北村紗衣らオープンレターに署名の学者」たちを『お子様学者』と呼んだのも、まったく同じ意味であり、与那覇がこれからやろうとしていることは、まさにこの「ゴツンとやる」ということなのである。
(02-04)『 何らかの被害を受けた場合、加害者に謝罪と補償を要求するのが普通ですが、謝罪と補償が一体であるという常識は疑ってみたほうがいい。リベラリズムの正義論では、共同体内の倫理を善、共同体間のそれを正義とします。この用語法を踏襲していうと、謝罪の要求とは善をめぐる問題、同じ共同体に属している者同士に成立する事柄です。罪の定義さえ違うかもしれない共同体外の者に対して、善を要求しても無駄ですから。その場合、放っておけば戦争になるわけですが、互いに殺しあいは望まないという場合、加害事件を解決するために同等報復が許される。目には目を、ですね。同等報復が制度化、合理化されると補償になる。ようするに正義とはバランスで、バランスが損なわれた状態が不正義なんです。秤が正義の象徴だったのも、均衡こそ正義だと了解されていたから。共同体外の者との間で損なわれた均衡を回復することが正義で、それは善悪とは別種の原理です。
では、善とは何かというと、同じ神を信仰する者たちの間での倫理ですね。善悪の基準は神から共同体に与えられるので、同じ共同体に属する者たちの倫理ともいえる。信仰する神が違えば倫理も違うので、たがいに善を要求しあうことはできません。この点からすれば謝罪を要求しての糾弾とは、善をめぐる領域の問題です。たとえば公民権運動は、実質的に白人社会でしかないアメリカ社会を、黒人を含めた普遍的な社会に変えようとする運動でした。善を要求する運動だから、糾弾と謝罪が問題になるわけですね。彼らと我々が別の世界に属していると了解されるなら、善ではなく正義の貫徹が問題になる。分離主義であれば差別者に謝罪など求めない、差別という不正義の補償として被差別者が差別社会から分離しても生きられる条件を要求する、ということになります。キング牧師が前者とすれば、マルコムXは後者の方向を向いていた。同等報復としての補償要求が認められないなら、差別・抑圧する共同体と差別・抑圧される共同体の戦争にならざるをえない。』(P16〜17)
ここで、笠井潔が言っているのは、北村紗衣が、呉座勇一や山内雁琳に対して行ったことは、「同じ社会に生きて、善を共有するメンバーとしての、善を求める問題解決」ではなく、「善を共有しない敵の抹殺」だった、ということである。
つまり、「オープンレター」や「民事賠償裁判」が「合法」なものだとしても、そこで実際に目指されていたのは、「善を共有しない敵」の「抹殺」なのだから、そうした態度で「他者」の臨む者は、その当人もまた、そのような「敵」として「抹殺」を企図されても、文句を言う資格はない、ということだ。
「そんなつもりではなかった」では、済まされないということなのである。
したがって、当然のことながら、「北村紗衣とオープンレターへの署名者たち」は、「同等報復」の標的になる、ということになる。
「ごめんなさい」では済ませてもらえないようなことまでしたのだから、そのくらいの自覚は持たなければならないし、この問題を見ている人は、「北村紗衣とオープンレターへの署名者たち」が犯した「過剰報復の過ち」の怖さを、よくよく学ばなくてはならないということなのだ。
謝っている相手を、それでも徹底的に叩きのめすようなことをした者は、自分が「勝負」に敗れた際は、「負けました」と認めて謝罪しても認められす、二度と身動きができないようになるまでやられても、文句は言えないということなのだ。
「わかってくれたんなら、それでいいよ」などとは、金輪際、言ってはもらえないようなことをやってしまった、ということなのである。
これからは「殺すか殺されるか」という、過酷な道を、好むと好まざるとに関わらず、自分で選んでしまったのだという事実を、「北村紗衣とオープンレターはの署名者たち」は、せめて認識して、報復に備えるべきなのである。
『 安全な場所に身を置いて、他人を徹底的に非難攻撃する、自殺まで追い詰めたら大成功で、それほど楽しいことはないという連中が大量に存在している。そうした炎上屋は、大量といってもネット利用者全体から見れば数パーセントといわれていますが。悪質な連中の声や存在感を増幅する装置がインターネットだということですね。その背景には日本社会の停滞や貧困化、あるいは自己責任論の跋扈とかいろいろな要素があるんでしょう。日本だけでなくインターネット社会全般に共通する現象ですが、いじましくも惨めで、しかも無自覚に暴力的な連中が大量発生し、キャンセルカルチャーが絶好の憂さ晴らしの機会を提供している。かつて水平社が糾弾闘争からの「事件師」の追放を呼びかけたように、その種の連中がキャンセルカルチャーを利用しないように注意しなければならない。たったいま実効的な排除が難しいとしても、とりあえず問題として対象化しておくことは不可欠でしょう。フェミニズムも他のマイノリティ運動や反差別運動も、ネットイナゴや「事件師」ならぬ「炎上屋」をどのようにチェックできるか真剣に考えないと、運動自体に被害が及んできますから。ネットイナゴ的な「われわれ」が敵を見つけて過熱化していくところは、ファシズム大衆運動と共通するところがありますね。
(中略)
たとえ差別者を敵としていても、つまり本人の主観では左翼やリベラルの側にいるつもりでも、スラッシュなしの(※ 個人の自覚と責任意識を欠いた)「われわれ」で体質的にはファシズムの場合が少なくない。そうした点では右と左を機械的に切り分けられない。左側に一応分類されているものを右側に分類し直していくと、左はほとんど残らなかったりする(笑)。笑いごとではすまないですが。』
(P28〜29)
ここで「ネットイナゴ」「炎上屋」と呼ばれているのは、何も「無名のその他大勢」のことだけではない。
北村紗衣のような「著名人」もまた、まさに「炎上屋」であり「ネットイナゴ」を「ファンネル・オフェンス」として駆使する「ネットイナゴの頭目」であり、騒ぎを起こすことで利益を得ることをねらう「事件屋」そのものなのだ。
だからこそ、こういう人物に「フェミニスト」づらをさせて野放しにしておくと、『フェミニズムも他のマイノリティ運動や反差別運動も(中略)運動自体に被害が及んで』、かつての反差別糾弾運動のように、信用を失い衰退することになってしまうおそれが低くはない、ということだ。
実際、すでにそうなりつつあるのではないだろうか。

そして、もうひとつは、「北村紗衣とオープンレターへの署名者たち」は、一般には、その表看板としての「思想的立ち位置」としては「リベラル・左翼=われ/われ」だと思われているが、「数の暴力」を平然と用いる「われわれ」意識(ネットイナゴ属性)の持ち主だという点においては、むしろ『体質的にはファシズム』だと考えた方が良い、という指摘である。
例えば、ナチスが「国民社会主義」と言いながら、その内実は「ファシズム(反個人の全体主義)」であったように、「北村紗衣とオープレターへの署名者たち」もまた、「他者」の存在を容認ぜず、「社会の敵は殲滅すべし」とする「全体主義者」だと考えた方が、その内実に忠実な評価だ、ということである。
ネット右翼をはじめとした右派や保守派は、「北村紗衣を含むオープンレター署名のフェミニスト」たちをして、「左翼」だと言い、それで「鬼の首でも取った」ように言うのだけれど、それは正しい認識ではないのだ。
あの人たちは、私が最初から指摘していたとおりに、「えせフェミニスト」であり「えせ左翼」であり「えせリベラル」であり「えせ人権主義者」であり「えせ反差別主義者」なのである。
あの人たちは、「フェミニスト」の「左翼」の「リベラル」の「人権主義者」の「反差別主義者」の「理想」を、「表看板」に掲げ、その「仮面」を被り、「正義の味方」になりすまして、自分たちの「党派利益」を求める、「ネットリンチ」をも辞さない、無自覚な「反社会的勢力」にすぎないのだ。
そんなわけで、笠井潔はこのインタビューで、こうした「キャンセルカルチャー」という現象を、持論にからめて、「世界内戦」の時代が新たな段階に入ったひとつの証左だとしている。
それはまさに「ロシア・ウクライナ戦争」が示しているように、完全な「弱肉強食」の時代の到来を意味するものだ。
要は、手段を選ばず「勝者こそが正義」だとされる世界の到来である。
その世界では、すでに「道義的な正義」は「きれいごと(建前)」として、実質的に存在を認められず、「他者への寛容」は「つけ込むべき弱点」としか考えられなくなりつつある。
だが、そんなことで、私たちは幸せになれるのだろうか?
実際、呉座勇一にくり返し謝罪させ、そのうえ職まで奪って「ザマアミロ」と溜飲を下げ、山内雁琳に対しても、職を奪っただけではなく、200万円以上もの賠償金を払わせ、今では周囲から腫れ物でも触るように大事に扱われている、「武蔵大学のテニュア教授」である北村紗衣は、一一しかし、本当に幸せだろうか? 日々、朗らかに過ごしているだろうか?
それとも、誰かが、自分(北村紗衣)の旧悪を暴いて、それを天下に知らしめ、そのことで自分もいつか「キャンセル」される日が来るのではないかと、そんな不安を内心で抱え、ひそかに怯えているのだろうか?
北村紗衣に、なにも後ろ暗いところがなく、自信に満ちて日々を朗らかに生きているというのであれば、私たちは、北村紗衣が「現にやったこと」を満天下に晒すことに、何の躊躇もいらないだろう。
なぜなら、それは隠さなければならないようなことでもなければ、それを理由に、北村紗衣が世間から白眼視されて、今の地位を追われることにもならないはずだからである。
だから、なにも遠慮することはない。
ただ、事実は事実として、明らかにされなければならないだけなのである。
○ ○ ○
さて、ここまでで十分に長くなってしまったので、あとは駆け足で済まさせていただく。
(03)の前田和男による「東京音頭の波及力とキャンセル文化」は、「キャンセル」というものが、いつの時代にも存在して、猛威を振るったものであることを確認するとともに、それが「永続」するものではないということをも語ったエッセイだと言えるだろう。
(04)の絓秀実の「四波を犬掻きする」は、「フェミニズム第四波」の問題を、思想哲学の文脈において論じたものだが、いささか「現実」から遊離しているように感じられた。
(05)の藤崎剛人による「キャンセルカルチャーは存在しない」は、「オープンレター」に署名した側の人間の「必死の言い訳」である。
そのタイトルのとおり「キャンセルカルチャーは存在しない。キャンセルされるべき人間がいるだけだ」との主張だが、しかし、この先、自分が「キャンセル」の対象になったときにも、そのように「私はキャンセルされるべき人間だっただけで、キャンセルカルチャーの被害者ではない」とそう言えるのだろうか。たぶん、笠井潔が指摘したとおり、そこまでは、想像もできなかったような文章である。
要は、それほどに頭が悪い人が「大学の非常勤講師」を務め「評論家」を名乗っているということである。
(06)の山内雁琳の「キャンセルカルチャーとは何か一一その現象と本質」は、タイトルどおりに「キャンセルカルチャー」とは何か、ということを的確に紹介したもので、この文章執筆当時、北村紗衣による「民事賠償裁判」の被告として係争中だったとは思えない、冷静で明晰な文章になっている。
じつのところ、山内雁琳の文章を読むのは、これが初めてだったのだが、頭の出来(明晰さ)という点では、北村紗衣が100人かかっても、山内には勝てないだろう。
だから、北村紗衣が「論争」ではなく、山内の「言葉尻を捉えての裁判」に持ち込んだのは、まったく正しい戦略だったと言えよう。もちろん「言論人として倫理」と「人間としての恥」を捨てての、もっぱら功利主義的な選択ではあるのだけれども。
ちなみに、この「北村紗衣・山内雁琳裁判」では、「祖父が治安維持法で捕まった共産党員」であったと吹聴する北村紗衣らしく、共産党系の弁護士8人による、裁判の内容には不釣り合いなまでに豪勢な「弁護団」を形成したが、一方、一介の大学講師でしかなかった山内雁琳は、弁護士1人を雇うしかなく、対等に裁判を闘うための金が無いので、そのためのカンパを募ったところ、それまでも「裁判に便乗した、悪質なビジネスモデル」だなどという難癖をつけられ、また、それを鵜呑みにした裁判所によって、通常の賠償金とはケタ違いの賠償金を課される憂き目にあった。
北村紗衣は、山内雁琳を思うさま痛めつけた上、過分な臨時収入まで、合法的に得たのである。
(07)の嶋理人による「「妄想の共同体」としてのネット空間」も、「オープンレターに署名した人」の「自己正当化」文である。
しかも、先の藤崎剛人よりも「タチが悪い」のは、自分が「オープンレターに署名した」という立場を明確に示さないまま、まるで「第三者」でもあるかのような書き方で、言葉だけは柔らかくして、読者に「好印象」を与えようとしている点である。
また、それが見え見えなところが、何とも「痛い」文章だ。しかも、この人も大学の講師なのである。
(08)の外山恒一の「云ってることは新左翼だが、やってることがイジメ」。
外山は、笠井潔と絓秀実の対談本 『対論 1968』(集英社新書)で司会を務めていた、笠井潔ファンの「遅れてきた全共闘」を名乗る、「右翼」スタイルの活動家だ。「右翼」スタイルの人というのは、どうも自慢話が好きな傾向があるようだ。
ちなみに、前記の対談 『対論 1968』では、昔は、理論家として敵対していたはずの笠井潔と絓秀実の手打ちがなされているが、傍目には、「過去の人」となった者どおしのもたれ合いという印象が否めない。
外山が、本誌『情況』に寄稿できたのも、笠井潔の紹介だと見て、まず間違いないだろう。昔から笠井は、「子分」に仕事の世話をすることで「党派」を維持しようとするオルガナイザーなのだ。
(09)藤田直哉の「SNSと、ナラティヴの戦争」。
藤田直哉は、笠井潔が「『容疑者Xの献身』論争」における(笠井潔曰く)『信任投票』に敗れた結果として、自らが設立した「探偵小説研究会」の会員評論家の一部を引き連れて、「本格ミステリ界」を割って出た後、新たに設立したグループ「限界小説研究会」(現「限界研」)に参加して、笠井に仕事を世話してもらった「子分」の一人である。
この「SNSと、ナラティヴの戦争」については、「間違いではないが、当たり前の話でしかない」という、藤田直哉らしい凡庸な文章だ。
(10)柴田英里の「加速するジェンダー系炎上とポリティカル・コレクトネスの現在」は、各種のデータを駆使して、タイトルに示した問題を論じた手堅い文章だが、やや退屈ではある。
柴田については以前、千葉雅也、 二村ヒトシとの鼎談集『欲望会議 性とポリコレの哲学』での、ポリコレ・フェミニズムに対する、威勢の良い挑発的なその言動を痛快に思い、その後の活躍に期待したのだが、どうやら「反体制」を貫いたせいで、かなり苦労をしたような様子で、『欲望会議』の頃のような「元気」が感じられなかったのは、ファンとして残念であった。この人には、もっと活躍してほしいと思う。
(11)の高井ホアンによる「「国体」にキャンセルされた歴史学者たち」だが、これも「歴史にキャンセルを見る」という、(03)と同趣旨の文章である。
(12)窮地に立つ「京大的文化」 (ホリィ・セン)
(13)あらかじめキャンセルされた文化 謎の「社員旅行」に迫る (山本華織・松山孝法)
(14)「私たちは清された展2022」潜入ルポ (情況編集部)
この3本は、いずれも「キャンセルカルチャー」そのものとは直接関係のない文章で、(12)は「権力によって排除される学生文化を、いかにして守るか」を語ったもの。(13)は「失われた(キャンセルされた)文化」にも、見直すべき美点があったのではという対談。(14)は、ネットから排除された「表現者」たちの展覧会を取材したもの。しかし、排除された作家たちは「所詮、ネットって、そんなものでしょう」と、いたって冷めており、そこに固執して抗うのではなく、ネット外でいかに生き延びて表現していくかを考えているところが、かえって新鮮であったとは言えるだろう。
以上、特集の全体を通して言えるのは、この特集号が刊行された「2022年」当時は、猛威をふるい「我が世の春」の栄華を誇っていた「キャンセル使い」たちも、本書でいろいろと警告的に語られていたとおり、今や、「驕れる者も久しからず」の運命を、まんま地で行きそうだ、ということである。
なにしろ、まだたったの2年しか経っていないのに、風向きの変化が、たしかに感じられる昨今だからだ。
(2024年12月2日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
