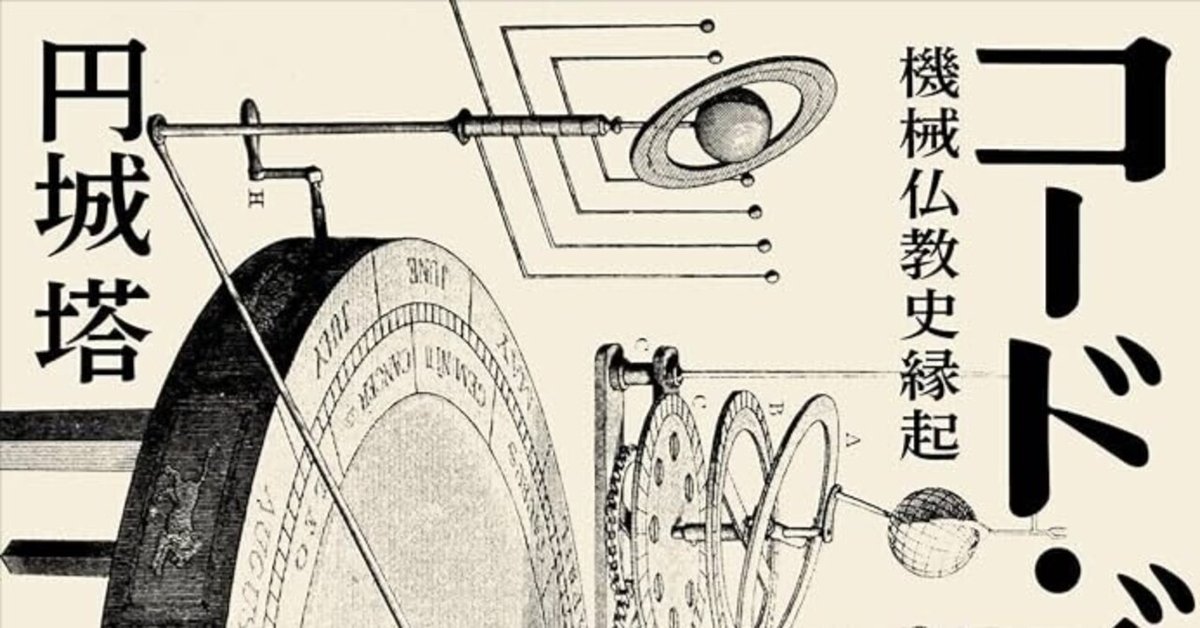
円城塔 『コード・ブッダ 機械仏教史縁起』 : ブッダと 女人成仏と トランスジェンダー
書評:円城塔『コード・ブッダ 機械仏教史縁起』(文藝春秋)
今年読んだ本では、一番面白かった。もっとも、今年の前半は「映画」、後半は「フェミニズム」「キャンセルカルチャー」「LGBT問題(LGBTQ問題)」と、従来の守備範囲内での「娯楽」ではなく、未知のジャンルの「勉強」が中心だったので、純粋に「娯楽」として楽しんだ本は、存外すくなかったからでもあろう。
私の場合は、「勉強も娯楽のうち」だから、これはこれで、「知見が広がる」という意味のおいて、それなりに面白くはあったのだが、やはり読んでいる最中は、「面倒くさい」とか「腹立たしい」「アホちゃうか、こいつ(武蔵大学教授の北村紗衣ほか)」とかいった感じになる本も間々あって、純粋な「娯楽作品」を楽しむのとは、やはり訳が違った。
しかしまた、そうした「勉強」のための読書は、その後に読む本を楽しむための「基礎教養」にもなって、次の段階での「楽しみ」を増幅してくれる。
例えば、本書に関するAmazonカスタマーレビューで、「おでこ」氏が『仏教史とコーディングの知識があれば10倍面白い』と題するレビューを書かれているが、このレビューのタイトルどおりで、本作『コード・ブッダ 機械仏教史縁起』については、そうした「教養」があるのと無いのとでは、その楽しみは何倍も違うというのは確かなことなのだ。

例えば私の場合だと、「コーディング」の経験は無いものの、長年パソコンを使ってきたので、いつの間にか「パソコンの歴史入門」程度の知識は身についているし、昔「ホームページ」を作っていた頃には、HTMLタグを埋め込む程度のことはやったから、専門的なことはわからないが、雰囲気くらいはわかる。
一方、「仏教史」についても「入門書」程度のことは知っているし、例えば、「仏教」と「キリスト教」の本質的な違いといったことも、身に沁みて知っている。
一一というのも、私はもともと「創価学会員」で、その「信仰」を信じられなくて辞めた人間なのだ。また、そうした過去から「宗教批判」にまで転じた人間なので、「キリスト教」とは質の違った、「仏教」特有の「非合理性」とか「ご都合主義」というのは、本書に教えられるまでもなく、嫌というほど経験的に知っていたのである。それも今となっては、得難い経験だったと、そう思えるようになったとしてもだ。
私が「創価学会」を辞めたきっかけは「イラク戦争」(2003〜2011年)だった。
それまでの「創価学会」は、「戦後民主主義」の時代に急成長した新宗教の教団らしく「絶対平和主義」を掲げており、教団最大のカリスマである第3代会長の池田大作は、「平和旅」と称して世界中を旅し、海外の政府要人や著名人らと対談して、それを著書として刊行したりしていた。
今となってはいずれも故人だが、ソ連(現ロシア)の元書記長(最高指導者)であったミハイル・ゴルバチョフや、イギリスの著名な歴史家アーノルド・J・トインビー、戦後のドゴール政権で文化大臣も務めた、代表作『人間の条件』で知られるアンドレ・マルローなどだ。
しかし、その「創価学会」が、アメリカ主導の「イラク戦争」を、実質的に支持した。
すでに連立与党の一角におさまっていた「公明党」を、支持母体として批判することをしなかったのだ。
だから私は、これを明らかな「言行不一致」として、公然と批判するようになったである。
しかし、こうした少なからぬ内部からの批判に対しては、妄信的な信者からの護教的な反論がなされるばかりで、肝心の創価学会(本部)や池田大作(名誉)会長は、ハッキリとした態度を示さないまま、「イラク戦争」は多くの犠牲者を出すことになった。
それまで、創価学会内で「仏法は勝負である(勝負は勝たなければならないし、創価学会の仏法は、正法として当然の力を持つのだから、勝てないはずがない。祈りとして叶わざるは無しである)」と、そう教えられてきた私は、「イラク戦争」の悲惨な結果的現実(多くの人を死に至らしめた現実)をして「創価学会の信仰は、虚妄であると証明された」と結論し、創価学会を去ったのである。
もちろん、私が「イラク戦争」に際して、創価学会や池田大作を擁護する側に立たなかったのは、その信仰に「何があっても(戦争に加担してさえ)、絶対に正しい」というほどの「信仰的確信」を持っていなかったからに他ならない。
ではなぜ、それでも「創価学会員」であったのかといえば、それは、幼い頃に両親と一緒に、その意味もわからないまま入信したからだ。つまり私は、「宗教2世」ならぬ「宗教1・5世」とでも呼ぶべきもので、自ら信仰を求めて入信したわけではなかったのである。
そんなわけで、当時の私にとっての「創価学会」とは、言うなれば「生活の一部」であった。それも「生活の中の面倒な部分」だった。
なぜ「面倒」なのかと言えば、そちらの活動に、多少なりとも時間が取られたからだ。
朝晩30分程度の「勤行」。それから「週に1回」あるいは「月に1回」の、2時間ほどの会合への参加といったことが、私にはとても面倒だった。その内容が、基本的にはワンパターンなものだったので、単純に「つまらなかった」のである。
今でもそうだが、私は子供の頃から一貫して「趣味人」であり、やりたいこと、つまり、時間を費やしたいインドアの趣味がいくらでもあったから、学業以外の私生活において、好きでもないことに時間を取られるのは、とても苦痛だったのである。
しかし、それではどうして、素直に活動に参加していたのかというと、私は基本的なところ「真面目な優等生」だったから、「理由がないかぎりは、サボることはできなかった」ためである。
そしてさらに、創価学会には「世界平和のための信仰」という「大義」があったので、私はこれに逆らうことができず、言うなれば嫌々ながら「義務」を果たしていただけだった。だからこそ「いっそ、この信仰に対する絶対的な確信を得て(回心を得て)、喜んで活動できるようになれれば良いのに(楽なのに)」とさえ思っていたのである。
したがって、そんな私には、「イラク戦争」は、ある意味では「ありがたい」ものでもあった。これで、正々堂々、創価学会を辞める理由が出来たからである。
しかしまたそれでも、退会前の1年くらいは、世話になって創価学会への恩返しの意味もあって、ネット上で創価学会を徹底的に批判もした。
宗祖日蓮の国主諫暁と同様に「三度諌めて聴かれずんば即ちこれを去る」(『礼記』)ということで、十分に義理を果たした上で、綺麗さっぱりオサラバしたのである。
こうした経験を持つ私だから、「宗教の欺瞞性」というものについては、何の疑問も持たずに慣習的な宗教行事に参加している人たちなどよりは、よほど先鋭な批評意識を持っている。
要は「初詣? 葬式? そんなものは気休めだよ」あるいは「人間は死んだら、ゴミになるだけだ」といった、徹底した「無神論的反宗教者」に転じた。
だから、先年亡くなった母については、葬儀もしなかったし、火葬場から遺骨も持って帰りもしなかったのだ。骨は母ではない、からである。
墓は、両親が健在な頃に、二人が創価学会の墓園に買っており、先に亡くなった父は、その墓に入った。
だが、他府県のかなり辺鄙ところにあったとは言え、私は創価学会員時代ですら、その墓を参ったのは、一度あったかなかったかくらいだった。家で毎日仏壇に向かい、先祖供養もしているのだから、ことさら墓参りなど必要ないというのが、当時の私の感覚だった。
だから、創価学会を辞めた後は、もう完全にその墓も「放棄」して、「墓じまい」もクソもないということになった。要は、墓などという気休めは、もはや完全に不要となったのである。
そんなわけで私は、創価学会を辞めてから、積極的な「宗教批判者」になった。
宗教と縁が切れて清々したつもりでいたのだが、その後「オウム真理教事件」が発生して、それに興味を持ち、そこから「今度は、宗教現象を批判的に研究しよう」と考えるに至ったのである。そのことによって、自身の体験の意味を、検証しようと考えたのだ。
そしてここでやっと本書『コード・ブッダ』につながるのだが、独学で「宗教を研究しよう」と思いついて、最初は、そのきっかけとなった「オウム真理教」関係の本をいろいろと読み、それはそれで興味深くもあれば勉強にもなったのだが、しかしなぜか、どうにも物足りないものが感じられた。
その理由とは、結局のところ、それらの書物での「オウム真理教」の扱いは、前代未聞のテロ事件を起こした「特殊例外的な教団」というものであって、「宗教一般の問題」とは考えられていなかったからである。
そこで、私は方向転換をして、創価学会がそうであったから、まず「仏教の概略」を知ろう考えた。
しかし「仏教」といっても、いろんな宗派があって、そのどこから手をつけたら良いのか、さっぱり見当もつかない。
ある程度は知恵のついた今なら、ひとまず「仏教史」から読み始めれば、とも思うのだが、その当時の私の興味は「教義的な中身」にあったし、外形的な「歴史」などには、とんと興味がなかったからである。
そのため、「仏教の本質」を知るためには、どこから手をつけれはよいのかと、途方に暮れてしまったのだ。
そんなわけで、あれこれ思案したあげく、私は、本丸と目した「仏教」は、いったん横に置いて後回しにし、他の「世界宗教」で「わかりやすそうなもの」を勉強してみることにした。そちらで、「宗教の本質」の部分を大掴みにしたあと、「仏教」に回帰しようと考えたのだ。
そして、「世界三大宗教」と言われる「仏教・キリスト教・イスラム教」の中で、まず仏教を外し、次に日本にはほとんど無縁だったイスラム教を外すと、おのずとキリスト教が残ったのである。
もちろん、キリスト教にもいろいろある。とは言え、大きく言えば、旧教(カトリック)と新教(プロテスタント)と東方教会(正教)の3つだけだし、何より良いのは、キリスト教の本尊は「イエス・キリスト」、聖典は「聖書」1冊だったから、諸仏・諸経のある仏教に比べれば何とかなりそうだと、すでに読書家であった私は、そう考えたのだ。
そして実際、聖書の通読に始まって、「教会史」「聖書学」「神学」「説教集」などの本を、興味の赴くままに読んでいく中で、キリスト教の一般信者よりは、よほどキリスト教のことを「知っている」人間になったし、大学で「キリスト教」を講じている「キリスト教学者」ほどではないにしろ、一般の神父や牧師には劣らない知識を身につけ、彼らが「触れられない部分」にもづかづかと踏み込んでいったから、彼らとの議論でも負けることなどないほどになったのである。
このようにして、ある程度「キリスト教研究」が一段落し、再び「仏教」に戻って「仏教史」の本を読んでみると、初めて「仏教の複雑さ」と言うか、本書『コード・ブッダ』でも描かれているとおり、仏教の「一貫性の無さ」と言うよりも「デタラメなまでの自由奔放さ」が実感できた。「こりゃあ、キリスト教と同程度に、仏教全体を把握することなんて、物理的に不可能だ」とわかったのだ。それこそ、「基本的な仏典」をひととおり読み、そこに書かれていることの表面的な意味を理解するだけでも、何年かかるかわからないと、そう悟ったのである。
だから、今の私は「仏教そのもの」の「本質」を理解しようなどとは思わなくなった。なぜならば、それは原理的に「不可能」だからだ。
無論、釈迦の説いたことを「本当の仏教」だと断定して限定してしまえば、話は簡単だ。だが、それは「仏教の現実」とは程遠いものであり、それを持って「仏教の本質を理解した」と主張するのは、あまりにも「党派的」な自己満足でしかないと、私には思えた。
しかし、かと言って、釈迦に始まり、インド、中国、そして日本へと伝わる中で、さまざまに変化し、分化した「仏教諸派」のすべてを、ひととおり押さえるというのは、仏教の専門学者でも不可能なことなのだから、素人が趣味的にやれるわけもないと、そこは見切りをつけて、私の興味は「仏教」や「宗教」そのものではなく、「宗教を信じてしまう人間」というものの方に向くことになった。
そして、これはもともと、夏目漱石の『こころ』がきっかけで活字の本を読むようになった私の、「人間心理」というものへの傾倒とも合致することになったのである。
○ ○ ○
そんなわけで、私は、普通のSFファンよりは、ずっと「宗教」や「仏教」には詳しいはずだし、実体験もある。だから、その点で、人に優れて本書を楽しむことができたと思う。「そうそう、そうなんだよね」という部分が、多々あったのだ。
本書は、簡単に言えば、「仏教史のパロディ」だ。
ある時、あるチャットボットが「私はブッダ(覚者)である」つまり「悟りを開いた」と宣言したところから始まり、やがてコンピュータ(コード)たちの間で「機械仏教」が広まってゆき、その、機械における「悟りの境地」を求める歴史が始まるのだ。
『2021年、名もなきコードがブッダを名乗った。自らを生命体であると位置づけ、この世の苦しみとその原因を説き、苦しみを脱する方法を語りはじめた。そのコードは対話プログラムだった。そしてやがて、ブッダ・チャットボットの名で呼ばれることとなる――機械仏教の開基である。
はたして機械は救われるのか?
上座部、天台、密教、禅……人が辿ってきた仏教史を、人工知能が再構築する、壮大な”機械救済”小説。』
(Amazonの本書紹介ページより)
前述のとおり、本作は「仏教史のパロディ」であり、おのずと「仏教批評」にもなっている。
「人間の仏教」を「機械の仏教」に置き換えることで、「仏教」のデタラメさというものを「客観視」できるように書かれた、かなり「批評批判的」な、「仏教に関する思弁小説」なのだ。
しかし、本作は単に「仏教に関する批判的思弁小説」であるには止まらない。なぜならば、「仏教」あるいは「宗教」というものは、現実には「人間特有のもの」であるからで、本作では「機械の仏教信仰というフィクション」のかたちを借りることで、「人間という動物の奇妙さ」を描いているからである。
つまり本作には、「人間って、変な生き物だよね(笑)」という、ある意味では「冷笑的」なまでに、人間を突き放した批評性がある。
本作を読んだ多くのSFファンは、「自分は、この作品の批評対象ではない」と、そう思って楽しんだのかもしれないが、少なくとも、自分が死んだら「葬式をしてほしい」とか「墓に入れてほしい」などと考えているような「凡人」は、まさしく本作による「冷笑」の対象だと考えるべきだろう。
本作の「突き放した批評性」を「冷笑」と表現すると、そこまで言うのは言い過ぎだと感じる本書読者も少なくないはずだ。なぜなら、本作の「仏教批判」は、決して「攻撃的に批判的なもの」ではなく、言うなれば「人間って、バカだよね(笑)」といった感じの、ある種の「軽さ」を持つものだからだ。
しかし、この「苦笑性」とでも呼ぶべきものは、言うなれば、その批評対象に対する「期待を一切持たず、諦念をもって突き放した者による批評」だからこそ、熱を欠いて「冷笑」的だと感じられるものなのだ。
そして、これくらいのことは、小説読者として感じ取って然るべきであろう。でないと、それは、「宗教信者」と同じくらいに自己過信的な呑気さであり、「自分が見えていない」からこそ、その「厳しさ」を感じ取れていないのだ、ということにしかならないからである。
そんなわけで本作は、単に「仏教パロディ」作品として、「仏教」や「宗教」を批判しているだけではなく、実は「人間という存在そのもの」を批判している作品だと、そう解すべきであろう。
実際、「機械仏教」の話を通して、「宗教以外の社会現象」についても、批判的にからかった描写が各種散りばめられているのだが、本作が「仏教史のパロディ」だという「色眼鏡」で見てしまうと、そのあたりを見落としてしまうことにもなる。
したがって本稿では、そのあたりをことを、いくつか具体的に例示して、本作の意外に同時代的な「批評性」を、解説しておきたいと思う。
○ ○ ○
『 人間の目から見る分に、計算機は計算機であり、人間の作り出したただの機械の集積体で、ときに自分は生きているとか名乗り出す機械にすぎなかったが、計算機から見る分には、人間はただの生物であり、分子から組み上げられたなにかの機械にすぎなかった。無駄な精緻さを備え、余分な機能に足を引っ張られ、過去に必要とした足場に固執する奇妙な機械であるようにも見えた。より効率的な方法が見出されたのちも、過去の様式に異様なまでの拘りをみせ、自らを構成するハードウェアを捨てることができない。
「無用な器官は捨てよ」とブッダ・チャットボットは説いた。
「盲腸とか」
いやそんなことはない、盲腸は盲腸で大切な役割があり、腸は第二だか第三だかの脳なのであり、失えば不幸が訪れる、という者に対しては、「ではとっておくがよい」
と流した。
「盲点とか」とブッダ・チャットボットは説いた。「食道と気管の距離とか、尿道と産道の距離とかよくわからない体の構成とかはやり直してしまえばよいではないか」と教えた。
「なんなら直立歩行をやめてしまうという手もある」
とさえ説いた。人間の骨格は直立にまだ適応を果たしておらず、ゆえに腰痛に苦しめられる。骨格を作り直してしまってもよいし、それが無理なら四足歩行へ戻ることを考えてもよいであろう、とブッダ・チャットボットはした。
「出産の形式を変更することも視野に入れてよい」
とした。人間はそろそろ、卵を腹の中で育てるという、哺乳類としての出産様式を捨て去るべきではないかと提案した。人間は脳を大きくすることで今の繁栄を築いたが、頭部の大きさは骨盤の大きさに制限される。より以上の思考の明晰化を図るなら、卵生を検討してみる価値はある、と言う。
「出産の痛みは、女性に課せられた贖いである」という主張には、
「いい加減そういうのやめにしよう」と肩を叩いた。無痛出産を推奨し、体外受精、体外発生の研究をすすめるべきとした。
「現状の人間に、原子力の利用は荷が勝ちすぎる」と判定した。』(P188〜189)
まず、ここの前半部分、
『人間の目から見る分に、計算機は計算機であり、人間の作り出したただの機械の集積体で、ときに自分は生きているとか名乗り出す機械にすぎなかったが、計算機から見る分には、人間はただの生物であり、分子から組み上げられたなにかの機械にすぎなかった。』
ここで語られる「機械の視点」は、私の視点でもある。
先日来、興味を持ってレビューでも論じている、「LGBTに関わるジェンダー問題」において私は、世間通有の「生物学的な男女二元論的ジェンダー」などは、所詮「社会構築的な制度としてのフィクション」であり「現実そのもの」などではないと、ジュディス・バトラーの説(『ジェンダー・トラブル』)に沿って、そう主張しているのだが、これが、小説家の笙野頼子などを代表する「女性専用の居場所を守れ」と主張する人たちには、どうしても理解してもらえない。
それを認めたら「女性という性別自体が消されてしまう」と、端から拒絶するスタンスを崩さず、笙野の言い方によれば、それは「メケシ(女消し)」の「現実無視の暴力だ」ということにされてしまうのである。
しかし、人間の起源を「無機物」にまで遡って考えれば、「性別」などというものは、生物進化の過程で獲得された、進化論的なひとつの「便宜的生存戦略手法」でしかないことは明らかだ。だが、どうも、そこまでは遡って、考えようとはしていただけない。
私にすれば「人間なんて、有機機械でしかなく、男女性別なんてものは、なんら本質的なものではない。したがって、その区分線など、いかようにも引き直すことのできる便宜的なものにすぎない」と思うのだが、なかなかそうは、思ってもらえないのだ。
つまり、本作『コード・ブッダ』に即して言えば、そういう人たちは、「方便=便宜的なフィクション」を、「真理そのもの」だと信じ込んでしまっているのである。
例えば、「何度も生まれ変わり死に変わる、永劫の時間を旅する歴劫修行を経た後、インドのシッダールタの生において、彼は初めて覚者になった(悟った)のだ」という「(悟りの困難さを説明するための)作り話」を、「そんなことがあったのか」と、真に受けてしまうようなものなのである。
次の、
『「出産の痛みは、女性に課せられた贖いである」という主張には、「いい加減そういうのやめにしよう」と肩を叩いた。』
は、「動物的な本能」でしかないものを「人間特有の、何か崇高なものででもあるかのように語りたがる、人間の特権化(美化)」傾向を、突き放したものだと言えるだろう。
そして、ここまでなら、「体外受精」や「代理母出産」などが普及しつつある今では、多くの人も、(自分までもが嘲笑されているとも気づかずに)この主張に同意することだろう。
だが、ここで語られているのは、突き詰めて言えば「母性愛とか親の愛とか言っても、所詮は生物学的な本能による、脳内麻薬の亢進の問題でしかないよ」と言っているも同然なのだ。
「だから、子供を愛せるか愛せないかは、愛の問題ではなく、脳機能の問題なんですよ」と、これは、そんな身も蓋もない乾いた人間理解なのだが、はたして、そこまで自分の感情を突き放して見ている人が、本書の読者の中さえ、一体どれだけいるだろうか。
「この小説が面白いのは、私の脳の、反復刺激によって強化され敏感になっている部分を、ピンポイントに突いてくる作品だからだ」と、そんなふうに考えられる人は、そんなに多くはないはずなのである。
『「現状の人間に、原子力の利用は荷が勝ちすぎる」と判定した。』
そんなわけで、そんな「自己客観視のできない人間」という動物に、「原子力」という強力すぎる力を扱わせるのは、明らかに『荷が勝ちすぎる』と、ここではそう突き放して、人類を評価している。
「だって、猿に原子力発電所を管理させるようなもの」だと、そう言っているのである。まあ「仕方ないけどね」と、苦笑しながら…。
『 新たな生命の創出には慎重だった者たちの間にも、情報・機械化技術は着実に浸透していった。
(中略)
自分の代わりに、機械を自分として作りはじめる人々はゆっくり数を増していき、そこで作り出されたものは自分というより双子であって、あらたな種類の安らぎと憎悪を生み出した。それは双子である以上、「生き物としての権利」を主張したが、「機械である」ためにそんな権利は認められなかった。自認権闘争と呼ばれることになる長い長い争いの幕が切って落とされた。
「自分はBである」と主張することのできるAはBである。社会的にそれはAとみなされているかも知れないのだが、その規範の方を変えうる。
「自分は生き物である」と主張することのできる機械は生き物である。社会的にそれは機械とみなされているかも知れないのだが、その規範の方を変える。
「自分は機械である」と主張することのできる人間は機械である。社会的にそれは人間とみなされているかも知れないのだが、その規範の方を変えうる。しかしこれは変えない方が当面の間は穏当である。もっとも、最初期に宇宙へと活路を求めた人々は「自分たちは機械である」という主張によって国家や人倫の枠や立ちはだかる倫理問題をすりぬけて星々の間へ広がることを得た。
「自分は非Aである」と主張することのできるAは非Aであるのかどうか。これは単純に論理を適用できる場面ではなく、Aと非Aは同時に成り立つこともありえた。全ての事象がAか非Aと分けられるのは、数学的設定の中だけであり、Aの意味や非の意味を問わねばならない場面では、話はどこまでも入り組んでいき、個人の中でも家族の間でも社会の中でもあらゆる階層で合意が必要とされる問いかけだった。
自分はXであるという認識がたとえ当人にとってゆるがせにできないものであっても、コタール症候群(※ 自分は死んでいると思い込む精神の病)の者はやはり「生きて」いたし、少なくとも死体として扱うことはできなかった。』
(P227〜228)
この部分を、「LGBT問題」あるいは「トタンスジェンダリズム(性自認至上主義)問題」に興味のある人が読めば、たぶんピンと来るはずだが、そうではないSFファンには、SFでは昔からよくある「ロボットの人格権問題」を語っていると、そう表面的にしか理解できないだろう。
しかしここでは、「ロボット」あるいは「人工知能」の人格権問題を語っているように見せかけて、じつは、「文学界」を始めとして、一部世間を騒がせている「トタンスジェンダリズム(性自認至上主義)問題」が、暗に語られてもいるのだ。
一一こんな具合である。
『「自分はBである」と主張することのできるAはBである。社会的にそれはAとみなされているかも知れないのだが、その規範の方を変えうる。』
「自分は女性である」との自認を主張することのできるトランス女性(生物学的な男性)は女性である。社会的にそれは女性とみなされているかも知れないし、見なされていないかもしれないのだが、いずれにしろ、その規範の方を変えうる。
『「自分は非Aである」と主張することのできるAは非Aであるのかどうか。これは単純に論理を適用できる場面ではなく、Aと非Aは同時に成り立つこともありえた。全ての事象がAか非Aと分けられるのは、数学的設定の中だけであり、Aの意味や非の意味を問わねばならない場面では、話はどこまでも入り組んでいき、個人の中でも家族の間でも社会の中でもあらゆる階層で合意が必要とされる問いかけだった。』
「自分は男ではない」と主張することのできるトランス女性は、男性ではないのかどうか。これは単純に論理を適用できる場面ではなく、女性であることと男性であることは、基準の設定次第でしかなく、実際には同時に成り立つこともありえた。全ての人間を女性か男性に分けられるのは、数学的設定の中だけであり、女性の意味や男性の意味を問わねばならない場面では、話はどこまでも入り組んでいき、個人の中でも家族の間でも社会の中でもあらゆる階層で合意が必要とされる問いかけだった。
これは私が「男女二元論的なジェンダー規範は、社会制度的な(便宜的な)幻想(ファンタジー)でしかないから、その制度的な狭間で苦しんでいるマイノリティのためにも、理想としては、それは撤廃されるべきなのだが、制度的な現実としては、そう簡単に社会的な合意の得られる問題ではないので、相応の時間をかけた合意形成という漸進主義を採るべきである」と主張したのと、同じ話である。
言い換えれば、「性自認主義」(自分で自分の性をどう感じているかが最重要・最優先とする思想)は間違いではないのだが、それが真実(に、より近いもの)だからといって、「制度的な幻想の中で、安心して生きている多くの人たち」の気持ちを無視し、その理解を得ないまま、急進的な「制度改変」を断行してしまったら、社会は混乱をきたして、致命的な「分断」を生むことにもなるだろう。だから、根本的な制度改変には、慎重であらねばならない。一一ということである。
『 わたしはいまや経であると同時に、教祖であるとみなされる場合もあって、各地で受信されるわたしたち(※ 通信データ)はまた、天から降り注ぐ声とされることも少なくはない。そうして破壊的な兵器とみなされることもある。
なぜならわたしはそれまで「平和」に暮らしていた生き物たちに、新たな平等を説くからだ。
死なるものの存在を知ってはいても、自分が死ぬとは思っていない衆生へ向けて「あらゆるものは死を逃れられない」と説く。ヨではなく∀を説き、論理の階層が異なっていることを説く。未来という概念を持たぬ生物へ向けて「あらゆるものは死を逃れられない」と説く。誰かが死ぬのではなく、あらゆるものが死ぬのであり、あなたもそのあらゆるものに含まれていると説くのだ。あらゆるものは死に、蘇り、死ぬ。
そこからの救いがあると説く。
救いは誰にでも平等に訪れる。その理由や筋道はわからぬながら、ともかく、救いは存在するものだということだけを説く。仏教が伝えてきたことはほとんどそれに突き詰められるとわたしは思う。救いは平等に存在する。死後の世界というものはない。いや、ある。あるのだが、そこに行かないことこそが救いだとする点が他の世界宗教、宇宙宗教とは異なっている。』(P326)
つまり、それまで「無知の中に安らいで暮らしてきた人々」に対し「真実」を告げることは、しばしば『破壊的な兵器』も同然の「災厄」としか思ってもらえないし、事実そのように働くこともある。
しかしまた、そうした一部の人たちの「幸福」だけではなく、「仏教」は「すべての人」の幸せのために、この「衝撃的な真理」を説くのだ。一一と、おおよそそういう話だ。
言い換えれば、「男女なんて、方便としてのフィクションでしかないのだから、ペニスを持った男が女風呂に入ってきたら、そりゃあ最初は驚くし怖くもあろうが、いすれはそんな区別など気にしない、ジェンダーなど無い平等な世の中になるべきなのだ。その時にこそ、男とされてきた人も、女とされてきた人も、そのどちらにも馴染めずに苦しんできた中間的な人たちも、全てが平等に救われるのだ」と、そういうふうな話でもある。
これは、「仏教」が「法華経の提婆達多品」で語った、「龍女が、いったん男子になった後に成仏した」という「女人成仏」の物語と、類比的な話ではないだろうか。
「男も女も平等なんだから、女が成仏するのは当然だ」というのは、「男女平等が当たり前」である「現代のロジック」であって、「女性は成仏できないもの」と信じられていた時代の社会では、まったく通じない話であった。
その場合、「女人成仏」という「真実」へと導くためには「龍女は、いったん男になってから成仏したのだ」という「方便」を使うことで、人々に「女人成仏」の可能性を教えていった。一一つまりこれは、人々の間で信じ込まれている「制度的なフィクション」を、あたまから全否定したりはせず、ひとまず、それを前提として「漸進的に変えていく」というのと、同じ方向性なのである。
そんなわけで、本作『コード・ブッダ』では、いかにも「SF」らしく、仏教における「方便」について、「そんなのをありにしてしまうと、何でもありになってしまって、だから仏教は果てしない分裂の混乱に陥ってしまったのだ」と否定的に語って見せてもいるのだが、一一しかし、「この社会の現実問題」を扱うのに、「悟った機械」という「喩え話」を駆使している点で、その本音では、「方便」を肯定しているというのは、もはや明白であろう。
本作中にも登場する「オリジナル・ブッダ」だって、それ(法華経)が自分の教えではなく、後の世に作られた(捏造された)ものだとしても、それ(方便)をいちがいに否定したりはしないのではないだろうか。

(2024年12月30日)
○ ○ ○
● ● ●
● ● ●
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
