
末木新 『「死にたい」と言われたら 自殺の心理学』 : 「死にがい」のある死なら、OKだ。
書評:末木新『「死にたい」と言われたら 自殺の心理学』(ちくまプリマー新書)
私が、「自殺」ということに興味を持つ理由は、端的にいって、それが「理解できない」からだ。
人間だれしも「死にたい」と思うことはあるだろうが、普通の場合、そういう状態が永遠に続くわけではないので、その「山」を越してしまえば、その苦しかった思いを、忘れてしまう。
また、後になって「あの時は、苦しかったなあ。でも、俺はそれを乗り越えて生きてきたんだ。だからこその、楽しいこともいろいろあるし、生きててよかった」なんて、いささか結果論的ではあれ、太平楽な感慨にふけったりすることもある。
それに、「死にたい」と思うことと、実際に「自殺行動」を行うこととの間には、大きな懸隔がある。
というのも、自殺したいと思っても、現実的にそれを考えた場合、嫌でも「どうしたら楽に死ねるだろうか? 苦しいのは嫌だな」とか「死んだら、俺の死体は、腐って見苦しいことになるんだろうな。そんな姿を、他人に見られるのは嫌だな」とか「あちこちに迷惑をかけることになるだろうな」とか「あの人を悲しませることになるだろうな」などと、いろいろ考えているうちに、自殺することのリアリティがなくなってしまい、なんとなく、辛いながらも生き続けて、いつの間にかその苦境から脱出している、というようなことが多いからだ。
じっさい、「嫌なこと」というのは、客観的に「嫌なこと」なのではない。
どういうことかというと、まったく同じ「嫌な事実」であっても、それを、どれくらい「嫌なこと」と感じるかには、大きな「個人差」があるからだ。
例えば、仕事でミスして「また、上司にネチネチと説教を喰らうだろう」という状況で、ある人は絶望的になって「死にたい」と思うだろうし、別の人は「1時間ほど、頭を垂れて反省していますというポーズをとりながら、適当に聞き流しておけばいいや」と考える。
このような「大きな違い」が、なぜ出てくるのかというと、それは「嫌なこと」というのは、客観的には存在せず、ある事実を「嫌なことだと感じる私がいる」だけだからである。
言い換えれば、どんなに「嫌なこと」であろうと、それを「嫌なことだと感じない私」がいたとすれば、その「ある事実」は「嫌なこと」にはならない。
例えば、脳の一部を麻痺させる薬があって、それを注射なり服用なりすることで「感情が働かなくなる」ようにすれば、たとえ、目の前で、自分の子供が殺されようと、世界が破滅しようと、その人には、それは「嫌なこと」だとは感じられないだろう。つまりそれは、「嫌なこと」ではない、ということだ。
たしかに、その人にも「ああ、息子が殺されてしまった」とか「ああ、これですべては終わりだな」という「事実認識」はあるだろう。「これは悲しいことだ」「残念な結果だ」と判断し、認識することは可能なのだが、しかし、薬によって「感情」が働くなっているから、「悲しいこと」だと分かっても、悲しくはならない。悲しいという感情が湧いてこない。「絶望的だ」と思っても、「絶望的な気分」にはならないのである。
つまり、「嫌なこと」とか「悲しい出来事」というのは、客観的には「存在していない」のである。
では、何が、客観的に存在しているのかといえば、それは、大多数の人には「嫌なこと」とか「悲しい出来事」と感じられるような「誘因的事実」とでも呼ぶべきものが存在しているだけ、なのだ。
「誘因的事実」とは、「そのような結果を誘い出す、原因的な事実」ということであり、これは「原因となりうるもの」ではあっても、決して「結果」そのものではないし、「必ず、その結果を引き出すもの(原因)」ではない。
事実そうだというのは、先の「薬物による感情麻痺」の例でもわかるだろう。
言い換えれば、この世の中には、客観的に「嫌なこと」とか「悲しい出来事」というのは存在しないのであり、存在するのは、それを「そのように感じてしまう私」だけなのだ。
極論すれば、「私が変われば」感じ方も変わり、これまでは「嫌なこと」だと感じていたことも、嫌とは感じなくなって、「嫌なこと」ではなくなってしまうのである。
そんなわけで、繰り返すが、「嫌なこと」とか「悲しい出来事」というのは、客観的には「存在していない」。
存在しているのは、それを「嫌なことだと感じる私」であり、これをもっと即物的にいうならば、それを「嫌なことだと感じてしまう、私の脳内物理学現象」が有るだけ、なのである。
薬物によって「嫌なこと」が「嫌なこと」で無くなるのは、それは「感じ方という、脳内の物理現象」だから(でしかないから)こそ、その「物理現象」を「薬物」によって操作すれば、「嫌なこと」が消えてしまうのだ。

そして、こうしたことは、私たちが日常的に行なっている、「物理的心理操作」でもある。
つまり、「感情的にしんどくなった」時や「ストレスが溜まった」時には、美味しいものを食べて寝るとか、カラオケに行って歌いまくるとかいうのがそれで、なぜ、こうしたことで「感情に変化が起こるのか」といえば、それは、これらの行為によって、脳の一部が刺激されて「脳内麻薬」が発出され、「興奮状態にある(過剰に励起された)感情」を抑えるからである。
では、なぜ、人間は、「ある状況」に置かれると(ある事実に直面すると)、過剰なまでに「負の感情」が励起されて、「嫌な気分」になったり「落ち込んだり」して、その感情を喚起した「状況」や「事実」を、「嫌なこと」だと感じるのだろうか?
それは、そうした「状況」や「事実」が、その人にとって「危険なもの」だからである。
「危険」なものを「危険」と感じられなくては、人間は容易に「死の危険」に晒されることになるだろう。だから「危険信号」として「嫌な感情」を励起して、「そこから逃げろ」とか「体勢をたてなおせ」とか「次の攻撃に備えろ」といった警告を与えているのである。
つまり、「嫌なこと」があっても、それに対して「嫌だ」と感じないような人は、「本能が壊れている」ということになる。「危機回避装置」が作動していないということであり、たしかにそんな人は「主観的には平和(能天気)」であり、側からはそれが好ましいことのようにも思えるかもしれないが、それも程度もの、だということなのだ。
言い換えれば、人間に必要なのは、いつ何時でも「平気(能天気)」でいられることなのではない。
大切なのは、必要な時には「嫌だ」と感じることによって「警戒」し体勢を整えて自己防衛するし、その必要がない時には力を抜いて、有事に備えるためにも「休息」しておくといった、適切な「切り替え可能性」なのだ。
したがって、人間は、常時「ビクビクしているだけ」あるいは「落ち込んでいるだけ」ではダメなのはもちろん、常時「のんき」で「太平楽」であってもいけない。
後者は、いかにも好ましそうに見えるけれども、それは「生物としての本能=生きるための本能」が壊れている、ということでしかないからで、そんな人は長生きできない。それは「痛覚がなくなった人」と、まったく同じことであり、「痛い思い」はしなくても、そのせいで「死の危険」にさらされるのである。

で、私がここで言いたいのは、過剰に「嫌なことが多い」と感じる人とか「自殺念慮のある人」というのは、要は「脳内の警報装置が、過剰作動している」のであって、決して、事実として「嫌なこと」が、山ほど世の中に存在している、といことを指すわけではない、ということである。
問題なのは、対象としての「嫌なことの存在」なのではなく、ある事実を、過剰に「嫌なこと」だと感じてしまう、その人の「脳機能状態」なのだから、そこを治療すれば、「嫌なこと」の大半は、消えてしまうという事実である。
しかしながら、これは、理屈でいうほど簡単なことではない。
もちろん、薬物によって、一時的に脳を麻痺させて「嫌なこと」を消すのは可能なのだが、それで「脳の癖」とも言うべき、その人固有の「感じ方」を変えられるわけではない。
たしかに、脳を麻痺させて「嫌なこと」を消すことできても、それはしばしば副作用的に「嬉しいこと」や「楽しいこと」も消してしまう。要は、「感覚の鈍麻」ということである。
こうした措置(強制的な感覚鈍麻)も、今まさに死のうとしている人に対してなら、緊急措置として必要なことではあろう。映画なんかでよくある、興奮状態で手がつけられない、自傷行為者に、ひとまず麻酔薬を注射する、というようなことだ。
しかし、こうしたことは、あくまでも「緊急措置」であって、治癒ということにはならない。
ただ単に感情を鈍麻させ、「嫌なこと」を消してしまうかわりに、「嬉しいこと」や「楽しいこと」も消してしまうのでは、生きている価値がない。あくまでも目指すべきは「過剰な反応」の部分であって、全体の機能を落とすということではないのだ。
しかしまた、では「嫌だと感じる感情」だけをピンポイントで消して、「嬉しい」「楽しい」と感じる感情だけを残せばいいのかというと、そうはならないというのは、前述の「いつも能天気なだけの人」ではダメだ、という事例のとおりである。
つまり、必要なのは、どのような「感情(情動)」も、「適切妥当」なだけ働くようにしなければならない、ということであり、当然のことながら、このような「ベストバランス」の実現というのは、きわめて困難なことである。実際、世の中にも、そんな「ベストバランス」を持った人など、一人もいないとも言えれば、個人差はあれ、たいがいの人は「ベターバランス」を持っている、とも言える。
つまり、「ベストバランス」なるものは、誰にもわからないし、それは、その人の置かれた状況によって、違っていて当然なのだ、ということでもあろう。
したがって、「体質改善」ならぬ、「脳の体質改善」というのは、容易なことではない。
そもそも、「ベスト」の状態というのは、「固定的なもの」ではなく、「変動的なもの」であり、目指すべきは「ベストな変動性」とでもいうべきものになるのだが、これはもう「理想」ではあるけれども、目標として設定できるほどの「具体性」を持たないものなのだ。一一では、どうするか。
要は、
(1)自分の感じていることは、客観的事実ではない(事実はあっても、その「感じ」は主観的なもの)ということを考えてみるということ。
(2)しかし、自分の感情というものは、自分の(感情を生む、自分の)頭だけではコントロールし切れるものではないから、具体的な、つまり物理的なコントロール方法を、常に準備しておき、何かあったら(嫌なことがあったり、落ち込んだりしたら)、とにかくひとまず、それをやって、物理的に「感情の変容」を促すということをする。
といったことだ。
つまり、「感情に囚われすぎてはいけない」けれども、一方「感情からは逃れきれない」から、「即物的に対処する」ということが重要であり、それは手近なところでは「美味しいものを食べて寝る」であったり「カラオケに行く」であったりするけれども、それですべてが解決するわけではないのだから、「ああ、今回のは、いつもと違って、かなりきつい」と感じた時に対応できるよう、常日頃から「相談する相手を作っておく」とか「病院へ行くのを躊躇しない」といった「準備」をしておく必要がある。

で、私が、こうしたことを、なぜ考えたのかといえば、たいがい「図太い人間」である私であってさえ、ごく稀に「落ち込む」ことはあった、からだ。
それが「永続的なもの」ではなかったからこそ、余裕のある時の私は、落ち込んでいた時の私を顧みて「あれは完全に、感情に取り込まれていたな」と、客観的に判断することができる。
「今となって客観的に見れば、たいしたことではなかったのに、過剰に心配していたな」とわかり、では「この次、同じような状況に置かれた時には、『この問題も、きちんと対処しておけば大ごとにはならず、いずれ過ぎ去ってしまうものでしかない』と、自分に言い聞かせよう」と考えるようになった。
要は、「心が弱っていた時の私」に、「私(本来の私)」は、負けたくないのである。
誰にも「支配されたくはない」から、そのような「自己コントロール」の手段を準備しておくのだし、その手段のひとつとして、「薬を飲む」「病院へ行く」ことも「躊躇しない」という「意志」をかためる。一一そこで躊躇するのは、「弱っている私」に負けている証拠であり、「負けそうな時には、頼れるものは何にでも頼り、使えるものは何を使ってでも、勝つ」というのが、「本来の私」であるとそう思っているのだ。
しかし、たぶん、私のように「強気」に考えられる人は、そう多くはないだろう。
言うなれば、私のこの「基本・強気」というのも、多分に「持って生まれたもの(才能)」と「生育環境」によるものであって、万人に等しく有るものではない。
私が「基本・強気」であるのと同様に、「基本・弱気」「基本・悲観的」な人というのも当然いるはずなのだが、「基本・強気」という構造を持ってしまっているために、私には、そうした人たちの「感じ方」は、基本的には理解できない。
だからこそ、その「基本・弱気」「基本・悲観的」な人の、最たるものである「自殺する人」とは「何なんだろう?」という、ほとんど私の「知解」の限界にあるものへの興味が尽きず、このような本を読んでいるということである。
だからこれは、私が「狂気」というものに惹かれるのと同じことで、「生物が、自分を殺す」というのは、基本的には同様のことだと感じられるからなのだ。
○ ○ ○
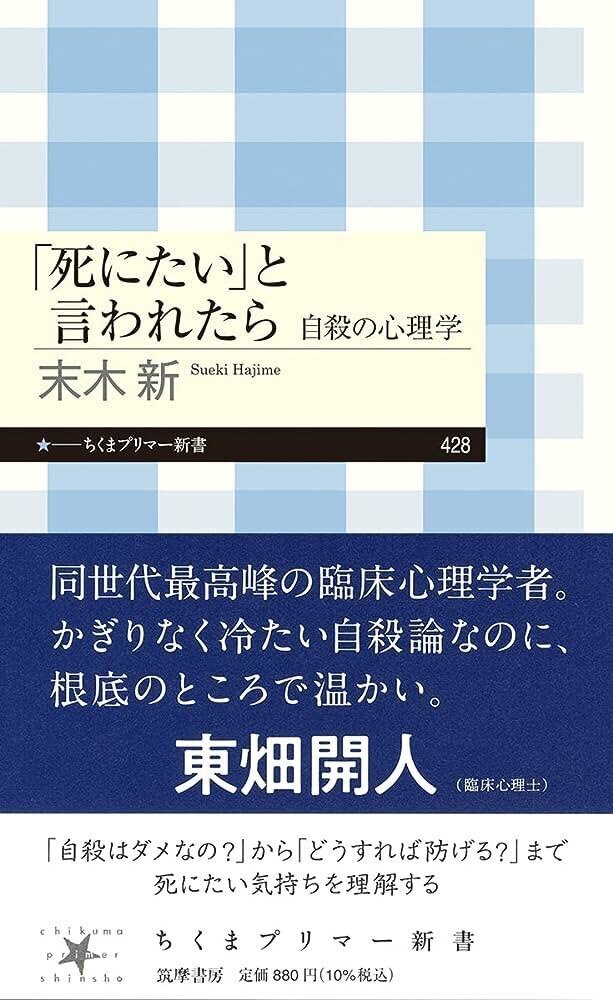
さて、本書であるが、本書の帯に、以前その著書のレビューを書いたことのある、臨床心理士の東畑開人が、次のような推薦文を寄せている。
『同世代の最高峰の臨床心理学者。かぎりなく冷たい自殺論なのに、根底のところで温かい。』
この、妙に「フォロー」に入った推薦文の意味するところは、本書を一読すれば、すぐに氷解する。
要は、著者である末木新は、「きれいごとの誤魔化し」を言わない人なのだ。
事実を、「科学的」に「客観的」に語ろうとするから、「きれいごと」や「甘い言葉」に馴らされた人には、著者の物言いは「冷たい」とか「配慮に欠ける」ように感じられる。
だが、無論、私の場合は、そんなふうには感じない。
本書著者もまた「基本・強気」の人であり「攻めの人」であるから、「誤魔化さないことで、打開できることがあるはずだ」と信じて、「科学的」「客観的」な事実を隠そうとはせず、それを示した上で、それと真正面から闘おうとするのである。一一つまり、著者は、徹頭徹尾「本気」なのだ。
本気で「自殺を無くしたい。無くすことはできなくても、少しでも減らしたい」と考えるから、刺激的な事実であろうとも、それが対処の必要なことであれば、隠したりはせず、「ここが問題なのだ」と示して、問題提起をする。
だから、本書著者は、推薦者の東畑開人がいうような『温かい』人というよりは、端的に「熱い人」なのである。
たとえ人から「冷たい」やつだと思われてもかまわないと、そんな覚悟を持っているからこそ、一見「冷たい」とか「配慮に欠ける」といったような言葉も、わかっていながら口にすることのできる、覚悟の人なのだ。
そして、そうした基本姿勢を、最も端的に表したのが「自殺は、本当のいけないことなのか?」という、挑発的な「問い」である。
当然のことながら、私たちは普通「自殺はいけないことだ」と言う。
だが、心の底から、本気でそう言っているのかといえば、たいがいの場合は、そうではない。
つまり「基本的には、自殺はいけないことだ。ただし、安楽死のような例外はある」といったことなのだ。
言い換えれば「自殺は何があっても、絶対にいけない」と言う人がいたら、その人は「自殺」について、本気で考えたことがないか、建前を口にしているだけかの、いずれかなのであろうということだ。
だから、著者はあえて「自殺は、本当のいけないことなのか?」と問うことで、読者に対し、「自殺」について、本気で考えることを促すのである。
では、著者自身は、本書において、この「問い」について、どう答えているのかというと、当然のことながら「場合によっては、自殺して良い」ということになる。
「自殺」は、総体として「自明な悪」なのではなく、「多くの場合に悪」であるにすぎないのだから、そうした「悪」を避けられるのであれば、その「自殺」は「喜ばしい自殺」になるはずだ、というロジックである。
そして、このロジックは正しいと、私は思う。
たとえば、海で溺れた子供を救うために、泳げない人が、思わず海に飛び込み、その結果、溺れ死んだとする。
この場合、多くの人は、それが「自殺行為(に等しい)」と考えるが、仮に子供を救えなかったとしても、彼の死が、決して「無駄だった」とは思わないだろう。
なぜなら、彼の「無私の行為」が、「人間の尊厳」の実在の証しとなり、「人間も捨てたものではない(絶望しなくても良い)」と感じさせてくれるものだからだ。
だから、上の例では「死ぬ覚悟をして、死んだ」わけではないとしても、同様の理由で「自分の命と引き換えに」という自覚があってなされる「自殺的行為」も、それは認められるべきだろう。
たとえば、自らの身の危険を顧みずに、危険な場所に入っていくジャーナリストや戦場カメラマンといった人たちは、ハッキリと「死の覚悟」まで持っており、だからこそ、それができるのである。
したがって、そうした行為は、今ここで死ぬということではなくても、一種の自殺だと考えていい。「自分の命と引き換えに、大切な何かを得る(守る)」という条件付きではあっても、それは「延長された自殺」とでも呼ぶべきものなのだ。

で、本書著者が語っている「好ましい自殺」「容認されるべき自殺」というのも、こうしたことなのである。
著者が挙げているのは(私が上に挙げたような例ではなく)生物学的な例が中心で、例えばそれは「産卵を助けるために、交尾のあとに、メスに食われてしまうオスのカマキリ」とかいった例である。
なぜ、こうした「自殺的行為」が、進化的なものとして生まれてきたのかといえば、それ以上の「代償」が、そこにあったからであり、その意味で、こうした「自殺行為」は(誰も悲しませずに、利益を最大化する)好ましいものであり、人間の場合にだって適用できることであるはずだ、という立論である。
本書著者の、こうした「冷たい」議論のタネを明かしてしまえば、要は、著者がここで考えているような「好ましい自殺」や「理想的な自殺」というのは、現実には、容易なことではない、という点にある。
たとえば、自殺を選ぶにしても、家族、友人知人、同僚など、すべての人が、その人の「自殺」に納得してくれるだけの「価値のある自殺」でなければならない。
「立派だったぞ。お前の選択は間違っていない」と、他人に言わしめる自殺などというものは、おいそれとはあり得ないというのは自明なことである。事実、自殺する人の大半は、自らの「感情」に呑み込まれていて、周囲のことなど気にする余裕もなく自殺するからなのだが、本書著者に言わせれば、当然それは「好ましい自殺」や「理想的な自殺」ではないから、そんな「自殺」は許されない、ということになるのだ。
つまり「自殺は、自明に悪であり、絶対に許されない」というような決めつけは、思考停止でしかなけれども、だからといって「どんな自殺も許されるというわけではない」のだから、「正しい自殺の条件」が揃っていないような自殺は、絶対に防がなければならない。
私たちは「自らも喜んで、他者からも祝福されるような自殺(覚悟の自死)」を目指して、今を懸命に生き抜くべきだ一一というのが、著者の議論なのだ。
だから、著者は、決して「冷たい」人ではないし、ありきたりに「温かい」人でもない。
著者は、本気の人であり、だからこそ、稀有なまでに「熱い」人なのである。
(2023年8月1日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
