
岸政彦 『断片的なものの社会学』 : ラノベ的な「ライト学問」
書評:岸政彦『断片的なものの社会学』(朝日出版社・2015年刊)
本書は「紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞」作品であり、ベストセラーにもなった本である。
私も「紀伊國屋じんぶん大賞」は、書籍購入の参考にしているので、この年のことも記憶しているし、もしかすると本書も買ったかもしれないのだが、例によって、結局は読んでいなかった(すでによく売れていたから、古本待ちにして、買わなかったかもしれない)。
先日、私が「note」にレビューを書いたのと同じ映画について書いている、他の人の「note」記事に本書からの引用があったので「そういえば、こんな本があったな」と思いだして、今さらながら、ブックオフオンラインで購入したという次第である。

で、読んでみての率直な感想は、
(1)面白くないことはないけれど、大したことはない。
(2)そもそも「社会学」書ではない。
という、身も蓋もないものであった。
(1)と(2)は、密接に関連していて、要は、本書が「社会学の本」ではなく「社会学関連書」であり、要は、
・社会学者が書いた「哲学的エッセイ」にすぎない。
のだ。
本書の眼目は「社会学では掬い上げられない、断片的なものについて考える」ということであり、言い換えれば、これは、本書に書かれているのは「社会学」的なものではなく、むしろ「反社会学」的なものだとすら言えるのである。
ただ、著者が「社会学者」だから、タイトルに「社会学」と付けられているだけで、半ば「タイトルに偽りあり」の本なのだが、そもそも、この本を無邪気に楽しめる人というのは、「社会学」そのものに興味が無いか、重きを置いていない人たちだろうから、そうしたことは問題にもならないのだろう。要は、売れれば勝ちなのである。
もちろん、「社会」を論じてさえいれば「社会学」だという考え方もあって、その意味で、本書を「社会学の本」だと強弁することも可能だろう。
だが、それを言うなら、多少なりとも「社会」と関わる「純文学」も、「社会派ミステリ」も、未来社会を構想する「未来SF」も、「社会派の評論」も「社会派のエッセイ」も「社会派の哲学」も、みんな「社会学」の一種だということになってしまうが、そんな夜郎自大な定義が無意味なのは当然として、それはいかにも愚かしい自己正当化にすぎない。
「社会学」の、最も基本的な「定義」とは、次のようなものである。
『異なる価値観をもった人間が多数集まって形成される社会はひじょうに複雑な関係で、理解するのも予測するのも難しい動きをみせます。天気の予報はできますが、「社会予報」が難しいのはこのためです。社会学は、調査とデータをふまえて社会の現実を理論的に理解しながら説明しようとする科学です。このような知識をもつことで、より社会を深く理解しながら、社会を変えていくための手立てを広く提案することが可能になります。』
(日本社会学会「社会学への誘い」・「社会学の定義」より)
つまり、社会学というのは「人間にはいろんな人がいる」というのは、「自明の前提」とした上で、「社会」というスケールで「人間行動」を客観的に考えていこうとする「客観主義的な学問(科学)」だということである。
したがって、「社会学」が示す「人間行動」から外れている「個人」がいるのは当然だし、それを「どうでもいい」と思っているわけではない。
けれども、まずは「人間の全体的な傾向性」を把握した上で、個々の問題も考えていこうという、そうした方向性の学問なのだ。
つまり「まずは、大局観を持とう。そのうえで、個々の問題を見ていけば、大きく誤ることはない」という、しごく良識的な考え方であり、その一方、「俺は特別な人間だ」などとアピールしたくて仕方のない「ありふれた人」には、あまり歓迎されない学問だと、そうも言えるだろう。
言うなれば、
「あなたは、ご自分では、個性的だとそうお考えかもしれませんが、意外にそうではないのですよ。なにしろ、宣伝に踊らされてベストセラー本に群がり、有名推薦者の言葉を鵜呑みにして、自分でもわかっているつもりになっているようなあなたが、個性的な人であるはずがないでしょう。でも、人間とは、そういうものなのですよ。自分では、個性的な動きをしているつもりでも、大局的に見れば、似たような動きしかしていない、今で言うところの「モブ」なんです。ですから、まずはその似たような動きの法則性を見つけようというのが、社会学という学問なんですよ。だから、あなたももう少し謙虚になって、自分がいかに平凡なことしかやっていないかを直視すべきです。それを十分に踏まえなければ、個性的であることなんか出来っこありませんよ」
と、そういう話なのである。

そんなわけで、本書『断片的なものの社会学』というのは、著者がどう言い繕おうと、基本的には、「社会」や「全体」には還元できない「断片としての個人」の大切さというものを、「今さらながらにアピールする」もの、にしかなっていない。
「断片的なものにこそ、真実が宿る」というのは、言うなれば「当たり前の話」でしかない。
というのも、「社会」や「全体」といったものは、「概念」であって、それそのものは「実在せず」、実在するのは「千差万別で、どれひとつとして同じもののない個々」だからである。そんなのは「わかりきった話」なのだ。
だが、「千差万別」であるはずの「個々」が、では、どこから見ても「個性的」かと言えば、そんなことはない。「個体=個性的な存在」ではないのだ。
実際のところ、多くの人は、「似たようなもの(微視的な個体差の範囲内に止まる存在)」であり、その意味で「凡庸」であるからこそ、「私を私(個別的存在)として承認してほしい」という承認欲求が、この社会には蔓延しているのだ。
「どうだ。私は、他に二人といないほど個性的だろう」と、そう自信を持って言える人など、ごく一部でしかなく「99パーセント」の人たちは、所詮「無個性な、その他大勢」としか見えないし、当人も、自分が「その程度のもの」だとしか感じていないからこそ「個性を認めてほしい」などと考えるのである。
つまり、今の世の中は「大局に立った客観的な認識」を欲するほど、自身を確立した人が少ないからこそ、「客観的な学問」は忌避され、「個人に寄り添ってくれる(かのような)」ものが、ありがたがられるのだ。
要は「優しい声をかけてくれる人は、良い人」であり、「君はここが問題点だから、ここを直した方がいいよ」などと言ってくる人は「上から目線の嫌なやつ」だと、そういう子供じみた認識なのである。
そんなことだからこそ、「社会学」的な「大局に立った客観的な認識」ではなく、「断片」の側に立って「小さな個別性こそが大切なのだ」と、自身を「断片的な存在だと思っている人たち」に寄り添っている(かのような)ものが、ありがたがられる。「私のことを、好きだ、大切な存在だと言ってくれる人が、良い人」なのである。
しかし、こんな「甘っちょろい」世の中だからこそ、いつも言うように「特殊詐欺」だの「投資詐欺」だのに引っかかる人が後を立たない。
こうした「馬鹿を馬鹿だと思って、カモにしている人たち」は、決して私のように、馬鹿に対して「あんたは馬鹿だ」とは言わないで、「いえ、あなたは、もののよくわかった人ですよ。私には、あなたのことがよくわかります」などと、うすら寒いお世辞を、平気で口にする、プロなのだ。一一そして、本書も、基本的には、そういう本だからこそ、「寂しい」人たちは、本書に「ありがたく縋ってしまう」のである。
○ ○ ○

では、どうして「この程度の本」を、多くの著名人が推薦したのかと言えば、それは次のような理由からだ。
(A)左派的な「弱者に寄り添う立場」への支持表明(自家宣伝)
(B)エリートらしい「社会的底辺者」に対する「オリエンタリズム」的な関心
(A)は、わかりやすい話だと思う。要は、「弱者に寄り添う強者」は、単なる「強者」には見えない。だが、彼ら自身は、実際のところ「強者になりたくて強者になった人」であって、自分自身が「弱者」になろうとは思わない。ただ「弱者の味方」であることをアピールしておけば、「弱者」からの妬みの標的にはならないし、それどころか「弱者の教祖」として、ありがたがられるのである。

(B)は、要は、主に「大学の先生」をやっているような「知的エリート」のことだが、こういう人というのは、基本的には、(例えば)大阪の下町の薄汚れたおっちゃんとかおばちゃんとは縁がないものだから、そういうものを読ませてもらうと「珍獣」を見せてもらうようなものだから、ありがたいということである。
ここで言う「オリエンタリズム」というのは、エドワード・サイードがその著書『オリエンタリズム』(1978年)で批判的に語ったところのそれで、要は、先進的で「文化の中心である西欧世界」から見た「(遅れた)東洋」への、倒錯的な憧れや賛嘆を言うものだ。
心の底では「東洋(オリエント)」を劣ったものだと見下し、かつ「進んだ西欧文化の中で、恵まれた生活を享受し、それを手放す気などさらさらない」にもかかわらず、その反動としての一種の「贅沢病」的な感性から、「貧しさの中にこそ、人間の真実がある」などという「いい気なこと」をのたまう西洋知識人の、自覚を欠いた「度しがたい上から目線」こそが、サイードの言う「オリエンタリズム(東洋趣味)」である。
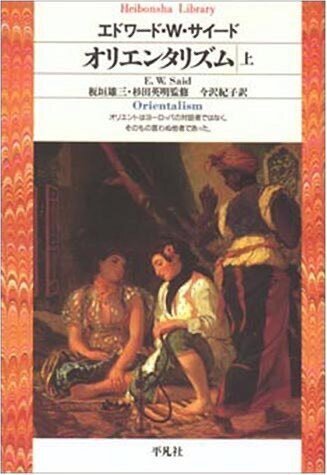
つまり、本書を絶賛するような「知的エリート」たちは、「西成の労務者のおっちゃんたち」と生活を共にしようなどとは金輪際考えない。
ただ、たまには、そういう「珍獣」を、檻の外から眺めて、餌を投げ与えてやったりするのは、自身の「優位」の確認にもなるから「楽しい」と、ただそれだけの話なのだ。
それだけのことで、「醜い珍獣にも優しい人(理解のある人)」だと思ってもらえるのなら、こんなに安上がり自家宣伝もないのである(現に著者は、自身を成功者だとは認めず、小さな者の一人であるかのように、しきりにアピールしている)。
○ ○ ○
そんなわけで、本書は「珍獣が見たいエリート」か、「自分は珍獣ではなく、エリートの側の人間だと思いたい珍獣」のための本だと言っても良いだろう。
そんな人たちには「大局に立った客観的な視点」など、疎ましいだけなのだ。
「知的エリート」ならば、「大局に立った客観的な視点」など、「すでにそんなものは、自分は十分に持っているから、今さらそんなものはいらない。そんな抽象的な動物行動学ではなく、珍獣を見せてくれ」ということになるし、所詮は自分が珍獣でしかないことを薄々感じていればこそ、その事実を認めたくない珍獣たちは「大局に立った客観的な視点」など、決して興味を持つことはなく、しかし、自分は「地を這う珍獣」ではなく「高みにあるエリート」だと思いたいものだから、『社会学』というタイトルさえついていれば、その中身を問うこともなく、「学問の権威」をありがってしまう、権威コジキなのである。
したがって、本稿のサブタイトル「ラノベ的な「ライト学問」」というのは、お手軽な「ライトノベル」が「文学」なのかどうかはわからないが、ひとまず「とっつきにくい文学」の代わりに重宝されているものであるのと同様に、本書も「とっつきにくい学問(としての社会学)」の代わりとなる「ライト学問」なのであろうと、そういう意味だ。
もちろん、「ラノベ」(の多く)が「文学」と呼ぶに値するものかどうか、かなり疑わしいのと同様に、本書も「学問」と呼ぶに値するものかどうかは、かなり疑わしい。
本書が、「社会をめぐる思弁的なエッセイ」だというのなら、何の問題もないけれど、「社会学」とつけているところが、いかにも安直な「ペテン」である。
もちろん、「聞き取り調査」も、社会学の重要な一部なのだから、その意味で「社会学」と呼んでも、嘘ではないだろう。
だが、そうして集められたデータを元にして「社会」を総体的に捉えようとする視点に反発して(あるいは、実質的に、軽んじて)、ことさら「個別性」にこだわるのであれば、「社会学」の看板の権威を借りるのではなく、「社会的なエッセイ」と名乗るべきであろう。ただの「エッセイスト」として、本書を書くべきだったのだ。
そして、本書を、単なる「社会的なテーマを扱ったエッセイ」と見るならば、存外「凡庸」であり、この程度のことなら、昔から多くの「文学者」が、エッセイだの随筆だの中で、いくらでも論じてきたものであろう。
だが、本書をありがたがる読者の大半は、本書の推薦者を含めて、そうしたものをほとんど読んでいないのだろうと、そう大いに疑われるのである。
(2024年2月29日)
○ ○ ○
