
岡本亮輔 『宗教と日本人 葬式仏教から スピリチュアル文化まで』 : 〈信仰なき宗教〉 の不気味さ
書評:岡本亮輔『宗教と日本人 葬式仏教からスピリチュアル文化まで』(中公新書)
本書は、採り上げられる話題の多彩さとその個々の面白さに目が捕らわれがちなのだが、見逃してはならない本書固有の重要ポイントは、「信仰なき宗教」というものの「不気味さへの着目」である。
じつのところ、最初は私自身が、本書を舐めていた。「まえがき」から「第2章」までを読んでいる間は「方法論を力説するわりには、書いてることはありきたりだな。宗教を表面的に捉えすぎていて、宗教というものの怖さがわかっていないんじゃないか」と、そんな印象を受けて、いささか退屈だったのだが、我慢して読んでいくと「第3章」から「おやっ?」と気にかかる指摘が目に付きだして、著者の語り口も、にわかに「重み」を増していったのである。
本書は、決してわかりやすいものではない。
わかりやすい「部分」というのは、集められた「素材」の面白さであって、著者の問題意識の「重さ」は、見過ごされがちなのではないだろうか。それは著者による、次のような言葉にも表れている。
『編集部につけて頂いた過分なタイトルからお察し頂けるかと思うが、テーマが明確だった前著(※『聖地巡礼』)と比べ、本書は扱う対象が大きく、構想段階での足踏みが長かった。何度も原稿を読み込み、本書を形にしてくださった同氏(※ 担当編集者)には御礼の申し上げようもない。』
(「あとがき」P215~216より。※は引用者補足)
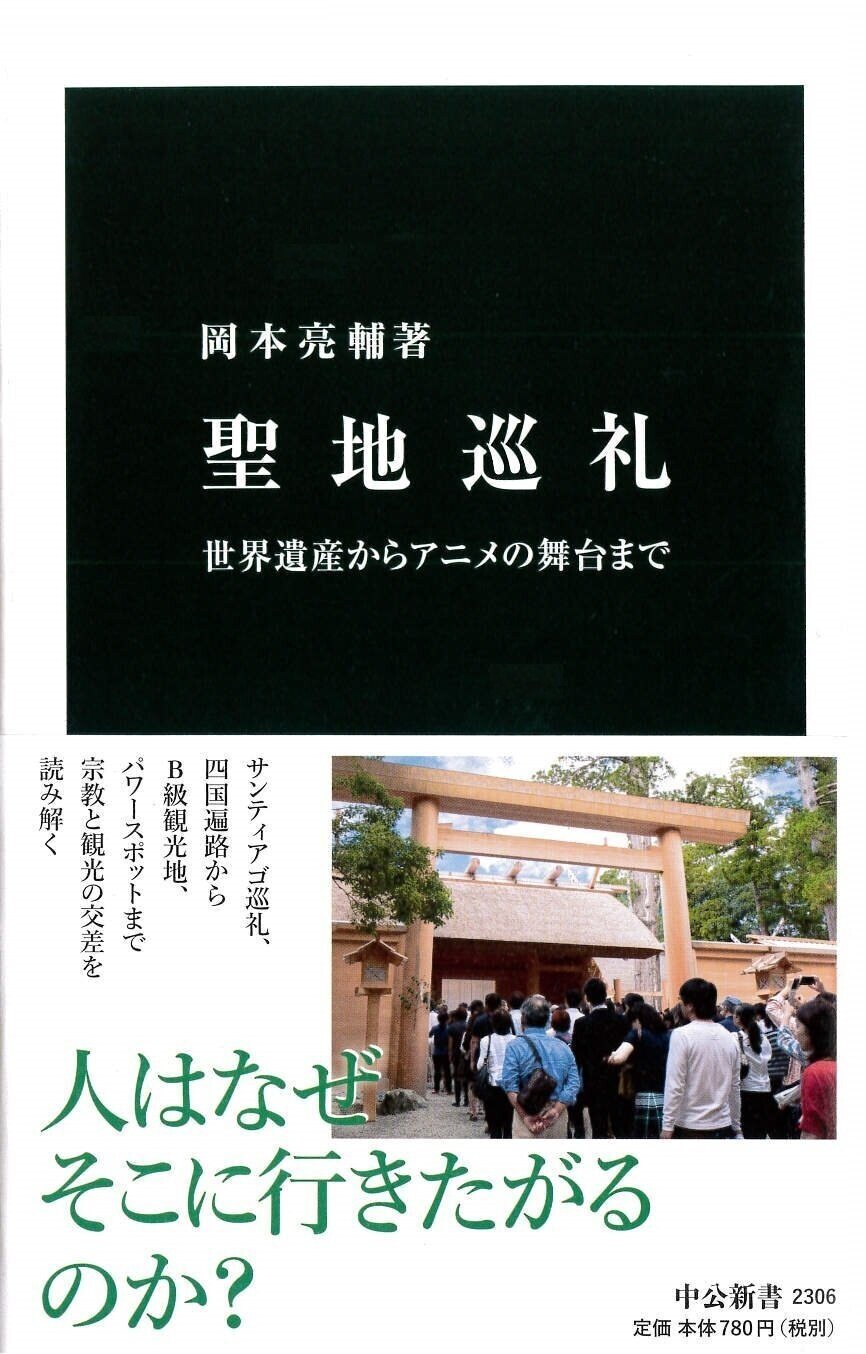
ここで著者が語っているのは、本書の売りは「個々の話題」ではなく、その背後に通奏低音のごとく存在する「日本人特有の宗教性」だということであり、その「固有性」を、これまでの学説の範囲で再説するのではなく、新たな言葉で語ろうとして悪戦苦闘した、という話なのだ。
したがって、著者の語りたかった「日本人特有の宗教性」についての「新しい理解」というのは、必ずしもうまく言語化できておらず、おのずと読者にも伝わりにくいものとなってしまっている。だからこそ私は『本書は、決してわかりやすいものではない。』と書いたのだ。著者が最も語りたかった肝心の部分については、読者が「楽しく読める」ような、わかりやすいものには出来なかった、ということである。
では、著者が語りたかった「日本人特有の宗教性」についての「新しい理解」とは、何か。
それは、著者が本書で繰り返す「信仰なき宗教」という言葉に、隠れているものなのであろう。
通常、「宗教」というものは「信仰(心)」を前提としている。「信仰」があってこその、「教義」や「教祖」や「教団」や「儀式」であって、肝心の「信仰心」がなければ、それらはすべて、その人に自覚があろうとなかろうと、「形骸化」した「宗教もどき」であったり「信仰ごっこ」にすぎない、ということになるだろう。
少なくとも、明確な「信仰心」を持つ人、(例えば、キリスト教の)自覚的信仰者であれば、「形だけの信仰」などというものはありえず、それは「偽物の信仰」でしかないし「宗教の名に値しない」ということになるだろう。
ところが、日本人の「宗教」というのは、もともと「信仰心」というほどの明確なものがなく、「形式」にすがることで「安心感」を得る類のものでしかなかった。だからこそ「厳格な形式規定」がなく、状況によって「ご都合主義的」かつ「融通無碍」にかたちを変えて、人々の「需要」に応えてきたし、人々も、そんな(ある意味で「いい加減」で「適当」な)「宗教」に疑問を持たないばかりか、むしろ、ありがたくそれに「依存」してきた。
実際のところ、「教義」や「教祖」や「教団」や「儀式」といった「宗教形式」にこだわりのない態度とは、「信仰」とは言い難い。「信仰」とは、それらをすべてひっくるめて「唯一の絶対真理」だと総体的に「信じている」という態度なのだから、それらが「どうでもいい」などということになど、なるわけがないのだ。
つまり「信仰心」とは、「宗教」が「主」であり、「私」は「従」である。「従である私」は、より素晴らしいものとしての「主である宗教」に、「私」のすべてを投企するのが当然で、それこそが「信仰」なのである(ということになる)。
一一ところが、日本人の「宗教心」とは、昔から、そして今もまた新たに、実は「そのまま」なのだ。つまり「信仰のない宗教」でしかないのである。
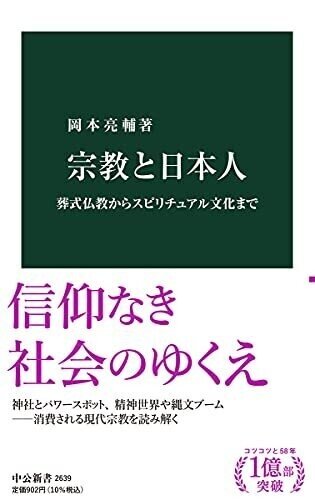
くりかえすが「信仰のない宗教」とは、元来「宗教」の名には値しないものだし、当然のごとく、そのように考えられてきた。それは「エセ宗教行為」であり「宗教ごっこ」でしかなく、その実態は、単なる「依存」でしかなかったと、そう理解されてきたのだ。
しかし、問題は、その依存対象が「宗教的な形式」を取っている場合、それがいかにこれまでの「宗教」的な内実を持っていなかったとしても、それはそれで「一種の宗教」なのではないのか、ということなのだ。
そして、私たち日本人の「宗教」とは、本質的な部分では、昔からずっと「信仰なき宗教」であり「依存目的の宗教的形式利用」という「奇妙な宗教」だったのではないだろうか。
明確な「信仰心」に基づく「信仰」というのは、わかりやすい「宗教」であり、それについては、その美点も難点も、研究的な蓄積がある。
しかし、そうした旧来の枠組みにおいて、これまでは「日本特有の宗教」を、誤って「エセ宗教行為」であり「宗教ごっこ」、所詮は「信仰なき宗教」であり「依存目的の宗教的形式利用」でしかないと、軽視してきたのではないか、舐めてきたのではないか。しかしそうした不用意な傲慢さは、果たして正しかったのだろうか。
くれぐれも言っておくが、私はここで、「日本には日本の信仰形式があり、それは西欧的な信仰観で正しく評価することはできない。日本の信仰には、日本の信仰固有の高い価値が存するのだ」などいう、ありきたりな「日本すごい」論を繰り返したいのではない。
私が言いたいのは、この「信仰なき宗教」「宗教らしからぬ宗教」という「奇妙な宗教」は、これまで見逃されてきた「宗教」として「危険なものなのかもしれない」ということなのだ。
一見「お遊び」めいていて「無害そう」なのだが、だからこそ「宗教らしい宗教」「明確な信仰心に支えられた宗教」とは違った、気づかれにくい「危うさ」を秘めたものなのではないか。
そして、著者が本書で言いたかったことも、これに近いことだったのではないだろうか。
例えば、近年流行の「(アニメの)聖地巡礼」など、見るからに「商業主義的」で、宗教的にはいかにも「無害」に見えるけれども、そういう「宗教に見えない宗教」の方が、かえって、気づかないうちに、人を害する「宗教性」を蔵してはいないだろうか。例えば、「現実」との関係を失わせる「新たな毒」といったものを有してはいないだろうか。

自覚的な「無神論者」である私は、これまで「宗教の害悪」を問題にしてきたけれど、本書に教えられたのは「宗教の名に値しないような宗教もどき、というメタ宗教」の危険性ということだったのである。
初出:2021年5月10日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
再録:2021年5月23日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
