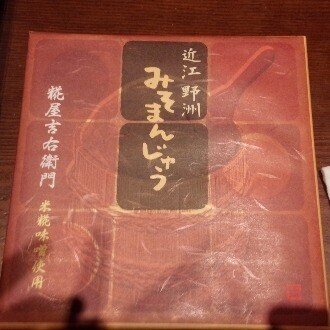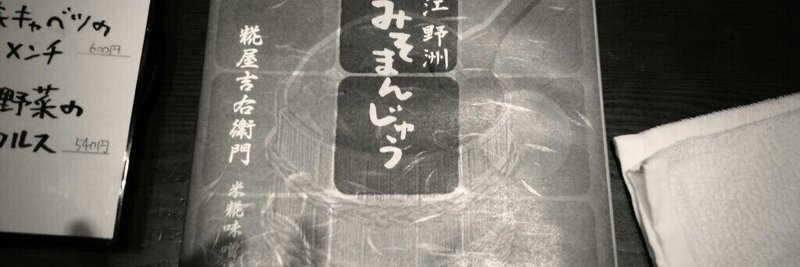
- 運営しているクリエイター
記事一覧
【書評】E・H・カー『歴史とは何か』(清水幾太郎訳)
今年、E・H・カー(1892-1982)の『歴史とは何か』(原著は1961年)の新訳が刊行されて話題となっている。60年振りの新訳とのことであるが、筆者はまだその新訳のほうを読んでいない。とはいえ、筆者はかつて歴史学を専攻していた学生であり、新訳の刊行を機に、60年前に刊行された岩波新書版(清水幾太郎訳)のほうを思い出し、手に取り再読し、歴史研究にまつわる事柄をあれこれと考えることとなった。
【書評】カフカ『変身』
本作は、プラハ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国領)の富裕なユダヤ人家庭に生まれた小説家フランツ・カフカ(1883-1924)の最も知られた小説作品である。カフカは、大学で法学を学び、裁判所での実習の後、体調不良ゆえに退職となるまで労働者傷害保険協会に勤め、その傍ら、その多くが未完となる小説を書き続けている。そのなかの一つが『変身』であるが、生前のカフカは無名の小説家であった。注目を浴びるのは
もっとみる【書評】マックス・ヴェーバー『職業としての政治』
本書は、マックス・ヴェーバー(1864-1920)による学生に向けた講演をまとめたものである。この講演が行われたのは、ヴェーバーの死の前年の1919年であると推定されているが、本書は、「政治」という概念を社会学的に定義するところから始まる。あくまで限定的な意味においてである。「今日ここで政治という場合、政治団体――現在でいえば国家――の指導、またはその指導に影響を与えようとする行為、これだけを考
もっとみる【書評】米原謙『山川均――マルキシズム臭くないマルキストに――』
本書はミネルヴァ書房の「ミネルヴァ日本評伝選」シリーズの一冊であり、社会主義者であった山川均(1880-1958)の幼少期から晩年に至るまでを仔細に叙述した伝記である。筆者が山川の名を知ったのは、大杉栄(1885-1923)というアナルコ・サンディカリストを調べていた頃である。山川は大杉と同時代人であり、思想的立場は違えど、ともに日本の社会運動の発展を語る上で欠かせない人物である。山川は共産主義
もっとみる【書評】時枝誠記『国語学史』
本書は、日本を代表する国語学者である時枝誠記(1900-67)によって書かれた国語意識の展開の歴史である。それは、元禄期以前から現代にまで及んでいる(と言っても、本書の初版の刊行が1940年であることから、昭和初頭までになる)。しかし、それは単なる歴史叙述ではない。時枝はこの翌年に、『国語学原論』という時枝自身の体系的著書を出版している。実を言うと、『国語学原論』執筆の経緯に、『国語学史』の執筆
もっとみる【書評】島田雅彦『カタストロフ・マニア』
何年か前に何度か、島田雅彦氏がコメンテーターとしてテレビの情報番組に出演しているのを見たことがあるが、某元野球選手が薬物事件で逮捕された際に、キャスターだった下平さやか氏から意見を求められた。詳しい内容までは覚えていないが、ありきたりなテレビ用の紋切り型のコメントに終始していたように思う。この数年前に行なわれた文芸誌での対談における島田氏の発言を引用しておく。
島田 直近の上の団塊は中上(健次