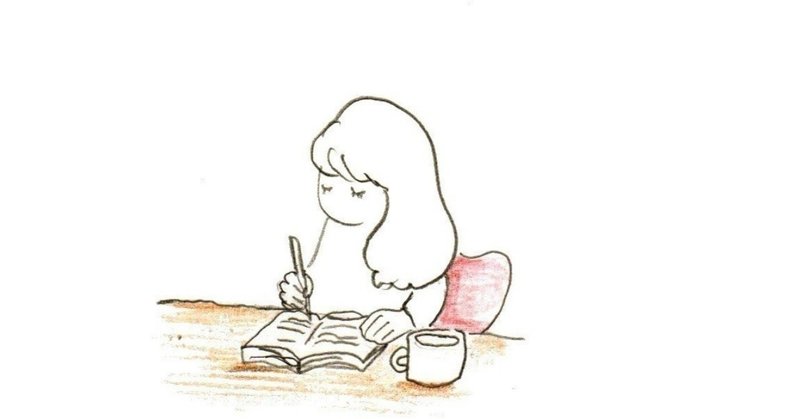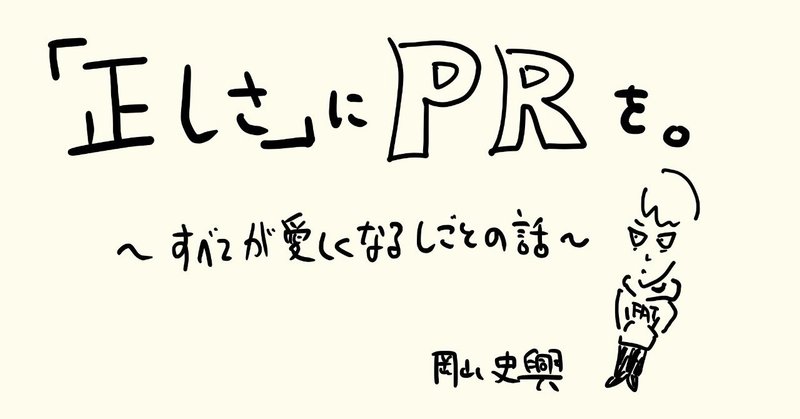#エッセイ
「モダン・ラブ」でアン・ハサウェイ演じる躁鬱病の女性がリアルすぎて辛い
今話題のアマプラオリジナル「モダン・ラブーNYの街角で」を見る。
30分×8話、単純な「男女が出会ってくっつくまで」の旧式的なラブ・ストーリーではなく、さまざまな形の愛情を描いたオムニバスで、1話1話が大変に濃い。
性別、年齢、立場、様々な事を超えて「愛」って成り立つんだなあ、人生って可能性の宝庫だなあ、と胸を打たれるお話ばかりなのだけど、特に私が心えぐられたのが第3話のアン・ハサウェイ演じる
『うまくいくはずがない、だから』と考えると割とうまくいく
『きっとうまくいく!』『なんとかなる!』
これは物事に取り組む前の私の口癖だった。
一歩を踏み出したい時、自分を鼓舞するためによく使っていた。このフレーズたちを使うとえいって飛び込んでいくことができた。
いわば勇気を出すための着火剤的な役割だ。
しかし
勇気は出せたけど….結果は出せなかったこと多数。
今はそれが何故だか分かる。
このフレーズの本当の意味は
「感動した!」と言ってもらえるぼくの料理には、圧倒的な戦略とロジックがある
はじめまして。鳥羽周作と申します。「sio」という代々木上原のレストランでシェフをやっています。
このnoteでは、ぼくがふだんどのようなことを考えながら料理づくり、お店づくりをしているのかをお伝えしていければと思います。
*
ただの「おいしい」ではなく「感動した!」と言われたいぼくが目指すのは、ただの「おいしい」ではありません。「感動」です。
日本に「おいしい」お店は無数にありますが、「
共感の時代だからこそ、わかり合えない相手を好きでいたい
今日書きたいことはタイトルそのまんまなのだけど。
現代が「共感の時代」だと言われてひさしい。
それ自体にはなんの異論もない。メーカーに勤めている身としても、嫌というほど感じている。
SNSを開けば「エモ」が表現をリードしているし。モノやサービスだって、機能よりも「共感」で買われる時代だ。
だけど、ふと思う。まわりを見渡せば価値観なんて無数にある。共感できるものだけを「正義」と捉えそうになる
素直になるゴールは果てしなく遠く見える
3年以上ぶりに風邪をひいた。しかも実家に帰ってきているタイミングで。
咳は出ないけど喉が痛い。熱はないけど頭が痛くてぼーっとする。
「夕ごはんできたよー!食べるー?温めるー?」と1階から叫ぶ母の声で目が覚めた。声を出しても聞こえないだろうと答えないでいると、同じ質問を叫びながらドカドカと2階に上がってくる音が聞こえる。
ようやく「食べる」と答えた私の声に異変を感じたのか「具合悪いの?」と聞か
一生人を傷つけない人はいないし、毎度毎度傷つけるわけでもない
放っておくとどんどん口数が減っていって、いざという時にうまく話せなくなる。
"うまく話せない"は、上手いこと言えないとかそんな高等なものではなくて、単語単語で息継ぎをしないと次の言葉が出てこなかったり、目の前にいる相手に話す内容を、30秒くらい考えてしまうことを指す。
話したいことはもちろんあるはずなのに、脳みそがうまく動かなくなってしまうのだ。そしていつも、「あぁ、またちゃんと話せなかった。