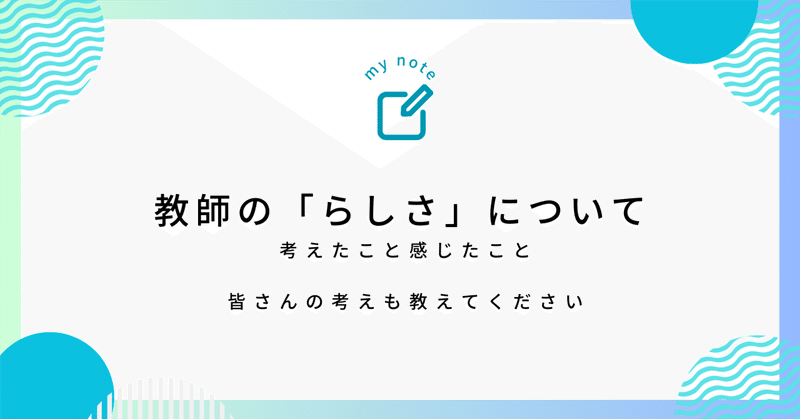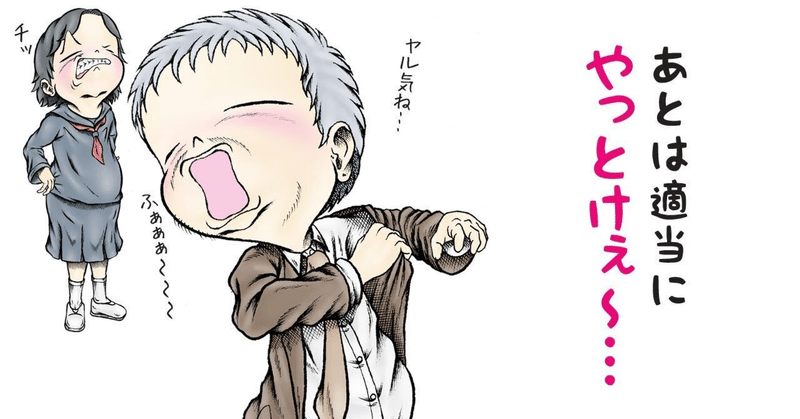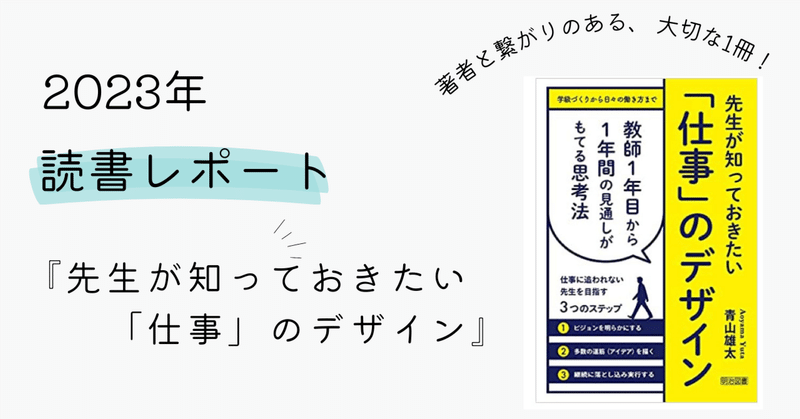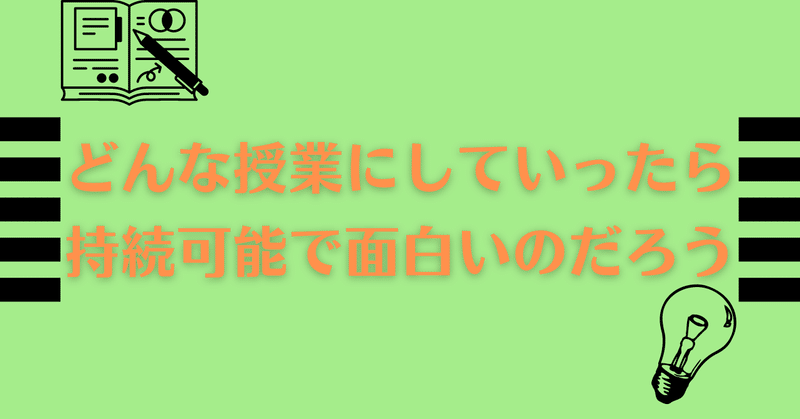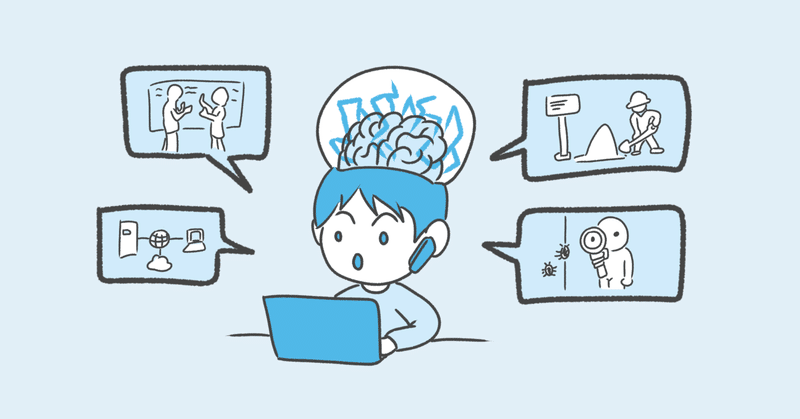#小学校
教師の「らしさ」について
学級には30〜40人ほど子どもたちがいます。子どもたち一人一人に個性があるように教師も一人として同じ人はいません。
今回は教師の個性。「らしさ」についてnoteを書いてみます。
FMC
麗澤大学非常勤講師、寺崎賢一先生も提唱されている「M・F・Cチームワーク指導」と言うものがあります。
年齢が近い先生もいれば威厳をもった先生もいます。また、優しく何事も受け止めてくれる先生もいます。
この
先生が身に付けるべきなのは時短術ではなく、「仕事」をデザインする力である?〜『先生が知っておきたい「仕事」のデザイン』を読んで小学校教員が考えたこと〜
「わからないことがわからない」
これは、初任時代に仕事を進める中で自分が感じていたことです。
教師として仕事を進めていく上で、授業自体は自分自身が生徒として経験してきたこと、そして教育実習で体験してきたことを通して、なんとなくイメージができている。
しかし、教師になって初めて授業以外の業務量の多さに圧倒されました。
週案、学年(学級)だより、会計…
毎週のように繰り返されるタスクに加え、毎日
最高のパフォーマンスを発揮する教師の思考法(前編)
2日かけて読了しました。仕事して、ご飯食べてゆっくりすると、つい本が遠のいてしまいますね笑
とはいえ、人間なので、浮き沈みあります。自分のペースで学んでいこうと思います。教室にもこういう子、いますよね?笑
さて、今回紹介するのは、丸岡慎弥さんの、
『最高のパフォーマンスを発揮する教師の思考法』
です。非常に勉強になりました。
本書の概要教師として、最高のパフォーマンスってどのようなことでし
教員の仕事を効率よくこなす方法
できることは児童生徒に任せる先生が全てやってあげようとするから時間はどんどんとなくなっていきます。任せられることは、多少クオリティが下がってでも児童生徒に任せることで、先生自身の仕事の量を減らすことができ、さらに児童生徒の頑張りに気がつき、価値を広めていくことができるなどたくさんのメリットがあります。具体的にわたしが任せたことは、
学級目標のポスター作成
班ポスターの作成
座席表
予定の管
ギフテッド(天才)教育について 考えてみた
こんにちは。寒さは続いていますが、少しずつ日の出の時刻が早くなってきて、明るい朝が少しうれしいMr.チキンです。
本当は今日あたり、教育に関係ない、Garminの腕時計の話を書こうと思っていたのですが、ギフテッドに関するニュースが目に入ったので、それについてお話をしたいと思います。
これは、教育全体がマイノリティ(少数者)に対してどのように関わっていくのか考えることと同じ問題だと考えています。