
青島もうじき 『私は命の縷々々々々々』 : 二つの「挑戦状」
書評:青島もうじき『私は命の縷々々々々々』(星海社FICTIONS)
若い読者には、いささか敷居の高い小説である。かと言って、無為に馬齢を重ねた高齢の読書家にだって、そう簡単に読みこなせる作品ではない。表紙画が今どきの綺麗で可愛いものだからいって舐めたりしたら、よく理解できなかったのを作者のせいにし、捨て台詞を吐きながら撤退するといった、醜態を晒すことにもなるだろう。
まさに「自民党派閥の裏金問題で、略式起訴されて議員辞職した谷川弥一議員の謝罪記者会見での居直り」と同様にだ。
だから、自信のない者は、若ぶって本書に手を出そうなどとは思わないほうが良いだろう。
一方、若い人には、個々の議論は理解できなくても良いから、主人公の感じる「違和感」を自分の中にも探ってみろと、そう助言したい。

さて、まずは本書がどのような作品なのかを、ごく簡単にまとめておこう。
(1)百合SF
(2)思弁SF
(3)SFミステリ
ということになる。
(1)の「百合SF」というのは、今の流行りだから、これが「ウリ」要素であろう。この作品、20年前なら男性キャラクターでやったのだろうが、今ではそうもいくまい。BLSFでは、すでにブームも去って読者も限られよう。
作者の年齢はよく知らないが、まあ、20代なかばから、いっても40歳までの、私から見たら「若い作家」であろうから、「文章」としては、とても読みやすい。つまり、今どきらしくリーダビリティは高い、ということだ。
しかし問題は、(2)の「思弁SF」の部分である。要は「頭を使います」ということであり、しかも、要求されるその頭の使い方とは、人文系の「哲学」的な方向性のもので、ハードSF的な「理系」のそれではない。
よって、そうした「思弁」に馴れていない人には「難しい」と感じられるのは避け難いところだろう。
だが、幸いなことに、本作で「思弁」されているのは、決して「哲学趣味」的に「高尚」なお話ではなく、優れて「今日的なもの」であり、かつ極めて「日本的なもの」だと言えよう。
つまり、今の日本社会において、まともに問題意識を持って生きていれば、多少なりとも考えざるを得ないような、案外身近な問題を扱っている。つまり「思弁」しているのである。
では、本作で扱われている「問題(テーマ)」とは何かというと、次のようなことである。
(A)「持続可能な社会」という倫理的命題に対して、個人は選択権を持たないのか?
(B)「生き方の形式の自由な選択」という大義名分は、強いられても良いものなのか?
つまり(A)なら、「温暖化による地球環境の悪化」というようなことが、典型的な例で、このままいけば、人類の住環境は悪化の一途をたどり、遠からず死滅するしかないという問題であり、それに対する個人の態度選択の問題だ。
この危機的状況を回避して、「生きるに値する、まともな環境」を次世代に残さなければならない、というのは現行世代の義務だというのは、ごく常識的な議論だろう。好き勝手に目先の快楽を追い求めた結果、地球環境を滅茶苦茶にしておいて、後の世代にその「ツケ」をまわす(例えば「核のゴミ」とか)というのは、あまりにも「非倫理的」であるというのは、ほとんどの人が納得のできる議論である。
だが、そうであるにもかかわらず、私たちが本当にそんな未来を回避することができるのかと言えば、「どうせ、できっこないよ」と思っている人が少なくないはずだ。
それを言ってはお終いだし、それをいうこと自体が「無責任(責任放棄)」的であるということにもなるから、公然とそういう人は少ないけれど、私のような「しーちゃん」的に「無責任」な人間は「SFの9割はクズである。ただし人間の9割もまたクズであり、当然のことながら、政治家などの社会的強者の9割もクズである」と思っているから、「地球温暖化阻止」など、お題目に止まって、実現できるわけがないと、そう思ってもいる。
ただ、だからといって「政治家などの社会的強者」に居直らせるわけにはいかないから「今の社会から多くの利益を得ているお前らには、相応の責任があるんだから、何とかしろ。でないと、殺されても仕方ないぞ」ということも平気で言える。
別にテロを称揚しているわけではないが、未来に絶望した人が増えれば、テロが起こるのは必然だからだ。
また、そんなわけで私も「黙って殺されるな」くらいのことは日頃から書いているし、間違ったことを書いているとも思わない。
ともあれ、もう「人類」にさほどの先はないだろうと思っている人は多いはずだ。そう思って当然の現実があるからで、こうした「未来図」に対しては、私のような高齢者だと「まあ仕方ないか。もうしばらくだから、何とか誤魔化し誤魔化し生き抜けよう」くらいのことしか考えないが、本来なら先が長いはずの若い人は、そうはいかない。「未来に希望が持てないが、まあ仕方がない」とは、思えるものではないからである。

だから私としても、若い人たちには申し訳ないとは思うので、せめて「子供や孫を持っている大人は、もっと責任を感じて、持続可能な社会を作るように、せめて声くらい上げろ」みたいなことを書いているが、そもそもこんな時代に、何も考えずに子供を作っているような「大人」に、そんな問題意識が持てるなどとは思っていないから、基本的には「希望はない」と思っている。
私が「声をあげる」のは、あくまでも、後の世代への「義理を果たす」という意識からであって、それで何とかなるとは思っていないのだ。
「オリンピックだ」「大谷翔平だ」と騒いだり「私の推しが」とか言っているような人たちが、この世界の先のことを真剣に考えているなどとは、とうてい思えない。そもそも考えたくないから、そういう「祭り」に逃避しているのではないだろうか。
で、なんでこんなことを書くのかといえば、それはこうした「悲観的な現実状況」が、本作の背景として、色濃く影を落としているからだ。
本作がどういう小説かというのを、私は先に、「百合SF」「思弁SF」「SFミステリ」と3つを挙げて紹介したけれど、そこにもう一つ付け加えるとすれば、それは、
(4)ディストピアSF
だということになる。
他の生物を含めた「地球環境」を(守り、そのことで「人類」を)守るためには、まず「人類の存続」が「自明の前提」であり「倫理」であるとされ、その「大義名分」の前には、「個人の自由な選択」が、やんわりとだが、今以上に否定された世界が、本作には描かれているだ。
本書の冒頭に掲げられた「用語集」は、そうした世界観を端的に示している。
『 用語集
◎ 倫理的生活環模倣技術
(ELB: Ethical Lifecycle Biomimetics)
生物の持つ生殖/生活環を模して人間へ導入する技術。この技術により、産み方/生まれ方の自由は社会へと実装された。全ての子どもは学園を卒業する高等部三年生で「進路」として自らの生活環を選択する。
◎ 環代(sustainable times)
「責任の主体となりうる人類には、絶滅しない義務がある」として、出生と選択と義務とが結びつけられた倫理思想史観的時代区分。ELBの普及に伴って幼児・子ども・大人の間には明確に線引きが為された。
◎ 学園
全寮制。自我が芽生えるとされる三歳になると、すべての人間は保護者の手を離れて学園へ入る。保育部、初等部、中等部、高等部に分かれる。浅織(※ 主人公)らの通う学園は歌浜を臨む小さな山の上に位置し、電車で数駅の場所には水族館もある。
◎ 生命指導課
子どもの道徳的な成長を目的として学園に常駐する、特殊な立ち位置の教員。稲穂をあしらった記草は、豊穣と繁栄を意味する。反論理的な言動を行う生徒に対しては「生命指導」を行う。
◎ 思弁服(memecouture/ミミクチュール)
生体繊維から成り、交友や思想を反映してひとりでにかたちを作り上げてゆく衣服。着る言語とも。高等部の生徒の制服として用いられ、それらは三年間の課程のなかでひとつの生態系を形成する。
◎ 『流体倫理の認識的操作』
ドイツの哲学者、ソラニ・ボーアドルトの主著。ふえるという責任を説いて現在の倫理観に大きな影響を与えた、かっての実存主義哲学者を論駁相手に据えたアフォリズム集。』(P8)
要は、一一地球上のすべての生命に対して、その責任を引き受けられるのは「人類」だけなのだから、人類にはその責任を引き受けるべき神聖なる「義務」がある。したがって、人類は何としても滅んではならない。そして、幸いなことに、人類が生き残るための技術として「倫理的生活環模倣技術」が生み出された。人類は、オスとメスの結合によって新しい生命を生み出すという旧来の形式だけではなく、多くの別種生物の繁殖方法を選択的に真似ることが可能になったのだ。いろんな形式があった方が、人類が生き延びる可能性は高まるはずだからである。
したがって、高校の卒業までに、こうした生命観や倫理観をしっかり学んだ上で、最後は自分の判断で、どのような繁殖形式を選ぶか、その決定の自由が与えられ、決して強制されることはない。ただし、子を成さない(子供を作らない)という判断は、あらゆる生命に対する責任放棄であり、その意味で「非論理」的なものであるから、犯罪として罰せられることもある。一一と、おおよそそんな社会である。
つまり、「自殺する権利」とか「子を成さない権利」というのが、反社会的なものとして認められていない、ある意味では「善意」と「正論」で踏み固められた「ゆるやかなディストピア」なのだ。
そこでは「こんな世界で生きていたくない」とか「こんな世界に子供を送り出したくない」という選択は、無しなのである。
さて、哲学・思想方面に興味のある人なら「反出生主義」という言葉を聞いたことがあるだろう。
「反出生主義」とは、次のようなものである。
『 反出生主義(はんしゅっしょうしゅぎ、はんしゅっせいしゅぎ)またはアンチナタリズム(英: antinatalism)は、生殖を非倫理的と位置づける見解。この種の考え方は、古今東西の哲学・宗教・文学において綿々と説かれてきた。とりわけ、アルトゥル・ショーペンハウアー、エミール・シオラン、デイヴィッド・ベネターが反出生主義者として知られる。
概要
種類・名称
ひとくちに「反出生主義」と言っても複数の種類があり、1. 誕生否定すなわち「人間が生まれてきたことを否定する思想」と、2. 出産否定すなわち「人間を新たに生み出すことを否定する思想」の2種類に大別できる。出産否定は生殖否定、反生殖主義、無生殖主義 (英: anti-procreationism) とも呼ばれる。
反出生主義(特に誕生否定)は、古今東西の哲学・宗教・文学において綿々と説かれてきた。ただし、それらをまとめて「反出生主義」と呼ぶようになったのは21世紀の哲学においてである。
21世紀の哲学者デイヴィッド・ベネターは、誕生は生まれてくる人にとって常に害であるとし、人類は生殖をやめて段階的に絶滅するべきだと主張した。このベネターの主張は、誕生害悪論とも呼ばれる。
英語の「antinatalism」という語は、もともとは哲学用語でなく人口政策(英語版)用語だったが、これを最初に哲学用語として使用したのがベネターとされる。2010年頃から、ベネターの影響のもとRedditなど英語圏のネットコミュニティで反出生主義運動が活発化した。
日本における「反出生主義」
日本語の「反出生主義」は、英語の「antinatalism」に対する訳語である。森岡正博によれば、この訳語の初出は2011年のウィキペディア日本語版である。具体的には、2011年にウィキペディアンの一人が 「デイヴィッド・ベネター」の記事を作成し、そこで「反出生主義」の訳語を与えた。2014年には別のウィキペディアンが「反出生主義」の記事を作成した。ベネターの思想自体は、2000年代に加藤秀一がロングフルライフ訴訟との関連で日本に紹介し、他の学者も言及していたが、学者で最初に「反出生主義」と呼んだのは2013年の森岡とされる。
2017年には、ベネターの著書の日本語訳が刊行されるとともに、日本のネットコミュニティでも「アンチナタリズム」と呼ぶ形で運動が波及し始めた。2019年には、雑誌『現代思想』で反出生主義の特集が組まれ、「反出生主義」の語を掲げた最初の書籍となった。2020年には森岡が反出生主義をテーマにした単著を刊行、2021年から大手新聞などでも反出生主義が取り上げられるようになった。
本来の反出生主義は「出産否定」に力点を置く思想だったが、日本では「誕生否定」に力点を置く思想として広まってしまった、という見解もある。』
(Wikipedia「反出生主義」)

とまあ、こんな感じで、簡単に言えば「生まれてきたって、ろくなこたあねえ。たしかに、たまには良いこともあるし楽しいこともある。だが、それよりもつらいことの方が多いんだから、こんな世界になんか生まれてこなかった方が良かった。それに、人類なんていない方が、他の生き物のためでもあろうしね」と、おおよそこのような考え方なので、こうした考え方自体は、古くからあった。
なお、本書の参考文献に、ドイツの哲学者ハンス・ヨナスの紹介書が挙げられているが、ヨナスはキリスト教の異端である「グノーシス主義」の研究者としても知られる人だ(要は、プロテスタントのキリスト教神学者なのだ)。
正統キリスト教の神が「産めよ増やせよ地に満ちよ」(旧約聖書「創世記」)と命じた「善なる神」であるのに対し、グノーシス派の考える創世神は「邪悪な神」であり「だからこそ、この世界には不幸が満ちているのだ」とする、論理的なものだ。「神が善なるもので、万能なのなら、その神が作った世界に、これほどの不幸があるはずないではないか」と、そういう反「神義論」的な考え方である。したがって「産むな増やすな地に満ちるな」となるのである。
当然、ハンス・ヨナス自身が、そう考えていたということではない。
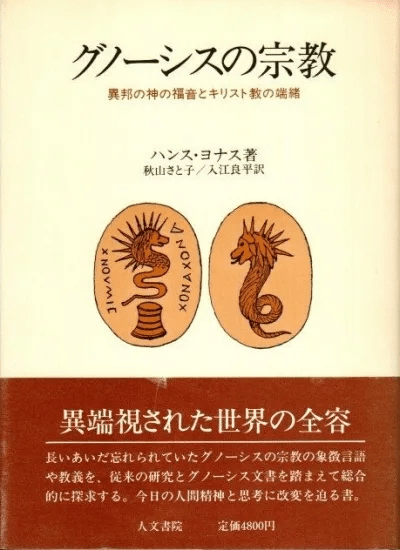
ともあれ、そんな「反出生主義」は、上の説明にもあるとおり、日本では、21世紀の哲学者であるデイヴィッド・ベネターの思想が紹介され、「反出生主義」というわかりやすい訳語が与えられ、その著作が翻訳されて、にわかに哲学方面でブームになった。
無論、地球環境の悪化という問題とともに、我が国では、経済の長期低落傾向や、我らが「安倍晋三長期政権」の果たした役割、例えば「経済的二極化」などの影響も大きい。多くの人が「こんな日本で生きていても、ろくなことがない。もううんざりだ」という気分でいたから、「反出生主義」と聞いて「そうだ、それだよ。まったく同感だ!」となったのである。
で、本書は、そんな「社会の空気」反映した作品なのだ。
「世界のために責任を持て」「命は何よりも大切だ」「生と性の自由とその選択権は最大に認める」けれども、しかしだからこそ「産まなきゃダメ」「勝手死ぬのもダメ」、そしてさらに「こんな倫理的な社会に疑義を呈することは許されない(再教育が必要だ)」と、そんな「ウザい社会」なのである。
だから、ジョージ・オーウェルなどが描いたような、これまでの「全体主義ディストピア」とは、ちょっと趣きがが違っているのだけれども、わかりにくくとも「全体主義」ということに違いはない。
「選択の自由を保証する」というけれど、それは「生きて産む」ことを前提とした「制限された自由」であって、「そんなもんは自由じゃねえ!」と、ちゃぶ台をひっくり返すような態度は許されない。それは「無責任」であり「非倫理的」な態度だとされるからだ。せっかく「すべての命を大切にしましょう。そのために、みんなが納得できる生き方や生殖方法をの選択を認めているのですよ。それなのに何ですか、その態度は?」ということである。

だから、本書に描かれるのは「地獄への道は善意で舗装されている」的な世界であり、それに「違和感」感じ、数年後の「選択」に抵抗を感じているのが、本作の女子高生の主人公である。
彼女は、自分を「同類」だと言ってくれた憧れの先輩や、友人たちとの交流の中で、どんな生き方を選択すべきなのかの思弁する。本作はそんな成長物語(ビルドゥングスロマン)だと言えるだろう。
要は、社会が「正義」だと言って押しつけてくる価値観に対して、どのように考えるのが「正しい」ことなのかを考える、という意味での「思弁小説」なのだ。
したがって、現在の世界あるいは日本社会の現実から逃避しているような人には、本書は「嫌な作品」である。
そんな「生々しい問題」なんか、考えたくないから「SF小説」(虚構の遠い未来や宇宙)に逃避しているのに、わざわざそんな問題を突きつけてくるのかよと、そう言いたくなるような作品なのだ。
だが、だからこそ「文学」としては、素晴らしいとも言えるのである。今どき、「文学」が求められていないとしてもである。
なお、本作が「今どきの日本SFだな」と思うのは、本作はディストピアに対する「抵抗」の物語ではあっても、「闘争」の物語ではない点だ。
日本SFの第一世代や第二世代、例えば、山田正紀などの世代が書いたら、たぶん「このディストピアを、いかにして破壊するのか」といった、男性的な「革命」の物語になっただろう。
たが本作は、良かれ悪しかれ、そうした破壊性を持たない繊細な優しさと同時に、情緒に流れる線の細さがあることも否定できず、そのあたりが、いかにも「今風」だとも言えるのである。
○ ○ ○
最後に、まだ説明していなかった、(3)の「SFミステリ」の部分についても少しだけ書いておくと、本作は一種の「本格ミステリ」であり、最後の最後で「ああ、そこへ落としたのか」と納得のできる「オチ」をつけていて、「本格ミステリ」としての「論理性」と「意外性」において、なかなか完成度が高い。

しかしながら、問題は、本作の場合「ミステリ小説としての謎」が、奈辺にあるのかがわかりにくいため、読者が本作を「ミステリ」として読まずに、ただただ「思弁小説」として読んでしまう点にあろう。
そのため、せっかくの最後「オチ」が、「なんだ、あれはこういうことだったのか」という「納得」に収まってしまって、本格ミステリ特有の「やられた!(騙された!)」という気持ちよさには欠けるのだ。せっかくの、「本格ミステリ」としてオチを活かしきれていない、惜しむべき書き方になってしまっているのである。
だから、私はここで、本作における「本格ミステリとしての謎」が、どこに設定されているのかをハッキリと指摘しておく。
それは「憧れの先輩は、なぜ失踪したのか?」である。
その謎の真相は、「SFミステリ」ならではのもので、「なるほど」と納得させる非常にスマートなものになっている。
ただし、この謎を論理的に解読するのは、相当に困難だろう。
というのも、この謎は、作中に「伏線」が張られているとはいうものの、かなり専門的な「生物学的知識」がないと気づきようもないものであり、しかも前述のように、多くの読者は、本作における「本格ミステリの謎」が、どこに設定されているのかに気づきにくい書き方になっているために、そもそもその「謎」を解こうとはしないからだ。

しかし、それではあまりにも勿体ないから、私はここで「本作の本格ミステリとしての謎」は「憧れの先輩の失踪の真相」であると明記して、読者の注意を促しておきたい。こう書いたところで、そう簡単に見抜けるようなものではないのだ。
そんなわけで、本作は二重の意味で、「読者への挑戦状」が仕組まれた作品だと言えるだろう。
ひとつは「SF本格ミステリ」として「真相が見抜けますか?」という挑戦であり、もうひとつはもちろん、この「生々しい現実問題に対する思弁」に「あなたはついてこれますか?」という挑戦である。
(2024年1月27日)
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
