
フランソワ・トリュフォー監督 『ピアニストを撃て』 &『あこがれ』 : トリュフォーの「嘘と真」
映画評:フランソワ・トリュフォー監督『ピアニストを撃て』&『あこがれ』(1960年・1958年、フランス映画)
フランソワ・トリュフォーという作家の特質が、かなりハッキリと見えてきた。本稿では、それをご紹介しよう。
本稿も、一応はいつものパターンで「映画評」としており、もちろんここでも『ピアニストを撃て』と『あこがれ』の2作を論評しはするのだけれども、本稿の目的は、「作家主義」という建前における作者であるフランソワ・トリュフォーという「作家」を論じることにある。つまり、本稿は「作家論」なのだ。
さて、まずは、本稿で主として扱う『ピアニストを撃て』(1960年)と『あこがれ』(1958年)の2作について、簡単に紹介しておこう。
『ピアニストを撃て』『あこがれ』という並びになっているのは、私が見た「ポニー・キャニオン版DVD」の収録順がそうなっているからである。
ではなぜ、制作年順ではないのかというと、新しい方の『ピアニストを撃て』は、トリュフォーの実質的デビュー作で出世作でもある『大人は判ってくれない』に続く「長編第2作」だからである。つまり、『あこがれ』の方は、『大人は判ってくれない』以前の「短編」作品であり、世間的には「習作」的な扱いななっているからだ。
したがって、商品の看板としては、あくまでも『ピアニストを撃て』の方でメインあって、『あこがれ』はあくまでも「付録」的に収められている。
だから、DVDのタイトルの並びも、収録順も、『ピアニストを撃て』『あこがれ』となっているし、表紙も『ピアニストを撃て』の方だけになっているのだ。
しかし、今では「ヌーヴェル・ヴァーグの巨匠」扱いになっているフランソワ・トリュフォーの、そんな「肩書き」に忖度することなく、忌憚なくその「出来栄え」を評するならば、『ピアニストを撃て』は「失敗作」であり、『あこがれ』の方は「好短編」ということになる。
つまり、『あこがれ』の方が数等よくできた作品なのに、「短編」ということで、その評価において、割りを食っているのだ。
だか、世間の評価とは、所詮その程度のものだ、とも言えよう。
ともあれここからは、このDVDへの収録順に、この2作品についての、私の前述の評価の、根拠を示していこう。
○ ○ ○
まず『ピアニストを撃て』だが、この作品は、単純に「破綻している」。
より正確に言うなら、「混乱した」「まとまりを欠いた」作品であり、ある意味では「統合失調」的な作品だとさえ言えよう。

私が見たDVDの字幕翻訳は、日本におけるトリュフォーの『長年の友人』である映画評論家・山田宏一が行っており、このDVDのカバー背面には、山田による短い解説文が掲載されている。
それは、次のようなものだ。
『「ピアニストを撃て」(1960)は、「大人は判ってくれない」(1959)に次ぐフランソワ・トリュフォー監督の長編第2作。不幸な少年時代をリアルに生々しく描いた自伝的な前作のひたすらなトーンから一変して、アメリカの犯罪ミステリー小説を原作として、デタラメなお遊び、転調に次ぐ転調、おふざけいっぱいの軽快なおとぎ話といった感じ。ヌーヴェル・ヴァーグの盟友、ジャン=リュック・ゴダール監督の「勝手にしやがれ』(1959)で刑事を演じていたダニエル・ブーランジェ(本職はシナリオライター)が2人組のギャングの1人になってホラ話をしたり、当時まだ無名の歌手ボビー・ラポワントのダジャレだらけのコミカルなシャンソンにフランス語のスーパー字幕が付いたり、即興撮影の勢いが画面を活気づけ、トリュフォーが愛した数々のアメリカ映画の影響がみられる愛すべき小品だ。
臆病で内気な主人公(シャルル・アズナヴール)や「女は魔物だ」と口走るダメ男(セルジュ・ダヴリ)にはいかにもトリュフォー的な弱い男の肖像が見出される。
遺作になった「日曜日が待ち遠しい!』(1983)までほとんどのトリュフォー作品の音楽を手がけた「映画狂の音楽家」ジョルジュ・ドルリューとの出会いの作品でもある。
『あこがれ』(1957)は、少年たちの性へのあこがれを描く25歳のトリュフォーの短編処女作。のちに「私のように美しい娘」(1972)のヒロインも演じるベルナデット・ラフォンのういういしいデビュー作でもある。』

ここで、『ピアニストを撃て』について、問題になるのは、次の部分である。
『不幸な少年時代をリアルに生々しく描いた自伝的な前作のひたすらなトーンから一変して、アメリカの犯罪ミステリー小説を原作として、デタラメなお遊び、転調に次ぐ転調、おふざけいっぱいの軽快なおとぎ話といった感じ。(…)2人組のギャングの1人になってホラ話をしたり、当時まだ無名の歌手ボビー・ラポワントのダジャレだらけのコミカルなシャンソンにフランス語のスーパー字幕が付いたり、即興撮影の勢いが画面を活気づけ、トリュフォーが愛した数々のアメリカ映画の影響がみられる愛すべき小品だ。』
「読める人」がこれを読めば、私が本作を、
『単純に「破綻している」のだ。より正確に言うなら、「混乱した」「まとまりを欠いた」作品であり、ある意味では「統合失調」的な作品』
と評した意味も、即座にご理解いただけよう。
要は、いかにも「映画オタク」あがりらしく、いろいろを「やりたかったこと」をつっ込んではみたのだが、結局は「まとまりのつけられなかった作品」なのである。
まただからこそ、『長年の友人』であるために、「失敗作でも失敗作とは書けないし、書かない」山田宏一でさえ、この「長編」を評して、最後は『愛すべき小品』と書かざるを得なかったのだ。要は、長編としての「結構を欠いている」ということである。
そのため、細かいところに「近視眼的」に注目して、全体を見ないようにしたのであり、細かいところだけを見て評価したから『小品』という評価になってしまったのだ。


ところで、私は上で、山田宏一のことを『長年の友人』と『』(二重カッコ)付きで書いたのは、単なる「強調」のためではなく、引用文だからである。つまり、私が勝手にそのように決めつけたわけではなく、山田とトリュフォーは「そんな関係にある」と、すでに公言されている、ということなのだ。
で、その出典はというと、山田の書いたトリュフォーの評伝である『トリュフォー、ある映画的人生』の「平凡社ライブラリー」から刊行された「増補版」のカバー背面の、次のような、売り文句としての紹介文である。
『学校をサボり、家出を重ねたひとりの不良少年は、いかに「映画」を通して、自らの人生を歩み出していったのか? 「大人は判ってくれない」でデビューし、ヌーヴェル・ヴァーグを先導した、映画監督トリュフォーの生涯を、
長年の友人である著者が、詳細な資料を交えて、あたかも一本の映画のように描いた評伝の決定版。
第1回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞作。』(※ 改行もママ)
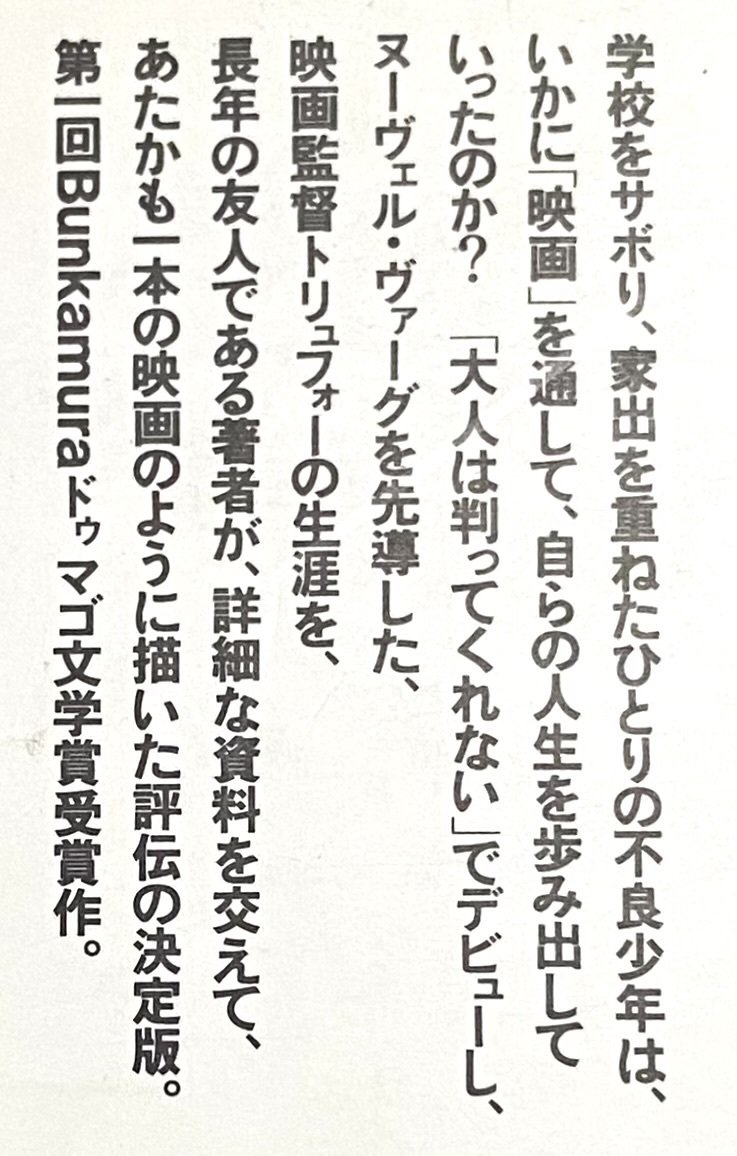
実際、山田にはトリュフォー関係の著書が多数あって、特に注目すべきなのは、トリュフォーの著書を7冊も翻訳している点であろう。
だから、山田がトリュフォーと「個人的に親密」だというのは間違いないところだろうし、こうした間柄からトリュフォーの著書の翻訳を一手に引き受けたおかげで、山田は、少なくとも日本においては「フランソワ・トリュフォーの第一人者」ということになったし、その立場からの「トリュフォーの布教者(宣伝員・御用評論家)」にもなったと、そう評し得るのである。

しかし、山田宏一が仮にも「映画評論家」を名乗るのであれば、批評対象である映画作家との、このような「癒着的な馴れ合い」は、明らかに不健全なもの(汚職)と評すべきであろう。
要は、山田には、トリュフォーに関しては「駄作であっても、駄作とは言えない」し、「駄作を、さも見どころがあるもののように、マシな部分だけを強調して褒める」というような、「ペテン性」もあるからだ。
そして、この点については、山田の著作を1冊読んだだけで、ハッキリとそれが判った。
『先にも指摘したとおり、もともと本書著者(※ 山田宏一)は、ゴダールよりもトリュフォーに親しみを感じていた人ではあったのだが、さすがにトリュフォーの(※ 1968年の「カンヌ国際映画祭粉砕事件」に関わる)露骨な「手のひら返しの転向」を見せつけられては、「なんだあいつは!」となるのも、むしろ当然のことであろう。
ではなぜ、いったんは「世間なみ」に、トリュフォーを「裏切り者の転向者」だと非難した本書著者が、いつの間にか「トリュフォー派」に、再転向したのであろうか?
もちろん、これは内心の問題だから、その真相を正確に知ることはできないのだけれども、当たり前に考えれば、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の現地体験をひとつの売り物とし、一方「ゴダール的な前衛映画」にはついていけない「凡庸な評論家」でしかない山田が、それでも自身の「ヌーヴェル・ヴァーグ」体験を、実のある売り物にし続けるには、無難にトリュフォーとの関係を回復した方が「経済的に得策」だったから、ではないだろうか。
つまり、トリュフォーが「映画監督として食っていくために転向した」のと同じように、本書の著者である山田宏一は「映画評論家として食っていくために(わかりやすいトリュフォーの方へと)再転向した」のではないのか。
少なくとも、そうした「常識的な推測」を否定するような事実を、本書に見出すことはことはできなかった。』
つまり、若い頃いったんは、トリュフォーの「手のひら返しの裏切り」に対し、「なんだあいつは!」と当たり前に腹を立てた山田も、その後の日本で「ヌーヴェル・ヴァーグ」に関する現地体験を売り物にして生きていくためには、気難しいゴダールに擦り寄るのは能力的にも無理だから、「話のわかる」トリュフォーに擦り寄ることで、トリュフォーの著書の翻訳者の地位を確保し、その優越的な立場を生かして「トリュフォー讃嘆本」を書くことで、自身の「日本での立ち位置」を確立した、ということである。
つまり、山田宏一は、トリュフォーと馴れ合い、「日本でのトリュフォーの宣伝員(布教者・御用評論家)」の地位を専属的に得ることと引き換えに、「映画評論家」としての魂を売った、ということである。
しかし、そんな山田宏一ですら、『大人は判ってくれない』に続く、期待の第2長編であった『ピアニストを撃て』については、諸手をあげて褒めることができなかった。
だから、苦しまぎれに『愛すべき小品』と評することで、「自分の眼(批評眼)」を持たない人たちを「欺こうとした」のである。
したがって、本作は、あれこれ細かい説明をするまでもなく、山田宏一の「いかにも苦しげな褒めっぷり」からして、「失敗作」であることは明らかだ、ということになる。
そして何より、このことは、山田情報のような「予断」なしに本作『ピアニストを撃て』を見れば、「何をやりたいのかわからない、まとまりを欠いた作品」にさか見えないという事実に、一目瞭然なのである。
ちなみに、『ピアニストを撃て』が「まとまりを欠いた失敗作」だとしても、失敗作には失敗作なりに「トリュフォーの個性が刻印されている」というのも事実である。
どういうことかということ、主人公のピアニスト、シャルリ・コレールという偽名で登場する、本名エドゥアール・サローヤンには、いつものごとく、トリュフォーその人が投影されているのだ。

エドゥアールは、もともとはピアニストとして一度は成功して、名声を得た人である。ところが、その名声によって人生を狂わせてしまい、最愛の妻を自殺で死なせることになってしまった。
それで、そうした「虚飾の人生」を捨て、名前まで変えて、場末の飲み屋のピアニストに、みずから身を落とした人物である。
そして、そんな主人公を描く本作のテーマのひとつは、「自分に自信を持つこと(臆病を克服すること)」の困難さ、なのだ。
これは、先日読んだ、植草甚一の著書『映画はどんどん新しくなってゆく』に書かれていたことで、植草が直接トリュフォーの口から聞いた話である。
『 ギャングが少年を誘拐していくとき、車のなかでの話し合間に、楕円形の黒いハリのなかで老婦人が卒倒してしまうサイレント技巧のみじかいショットをいれたあたり、特別なフィーリングをだそうとした試みだろうというくらいしか、ぼくには説明できないのですが、とにかく最初は、この映画から受けた印象を書くことができなかったのです。それをこういうふうに考えてきたことが、はたしていいか悪いか、ぼく自身にも疑問になる点があります。けれどトリュフォーが、どうしてこれをつくりたくなったかと考えたとき、逆にいくらでも書くことができるようになりました。というのも、こういうような映画のつくりかた、つまり作者自身の臆病さを描こうとした例は、いちどもなかったからなのです。トリュフォーが『臆病がテーマだが、ほかにもあるんだ』といったのは、たぶん(※ 臆病な主人公が)彼自身でもあることを、はっきり口にしたら、生意気に思われるという気持があったからではないでしょうか。このような意味で、こんな謙護な映画も、いままでになかったのです。』
(植草甚一『映画はどんどん新しくなってゆく』P88)
つまり、植草甚一も『ピアニストを撃て』を「褒めあぐねていた」のだが、『けれどトリュフォーが、どうしてこれをつくりたくなったかと考えたとき、逆にいくらでも書くことができるように』なった、というのである。
「作品を褒めることはできない」が、「トリュフォーが何を語りたかったのかというのはわかる」し、それは「臆病=自信の無さ(の克服)」ということであったのだ、ということだ。
だか植草は、この着眼点をして、作者であるトリュフォーを褒めることで、作品そのものは褒められないという事実を「誤魔化そうとした」。
要は、作家を褒めて、「いい話」風にまとめることで、読者の持つであろう「作品に対しては否定的」という当然の印象を「薄め」、そのことで『ピアニストを撃て』への、自身の「否定的評価」を誤魔化そうとしたのである。一一そしてそれが、締めの言葉である『こんな謙護な映画も、いままでになかった』という言葉の意味なのだ。
また、この言葉は、山田宏一による『愛すべき小品』という評価と同種の、読者に対する「ペテン」だったのである。

だが、トリュフォー自身が『臆病がテーマだが、ほかにもあるんだ』と言った点は、注目に値する。
この点をして、植草は『たぶん彼自身でもあることを、はっきり口にしたら、生意気に思われるという気持があったからではないでしょうか。』と、ことさらに「好意的な解釈」を示すことで、自身の文章を「きれいごと」でまとめているのだが、客観的には、そんな「恣意的な解釈」で済ませてはならない。
つまり、ここでトリュフォーが『臆病がテーマだが、ほかにもあるんだ』と言ったのは、「臆病」が「テーマの一つである」のだと、反語的に認めている、ということであり、さらに言えば、自分は「臆病な人間なんだ」と、暗にアピールしている、ということでもあるわけなのだ。
植草は、この「誘い水(誘導的な自家宣伝)」に、ありがたく(も無自覚に)乗せてもらった、だけなのである。
しかしながら言うまでもなく、本当に「臆病」な人間は、「私は臆病です」とわざわざアピールして「謙虚ぶる」ことなどしない。そんな「余裕」も「図太さ」も無い。

「私は臆病です」と、あえて表明する人というのは、そう認めても、それで人から害される「怖れはない」と、そう図太く踏んでいる(読んでいる)ということであり、さらに「臆病である」と主張することは「相手を安心させる」ことだということまで、承知してやっているのだ。
言い換えれば、本当に臆病な人は、他人から害されるのを怖れるから、自分から「私は臆病です」とはアピールしないものだ、ということなのだ。これは、少し考えればわかることでしかない。
したがって、「私は臆病です」とアピールする者は、聞かれもしないのに、私は「無学です」とアピールする人と同じで、「私は、学は無いけれども、本質的な知恵は持っている」と考えている人のような、ある意味では「図太い自信家」でさえあり、そうだからこそ、あえて「私には学がありません」とか「私は臆病な人間です」などと「謙虚ぶって」見せて、相手の自分に対する「印象」を、コントロールしようとするのである。
そして、このようなトリュフォー自身による「イメージ・コントロール」に調子を合わせるのが、「日本でのトリュフォーの宣伝員」である山田宏一である。
だからこそ山田は、トリュフォーを「子供好き」の「愛の映画作家」だなどと、わかりやすくも通俗的な、情に訴えるイメージを、拡散し続けてきたのである。

では、トリュフォーという作家の本質は奈辺に在するのかと言えば、それは「元不良少年らしい強かさ(世渡りのうまさ)」であると、そう断じて良いだろう。
だからこそ彼は、『カイエ・デュ・シネマ』誌のメンバーのなかで「最も戦闘的で、尖った評論家」として、「カンヌ国際映画祭粉砕事件」を先導し、その「金儲け主義」を批判したにも関わらず、その後は、あっさりと「資本」になびいて、ぬけぬけと転向することもできたのである。
そして、そのことを、元盟友であるジャン=リュック・ゴダールから「裏切り者」と批判されると、ゴダールのことを「私に映画制作費の無心に来たが、私が断ったことから、それっきり縁が切れた」と、暗に「ゴダールの私に対する批判は、結局、私から金を引き出せなかったための逆恨みに過ぎない」と語っているのである。
つまり、トリュフォーという人は、このように「直接的に批判することはせず」、それで「いい人」ぶって見せてはいるのだけれども、「暗に示唆する」ことで、他人をコントロールしようとする、陰険なところのある人なのである。
そして、私はそのあたりのことを、『大人は判ってくれない』のレビューで、「不良少年の嘘泣き」的な「強かさ(面の皮の厚さ)」だと、指摘しておいたのだ。
『「これは映画であり、私の自伝ではありません。だから、私は何も嘘などついてはいませんよ」などというのは、それこそが何よりも「嘘」なのだ。
「私に騙す気なんて、これっぽっちもありません」という言葉が、そもその「大嘘」なのである。
多くの観客は、「可哀想な少年」に同情することで、自分が「物分かりが良く、優しい人間」だと感じる。そのことで、本作から満足を得るのだ。
だが、そういう人たちは、不良少年なら、真に迫った「嘘泣き」くらい、それが有効と思えば平気でやるものだ、という現実を見る気などないし、そうした悲しむべき「現実」に責任を持つ気のない、そうした「お見物衆」たちは、いつだって簡単に、「感動」して見せることができるのである。
しかし、「不良少年の涙」に騙されるという痛切な経験を何度もした者は、だからその後は「(モスクワのように)涙を信じない」ようになる、というのではなく、真相が判明するまでは、「疑う責任を放棄しない」ようになるのである。
結果に責任を持たず、ただ無責任に「信じるだけ」なら、それは馬鹿にでもできるのだ。「騙された」と嘆いて済むのは、無責任な立場の者だけなのである。』
つまり、第2長編『ピアニストを撃て』でも、トリュフォーは「自身を正当化するために、裏返したかたちで、主人公に自己を投影している」のだ。
「この主人公は、有名になった自分に、しかし自信の持てなかった、謙虚な人物だ」と描くことで、暗に「自分もそういう人間だ」と語り、暗に「この映画も、自伝的な側面のある作品」だと、そう「臆面もなく」語っているのである。
ただ、前作の『大人は判ってくれない』で、そうした「自己美化」を全面展開してしまったために、言うなれば、その直後の第2作『ピアニストを撃て』では、やることが無くなってしまった。
同じようなものを作れば、批評家から叩かれるのは目に見えているから、方向性を変えて主人公を大人にした。
しかし、その大人の主人公は、『大人は判ってくれない』で描いた「判ってくれない大人」であってはならないから、「大人らしい厚顔さ」を持たない、自信のない、臆病で謙虚な人物にしたのである。
それで「同情を引こうとした」という点では、『大人は判ってくれない』と同じことを、トリュフォーは考え、狙っていたのだ。

だが、『大人は判ってくれない』主人公である美少年に比べると、本作『ピアニストを撃て』の主人公は「いかにも、しょぼくれた中年男」だから、前作ほど観客を惹きつけることが困難だというのは、トリュフォー自身も理解していた。
だから、「映画オタク」的な知識を総動員し、手を替え品を替えあれこれやってみたり、あれこれの作品の「パロディシーン」を入れたりして、初期「ヌーヴェル・ヴァーグ」お得意の「目配せ」を振り撒いてみたのだが、その結果は、最初に書いたとおり「まとまりのない、何をやりたかったのかわからない作品」ということに、結果してしまったのである。
○ ○ ○
では、短編『あこがれ』の方はどうだろうか? 一一こちらについては、最初に書いたように、「好短編」に仕上がっている。
ではなぜ、『あこがれ』は、作品として成功したのかと言えば、それは本作が「不良少年(悪童)たちを生き生きと描いた作品」だったからだ。
要は、「自伝的要素」を比較的ストレートに反映させたから、登場する少年たちは生き生きとしたものになった。そもそも、トリュフォーの描く「不良少年」というのは、どの作品でも、たいがいは生き生きと良く描けているのだ。

『大人は判ってくれない』は無論のこと、ワンシーンしか登場しない、『ピアニストを撃て』の悪童たちですら、妙に生き生きとしているのだが、このことが意味するのは、トリュフォーが「子供好き」だということではなく、「子供の悪戯っぽさが好き」だということであり、要は「不良っぽい少年(悪童)が好き」だということなのだ。
そしてそれはもちろん、彼自身の「子供時代の愉快な記憶」が、その点で最も活き活きと反映される、ということなのである。
『あこがれ』は、思春期手前の悪童たちが、ある年上の(二十歳前くらいの)女性に「あこがれ」、彼女にほのかな恋情を抱き、性的な興奮まで覚えるのだが、なにしろ「まだ子供だから、自分の中に生まれた衝動の正体が何かを自覚しないまま、彼女の恋路を邪魔するような悪戯や嫌がらせばかりをしてしまった」と、そういうお話である。

なお、本作では、役名と俳優名は同じ)
この「まだ子供だから、自分の気持ちがよく判っていなかった」というのは、子供の側に立った「(大人になった後の悪童のひとりの回想的)ナレーション」によって語られるのだが、このあたりが、いかにも「トリュフォーらしい」ところだろう。
つまり、子供たちの実際にやったことは、この年上の女性とその恋人である彼氏に対する嫌がらせ的な悪戯に他ならないのだが、ナレーションは「悪童たちの立場」に立って、とにかく「子供だったので、自分たちのやっていることがよく判っていなかったのだ」と「言い訳」をし、観客から「子供のことだから、仕方ないよな」という「理解と共感」を引き出そうとするのである。

結局この物語は、一人で旅に出た「彼氏」が、旅先での不慮の事故で死んでしまうことにより、「あれほど溌剌として輝いていた彼女も、喪服に身を包んで、別人のような大人になっていた」というラストとなり、その姿を見て、語り手でもある「(成人した後の)悪童」は、その女性の「不幸」が「自分たちの責任ではない」ことは判っていても、それでも彼女の恋路を邪魔したことへの「やましさ」が拭えず、そうした苦い経験をすることによって「自分たちも大人になっていった」と、そう「感傷的」に語って、この物語は幕を閉じるのである。
したがって、この作品は、ナレーションによって「言い訳」をし「自己正当化」をしながらも、「悪童」たちの「悪行」を、ストレートかつ生き生きと描くことのできた作品なのである。
そしてその点において本作『あこがれ』は、「好短編」だと呼んで良い、よくまとまった完成度の高い作品になってはいるし、その反面、トリュフォーのトリュフォーらしさである「自己正当化(自己美化)」という性格のよく出た作品だとも言えるのだ。
本作『あこがれ』にも、『ピアニストを撃て』にも、「原作小説」はあるのだけれど、だからと言って、この両作が「自伝的作品ではない」ということにはならない。原作があっても、それはアウトラインだけ、というのは、「ヌーヴェル・ヴァーグ」初期作品には、よくあることなのだ。
したがって本作も、「自伝映画」ではないけれども、明らかに「自伝的要素」の込められた「自伝的作品」であり、その意味では代表作である『大人は判ってくれない』と同一線上にある作品だと言える。
だが、このことから言えるのは、トリュフォー作品の場合、「自伝的要素」の込められた作品では、その部分は生き生きとするが、それが少ない作品は、そうはいかない、ということである。
トリュフォーの作品では、初期の「自伝的作品」が高く評価される一方で、その要素が消費された後のオーソドックスな作品では、さほどの評価を受けられなかったというのも、トリュフォーが、そうした作家的な特質を持っていたからであろう。
トリュフォーという映画作家は、その「不良体験」において、「悪童」たちを描かせれば天下一品であった。
しかし、それを描く場合には、常に「自己正当化のための言い訳」をワンセットのものとして、作品に仕込まないわけにはいかなかったし、さらに言えば、いつも「悪童」ばかりを描いているわけにもいかない。
つまりそこに、フランソワ・トリュフォーという映画作家の「限界」があったのであり、そこを「子供好き」の「愛の作家」などという「腑抜けたヨイショ」で持ち上げてみたところで、それには限界があったということであろう。
たしかに、トリュフォーは、「ヌーヴェル・ヴァーグ」を先導した作家だから、その点での「歴史的評価」は世界的なものと考えて良いだろう。
だが、トリュフォーという作家の「総合的評価」という点では、『長年の友人』である山田宏一の「尽力」によって、日本では、世界水準よりもかなり高めになっているのではないかと、私は睨んでいる。
私が、トリュフォー作品として次に鑑賞を予定しているのは、「もう一つの代表作」とも目されているらしい、第3長編『突然炎のごとく』である。
だが、私の場合は、この作品を、世間の「色眼鏡」を掛けて、単なる「傑作」として見るのではなく、トリュフォーの長所が、どこにどのように出ているのか、そういうところを見ていきたい。
そして、その後の作品が、どのようにしてどうなっていくのかをも、しっかりと見届けたいと考えている。

(2024年7月26日)
○ ○ ○
● ● ●
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
