
若松英輔・ 山本芳久 『危機の神学 「無関心というパンデミック」を超えて』 : 通俗カトリックの 〈自己権威化〉神学
書評:若松英輔・山本芳久『危機の神学 「無関心というパンデミック」を超えて』(文春新書)
『そのとき、イエスはこう言われた。「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです。」』 (「ルカによる福音書」より)
人はしばしば、自分が何をしているのか、どんな言葉を口にしているのかに、まったく無自覚なことがある。
ましてや、自分が「主流派」で「大勢の側」であってみれば、自信満々に「自己肯定的な言葉=他者否定的な言葉」を口にするのだが、それが、遠く離れた「第三者」から見れば、いかにも傲慢で愚かなものにしか映らないということに、まったく気づかない。
例えば、磔刑にされた十字架上のイエスを馬鹿にし、からかった人たちなどがそうだ。
彼らはその当時、自分が「主流派」で「大勢の側」であると確信して、自信満々に「自己肯定的な言葉=他者であるイエスを誹謗する言葉」を口にした。しかし今日では、それがいかに愚かなことであったかが、明白になった。

何もこれは、キリスト教や宗教の話ばかりではない。
ナチス政権下における「ユダヤ人迫害」に加担したドイツの一般市民、現人神天皇を担ぐ軍国日本において、反戦主義者や社会主義者や「天皇は人間である」とした学者などを迫害した人々も、その当時は「主流派」で「大勢の側」であってみれば、自信満々に「自己肯定的な言葉=他者否定的な言葉」を発したのだ。
『 本当にその通りで、引用をしませんでしたが、教皇フランシスコ自身、(※ 聖書の「善きサマリア人」の話における、強盗に襲われて道端に倒れている人の傍を)最初に取り過ぎた二人が、両方とも祭司とレビ人という神に仕える人だった点が非常に重要だと言うわけです。一見神に仕えているように見える人が本当に神に仕えているとは限らない。そうでないような人こそ神に本当に仕えていることはある、という言い方で、狭い意味でのキリスト教という枠を超えて、根源的なものとつながる生き方を説き直している。』(P273、山本芳久の発言)
少し解説しておこう。「善きサマリア人」の譬えとは、新約聖書に描かれたイエス・キリストの譬え話の中でも、最も有名なものの一つである。
ここに登場する『祭司とレビ人』は、キリスト教徒ではなく、ユダヤ教徒で、イエスの生前には、まだキリスト教は存在してはいないのだから、この話をしているイエス自身も、そのユダヤ教徒であることを忘れてはならない。
つまり、『祭司とレビ人という神に仕える人』というのは、ユダヤ教における「(旧約)聖書」の教えを厳格に守る、最も「正しい人=義なる人」だったのだ。
一方、サマリア人というのは、ほとんど同様の信仰を持ちながらも、教義上の微妙な違いなどもあって、信仰的に差別され、見下されていた少数派だった。
そして「善きサマリア人」の譬えとは、強盗に襲われ血まみれになって道端に倒れている人を見て、『祭司とレビ人という神に仕える人』たちは、その教義に従って「血穢」を怖れて、けが人を避けて通ったのだが、後で通りがかったサマリア人は、そんなことなど意に介さず、けが人を助けた、というお話である。
イエスは、彼が「正しい信仰」を持っているかどうかを試しに来た人たちに、この譬え話をして「どちらが(神の前において)正しい行いか」と問うたのだ。

同様に「教義や神学に精通して、立派な説教のできる、地位も立派な(祭司とレビ)人」であっても、本当のところ「信仰を誤っている」場合というのは、イエスの時代からすでに珍しいものではなく、むしろ「正統な信仰者ではなかった」人の方が、その自然な人間的善意において「神の意に沿う行動をし得た」という、これはそういうお話なのである。
そして、ここで何より皮肉なのは、この教皇フランシスコによる説教を紹介して『一見神に仕えているように見える人が本当に神に仕えているとは限らない。』などと言っている、カトリック神学者の山本芳久自身が、実は『一見神に仕えているように見える人が本当に神に仕えているとは限らない。』人、だという事実なのだ。
○ ○ ○
私は、本書の対談者である、カトリックの一般信徒(平信者)である若松英輔と、カトリックの神学者である山本芳久の著作を、これまでに何冊かずつ読んでおり、それぞれに、すでに批判を加えている。
また、そんな両者の、前の対談本である『キリスト教講義』(文藝春秋・2018年)についても、刊行当時に批判的なレビューを書いている。
だから、今回、本書を読むにあたっても、内容的に期待するところはなかったが、3年ぶりの対談で、二人の関係がどのようになっているかに興味があったので、読んでみることにしたのだ。

前記レビューを読んでいただければ、そこに詳述しているのだが、ここでも簡単に説明しておくと、前対談本『キリスト教講義』は、個人の「霊性」を強調する「霊性主義者(スピリチュアリスト)」である若松が、カトリック教会最大の「正統」神学者であるトマス・アクィナスの研究家である、カトリック保守派の神学者(神学研究者)の山本に対し、「教会の権威よりも、個人の霊性の重要さ」を訴え、一方、山本の方は、世俗的な人気知識人である若松の主張を、表面上はウンウンと物分りよく肯定しながら、教会の側に取り込もうとする、そんな両者の思惑が隠微に交錯する著作であった。
もともと、「文学」畑の人間である若松は、よく本を読んでいるし、評論家として「筆も立てば、弁も立つ」からこそ、人気評論家になり得た人物なので、世俗的な人気や説得力という点では、山本が若松に遠く及ばないのは明らかだ。
しかし、何と言っても、カトリックの信仰においては、山本は「正統」であり、若松の「個人主義的な霊性主義」というのは、世間的には人気はあっても、カトリック的には、きわめて「異端」に近いものでしかない。
したがって、山本が、カトリック的に、若松の「霊性主義」を批判することは、さほど難しいことではないなのだが、しかし「今は、そんな時代ではない」。つまり、今は「世俗」が力を持つ「世俗主義の時代=近代以降」であるからこそ、キリスト教信仰は「ジリ貧」の危機に見舞われている。
だから、内心では若松の信仰を「それは異端だよ」と思っていても、それで斬り捨てて済む問題ではない。
そうではなく、なんとか、この「世俗の人気者」を「教会」の側に取り込んで、利用しようというのが、山本の立場なのである。
つまり、本心は別にして、本書でも山本は、たいへん物分りが良く、一見したところ「リベラル」であり「庶民主義」的であり「フランシスコ支持派」であるかのように振舞っているのだが、本音はそうではないのだ。

本書でも、若松英輔は、怪獣博士による『怪獣図鑑』ごとく、これでもかという調子で「いろんな著名人(権威者)」を次々と引き合いに出して、ペダンティックにその博識ぶりを開陳してみせる。無論このあたりは、とうてい山本の及ぶところではない。
しかし、若松の「北斗百烈拳」的な「手数」勝負のそれは、教養コンプレックスのある読者には通用しても、「教会正統の権威」の光背を背負っている山本には、本音のところでは、まったく効果のないものでしかない。
しかし、山本は、それが「世俗的には効果がある」と知っているから、「鋭い指摘です」とか「神学にも通じるところです」といったように、さも感心したかのごとく褒めて見せるのだ。
私は、以前に書いた、若松に関するレビューで、若松の特徴を次のように紹介した。
『若松英輔の「霊性の哲学」とは、一種のシンクレティズムだと言ってよいだろう。
普通、シンクレティズムと言うと『相異なる信仰や一見相矛盾する信仰を結合・混合すること、あるいはさまざまな学派・流派の実践・慣習を混合することである。』(Wikipediaより)というようなことになるが、若松の独自性は、優れた個人(主に故人)を習合して、一種のマンダラに仕立てあげている点で、それは本質的に宗教的であると同時に、雑誌編集的であるとも言えよう。
若松の博捜によって呼び出された、聖人たちの居並ぶ姿は、白亜の神殿に勢ぞろいしたオリュンポスの神々にも似て豪華絢爛であり、それでいて親しみやすい。』
(若松英輔『霊性の哲学』についてのレビュー、「スピリチュアルな時代の「教祖の文学」」より)

(「ゼウスを中心としたオリュンポス12神」一部)
今回の対談でも、二人がやっているのは「若松英輔が横に展開し、山本芳久が縦に権威づける」ということである。
前回は、若松の方に、暗に「教会権威主義ではなく、個人の霊性重視を」という「教会批判」の側面が隠されていたが、今回の対談では、そうした「教会権威主義批判」は完全に影を潜め、逆に、若松の方が「教会権威」へと、すり寄っている。
若松は、前回の対談では「霊性主義者」を「個人主義者」として称揚したのに対し、今回は「霊性主義者は教会主義者である」という方向へと、ご都合主義的に「合理化」しているのだ。
例えば、フランシスコの時代になって「復権」した神学者ロマーノ・グァルディーニが、保守派神学者であり保守派教皇として知られた、前教皇ベネディクト16世と親しかったかのように書いているが、これはその実際を意図的に隠蔽し、ごまかした説明だ。
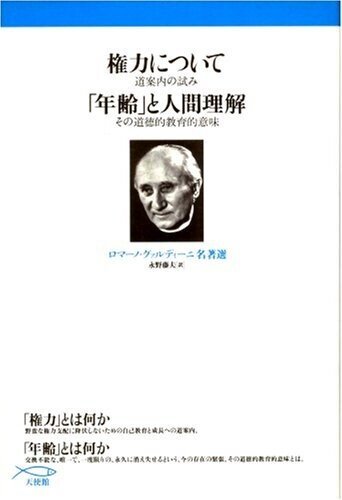
グァルディーニが、フランシスコになってから「復権」したと言うのなら、それは、その前のベネディクト16世や、ベネディクト16世に保守路線を引き継いだ前々教皇ヨハネ=パウロ2世の時代には、冷や飯を食わされていた、ということに他ならない。
では、そんなグァルディーニが、ベネディクト16世と「親しかった」とは、どういうことか?
それは、のちにベネディクト16世になる、保守派神学者である、ヨーゼフ・ラッツィンガーが、1981年11月に教皇ヨハネ・パウロ2世により、教理省の長官に任命された「カトリック神学者のトップ」だったからである。
ラッツェンガーは『教皇位を受けるまでその地位にあった。教理省はかつて検邪聖省といわれていたもので、古くは異端審問を担当した組織である。』(Wikipedia「ベネディクト16世」)
これが意味するのは、ラッツェンガーに睨まれた「リベラル神学者」は、冷や飯を食わされ、下手をすれば「異端」認定されて、カトリック教会に居場所を失うことになる、ということである。
そして、事実、そういう神学者は、少なからずいた。
例えば、戦中ナチスドイツと協定を結んでいたバチカンが、敗戦後に大きくリベラルな方向に舵を切ったことで知られる「第二バチカン公会議」を主導した、若手リベラル神学者の一人であったハンス・キュンクは、この公会議では同じ「若きリベラル神学者」であったラッツェンガーが、保守派に転向した後、徹底的に嫌がらせ(辱しめ)を受けることになる。

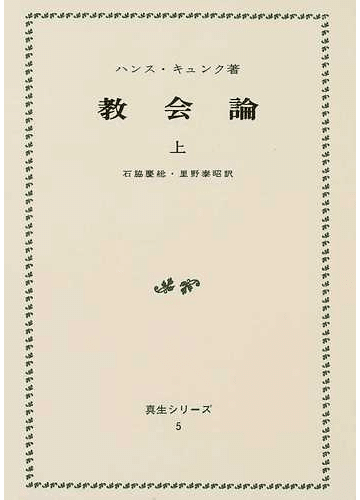
(ハンス・キュンクと、開かれた教会を訴えた『教会論』)
そして、そうした歴史的事実は、ラッツェンガーの側から書かれた、「ベネディクトゥス一六世=ベネディクト16世」の評伝である、今野元『教皇ベネディクトゥス一六世 「キリスト教的ヨーロッパ」の逆襲』(東京大学出版会)にすら書かれている事実で、リベラルなキュンクは、教会が急激なリベラル化の後の反動で保守化した(ヨハネ=パウロ2世やベネディクト16世の時代を含む)長い時期には、カトリック教会の「外」で、「第2バチカン公会議」の掲げた理想たる「教会の一致(エキュメニズム)」の運動を進めざる得なかったである。
つまり、グァルディーニがいかにリベラルな神学者であったとしても、キュンクのような迫害に堪える強靭な精神の持ち主でないかぎりは、現代の「異端審問所のトップ」であったラッツェンガー教理省長官であり、のちの教皇ベネディクト16世と対立することなど、およそ不可能であり、少なくとも「表面上は仲良く」していなければならなかったのである。

(※ 写真は、ベネディクト16世。その伝統的権威を誇示するため、保守派教皇は派手な冠や法衣を好んだ。質素なフランシスコとは、まさに真逆)
そして、ラッツェンガー教理省長官、のちの教皇ベネディクト16世の「リアルな人間性」がどのようなものであったかは、彼を恐れないで済む立場の有識者には、明らかなものだった。
例えば、「ガリカニスム」の伝統により、バチカンの統制に抵抗できたフランスカトリック教会の神父で、多くの国民から「アベ・ピエール(ピエール神父)」の名で親しまれた、本名「アンリ・アントワーヌ・グルエ」は、教皇になったばかりのラッツェンガー(ベネディクト16世)について、忌憚なく次のように語っている。
『『 ヨハネ・パウロ二世の後、次の教皇がいったいだれになるのか、明らかに人々の関心は高まりました。そのなかで人々がたった一つ心配していたことがあります。ヨーゼフ・ラッツィンガー枢機卿が教皇に選ばれることです。彼は以前の「教理省」(※ 引用者註・かつて異端審問を担当した、元「異端審判所」であり、元の「検邪聖省」)にあたる、信仰の教義を考える部門のトップでした。
私はこの良識ある指摘を最初にした一人だと思っています。私たちはよく社会のいたるところで、大きな責任のある立場に就く人がそれに見あった人になっていくのを目にします。責任ある立場に就いた人がかえって威圧的にふるまうこともありますが、多くの場合は余裕ができ、温和になり、自分を律していくものです。つまり一度頂点をきわめると人は今までよりも寛容になり、開かれた人になっていくものです。
ラッツィンガー枢機卿もベネディクト一六世となり、やはりこのように変わっていくでしょう。教皇選出当夜、彼のまなざしはすでに幸せそうで、穏やかでした。そして教皇として最初に述べた言葉は、他のキリスト教宗派(プロテスタント、英国国教会、東方正教会)や他宗教との開かれた対話を示唆するものでした。今後の彼の行動を待ちましょう。すでに変化の兆しが見られるのですから。
ラッツィンガー枢機卿が、有利な材料ではない七八歳という高齢にもかかわらず教皇に選ばれたことはとりたてて驚くにはあたりません。枢機卿たちは実はお互いにほとんど知らないのです。ところがそんな枢機卿のだれもがラッツィンガーのことはよく知っていたのでした。さらに言うならば、枢機卿たちの最大の関心事は安定です。波風を立てる必要はなく、冒険もいりません。ラッツィンガーを教皇に選ぶことでヨハネ・パウロ二世の方針を継続していくことができるのです。ラッツィンガーが高齢のためにそう長くは教皇を務められないことも彼らはもちろんわかっています。これは都合のよいことであり、枢機卿どうしがお互いをよく理解しあい、次の次の教皇にはだれがもっともふさわしい人物かを落ち着いてじっくり考えることができるわけです。それが今回ラッツィンガー枢機卿が教皇に選出された大きな流れなのです。
ベネディクト一六世が在位中に、リベラルと思える二つの方策をとったとしても私は驚きません。一つは再婚した人々に聖体拝領を認めることであり、もう一つはすでに子育てを終えた既婚の、つまり「年配の」男性の叙階を可能にしていくことです。これが聖パウロが言うあの「既婚聖職者」です。一方、女性が叙階され司祭職に就くことや同性愛の糾弾について、彼が立場を変えることはないと思います。』
(アベ・ピエール『神に異をとなえる者』P36〜39「ベネディクト一六世の即位」全文)』
あるいは、長年ドイツを率いてきた「キリスト教民主同盟(CDU)」のアンゲラ・メルケルは、プロテスタントではあれ、初めてドイツ出身のローマ教皇となったベネディクト16世とも面識はあったものの、心から親愛の情を覚えたのは、その次の南米出身の教皇フランシスコだったと、メルケルの著書『わたしの信仰 キリスト者として行動する』(新教出版社)の原書の編者であるフォルカー・レージングが、「編者解説」で次のように紹介している。
『(※メルケルは)ヨハネ・パウロ二世の後継者であるベネディクト十六世とは、彼がまだ枢機卿だった時代にすでに知り合っている。彼の知性に強い印象を受けたとメルケルは親しい人々にくりかえし語っているが、ドイツ出身の教皇とドイツの女性首相とのあいだには個人的な親近感は生まれなかった。
現教皇のフランシスコに対しては、メルケルは珍しく心を動かされたようだ。二人はこれまで何度もバチカンで面談している。難民危機が二人を精神レベルで兄妹にしたように見えるかもしれない。(中略)
メルケルにとっては、フランシスコは神学者としてよりも、外側からヨーロッパを見ているアルゼンチン出身の教皇として興味を抱かせる対象である。』
(P17〜18)
以上のようなことは、ベネディクト16世の時代に「神学者」になった保守派の山本芳久は無論、いくら若松英輔が「教会」について無知だったとは言え、おおよそのことは知っていたはずだし、教会「正統」権威にすり寄り始めた今なら、すでにはっきりと知っているはずだ。
だが、そんな若松は、本書において、グァルディーニとベネディクト16世を結びつけ、リベラルなフランシスコとベネディクト16世を結びつけて、世間では「リベラルと保守」という図式で見がちだが、カトリック教会の現実はそんなに単縦なものではなく、「神学的」に深いところでは、両者は継続しており、一つなのだ、などという「権威主義的レトリック」で、部外者を煙に巻こうとするのである。
したがって、「カトリック教会の歴史的現実」に無知な(カトリック信者を含む)読者は、若松英輔と山本芳久の「かけあい漫才」に乗せられて、すっかり騙されてしまう。
臆面もなく、両者がお互いに褒めあうことで、お互いの「権威」を保証しあうという、見え透いた手口でしかないのだが、「現実」を知らない読者は「きっとすごいのだろう」ということで、「すごい」と思わされてしまうのである。
しかし、本書で、若松英輔の「聖性(スピリチュアリティー)」という言葉が後退して、カトリック教会の「神学」という言葉が前面に出てくるのは、若松の立場が、「個人の神=イエス・キリスト」ではなく、「神の身体としての正統教会」に移動した、何よりの証拠でしかない。
そして、なぜそうなったのかと言えば、それは普通に考えて、若松英輔の「霊性主義」は、東日本大震災後の一時期を除けば、「オウム真理教事件」を経験した現代日本においては、どうしたって、その「うさん臭さ」は拭いきれなかったからである。

例えば、SF系の文芸評論家である岡和田晃は、小説家・倉数茂との対談「新自由主義社会下における〈文学〉の役割とは」で、次のように語っている。
『私がしばしば、批評を表現として認めろと言っているのは、別に批評に権威を回復しろという意味じゃなくて、そもそも例えば小説を書いたりゲームを作ったりするのと同じような表現の一角としての批評的な知性というのが存在して、それによってしか得られない世界の輪郭の可視化の方法というのがきっとあるはずだということのつもりなのですね。
そのため『反ヘイト』の冒頭に今の批評の三類型っていう非常に辛辣な文章を入れてるんですね。一つは極右(ネトウヨ)批評で、もう一つはオタク(サブカル)批評で、もう一つはスピリチュアルな批評っていう。なぜこういうのを思いついたかっていうと、文芸批評やってる時に、編集者と打ち合わせをしていて気づいたんですね、あ、状況として、そうなっているなと。
ただ具体的な固有名を出して批判すると「岡和田は浜崎洋介を嫌いなのか」みたいな党派的な受け止められ方をすることが多いのですが、そういうレベルではなくて、もう完全に売れ線の批評というものが三つに分類されるような状況というのがあって、それはスピリチュアルな商品として流通するようなレベルのものからハイレベルと思われているような文芸評論までけっこう幅広くその分野に当てはまってしまう側面があると思うんですよ。』
『司会女性 他にご質問ある方はいますか? はい、そこの方、ありがとうございます。
参加者B(著名な作家・評論家) 極右の批評と、オタクの批評っていわれるとだいたい顔が浮かぶんですけど、スピリチュアル批評って僕はあんまりよくピンとこないんですけど具体的にはどんな人の――。
岡和田 具体的に?!(笑)
参加者B 名前言えないの――。
岡和田 いや、言えなくないですよ。若松英輔さんですね。だめですか?
参加者B いやいやいや(笑)。
岡和田 あのね、もうちょっと具体的に言いますと、若松さんの仕事にも、僕はいい文章たくさんあると思うんですよ。パスカル・キニャールの本の解説でご一緒したこともあります。
若松さんは、たくさん批評の本を書かれているのですけど、やっぱりちょっと超越性に逃げるところがあるなぁと思っていて。
あのね、具体例を一つだけ出すと、3.11の後に石巻市ではたくさんのタクシーの運ちゃんが幽霊を見つけたっていう社会学的な研究があるんです。幽霊を乗せちゃうんですよ。
それを学生が実際に調査したっていう本が社会学と称してベストセラーになって(『呼び覚まされる 霊性の震災学』)。ゼミの先生が学生に聞き取り調査をさせたんですが、明らかにいろんな別々な運ちゃんが幽霊を乗っけてるんですね。乗っけて途中で消えるんですよ。
それはやっぱり3.11の後の集合的なトラウマがあるっていうのが一つの解釈だと思うんですけれども、その研究書の目玉論文では、ある種のスピリチュアル批評を元にして、まぁ霊界的なものが存在するんじゃないかという結論になってたんです。
つまり現世の後にスピリチュアルな世界というのが前提になっているような論文っていうのはけっこうあって、典拠として示された一番文学的に高度なものの一つが若松英輔さんの本なのです(『霊性の哲学』)。
この件に限らず、より低レベルなものだと本棚のスピリチュアルコーナーにあるようなものもスピリチュアルな批評だと言えるように思うんです。
それらの問題点はやはり、社会問題の一番重要な部分というのを「霊界」や「癒し」で逃げているという部分にあると思うんですね。そことは戦っていきたい……というのはお答えになってますか?
参加者B それ今まで批評と思ってなかった(笑)。
岡和田 いやあのね、若松さんのお書きになる批評にはいい批評もありますよ。面識こそありませんが、ご本人のお人柄もいい人ではないかと思いますし、そういう意味では喧嘩をしたくないんですね。罵倒のやりあいみたいに彼となってもしょうがないんです。そのため、彼については『反ヘイト』では名指しをしていません。
ただ実際にある種の霊的空間が存在してそこでタクシーの運転手がいろいろ幽霊を見ているみたいな言説の前提になっちゃってるという事実があるので、やっぱり、社会学が踏み越えてはいけない一線を踏み越えてるわけですよ。そういった言説の基盤の一つが、スピリチュアル批評が担保してると思うんですね。スピリチュアルな部分の支持基盤を崩したいと。構造を変化させたいんです。
参加者B ありがとうございます。』
見てのとおり、岡和田晃は、若松英輔の批評が「スピリチュアル批評」であり「問題がある」と思いながらも、同業者から質問されなければ、その「本音」を口にするのを避けていた。これが「出版業界の現実」なのだ。
若松英輔を「うさん臭い」と思っている業界人や評論家は大勢いるのだが、なにしろ若松は「売れっ子」だから、それを批判して「損」をしたくない。
言わば、カトリック教会において『現代の「異端審問所のトップ」であった、ラッツェンガー教理省長官であり、のちの教皇ベネディクト16世と対立することなど、およそ不可能』だったほどではないにしても、やはり「売れっ子」は敵に回したくない。
私はなにも、『喧嘩』をしろとか『罵倒のやりあい』をしろ、などと言っているのではない。
文芸評論家として、普通に、「おかしいものはおかしい」という「評価を語れ」と言っているだけなのだが、若松英輔との接点がさほど多いわけでもない、SF系の評論家である岡和田にして「コレ」なのだから、若松に近い位置にいる小説家や出版業界人が、表立って若松を批判することなど、考えられなかったのである。
しかし、近年の若松は「霊性主義(スピリチュアリズム)」を強調しすぎていたし、またその「反・教会主義」「反権威主義」を、世俗的「人気」を後ろ盾にして強調しすぎた。
つまり、最初は若松の「霊性主義」という言葉の目新しさに惹かれた(カトリックの無知な一般信者を含む)一般人も、そればかり聞かされると飽きが来るし、だんだんと「ちょっと、うさん臭いんじゃなの?」と思えてくる。
実際、国分太一・美輪明宏・江原啓之が出演して、2005年から2009年までテレビ放映された人気番組『オーラの泉』の頃は、「スピリチュアリズム」が一大ブームを巻き起こしたが、その後は相応な落ち着きを見せている。
もちろん、このブームによって「スピリチュアリズム」が一般化し浸透したので、ブームは落ち着いた、とも言えるのだが、しかし、ブームが過ぎた後にも、同じ調子でやっていれば「ちょっとこの人、おかしいんじゃないの?」となるのは、「流行」現象の常なのである。

したがって、「文学」の世界において「霊性主義(スピリチュアリズム)」を主導した若松英輔も、そんなものばかり書いておれば、やがて岡和田晃のように「うさん臭い」と感じる人たちが出てくるというのは必然であり、そうなると、カトリック信仰の場においても、若松英輔の「後ろ盾」だった「世間の支持」が弱まったことになり、若松の立場そのものも弱まることになる。
そこで若松英輔は、従来の「反・教会権威」的な立場から「教会権威」の方へすり寄り始めた、というのが今回の対談『危機の神学』であり、前回の対談『キリスト教講義』との根本的な違いなのだ。
○ ○ ○
じっさい、若松英輔という人は、その人当たりの良さそうな感じからは窺いにくい「強かな現実主義者」の側面を持っている。
つまり、いつまでも「反・教会」的な「霊性主義(スピリチュアリズム)」者であるのは「得策ではない」と判断し、手のひらを返して利口に立ち回るくらいの「要領の良い厚顔さ」は、持ち合わせているのである。
若松英輔は、2007年に「求道の文学――越知保夫とその時代」で第14回三田文学新人賞を評論部門で受賞して、「文学」の世界に足がかりを得るが、本格的に売り出すのは、2011年に『井筒俊彦 叡知の哲学』を刊行して話題となり、その直後から「東日本大震災」に関わる「霊性主義(スピリチュアリズム)」的な著作である、『神秘の夜の旅』(2021)、『魂にふれる 大震災と、生きている死者』(2021)、『死者との対話』(2012)などの刊行によってである。
そのあたりから著述家として売れ始め、2016年に『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』で第2回西脇順三郎賞を受賞して、「評論家」としての立場を確立したと言えよう。(Wikipedia「若松英輔」)
若松は、まだ無名だった2007年に『ミッチェル・メイ・モデル 「スピリチュアリティ」と「ビジネス」を高い次元で融合した男。』( ヴォイス)という、米国の有名なヒーラー(霊的な力で病いを癒す人)であるミッチェル・メイの書いた「ビジネス書」を翻訳刊行し、同書にメイを絶賛する文章を寄せている。
つまり、この頃の若松英輔は、とうていカトリックとは思えないほど、「霊性主義(スピリチュアリズム)」者どころか、ほとんど「神秘主義者(オカルティスト)」だったのだ。

ところが、出版業界で「売れっ子」になった後は、この種の「超能力」的なものからは徐々に距離をおいて、あくまでも「精神的」なものとしての「霊性主義(スピリチュアリズム)」者であることを強調するようになる。端的に言えば、ミッチェル・メイのような「超能力者」については、言及しなくなるのである。
そして、このあたりに、若松英輔という人の「世俗的な立ち回りのうまさ」が、すでに窺えたのだ。
若松が著述家として「売れっ子」になる以前から、「ミッチェル・メイ・モデル」的なビジネスにおいて付き合いのあった大瀧純子は、若松英輔の公式ホームページ「読むと書く」に次のような文章を寄せている
『2020-09-25 ミッチェル・メイが与えてくれたもの
あるマンションの小さな一室で、「読むと書く」の講座をほそぼそと始めた6年前、私たちの本業は米国のシナジーカンパニーが製造しているオーガニック・ハーブサプリメントを輸入し、販売することでした。
52種類のハーブをブレンドした「ピュアシナジー」という製品が一番人気で、それなしに今の私たちは存在しないといっても過言ではないほど、多くの方に支持され、ご愛用頂いてきました。
そのことと「読むと書く」の講座や若松さんの活躍はまた別のもののように感じてきたのですが、先日、そうではないことに気がつきました。なぜ、今までそこに思い至らなかったのか不思議なくらいです。
「ピュアシナジー」の生みの親はミッチェル・メイ。60代のユダヤ系アメリカ人です。特別な才能を与えられ、ヒーラーとしての活躍ののち、今から30年ほど前に会社を創業しました。
彼と若松さんとの出会いは今から20年以上前になります。その不思議な出会いのお話しはまた別の機会に、と思いますが、先日、久しぶりに彼と電話で話しをしました。
若松さん、ダニエル(現CEO)も参加して、フランクな雰囲気のなか、互いの近況報告をするなかで、「読むと書く」の事業の話になりました。内容について詳しく話したのははじめてです。
たどたどしい説明で、理解して貰えただろうかと不安を感じるなかで、自分でも思ってもみなかった言葉が口をついて出ました。
「私たちが今やっていることは自分たちの手でピュアシナジーを作って、人々に届けることなんです」
「植物のかわりにコトバを集めて・・・。こころやたましいを深いところから支えられるコトバを」と。
本当にそうだ、やっとそれに気がついた、という驚きと同時に、安堵の気持ちになっていました。
しばしの沈黙が流れ、何かを深く考えているときの、瞑想中のような、静かなミッチェルの顔が画面に映っています。彼らしい、強さと威厳のある表情でもあります。
数秒のことが永遠にも感じられるほど、濃密な時間でした。やがて彼はやわらかな笑顔を見せて、ゆっくりと口を開きました。
「あなたたちを心から誇りに思うよ。ほんとうにありがとう」。
気づけば涙が頬をつたい、エイスケも涙をこらえていました。
続きは次回に・・・
※18年間にわたりシナジーカンパニー製品を販売させて頂きました。2019年、日本での輸入・販売は終了しています。』
『2020-10-30 信じること・・・若松さんとの出会い
もうだいぶ前になりますが『女、今日も仕事する』(ミシマ社)という本をださせて頂きました。そのなかにも一部書かせて頂いたと思いますが、若松さんとは20年近く前にはじめて会いました。ナチュラルハウスというオーガニック関連商品を扱う会社の商談室で、若松さんは商品を売り込みに来たいわゆる「業者さん」、私は新米バイヤーでした。まだ二人とも30代前半で、息子は小学2年生でした。
実際に顔を合わせたのはそれが初めてだったのですが、それ以前に、互いの会社が開発した商品(ハーブサプリメントのシリーズ商品)は知っていました。若松さんの方が先に販売していましたが、私はその半年ほどあとに商品を完成させ、アロマセラピーサロンや小売店などに卸し始めていました。その商品を見つけて、誰が開発したのだろう?とずっと興味をもっていたと若松さんはその時話してくれました。その少し前に当時の薬事法が改正され、メイドインジャパンのハーブサプリメントが製造・販売できるようになってすぐのことです。
当時の若松さんは、とにかく早口で弁が立ち、エネルギッシュ。押しも強めで営業マンらしい印象でした。今も変わらないのは知識が豊富で行動力があるところ。まずは良い印象を持ちましたが、あるとき、仕事の打ち合わせを喫茶店で、という約束をしたさい、2時間も連絡なしに待たされたのは今も忘れられません(笑)。その後、一緒に仕事をすることになるのですが、ほんとうにいろんなことがありました。良いことばかりではありません。会社は何度も危機を迎えましたし、もうこの人とはやっていけないと不信感に陥ることもありました。若松さんも、そして私も、人間としても仕事人としても「未熟だった」のだと思います。
けれどもここまで一緒にやってこられたのは、互いの可能性を信じられたからではないか、と思っています。まだ本も出されていませんし、仕事も会社も綱渡りで危なっかしかった若松さんでしたが、私にはないものを彼は持っていたし、逆もそうだったと思います。結果的に、会社の代表は私にかわり、同時期から若松さんは(今では多くの)著書を出すようになり、世に認められはじめ、「読むと書く」などの講師、そして大学の教授にもなりました。
若松さんが言ってくれた今も覚えている言葉があります。「僕は会社をうまくやっていく能力は足りなかったけれど、大瀧さんを見つけてきたことが僕の最大の功績だよ」と。 私から言葉を贈るとしたら、「言葉そしてコトバの力を教えてくれてありがとう。今、この読むと書くの現場にともにいられることが本当に幸せで、誇り高いです。これからもよろしく」と言うかしら。面と向かっては照れくさくて言えないかも知れませんけれど。 そして、信じることで互いの能力を開花させることができる、その経験の重みと素晴らしさを今あらためて実感しています。』
つまり、大瀧と若松は、ミッチェル・メイの会社が販売していた「オーガニック・ハーブサプリメント」の輸入代理店をやっていたというわけである。
そして、その流れで、前記の『ミッチェル・メイ・モデル 「スピリチュアリティ」と「ビジネス」を高い次元で融合した男。』を刊行したのだ。
ミッチェル・メイが、どれだけすごい人物かを、日本人に知らせないことには、肝心の「オーガニック・ハーブサプリメント」も売れないからである。
ともあれ、旧友である大瀧純子の文章で注目すべきは、私たちの持つ「若松英輔のイメージ」とはちょっと違った、次のような部分である。
『 当時の若松さんは、とにかく早口で弁が立ち、エネルギッシュ。押しも強めで営業マンらしい印象でした。今も変わらないのは知識が豊富で行動力があるところ。まずは良い印象を持ちましたが、あるとき、仕事の打ち合わせを喫茶店で、という約束をしたさい、2時間も連絡なしに待たされたのは今も忘れられません(笑)。その後、一緒に仕事をすることになるのですが、ほんとうにいろんなことがありました。良いことばかりではありません。会社は何度も危機を迎えましたし、もうこの人とはやっていけないと不信感に陥ることもありました。若松さんも、そして私も、人間としても仕事人としても「未熟だった」のだと思います。』
つまり、かつての若松英輔は「やり手の営業マン」そのものだったのである。無論「機を見るに敏」な人であったことは間違いないだろうし、それが後に「出版業界」でも役に立ったというのも、想像に難くない。
そして、そうした「機を見るに敏」さというのは、当然のこと、カトリック教会との関係においても発揮されたであろう。それが『従来の「反・教会権威」的な立場から「教会権威」の方へすり寄り』なのではないかという「読み」は、ごくごく常識的なものだと思うのだが、いかがだろうか?
○ ○ ○
このようなわけで、本書『危機の神学』は、平たく言ってしまえば「無内容」である。

(教皇フランシスコ、受刑者の足洗う イタリアの刑務所で「洗足式」)
現教皇であるフランシスコを持ち上げて「弱者の側にあること」を強調して見せるわりには、では「これまでの自分たちはどうであったか」とか「これから自分たちは、具体的に何をなすつもりか」といった話は、完全に全く出てこない。
本書で語られているのは、「フランシスコは素晴らしい」「神学的思考は、深く本質的であり重要だ」「カトリック教会は、歴代教皇において一貫しており、保守だのリベラルだのといったことを超越している」といった、具体性のカケラもない話ばかりで、最後まで「自画自賛」に終始しているのである。
私にこの評価が、嘘だと思うのなら、本書を読んで、是非ともその目でお確かめいただきたい。
イエスの口真似ではないが『はっきり言っておく』(新共同訳)と、本書のような「無内容で口先だけの、権威主義的空言の書」をありがたがるのは、「現実逃避」したいだけの「権威主義者」だけであって、本書のようなものに最も嫌悪を示すのは、私ではなく、教皇フランシスコその人であろう。
(2021年12月26日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
