
中野美代子 『西遊記の秘密 タオと煉丹術のシンボリズム』 : 楽しく果てしない「学問」
書評:中野美代子『西遊記の秘密 タオと煉丹術のシンボリズム』(福武文庫・岩波現代文庫ほか)
中国文学者・中野美代子は、私の大好きな作家だ。
翻訳書や共著を除くと、40冊にも及ぶ著作を持つ作家だが、たぶん私は、そのすべてを所蔵している。しかしながら、そのうちで読んだものは、ごく限られている。
一一という話は、中野の小説集『契丹伝奇集』についてのレビューで、2年弱前にも書いている。
『中野美代子の著作は、翻訳書や共著を除くと40冊ほどになるが、たぶん、私はそのすべてを所蔵している。一一所蔵しているのだが、読んだものはごく一部だった。
昔の読書ノートによると、前記『カニバリズム論』の他に『孫悟空の誕生』『南半球綺想曲』『耀変』『中国人の思考様式 - 小説の世界から』の5冊だけ。これに今回の『契丹伝奇集』を加えても、わずか6冊(他に、弟子の武田雅哉との共編書『中国怪談集』も読んではいる)。
昔読んだ5冊の中で、はっきりと印象に残っているのは、最初の『カニバリズム論』と、久生十蘭のパスティーシュ長編小説『南半球綺想曲』だった。本文庫『契丹伝奇集』所収の『耀変』は、初版の響文社の単行本(古本)で読んでいるのだが、内容をほとんど記憶していなかった。当時の私にはあまり楽しめなかったということであろう。』
さて、そんなわけで、今回は『孫悟空の誕生』に続く、『西遊記』研究の2冊目にあたる本書を読むことになった。
上にも記したとおり、『孫悟空の誕生』は、さほど楽しめなかったというよりは、内容がまったく記憶に残っていない。読書ノートをつけていたから読んだというのは、確認してわかったが、でなければ、読んだかどうかすら記憶に残らなかっただろう。
ちなみに、『西遊記の誕生』を読んだのは、平成元年(1989年)の1月で、元号が変わった直後。すでに30年以上前のことで、私も二十代後半で若かった。
だが、だからこそ、当時は楽しめなかったものでも、今なら楽しめるのではないかという自信が少なからずある。なにしろ、当時と今とでは、教養が違うのだ。
当時の私が、この私の文章を読めば腹を立てるのかも知れないが、私も伊達に、あれから30年以上生きてきたわけではないので、当時の私が、今の私と互角に渡り合うことなど、所詮、無理な話なのである。「まあ、今後も、しっかりと本を読みたまえよ」てなもんである。
ただまあ、本書を楽しみにしていたのは、何も私に教養がついたというだけが理由ではない。
本書『西遊記の秘密』のサブタイトルは「タオと煉丹術のシンボリズム」で、もともと私の好きな「オカルティズム」や「中華幻想」を扱った作品であり、しかも30数年前とは違って今の私は、澁澤龍彦的な「趣味のオカルティズム」に興味があるだけではなく、その後に、キリスト教を中心とした「宗教」を、関連書でかなり学んだので、「文学趣味」的な側面だけではなく、「人間学」的な側面においても、本書を楽しむことができるはずだと、そう考えたのだ。
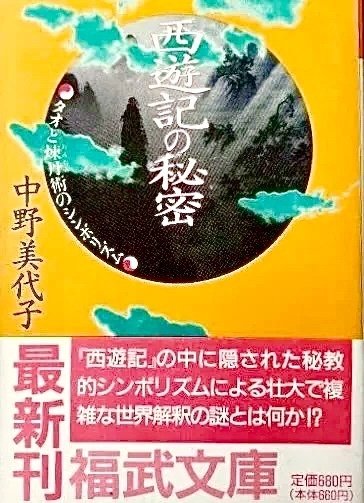
西欧においてキリスト教が広く信じられ、日本では仏教や神道が広く信じられたのと同様、中国では仏教と同時に「道教」が庶民の生活に深く溶け込んで、大きな影響を今も残している。
そうした点で、『西遊記』に秘められた、「タオ(道)」を中心的概念とした「道教」、そしてそこに含まれる長命術として始まった「錬丹術」の錬金術的神秘思想の影響を読み解こうとする本書は、ある意味では、人間に普遍的な「神秘指向」や「アナロジー思考」を剔抉するものとして、『西遊記』や「中国文学」といった話に限定されない、人間学的な深みを持った研究書なのである。
単に「中国人は、変なことを考えるなあ」といって楽しむだけではなく、しかし、そこには私たちが今なお持っている「根源的発想」が、形式を変えたかたちで表れているのだ。
だから、「道教」であれ「錬丹術」であれ、それ自体としては、私を含む多くの日本人には馴染みのないものだが、だからこそ興味深いのと同時に、しかし、その「精神誌」的なものまで読み込むならば、それは、「キリスト教」や「キリスト教神秘主義」や、あるいは「仏教」や「神道」とその「密教」的なものにまで通じていき、それらに秘められた「人間的な本質」を探ることも可能なのである。

本書で探求されるのは、『西遊記』に秘められた「道教」のシンボリズムといったことであり、それは「今の日本の大学」では「役に立たない(金儲けにならない)学問」として退けられがちなものなのしれないが、しかしながら、一見「無駄」と思える「文化研究」を通して、その奥にある、人間の「普遍性」を探るという意味では、実のところ本書は「学問らしい学問」の精華であり、今どき珍しい「贅沢な学問」だと言えよう。だから、これを楽しまない手はないのである。
○ ○ ○
それにしても、本書を読んで、まず「面白い」と感じたのは、中野美代子の「人柄」である。
じつのところ、私はこれまで、中野美代子という人が、よく分かっていなった。
前記『契丹伝奇集』のレビューに、
『高山宏が、本文庫『契丹伝奇集』に収められた、本書単行本刊行時に寄せた書評「『契丹伝奇集』をめぐって 奇譚を口実にポップ・マニエリスム」で『ポスト澁澤龍彦の一番手と目されている中国文化史家、中野美代子氏』と書いているとおりで、私は、大好きな澁澤龍彦周辺の文学者として中野美代子に注目し、その著作を片っ端から蒐めだしたのだった。』
と書いたように、私にとっての中野美代子は、まず「澁澤龍彦周辺の人」という認識だったのだが、ある時、中野が、ジャーナリスト「本多勝一」に関する研究書『本多勝一を解説する』(晩声社 1992年)の、編者代表を務めているという「意外な事実」を知った。
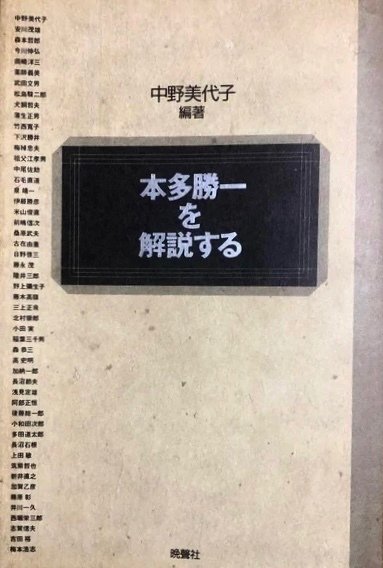
「本多勝一」のことを知っている人なら、この人が「澁澤龍彦」とはおよそ縁遠い世界の住人だというのを、容易にご理解いただけよう。
『1963年の朝日新聞連載『カナダ・エスキモー』が注目を集め、つづいて1964年には『ニューギニア高地人』を連載、反響を呼んだ。本多はベトナム戦争の取材に取り組みたかったが、一連の連載が好評を博したため、1965年には『アラビア遊牧民』を連載。これらのルポルタージュは「極限の民族」三部作とされ、文化人類学にインパクトを与えた。1964年に菊池寛賞を受賞。
1967年にはベトナム戦争が苛烈を極める南ベトナムを1年にわたって現地取材、翌1968年には北ベトナムを取材し、ルポルタージュを連載。1968年に第11回JCJ賞および第22回毎日出版文化賞を受賞、1969年にボーン・上田記念国際記者賞を受賞。
1969年にはアメリカ合州国を半年にわたって取材。
日中国交正常化前の1971年には中国における戦争中の日本軍の行動を中国側の視点から掘り起こした『中国の旅』を連載。本書は南京事件論争の大きなきっかけとなった。
1982年には『日本語の作文技術』を発刊し、自身最大のベストセラーとなる。
朝日新聞編集委員を長らく務め、1991年に定年退職。
『朝日ジャーナル』の最終号となった1992年5月29日号の連載コラム「貧困なる精神」において有志による日刊新聞の発行構想を発表した。
『噂の真相』1993年2月号のインタビューで日刊紙に先行して週刊誌の創刊を予定していることを公表。1993年7月から4号発行された月刊金曜日の編集委員となり、「創刊の言葉」の原案を起草。1993年11月の週刊金曜日発刊後も編集委員を務める。1994年5月から1997年3月まで編集長を務めた。』
(Wikipedia「本多勝一」)
つまり、激動の70年代、朝日新聞記者として、世界の「現場」に赴いて、生々しいルポルタージュを書いて評判となり、それまでは一般に知られなかった「南京大虐殺」の問題を「被害者である中国の側(殺される側)」の視点から初めて日本に紹介し、今に続く論争をまき起こして、左翼リベラルのスターと呼んで良い存在となった人である。
したがって、「サド裁判」で、国家に楯突いたこともある反体制派ではあれ、「世事」や「政治」とは一線を画した澁澤龍彦とはほとんど交わることのない、「世俗社会の政治問題」の世界で活躍したのが本多勝一なのだが、そんな本多を、中国文学の研究者であり「澁澤龍彦周辺の人物」で、要は「ブッキッシュ(書物的)」な世界に生きている人だと、私がそう思い込んでいた中野が、ほとんど「畑違い」という印象のある本多勝一についての、肯定的な評論集の「編者代表」だと知った時には、流石にこれは「同名異人」だろうとさえ疑ったほどだったのである。
ところが、本書を読んでみると、中野が「本多勝一」を支持するというのは、「十分あり得る」ことだというのがわかった。
どういうところかというと、中野美代子という人は、一言でいうと「男前な性格」の女性なのである(喩えて言えば、イメージとして、女優の天海祐希みたいな人だと言えば、わかりやすいだろうか)。
つまり、良いことは良い、ダメなことはダメだと、キッパリと言い切って臆するところのない、さっぱりした性格の人なのである。だからこそ、基本的には「反権威」であり「反体制」派だ。
それに、先日読んだ、澁澤龍彦の評伝『龍彦親王航海記』(磯崎純一)によると、中野は澁澤に直接会ったことがないそうだ。
澁澤の方が中野の著作(『カニバリズム論』)を評価した立場なのだから、中野にその気があれば、澁澤と「お近づきになる」ことは、容易だったはずだ。だが、そういう「有名人の取り巻き」的な世俗的関係を必要としなかったのが、中野美代子という人なのであろう。本書を読めば、中野美代子という人の「学問愛」がひしひしと伝わってきて、澁澤の「文学的ディレッタンティズム」とは、質的に違うものが感じられるはずである。

そしてそんな「学者」であるからこそ、誠実な研究に対しては、誰よりも「敬意」を忘れない人なのだが、その一方で中野は、違うものは違うと言い切ってそれを実行し、やはり、学者社会の序列的なものに妥協して馴れ合うような人ではなかった。
例えば、次のような、幾つもの箇所(引用箇所)に、中野のそうした性格が、とてもよく表れているはずである。(※ なお、原文傍点部分はゴシックで表記し、ルビはあとカッコで記した。ページ数は、福武文庫のものである)
(1)『断っておくが、『西遊記』の主人公たちを五行や八卦、さらには錬丹術の第一質料(プリマ・マテリア)などにあてはめるのは、もちろん、こじつけである。とはいえ、くりかえし強調しているように、こじつけにも一貫した論理が必要である。』(P147)
「こじつけ」に傍点が付されているように、中野にとっては『五行や八卦、さらには錬丹術』といったものは、「信じるもの」でも「真に受けるもの」ものでもなく、「多くの人(庶民)が信じたもの」としての「事実」であった、ということだ。だから、肝心なのは「彼らの信じたことを信じる」のではなく「彼らはどのように信じたのか」という事実を探ることなのである。
彼らが信じたことは「非合理」の「非現実」ではあったけれども、彼ら自身は、それを無理にでも「合理的な現実法則」を語るものとして信じていたのであり、そこに「人間というものの不思議」があるからである。
(2)『 中国の古典に登場する聖数としては36と72がもっとも頻度が高いであろう。そこで、近年はこれらの数字について論じる学者も少しずつあらわれてきた(中略)。しかし、その議論は、事例を列挙し、それぞれが実際の数であるか概数であるかを文献的にたしかめて終わるにとどまって、数字そのものの神秘性やその論理には立ち入らないのがふつうである。せっかくのおいしい素材をまずく調理するのは、中国学一般に共通する傾向であるが、数字についても同断であること、嘆いておいてよいのであろう。』(P198〜199)
学問が「厳密」でなければならないというのは、当然の話である。しかし「厳密」であることと「しかつめらしい」ことは、決して同じではない。
「厳密」なればこそ、深く「楽しめる」ということがあるし、逆に、真面目そうな顔で、ルーチンを退屈にこなしているだけの研究者というのも少なくない。
そして、「学問」の世界では、時に「中身の真面目さ」よりも「見かけ上の真面目さ」が重視されたりする。「退屈な事実の羅列だから、真面目な研究だ」などと評価されてしまうことが、案外少なくない(特に「象牙の塔」の時代は)。
なぜそうなるのかといえば、そうした「中身(質)」を問わない、「見掛け(形式)」の方が、誰にでも評価が容易だからであるし、物事の本質を問わない分、上の人には「扱いやすい」からである。
例えば、ミステリー小説でもSF小説でもいいが、作品中のトリックやアイデアについて「これは、前例のあるトリック(アイデア)だ」という指摘なら、「オタク」にだってできる。
しかし「この作品における(この作者における)、このアイデアの必然性とは何か?」といった本質的な問いは、知識が豊富なだけの「オタク」(的な学者)には不可能だ、というのと同じことであり、また、権威に盲従せず「本質を問う」者は、体制側には危険な存在なのだ。
(3)『ここでもまた、実在する北斗と南斗からのアナロジーで、東斗・西斗・中斗をでっちあげる観念的操作が見られ、それは、錬丹術におけるあの隠秘主義(オカルティズム)の根底をなす精神であった。このことは、道教について述べる多くの書物が看過しているので、ここで改めて強調しておきたい。』(P212〜213)
ここで語られていることは、キリスト教で言うならば、「三位一体論」と同じことだと言えるだろう。
つまり「もっともらしい体裁」を整えるために、後付けで、いろんな概念を「でっちあげ」ているだけなのだが、表面的なところで魅惑されている人には、「でっちあげの非事実」でさえ「深い神秘」だと感じられてしまうということだ。
そして、そのことは、何も中国人やキリスト教徒に限られる話ではない。
多くの日本人もまた同様に、「原始人」的なのである。
(4)『位業とは、いわばヒエラルヒーのことであるから、この『位業図』を読めば、道教神の体系がすっきりわかるかといえば、そうはいかない。また、いまの場合、道教神すべてについてそんなにくわしく知る必要もないし、興味もない。まあ、このあたりは専門家にまかせておこう。』(P234)
『位業図』には、道教神のヒエラルヒーが、わかりやすく表現されている。しかし、だからそれで『すっきりわかるかといえば、そうはいかない。』。
なぜなら、「道教神」というのは、そもそも実在しない「フィクション」だからで、人によって、いろいろな位置付け配列がなされており、そのヒエラルヒーに「正解」など、もとから存在しないためである。
したがって、そんなものをいくら深く研究しても、「道教神のヒエラルヒー」に関しては、決して「正解」は得られない。得られるのは「人間って、存在しないものに、ここまで執着できる、不思議な生き物なのだなあ」という、事実の重さである。
しかしまた、そうした研究も、それはそれで学問的には意味がある。「不毛な事実」を徹底的に研究するからこそ、その「不毛さ」の重さを深く感じとることもできる。
けれどもまた、「不毛さの研究」というのは、よほど好きな人にしかできないものだというのも、言うまでもない事実なのだ。
(5)『(※ 『雲笈七籤』には)やたらに最高神ばかり出てきたが、どれがいったい本当の「最高神」なのかというと、依然としてわからないのである。そこで、現代の台湾と香港における実際の道教儀礼や、今世紀はじめの清末から民国初にかけての「天地三界十八仏諸神」絵図などでながめたほうが、てっとりばやいであろう。』(P235)
『最高神ばかり出て』くるのは、そもそも「神」が実在しないから「どうとでも表現できる」ということに他ならないのだが、だからこそ、いくら文献に当たっても、「どの説が、一般的なものなのか」は分かりにくいので、実際に今も庶民の中に残っている儀礼を確認した方がよほど分かりやすい、という話である。
(6)『 (※ 『西遊記』の作中に登場する)この種の道士たちの詮索は、大しておもしろいものではないが、小説のなかのかれらのヒエラルヒーを厳密に追求していけば、『西遊記』の成立に最終的にあずかった人物の道教における立場についてのヒントが得られるかもしれない。しかし、私の手にはあまるので放棄した。』(P242)
『西遊記』作中の道士たちのヒエラルヒーを詳しく分析することで、「道教」についてどのような考え方の持ち主が、『西遊記』に決定的な形式を与えたのかが推測できるはずだという話だが、いうまでもなく「道士」や「道教」の研究は、それ自体、生涯を賭けても完全な解読の不可能なものなのだから、『西遊記』の研究という本来の目的に立てば、いくら面白そうでも、脇道をそこまで深く探究している暇はない、ということだ。
そしてここで大切なのは、中野美代子が繰り返し「自分の知らないことは知らない」と明記している点である。
というのも、二流の学者にかぎって「周辺諸学にも通じていますよ」みたいな顔をしたがるからであり、またそうしたことに、ころりと騙されてしまう「素人読者」が少なくない、という事実があるからである。
例えば、私がいま読み始めたばかりの、カトリック神学者カール・ラーナーの著書『キリスト教とは何か 現代カトリック神学基礎論』(邦訳・1981年)で、ラーナーは「必要だから、あるいは、知っておくべきだからといって、そうした周辺学問まで収めることは、ひとりの人間には不可能だ。キリスト教神学という学問一つをとってみても、今やそれは多岐にわたっており、そのすべてを知っている神学者など、一人もいない。だから、すべてを知る必要などはないけれども、少なくとも、その知りうるところに誠実であることにおいて、その探究は、決して無意味ではない」という趣旨のことを、開巻早々わざわざ断っている。
こういうことは、ラーナーほどの篤実な神学者だからこそ言えるのであって、世俗向けの著書だけは多い、知ったかぶり日本の神学者などには、爪の垢を飲ませたいほどの「謙虚さ」であり、本物の「確信」だと言えるだろう。

同様に、中野美代子も、「知らないことは知らない」と包み隠さずに言えるほど、自分にできる精一杯の努力をしている、ということである。
人並み以上の地道な研究の裏付けがあってこそ「私はまだまだ無知だ」と平気で言えるのであり、また「学問を楽しんでみせる自信も持てる」のである。
(7)『演劇の定義はいろいろあろうが、なにはともあれ、約束された空間わけても約束された虚構の空間すなわち舞台が、物理的にも心理的にも確立なりなければ、演劇は成りたたない。たとえば、観客は実生活の場の延長である観客席にいるが、すぐ目の前の舞台を、現実から隔離された約束された空間であり、その舞台の上で展開される時間の流れや事件も、現実とは別個の、ある約束ごとに支配されたりされたものであることを認識しなければ、演劇は成りたたなくなる。劇中の殺人犯を、観客のなかの刑事が舞台にのぼっていって逮捕するのはこっけいであること論を待たないが、しかし、国家権力はしばしば、このような約束ごとの原理、ないし虚構の原理を踏みにじる。
中国人がこのような虚構の原理にきわめて冷淡であったこと、私はすでにいく度か指摘した。例としてあげたのは、ヨーロッパ人のユートピアに対する桃源境、物語における自己完結性の欠如、絵画における額縁の意味などであったが、演劇の発生が異常におそかったこともまた、有力な例としてあげることができるであろう。つまり、中国の物語や小説の本質を考えるためには、中国演劇史の空白の部分が、思索上のおもしろい材料となるわけである。』(P279)
『劇中の殺人犯を、観客のなかの刑事が舞台にのぼっていって逮捕するのはこっけいであること論を待たないが、しかし、国家権力はしばしば、このような約束ごとの原理、ないし虚構の原理を踏みにじる。』一一という部分に、容易に、中野美代子の反体制的な意気を感じることができよう。
ただ、『中国人がこのような虚構の原理にきわめて冷淡であった』云々の部分は、私個人の「特性」とも関わってくるので、この点については、後で別に論じたいと思う。
(8)『なお、余談であるが、中国人のなかにも、(※中国の学会において通説となっていた)呉承恩作者説に強く反対する学者もいる。『西遊記釈義』を書いた台湾の陳敦甫で、かれはこれを邱処機の作とすることをに固執するあまり、呉承恩説を否定するのであるが、邱処機の作であるという誤った大前提を除けば、呉承恩説への批判の筆法はなかなかに正鵠を射ている部分もある。ただし、逆に、邱処機説をとなえる論法は、呉承恩説をとなえる学者たちの論法と、なんら逕庭もない。にもかかわらず、私が陳敦甫の邱処機説を一笑に付することをあえてしないのは、世の呉承恩説信奉者たちの、みずからの誤れるを前提には少しも懐疑的にならぬまま、他の誤れる前提を笑うことの愚に、多少の皮肉まじりの微笑を送りたいからである。ミイラとりは、いつでもミイラになりうるが、みずからもその轍を踏まぬように、陳敦甫氏を顕揚しておくこと、決してわるいことではあるまい。』(P302)
例えば、私は先日、ミステリ作家でカトリック信者である清涼院流水の著書『どろどろのキリスト教』のレビューで、正統派カトリックが、グノーシス派の「神解釈」を「異端」の説だとして否定するのは、所詮『目糞鼻糞の類い』だと、わかりやすく断じておいた。
ここで中野美代子が語っているのは、それとまったく同じことなのである。
『はっきり言ってしまえば、「父なる神(イェホバ)」とか「神の子イエス」とか「復活」とか「神の国」とか言っている段階で、「キリスト教」とは「宗教」という名の「現実逃避のためのフィクション」にすぎないし、そもそもが「実態のないフィクション」なのに、その中(※ それを前提として信じる者の内部)で「こちらは真実であり、あちらは間違いだ」などと言っているのは、実のない「目糞鼻糞を笑う」の類いでしかないのである。』
(9)『 本書のあちこちに書き散らしたことだが、一見いかにも荒唐無稽、でたらめだらけであるかのごとき小説『西遊記』は、じつは、世界を解釈しようというメタフィジックな欲求にとりつかれた人びとがでっちあげた、壮大なるテクストなのであった。しかし、そのテクストは、タオと錬丹術のシンボリズムと隠語(クリプトロジー)に満ち満ちた、すこぶる硬派な、そして一方、すこぶる軟派なものであるらしいのだが、本書が解読できた部分は、そのほんの一部にすぎない。
思えば、私の『西遊記』への接近は、文学アカデミズムの領域の外であって、子供と同じような好奇心から出発したといえるであろう。なぜサルが飛行するのか、しかもなぜ、ひとッ飛び十万八千里なのか一一などといった子供の素朴な疑問を積み重ねていくと、疑問そのものが、この小説のでっちあげにあずかった人びとの、世界解釈の欲求に似ている。』(P340)
『世界を解釈しようというメタフィジックな欲求にとりつかれ』るとは、どういうことか。
それは「意味のないところに、無理矢理にでも、深い意味を見出したいという欲望に、とり憑かれること」である。
例えば、墓場で「幽霊」を見た、と思った。確認してみると「枯れ尾花」であることがわかった。しかし、『世界を解釈しようというメタフィジックな欲求にとりつかれた人びと』というのは、枯れ尾花を幽霊と見間違えてしまうこと自体に「意味」を見出そうとしてしまう。
例えば「枯れ尾花は、霊的な憑代となる特性を持った植物であり、それは中国古典のこれこれにも書かれているとおりであって、決して、見間違いで済まされるような、単純な話ではない。そうではなく、人間の直観が、枯れ尾花に隠された、世界の神秘の一端を明かしていると、そう考えるべきなのだ」といった具合である。
こんな彼らには「イエスが、死後三日目に復活した、なんてあり得ない話だろう。それは神話だよ」という説明は、決して通用しない。なぜなら、そんな「無味乾燥な世界」には堪えられないと、彼らはそう感じているからである。
(10)『 それにしても、本書の末尾が「おとなしい斉天大聖」になったとは、我ながらおどろいている。前著『中国の妖怪』が、「国家のなかの妖怪」をもって「むすび」としたときも、思わぬ方向へと、しかも、必然的に筆が走っていくのにおどろいたが、孫悟空とても妖怪である以上、国家権力との関係において、規範的な存在でなければならぬ道理だ。してみれば、自分でおどろくほうがおかしいのであり、私は、いつなんどきでも、「国家のなかの孫悟空」を見すえる肝っ玉だけは、もっていなければならないであろう。』(P341)
このあたりは、中野の「反体制」体質が、分かりやすく出ている部分であろう。
『孫悟空とても妖怪である以上、国家権力との関係において、規範的な存在でなければならぬ道理だ。』とは、どういう意味かというと、要は、「妖怪」というのは、国家権力によって懐柔され利用される存在でもある、ということだ(例えば、方位を司る、青龍・朱雀・白虎・玄武の「四聖獣」なども、その一種)。
つまり、天界に登って暴れまわる、おそれを知らぬ狼藉者の孫悟空というのは、共産主義革命の時代の中国では、ヒーローとして、国家的にも持ち上げられた。ところが、国家が安定してくると、「反体制派としての孫悟空」は「おとなしい斉天大聖」になってしまう。

だから、孫悟空や『西遊記』を考える場合にも、単純に「庶民」の中のそれとしてだけではなく、「権力」によって作られるそれとして考えることをも忘れてはならない、ということだ。
(11)『 本書もまた、多くの先学のすぐれた業績なしには成稿はおぼつかなかった。わけても、わが太田辰夫先生の膨大なご業績は、一刻も早く一本にまとめ、世界中の後学が容易に参看できるようになるのを切望していたところ、本年六月、『西遊記の研究』と題して、研文出版より刊行されたのは、まことに喜ばしいことである。ただし、この『西遊記の研究』は、先生既発表の二十数篇の関係論文ことごとくを収めた論文集ではなく、主要論文を増補し整理したかたちになっている。そのことについての私見の一部は、書評というかたちで、東方書店刊『東方』十月号に執筆した。本書成稿後の刊行であるので、太田先生が『西遊記の研究』において、新たに展開された刺激的な学説を本書が吸収できなかったことは残念である。しかし、ともあれ、太田先生のご業績が、たまたま本書に先立ってまとめられたこと、だれよりもうれしく思っている。
オーストラリア国立大学名誉教授柳存仁博士のご業績も、本書でかなり利用させていただいた。一九六五年から六七年まで同大学に勤務していた私は、学部はちがったけれども柳博士のご指導を受け、また博士が主任教授であった中国学科での授業も担当させていただいた。帰国にあたって、また帰国後に頂戴したご著書は、本書で総動員したかたちであり、最近も貴重な資料を拝借するなど、渝わらぬご指導を仰いでいる。
英国の碩学、ジョセフ・ニーダム博士の気の遠くなるような大著『中国の科学と文明』もまた、本書では欠くことのできない参考文献であった。とくに、邦訳の出ていない第五巻(五分冊)は、中国錬丹術についての空前絶後の著作であり、読みはじめたらやめられないという、気のあせる執筆に没頭している身にとっては、まことに困った書物であった。
太田辰夫先生、柳存仁博士、そして、ジョセフ・ニーダム博士、この偉大なる三先学に心から畏敬と感謝の念を捧げたいと思う。』(P342〜343)
見てのとおり、「儀礼的形式」を超えた「謝辞」であることは、一目瞭然であろう。
これは、中野美代子自身が、「学問」を心から愛しているからであり、このあたりが、「文学的趣味人(ディレッタント)」であり、それゆえに、「野暮になる」からと「元ネタ」をわざと明記しなかった澁澤龍彦との、体質の違いだと言えるだろう。どちらが「正しい」という話ではなく、「趣味の違いが、表現の違いとして表れている」ということである。
○ ○ ○
さて、では最後に、先送りしていた、(7)の部分の問題を論じてみたい。
『中国人がこのような虚構の原理にきわめて冷淡であったこと、私はすでにいく度か指摘した。例としてあげたのは、ヨーロッパ人のユートピアに対する桃源境、物語における自己完結性の欠如、絵画における額縁の意味などであったが、演劇の発生が異常におそかったこともまた、有力な例としてあげることができるであろう。』
これは、どういうことを語っているのだろうか?
要は、西欧の場合は、「現実と虚構」がキッパリと切り分けられており、それぞれに「自己完結」しているのだが、中国の場合には、その両者が「メビウスの輪」のごときかたちで、不思議に連続している、ということである。
例えば、キリスト教の天国や地獄は、この世とは別のところにあって、歩いていけるような場所ではない。
ところが、中国における「桃源郷」というのは、日常生活からの延長上にある「山の中」「海の彼方」のどこかに存在している、と考えられている。「壺中天」なんてものも、日常生活の中にある壺と「別天地」が隣接している感覚を表現したものだと言えるだろう。
そして、こうした「中国的な連続性」の感覚は、日本にも流れ込んできており、それが「山中の異界」とか「竜宮城」とか「補陀落」とかいったものになっているのである。

で、私などもやはり、この「連続性」のリアリズムを持っていて、「異界」は、この現実と切れたところにあるとは「感じて」いない。だからこそ、「異界探訪」ものの小説やマンガを好むのであろう。
また、私が「トリックスター」を自称するのも、同じ感覚からだ。
「トリックスター」は「現実と虚構を往還する存在」であり、事実私は、
『「ネトウヨ」ばかりではなく「左翼」とて同じことで、多数派であることにあぐらをかいて「信念」を振り回すばかりの者が少なくなかったから、私はやがて、この論争を「小説仕立て」の「メタ・論争」形式にしていったのだ。つまり、「論争をやっている私」と「その論争を読んで、批評する私」の「二重化」を、その論争の中で行なって、要は、議論にならない相手を、ひとまとめにして揶揄いはじめたのである。』
では、このように「異界」を「身近に感じ」たがる(切り離したがらない)私が、どうして、キリスト教や仏教の語る「天国や地獄」あるいは「極楽浄土」といったものをまったく信じず、むしろきわめて批判的なのかというと、それはこれらのものが、『自己完結』的に「この世の現実」から切り離されて考えられている、からではないかと思う。
つまり、私は「この世のリアリズム」に立脚して「そんなもん、あり得ない。あるというのなら、ここで見せてくれ、触らせてくれ」という「連続性」の感覚を強く持っているからなのであろう。
言い換えれば、私にとっては「この世(現実)」と「異界」とは「連続的」なものであり、それぞれに『自己完結』して「切り離された、別々のもの」ではない、ということなのだ。
だから私は「本当にあるというのなら、ここで見せてくれ」と要求するのだが、宗教信者にとっては「それとこれとは、別次元の話」だから、そんなことは不可能だ、で済ませてしまうのである。キリスト教的に言えば、
『「神の国は、見える形では来ない。 『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ。」 』
(「ルカのよる福音書」17:21)
というような、「絶妙かつ、すり替え的」でもある話になるのであろう。
要は、それは「この世」からは「自己完結的に独立した存在」であるから「具体的(現世的)には示せない」ものだという、言い分だ。
だが、私は、こういう「それはそれ、これはこれ」という「区別」など認められない(実感を持てない)から、「示せないものが存在するなんていうのは誤魔化しであり、それは、信じるに足る具体的な根拠がない、ということだ。信じるに足る根拠があるというのなら、ここで示して見せろよ」と要求して、「それは(ここでは示せないけれども)別にある」と信じている人たちを困らせるのである。
このように考えていくと、『自己完結性』の強いキリスト教というのは、きわめて「抽象的(観念的)」なものであり、だからこそ「学問」も生まれてくれば、「演劇」も発達したのかもしれない。
「それはそれ、これはこれ」と割り切って考えられるから、それらを「現実そのもの(生活)」と切れたところで、独立的な価値として重んじられるのである。
ところが、「中国的・日本的な発想」である「連続性」においては、それらは「生活実用性」とつながっており、「純粋な抽象観念」というものに、どこか不信感を持っていると言えるのではないだろうか(この感覚は、寺山修司的と言えるかもしれない)。
「いくらご高邁な理屈を語ったところで、あなただって美女の前ではデレデレするんでしょ」みたいなリアリズムが、私たちにある。(「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」)

そしてこれは、単に中国や日本の話には止まらず、庶民とは切れた「特権階級のリアリズム」が感じられなくなった現代においては、キリスト教圏と言えども、「自己完結的な観念」に、心底リアリティを感じることが出来なくなってきており、その意味で、伝統的なキリスト教が廃れる一方、感覚的で熱狂的な「ペンテコステ派」が世界的に勢力を伸ばしている、といったことなのではないだろうか。
○ ○ ○
そんなわけで、私は、単純な「自己完結的な観念主義」を認めないし、その一方「自堕落な感覚的連続主義」も認めない。
それらは、『孫悟空』がそうであったように、時代の中で「でっちあげられていく」ものでしかなく、私たちは常に「それは、何によって生み出されたものなのか?」という問いを発し続けなければならないのではないだろうか。
そうした意味でも、「学問」とは、必ず「果てしのないもの」であり、だからこそ「楽しい」とも言えるのだから、安易な「結論」になど、貧乏くさく飛びつきうべきではないのである。
ともあれ本書は、そんな具合に、じっくりと味わうべき、「贅沢な一書」なのだと言えよう。

(2023年6月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
