
岩下壮一 『信仰の遺産』 : コップの中の 神学論争
書評:岩下壮一『信仰の遺産』(岩波文庫)
カトリック神父 岩下壮一の神学的著書『信仰の遺産』つまり本書の読者の9割がたは、たぶん熱心なカトリック信者なのだろう。残りの1割には、プロテスタント信者や非クリスチャンのキリスト教研究者や哲学研究者、そしてごくごく少数の非クリスチャン一般読者がいるだろう。私は、最後の部類に属する「暫定的無神論者」なのだが、その視点から、本書をご紹介したいと思う。
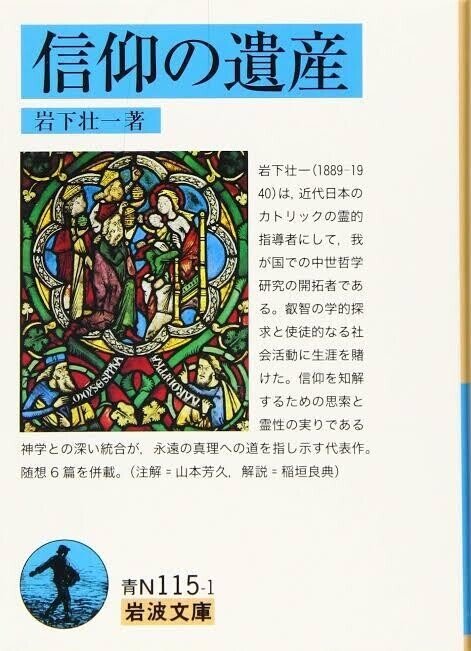
私はさる事情から「二十世紀最大の神学者」と称されることのあるプロテスタント神学者、カール・バルトに興味を持ち、ここ数年間、キリスト教入門書から入ってプロテスタント神学書を趣味的に読んできたのだが、今回初めて、「カトリック」の党派性をハッキリと打ち出している本書を読んで、キリスト教というものの輪郭が、とても鮮明になった。
本書における岩下壮一の論文は、その主眼を「プロテスタント批判」においていると言っても過言ではないだろう。
岩下は、明治22年(1889年)に生まれ、昭和15年(1940年)に51歳で没した人で、日本史的に言えば、日清・日露戦争、満州事変、日中戦争を経験し、太平洋戦争の開戦と敗戦を見ずに亡くなったことになる。つまり、日本が国際的に登り調子の時代に成長し、軍国日本への坂を転がり落ちた時代を経験したと言い換えても良い。そんな時代のクリスチャンである。
また同時に、決して忘れてならないのは、彼が、東方教会やプロテスタントとの対決姿勢を改め、「教会の一致」を目指そうという基本方針を打ち出した「第2バチカン公会議」(1962~1965年)以前のカトリック者だということだ。
さて、「神の実在」や「イエス・キリストの神人(二重)性」などの教理を額面どおり信じることが出来ない、その意味で「無神論者」である私からすると、岩下の語った「プロテスタント批判」におけるカトリックの優位性(正統性)とは、所詮は「五十歩百歩」のものでしかないし、彼のやっていることは「キリスト教界における(理論的)内ゲバ」でしかない。
というのも、岩下は、カトリック界では「信仰と理性の両立」というカトリック界の立場を誠実に追及した人ということになっており、それは「カトリック界においては」という限定付きでなら正しいと言えるかもしれないが、所詮その「理性」とやらは「神の実在」や「イエス・キリストの神人(二重)性」などの教理を鵜呑みにするという「信仰」、非クリスチャンからすれば「非理性的妄信」を大前提とするものでしかなく、その意味ではプロテスタントと「五十歩百歩」だからだ。
岩下は、ルターに始まるプロテスタントの教理を否定するにあたって、主にルターを批判しているが、岩下のルター理解の基本は「ルターの主観主義」ということである。つまり、ルターは、神は個人的な「啓示」においてのみ知り得ると言ってるが、それは所詮、近代個人主義的な主観主義でしかなく、まったく不確かなもの(救いをもたらさないもの)である、という理解である。
これに対して、プロテスタントなら「いや、ルターは『恩寵のみ』だけではなく『聖書のみ』とも言っているのだから、決して特別啓示のみだと言っているのではない」と反論するかも知れないが、岩下に言わせれば「聖書の解釈を、教会の伝統と権威に委ねず、個人の解釈に委ねてしまうプロテスタントの神理解は、所詮主観主義でしかなく、人に救いを与えない」と批判するのである。
つまり、岩下の立場は、「キリスト教原始教会」の流れを汲むと主張する「カトリック教会の権威と伝統」を「信じる(信仰する)」かぎり、プロテスタントに対して圧倒的な優位に立っている。
しかし、そもそもルターが、そしてプロテスタントが「改革」の必要性を感じたのは、「原理的に言えば堕落するはずのない正統教会が、現に堕落していたという事実(現実)」があるからであり、つまりそんな「現実」を(岩下のように)無視(あるいは、不当に軽視)するのでなければ、プロテスタントが「カトリック教会の権威と伝統」を全面的に「信じる(信仰する)」ことができず、「修正=改革」を加えようとしたのは、きわめて理にかなったことだったと言えるのである。
にもかかわらず、岩下があるいはカトリックが、プロテスタントを「カトリック教会の権威と伝統」を「信じる(信仰する)」ことが十二分に出来なかったという点を挙げつらって「異端」扱いにするのだとしたら、それは「権威主義的偽善」でしかないと言いえよう。
しかしまた、カトリックにしろプロテスタントにしろ、最後の最後は「信仰」を持ちだして「理性の限界=人間知性の分」を力説するのだったら、(岩下が「見下した態度」で語っている)バルトが「神は、人間の知性では絶対的に知り得ない」と「理性」を「信仰」から切り離した極論的「(岩下言うところの)主観主義」の方が、まだしも「筋が通っている」とも言えるのである。
つまり、プロテスタントとカトリックの両者における違いとは、前者がその根本に「信仰」を置きつつ「理性」的探求(理論構築)を重視するのに対し、後者は最初から「信仰」と「知性」のご都合主義的「二刀流」(ダブルスタンダード)を使う、という点にある。
だから前者は、方法論的には比較的一貫性があるのだが、根拠の最後の最後で「信仰」が出てくるから「不徹底」だと言われる露骨な弱味がある。一方、後者は最初から臆面もない「二刀流」を振り回すことによって「信仰と理性の両立」を実行しているなどと強弁できもしているのである。
だが、その「非理性性」において、所詮は「五十歩百歩」なのだ。
なお、本書に付された「注解」と「解説」も、当然のことながら「カトリックの党派的バイアス」が掛かっている。つまり「(多少は抑制された)身内びいきの仲人口」だと思って間違いない。
「解説」に比べると「注解」の方は、かなり抑制的ではあるものの、本書の主人公である岩下壮一の事跡を「より良く」見せようとする意識はおのずと働いているので、非クリスチャンから見れば「中道右派」的なものに留まっているとも言えよう。
ともあれ、本書で「カトリックがわかった」とか「プロテスタントがわかった」とか「キリスト教が分かった」などという、おっちょこちょいなことは考えない方が良い。
はたしてこういう言い方は、「岩下壮一的に挑発的」過ぎようか?
初出:2015年4月17日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
