
斉加尚代監督 『教育と愛国』 : 〈洗脳教育〉の成果はすでに?
映画評:斉加尚代監督『教育と愛国』
先日、公開されたばかりの、ドキュメンタリー映画『教育と愛国』を観てきた。


この映画は、もともとは、2017年にMBSでテレビ放送された『映像‘17 教育と愛国~教科書でいま何が起きているのか』であり、これが『放送直後から大きな話題を呼び、その年のギャラクシー賞テレビ部門大賞、「地方の時代」映像祭では優秀賞を受賞し』た後、『2019年に番組内容と取材ノートをまとめ書籍化(岩波書店刊)』もされた作品で、このたび、追加取材を加えて再構成し、映画作品にしたものである。

私は、書籍版『教育と愛国』のレビューを、同書刊行当時に書いているが、今回映画版を観て、テレビ版も視ていたことを思い出した。きっと、書籍版を手に取ったのも、テレビ版の印象が残っていたからであろうと思うのだが、それをすっかり失念していたのである。
なお、この映画の内容は、次のとおりである。
『 ひとりの記者が見続けた“教育現場”に迫る危機
教科書で”いま”何が起きているのか?
いま、政治と教育の距離がどんどん近くなっている。
軍国主義へと流れた戦前の反省から、戦後の教育は政治と常に一線を画してきたが、昨今この流れは大きく変わりつつある。2006年に第一次安倍政権下で教育基本法が改変され、「愛国心」条項が戦後初めて盛り込まれた。
2014年。その基準が見直されて以降、「教育改革」「教育再生」の名の下、目に見えない力を増していく教科書検定制度。政治介入ともいえる状況の中で繰り広げられる出版社と執筆者の攻防はいま現在も続く。
本作は、歴史の記述をきっかけに倒産に追い込まれた大手教科書出版社の元編集者や、保守系の政治家が薦める教科書の執筆者などへのインタビュー、新しく採用が始まった教科書を使う学校や、慰安婦問題など加害の歴史を教える教師・研究する大学教授へのバッシング、さらには日本学術会議任命拒否問題など、⼤阪・毎⽇放送(MBS)で20年以上にわたって教育現場を取材してきた斉加尚代ディレクターが、「教育と政治」の関係を見つめながら最新の教育事情を記録した。
教科書は、教育はいったい誰のものなのか……。』
(「映画「教育と愛国」公式WEBサイト」、「イントロダクション」より)
「右派政権」と呼ばれた安倍晋三(第1次)政権によって「教育基本法」が改定され、「愛国心」が明記されて以降、日本の教育が「右傾化」しているというのは、読書家ならば、もはや「常識」に類する話ではある。
けれども、そうした変化に対する危機意識は、テレビ版『教育と愛国』が放映された2017年当時ですら、「よほどの問題意識がある読書家」にしか意識されていなかったことなのだが、こうした教育を取り巻く状況の変化を、世に広く知らせたのが、このテレビ番組であったと言えるだろう。

(「保守論壇のマドンナ」と呼ばれる櫻井よしこ)
そして、今回の映画版では、テレビ版『教育と愛国』放映以降の最新状況の含め、今世紀に入って以降の、我が国における、教育をめぐる政治的状況の歴史的変遷と、その主たるエピソードを知ることができる。
したがって、「愛国教育化」の問題について、本の1冊も読んだことのない方は、ネット情報程度で漠然と「だいたい知っている」つもりに安住するのではなく、まずはこの映画を観て欲しい。
そうすれば、今よりは踏み込んだ、明確な問題意識を持つことが出来るようになるだろうし、そこからさらに問題意識を深める努力の必要性を認識することにもなろう。この問題は「どこかで誰かが、なにやらイデオロギー的に揉めている」といった、呑気な話ではない、ということである。
○ ○ ○
例えば、これは、この映画の内容とは直接関係のない話なのだが、私が昨今の若者に感じる「不安な点」として、「素直すぎる」ということがある。
言い換えれば、「疑うことを知らなさすぎる」し「批判的精神が欠如」していて、もともと日本では強かった「同調圧力」に対する「迎合(無条件降伏)傾向が強まっている」と感じられるのだ。
1962年(昭和37年)生まれの私は、いわゆる「全共闘」世代ではない。その下の世代であり、左翼学生運動が、国家権力による弾圧によっての分裂・先鋭化の果てに、「内ゲバ」などによって無残な敗北を喫して崩壊していくのを、子供心に見るともなく見ながら育った世代だ。

だからこそ、私の世代は「三無主義(無気力・無関心・無責任)」だとか「シラケ世代」などとも言われた。要は「政治的な理想を掲げて頑張ったところで、何も変わらない」という「諦め(諦観)」を、知らずに内面化して育った世代だったのであろう。
実際、私自身も、日本が最も豊かな経済状況にあった時代に育った、基本的には「ノンポリの趣味人」つまり「政治的信念を持たない、趣味に耽溺するオタク」として成長してきたと言えるだろう。
そんな私が、多少なりとも「政治」に興味を持つようになったのは、わが家がたまたま「創価学会」に入会していたからだ。
当時の創価学会は、第三代会長・池田大作(後の、創価学会インターナショナル会長)の主導する「平和主義」を、しきりに喧伝標榜していた。ところが、その長年の金看板を、のちに政権与党になったとは言え、同じ信仰で結ばれていたはずの「公明党」が「イラク戦争の支持」によって覆し、創価学会の「絶対平和主義」を素朴に信じていた多くの会員の信頼を裏切る「背信行為」に出たからである。
つまり、上の全共闘世代のように「日米安保反対」「反米反帝」といった明確な「政治問題」については、まったく知識や問題意識を持たないまま、抽象的な綺麗ごとでしかない「平和主義」をさんざん刷り込まれ、そのあげく、それを見事に裏切られたショックによって、初めて「戦争」や「政治」の問題を、そして「宗教」の問題を、具体的なものとして考えるようになったのだと言えよう。
だから、「戦争」体験も無ければ、「左翼学生運動」の体験もしていない、私の同世代の多くが、「戦争」や「平和」や「政治」や「国家」の問題について、ろくに興味を持ってはおらず、おのずと無知であるというのは、ごく自然なことであり、私の場合は、たまたま特殊な環境にあったから、否応なく、それらを向き合わさせられたのだ、とも言えるだろう。
経済的に豊かで、「戦争」や「平和」や「政治」や「国家」などという、言うなれば「天下国家」の問題になど興味は持たず、ひたすら「日々の幸せ」だけを求めていたのが、私の世代なのではないだろうか。
そして、その私たちの世代は「爺さん婆さん」の年齢になりつつある。
「子世代」は無論、すでに「孫世代」が少なくないのだが、しかし、そんな今の日本は、すでに私たちの世代が育った「GNP(国民総生産)世界第2位」とか「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代の日本と、同じではなかった。
(まだ統一されていなかった)西ドイツを抜いて、日本のGNPが世界第2位になったのは1968年であり、私の6歳時。アメリカの社会経済学者エズラ・フォーゲルの著書『ジャパン アズ ナンバーワン: アメリカへの教訓』が刊行されたのは1979年であり、私が17歳の年だ。この後も、日本経済の黄金期(1980年代の安定成長期、ハイテク景気〜バブル景気)は続いて、1991年の「(経済)バブル崩壊」時、私は29歳。一一私の世代が、どんな時代に生を受け、どんな時代に育ってきたかは一目瞭然であり、世界標準に比して、その「政治」に対する問題意識の希薄さが顕著であったのは、いわば必然的なものであり、ある意味でやむを得なかったのかもしれない。
要は、日本は豊かな国であり、天下国家のことなど政治家に任せておけばよかったのである。それで、未来には何の心配も無かったのだ。

そして、そんな私たちの世代が、子供をつくり育てた。当然、その子育ても、「日々の幸せ」だけを求めるものであって、何の不思議もない。
さらに言うと、私たちの世代は「経済発展」と同時に、「受験戦争」「学歴社会」の時代でもあったからこそ、子の世代に対しては「心の豊かさ」を与えてやりたいと考え、それが「習い事」の流行にもなったのだろうが、それはやはり「日々の幸せ=家族的な幸せ」的なものであって、「天下国家」を考えるようなものではなかった。
だが、そんな「子の世代」が生きたのは、バブル経済の崩壊期に生まれて、日本がどんどん落ち目になり、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われて高くなりきっていた鼻を決定的にへし折られて、日本人が深くプライドを傷つけられた時代だった、と言えるだろう。「日本は、世界一恵まれた、素晴らしい国」だったはずなのに、客観的・数字的には、そう主張することが出来なくなっていた。
一一そこで、必然的に求められたのは、「伝統」や「心」や「精神性(霊性)」といったものであった。
「経済では敗れたが、しかし日本の本来の美点は、むしろその優れた精神性にこそあった、それを育んだ歴史にあったのだ」と、そう考えたかった。そう考えないではいられなかった。
そう考えないでは、経済的没落による「心の傷の痛み」を耐えることができなかった。だからこそ「愛国心」が必要だった。「愛国心」という「すがりつくべき杖」が必要だった。その根拠としての「(世界に冠たる)美しき伝統」という「(非日本的人な)自己賛美的幻想」が必要だった。それに「現実逃避」しないではいられなかったのである。
○ ○ ○
だから、そうした「落ち目の日本」で育った「子世代」は、「精神性」を求めた、「心の豊かさこそが大切だ」と、半ば「負け惜しみ」的な精神主義を走らざるを得なかった。
だからこそ、「美しい国」「麗しき伝統」といったことをアピールをする「保守」政治家が力を増すことになった。第2次安倍晋三政権が8年もの長きにわたったのは、ひとつには、こうした「日本人の、深く傷ついたプライドの痛み」のゆえであったと言えるだろう。

だが、いつまでも「日本人は、本当は優秀なんだ。中国人や韓国人なんか、本来、敵などではない」などという「負け惜しみの現実逃避」に捉われているべきではない。
そうではなく、現実を直視して、叩きつけられた地べたに手をついて、立ち上がるべきであり、それだけが日本を救うのである。
しかしまた、それを妨げているのが「愛国心」教育であり、それを信じたい「子世代」と、それに育てられ、いわば洗脳教育を受けた「孫世代」の「人間的実体性を欠いた現実認識」であろう。
「子世代」は、現実的裏づけのない「自尊心(愛国心)」にしがみつき、「孫世代」は、とにかく「みんなと同じように、素直にそれを信じる」ことを強いられてきた。
つまり、「子世代」は、自ら「幻想」にしがみついたが、「孫世代」は、その「幻想」を疑うことを許されなかった世代だと言えるだろう。「孫世代」は、そうした「幻想」を強いられ、それに疑いを挟むことは、即「仲間はずれ」にされることを意味することになった。だから、みんな、似たり寄ったりの「素直な良い子」になって、「思考停止」したのである。
私たちの世代は、「三無主義」だとか「シラケ世代」などと言われたが、それでもまだ「反抗心」を持っていたように思う。
呼び名は変われど、今でも「不良」や「ヤンキー」というものは存在するのだろうが、その意味するところは変わってきているように、私には思える。
つまり、私たちの時代の「不良」や「ヤンキー」というのは、「大人」や「社会」に反発し、反抗した。「大人」や「社会」が支持する「既成の価値観」を疑い、それに素直に従おうとはしなかった。まずは「疑う」ということをし、ひとまず「反発」して、既成の価値との対決の時間を確保し、その中で自分の価値観を鍛え上げ、やがて「大人」になっていったのである。


ところが、今の「不良」や「ヤンキー」は、表立った反発や反抗ということをしない。既成の価値観と対決しようとはしない。
そうではなく、それを頭から信じ込んでいるか、あるいは、頭から信じてはおらず、内心で嘲笑しながらも、うわべだけは調子を合わせるといった、裏表を使い分ける世渡りを「賢明」だと考える。
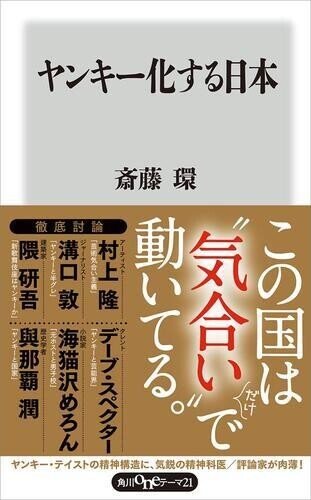

昔の「不良」や「ヤンキー」は「自分たちの方が正しい」と考え、そう主張したが、今の「不良」や「ヤンキー」は、そもそも「正しさ」など信じておらず、それに価値を見い出さなくなってしまったのではないか。
それらを、所詮は「奇麗ごと」でしかないと考えて、「正邪善悪」ではなく、「損得」を考えることこそが「利口で正しい」生き方だと、そう考えるようになったのではないだろうか。

では、どうしてそんなことになってしまったのかと言えば、その一端は、たしかに「愛国心」教育にあったはずだ。
なぜなら「愛国心」教育とは、実際のところ「現実的根拠」があってなされたものではなく、「損得打算」によって方法的に採用された「タテマエ的幻想」主義教育に過ぎないからであり、それを子供たちは、肌で感じて育ってきたからである。
「日本が特別に素晴らしい国、なのではない。そうではなくて、日本は素晴らしい国だ主張することが重要なのだ。そうしないと、外国から舐められて、損をする」という、「愛国心」教育の「本音」を、子供たちは素直に内面化していったのではないだろうか。
実際「美しい国」「麗しい日本の伝統」などと声高に語っていた安倍晋三首相が、裏でやっていたのは、「森友学園・加計学園」問題や「桜を見る会」問題などに象徴される「お友達政治」であり、要は、自分と自分の仲間への「利益誘導」でしかなかった。



タテマエの過剰な「奇麗ごと」に反して、実質は「損得打算」でしかなかったから、子供たちは、今の「愛国心」教育に、「善悪美醜の価値観」ではなく、「損得打算」を学んだのではないだろうか。だからこそ、それを追認するにしろ、同調できないにしろ、結局は「表立って反抗しない、賢く素直な子供(匿名でなら、何をするかわからない子供)」に育ってしまったのではないだろうか。
○ ○ ○
そうしたことからか、彼らは「無個性」である。私たちの世代のように『個性、オンリーワン、創造性、破天荒、異端児、独創性、型破り、反逆児、前衛的、奇抜、エキセントリック』であることなど求めず、おおむね次のように考えるようになったのではないか。
『 研究室の帰り道、チャンは、「普通」について考えた。そして、あらゆる美徳の中で、「普通」がもっとも過小評価されているのではないかと思った。個性、オンリーワン、創造性、破天荒、異端児、独創性、型破り、反逆児、前衛的、奇抜、エキセントリック。それらはたしかに重要な美徳かもしれないが、「普通」はそれよりもっと重要だ。
「普通」とは、ルールを守ることだ。そして人々はルールを守らなければ生きていけない。カンボジアにはルールを守らない人間が数多くいて、かくいう自分自身もルールを破ることがあるが、大事なのはほとんどの場合、ルールを遵守しているという事実だ。
「普通」でなくなるのは簡単だ。道端で「殺してやる!」と突然大声を出せばいい。映画のチケットを買う列に割りこめばいい。挨拶を無視して屁をこきながら睨み返せばいい。露店で買い物をしたあと、支払いの紙幣を相手に投げつければいい。裏返しにした服を着て、そのことを指摘されたら相手を引っ叩けば良い。』
(小川哲『ゲームの王国』文庫版下巻P234)
つまり、無駄に反発反抗したりすることのない「素直でおとなしい優等生」であることこそが素晴らしいし、「社会もそれを認めてくれる」と考えるようになったのではないだろうか。
しかし、こうした「社会従属的な発想」というものの根底には、たぶん「未来への絶望」に由来する「諦観」がある。
『ああ、この先の「人生」は下り坂なのかもしれない。そんな不安がよぎった。これからの「人生」は、一度つかんでおきながら結局は捨ててしまった九十一のことを思いながら、それでも五十四を受け入れて生きていくべきなのかもしれない。』(同上P270)

「経済的豊かさになんか満足できるものか、私は、心の豊かさこそを求める」などと言って、どんどんカードを切っているうちに、いつの間にか、「経済的な豊かさ」も「心の豊かさ」も失って、「その他大勢」と書かれた最後のカードだけを手に、「下り坂」を転がり落ちていくだけの自分に、ハタと気づいてしまったのではないだろうか。
そして「ならば、もう無駄な抵抗はやめて、このまま転がり続けよう。みんなもそうしているのだから」…。
○ ○ ○
私は、今の子供たちの「素直さ」や「おとなしさ」に、危険な兆候を見てしまう。
これはもう、種族の滅亡を前にした者の、ある種の静謐さなのではないか。片足を「あの世」に突っ込んだ人間の「諦めの境地」に近いものなのではないか?
だから、私は「疑え!」「怒れ!」「声を上げろ!」「反抗せよ!」ということを、身をもって示して見せている。
「そんなに我慢しても、幸せになれるわけではないんだ。ならばせめて、窮屈な保身を脱して、自由を果実を味わってから死んでもいいのではないか」と、そう反時代的に訴え続けている。
これはきっと、私なりの「人間教育」なのである。
(2022年5月24日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
