
ドン・シーゲル監督 『ダーティハリー』 : さそり座の評論家・北村紗衣
映画評:ドン・シーゲル監督『ダーティハリー』(1972年・アメリカ映画)
ひさしぶりに『ダーティハリー』(シリーズ第1作)を見た。たぶん子供の頃にテレビ見て以来だと思う。
私は1962年生まれなので、本作が公開されたのは10歳の時。
その頃に映画館で見ていたのは「東映まんがまつり」で『長靴をはいた猫』(1969年)などのアニメを見たとか、「ゴジラ」シリーズの第11〜13作(1971年〜1973年)にあたる『ゴジラ対ヘドラ』『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』『ゴジラ対メガロ』などの怪獣映画だろうか。無論、旧「ガメラ」シリーズも見たと思う。一一そんなわけで、「洋画」というのは基本的に、テレビで見るものだったのである。
『ダーティハリー』の公開が1972年となると、当時のことだからテレビに落ちるのは、おおむね3年後くらいで、1975年前後、私が小学校の低学年頃だから、その頃には十分に楽しんだろうし、「見た」という記憶が残っていたとしても不思議ではない。
それでもたぶん、シリーズの続編とごっちゃになったり、『ダーティハリー』と同じくクリント・イーストウッドが主演する刑事ものの『ガントレント』(1977年・監督もイーストウッド)なんかの「バスを撃ちまくりシーン」の印象なんかとも一体化しつつ、「マグナムを撃つ刑事」という「絵」が、ハッキリと思い出せる。情報の重ね塗りによって、多少変形されながらも記憶が強化されたということなのであろう。

さて、今回、ひさしぶりに『ダーティーハリー』を見ることにしたのは、無論「ポンコツ映画評論家の北村紗衣」が、メチャクチャな『ダーティーハリー』評をやっていて、それだけなら相手にもしなかったのだが、私が、他の人の「note」記事に書き込んだ、「頭が悪い」という率直な感想にでも反応したのか、いきなり同じコメント欄に、その記事とコメントに対する「管理者通報した旨の報告」を書き込んできた。
このあたり事情は、次の記事にも書いているので、ここで繰り返すのは止して、興味のある方には、そちら(下)を読んでもらうことにしよう。
そんなわけで、本稿ではもっぱら、「北村紗衣の『ダーティーハリー』評」などとは比べ物にならない、私の「真っ当な『ダーティハリー』評」を披露させていただくととも共に、私のそれとの比較で、「北村紗衣の『ダーティーハリー』評」がいかに「メチャクチャ」であり、北村紗衣がいかに「ポンコツ」評論家かということを、懇切丁寧に切り刻み、噛み砕いて論証していこう。
だが、べつに食べると言っているのではないから、安心して欲しい。食べたらお腹をこわすだろうし。
○ ○ ○
問題の「北村紗衣の『ダーティーハリー』評」とは、「太田出版のwebマガジン OHTA BOOK STAND」での、北村紗衣の連載「あなたの感想って最高ですよね! 遊びながらやる映画批評」の第3回「メチャクチャな犯人とダメダメな刑事のポンコツ頂上対決? 『ダーティハリー』を初めて見た」のことである。
映画を見る目のない北村紗衣が、いつもの如くせいぜいツッパって「メチャクチャな犯人とダメダメな刑事のポンコツ頂上対決?」なんてことを言っているのは、まあどうでもかまわない。
自分に「見る目が無い」のを、作品のせいにするような輩など、いくらでもいるからだ。
しかし、それにしたって、連載タイトルである「あなたの感想って最高ですよね! 遊びながらやる映画批評」というのは、あまりにも酷い。
「あなたの感想って最高ですよね!」というのは、いちおう表面的には「広く世間一般の人々に、媚を売っている」ということなのだろうが、このタイトル、実は「ダブル・ミーニング」なのだ。つまり「二重の意味」が込められている。
ちなみに、この「ダブル・ミーニング」というのは、「ミステリ小説業界」でよく使われる言葉であり、要は「言葉に二重の意味を持たせる」こと。
そうすることで、作中の「犯人」が「名探偵」や「警察」を、あるいは「ミステリ作家」がその「読者」を、「欺いたり」「揶揄ったり」するのである。
つまり、これは「レトリックによる、騙しのテクニック」なのである。
では、「あなたの感想って最高ですよね!」という言葉には、「広く世間一般の人々への媚売り」以外に、どんな意味が込められているのか。
それは無論、「私の感想って最高ですよね!」という「自賛」である。
ここでの『あなた』とは、この映画感想記事の読者から見た場合の著書である『あなた』、つまり北村紗衣当人のことでもあるわけなのだ。
「視点」を逆転させることで、「主語」が指す対象を逆転させているのである。
なんで、北村紗衣が、こんな「ダブル・ミーニング」による「自賛」なんていう、つまらないことをやっていると言えるのかといえば、それは、ひとつには、今回取り上げる「第3回」でも当人が語っているとおり、北村紗衣自身が「ミステリマニア」気取りでいるだからだ。そのため、こうした「自賛に見せない自賛」「自慢話に見せない自慢話」を駆使して、ひとり内心で「悦に入っている」のである。
そしてもはやこれは、北村紗衣の「性癖」的な常習行動でもあるのだ。
このことについては、北村紗衣の2著『お砂糖とスパイスと爆発的な何か 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門』と『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード ジェンダー・フェミニズム批評入門』のレビューに詳しく説明しているので、是非ともそちらをご参照いただきたい。
この2つのレビューを読めば、その人は「北村紗衣は、どうしようもないポンコツ評論家」だということを、事実に即してハッキリと理解できるから、以降、北村紗衣の「ひけらかしだけの稚拙な文章」を無駄に読んだり、世評に流されて「うっかり北村紗衣を褒めて、あとで赤っ恥をかく」ようなことにもならないはずからである。
「特殊詐欺などに対する防犯上の心得」として警察もよく言うとおり、「手口を知っていれば、騙される確率もグッと下がる」のだ。
逆に「私は騙されない」などと自己過信している「無知な人」こそが騙される。一一だがら、北村紗衣の「騙しのテクニック」を知っておくべきだし、知っておいて損はないのである。
○ ○ ○
さて、私の『ダーティハリー』の評価だが、結論を先に言ってしまえば、本作は間違いなく「傑作」である。そう、私も保証しよう。
したがって、北村紗衣がこの作品の「面白さ」を理解できなかったのは、北村が「当たり前のセンスすら欠いていた」からに他ならない。
件のインタビュー記事で語られているのは、所詮、自分の「無能力」を正当化するために、つまらない知識をあれこれ総動員して、駄弁を連ねているに過ぎないのだ。
だから、北村紗衣が本作『ダーティハリー』を否定的に評価したからといって、なにも気にすることはない。
所詮は、日本の「無能な三流映画評論家」でしかない「タレント教授」が、その「にわか人気」に乗って、「調子こいている」だけなのだ。
ご当人は「私は、大学で映画を講じてもおり、映画研究の王道を行っているのだから、私の言うことは間違いない」ということをおっしゃるのだが、当然のことながら「大学教授」にもピンからキリまでいて、その大半は「クズ=凡庸」なのである。
ここでお馴染みの言葉を引用しておくと、次のようなことなのだ。
『SFの9割はクズである。ただし、あらゆるものより9割もクズである。』
(シオドア・スタージョン)
たしかに、基本的な知識を年若い学生に説くくらいのことなら、本を読んで知識さえ蓄えていれば可能であり、特に才能など必要はないが、優れた(面白い)「批評」というのは、センス(鑑賞眼、洞察力)が無くては、できないことなのだ。
基本的な知識を持たない者に基本的な知識を説くだけ、簡単な質問に答えるだけなら、機械にだって出来ることで、インスピレーションをうむ批評的な才能など無くても可能なことでしかないのである。
○ ○ ○
まずは、『ダーティーハリー』の「あらすじ」を紹介しておこう。
『サンフランシスコのとあるホテル屋上のプールで泳いでいた女性が、何者かによって射殺される。捜査にあたるのは「ダーティハリー」ことサンフランシスコ市警察本部捜査課のハリー・キャラハン刑事。狙撃地点に残されたメモで犯人はスコルピオと名乗り、市警察に10万ドルを要求。応じなければ、次はカトリックの司祭か黒人を殺すという。市警察は支払いを拒み、次の犯行を防ぐために市内の高層ビルに多数の警察官を配置する。警戒中のヘリコプターが不審人物を発見するが、犯人を逃がしてしまう。
犯人は10歳の黒人少年を殺害したあと、さらに少女を誘拐し身代金を要求する。市は10万ドルの支払を決意、金の引渡しをハリーは命ぜられ、相棒のチコ・ゴンザレスが車で後をつけることとなる。犯人は銃を捨てたハリーを殴打し殺そうとするが、そこへチコが駆けつけて銃撃戦となる。チコは負傷するが、ハリーが隠し持っていたナイフを腿に突き立て、スコルピオは足を引きずりつつ逃走する。
犯人が傷の手当を受けた夜間病院の医師の話から、ハリーはスコルピオの居所を突き止めて追いつめ、刺し傷と銃創の上を踏みつけて少女の居場所を吐かせたが、少女は既に死んでいた。さらに、ミランダ警告を無視した逮捕と自白強要が違法とされ、そのほか決定的証拠もなく結局犯人は放免される。地方検事局のオフィスで「加害者にも人権はあるのだ」と諭されるハリーだが、「被害者の人権は誰が守るのか?」と、逆に怒りを露わにする。こうした中、スコルピオはさらに黒人の無免許医に金を渡して自分を殴らせ、それをハリーの仕業だと警察に届け出たことから、ハリーは市長と上司のブレスラーによって、謹慎処分を受ける。
スコルピオは病院を退院すると酒屋で拳銃を強奪し、生徒たちが乗ったスクールバスをバスジャックする。橋の上からバスの屋根に飛び乗ったハリーに対して、スコルピオはバスを捨て採石場に逃げ込み銃撃戦となる。採石場を出て近くの池で釣りをしていた少年を人質に取ったスコルピオだったが、ハリーの撃った弾丸は少年をかすめて肩に命中。拳銃を落とし、ハリーはいよいよスコルピオを追い詰める。
スコルピオは落とした拳銃に一度手を伸ばすも躊躇する。それに対し挑発するハリー。結局、スコルピオは拳銃を取りハリーを狙うも、一瞬早く銃口を向けたハリーに胴体を撃ち抜かれ絶命、死体は池に落ちる。しかし警察の人間としての誇りを失ったハリーはポケットから警察バッジを取り出すと、池に放り投げるのだった。』
(Wikipedia「ダーティハリー」)
スコルピオによる最初の「屋上プール狙撃殺人事件」が発生した後、その捜査にあたっていた、本編の主人公、ダーティハリーことハリー・キャラハン刑事(以下「ハリー」と表記)が、スコルピオの事件とは無関係な「銀行強盗」にたまたま行き当たって、これを「解決」するシーンが描かれる。


これは、ハリーがどんな人物なのかを、観客にわかりやすく紹介するためのシーンであり、当然、このシーンを見れば、普通の人なら、主人公ハリーが「非現実的なスーパーヒーロー」であることなど、すぐに理解できるはずだ。
ハリーは、強盗を終えて銀行から出てきた、銃器で武装した複数の銀行強盗に対して、身を隠すこともせず真っ直ぐに近寄っていき、逃げようとする強盗犯の車を、その拳銃「44マグナム」で撃って横転させ、徒歩で逃げようと銃を向けてくる犯人には、肩や脚を撃つなどして逃走不能にしてしまう。そして、応援が駆けつける前に、あっさりと犯人たちを全員「捕まえてしまう」のである。
そんなわけなので、普通に考えれば、本作が「ヒーローもの」の「ファンタジー」であることなど、誰にでもわかるはずなのだ。そのように作られているのである。
銃器で武装した複数の銀行強盗犯に対して、身も隠さずに近づいていくような、バカな警官など「実在しない」。
いたら、その警官は「頭がおかしい」のであり、ケガをする前に病院送り間違いなしだ。そんな危なっかしい部下を、現場に出す上司などいないのだ。なぜなら、すぐに殉職すること間違いなしだからである。
そんな馬鹿に、不必要に殉職などされたら、その上司の管理責任が問われて昇進にだってかかわるし、殉職などの重大事案は、上への報告も大変で、針の筵に座らされること間違いなしだからである。
それに、銃というものは、ああ簡単に当たるものではないというのも、常識で考えればわかることで、ハリーの射撃が、ここぞという時には「百発百中」なのは、もちろん彼が「フィクションの中のヒーロー」だからに他ならない。彼の撃った弾が当たらない場合というのは、そこで当たってしまったら「物語にならない場合」だけなのだ。
また同様に、「フィクションの中のヒーロー」だからこそ、ハリーは、弾にあたってはならない時には絶対に当たらないし、当たっても死ぬことはない。それでは、そこで「物語」が終わってしまうからだ。
つまり、本作で描かれているハリーという主人公は、まさに「絵空事」であり、その意味での「スーパーヒーロー」なのだが、それは無論「作り手=監督をはじめとした制作スタッフ」は無論、「観客」とて、そうとわかった上での「作劇上のお約束」なのである。
だから、「なんで身を隠さないんだよ」とか「なんで百発百中なんだよ」と評するにしても、それは「本気」で言うのではなく、あくまでも、それが「お約束」であることを承知した上での、「冗談としてのツッコミ」に過ぎない。
そんなツッコミを「本気」でするのは、「頭がおかしい」のか、よっぽどの「馬鹿」でしかないのである。
そもそも、サンフランシスコ警察のいち刑事でしかないハリーが、どうして自分だけ「44マグナム」なんて、無駄に物騒なしろものを常時携帯していられるのかといえば、それは無論「フィクション」だからである。
主人公の刑事が、当たり前に貸与された「38口径の拳銃」で、犯人とパンパン撃ち合っても、際立った「絵」にはならない。それがいくら「リアル」だとは言っても、「娯楽作品」というのは、「面白さ」のために「リアル」を追求することはあっても、「リアルのためのリアル」を追求したりはしないのだ。
そんな無意味なこだわりは、「創作」というものの本質を理解しない、「オタク」の偏狭なこだわりでしかないのである。

そんなわけでハリーは、なぜか一人だけ「44マグナム」を使っているし、それが上司に咎められることもない。なぜなら、そんな理由は「娯楽映画」においては、まったく重要ではないからで、「刑事は、44マグナムなんか使わない」という「リアルさ」よりも、「かっこいい刑事が、デカいマグナムで撃つ」という「絵」の方が重要なのである。
したがって、そんなことについて「なんで?」などと、そんな「的外れ」なことを考えたり尋ねたりする者は、「フィクション」というものを、本質的に「理解できない人」なのである。
さて、ここまでの議論のポイントは、「娯楽映画(娯楽フィクション)」というのは、「リアル」であることよりも、作中での「らしさ(別様のリアル)」が重視されている、という「創作上の常識」である。
そして、映画などの「創作(フィクション)」における「リアルさ」とは、作品を「より面白くするため=観客を白けさせないため」に追求されることはあっても、「リアルであること」そのものが目的ではない。
「リアルな刑事」や「リアルな警察活動」を見たければ「映画なんか見に来るな。近所の警察署へでも行け」(声・山田康雄)という話なのである。
さて、こうした「常識」を踏まえた上で、ハリーを見るならば、ハリーは典型的な「フィクションのスーパーヒーロー」だというのがわかるだろう。
無論「スーパーヒーロー」と言っても、「摩天楼よりも高く飛ぶ」わけでもなければ「列車よりも早い」わけではない。けれど、なにしろ、銃弾に当たることは滅多になく、当たっても大した怪我ではなく、重症であっても、すぐに回復するのだから、「生身のリアルな人間」ではないことだけは確かなのだ。
それは、本作の犯人スコルピオだって同じで、太ももをナイフで深々と刺されて、大量の出血をしているというのに、痛がったりビッコを引いたりはしながらも、常人以上に元気に逃げ回る。
さらには、ハリーに濡れ衣を着せるために、裏稼業の人間に金を払い、わざと自分に暴行を加えさせて大怪我を負いながら、それもすぐに回復するし、後遺症も無い。たしかに傷跡が残っていたり、包帯を巻いていたりはするのだが、その痛みに苦しんでいる様子は、まったく無い。
その意味で、この犯人も、まったく「リアルではない」のだが、そのことで腹を立てるような観客は、普通はいない。

ハリーにナイフで太ももを刺されて、そのまま出血多量で死んだら、映画にならない。わざとケガをすることでハリーを嵌めても、そのケガのせいで「半年入院しました」とか「後遺症で歩けなくなりました」ということでは、映画にはならないから、現実的に考えれば「不自然」に元気であったり、回復が早かったりしても、「観客」の方だって、そこはそれで「お約束のうち」だと了解して、あえて「なぜ」などと、間抜けなことを問うたりはしないのである。それが「映画内宇宙の空気」なのだ。
だからこれは、他のキャラクターだって同じで、なぜ「検事」は、あそこまで「弱腰」なのか。あるいは、法律の手前弱腰だったとしても、どうしてハリーに対して、一抹の共感も示さないのか。どうして「君の気持ちはわかるよ。でも、君はやり過ぎたんだよ」というくらいのことを言わないのかといえば、それは「検事」もまた「憎まれ役」の「引き立て役」だからであって、「検事のリアル」がああいうものだから、というわけではないのである。
そもそも、一介の刑事が、ジャックされたスクールバスの上に、高架の上から飛び移るとか、そんなこと「リアルではあり得ない」というのは、誰にでもわかることで、そこで怒りだす客のほうが「頭がおかしい」のだ。
その客は、みんなが当たり前に受け入れることのできる「お約束」を理解する能力が無いから、本気で怒りだすのである。

こうした「フィクションゆえの嘘」を挙げていけばキリがないので、これくらいにしておくが、要は、本作は「娯楽アクションのフィクション」であり、普通の人は、その「お約束」を自然に受け入れて、「作品」を楽しむことが出来る。
それこそが「正常な人間」の理解力なのだが、ごく稀に、そうした「理解力が欠落している」ために、「どうしたあんなに、彼の撃った弾は当たるの? 全然リアルじゃないじゃない」などと真顔で言う人がいて、さらには、そんな自身の「ズレた感覚」を正当化するために、現実の「警察官の射撃における命中率」なんて数字を引っ張ってきて、「だから、私の意見の方が正しい」などと、したり顔でやるのだから、「頭のおかしい」人は、それこそ素人の手には負えない。
したがって、そういう人に対しては、
「ほうほう、そうですか。さすがは武蔵大学の教授だけはありますね。一般人とは、着眼点も違えば、知識量も違います」
などと、適当に煽てておけば良いのである。
そんな馬鹿をつかまえて、まともに「あんたは、これこれという理由から馬鹿だ」などと立証したところで、「馬鹿」が納得するはずもなく、「興奮して暴れだす」のが関の山なのである。
なのに、それをやってしまったのが、映画マニアのブロガー須藤にわか氏の「note」記事、
・「北村紗衣というインフルエンサーの人がアメリカン・ニューシネマについてメチャクチャなことを書いていたのでそのウソを暴くためのニューシネマとはなんじゃろな解説記事」

だったのである。
その結果、凶暴化した「さそり座の女」から、「メチャクチャ」な攻撃を受け、当初は「話し合い」による説得を試みたが、当然のことながら、まともな話し合いになどならず、まともな須藤氏の方が、折れざるを得なかったのである。
で、その結果として、上の記事は、現在アップされている、
・シェイクスピア研究者の北村紗衣さんがアメリカン・ニューシネマについて俺の個人的なニューシネマ観とはかなり違うことを書いていたのでそれを説明しつつニューシネマのいろんな映画を紹介する記事〔改訂版〕
に差し替えられることになった。
見てのとおり、
・「北村紗衣というインフルエンサーの人」→「シェイクスピア研究者の北村紗衣さん」
・「アメリカン・ニューシネマについてメチャクチャなことを書いていたのでそのウソを暴くためのニューシネマとはなんじゃろな解説記事」→「アメリカン・ニューシネマについて俺の個人的なニューシネマ観とはかなり違うことを書いていたのでそれを説明しつつニューシネマのいろんな映画を紹介する記事」
へと、いかにも興奮した馬を「どうどう」となだめるが如き、痛ましい「表現の変更(自粛)」を強いられてしまったのだ。
要は、「頭のおかしい人」を「頭に障害のある人」と言い換えたようなものである。
須藤氏としては「政治的に正しい表現」にしたというよりも、「私はインフルエンサーではありません。シェイクスピアの研究家です」という北村紗衣の「自己申告」を、そのまま受け入れてあげたのである。
要は「これで勘弁してよ」ということだったのだ。
だが、こうした「一方的な妥協」だけでは、さすがに気が済まないというのが人情で、その後、須藤氏は、自身の正当性を説明する「追記」をなさっているので、興味のある方はぜひ読んであげていただきたいと思う。
閑話休題。
そんなわけで、本作『ダーティハリー』の本質は、「娯楽アクション映画」であり、言うなれば「男のファンタジー」である。
こんな男は「現実(リアル)」にはいないのだが、普通の客は、それを承知の上で、自分がなりたくてもなれない、カッコいい男ハリーの「超人的な活躍」を、ハリーに感情移入することで楽しむのだ。
ハリーが警察官の身分を捨ててでも「狂気の犯罪者」を抹殺する自己犠牲的な姿に、自分ではとうてい真似できないなりに「共感する」のである。

無論、現実にこんな刑事がいたら、危なっかしくてしょうがないし、何より、その「独善」と「心得違い」が批判され、それこそが、正されなけれならないだろう。
一一だが、所詮本作は「フィクション」であり、ハリーは実在していないのだから、「現実の基準」で、彼を裁いても意味はない。
例えば、スーパーマンに対して「航空法を遵守しなさい」などと、一一冗談で言うのは良いのだけれど、本気で言うのなら、それはその人の「頭がおかしい」のだ。
いや「頭が不自由すぎる」のだ。「頭が機能不全」状態なのである。
しかしながら、本作『ダーティハリー』が「傑作」となっているのは、単に「超人的なヒーローが活躍するから」ではない。
「超人的なヒーロー」が、その「超人的な力」によって、自分よりもずっと劣る「悪党」をやっつけたところで、そんな「出来て当然のこと」をやるだけでは、面白くもおかしくもない。
だから、こうした「ヒーロー物」の「定石」として、「ヒーローが、その能力を十全に発揮できない状況」が設定される。
「すごい力を持っている」のに、それを発揮できない状況がしばらく続くからこそ、その状況を乗り越えたヒーローが、最後にその「本領を発揮した活躍」を見せた時に、観客は「スッキリする快感」を覚えるのだ。つまり「カタルシスを得る」のである。
言うまでもないことだが、「娯楽映画」を見に来る観客たちは、イライラさせられるために来るのではなく、「最後は、スッキリとさせられる」ことを期待して来るのである。
つまり、本作において、「スコルピオ」がことさらに「憎たらしい」のは、その方が、ハリーが彼を倒した際の「カタルシス」が大きいからだ。
スコルピオが「自身の身の安全をほとんど考えていないような、無謀な連続犯行を犯す」のも、それは、犯人が「小心かつ無難に、地味な犯行しか犯さない」ようなやつだったなら、スカッとする「アクション映画」にはならないから、なのだ。
刑事も犯人も、かなり「常人離れ」した人間だからこそ、彼らの対決は「普通では見られない、派手な見せ物」にもなり得るのである。
そんなわけで、本作『ダーティハリー』が「傑作」だと言われるのは、「娯楽アクション映画」として「定石」を踏まえつつ、「新しい(一匹狼の)刑事像」を確立した、「よく出来た作品」作品だったからである。
言い換えれば、「現実の刑事」や「現実の警察」をそのまま描いたわけではないだけではなく、「現実の殺人鬼」をそのまま描いたわけでもなければ、「現実の検事」や「現実の市長」をそのまま描いたわけでもない。
それらはすべて、観客たちが最終的に受け取るべき「カタルシス」のために、わざと「誇張」して表現されたものなのだ。
そして、そうした「娯楽作品における誇張表現」としての「演出」が成功していたからこそ、本作は「娯楽映画」としての「傑作」になったのである。
一一ただし、こうした「演出」は、「普通の感受性」を持った人向けに調整されたものであって、すべての人に適合するわけではない。
極端に言えば、犬や猫が本作を見ても、ましてや「チョウ」や「ハチ」が『ダーティハリー』を見ても、決して「面白い」とは思わないのだ。
そう感受する「感覚器」なり「脳部位」なりが無いのなら、それはわからなくて当然なのである。その意味では、『ダーティハリー』という作品は、と言うか、「すべての映画」は、すべての存在に対して平等に「わかる」ようには、出来ていないのだ。そんな作品など「あり得ない」のである。きわめて遺憾なことなのではあるが、仕方がないのである。
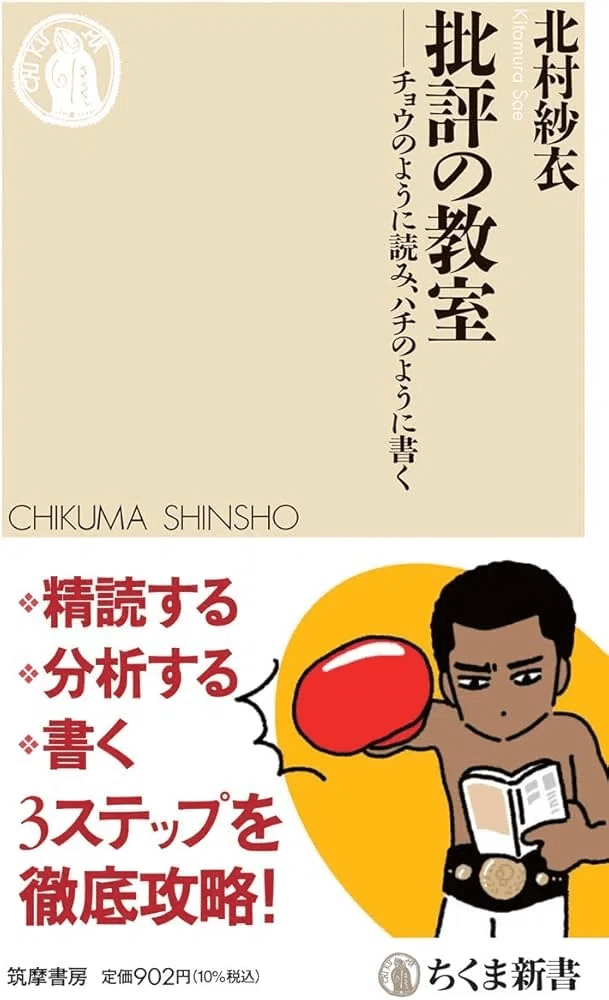
了然和尚なら、きっとつぶやくはずだ。「きちがいじゃが、仕方がない」と、似たようなことを。
○ ○ ○
さて、ここからは、「インタビュー」への応答として語られた、北村紗衣の『ダーティハリー』論について、北村紗衣の言葉を「逐語的に引用」しつつ、これに論評を加えていきたい。
ここで、北村紗衣の言葉を、ほぼ全部、そのまま引用するのは、「著作権の侵害」が目的ではなく、北村紗衣の言葉を論評するのに、恣意的な「要約」や「切り取り」をしたくないからである。
「私はそんなこと、言ってません」などと思わせたり言わせたりするような、無用の不愉快を、誰よりも北村紗衣に与えたくないからである。

そしてさらに言えば、本稿の読者が、いちいち北村紗衣の元記事を参照するの労を省くためでもある。
また、そうすることにより、本稿の読者が
、「元記事」確認の労を避けて、本稿だけを読んで判断するというような、私にとっても北村紗衣にとっても「好ましくからざる事態」を避けるためだ。
そのためには、北村紗衣が発言を「そのまま引用」しておけば、それに越したことはないのである。
それでも、北村紗衣が、「著作権侵害」だとかいったケチなことを言ってきた場合は、やむを得ず「要約」に切り替えることにするが、その場合には、後で「私は、そんなこと言っていない」などとは言わないようにしていただきたいものである。
一一まあ、言うのは勝手だが、そんなことをすれば、世間の物笑いの種が、またひとつ増えるだけだというくらいのことは、誰よりもご自身のために弁えてもらえればと思う。これ以上、わざわざ自分から恥を晒して、自分の立場を悪くする必要などないのである。
○ ○ ○
さて、前述のとおり、原文は、インタビューをテキスト化したもので、インタビュアーの言葉もふくまれているが、こちらは、文頭に「一一」という棒線が付され、区別されている。
そこで、ここでもそれに準拠して、それをそのまま引用しておく。文頭に「一一」のないのが、北村紗衣の言葉だということだ。
なお、引用文は『』(二重鉤括弧)で括り、文頭には「整理番号」を振っておいた。無論これは、原文には無いものである。
では、検討を始めよう。
(01)『音から気づけることがある
――初めて見た『ダーティハリー』はいかがでしたか?
すんごく面白くなかったです! 理由はいろいろあるので、あとでお話するとして、文句なくよかったのは音楽でした。
担当しているラロ・シフリンは有名な作曲家で、ジャズ系の、少し変わったリズムを使うところに特徴があります。『燃えよドラゴン』(1973年)や、映画にもなったドラマ『スパイ大作戦』(1966年)のテーマ曲なども作っているんですけど、『スパイ大作戦』のテーマ曲なんて5拍子ですからね。珍しい拍子です。
不穏な出来事が始まる少し前から緊張感が高まるような音楽が流れ出すシーンが序盤にありました。映像をただ普通に編集しても、それほど緊張感は高まらなかったと思うので、すごく上手だと思いました。シフリンは70年代前後のスリリングな映画やドラマに曲を提供していて、おそらくそういった曲が得意だったんでしょうね。
アカデミー作曲賞を受賞していてもおかしくないと思うくらい『ダーティハリー』は曲がよくできていたので調べてみたら、シフリンは一度も作曲賞を取っていないんですね。名誉賞は年をとってから受賞しているようなんですが。
アカデミー作曲賞ってどこを評価しているのかがよくわからないところがありませんか? エンニオ・モリコーネという有名な作曲家もアカデミー作曲賞をなかなか取れなくて。60年代から映画音楽を作っている人なんですが、高齢になった2007年に名誉賞を取って、2016年にクエンティン・タランティーノの『ヘイトフル・エイト』(2015年)でようやく作曲賞を取っていました。
――音といえば、『ダーティハリー』で使われている銃声はのちに『ターミネーター』(1984年)でも使われていることで有名ですよね。
そうなんですね。他の映画に別の映画の音が使われることって結構ありますよね。おそらくハリウッドのスタジオが効果音をいろいろと録り溜めて再利用しているんじゃないですかね。』
『アカデミー作曲賞ってどこを評価しているのかがよくわからないところがありませんか?』とのことだが、それはたいがいの賞がそうで、例えば北村紗衣自身が受賞している「表象文化論学会賞」とか「女性史学賞」とかも、人に言わせればそうなるだろう。
蓮實重彦は、アカデミー賞だけではなく、ほぼすべての映画賞がそんなものでしかないと語っていたが、この意見は私もまったく同感である。およそすべて賞には、業界政治的な「裏がある」のだ。
ともあれ、北村紗衣先生は「音楽」には詳しいようで、そこだけでも楽しめたのは、せめてもの救いであったのだろう。幸いなことである。
(02)『ポンコツな犯人のサスペンス
――ではそろそろ『ダーティハリー』のつまらなかったところを教えてください。
ええっと、まず私は警察のことを信用していないんですよ。というのも、おじいちゃんが治安維持法で逮捕されていますし、子どものころから親に「警察を見たら逃げなさい」としつけられてきたんですよ。私の家が警察を嫌いだったんです。別に誰も犯罪を犯しているわけじゃないんですけど。
私の出身地である北海道の人って、警察に対する不信感がたいへん強くて。2003年に発覚した北海道警の裏金事件が有名ですけど、90年代くらいから現在まで北海道の警察って不祥事続きなんです。』
北村紗衣先生の「警察嫌い」は有名である。ご当人が、そう語っているからそうなのだろうが、詳しいことはよくわからない。
『2003年に発覚した北海道警の裏金事件』については、私も以前に、関連書のレビューを書いているので、ぜひこちらを参照してほしい。
この問題に対する、「元警察官」である私の考え方も、そこにはっきり示してある。
ちなみに、道警の裏金問題に果敢に挑んだ『北海道新聞』であったが、残念なことに最終的には、新聞社の方がその政治的圧力に屈してしまい、現場を走り回った記者たちは、結果として、ハシゴを外されるかたちで孤立させられ、冷飯を食わされることになる。
青木美希も、そうした、元「北海道警裏金問題取材班」の一人で、職場を追われたあと、フリーのジャーナリストとなり、ノンフィクション作家になった人である。
つまり、彼ら彼女らの多くは、最後は「孤立無縁」となり、北海道を去らざるを得なくなったようだ。残念なことに、しっかりとした「救いの手」は、地元では差し伸べられなかったようである。
ちなみに、「Wikipedia」にもあるとおり、昔「治安維持法違反」で捕まったという北村紗衣の祖父は、
である。
順次郎は、戦前の共産党員であり、昭和2年の「集産党事件」で検挙されている。
この事件の「Wikipedia」の記述は次のとおり。
『集産党事件
治安維持法違反として、1927年(昭和2年)11月に名寄を中心とし、稚内・士別・旭川・剣淵等で活動していたマルクス・レーニン主義者を大量検挙した共産党弾圧事件。これは前年の京都学連事件に次いで全国2件目、北海道では初の治安維持法違反を名目として行われたものであったため、世間を沸かせたうえ警察側も思想取締り強化を再認識した事件であった。
「集産党」は、大正デモクラシーの思想的な影響を受け民主主義的考えをもつ者を中心として名寄で結成された「名寄新芸術協会」のメンバーが「党員」と目された政治結社であり、結党はされていたものの実体を周知していない者も多かった。そのため、検挙者のなかには自分がなぜ検挙されたのか、いつ党員にされていたのかも認識していない者も存在した。 この事件では、北村を含む「名寄新芸術協会」のメンバー計11人有罪とされたが、北村は第1審の有罪判決を上告し執行猶予付きで実刑を免れている。 このように、本事件ではもっぱら「名寄新芸術協会」のメンバーが検挙の中心となったために、本事件を「名寄集産党事件」と言う場合もある。
北村は、1927年(昭和2年)に旧制新潟県立農林学校を卒業後「名寄新芸術協会」に加入、戯曲を書きつつ農民運動に加わっていた。 北村は、高校在学中から小作争議の応援演説に行くなどしており、すでにこの頃には、日農北連(日本農民組合北海道連合会)の荒岡庄太郎からも人手が足りないと声がかかるなど、運動家とのコネクションも有していた。このように、名寄新芸術協会における文芸活動や日農北連での農民運動を通して、今野大力、小熊秀雄、小林多喜二らと親交を持った。
この事件の真相について、後年北村は党側ではなく検挙側にあったのではないかと推測している。北村によると、定説としてはソ連革命10周年に「反抗を発散せよ」とした不穏文書を党や党員が獲得したためとされているがそれはウソで、検事側の働きかけに特高警察が呼応したことが真相であるとする。』
北村順次郎は、戦闘的な共産党員と言うよりは、「芸術家グループ」寄りだったようなのだが、そんな芸術家の一人である小林多喜二が、警察での拷問によって殺されたというのは、有名な話である。
その点、北村順次郎は、警察で殺されることもなく『第1審の有罪判決を上告し執行猶予付きで実刑を免れている。』というのは、誠に幸運なことだったと言えるだろう。
ちなみに上の引用文の末尾の部分が、たいへん「意味のとりにくい悪文」になっているので、「ウィキペディアン」の肩書きを持つ北村紗衣には、是非とも、「祖父に関するこの文章」を、読めるものに直していただきたいものである。次の部分だ。
『この事件の真相について、後年北村は党側ではなく検挙側にあったのではないかと推測している。北村によると、定説としてはソ連革命10周年に「反抗を発散せよ」とした不穏文書を党や党員が獲得したためとされているがそれはウソで、検事側の働きかけに特高警察が呼応したことが真相であるとする。』
なお、北村直次郎の死去が1984年だから、『北海道新聞』による「道警裏金問題」スクープのことは、当然知らないはずだが、順次郎が社主を務めた『道北日報』は現在も存続しているので、『北海道新聞』が「道警裏金問題」でスクープを取っていた頃や、それ以後「被弾圧期」に、同じ北海道の新聞社としての『道北日報』の動きが、どのようなものであったのか、そのあたりを、関係者の身内として、お孫さんの「さえぼう」教授に、取材できるものならしてほしいところである。
ひと口に、「治安維持法」にかかわる同じ「被害者」とは言っても、小林多喜二のように殺された者もいれば、生きて帰ってくる者もいるのと同様、北海道の新聞社と言っても、「権力への対峙の仕方」はいろいろだったようであり、無難に生き残った者は、えてして自分に都合の良いことしか語らないものだからである。
(03)『考えてみたら警察映画を全然見てこなくて。映画に限らず、ミステリ好きなのに、有名なミステリ作家であるエド・マクベインが書いた警察小説も最近になって初めて読んだくらいです。基本的に警察を信用してこなかったからなのかもしれません。
『ダーティハリー』がつまらなかったのは、私が警察嫌いだからつまらなかったからだけではなくて、理由はたくさんあるんですよね。というか、名作として有名なんだからスリリングな映画なんだろうと思って期待して見たら、全然そんなことがなくてむしろ困惑しました……。』
北村紗衣は、いささか「偏見」と「思い込み」が激しいようだ。
当たり前の話だけれど、「警察官」も人間だから、当然のことながら色々いて、私のように、ネット右翼から「パヨク」だの「売国奴」などと言われ続けてきた者も、現にいるのである。
これは、例えば「共産党員」だって同じで、皆が皆、同じように「共産主義」の理想を向かってまっすぐに頑張った人ばかりではない。
例えば、やむを得ないこととは言え、「仲間を警察に売って、自分だけ生き残った」ような者も、現に少なからず存在するのである。
だから、もちろん「警察官ゆえの限界」「共産党員ゆえの限界」「武蔵大学教授ゆえの限界」といったものはあるにせよ、あまり人を「肩書き」だけで判断しない方が良いと思うし、それが「文学的な人間主義」というものでもあろう。
まあ、あんまりそんなことばかり言っていると、生きて帰ってはこられないのかもしれないが。
ちなみに『名作として有名なんだからスリリングな映画なんだろうと思って』というのも、当然「偏見」の一種である。
すなわち、『名作で有名』なら『スリリングな映画』だ、とは限らない。
「アメリカン・ニューシネマ」と言っても、色々あるくらいだから、ましてや『名作で有名』な作品と言っても、それはなおさら色々あるのだ。あって当然なのである。
ちなみに、北村紗衣はわからなかったようだが、本作『ダーティハリー』は「スリリングさ(スリル)」が売りの作品ではない。
そうではなく、「堪えて堪えて、最後に爆発する際のカタルシス」を狙った作品なので、そこを「理解できない」と、見当はずれな失望を味わうことになるだろう。
しかし、魚屋へ行って「大根を売っていない」と怒っても、それはお門違いなのである。
豆腐屋に「痛快娯楽大作」を期待したりするのと同じ、お門違いなのだ。

『ダーティハリー』が、「スリリングさ」を狙った作品ではない、というのは、スコルピオに誘拐された少女について、身代金要求の連絡が入った段階で、すでにハリーが「殺されていますよ」と、あっさり断じるところからもわかる。
つまり、「スリリングさ」を狙ったのであれば、誘拐された少女の生きている可能性を最大限にアピールしておかないといけないのだ。
ハリーがスコルピオの指示に従って、身代金の入った黄色いカバンを下げて東奔西走させられるという苦労も、少女が生きていればこそ意味がある(スリルを醸成する)のであって、少女の生きているの可能性が低ければ、ハリーの苦労は、最初から徒労にしか見えないからである。
だから、「スリル」を醸成したかったのであれば、主人公のハリーに「もう殺されてますよ」などとは言わせないはずなのだ。彼の言葉は、この物語の中では「予言」として働くからである。
で、結果はと言えば、やはりハリーの予想したとおりに、少女はすでに殺されていた。
スコルピオはただ、警察を、ハリーを揶揄い弄びたかったがために、余計な手間をかけてまで、ハリーを走り回らせたのだ。
したがって、なぜ、はじめから「少女はすでに殺されているだろう」などということを「主人公の言葉」として語らせ、「少女が生きているかもしれない」という可能性において生ずる「スリル」を削ぐようなことをしたのかと言えば、それは「無駄とわかっていながらも、一縷の望みにかけて奔走する主人公の苦しみ」と「人の心を弄ぶ悪役の憎たらしさ」を、観客に植えつけるためなのである。
そうした「忌々しい状況」を描くことで、最後にハリーがスコルピオを射殺しても、むしろ観客は、それを支持して溜飲を下げ、カタルシスを感じるように、意図して「作られている」ということなのだ。
だから、本作を見る前に、北村紗衣が「誤った期待」を抱いていたのはやむを得ないとしても、本作を見終わった後なのであれば、「この程度のこと」は、当然理解していなければならない。
だが、どう見ても北村紗衣は、それが全くできなかった様子なのである。
(04)『犯人のスコルピオってゾディアックがモデルですよね? で、実在する凶悪犯を褒めるのはあんまりよくない気がするんですけど、ゾディアックに比べるとスコルピオってポンコツ過ぎませんか? 犯行に一貫性がないし、どう見てもつかまりそうなことをやっているし……実際のゾディアックは捜査を攪乱したりメディアを操作したりして今も正体がわかっていませんし、もっとはるかにずる賢くて怖い犯罪者だと思います。実在のゾディアックのゾッとするような恐ろしさに比べると、スコルピオはただのメチャクチャな暴力犯罪者みたいな感じで……。』
北村紗衣らしい「無駄な知識のひけらかし」である。
そもそも「現実の犯罪者」と「フィクションの犯罪者」を、同列に比較して、「フィクションの犯罪者」が「非現実的」だと批判しても仕方がない。
「現実の刑事は、あんなに射撃がうまくはない」と、真顔で注文をつけるのと同じレベルのことである。
(05)『ハリーが黙秘権など被疑者の権利を伝えるミランダ警告をしなかったことを理由に、一度捕まったスコルピオが釈放されていました。ここでハリーが正式な手順を踏んで逮捕していたら、スコルピオはそのまま裁判にかけられて重罪で刑務所に入っていましたよね? この犯人は単に運がよかっただけで、あまりにも行き当たりばったりな生き方をしていません?』
なにしろ、スコルピオは、見てのとおりの「異常者」という設定であり、しかも「フィクション」なんだから、作劇上の都合で『行き当たりばったりな生き方をして』いても、なんら問題はないのである。
それはハリーが、銃器で武装した複数の銀行強盗の前へ、物陰に隠れることもなく、まっすぐに歩いていくのと同じことである。それに対して「ハリーは、身の安全を何も考えないバカなんですか?」と非難しても、「考えてないのは、オマエの方だ」(声・山田康雄)と返されるのが関の山なのである。
(06)『冒頭では、ビルの屋上のプールで泳いでいる女性を遠くのビルから撃ち殺してました。健康な女性が、あの距離で後ろから肩を撃たれて即死することにも疑問なんですが、なによりスコルピオが脅迫文を狙撃地点に残していて、「こいつ、大丈夫か?」って思ったんですよ。ハリーが見つけたからよかったものの、普通だったら新聞社とか警察に直接送ったり、接近して撃ったあと現場にメッセージを残したりしません? 誰にも見つからなかったら元も子もないじゃないですか。』

そもそも被害者女性は、「撃たれて即死した」のか「撃たれたことで失血死した」のか「撃たれたことで溺死した」のか、そんなことハッキリとは描かれていないのだ。
「撃たれたので死んだ」と描写されているだけなのである。
また、スコルピオが脅迫文を射撃現場に残しておいたことについて『「こいつ、大丈夫か?」って思ったんですよ。ハリーが見つけたからよかったものの』とのお言葉だが、射撃可能地点はごく限られており、現場に薬莢まで残しておいたのだから、ハリーではなくても、そこに、これ見よがしに置かれていた脅迫文くらいは、警察が必ず見つけただろう。
したがってこれも、脅迫文と言えば郵送するものだというのは、「雑学」による、つまらない「思い込みの決めつけ」でしかない。
猟奇殺人においては、現場付近に「挑戦状」が遺留されているというのは、実際にもあるパターンなのである。
(07)『犯人があまりにポンコツなので、サスペンスとして全然面白くなかったんです。』
そうではなく、本作を「サスペンスもの」と見た段階で、本作を理解できていないためなのだと、そう理解すべきであろう。
スコルピオは、あくまでも「憎たらしいポンコツ」なのである。
(08)『スコルピオがポンコツに見えるのは、我々がすでにゾディアックに関する知識をたくさん持っているからなのかもしれません。デヴィッド・フィンチャーの『ゾディアック』(2007年)とか、後続の映画をいろいろ見ているわけですし……この映画が公開されたのはゾディアックがいろいろと活動していた時期だと思うので、まだ冷静に検証されてはいないでしょうし、当時の人たちにとっては生々しくて、犯人がポンコツだとしてもすごく怖かったのかもしれないですね。』
また、北村紗衣らしい「雑学自慢」である。

ちなみに、私の北村紗衣プロファイルからすると、北村紗衣は「犯罪者にこそ惹かれている」ようにも見える。
「警察もの」は嫌いだから見なくても、「狡猾な犯罪者もの」なら、好きでいろいろ見ているようだ。いかにも、らしい「趣味」だと言えるのかもしれない。
(09)『――調べてみたところ、スコルピオンはベトナム戦争時にアメリカ軍が使っていたブーツを履いているという話がありました。
『タクシードライバー』(1976年)や『ランボー』(1982年)の主人公と一緒で、スコルピオはPTSDを抱えた帰還兵ってことなんですかね? つまり冒頭の遠距離から女性を撃つシーンは、スコルピオンがベトナム戦争のときにスナイパーで、メンタルを崩してしまっていることを表現している?
でもそうなんだったら、スコルピオが帰還兵であることをもっとちゃんと描いたらいいのにって思いますけどね。』
たしかに、ハッキリとそのように描いているわけではなく、その「可能性」を示唆してはいる、程度に考えるべきであろう。
というのも、本作について、映画評論家も町山智浩は、北村紗衣の『ダーティハリー』も「アメリカン・ニューシネマの内かも」論に対して、
『町山智浩
@TomoMachi
『ダーティ・ハリー』がニューシネマとして論争になってるようですが、『ダーティ・ハリー』は狭義の「アメリカン・ニューシネマ」には含まれません。既存のハリウッド・システムとベテランの職人による、むしろ反ニューシネマです。
午前8:14 · 2024年8月26日』
と「X」に書いているとおりで、『ダーティハリー』は、『タクシードライバー』の主人公トラヴィス・ビックルを裏返したようなかたちで、スコルピオを、ハッキリと否定的に描いたと考えた方が良いだろう。
事情はどうあれ、犯罪は犯罪だと。
もちろん、「ベトナム帰還兵」そのものを悪く描くわけにはいかないから、あくまでも「ほのめかす」に止めたのだろうし、その使用銃器を、日本製やドイツ製のもので固めたのも、スコルピオが「枢軸国的なファシスト」であり「反アメリカ的・反民主主義的」だということを匂わすことで、言うなれば「中和」が図られたのだとも考えられよう。
(10)『ポンコツ頂上対決
60年代後半から70年代に、アメリカン・ニュー・シネマ(英語ではニュー・ハリウッドと呼ばれます)という潮流がありました。何らかの体制に抑圧されている若者たちが、なんとかして現状を打破しようする反体制的な要素と、あからさまな暴力やセックス表現が主な特徴として挙げられます。あとでお話すると思いますが、私はニュー・シネマ自体があんまり好きではありません。』
この「雑な定義」が、須藤にわか氏や、多くの映画ファンの逆鱗に触れたところである。このあたりについては、須藤氏の反論でも読んで貰えば良いと思う。
ともあれ、このように、北村紗衣という人は「嫌いなもの」を、感情を排して客観的に評価することのできない人である。
また、その出来ないことを、して見せているつもりでも、その素っ気なさがハッキリと見えてしまってバレバレだというのは、北村紗衣が、ある意味では「正直」な人だと言えるのであろう。だからこそ、「謙遜を装った自慢話」というパターンも、人によっては見抜かれてしまうのである。
一一この点については、すでに紹介した下のレビュー、
の中で、北村紗衣の「愛の理想郷における、ブス 一一夢見るためのバズ・ラーマン論」を論じた部分を、ご参照願いたい。
(11)『『ダーティハリー』もこのニュー・シネマの影響下にある警察映画だと思うんですが……でもニュー・シネマ的なのかどうかがよくわかりませんでした。』
結局『ダーティハリー』と「アメリカン・ミューシネマ」の関係は、わからなかったそうなのだが、ならば『ダーティハリー』を論じる回で、なにも無理やり「アメリカン・ニューシネマ」を否定的に論じる必要もなかったのに、という意見も、ネット上で見られた。
しかしながら、こんな「ポンコツな『ダーティーハリー』論」だけでは「もたない」ので、話を「アメリカン・ニューシネマ」へとズラし、その上で「ヘイズ・コード」に関する知識を、無理やりにでも「ひけらかしたかった」のだと、そう理解することもできよう。
『ダーティハリー』という作品への「読み」は素人以下でも、「知識では負けないぞ」とそんな「可愛い」ところもあるのだと、そう言って言えないこともない、ということだ。
(12)『というのも、この映画は、アメリカで民主主義が機能していないためにハリーのような法を守らない刑事が活躍してしまう、みたいな話だと思うのですが、これを風刺として描いているのか、それともハリーのことをかっこいい警察だと肯定的に捉えているのか、いまいちよくわからなかったんです。そこがすごく引っかかったんですよね。』
う〜ん、なんとも「雑なまとめ方」だ。
なぜなら、ここで言うアメリカの『民主主義』とは何を指しているのか、が問題だからである。
例えば「犯罪者の人権を徹底的に守る」ことが「民主主義」なのか、それとも「それが行き過ぎていると思える現状に異を唱える」ことこそが「民主主義」なのか、といった問題だからだ。
本作に満ちた気分は、明らかに後者で、要は「民主主義や人権の形式化」を批判しているのである。
つまり「犯罪者の権利を守るというのは、大いに結構。しかし、それが形式に堕した結果、なにか肝心なものを忘れてはいませんか?」というような気分である。
(13)『ニュー・シネマは多くの場合、アメリカ社会が正常に機能していないのだから暴力が発生するのだ、みたいな話になっています。』
これも「雑なまとめ方」でしかなく、「そうなのか?」といった程度の放言にしかなっていない。
(14)『でも、ハリーは刑事ですよね。法を守らないといけない立場の人が、社会が機能していないことを理由に法を破ってもしょうがないんだと描くのって、どうなんですかね? 反体制なんですかね?』
そこは「フィクション」だから、「あり」だろう。
現実に法律をやぶれば、その法律が正しかろうが間違っていようが罰せらるのだから、せめて「フィクション」で異を唱えるというのは、許されてしかるべきであり、それこそが「表現の自由」の範疇である。
そんなことさえ許されないのだとしたら、「大学の先生が、そんな粗雑な話をしてもいいのか」とか「そんな配慮のない口のきき方をしてもいいのか」と、そんな窮屈な話にもなろう。
そもそも「法律に従うこと」が必ずしも「正しいこと」ではないからこそ、北村紗衣の祖父は「共産党員として逮捕された」のではなかったのだろうか。
それとも、法律で禁止されている「非合法活動に従事している共産党員」なら、北村紗衣の祖父は、法律に従って、その人物を警察に売り渡したりしたのだろうか?
(15)『ちなみにハリーのことをファシストだという人もいます。一方で、クエンティン・タランティーノは、公開当時にポーリン・ケールなどの映画批評家がハリーをファシストだと批判していたって言っていたけどそうじゃなくてどっちかというと反動的なんだ、と自著の『Cinema Speculation』で言っていました。私の意見ですが、ファシストというのは権威主義的・国家主義的な方向に行くと思うので、どうも法律が細かいことまで決めているのが気に入らなくて法を破るハリーはあんまり国家や権威じたいは尊重しておらず、ファシストとは違うんじゃないかなと思っています。まあ、警官すら国家や権威を信用していないというのはニュー・シネマ的なのかもしれないですね。』
あまりにも低レベルの議論なので話にもならないが、『法を破るハリーはあんまり国家や権威じたいは尊重しておらず』というのは、正しいと思う。
なお、ここで言う「反動的」とは、要は「伝統主義」者のそれを指して、進歩主義者の立場から評した言葉なのである。
さて、私が以前、ドン・シーゲル監督の『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(1956年)論じた際にも触れたことだが、ドン・シーゲルには、赤でも青でも白でもなく、とにかく「群れる」「数に頼む」「組織の力」といったことが嫌いな、「一匹狼」好みがあったようだ。それで、映画会社とよく揉めていたのだ。

(16)『――スコルピオは旧日本軍のライフル、ナチス・ドイツが開発したMP40、そしてワルサーP38と、第二次大戦時の日本とナチスの銃を使っていました。しかも黒人の少年を殺している。ハリーよりもスコルピオのほうがファシストで、差別主義者のように描いていませんか?
確かにそうですね。ゲイカップルと思われる人たちを殺そうとしていましたし。』
ここでのインタビュアーの意見は、よそで何度も語られている「半通説」である。
しかし、それに対する北村紗衣の返答は、問いへの回答にはなっておらず、無理やり自分の興味の範疇へとずらしてしまうところが、いかにも視野と守備範囲の狭い人なのだと、ここでも再確認させられよう。
(17)『そうそう、ハリーってたぶん親はカトリックなんだろうなと思って見ていました。途中でカトリック教会が脅迫されますけど、一応ハリーは教会は尊重しているみたいでしたよね。それにハリー・キャラハンっていう名前で、キャラハンはカトリックが多いアイルランド系の名前です。』
イギリス文学の研究者らしい「雑学」披露で、とても勉強になる。
(18)『カトリックのアイルランド移民の警察官が、ナチスっぽい犯人と戦うって考えると、やっぱりハリーはファシストっぽくはないですよね。ちなみにアメリカにはアイルランド系の警察官が結構いて他の映画にもよく出てくるので、ルーツに注目するのもいいかもしれないです。』
だから、普通は誰も、ハリー・キャラハンを「ファシスト」だなんて思わないので、それを否定しても、あまり意味はないのだが、どうやら、そうした関連性までは想像が及ばなかったようだ。
(19)『――『猿の惑星』(1968年)の回で北村先生は、映画と主演のチャールトン・ヘストンの考え方がリンクしているのではないかというお話をされていました。『ダーティハリー』も、クリント・イーストウッドの考え方が反映されていると思いますか? イーストウッドは長年共和党支持者で、リバタリアンだと公言していますよね。
どうなんでしょう。
リバタリアンもいろいろあるんですけど、基本的には法的な規制を極力少なくして、個人的・経済的自由を尊重する立場の人ですよね。ハリーがリバタリアンなのだとしたら、ミランダ警告みたいな細かい事務手続きを廃止する方向に動くような気もしますけど、どうなんですかね。まあ、廃止したいのかな……。』
廃止したいだろうね、当然。一目でわかる。
(20)『多くのリバタリアンはおそらく、警察組織自体は否定せず、最小限の予算を出すことに反対はしないと思います。警察なんていらないと考えるリバタリアン・アナキストは少ないですよね。でも、ハリーは警察ですし……まあ『ダーティハリー』はリバタリアン的な映画だとは言えるかもしれないと思います。』
ハリーは、「ファシスト」でもなく「アナキスト」でもなく、政府の介入を最小限にして、個人の主体的な判断を尊重するようしたいと望む、「リバタリアン」的な人だというのも、見ればわかることだろう。
(21)『ただ、たぶんミランダ警告をしなかったのって、別に積極的な政治行動としてではなく、単に警告しなかっただけに見えるんですよね。警察官なので「逮捕するときはこういう手順でやりなさい」って訓練されているはずですよね? それをしないのって留置所に鍵をかけないのと同じレベルでおかしいわけじゃないですか。職務怠慢ですよ。「警察なんだからちゃんと仕事しろよ」って思っちゃいました。実はスコルピオと同じでハリーもわりと無能なんじゃないですか?』
「共産党は非合法であり、入ってはいけないと決まっているんだから、日本人なら法律を守れよ」という議論と大差がないということに、たぶん気づいてはいないのだろうな、この映画評論家の大学教授は。
これではやはり、批評家として、いや、映画鑑賞者として、言いたくなくても、「無能」としか呼びようがない。
(22)『そうか、この映画はゾディアックに比べて愚かなスコルピオと、無能な警察官のハリーによる、ポンコツ頂上対決映画なんですね!』
そんな評価を語るポンコツ評論家。その頂上に立つのは、北村紗衣その人だと、私は確信する。
(23)『そもそもリアリティに疑問があるところもけっこうあります。同じところを疑問に思っている人はたくさんいるみたいなんですが、捜査に問題があったら裁判のときに警察側が不利になるとは思うんですけど、警官を撃った容疑で逮捕され、誤認逮捕の可能性はほぼないスコルピオを裁判もせずにそのまま釈放したりはしないんじゃないですかね。しかもスコルピオは明らかに警察に目をつけられているのにその後もすぐ犯罪を続けていて、捕まるに決まってるじゃないかと思うし……やっぱり犯人も警察もどっちもポンコツですよね……。』
わざと、主人公の周囲を「ポンコツ」に描くことで、主人公に試練を与え、物語を駆動させるという演出だ、くらいのこともわかっていない、ポンコツ映画評論家。
(24)『この映画はたぶん、警察が機能していないので、ハリーのような刑事が必要だってことを描いているんだろうとは思いますが、それにしても現実を曲げて、警察をすごく無能に描いていると思いました。女性に対する性暴力を、プロットをすすめて警察の行動を正当化するためだけに使っているあたりとかも問題ですね。』
警察が嫌いで、警察のことをよく知らない北村紗衣でさえ『現実を曲げて、警察をすごく無能に描いていると思』ったくらいなのなら、「なぜ、現実を曲げているのか」まで考えるべきであったのだが、その能力は無かったのだろう。
また、だからこそさっさと、お得意の分野に話をズラそうとしているのだ。「ジェンダーがらみなら、私に任せておけ」と。
だが、そんなことだから「ワン・トリック・ポニー(一つの芸しかできない子馬=ワンパターン)」などと言われるのである。
この事実については、下の拙稿で、北村紗衣の『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』の「あとがき」を論じた部分を、参照のこと。

(25)『……やっぱり、この映画がハリーのことをどう捉えているのかの解釈が難しいですね。スコルピオみたいな人がいたら逮捕しないといけないというのはほぼすべての市民が同意すると思うんですけど、一方でそれに対抗するために法律を守らなかったり、自分がやったポンコツな失敗を暴力で回収するみたいなことをやっていいのかどうかっていうことで、人によって受け取り方は違うと思うんですよね。私は警察がポンコツすぎてハリーの行動にずっと呆れていました。』
私にとっては『この映画がハリーのことをどう捉えているのかの解釈が難しい』ということは、まったくない。至極わかりやすい映画である。
むしろ、この娯楽映画が「わからない」人の方をこそ「ポンコツ」だと考える方が、よほど合理的であろう。
(26)『ちなみに今回、『ダーティハリー』の3年前に公開されている『ブリット』(1968年)も一緒に見ました。『ブリット』もシフリンが音楽を担当していて、さらにスティーブ・マックイーンが演じたフランク・ブリット警部補のモデルって、ハリーのモデルと同じ、実在する警察官のディヴィット・トスキなんですよ。トスキは、ゾディアック事件の捜査で有名な警察官です。』
またもや「映画雑学」の披露。
映画マニアではない私には、そんな話でも勉強になる。
(27)『『ブリット』は撃たれた人が死ぬまでに時間がかかったり、ブリットが独断で何かをやろうとすると政治家が介入してきたり、ミステリとしてもうちょっとリアリティがあるし、サスペンスが盛り上がるところもあって面白いと思いました。』
『ダーティハリー』においても、最初に射殺された女性が「即死」だったかどうかまでは描かれていない、というのは先述のとおりである。
なお、個人的な話で恐縮なのだが、仮にも「SRの会」に所属していた元ミステリマニアとしては、この人に、知ったかぶりで「ミステリ」を語ってほしくない。
もしも直接会う機会があれば、どれくらい読んでいるのか、黒っぽいところをいろいろ質問してやろう。
(28)『アメリカン・ニュー・シネマで悪化したこと
――アメリカン・ニュー・シネマ自体があまりお好きではないとおっしゃっていましたが、その理由を教えてください。
60年代後半から70年代の潮流であるニュー・シネマは、それ以前にあったいろいろな制約が外れ、暴力やセックス描写ができるようになり、そしてアメリカの秩序を問うような映画がたくさん作られた時代です。
そのくせに、結局は男性というか、主に白人男性が中心であることは問い直してないんですよ。見方によっては、むしろ悪化している。もちろん『バニシング・ポイント』(1971年)には黒人DJが出てきますし、『俺たちに明日はない』(1967年)には女性が重要な役として出てくるので、全部が全部そうというわけではないんですけど。』
『全部が全部そうというわけではないんですけど。』って、それは当たり前だ。
全部が全部そうなったら、それこそ「ファシズム」である。
(29)『1934年頃に、通称「ヘイズ・コード」(モーション・ピクチャー・プロダクション・コード)という、保守的・道徳的な見地から暴力やセックス描写などを自主検閲する規制がハリウッドで厳しく施行されるようになりました。その前からコードじたいはあったんですけど、あんまり守られてはいなかったんですね。それ以前の、トーキーが始まった1929年から、1930年初頭までのアメリカ映画を、「プレコード・ハリウッド」と分類します。』
はいはい。
(30)『このプレコード時代って、メイ・ウェストみたいなおもしろおかしくてキャラの濃い女優が主演を務めるきわどい映画なんかもけっこう作られていたんです。プレコードが終わってヘイズ・コードの時代になってからも、キャサリン・ヘプバーンやベティ・デイビスが出ているような、女性のスターによる女性のための映画は数多く作られていました。もちろん、そうした俳優はエリート白人女性の役を中心的に演じていたので限界もあるんですが、少なくとも奥行きのある女性キャラクターが活躍する映画じたいはニュー・シネマ以前のハリウッドに意外と存在していたんですよ。』
はいはい。
(31)『参考:【お砂糖とスパイスと爆発的な何か】知られざるプレコード映画の世界(1)~実は奥深い映画規制「ヘイズ・コード」(北村紗衣)
60年代くらいになるとヘイズ・コードは事実上無効化されています。ニュー・シネマはまさに、ヘイズ・コードの規制が無効になったあとに生まれた潮流で、アメリカをリアルに描くことができるようになった……はずなのに、プレコード時代では見られた女性中心的な映画はあんまり作られなかったんです。』
それは残念ですねえ。

(32)『ニュー・シネマが男性中心的だっていう話は映画評論家のモリー・ハスケル(『崇拝からレイプヘ――映画の女性史』)をはじめとしていろんな人がしているのでそんなに新しい論点じゃないんですけど、映画を見た後にどういう時代の流れにあるものなのかを調べると、いろいろ感想を話しやすくなるかもしれません。』
『そんなに新しい論点じゃない』と言うよりも「まったく新しくない論点」てあり、いっそ「今更それを持ち出すのかというくらいな古典的な論点」だと、評すべきであろう。
まあ、今でさえまだまだ男性社会なんだから、当時がそうだったのはむしろ当然だし、ルールを作ったからと言って、急に変わるものではない、というのも当たり前の話。
なにしろ、いかに「正しい」と思えることであっても、「強制」は可能な限り避けなければならない。
でないと、ファシズム的な「独善」が、まかり通ってしまう事態にもなりかねないからだ。
つまり「説明し、説得し、納得して受け入れてもらう」ということが大切なのだ。
(33)『以上が、『ダーティハリー』を初めて見た私の感想です。』
ご苦労様でした。
(34)『今回出てきたポイント
ここまでいろいろお話ししてきた内容から、映画を見る際のポイントを紹介したいとおもいます。
ひとつめですが、たぶんみんなあまりこの映画をミステリとか実際の事件をヒントにしたサスペンスとしては見ていない……のかもしれませんが、その観点から見るとなんだかダメな犯人とダメな警察がダメダメな対決をしているだけの作品みたいに見える、ということです。私がもともとタイトなサスペンスとかずる賢い犯人によるトリックなんかが好きだからそう思うのかもしれませんが、ミステリファン的には全然、面白いと思えなかったです。』
そういう問題ではない。


ただ、北村紗衣先生が『ずる賢い犯人によるトリックなんかが好き』だというのは、これまでの「言動」からして、とても納得のいくところではある。
例えば、「言論」ではなく、いきなり「管理者通報」するとか「オープンレター」とか「スラップ訴訟」とか、敵を嵌めることを楽しんでいるようにしか見えないのだが、そうではないのだろうか?
(35)『 とくに犯人があまりにも行き当たりばったりでイライラしました。ちなみに『フレンチ・コネクション』(1971年)も一緒に見たんですが、やっぱり全然面白いと思わなかったので、もう1970年代の警察映画にはミステリ要素は期待できなくて、こういうものだと思って見るしかないのかもしれないですね……私には向いていないようです。』
だから、「ミステリ、ミステリ」と連呼するのは、止めていただきたい。
私は、間違いなく「本格ミステリマニア」だったけれど、それとは「別種のもの」として『ダーティハリー』も『フレンチ・コネクション』も楽しむことができたのだ。
要は、単純に「受容能力」の問題だと考えた方が良いと思う。
だから、「ワン・トリック・ポニー」さんとしては、もう少しは「謙虚」になってはどうだろうか。
一一もちろん、無理だとわかっていて、言っているのだが。
(36)『 ふたつめですが、アメリカン・ニュー・シネマはかなり男性中心的な潮流で、『ダ―ティハリー』にもそういう要素があるということですかね。まあ、『ダーティハリー』が男性中心的な映画なのは指摘するまでもない……というか、見たらたちどころにわかると思うんですが、正直なところ、私はものすごく男性中心的な映画なのかなと思って見たらそれ以前の問題として犯人も警察もダメすぎなのが驚きました。有名作だし、男性中心的とはいってももうちょっとよくできた映画なのかと思って見始めたんですが、素で面白くなくて……。』
「男中心の映画」であることと「傑作であること」とは、話が別だということくらいはわかってほしいものだ。
当然のことながら、「男中心の映画」にも、「傑作」もあれば「駄作」もある。
それは、「男」にも「勇敢な人」もいれば「ヘタレ」もいるし、「女」にも「正直な人」もいれば「確信犯的な嘘つき」もいる、というのと同じことなのである。
(37)『 あと、アメリカにおける警察の位置づけを考えながら見たほうがいいのかなと思います。最近は警察による問題行動、とくに人種差別に起因する暴力や腐敗が批判されているので、『ダーティハリー』みたいな映画はたぶん見ていてかなり居心地悪く思う人も増えているだろうと思います。まあ、北海道出身者としては警察がポンコツなのは通常営業ですが……。』
まともな文芸評論や映画評論を読んできた者としては、ポンコツ映画批評は「通常営業」ではないので、もう少しなんとかしてもらいたいものである。
(38)『 最後に音声ですね。ラロ・シフリンの音楽はリズムの使い方に特徴があってとにかくカッコいいと思いますし、音を使って盛り上げる演出じたいは良かったと思います。私は映画じたいは全然面白いと思わなかったのですが、音楽は映画から切り離して聴けるくらいはクールだと思いました。大きくて音響のいい映画館で見るともっと緊張感があって面白いのかもしれないです。』
私は音楽のことはよくわからないのだが、北村紗衣は、映画評論は辞めて、音楽評論に進んだ方が良いのではないかと思う。
一一まあ、先方さんが、どうおっしゃるかは知らないが。
(39)『まとめ
最後に、私が『ダーティハリー』の批評を書くとしたらどうするかをお話ししますね。』
書かない方が、身のためだろう。
(40)『 たぶん名作と言われてみんなに愛されている作品でも今見て面白くなかったらけなしていい! ということで、犯人も警察もグダグダじゃないか、という方向性で書くと思います。』
まあ、そうでしょうね。
(41)『 比較的ぬるい展開を演技と緊張感のある音楽でなんとなく面白い感じに仕立て上げているだけの「雰囲気名作」なのではないかと……時代背景を考えつつ、1970年代というコンテクストで見ると新しかったのでしょうが、2024年に見てスリリングな映画かどうかは多いに疑問だ、という内容にしますね。』
やっぱり、書く値打ちのない、「ぬるい」とさえ評し難い文章になりそうだ。
まあ、それでも「北村紗衣ファン」なら、なんでも喜ぶんだろうから、好きにすれば良いと思いはするが、その程度の駄文が「日本の映画評論」だと、万が一にも思われる事態など、映画マニアたちは、想像したくもないはずである。
私が、北村紗衣に「ミステリ、ミステリ」と言ってほしくないのと同様に。
それにしても、なんとスカスカな『ダーティハリー』の「感想雑談」であったことよ。
私は『ダーティハリー』の中古DVDを「ブックオフオンライン」で、330円で買って見たので、出来れば多くの人にも、『ダーティハリー』を実見して、自分の目で確かめていただきたい。
そして、あなたの評価が、北村紗衣に近いか、年間読書人に近いのかを、ぜひとも公言していただきたいと思う。

(2024年10月2日)
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
