
大塚康生 『作画汗まみれ』 : 〈職人〉という イデオロギー
書評:大塚康生『作画汗まみれ 改訂最新版』(文春ジブリ文庫)
いささか、大塚康生という人を舐めていたようだ。
本書を「日本のアニメの草創期を知る」といった観点から読むアニメファンが、もとより読者の大半なのではあろうが、私は古い「アニメファン」ではあっても、単にそれだけではなく、批評書も読めば思想書も読む、「読書家」でもある。
そんな私が、本書を読む上で、最も重要なポイントと考えるのは、大塚康生という人は、単なるアニメーターなどではない、というのは無論、単なる「アニメ(動画)の職人」でもない、ということだ。
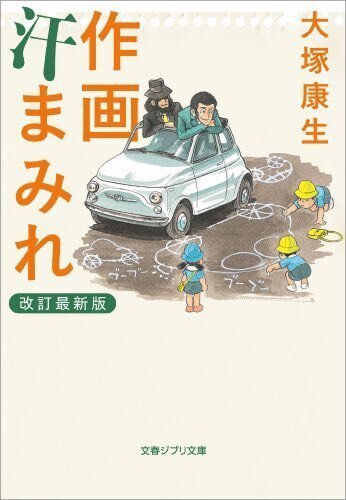
私たち古いアニメファンが「大塚康生」という名前を聞いてまず思い浮かべるのは、高畑勲と宮崎駿の古い「同志」であるとか、最初の『ルパン三世』や同映画長編『ルパン三世 カリオストロの城』、あるいは宮崎駿の出世作である『未来少年コナン』の作画監督を務めた人、とかいったことだろう。
この三人の出会いは、テレビアニメの放映が始まる前の「東映動画(現・東映アニメーション)」の設立(1956年)を発端とする。つまり、手塚治虫の「虫プロ」による最初のテレビアニメーション『鉄腕アトム』が登場(1961年)した、アニメが映画からテレビへと主戦場を移す、端境期の時代にまで遡るのだ(高畑は59年、宮崎は63年に入社)。
大塚は、「東映動画」との合併がすでに決まっていた、森康二や大工原章といったアニメーターたちの所属していた「日動映画」に入社し、それで「東映動画」の設立(1956年)と同時に、第1期生として入社した人だ。
つまり、大塚の先生筋にあたる森康二や大工原章といった人たちは、「東映」が専門の動画部門をつくる前からアニメーターだった人たちであり、東映本社が、ディズニーを意識して、本格的なアニメーション制作に乗り出すために、外部から招いた人たちである。
したがって、大塚康生は東映動画のアニメーターとして、最古参の一人だと言えるだろう。高畑勲や宮崎駿が、大塚の「同志」あるいは「同士」だと言っても、明確に「後輩」であることを忘れてはならない。

高畑勲や宮崎駿が、作品作りの先頭に立つ「監督」となり「アニメーション作家」になったのに対し、大塚康生は、生涯「いちアニメーター」であり、「動画の職人」という立場にあることを自ら強調し続けたから、私たち古いアニメファンは、そうした大塚の「自己規定の言葉」を素直に受け入れて、「大塚さんは職人なんだ。作画に対しては徹底したこだわりを持つけれど、アニメ作りに関して、自己の主義主張を(宮崎駿のように)強く推し出す人ではないのだ」と、おおよそ、そんなふうに思っていた。
もちろん、大塚康生が、高畑勲や宮崎駿らと共に、東映動画に設立された「労働組合」のリーダーだったことくらいは知っているだろう。だが、その場合でも、なんとなく「高畑さんなら頭もいいし、粘り腰の理論家だから、労働組合のリーダーにぴったりだったろうな」とか「宮崎さんは、なにしろ人並み外れた馬力の持ち主だったから、高畑や大塚とともに、労働組合でも、とんでもない馬力を発揮して活躍したんだろうな」という感じのイメージを持ち、それに比べると、「動画の職人」である大塚康生には、「労働組合の闘士」だとか「組合の指導者」といった印象は薄く、なんとなく「後輩である、高畑勲や宮崎駿をバックアップし、彼らを見守り支える立場だった」のではないかという、漠たる「印象」しか持っていなかったのではないだろうか。

だが、本書を読んではっきりとわかったのは、大塚康生という人は、単なる「動画の職人」さんなどではなく、明確なイデオロギーを持っており、しかもそれに沿って、文章を書き発言をする、自覚的な「思想家」であり「運動家」だという事実だった。
一一そして、特に私たちが気をつけるべきなのが、「職人」という言葉が、半ば自覚的に「煙幕」として使われていた点である。
たしかに、大塚康生は「動画の職人」である。しかし、それが「すべて」ではないということに注意して、私たちは、彼の文章を読まなければならない。
そもそも、「職人」さんが「アニメは、こうあるべきだ」とか「人間は、こうあるべきだ」とかいったような文章を、依頼があってのこととは言え、わざわざ書くはずがないし、書けることももっと限定されていて、決して本書のような、明確なビジョンを持った本など書けるわけもない。
つまり、大塚には大塚の「思想」があって、それは「アニメーションの作画」に限定されるような、「職人」的な「狭い範囲でのこだわり」などではないのだ。
彼が、東映動画の労働組合において、最初のリーダーになり得たのは、決して「古参アニメーター」だったからではなく、労働運動に関して、明確なビジョンを持ち、それを語れる人であったからだ。
つまり、本書の「解説」で高畑勲が、
『 大塚さんは私がはじめて出会った原画家でした。そして、はじめて演出をした作品の作画監督でもありました。労働組合運動に導き入れたのも大塚さんなら、劇場用長編に演出として迎えてくれたのも大塚さんでした。』
(「人生の兄貴分」、本書P326)
『 大塚さんが月給大幅ダウンにもめげず、麻薬取締官事務所を辞めてアニメーターの道を歩みだしたのがなんと26歳、並大抵の決断でできることではありません。当時、アニメーションは気息エンエン、諸先輩の努力によってかろうじて生きのびているにすぎない日陰の花でした。私たちはそんな前歴の大塚さんから、仕事だけではなく人生の兄貴分として実にさまざまなことを教わりました。それはレーニンを読むことから、(※ アジテーションビラ作成のための)ガリ版の上手な切り方にまで及びます。』(前同P328、「※」は引用者補足)
と書いているとおりで、高畑勲を組合運動に引き入れて、当時の流行だったとは言え、「マルクス・レーニン主義」を叩き込んだのも大塚康生であった。これは、宮崎駿においても、ほぼ同様の事情だったのではないだろうか。
ちなみに大塚は、旧制中学卒、今でいう高卒で、当時としては決して珍しくはなかったものの、学歴エリートということでもなかった。
むしろ、高畑勲は「東京大学卒」だし、宮崎駿は「学習院大学卒」で、彼らこそ、まぎれもない「学歴エリート」だったのだから、そんな彼らに対し、いくら会社の先輩であり、優れたアニメーターだからといっても、普通なら、「レーニン」を読むことの必要性を教える、なんてことはできなかっただろう。

つまり、少なくとも、その当時の大塚は、バリバリの「マルクス・レーニン主義者(共産主義者)」であり、自伝的な記述では、もっぱら「機関車や戦闘機などの絵を描いていた、田舎の少年」といったことしか書かないし、言いもしないが、内実はそんなヤワなものではなかったということであり、かなり意識的に、自身の「思想信条」の部分は隠していた(おおっぴらに語ることはしなかった)ということである。
考えてもみて欲しい。いくら、当時は「共産主義運動」の機運が高まっていたとは言っても、所詮は高卒の者が、レーニンなんかを、当たり前に読んでいたりするものではない。
実際、当時の運動家の多くは、つまり、党派理論家や知識人的リーダーを別にしたら、マルクスさえろくに読んでいなかっただろうし、ましてレーニンまで読んではいなかっただろう。

高畑勲が、ここで「マルクス」を出さずに「レーニン」を出したのは、今となっては、そのほうが「政治思想臭」が少ないと考えたからかもしれないし、「労働運動の現場」においては、「思想家マルクス」より「革命指導者レーニン」の教えの方が、実践(実戦)的であるから、大塚がレーニンを優先した、ということだったのかもしれない。
だが、いずれにしろ、漫画家になりたくて田舎から出てきた少年が、大卒のエリートを捕まえて『レーニンを読むこと』を教える、などと言ったことができようはずがない。
大塚は、自分のそうした「思想遍歴」的な部分は、故意に隠していたと、そう考えるべきなのだ。
私たちが「東映動画の労働運動」のリーダーというと、高畑勲や宮崎駿の方を思い浮かべるけれど、実のところ、彼らを労働運動にオルグして、育成したのは大塚康生だったのである。
無論、大塚は「旧制中学卒の自分より、学歴エリートの彼らをリーダーに据えた方が、経営者側との交渉においても、外部に向けても、有利である(説得力がある)」という「戦略構想」があったのだろう。自分が前に出るよりも、若くて元気な彼らをリーダーにした方が、運動にプラスであり、自分は目立たない「参謀」役であるべきだ、と。
ここで勘違いしてもらっては困るのだが、私は大塚康生が「マルクス・レーニン主義者(共産主義者)」であったこと、あり続けたであろうことを、責めているのではない。また、それを隠していたことを責めているのでもない。
私の世代は、ソ連「共産主義」の歴史的実態(秘密警察と密告社会・収容所群島)を幼い頃に知らされているから、「マルクス・レーニン主義(共産主義)」に対して、なんとなく「怖い」「危ない」といった印象を持っている。
また、彼らの考えた「革命」とは、最後は日本の「資本主義」の転覆を意図するものだから、「恐ろしい全体主義(的独裁主義)」なのではないか、という印象を持ちがちなのであるが、本来の「マルクス・レーニン主義(共産主義)」というのは、そういうものではなく、文字どおり「資本家と労働者」という「資本主義」の根本構造を廃棄して「共産社会」を実現することを目指したものなのだから、当然「独裁的という意味での全体主義」ではない。「個人が全体に従属させられる、全体主義」ではなく、「一人は皆のために、皆は一人のための」働くというのが、本来の「共産主義」なのだ。

また「マルクス・レーニン主義(共産主義)」の「暴力革命論が怖い」というのも、歴史や政治の現実をまともに考えたことのない人の、「幽霊が怖い」と大差のない、単なる「印象論」だ。
歴史を顧みれば、「暴力」をいっさい伴わない「社会変革」なんて、まったくの不可能事である。
「社会構造の変革」が、多くの人に支持されたからと言って、それまでの「既得権益者である、資本家や権力者」たちが、ハイそうですかと権力を譲り渡したりしないのは、分かりきった話だし、歴史的な事実でもあろう。
無論、まれに「無血革命」的なものもあるが、それは国民の大半が革命勢力の側についたり、周辺諸国や大国が革命勢力の側についたりして、要は、革命勢力の側が、より強い「暴力」を潜在的に持ってしまったから、武力弾圧しきれないと見切って、やむなく「権力の座」を譲るにすぎないのだ。決して、納得して譲るわけでもなけれな、非暴力主義のゆえに暴力的抵抗をしなかったというわけでもないのである。
つまり、私がここで言いたのは『私は大塚康生が「マルクス・レーニン主義者(共産主義者)」であったこと、あり続けたであろうことを責めているのではない。また、それを隠していたことを責めているのでもない』ということである。
私は、どちらかと言うと、「左派」だし、明白に「反体制」だ。何かにつけて、おおむね「主流」「多数派」が嫌いであり、自分のテーマソングとして、大塚康生が作画監督を務めた作品『侍ジャイアンツ』のエンディングテーマである「サムライ番場蛮」(作詞:東京ムービー企画部)を挙げたことが、これまでに何度もあるくらいの人間なのだ。
いばった奴は きらいだぜ
そっくりかえった でっかい面の
鼻をあかしてやるのが趣味さ
(ザマァミロ!)
デッドボールの 一つや二つ
蛙の面に しょんべんだ
(ああ いい気持!)
という感じである。
そもそも、私は、主流の「現状追認」的なものが嫌いであり、そんな「薄っぺらい虚妄」が嫌いだからこそ、「デッドボール」的な評論文を書き続けてきたのであって、それは、このレビューだってまったく同じ。
誰が、天下の大塚康生をつかまえて「彼を、単なる職人だなんて、思っているやつはバカだ。大塚は、思想家でもあり、党派理論家でもあったのだ」なんてことを言ったりするだろうか? そんなこと、アニメオタクには想像もできないし、気づいたところで、無難に「自粛」してしまうのが関の山だが、恐れながら、この番場蛮、デッドボールになることを恐れて、内角ギリギリを責められないなんていう臆病者ではないのである。
では、なぜ私は、大塚康生が「思想家でもあり、党派理論家でもあった」なんてことを書くのかと言えば、それは「政治的思想信条」の問題ではなく、「アニメとは何か」という問題においても、大塚康生は「本音を隠して、思想的影響力を行使しようとしていた」とわかったからである。つまり私は、
『「動かして見せる」(※ という)アニメーションの王道』(P301)
という、この「イデオロギー(政治思想)」を相対化するために、大塚の「職人」擬態を、あえて暴いたのである。
このレビューをここまで読んでくださった読者の中には、私が以前に書いたレビュー「アニメーションの定義:「アニメ大国の神様たち」による定義の問題点」を読んでくださった方もいると思うが、私がこのレビューで「仮想敵」としたのは、大塚がここで言っているような、『「動かして見せる」(※ という)アニメーションの王道』という「イデオロギー」である。
私が、大塚が大嫌いな「止め絵」を多用したアニメ演出家・出崎統のファンであり、その作品を、天才的な画力で支えた杉野昭夫のファンだったから、特に感じるのかも知れないが、『「動かして見せる」(※ という)アニメーションの王道』だなどという強調の仕方は、あきらかに、出崎統のような演出法を否定するようなものだし、一枚絵が得意な杉野昭夫のようなアニメーターを「見下す」物言いだと言えよう。
実際、私が前記のレビュー「アニメーションの定義」を書いたのも、それはそのレビューを書くきっかけとなった、三沢典丈著『アニメ大国の神様たち 時代を築いたアニメ人 インタビューズ』の中に、故・出崎統に関する、次のような記述があったからだ。
『出崎さんは取材時、手塚さんのアニメ制作手法や自身の作品に辛辣な評価をしたとして、東映動画出身の宮崎駿さんに対する憤りを隠さず、その作品を「見ない」とまで言い切っていた。』

実際、宮崎駿は「動かしたいアニメーター」であるし、だからこそ大塚康生の影響をストレートに受けて『「動かして見せる」(※ という)アニメーションの王道』という考え方に、強く共感したのだろう。私のこの「宮崎駿観」については、どこからも異論は出ないと思う(ただし、宮崎作品も、動きが面白かった初期作品に比べると、近年の作品は、さほど動かす必要のないところまで、資本の潤沢さに飽かせて、贅沢に動かしている作品、なのではないだろうか)。

で、私は、拙論「アニメーションの定義」の中で、宮崎駿を標的に据えた。
と言うのも、高畑勲の作品は「細やかな演技」として必要な「動かす」ことへのこだわりはあっても、宮崎駿の初期作品のように、空を駆け地を走り回るような作品を作る人ではなかった(むしろ、そうしたものを「没入型」作品と見て、否定的だった)からであり、そして、もうひとりの「同志」である大塚康生の方は、「職人」さんとして、「自分の信念や好み」を、その範囲内において語っているだけの人だろうから、敵視するまでもないと、そう思っていたからである。
だから私は『「動かして見せる」(※ という)アニメーションの王道』という「イデオロギー」は、主として宮崎駿のものであると考えていたのだが、本書を読むことで、じつはその奥に、大塚康生が控えていたということに、遅まきながら、やっと気づくことができたのだ。
○ ○ ○
『「動かして見せる」(※ という)アニメーション』は、決しての『王道』などではない、という事実は、前記の拙稿「アニメーションの定義」で詳しく論じておいたから、ここでそれを繰り返すことはしないが、ごく大雑把に言えば、次のようになる。
「アニメーション(動画)」とは、本来「技法」であって、それだけで存在するもの(作品)ではあり得ない。つまり「アニメーション」は「独立したジャンル」ではなく、いろんな「作品」の中に取り入れられる「技法」でしかないから、「アニメーション作品(アニメ)」にも、現に「いろいろある」のだし、「いろいろ」でしか、あり得ないのだ。
「アニメーションという技法」は、主に「映像表現作品」に用いられる「ひとつの技法」であって、それが無くても「映像作品」は作れるし、その技法を取り入れるにしても、その度合いは、作家の個性や判断によって、いろいろとならざるを得ない。
まして、拙稿「アニメーションの定義」でも書いたとおり、そこそこの「尺(長さ)」を持つ作品は、それゆえに「よく動いている」だけでは、優れた作品にはならず、「よく動く」というのは、「必要な時に、必要な分だけ、必要なかたちで動く」というものであって、ずーっと動いていれば「良い作品」になる、というわけではなくなってしまう。
一一だからこそ、一部の「短編」は別にして、一般的であり主流でもある「テレビアニメ」や「アニメ映画(長編アニメーション)」には、「ストーリー性」や「ドラマ性」が与えられるのであり、これは、本書に収録された高畑勲の論文「60年代頃の東映動画が日本のアニメーションにもたらしたもの」でも指摘されているとおりである。
つまり、それなりの長さを持つ「テレビアニメ」や「アニメ映画」の場合は、「技法としてのアニメーション」とは直接関係のない、「ストーリー性」や「ドラマ性」といったものまでが、世間の求めに応じて導入される。
そしてその結果、「スポーツ選手のような運動能力(動き回り走り回る)」が優れているだけでは「もたない」ということになって、例えば「高倉健の、背中の演技」みたいなものも、おのずと必要となってくるのである。そこでは「やたらに動かない」ことにこそ、「積極的な価値」があったりもするのだ。

したがって、大塚康生の言う『「動かして見せる」(※ という)アニメーション』は、決して『王道』ではない。
そもそも「アニメーション作品」には(ディズニーも「王道」ではあり得ないように)『王道』など「存在しない」のであり、大塚のこの「意見」は、所詮、大塚個人の「美意識と経歴」から出た、個人的な「イデオロギー」でしかないのである。
私はかつて「ミステリー小説(推理小説)」の世界において、「本格ミステリこそ、ミステリーの王道」と書いた、ミステリ作家・山口雅也を批判した。
山口は、本格ミステリ作家であるクリスティアナ・ブランドの作品集の「解説」の中で、そんなことを書いたのであり、そこには、そこで語られるべき作家(ブランド)も、語る自分も、その作品集を読む読者も、みんな「本格ミステリ」愛好家だろうという「甘え」があったから、こういう不用意な書き方をしたのだろうが、「物書き」は、自分の言葉に責任を持たなければならないし、責任を負わされる覚悟を持たなければならない。「そのつもりではなかった」では、済まされないのである。
私が、山口のこの言葉を問題にした理由は「じゃあ、本格ミステリ以外のミステリ作品、例えば、ハードボイルドや冒険小説は、ミステリにおいては、傍流なのか?」という、意地悪な「批判的問いかけ」の言葉に尽きていよう。
当時は「新本格ミステリ」ブームの真っ只中であり、山口はその中でもトップクラスの人気作家であったから、言うなれば「わが世の春」の栄華を極めており、その意味で「調子に乗っていた」のであろう。だから、周囲への配慮を欠いて、脇の甘い「本音」を漏らしたのである。
もちろん「ミステリー小説」の起源を、一般に言われる、E・A・ポーの「モルグ街の殺人」だと考えれば、「ミステリー小説の(原初的)本質は、本格ミステリ的な、論理性にこそある」と、そう言えるだろうし、「ミステリ史」の興味があるような人は、一般に、そのように考えているだろう。しかし、これは本来、議論が本末転倒しているのだ。
「ミステリは「モルグ街の殺人」に始まったから、論理性を重視する本格ミステリこそが王道だ」という議論になっているのだが、この議論は、じつは「本格ミステリの好きな人が、その起源を探した結果、ポーに至った」ということでしかない。

言うまでもないことだが、「ミステリー小説」というのは、ポーが「突然、独りで生み出した」ものではななく、それまでの「文学史」的変遷の中で、たまたまポーにおいて、「今から見れば、典型的なかたちの作品」として生まれたにすぎない。
言い換えれば、例えば「冒険小説」の視点から「ミステリー小説の起源」を探るならば、当然のこと、ポーなどより、はるか昔に遡ることになるのは、必定なのだある。
したがって、「ミステリー小説」というのは「便宜的な、小説ジャンル概念」であっても、それに「実態」はないし、その「本質」なども当然無い。
あるのは、いろいろな傾向を含み持ちつつ、大雑把には存する「傾向性」でしかない。
だから、ある作品を「ミステリー作品」だと認める人がいれば、「あんなもの、ミステリー小説じゃない」と言う人もいるのであり、どっちの意見も、ある程度は正しく、ある程度は間違ったものでしかない。そもそも「存在しない」ものは「定義できない」し、その「本質」を確定することもできない。
一一これは「分かりきった話」なのだが、こんな「分かりきったこと」もわからないような「頭の悪い人間」が、「多数意見」や「個人的な好み」にしたがって、やれ「あれはアニメじゃない。これこそがアニメだ」などと言うのである。
だが、宮崎駿は微妙だが、少なくとも高畑勲と大塚康生は、「アニメーション(作品というもの)に、確定的な本質はない」ということに気づいていたはずだ。
だから、高畑勲は、先輩である大塚康生や、盟友である宮崎駿を賞揚しつつも、「アニメとは、こうでなければいけない」といった言い方は慎重に避けて、自分はどのような作品を作りたいのかを語るだけで、決して自分の作品が「アニメの王道だ」などとは主張しないのだ。
あくまでも、望まれて「いろいろな作品」があるけれども、私が作りたいのは、こういうものだ、としか(賢明にも)言わない。「浅い(安直な)」作品はあっても、方向性としてアプリオリに「間違っている」作品がある、などと迂闊に断じたりはしないのである。

ところが、大塚康生の場合は違う。
大塚は明確に『「動かして見せる」(※ という)アニメーション』こそが『王道』だと主張し続けていたわけだが、その断言の印象が、意外に薄いのは、彼が自身を「動画の職人」であると自己規定して、あたかも「主義主張など語らない」かのような顔をしていたからであり、私たちが、それにまんまと騙されていたからである。
大塚康生は、なんとなく「素朴な職人」という印象を与えていたけれども、最初に指摘したように、彼はそんなヤワなものではない。大塚は、明確に「アニメとは、動かなくてはならない(動きの少ないアニメは、邪道である)」という「イデオロギー」を、一貫して主張し続け、多くの「アニメーター(動画の職人)」たちの支持を取りつけてきた。
しかし、大塚のうまいところ、政治的に巧みなところは、そうした「イデオロギー」を、ほとんど「政治臭」をさせないかたちで訴えたところであろう。そして、そのための武器が、「職人」という名称の「仮面」である。
私たちは一般に、「職人」というと「無口で(理屈は言わず)、自分の仕事を黙々とこなしている人」という印象を持っており、これがしばしば「自己主張をしない人」とか「自己主張の無い人」だなどといった「誤ったイメージ」で捉えがちだ。
だが、「職人」というのは、得てして「強固に自己を主張する人」であり「自分の考えを曲げない人」であり「信念の人」なのだ。つまり、一般には「思想」とか「哲学」などとは呼ばれないものの、「自身の世界理解としての信念」を強固に持った人たちなのである。
そして、大塚康生の「職人」とは、そういう「信念の人」ということであって、「ノンポリ」とは真逆な「イデオロギーの人」だということなのである。
無論それは、単に「政治思想」のこと(だけ)ではなく、「アニメと何か」という「哲学的な問い」に対しても、そこへ自身の「イデオロギー」を持ち込んで、『「動かして見せる」(※ という)アニメーション』こそが『王道』だと、確信犯(思想犯)的に主張できる人なのだ。
高畑勲のように「客観的であろう」などとは考えずに、自分の「考え(イデオロギー)」を貫き通そうとする人、きわめて「頑固」な、その意味での「職人」気質の人なのである。
だから、彼が「動画の職人」を名乗り、自分が「職人」であることをやたらに吹聴し強調したのは、自分が、少々「原理主義的」で偏狭な「主義主張」で語ったとしても、「あの人は職人だから、自分の美意識を語っているだけで、悪気はないんだよ」と、そう解釈してもらうための「免状」として、「職人」という肩書きを、自覚的に利用した、ということなのである。
大塚は「職人的に、ただ作っている(描いているだけの)」人なのではなく、「職人的に、頑固に自分の美意識や好みを主張し、人にも認めさせようとした、自覚的な運動家」だった。
くりかえすが、私たちは、大塚康生をいう「知恵者」の朴訥そうな演技に、まんまと騙されてきたのだ。大塚康生は、決して、ジープやプラモが大好きな「動画の職人」などというような、害のない「微笑ましい」だけの人などではなかったのである。
○ ○ ○
したがって、結論的に言えば、やはり『「動かして見せる」(※ という)アニメーション』が『王道』だなんてことはなかったのだ。
それは「大塚康生のイデオロギー」であり、その賛同者の「理想」であって、「客観的な事実」でもなければ「普遍的な理想」でもなかった。
事実、そのような「イデオロギー」を振り回されたおかげで、迷惑をこうむった人や、不快な思いをさせられたり、不利益をこうむった人も、大勢いるのである。例えばそれが、組合運動にうんざりして、東映動画を去って「虫プロ」に移った人たちなどであろう。
大塚は、本書の中で、かつての「東映動画」において、組合運動をとおして勝ち得たものを、「今は失われた理想」のように、美しく描いて見せる。
つまり「できるかぎり、いろんな立場の人の意見を聞き、それを生かして、みんなで作品を作り上げていった」というような、「共産主義的ユートピア」の「神話」である。あるいは、「名作」と呼ばれる、『太陽の王子 ホルスの大冒険』的ビジョンだとも言えよう。

だが、すべての人が、大塚が言うようには感じていなかったからこそ、東映動画を去ったクリエーターたちも少なくなかったのだ。私たちは、その「現実」を、決して看過すべきではない。
大塚は、明らかに、自分たちの過去を「美化」している。「美化」という言葉が悪ければ、「見たいことだけを見て、自分に都合の良いところだけを書いている」と、そう言えるだろう。
その意味で、大塚の描く「過去」は、きわめて「党派」的なものであり、いかにも「共産主義」イデオロギーの優等生だった人らしいと言えるだろう。
そんな大塚にとっては「みんなのための闘い」において「団結できない人」「団結を乱す人」は、許しがたいのである。だから、先輩や、そのあと一緒に仕事をすることになる有力な友人は別にして、『「動かして見せる」(※ という)アニメーション』を『王道』だと考えないような人を、名指しはしないで、誹るのである。まるで「日本のアニメをダメにした戦犯」だと言わんばかりに。
だから、大塚の描く「人物像」を真に受けるのは、危険だ。それは、明らかに「イデオロギー」のフィルターを通したものであり、かつ冷静に「党派的損得」を計算した、戦術的な「言葉」だからである。
さも、自分は「職人」だから、「主義主張で物は言いません」みたいなフリをしているが、そうではない。「主義主張」を有効に伝えるためにこそ、あえて、高畑や宮崎を表に立て、自分は一歩下がった場所から、方向づけをしていたのと、これは同じことなのである。
したがって、私が大塚康生を批判するのだとしたら、それは、大塚の「本音を糊塗する」という、その「政治性」にあると言っていいだろう。
レーニンがそうであったように、「政治家である革命家」というのは、「信じたところをそのまま語る」ことが大切なのではなく、「結果としての勝利」が大切なのだ。そのためだったら、「嘘」だってつく。それが「政治家」であり「革命家」なのである。
そして彼らは、「理想のための犠牲」は、止むを得ないものと考える。すべての人が生き残ることができないのならば、より「正しい方」である我々が、特に「民衆のための前衛」である我々が生き残るべきだし、そのためには多少の「方便」や「犠牲」も許される一一と、そう考えるのが「政治的な人間」だ。
で、私は、こういったものが「嫌い」なのだ。理屈としては、そういう「立場(結果主義)」も認めないではないのだけれど、生理的にはそういう、理想のために「策を弄する」「本音と建前を使い分ける」みたいなことが嫌いなのだ。
大塚は本書の中で、『侍ジャイアンツ』の演出をめぐって、監督の長浜忠夫とぶつかって、作品から距離をおいたことを紹介している。
主人公の蛮が、川上監督と面と向き合って、お互いに相手の目を見つめながら「俺は、巨人軍の腹破りをしてやる」などと真っ向勝負のセリフを吐く(青い炎が燃え上がる)といった長浜演出が、どうにも大仰で芝居がかっており嘘っぽくて、そんな芝居は描けない、ということだったのであろう。
正確には、このシーンとは特定できないが、こうした、何かにつけてわざとらしい、熱血の俺様(一匹狼)ぶりが、共産主義的感性を持つ者としては、受け入れ難かったのだろう。
アニメマニアなら知ってのとおり、長浜忠夫という人は「芝居がかった演技」を要求する人だった。
元の人形劇にしろ、アニメにしろ、それらは「死物」であるからこそ、それに命を吹き込むためには、現実にはオーバーすぎるくらいの演技や演出でちょうど良い。そうした力と熱が、観る者を作品世界に引き込むんだ、というような考え方であった。
つまり、「誇張」が必要と考え、またそうした「過剰さ」が好きな、下町江戸っ子的(火事と喧嘩は江戸の華的)人情家の、熱い人だった。
そのため、「声優」の演技に対しては注文も多ければ厳しくもあった人で、作品途中で、役を降された声優が何人もいたはずで、そうした声優の演技というのは、今でいう「フラットでナチュラル」なものだったのである。

このように、長浜の演出観とは、「歌舞伎」的なものだった。顔に隈取りをし、派手な衣装を着て、殊更に誇張された「見得を切る」。
それでこそ、観客は「娯楽作品」としての「歌舞伎」を楽しむことが出来たのであり、そんな長浜からすれば、「新劇」的な「リアリズム」は、作り手の、独り善がりのイデオロギー(マスターベーション)だと、そう感じられたのであろう。
だとすれば、大塚康生が長浜忠夫とぶつかったのは、当然である。両者の「アニメ」観は、水と油ほどに違っていたのだから、両者は、ぶつかるべくしてぶつかったのだ。
つまり、長浜忠夫が、大衆娯楽としての「歌舞伎」派だとすれば、大塚康生や高畑勲は、明らかに「新劇」的リアリズムの立場にあった。そして「新劇」にも、左翼的なイデオロギーの影が差していたことを、私たちは思い出すべきであろう。
しかし私は、「新劇」が「左翼的」であったことを批判しているのではない。
「政治」であれ、アニメのような「芸術」表現であれ、その人が選ぶ「立場」には、一貫した「好み」が、否応なく反映されるという事実を、私は指摘したいのだ。
つまり、長浜が「歌舞伎」派で、大衆向けの「誇張表現」を好んだのに対し、大塚や高畑が「新劇」的なリアリズムを好んだのは、たぶん、長浜が「大衆娯楽的資本主義」を否定しなかったのに対し、大塚や高畑は、そうした価値観を「大衆の知性を眠り込ませる、権力の道具」的なものとして否定的に見ていたということだろう。
「大衆は、決してバカではない。正しく啓蒙されれば、大衆は皆とともに助け合っていく、階級なき社会の正しさを理解できるはずだ。しかし、権力者は、大衆の覚醒を恐れるが故に、甘ったるい飴を与え、刺激的なサーカスを与えることで、大衆をその幻想の中に眠りこませようとする。だから、作家たる者(前衛党である我々は)、大衆に益し、その覚醒を促す作品を作るべきであろう。もちろん、それは、この資本主義社会の中では、決して容易なことではない。端的に、興行的に難しいからだ。しかし、我々は、泥絵の具で描いたような派手派手しい作品ではなく、作家的良心に従って、人間と社会の真実を描いた、リアリズムを基本とした作品を作らなくてはならない。大衆が、本物の美を見出す力を持っていることを信じて、そのための作品を作らなくてはならないのだ」一一と、おおよそ、こういうふうな考え方なのであろう。これが間違っているとは、私も思わない。
しかし、そうした観点から批判されたも同然の長浜忠夫は、どのようなことを考えていたのだろうか。
これも私の長浜理解だが、彼は「人形劇」時代から一貫して、「子どもでも楽しめるもの」「学のない庶民でも共感できるもの」を作ろうとしていたのではないだろうか。
それこそが「本物」であり、自分が見ている子供や大人こそが、本物の「庶民大衆」だと、そう信じていたから、彼はそうした人たちの「誰もが楽しめる作品」を作ろうとしたのではないか。
一部の「知的エリート」や「政治意識の高い人たち」のための作品ではなく、そうした「リアルな庶民」のための作品を作ろうと、その過剰なまでの情熱を注ぎ込み、それでしばしば人ともぶつかったのである(長浜が『ベルサイユのばら』で、人気女優の田島令子とぶつかって、監督を下されたのは周知のとおりである)。
長浜は『ど根性ガエル』だとか『侍ジャイアンツ』といった作品だけではなく、例えば、例えば『未来ロボ ダルタニアス』といったロボットアニメにおいてさえ、子供と庶民を描くのが好きな人だった。
だから、そんな彼は、いかにも「庶民」らしく、悟ったような顔をしている「エリート」が嫌いだった。「我々こそが、王道であり正統だ」などと臆面もなく言えるような人間が、嫌いだった。だからこそ、そんな相手に対しては、馬場蛮のように「威張った奴は嫌いだぜ」とばかりに、デッドボールも辞さないような「熱血漢」であった。つまり、「ロマン派」だったのである。だからこそ、大塚の「左翼リアリズム」など、鼻もひっ掛けなかったのではないだろうか。


もちろん、「理想」も大切だし「リアリズム」も大切だというのは、論を待たない。
しかし、人間は、そう単純なものではないし、なにしろ「ひと色」ではない。良い悪い以前に、人間は「色々」であるから、ひとつの「理想」で満足しろと言われても、「やなこった」と、ひとまず逆らって見せることが好きな人間だっているのである。
しかしながら、そういう「へそ曲がり」がいるからこそ、この社会は「ひと色」の染まってしまう「全体主義」からも、ようよう逃れることもできるのだということを忘れてはいけない。
たしかに「(動くべきところで)動かないアニメ(電気紙芝居)」よりは、「(動くべきところで)動くアニメ」の方が、面白いに決まっている。
しかしそれは、「不真面目よりは真面目の方が、良いに決まっている」とか「グータラ者よりは勤勉な人の方が、良いに決まっている」といったことと同じで、「理屈としては」そのとおりだけれど、しかし、それでも現実には、必ず「不真面目な人」や「グータラ者」は生まれてくるのだし、そんな彼らにも、生きる資格を認め、生きる場所を保証してこその、「正義」なのだ。
ユダヤ人と知的障害者と同性愛者は「社会を腐らせる元凶(悪)」でしかないから、排除抹殺すべきである、といった「純粋思考の正義(健康の帝国主義)」は、何よりも危険だということを、私たちは歴史に学ぶべきなのである。
そして、これは「アニメ」だって、まったく同じなのだ。
『「動かして見せる」(※ という)アニメーションの王道』という言葉には、あきらかに「それ以外は、邪道」であり「アニメを腐らせる、資本主義的妥協の産物」という非難が込められている。
しかし、大塚自身、それと妥協しないことには生きてこれなかったのだし、なんだかんだとうるさい注文をつけてみたところで、結局最後は「お上から勲章をもらった人」なのだ。
「作家ではなく、職人としてもらった」などと威張ってみたところで、「お上=お国」は、大塚の(業界的な)権威を利用したかっただけだし、看板をちょっと掛け変えるだけで、大塚に勲章を与えることも出来たのである。
それは、「軍国主義日本」から「民主主義国日本」へと「看板」は架け替えても、アメリカの実質的支配下においても、結局は、戦時の権力者たちが、戦後も日本の主導権を握ったというのは、周知の事実。
だから、厳格にいうならば、大塚は「勲章」などもらうべきではなかった。本物の「職人」なら、「勲章」など欲しがりはしない。「勲章」なんてものは、その人の内実の保証になどならないというのは、「革命のために、権力に抗して死んでいった、無名の人々」の存在が、何よりもそれを証明しているのである。大塚だって、レーニンやスターリンのようなかたちで、死後まで崇拝されたいと考えたわけではあるまい。
だから、アニメも「いろいろ」であるべきだ。いや、現に「いろいろ」でしかありえないのだ。
その現実を、「理想主義的純血主義」が否定した時、また歴史の悲劇が繰り返されるのだということを、私たちは決して忘れてはならない。
「動くアニメ」は「面白い」。しかし、アニメは動く「べき」もの、などではない。
むやみに動いてもいいし、むやみに動かなくてもいい。結果として、それがその作家の「最良の部分」を表すために必要なものなのであれば、それでいいし、そうあるべきなのだ。
私たちは、「歌舞伎」的なものも否定すべきではないし、「高倉健」的な背中の演技も否定すべきではない。無論、高畑勲のような「リアリズムの思想」も、宮崎駿的な「活劇的ロマン」も否定すべきではない。
結論として言えるのは、「アニメーションに、王道など無い」ということだ。
私たちは「イデオロギーのための個人」ではなく、「(真に)個人のためのイデオロギー」を持つべきなのである。
(2023年1月30日)
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
