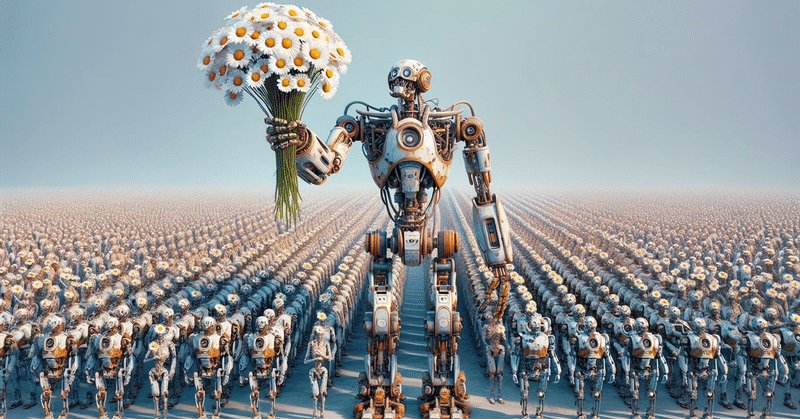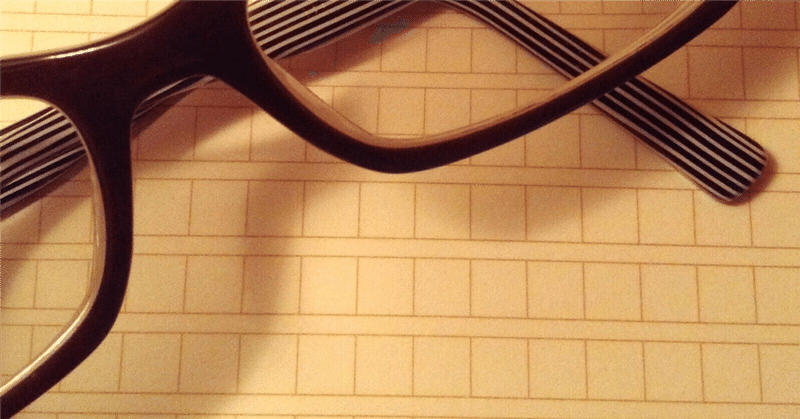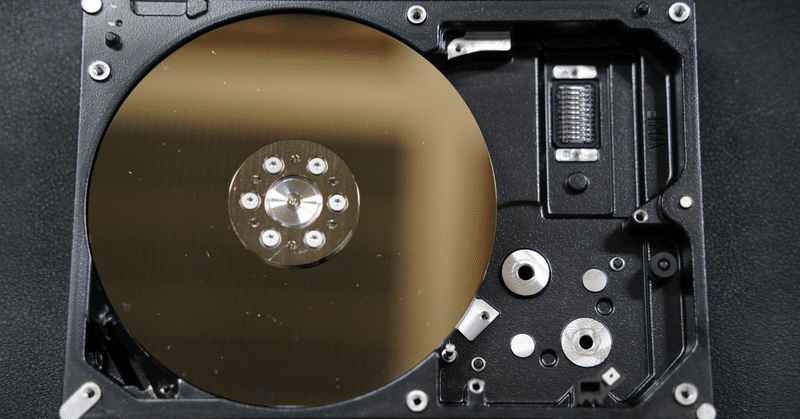#推薦図書
オリバー・バークマン『限りある時間の使い方』読んだ
大ベストセラーである。
原題は4000 weeksである。つまりアメリカ人の平均寿命である80歳弱くらいで死ぬとしたら、人生は4000週間しかないって意味だ。
だからこの邦題は間違いではないが、時間管理術の本かと誤解する人も多いだろう。私も誤解した。
著者はかつて生産性に心臓を捧げた民であったらしい。それが1周回って、そんなことに意味はないと気が付いたとか、、、
だから時間管理とかタスク管
安川康介『科学的根拠に基づく最高の勉強法』読んだ
今月の意識高い一冊シリーズ。
けっこうよかった。今どきの意識高い系らしく、きっちり参考文献がつけてある。また重要な論文については、細かく解説してあるので説得力がめちゃ高い。
著者の安川康介氏はアメリカで内科医してるお方で、ああ慶応のお医者さんだなあって感じ。こういうスマートさは東大京大のお医者さんにはあんまりないんだよね。うまく説明できないけど。
まあそれはよいとして。
まず第1章では、科
為末大『心のブレーキを外す。』読んだ
Twitterとかで為末大さんて面白い人だなあと思っていたが、今井むつみ氏との対談を読んでさらに興味が湧いてきた。
というわけで一番さらっと読めそうなのを図書館で借りてきたのだ。
タイトルのとおり、自分で勝手に決めた制約をいかに越えていくかというお話である。
為末さんは、自分に揺さぶりをかけると表現していた。例えば、室伏広治氏はベンチプレスをするときに砂袋のようなものをバーベルにぶら下げてい
猫山課長『銀行マンの凄すぎる掟』読んだ
著名なnoterである猫山課長さんが本を出されたので買った。
猫山課長さんは週2ペースでクオリティの高い記事をアップされていて、いつも楽しく読ませていただいている。課金していいレベルなのだが、ただで読める。ありがたいことだ。
だから本を一冊買うくらい、どうということはないのである。
電子書籍は来月でるみたい。
著者は20年以上地方銀行に勤務し、支店長などを勤めたのち現在は本部でコンサルティ
アレックス・バナヤン『サードドア 精神的資産のふやし方』読んだ
けんすうさんの本で強く推奨されていた『サードドア』読んだ。
たしかにめちゃくちゃおもろかった。
大学に入ったばかりですでに学業にやる気がでなくなった主人公は、次世代をインスパイアするために著名人にインタビューしようと決心する。
そのミッションにはほとんど共感できない。著名人に会いまくることがなんで若い人たちに活気を与えることにあるのかよくわからない。
ただその著名人というのがビル・ゲイツ、
今井むつみ『学ぶとは何か』読んだ
引き続き今井むつみ氏の著書を紹介していく。
ちなみにKindle Unlimitedだよ。
内容はおおむねタイトルのとおり。
学ぶためには、まず知識を身に着けなければいけないということで、記憶力がよいとはいかなる事態であるかから始まる。
記憶力の良さを4つの型に分類する;瞬間記憶力型、記憶力世界選手権チャンピオン型、シャーロック・ホームズ型、将棋プロ棋士型。
著者は明言はしていないが将棋
鈴木祐『YOUR TIME』読んだ
また意識高いシリーズ。これもかなり良い。さる超有名なインフルエンサーがおすすめしており、そのときたまたまAudible版が無料だったので聴いてみたのだ。
そしたら非常に良かったので電子書籍を購入したというわけである。
本書はタイトルからもわかるとおり時間管理を主題としている。しかし、世に流布する時間術はほとんど無効であるという不都合な事実からお話は始まるのだ。
著者は文献マニアであり、時間術
ジョシュア・フォア『ごく平凡な記憶力の私が1年で全米記憶力チャンピオンになれた理由』読んだ
アンダース・エリクソンの本で紹介されていたジョシュア・フォアの本を読んだ。
フォアはナショジオなどに記事を投稿しているジャーナリストである。全米記憶力選手権の取材したのを契機に記憶に関心を持ち、1年後の同大会で優勝するまでを描いたもの。
なお、アメリカの記憶力選手権のレベルはとうていヨーロッパには及ばないとのこと。
著者はジャーナリストだから、グランドマスターやアンダース・エリクソンの指導のも
ドミニク・オブライエン『記憶に自信のなかった私が世界記憶力選手権で8回優勝した最強のテクニック』読んだ
記憶術についてもう少し。
今度は世界チャンピオンのドミニク・オブライエン氏の本を読んだ。
書いてあることは基本的に池田義博氏のものと同じだが、より具体的なのでこの人たちがいかに傑出しているかがよくわかる。
方法論としては場所法とかジャーニーメソッドとか呼ばれる、場所に紐づけて覚えていく方法がメインである。
だから空間把握能力も高まると思われる。
それから人物と関連づける方法。こちらは一人の
植田文也『エコロジカル・アプローチ「教える」と「学ぶ」の価値観が劇的に変わる新しい運動学習の理論と実践』読んだ
Footballistaなどの意識高い系のサッカー雑誌にエコロジカルアプローチという言葉がよく登場するが、SDG的なものとは関係ない。
周囲の環境とのインタラクションから選手が自発的にスキルを習得するのがエコロジカルアプローチである。
本書は、Footballistaによく寄稿している植田文也氏による解説である。
エコロジカルアプローチから導き出されるトレーニング方法として制約主導トレーニン