
小川哲 『ユートロニカのこちら側』 : 〈後期クイーン的問題〉の作家・小川哲のユートロニカ
書評:小川哲『ユートロニカのこちら側』(ハヤカワ文庫)
小川哲の作品を読むのは、短編集『嘘と正典』に続いてのまだ2作目なのだが、小川の関連したものとして、リモート会議本『世界SF作家会議』での発言と、アンソロジー『異常論文』の収録短編小説「SF作家の倒し方」を読み、樋口恭介・東浩紀との鼎談「『異常論文』から考える批評の可能性 ──SF作家、哲学と遭遇する」」を視聴してはいる。

予備知識なしに、最初に小川の短編集『嘘と聖典』に接した私は、この作品集のレビューを「小川SFにおける〈静かな諦観と叙情性〉」と題して、おおむね肯定的に評価した。
しかし、その後に接した、『世界SF作家会議』、『異常論文』所収短編「SF作家の倒し方」、鼎談「『異常論文』から考える批評の可能性」については、いずれも、あまり良い印象は受けなかった。
こうした現在の視点から、デビュー作長編である本作『ユートロニカのこちら側』を読み、併せて本書刊行時のインタビュー記事を読んでみると、奇妙な振れ幅を持つ小川の「個性」のようなものを、ある程度は理解することができたように思えた。
その個性とは「どうにもならない世界ならば、せめてこちらがコントロールする側に立とう」という「消極的な意志」である。
本稿タイトルの「〈後期クイーン的問題〉の作家」とは、そういう意味だ。

○ ○ ○
『巨大情報企業による実験都市アガスティアリゾート。その街では個人情報――視覚や聴覚、位置情報等全て――を提供して得られる報酬で、平均以上の豊かな生活が保証される。しかし、誰もが羨む彼岸の理想郷から零れ落ちる人々もいた……。苦しみの此岸をさまよい、自由を求める男女が交錯する6つの物語。第3回ハヤカワSFコンテスト〈大賞〉受賞作、約束された未来の超克を謳うポスト・ディストピア文学。』(カバー裏の内容紹介)
平たく言ってしまえば、作中の「アガスティアリゾート」とは、個人情報を売る見返りとして「生活上の便益と安心」が保証された実験都市、だと言えるだろう。
だが、これはもう「未来」の話ではなく、中国などではかなり進んでいる「現実」の、半歩先でしかない。
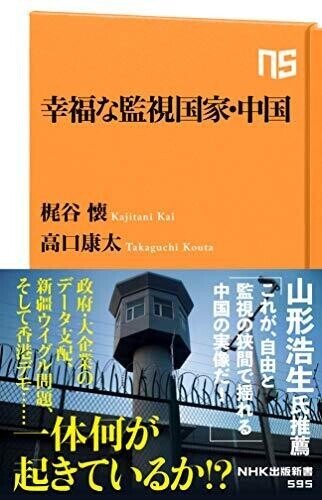
本作単行本の刊行は2015年だが、2019年に刊行された、梶谷懐、高口康太『幸福な監視国家・中国』(NHK出版新書)について、私はレビューで、次のように書いている。
『2019年8月刊行の本書は、今も中国で着々と進んでいる「監視国家」化を紹介して、それがジョージ・オーウェル『1984』流の「真っ暗なディストピア」という「紋切り型」ではない、という「事実」を指摘した上で、さらにそれが「独裁国家・中国」特有の問題ではなく、日本を含むあらゆる国に関わる、普遍的な「テクノロジーと統治」の問題だということを伝えている。』
そして、本作『ユートロニカのこちら側』の肝となる部分である「下から望んで管理下に入る、ボトムアップのディストピア」という側面について、次のように論じている。
『中国における「監視社会」の問題は、端的に言えば「良い面もある」という点にある。
「良い面もある」からこそ、危険であり、人ごとではないのだ。
IT技術や人工知能などの進歩によって、私たちの社会はとても便利になっている。これは日本だけの話ではなくて、世界のどこでも基本的には同じだし、中国でも同じなのだ。中国は、この「便利さ」を「餌」として、「監視社会」化を推し進めているのである。
例えば、このレビューだって、ネットがあるから多くの人に読んでもらえる。ネットが普及する以前だったら、アマチュアが文章を書いて、それを人に読んでもらおうと思えば、印刷して編冊して、手配りしたり、郵送したりしなければならず、手間と費用がとてもかかった。ところが今は、書いてSNSにアップすれば、それで不特定多数の人に読んでもらえる。
だが、多くの「便利」には、代償が付きものだ。ネットやSNSの利用には、登録が必要であり、そこで個人情報の提供が求められる。また、情報発信すること自体が、情報の提供にもなっている。「私はこんな人間だ」「こんなものを買っている」「あそこへ行った。誰それと会った」などなど。
単なるポイントカードでも、登録時に情報提供が求められるし、キャッシュカードやクレジットカード、最近流行りの「なんとかペイ」とかいったものも、みんなそうだ。個人情報を提供し、購買行動などの個人情報を提供し続けることで、便利なサービスを受けているのである。
そして、中国の「監視社会」というのも、基本的にはこれと同じである。
個人情報を提供すれば、便利なサービスが受けられる。個人情報を提供したところで、ことさら「反社会的」あるいは「反国家的」を言動をしなければ、不利益を被ることはない。つまり、普通の人にとっては、「監視国家」化は、サービスの充実という点において、便利なのである。だから、多くの人は進んで情報提供して、その監視下であり庇護下に入っていくのだ。
つまり、こうした点においては、すでに中国も日本もアメリカもないのであり、今の中国の姿は、近い将来の日本の姿かもしれない。だから、よくよく注目し、考えなくてはならない。
もちろん、日本と中国の違いはある。著者が指摘するとおり、中国特有の世界観が、こうした「上からの見えない管理」を、世界に先駆けて徹底させたという部分もある。
また、著者はなにも、中国と日本を一緒くたにしているわけではないし、こうして進化した「監視統制」技術が、新疆ウイグル地区における非人道的な差別政策に悪用されている事実も、その非道さも十二分に承知しているし、それを非難してもいる。
しかしそれは、日本の、あるいは世界の国々の、将来的な「似姿」かもしれないのだ(ネトウヨならきっと、外国人区別(差別)に使え、と言うだろう)。
中国そっくりそのままではなくても、「技術的な進歩」の問題と「人間の(易きに流れる)性向」の問題として、その「似姿」になる可能性は否定できないのである。』
まさに「アガスティアリゾート」こそが、それではないだろうか。

しかし、そうした「下から望んで管理下に入る、ボトムアップのディストピア」というビジョンに対して、小川哲は悲観的に批判的であると同時に、一種の「憧れ」に近いものをにじませている。
まず「悲観的に批判的」な側面だが、これは私が『幸福な監視国家・中国』のレビューで指摘した、人々の「易きに流れる」傾向に対してだ。
小川は、2015年11月24日の「第3回SFコンテスト受賞者インタビュウ」で、インタビュアーの質問に、次のように答えている(https://cakes.mu/posts/11547)。
『監視カメラもそうですが、今年二月の川崎市中一男子殺害事件で犯人が捕まるきっかけがLINEだったことにはびっくりしました。LINE上での私的なやりとりを、会社が情報提供しているわけですよね。そういう規約書にOKを出して使っている。LINE社は日本中の片思いや不倫を把握している可能性があるわけで、でもだから使うのをやめられるかというとそうもいかない。いくら監視が嫌だと言っていても便利さの前に負けてしまう。そういうリアリティというか、諦観はあります。』
『冷戦後の、そして僕の世代のリアリティだと思います。独裁者や独裁国家を主題にしてディストピア小説を描こうとすると、大掛かりな仕掛けが必要になる。ジョージ・オーウェル的ではなく、トマス・モア的に、理想を追求した結果発生するディストピアという構図の方が理解がしやすい。みんなで理想を追求するとその過程で価値観の更新がおこり、その更新についていけなかった人にとってはディストピアになってしまう。作中にも書きましたが、独裁者がいるのではなくて、民意自体がユートピアにもディストピアにもなるんだと思います。これからの文学や思想は、民意とも闘う必要が出てくるかもしれません。』
このように、いちおうは『民意とも闘う必要が出てくるかもしれません。』と言いながらも、本音としての『諦観』が強く、『その更新についていけなかった人』たちのように、反時代的に『民意』と戦う、つもりはなさそうである。
インタビュアーが重ねて『現実世界でもこのような民意の暴走はありえるように思います。』と水を向けると、小川は、
『ありえるでしょうね。ただ、僕の考えるSF読者は現状への批判的な視線をもっているはずなので、一方向にがーっと流れていく人たちがいたときに、その流れを相対化してみることができるんじゃないかと思っています。』
と答えているが、要は、SFにも、そして作家である自分にも、そうした流れを『相対化してみること』しかできないであろうという『諦観』が、『僕(※ 小川)の考える(※ 呑気な)SF読者』とは違って、小川自身には抜きがたくある、ということだ。
実際、最相葉月『星新一 一〇〇一話をつくった人』のレビューでも指摘したとおり、日本のSF界自体が、一種の「アガスティアリゾート」であり、SF作家はもちろん、SFファンだって、ほぼ全員がそこでの安住を望んで、反抗など思いもよらない、本質的な批評性を欠いた人たちだからである。
では、一方で小川が「アガスティアリゾート」的な「便利な監視社会」に感じている、「憧れ」的なものとは何か。
それは、「アガスティアリゾート」の「ユートロニカ」というイメージにある。
小川は、インタビュアーの『タイトルにもなっている「ユートロニカ」という言葉です。作中では「永遠の静寂」という言葉が当てられてもいます。これは造語でしょうか。』という質問に答えて、次のように解説している。
『ユートピアとエレクトロニカの造語です。僕はエレクトロニカという音楽のジャンルがすごく好きで、これは楽器の使い方やビートの刻み方で規定されるジャンルではなく、基本的に叙情的なテーマが重視される電子音楽なんですね。そのイメージが本作に合っているのではないか、と。タイトルは最初から決めていたわけではなく、最後にどうしようかと考えたときに、思いつきました。』
つまり「ユートロニカ」というのは、小川にとっては、必ずしも否定的な意味を持つ言葉ではないのだ。いや、むしろ一種の「憧れ」を込めた言葉だと言えるだろう。
要は、不安定でガチャガチャした「人間世界」ではなく、機械的に調節され調律された「静謐な世界」。人間の度し難い「欲望や業」によって、騒々しく振り回されることのない世界。言ってしまえば、一種の「涅槃・寂光土」的な世界。一一小川は、そんな「静謐な世界」に「憧れている」のであり、裏を返せば、小川は「人間的な、ドロドロガチャガチャした世界」に、すっかりウンザリしており、その意味で「人間世界」に望ましい未来などないと、そういう『諦観』を持っているのである。
しかし、小川のこうした『諦観』は、どこから来たものなのだろうか。
私は、そのヒントを、小川の、樋口恭介・東浩紀との鼎談から得ることができたように思う。

小川はそこで、(政治的立場を云々されるのが嫌だからと)詳しくは語らなかったが、両親が「共産党員」であったと明かしている(あるいは、支持者であったか)。
そして、前記の「第3回SFコンテスト受賞者インタビュウ」では、その両親を、次のように紹介している。
『僕の父親が海外小説──特にSFとミステリのオタクで、家に父の本が大量にあったんです。僕の部屋にもその本棚が置かれていて、することがないと父の本を読む習慣がありました。もともと《ズッコケ三人組》や宗田理といったものしか読んでいなかったのですが、中学生のとき、事前情報も何もなくいきなり筒井康隆の『農協月へ行く』を手にしたのが最初だと思います。他にも小松左京の『日本沈没』を知る前に「日本以外全部沈没」を読んで「日本以外、全部沈没したんだ」と素直に受け取ってしまったり(笑)。それとレイ・ブラッドベリやフレドリック・ブラウンはこのころ知りましたね。
SFの次はミステリ小説でした。母親がミステリ専門の読書家で、母の読み終わった宮部みゆきや東野圭吾を読むようになりました。SFはそれから数年くらいは手をつけずに、古典に行ってしまって。戻ってきたのが、大学院試験の勉強をしていたとき。気分転換でテッド・チャンやグレッグ・イーガンを読みまして、それ以来ほとんどSFしか読んでいないという状態です。
(中略)
僕は文芸サークルに入っていたわけでも、周りに作家志望者がいたわけでもなかったので、継続して書いてきたわけではありません。高校生のときには何か書いていたみたいで、全く記憶にないその作品が実家のパソコンに残っていたのですが、五年後ぐらいにそれを母親が知り合いの編集者に見せる、という事件があったんですね。で、僕の作品を読んだ編集者が「この子にはもしかして才能があるかもしれない」なんて言い出したと。』
つまり、本作『ユートロニカのこちら側』第5章の語り手である「ユキ」と同様、「議員(政治家)」とまではいかなくても、小川の両親は「共産党系の進歩的知識人」だったということであり、知り合いに編集者がいたというのだから、左翼出版社にコネのある「教員」あたりだったのではないだろうか。
しかし、だからこそ小川哲自身は、「人民大衆」に対して『諦観』を持つようにもなったのではないか。
いくら民衆に期待したところで、民衆というのは「易きに流れる」存在であり、民衆による「革命」などというものは起こりえない。理想は理想であって、決して実現することはないだろう、と。
例えば、同じ『諦観』を、より厳しい言葉で言い換えれば、こんな具合にもなろう。
『「……私は、あらゆる革命の敗北の、その究極の根拠を発見したのです。
なぜ、一切の革命は常に絶対に敗北するのでしょうか。歴史は、敗れた革命の残骸で埋めつくされているではありませんか。なぜ、革命はいつだってまるで悪い運命に呪われているもののように絞殺され続けてきたのでしょうか」
「なぜです」と日本人は陰気な声音で尋ねた。
「理由は、そう、わかってしまえば実に簡単なことなのです。それは、革命のなかにいつも解き難い矛盾と背理が含まれていたからです。革命は、胎内に敵対者の罠をはらんでいたのです。その罠とは、〈革命は人民による人民のための事業である〉という愚昧な命題です。この命題こそが、革命の敗北の根拠なのです。革命そのものとこの命題のあいだにあるものは、決して解くことのできない矛盾と撞着だけです。
そうです。革命と人民は本質的に無関係です。いいえ、あらゆる歴史の現実が露骨に示しているのは、革命の最悪の敵が人民そのものであったという事実なのではありませんか。革命の真の敵は、刑務所や軍隊や政治警察や武装した反革命ではなく、……人民という存在だったのです。乳臭い牝牛みたいに愚かな善意で目を曇らせた革命家たちは、いつもこの露骨な真実に無自覚でしたが、人民はその小狡い臆病な獣の本能で熟知していました。人民の熱狂的な支持と拍手のもとで、あるいは保身のための無言の加担によって、無数の革命家たちは投獄され拷問され虐殺され続けてきたのです。(以下略)」』
(笠井潔『バイバイ、エンジェル』より、角川文庫P361 〜 362)
『 〈人民〉とは、人間が虫けらのように生物的にのみ存在することの別名です。日々、その薄汚い口いっぱいに押しこむための食物、食物を得るためのいやいやながらの労働、いやな労働を相互の監視と強制で保障するための集団、集団の自己目的であるその存続に不可欠な生殖、生殖に男たちと女たちを誘いこむ愚鈍で卑しげな薄笑いにも似た欲情……。この円環に閉じこめられ、いやむしろこの円環のぬくぬくした生温かい暗がりから一歩も出ようとしないような生存のかたちこそ、〈人民〉と呼ばれるものなのです。つまり人民とは、人間の自然状態です。だから、あるがままの現状をべったりと肯定し、飽食し、泥と糞のなかで怠惰にねそべる豚のように存在しようと、あるいは飢餓のなかで、その卑しい食欲を満たすため支配的な集団にパンを要求して暴動化し、秩序の枠をはみ出していくように存在しようと、どちらにせよただの自然状態であることに変わりはありません。
だから人民は、本質的に国家を超えることができないのです。国家とは、自然状態にある個々の人間が、絶対的に自己を意識しえない、したがって自己を統御しえないほどに無能であることの結果、蛆が腐肉に湧き出すように生み出された共同の意志だからです。制度化され、固着し、醜く肥大した観念、生物的生存と密通し堕落した観念、これが国家だからです。』(同・P363 〜 364)
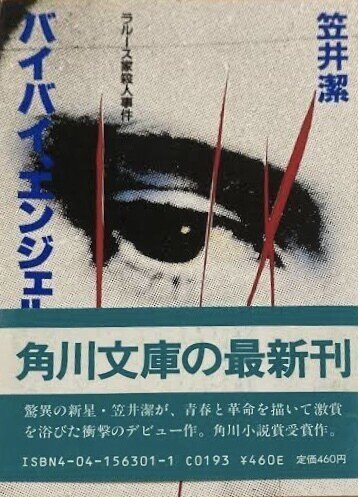
つまり「豚のような人民大衆」は、「恵まれた生活環境」という「餌」さえ与えられれば、それで満足してしまうような「尊厳なき存在」なのだ、ということである。
そんなふうに小川は、両親の「共産党員としての徒労」を通して、『諦観』を育んだのではないか。
だからこそ、そんな彼なら「ユートロニカ」に憧れもするのだ。
そこではすでに「革命」は失効しており、動物的欲望をほぼ満たされた「人民大衆」は、欲望に駆られて豚のように、ブーブー泣きわめくこともないからである。
○ ○ ○
これが、あながち邪推ではないかもしれないのは、樋口恭介・東浩紀との前記鼎談において、小川が淡々と「色々と書きたいものはあるが、今は読者に届くものを書かなければならない」「ひとまず直木賞をとりたい」という趣旨のことを語っていたからだ。
言うまでもないことだが、小川が「直木賞」を信仰的に崇めているなどといったことは、まずあり得ない。小川は、もっと明晰に「醒めた人間(ニヒリスト)」であり、しばしば「メタレベル」という言葉を口にして、そうした観点の重要性を語っているのがその証拠で、事実、小川哲作品の「醒めた諦観」は、そうした視点によってもたらされている。
だから、小川が「直木賞がとりたい」と言う時、それは純粋に「直木賞」に憧れているなどといった「ナイーブ」なことではなく、直木賞が取れれば「ひとまず、作家として食っていく目処が立つ」ということでしかない。
言い換えれば、前記鼎談でも「芥川賞」作家に触れていたように、小川の描きたい小説とは、必ずしも「直木賞」の対象となる「大衆文学」ではないのだ。
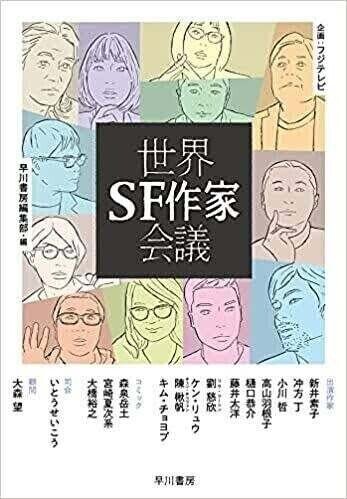
何人かの芥川賞作家がSF作品を書いているように、小川だって、芥川賞の対象になるような作品を書きたいという気持ちはあるのだが、仮にそれでうまくいったところで、「芥川賞」では食っていけないからこそ、プロ作家の保証として、今は「直木賞」を取りに行っているということであろうし、ひとまずその方が、SFファンも含めた、広範な読者の支持を受けやすいと、そう計算しているのであろう。
そしてそれが、今のところ、嫌でも、この「資本主義リアリズム」(マーク・フィッシャー)の世界という「(ユートロニカの)こちら側」である「大衆消費社会」に生きなければならない、彼の『リアリズム』なのではないだろうか。

もちろん私は、小川哲のこうした「計算高さ」を批判しているのではない。
家族を食わせていかなければならないプロの作家としては、このくらいの計算高さはあって当然だし、その上で、ある程度「読者を操る(意図的に誤解させる)」くらいのことはするだろう。
小川は、本作『ユートロニカのこちら側』の中で、「アガスティアリゾート」という「ユートロニカ」に適応しようとしない、いかにも「人間くさい」人物を何人か登場させており、多くの読者はむしろ、そうしたキャラクターたちに感情移入したはずなのだが、一一無論これも、作者の「計算のうち」だということである。
『書いていて一番楽しかったのは第四章のドーフマンです。変なヤツを書こうと思ったんですね。それまでは「SFとはこういうもんだ」と自分の中で抑制しながら書こうとしていたけど、四章まで書き進んで「もういいじゃん、自由にやって」となった。思い入れがあるのは刑事スティーヴンソン。もともと彼が主人公の長篇を書く予定でしたから。』
つまり、「ディストピアとしての管理社会に抵抗する主人公」というのが、小川が『それまでは「SFとはこういうもんだ」』と感じていた、退屈な「SF的紋切り型」だったのだけれども、そこを押さえ書かないと「一般ウケ」しないと考え『自分の中で抑制しながら書こうとしていたけど、四章まで書き進んで「もういいじゃん、自由にやって」となった』結果、生み出されたのが、「アガスティアリゾート」の基本システムである「犯罪予測システムBAP」を開発した、変態っぽい、クリストファー・ドーフマン博士だった、というわけだ。
要は、小川は「ディストピアとしての管理社会に抵抗する主人公」などというものが、「現実」には存在し得ない「絵空事」であり、しかしそれを承知で、あえて「娯楽商品として書く」というのが、商業作家としての『リアリズム』だと、そう考えたのではないか。
そして、そんな『諦観』を持っていたからこそ、第3章までは「一般受け」を意識して、嫌でも「書きたいこと」自制してきたのだが、本来、小川が書きたいキャラクターとは、そうした「紋切り型」の視点からすれば「マッド・サイエンティスト」と呼ばれるであろうドーフマンの方だった、ということなのではないだろうか。

だから、『思い入れがあるのは刑事スティーヴンソン。もともと彼が主人公の長篇を書く予定でしたから。』と答えているからといって、これがそのまま「いちばん共感できるのは刑事スティーヴンソン」だという意味ではない、と考えるべきだろう。
無論、だからと言って、読者を偽るための「フォロー」として言っているだけとも、断じられない。
言うなれば「刑事スティーヴンソン」は、「理想としての共産社会の実現を願った、理想主義者だった両親」への共感と反発、そのアンビバレンツな感情が込められた、愛着ある「敗者」としてのキャラクターだったのではないだろうか。
したがって、前記インタビューで『今後の抱負』を訊かれて、
『アイディアは何個か浮かんだり消えたりしていますが、具体的に真剣に考えているものはまだありません。まずは出版したあとの反応、誰に読まれているのか、どういう風に読まれているのかをフィードバックしたい。ハードな方向に振り切るのか、リアリズム路線でやっていくのかも考えています。文学の役割の一つに、世間から光があたっていない弱者や忘れられているものをとりあげることがあります。生半可な技量や知識でやると陳腐なものになるので、どれぐらいやれるかはわかりませんが、SFというジャンルで光があたっていないものを探してみたいです。』
と答えた言葉も、なかなか意味深である。
つまり『ハードな方向に振り切るのか、リアリズム路線でやっていくのかも考えています。』という言葉には、「ハード」に、この度し難い現実社会(の行く末)を描く方向に進むのか、そんなものは「ウケない」という「資本主義リアリズム」にしたがって、読者に喜ばれる小説を書くという「リアリズム」路線を続けていくか、そのあたりを、読者の反応を見ながら考えていると、そんな意味かもしれないし、前者の可能性を開くためにも、まずは「直木賞の受賞が必須だ」ということにもなるのであろう。
また、『文学の役割の一つに、世間から光があたっていない弱者や忘れられているものをとりあげることがあります。』というのも、あくまでも『文学の役割』ということであって、自分の「やりたいこと」だとは言っておらず、せいぜい『SFというジャンルで光があたっていないものを探してみたい』という、いわば「新機軸」としての狙いを語っているだけ、とも取れるのだ。
○ ○ ○
さて、このように見れば、小川哲の「醒めた諦観」と「作家的正論」の間にただよう「齟齬」に、いちおうの説明をつけることも出来るのではないかと思う。

ともあれ、私はまだ、小川の今のところの代表作(直木賞候補作)『ゲームの王国』を読んでいないので、この作品を読めば、私のこうした「小川哲」観も、おのずと修正されるかもしれないし、逆に補強されるかもしれない。
どちらにしても、「共産党員(シンパ?)」の両親を持つことによる「屈折」が感じられる、という意味において興味深い作家・小川哲を、しばらくは追いかけてみたいと思っている。
(2022年2月28日)
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
