
古田徹也 『このゲームにはゴールがない ひとの心の哲学』 : 「懐疑しなくていい」 という話ではない。
書評:古田徹也『このゲームにはゴールがない ひとの心の哲学』(筑摩書房)
本書はたいへん読みやすく、ある意味で、とてもわかりやすい哲学書である。
その「読みやすさ」のゆえに、どんな読者でも、本書に書かれていることを、自分に引きつけて「自分の興味の範囲内での理解」を得ることができるのだが、言い換えればそれは、読者個々のレベルによって、きわめて浅い理解から、深い理解まで、幅広い層に「理解できた」と思わせて(誤解させて)しまう、そんな「危険性」のある本だとも言えるのだ。
内容が同じでも、これが昔の哲学書のように、硬く読みにくい文章で書かれていて、その意味で「難解」な本であったなら、普通の読者は、そこで「難しい」となって、そこに書かれていることが「難しい」問題なのだと、実感できるだろう。
また、書き手(哲学者)の方も、「これくらいは、頑張って読み解け」という感じで、「一見さん」をお断りするために、わざと難しく書いていた側面もあったわけだ。「そう簡単に、分かったつもりになるなよ」というのを、字面の難しさで「わかりやすく見せつけた(わからせた)」のである。

本書は、「懐疑論」批判の書である。
ただし、それが「目的」ではないから、本書を一読して「なるほど。たしかに懐疑論は間違っていますよね。私もそう思います」と、そう納得して終わったら、本書を誤読したことにしかならない。しかし、ここは勘違いしやすいところだから、くれぐれも要注意だ。
本書はたぶん、まともに「懐疑論」なんて持ったことのない人ほど、簡単にわかった気にしてしまうようなところのある本なのである。
例えば、脳科学や進化論の本なんかを読んでまで、「世界は、私が見たままのかたちで存在しているのか?」とか「心は存在するのか?」とかいったことを、大真面目に考えようなんて思いもしなかった人なら、当然、「世界」や「心」などの「実在(の確証)」の問題についても、きわめて主観的に「そんなもの、あるに決まってる」としか考えないはずだ。
したがって、「懐疑論の必然性」など思いも寄らないから、本書の「懐疑論は誤っている」という部分だけを、よく理解できないまま「まあ、そうだろうな」と、あっさり呑み下してしまうのである。
そして、そんな「すぐに分かった気になる人」とは、例えば、「宗教」だの「オカルト」だのといった「立証不能なもの」を信じている人なんかが、その代表的な実例であろう。
自分個人は、それを「絶対に正しい(真理だ)」と信じているけれども、それを立証することができず、そこを「弱み」と感じているからこそ、「すべての思考(言語ゲーム)は、究極的には、絶対的根拠を持ち得ない(から、絶対的認識への到達を自明のごとく求める懐疑論は、間違っている)」といった議論に、これ幸いと飛びつくのである。
「科学みたいに、突き詰めて考えたって、所詮は無駄なんだよ(決定的根拠を欠いているということでは、宗教も科学も同じ)」だというわけだ。
だが、無論こうした考えは間違いであり、本書で語られているのも、そんなお易い話ではない。
本書の著者は、ウィトゲンシュタインの研究者であり、本書で語られるのも、ウィトゲンシュタインとその哲学を踏まえたスタンリー・カヴィルの議論なのだが、要は、ウィトゲンシュタインが、「科学みたいに、突き詰めて考えたって、所詮は無駄なんだよ」みたいな、「雑な話」をするわけがない、ということである。
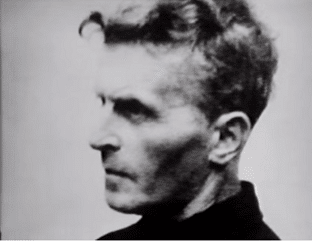
だがまあ、かくいう私も「哲学」の素人だから、本書を十全に理解できたわけではない。一一と言うか、本書の趣旨からしても、どんな書物であろうと、そこから著者(他者)の考えを100%正しく読み取ることなど原理的に不可能で、引き出しうるのは、その読み手の力量の範囲内に止まらざるを得ない、ということになる。
だから、私が上で書いたことは「俺はわかったけど、お前らにはわかるわけない」という話ではなく、「簡単にわかったつもりになっているお前らほど、俺はバカじゃない」ということだと言えるだろう。
そんなわけで、これから私が書くのは、本書の「内容紹介」ではなく、「私の理解したところ」である。
「内容紹介」というのは、「雑に読める人」ほど易々とこなしてしまうようなルーチンだが、私はそれが苦手だから、嫌でもこうなってしまうので、「あらすじ」を読んで、読んだつもりになれる人のご期待には沿いかねると、あらかじめ断っておきたいと思う。
○ ○ ○
とは言え、ある程度は、本書の議論を紹介しないと、私の理解してところを理解してもらえないので、ごく大雑把に、本書の議論を紹介したい。
前述のとおり、本書は「懐疑論批判」の書である。
そして「懐疑論」とは、「それ本当なの?」と懐疑する議論のことだ。
具体的に言えば、「目の前に見えているリンゴは、本当に実在しているのか(幻覚なのではないか)?」とか「あそこに立っている人は、本当に人間なのか(よくできた人形なのではないか)?」とか、あげくは「私が見ているこの世界は、本当に存在しているのか?(夢を見ているだけではないのか?)」といった、「根本的な疑い」を立てる議論のことである。

なんで、こんな気難しいことを言うのかというと、それは「懐疑論」が、「盲信を捨てて、確実な知識を」という「近代合理主義」に由来する「科学的思考」に立脚する立場だからだ。
この立場からすれば、「(キリスト)教会」や「偉い人」が言っているから、「実際のところ、確かめたわけじゃないけど、まあ信じていいんじゃないか。たまに間違いもあるけど、たいがいはそれでうまくいくんだから」というような「いい加減」は容認できない。
「そんなことだから、科学者を黒魔術師だとか言って、焼き殺したりすることにもなったんだよ。だから、もっと厳密に検討して、ひとつひとつ確かな知識を積み上げていかなきゃダメだろ!」ということで、ひとまず「当たり前」を疑ってみるというのが「方法的懐疑」というやつなのである。
つまり、デカルトがやったように、確実なところから、ひとつひとつ確かなことを積み上げていってこそ「真相に至りうる」のであり、そんなデカルトの「思考のための絶対確実な土台」というのが、有名な『我思うゆえに我あり』という「自己認識」。「考える私がいるという事実は(私には絶対に)疑い得ない」というところから、出発するわけである。
当然、「それ以外」は、すべて疑う。
自分の手足の存在も、目の前のリンゴも、話しかけてくる奥さんも、それを私が「見ている」「感じている」というのは事実だけれども、「見えているから実在する」とか「話しかけてくるから、会話が成立するから、それらの他者は実在している」とは言えない。そんなものは「夢の中」でだって成立するからである。
だから、懐疑論者は、何でもかんでも「それは確実か?」と問うわけなのだ。
だが、ウィトゲンシュタインとその哲学を依拠したスタンリー・カヴィルの議論としては、『我思うゆえに我あり』つまり「考える私がいるという事実は(私には絶対に)疑い得ない」というのが、そもそもの間違いだ、ということになる。
なぜかと言うと、その認識における、「思う(考える)」とか「感じる」とか「私」って「何なのよ? その言葉を規定している根拠の方は問わないの?」という話になるからだ。

つまり、本書で懇切丁寧に説明されている「懐疑論」の問題点とは、結局のところ「原理的に問い切れないものを問うている」ということであり、それは「人間存在の不確かさに由来する不安から来る、無い物ねだりだ」というような理屈になるわけである。
そしてそのことを、人間が「言葉を身につけ、世界観を形成していく」過程を跡づけることで、証明しているのだ。
実際、このことだけなら、さほど難しい話ではない。本書で何度も説明されているとおり、物事を疑うためには、信じられる「土台(基盤)」が、どうしても必要なのだ。
例えば、無重力の宇宙空間では、少し離れたところに「歩いて移動する(到達する)」ということができない。なぜなら、歩くための土台である「地面」がないから、地面を蹴って前に進むということはできないのである(だから、宇宙飛行士は、宇宙遊泳の際には、ガスを噴射することで移動したりする。ガスを吹き出し、その反作用で、ようよう推進力を得るのだ)。

同様に、あることを「疑う」ためには、その基盤となる「信じられること」が最低ひとつはないといけないのであり、デカルトもそれがわかっているから、「我思う我」だけは「私(我)」には疑えないものであり、だからそれを「基盤=思考の起点」としたのである。
だが、「我思うゆえに我あり」というのは「言葉」であり、それは人間が成長する中で構築してきた「道具(架構物)」にすぎない。「我思うゆえに我あり」というも認識が、それ自身として厳然と存在しているのではない。
それは、「言葉」によって構築された「二次的制作物」であって、すべてを疑うための「基盤」にはなり得ないのだが、デカルトをはじめとした「懐疑論者」は、そのことを都合よく忘れていると、ウィトゲンシュタインとカヴィルに依拠して、本書著者は語っているのである。
そもそも、デカルトが「我思うゆえに我あり」なんて考えられたのは、言葉を学んだからなのだ。
仮に彼が「狼に育てられた少年」であったならば、つまり「人間の言葉」を会得しなかったら、「我思うゆえに我あり」なんてことは考えられない。
彼は、狼がそうであるのと同様に、世界は「自明なもの(存在)」として「在るとか無いとかいった議論」の対象にはしようのないものとして、存在しているはずなのだ。
言い換えるなら、デカルトが「我思うゆえに我あり」と考えられるのは、彼が人間社会に生まれ育ち、親をはじめとした人間社会の中で、「言葉」を学んだからに他ならない。
だが、懐疑論者というのは、その「親」や「社会」や「世界」を「自明なものとしてはいけない」という立場であり「それらも例外とせず、疑いを持って検討せよ」と言うのだから、「親」や「社会」や「世界」があったればこそ、身に着けることのできた「言葉」というものの存在も、疑うのが、当然ではないか。
ところが、そこ(言葉)だけは疑わないというのだから、懐疑論者の懐疑は、根拠(基盤)を欠いて「空回り」している、ということになるのである。

では、「言葉」を疑えば良いのかというと、そうはならない。
なぜなら「言葉によって言葉を(根本的に)疑うことはできない」からだ。
懐疑論の立場からすれば、本来であれば、「言葉の実在性」さえ疑うべきなのだから、「言葉」を疑うにしても「言葉を使ってはいけない。それは思考(検討)の確実な基盤にはならない。なぜならそれは、懐疑のための基盤ではなく、懐疑の対象そのものだからだ」ということになってしまうのである。
しかし、言うまでもなく、「言葉」を使わずに「思考する」というのは、「人間には不可能」である。そもそも、「思考」とは「言葉を操作する」ということだからだ。
したがって、「懐疑論」は、合理的な「基盤」を欠いており、言うなれば「底が抜けている」から、そんな議論は「成立しない」、ということになるのである。
○ ○ ○
だが、「懐疑論は成立し得ない。だから、疑ぐるだけ無駄」だという考えが、大きな間違いであるというのも、「常識ある(言葉をあやつれる)人間」には、自明のことでしかない。
要は「何でも盲信していれば良い、というわけではない」ということだ。
人間は「言葉」をあやつることによって、あらゆることを「懐疑」してきた。そのおかげで「漠然と信じてきた(無根拠に信じてきた)」ことの多くが「誤り」であり「非事実(非現実)」であることを知り、それによって「無知の桎梏」から逃れることができて、一定の自由を手に入れることができたのだ。
だから、「物事を疑う」ということは、絶対に「必要」なことであり、それに対し「そもそも、疑うための絶対的基盤がないのだから、疑うのは間違いであり、疑うだけ無駄だ」などというのは、「知ったかぶりの馬鹿」の言い草でしかないのである。
では、「疑うための絶対的な基盤が無いのに、それでも懐疑は必要だし、疑うことはできる」とは、どういうことなのだろうか?
それは「完全な否定(や肯定)はできない(決定的な結論は出せない)けれど、それが検討すべき対象であると疑うことなら、おおむね出来るし、すべきである」というようなことだ。
「絶対間違いない(絶対確実)」ということを求めなければ、疑う(懐疑する)ことは可能だし、そもそも「絶対確実な認知」というものは「原理的に存在しえない」のだから、「存在しないもの」に固執する体の「(確信犯的)懐疑論」は、「知的」なのではなく「偏執(病気=呪い=信仰)」でしかない、ということなのである。
私たちに可能な「懐疑」とは、どういうことなのかを、譬え話で説明しよう。
先ほど「宇宙空間での移動」の話をしたけれど、それと同じような話である。
ある宇宙空間に「蜘蛛の巣のような構造物」を作ったとする。これが「構築可能なもの」だというのは、多分ご理解いただけよう。
惑星でも衛星で宇宙ステーションでも何でもかまわないが、ある物を起点として、その構造を拡大していき、その結果として、巨大な「蜘蛛の巣のような構造物」としての「世界」を構築したとする。
その片隅に住んでいる人間にとっては、自分がいま依って立っている「大地」は、「堅牢な基盤」だと考えることができるし、事実そうしているだろう。だからこそ、そこを基盤として、いろんな構築物を建てることもできるのだ。

しかし、この巨大な「蜘蛛の巣のような構造物」としての「世界」を、遠くから眺めれば、それは宇宙空間に、ふわふわと寄る辺なく浮かんでいる「蜘蛛の巣」のようなものにしか見えない。その構造物は、どことも繋がっておらず、宙に浮いているのである。
だが、「客観的」にはそうであっても、その「蜘蛛の巣」世界の中に生きている人間にとっては、それは「確かな基盤」となっている。この場合、こうした「架構された大地」を、確かなものと考えるのは間違いなのだろうか?
例えば「地球は、大地は、地面は、信用して良い」と考えるのは、間違いなのだろうか?
厳密に言えば、「地球」も「大地」も「地面」は、不確かな「構造物」に過ぎない。
地震によって「地面」は崩れ、「大陸移動」からもわかるとおりで、「大地」だって確かなものではない。アトランティスみたいに、消えてしまわないとも限らない。もちろん「地球」だって、宇宙にプカプカ浮かんでいるものに過ぎず、太陽の引力によって、相対的な安定を得ているとはいっても、その太陽がいずれ燃え尽きて消滅したりしたら、地球だって存在しなくなる蓋然性が高い。
一一要は、この世には「絶対不変で確実なもの」など存在せず、私たちは常に「仮構的に確実なもの(相対的に確実なもの)」に依拠して生きるしかない、ということなのだ。

だから、「言葉」というものまで疑ったのでは、そもそも「生きることができない」し、当然「考えること」などできるわけもないのである。
つまり、たしかに本書の大半は「懐疑論批判」に費やされているのだけれども、それは「懐疑論」が「間違っているから、不必要なもの」だという話ではないのだ。
本書で語られるのは、その真逆の「人間とは、他者(性)との詰められない関係をそのまま受け入れることのできない存在だ」からこそ、その「存在論的孤独」という本質において「確かなつながり」を、どうしようもなく求めざるを得ない悲しい存在なのだ(「すべては不確実だ」と言って澄ましていられるような、強い存在ではないのだ)、ということである。
だから、「懐疑論」というのは、一般に考えられているほど「確かなもの」ではなく、むしろ「不確かな基盤の上に構築されるしかない構造物」に過ぎないのだけれど、それは、人間には「避け得ない行為」なのだ、ということなのだ。
だからこそ「それを避け得る」と思っている人は、自分のことが何もわかっておらず、ただ、ご都合主義的かつ場当たり的に「信じたいものを信じ、疑いたいものを疑っている」だけの、愚かにも無責任な人間でしかない、ということになる。
その意味で、「懐疑論」を否定しさることができると考える人(反懐疑論者)もまた、「懐疑論者」と同じ穴の狢でしかない、ということになるのである。
だから、本書著者は、ウィトゲンシュタインの立場を次のように説明している。
『 もっとも、彼(※ ウィトゲンシュタイン)がオースティン(※ ジョン・L・オースティン)と同様に、日常言語で営まれる日常生活のありようを重視し、懐疑論という混乱から日常への回帰を目指していることは間違いない。ただし彼は、その回帰すべき当の日常とはいかなるものか一一他者(※ 原理的には、理解不能な人間存在)とともにある我々の日々の生活とはいかなるものか一一について、オースティンとは根本的に異なるビジョンをもっている。それは、他者の心(※ という到達不可能なもの)についての懐疑論への道筋が常に(※ 必然的に)開かれており、現実に少なからぬ人々を懐疑論を生きることへと誘っている場、として日常を捉えるビジョンだ。ウィトゲンシュタインは、懐疑論的な問いを不真面目な問いとして切り捨てるのではなく、むしろその引力と、我々にとっての身近さを、正当に見定めようとするのである。
前章で、ウィトゲンシュタインが懐疑論の言説を〈文法的基準に適っていない、意味の不明瞭な言葉〉として特徴づけていることを、カヴェルによる解釈を経由しつつ跡づけた。しかしこれは、反懐疑論のように懐疑論を論駁する試みではない。懐疑論の混乱を露わにするウィトゲンシュタインの分析は、本章の第三節以下で見てきた通り、文法的基準の無根拠性を同時に露わにするものである(※ 不明瞭なのは、懐疑論だけではない、ということ)。そしてその無根拠性は、我々の不安を膨らませ、繰り返し懐疑論へと向かわせる当のものだ。その循環にウィトゲンシュタインは向き合い、何度も懐疑論へと立ち戻り、またそこから不安定な日常へと回帰しようとする。カヴェルは、まさしくここに、ウィトゲンシュタインの哲学の際立った特徴を認めている。彼によればウィトゲンシュタインは、この円環的構造の具体的なありようを引き受ける以外に、日常に回帰する哲学的思考の真の道筋はない、と考えるのである。
懐疑論の諸条件への具体的なかたちの屈服と、そこからの具体的なかたちの回復、その果てしなき反復……円のような、自分の尾を踏む(※ ママ)蛇のような果てしなさ。ウィトゲンシュタインにとって、この屈服と回復こそが哲学と呼ばれる営みにほかならない。(DK:30/57)』(P199〜201、傍点は省略した)
「その認識に根拠はあるのかと疑い、しかし、その疑いこそ根拠のない観念だろうと見抜いて日常に回帰し、しかし、日常もまた絶対的な根拠を欠いているからこそ、根拠を問わないではいられないという懐疑論を、人は必然的に持たざるを得ず、しかし、その必然的な疑い方は無根拠なのだと指摘して、日常の無根拠な現実にまた立ち戻る」という「ウロボロス(自らの尾を呑む蛇)的円環」を生きるのが、「哲学する」ということなのだ、という話である。
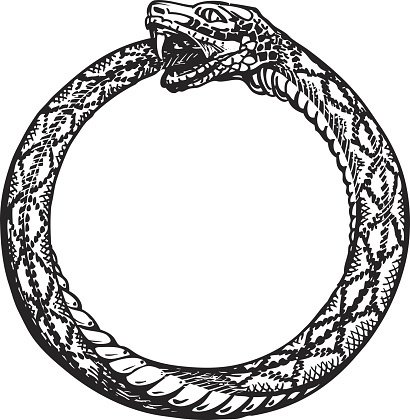
だから「なんだ、やっぱり懐疑論なんて、難しげなことを言ったところで、所詮は無根拠だったんだ。私たちは、この不確かな世界の中で、信じられると思ったものを信じて生きていけばいいんだ。例えば、我が神の存在のように」というような考えは、間違いなのである。
厳密には「間違いだと断ずることはできない」のだけれども、そんな考え方は「横着で不誠実」なものであり、そんな立場を選ぶ人とは、所詮「哲学とは縁なき衆生」でしかない、ということになる。
だから、本書を、簡単に「わかった」などと思うのは、いかにも愚かなことなのだ。
なぜなら、「わかった」のであれば、その読者自身が、この「哲学的円環」に身を投じて、「物事を徹底的に疑うと同時に、疑うことそれ自体も疑う」という「ゴールがないゲーム=困難」を、誠実に引き受けなければならないからである。
だが、そんなことのできる人が、一体どれだけいるだろうか?
多くの人は、本書の「あらすじ」を聞いて、その「幻想」に安住しておしまい。一一というのが、関の山なのではないだろうか。
しかし我々は、「懐疑」すべきなのである。
たとえ、自分自身が「完璧」ではなくても、自分自身をも「懐疑」しつつ、「懐疑」すべきなのだ。
(2023年5月7日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
