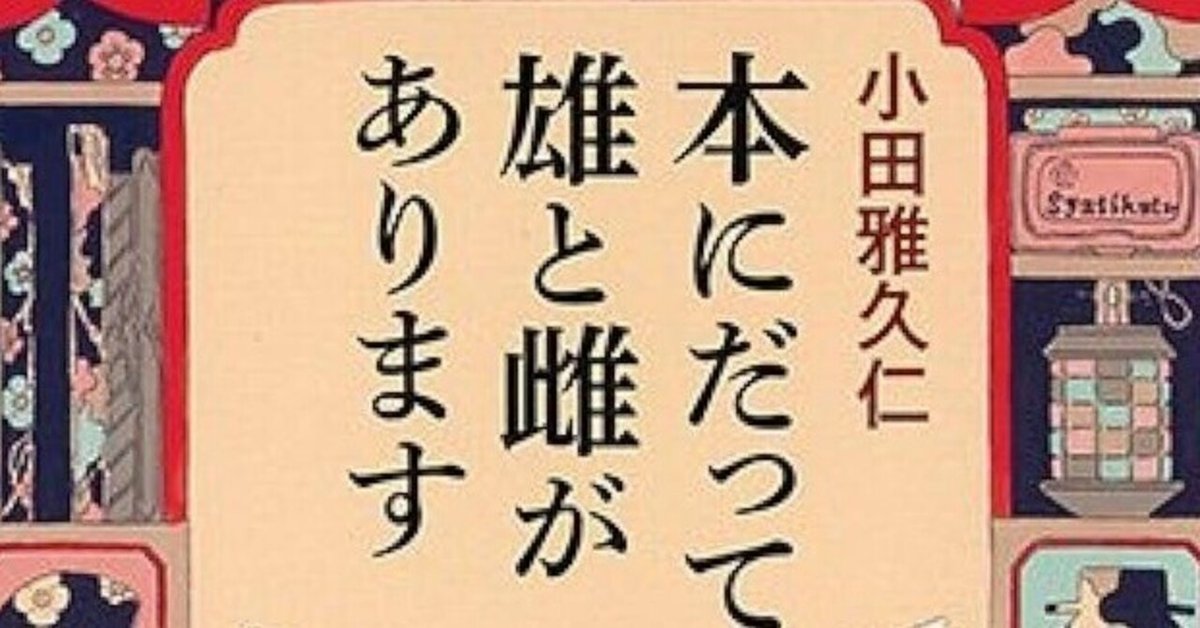
小田雅久仁 『本にだって雄と雌があります』 : 本をめぐる〈愛の物語〉
書評:小田雅久仁『本にだって雄と雌があります』(新潮文庫)
「読書家」ましてや「愛書家」を自負するのならば、ただちに本書を読むべきである。
私は、本書を初版単行本で買っておきながら、読むのが今になってしまったことを深く後悔している。いや、死ぬまで読めないままになるだろう積読本が山のようにあるのに、新刊でもない本書を、死ぬまでに読めたことを、むしろ僥倖としてして喜ぶべきなのだろう。その意味で、本書と本書の著者を強く推し続けてくれた、大森望に心からの感謝を送りたいと思う。
大森の薦めによって、同じ著者の『禍』や『残月記』を読んだのも、今となっては本書を読むためだったとしか思えない。それくらい本書は、「面白かった」という言葉には収まりきらない「豊かな読書体験」を与えてくれた、稀有な傑作であった。大森にも、そして作者にも、感謝して仕切れないほどの「読書の喜び」を、本書は与えてくれたのである。
本書著者である小田雅久仁が、「日本ファンタジーノベル大賞」の出身者であることは、かねてから知っていた。だが、のちに同賞を受賞するとは言え、同賞に興味を持っていた初期の頃には、小田は大賞受賞者ではなかったから、気にはしながらも読むまでには至らなかった。しかしながら、本書の初版単行本が刊行された際には、『本にだって雄と雌があります』というユニークなタイトルに、おおいに目を惹かれた。
また、気になったのは、帯に刷られていた推薦者が、大森望と岸本佐知子という「組み合わせ」だったことも大きい。
『どうかしてます。いい意味で。一一岸本佐知子(翻訳家)
すでに古典の風格。殿堂入り確実!一一大森望(書評家)』

大森望という人は、今では、SF小説の「翻訳家」や「アンソロジスト」という印象が強いが、それまでは、ここでそうあるように「書評家」という肩書きがメインだった人のように思う。私のような古い読書家には、大森望といえば、書評家・豊崎由美とのペアで人気を博した『文学賞メッタ斬り!』シリーズの印象が強いし、以前の「SF冬の時代」には、当時ブームだった「新本格ミステリ」方面で「非正統派のミステリ」のバックアップに尽力している人、という印象が強かった。もとがSFの人だから、エラリー・クイーン式の端正な本格ミステリよりも、そこから大きく逸脱した「変なミステリ」の方に興味があったのであろう。
一方、私の方も、中井英夫の『虚無への供物』や竹本健治の『匣の中の失楽』なんかでミステリに入った人間なので、決して正統派の本格ミステリファンとは言えないのだが、それでも「本格ミステリ」の端正さには強く惹かれるものがあったので、そちらを中心に読んでいた。そして、大森望が推薦するような「非正統派の新本格ミステリ」の「変さ」にも興味を持って時々は読んだのだけれど、それらはおおむね、私の期待水準には遥かに届かないものだった。今となってみれば、「変なもの」が好きだからこそ、そちらへの期待水準が高すぎたということだったのかもしれないが、いずれにしろ「大森望は、変なものばかり推薦して、この人の推薦はあまり当てにならない」という評価が、私の中で醸成されていった。
そして、そんな大森望と、「変なミステリ」ばかり書く私の好きな作家・竹本健治が、連名で推薦文を書いた新人作家が、かの「清涼院流水」だったのである。一一だから、私はそれ以降、この二人の推薦文は「博打にすぎて、信用ならない」という評価をするようになったのだった。
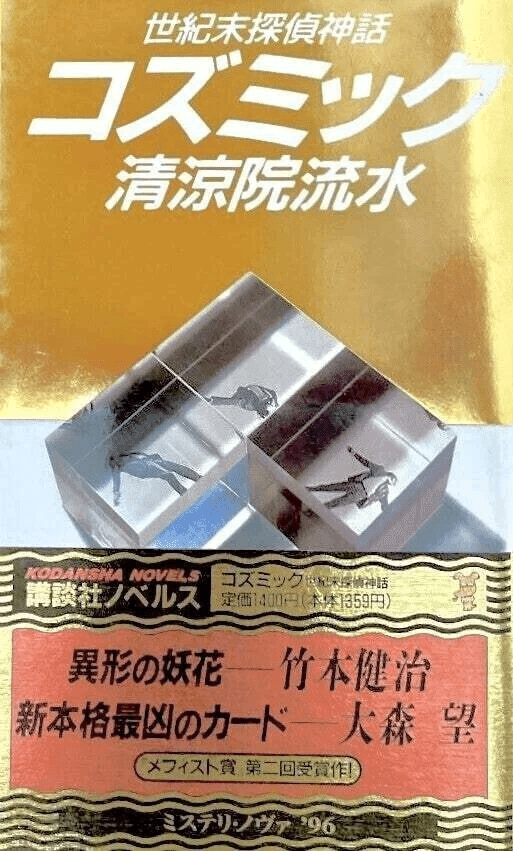
本書『本にだって雄と雌があります』を初めて目にした時も、推薦者が大森望だけだったら買わなかっただろうと思うのだが、もう一人の推薦者が翻訳家の岸本佐知子だったので、これはちょっと気になった。
というのも、岸本は「世界の現代文学」の面白いところを紹介する目利きとして、当時かなり注目されており、私も岸本の翻訳書は、ひととおりは買っていたからである。岸本のセレクションの面白いところは、まず「読んで面白い作品」を紹介するのだが、それが「現代文学の最前線」の作品でもある、という点である。つまり、世界的にみれば「最前線の文学」でありながら、いわゆる「難しい作品」ではなく、基本的に「読んで楽しい作品」を紹介してくれるところが、現代文学紹介者としての岸本佐知子の魅力だったのだ。

そんなわけで、大森望と岸本佐知子の二人が推薦しているとなると、本書が、決して「オーソドックスな作品」ではないだろうというのは、容易にわかった。そして「難解な作品」でもないはずだ。ならば読んでみる価値はありそうだと、そう判断して購入したのである。
だが、こういう「ジャンル分けの難しい作品」というのは、どうしても後回しになってしまいがちだ。その時に興味を持っている「文学ジャンル」や「テーマ」から外れる本というのは、古典的名著や名作と同じで、読むべき価値はあるけれど、さりとて「いま読まなければならない」わけでもないからである。
だから、本書についても結局は積読の山に埋もれさせてしまったのだが、昨年退職して時間的な余裕ができたこともあって、気になっていた作家・小田雅久仁を読むことにした。あまり著作が多くはないようだし、それでも大森望が相変わらず推薦しているので、そろそろ読もうかと、最新作の『禍』を読み、「これは(匂い立つ世界の立ち上がってくる小説の)書ける作家だな」と感心した。続けて、ベストセラーにもなった『残月記』を読んで、この作家の力量は間違いないと確信し、過去作もひととおり読まなければならないと思った。そして、過去作のうち、先に手に入ったのが本書『本にだって雄と雌があります』だったというわけだ。当然、10年も前に買った初版単行本は、積読の山に埋もれて、すでに発掘不可能となっていたのである。
○ ○ ○
『 あんまり知られてはおらんが、書物にも雄と雌がある。であるからには理の当然、人目を忍んで逢瀬を重ね、ときには書物の身空でページをからめて房事にも励もうし、果ては跡継ぎをもこしらえる。毛ほども心あたりのない本が何喰わぬ顔で書架に収まっているのを目に止めて、はてなと小首を傾げるのはままあることだが、あながち斑惚けしたおつむがそれを買いこんだ記憶をそっくり喪失してしまったせいばかりとは言えず、実際そういった大人の事情もおおきに手伝っているのだ。
というのが、私の母方の祖父、つまり君の曾祖父ということになるのだが、深井興次郎の回りくどい言い分である。要は、ただでさえ夥しい蔵書が余人の知らぬ間に増えに増えて書斎や書庫から土砂のように溢れ出したことへの言い訳であり、さらにそれが廊下を着々と這いすすみ、存外器用に階段まで下ってみせて、とうとう一階にまで陣を取るに至ったことへの言い訳であり、ついには與次郎とその妻ミキ、そして生まれる家を選べなかった四人の子らをもろとも冷たい土間へ蹴落とさんとその日常生活の場を喰い荒らし、いやいやここまで来ればいっそのこと、と厠にまで厚かましく本棚が立った事態への言い訳なのである。ミキ曰く、
「布団並べてお父はんと一緒に寝てるやろ。ほんだら、屋敷のどっかで、ときたま、カタカタ、とか、コトコト、とか、パタパタ、とか得体の知れん音しよるんよ。ほんで、言うわ言うわと思てむしろ待ってしまうねんけど、お父はん、やっぱり布団の中でうれしそうに言わはるわけや。『ああ、また本が増えてまうなあ。わしらもあいつらに負けんと、もうひと頑張りしよか』って。わて、たいがい寝たふりしたってんけどな.....」
しかし與次郎の屁理屈といっても数あるそれの一つに過ぎず、であるからにはほかにもあれこれ思いついては開陳してみせたわけで、その一つがこうだ。(以下略)』
(文庫版・P7〜8)
もう、この冒頭だけで、読書家や愛書家は、本作の世界に引き込まれてしまう。
そして、私も蔵書家の一人として、ひとこと言いたくなってしまう。
「本には雄雌があって、知らぬ間に子供を作ってしまうから、本は勝手に増えるし、憶えのない本を書架に見つけることもあると、そうおっしゃるけれども、私の場合は、そんなことはない。たしかに、買った本を忘れていることはある。しかし、見れば『しまった、買ってたんだ』と思うことはたまにあっても、『こんな本は知らない』とか『買ったはずがない』とかいうことはない」と、そう反論した上で「本は、雌雄が交合せずとも、単性生殖で増えることだって、ままある。つまり、本が自己増殖して、同じ本がダンボール箱いっぱいになっているなんてことが、少なくとも、かつては時々あった。たとえば、京極夏彦の初期の本は新書版ながら、その分厚さにおいて〝レンガ本〟などと呼ばれたものだが、その代表格である『鉄鼠の檻』や『絡新婦の理』なんて本が、いつの間にやら増殖して、それらを積めば、犬小屋など簡単に作れるくらいの冊数には、長くはかからず増殖していた。そうした本は、たいがいの場合、段ボール箱に箱詰めにしてあるから、外からは見えない箱の中で、こっそり細胞分裂的に自己増殖したのかもしれない。だが、それでは、段ボール箱の中は、当初はスカスカだったのかというと、そのあたりが定かではない。もしかすると、『鉄鼠の檻』やら『絡新婦の理』やらが、テレパシーのようなものを使って私を操り、増殖に適した段ボール箱の中という環境を、私に準備させたのかもしれない。恐ろしいことである。だから、私の友人などは『彼の家には、本が積んであるだけではなく、段ボール箱が積んであって、その中がぜんぶ同じ本なんですよ。で、それのひとつを開けてみると〝ほぅ〟なんて声がする。なんとその中身は全部『魍魎の匣』だったんです」などと無いこと無いことを言う。『魍魎の匣』について言えば、そこまでは増殖していないはずだ。かのシリーズでは一番好きな作品なので、その意味ではちょっと残念だけれど」などと、負けず嫌いに、注文だか自慢話だかを付けたりする。一一何が言いたいのかというと、本の増殖は「雌雄交合」だけではなく、「単為生殖」や「無性生殖」などもあるという厳然たる事実だ。
一一とまあ、冗談はさておき(…)、読書家、愛書家、蔵書家ならば、本書に惹かれないわけがない。
しかし、本書は、全編この調子の「冗談小説」あるいは「ユーモア小説」かと言えば、そうではない。
幾人かの人がすでに指摘しているとおりで、本書は、ガルシア=マルケスの『百年の孤独』を思わせるような「マジック・リアリズムによる、一族の物語」でもあり、この現実世界を丸ごと包摂せんかのごとき「稀有壮大な物語」であり、そして「夫婦愛の物語」でもある。
したがって、本書は、日本的には「分類不可能」な作品、ということにもなる。
つまり「SF」「ミステリ」「ファンタジー」「幻想文学」「純文学」、あるいは「マジック・リアリズム小説」などといった区分には収まらない、それらすべての要素を包含した、スケールの大きな作品であり、言うなれば「世界文学」としての「現代文学」だというのが、最も適切な表現なのであろう。

だが、我が国においては、こうした「分類不能な作品」は、おおいに割りを食うことになる。多くの読者は、「ジャンル」という「レッテル」で作品を選び、その「レッテル」の線に沿って作品を評価することで「安心」を得ようとする。「SFとしては」どうとか、「ミステリとしては」どうだとか言っておけば、自身の見識の狭さを問われることもないと、そう思っているからだ。
しかし、言うまでもなく文学における「ジャンル区分」などというものは、便宜的なものでしかなく、そんな「大雑把な区分」に収まってしまう作品など、言うなれば「田舎の名士」みたいなものとも言えよう。たしかに「一廉の人」ではあろうが、世界に出れば「無名に等しい」ということである。
だが、本書はそうではない。本作は、そんな小さな「日本的な枠」に収まっているような作品ではない。本作はまさに「世界文学」の域に達した作品であり、だからこそ、岸本佐知子が推薦し、大森望が『すでに古典の風格。殿堂入り確実!』としたのである。大森のいう「殿堂」とは、日本文学の中での「殿堂」ではなく、文学全体における、そしておのずと全世界的な「殿堂」ということであり、「古典」というのも同じスケールにおいて、という意味だ。
だが、本書が、一般的なレベルで、そこまで正しく評価されているとは言い難い。
というのも、本書が日本で出版され、まず日本の読者に読まれるに止まっているからである。もしも著者が英語圏の人で、出版されたのが英語圏であったなら、評価のされ方はもっと違っていただろうと思わずにはいられない。本書は「日本ローカル」には収まりきらない、「世界文学」的な「世界性」を持った作品なのだが、そのスケールの大きさが、日本の「盆栽趣味」的な狭い視野には収まりきらず、「理解不能」という読者も少なからず出てくるのである。
だが、本作冒頭部の飄逸な雰囲気を面白いと思った人も、それを面白いとは感じなかった人も、どうか最後まで読んでほしい。本作は、冒頭部だけで、そのすべてが予想できるような「こぢんまりとした作品」ではない。
本作には、真摯な「歴史批評」があり、人の生死を丸ごと相対化してしまうような「幻想的ビジョン」があり、そして「家族愛」や「夫婦愛」も、しっかりと描かれている。
こういう褒め方はあまり好きではないけれど、本作は、けっこう「泣ける小説」なのだ。しかも、その「泣ける」は、しみじみとしたその感動において、生まれてきたことの幸福を改めて感じさせられ、そのせいで思わず流れる「温かい涙」の謂である。
だから、読書家なら、ぜひ本書を読むべきだ。
ただし本書は、若い読者には「わかりにくい」部分があるかもしれない。だが、その場合は、本書を、5年なり10年なり、あるいは20年なり30年なり寝かしておいて、少し歳をとり、人生経験を重ねてから読んでみると良い。そうすれば、きっと見えてくるであろう世界を、本書は描いている。
読書家でないのなら読まなくても良いかもしれないが、しかし読書家ならば、死ぬまでには本書を読むべきである。
でないと、絶対に、あの世で後悔することになるからだ。
(2023年12月3日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
