
アレックス・ガーランド監督 『シビルウォー アメリカ最後の日』 : 本当は「難解」な映画
映画評:アレックス・ガーランド監督『シビルウォー アメリカ最後の日』(2024年・アメリカ映画)
アメリカ社会の「分断」の先にある「内戦の可能性」を描いた映画一一だというくらいのことなら、どんなに無知で思考停止した人にでもわかることだろう。
彼らとて、さすがにテレビやネットニュースくらいは見ているから、アメリカ社会の「分断」という言葉くらいなら、何度も耳にしているはずなので、「その問題を扱った、一種の風刺的かつ警告的に、アメリカの近未来を描いてみせた作品」なのだな、という程度のことならわかるはずなのだ。
だが、本作の真価は、その程度に止まるものではない。

本作の真価に、気づける人と気づけない人との差が、奈辺に存するのかといえば、それは本作で描かれる『テキサス・カリフォルニアが連合する「西部勢力(WF)」』などの19州と「連邦政府」との内戦という設定を知らされて、
(1)「あれっ?」と気づく程度の「知識」があるか否か
そして、それに気づいたら、
(2)それが「どうしてそうなのか?」ということを「自分の頭で考える能力」があるか否か
ということになる。
まず、(1)は比較的容易だ。
なにしろ本作の中でハッキリとそう語られているのだし、「テキサス」といえば「カウボーイ」をイメージさせるほど「保守的」な印象の強い南部の州で、一方の「カリフォルニア」といえば「西海岸」の「自由」というイメージが強い。
つまり、「保守」色の強い「テキサス」と、真逆に「リベラル」色の濃い「カリフォルニア」の連合と言われれば、「あれっ?」と思うくらいのことは、さして難しいことではないのだ。
明らかにトランプ前大統領を思わせる「全体主義的な大統領に支配された連邦政府」に楯突き、独立の自由を主張する勢力、というのなら、「カリフォルニア」はいかにももっともらしいのだけれど、「テキサス」の方は不似合いな印象が強いはずである。

したがって、「西部勢力(WF)」に南部の「テキサス」を加えたというのは、明らかに意図的なものなのだが、しかし、本作の中では、この「不自然と思える設定」の意味が語られることはない。
要は「種明かし」がなされないのであり、その意味するところは、もちろん、ガーランド監督が「あなたが、自分自身の頭で考えてみてください。それが重要なのです」と考えている、ということである。
だから、「西部勢力(WF)」に「テキサス」が入っているということに「違和感」を感じないような「無知」な人は、そもそも、この映画の意図するところがわかるわけもなく、ただの「近未来戦争SF」だ、くらいのことしか考えられないだろう。
しかしまた、「テキサス」問題に気づいたとしても、そもそも「自分の頭で考える(考察し解釈する)」といったことのできない、(口をアーンと開けて、正解を与えてもらうのを待っているだけの)「お子様」なら、本作は「観客に優しくない映画」だと反発して、せいぜい腹を立てるくらいが、関の山であろう。
そんなわけで、本作は、観客に「知識と思考力」を要求する、なかなか「敷居の高い」映画なのだ。
ハリウッド式に「一から十まで全部説明してくれるエンタメ映画」しか楽しめない者には、「理解不能な作品」ということにしかならないのである。
本作が、わかりやすく「哲学的なテーマ」でも「わかりやすく提示してくれるような作品」であったなら、そうした「思考力のない観客」でも、その「明示されたテーマ」について考えてみるくらいのことはできるだろう。
だが、本作の場合、見た目に「わかりやすそうな映画」だからこそ、その「秘められたテーマ」については、「知識と思考力」以前の「物を見る目」が必要となる。「何が問題なのか」に気づくだけの「センス」が求められるのだが、そのことに気づくのは、まあ、100人に1人だと考えて良いのではないだろうか。
ともあれ、そうした意味において本作は、「難解」な作品なのだ。
○ ○ ○
さて、そんな本作を、私が見ようと思ったのには、それなりの理由がある。
ハッキリ言って、本作が単なる「アメリカ社会の分断の先を描いた、近未来戦争SF」的な作品であり、「それだけ」だと思っていたなら、見てはいなかったはずだ。
だが、私は最近、論壇において問題視され始めており、『情況』誌までもが2年前には特集さえ組んだ、アメリカ発の「キャンセルカルチャー」というものの存在を知って、それに興味を持った。

そして、それを学ぶための手始めとして、前嶋和弘の『キャンセルカルチャー アメリカ、貶めあう社会』という本を、つい先日、読んだのだ。
その結果、アメリカ社会における「分断」というのは、私たち日本人が思っているような甘いものではないというのを、そこで知らされて、本作も、同様の問題意識から、つまり、日本人が思っているようなお易い認識ではなく、もっと「切迫した危機感」から作られた映画なのかもしれないと、そう考えて、本作を見ることにしたのである。
この「読み」はドンピシャで当たっていた。
本作を見れば、単に「アメリカの内戦が描かれた、近未来戦争映画」などではなく、「社会的分断によって、人間と人間社会がどのように変わってしまうのか、その恐怖をリアルに描いた作品」だというのを、否応なく知られされることになる。
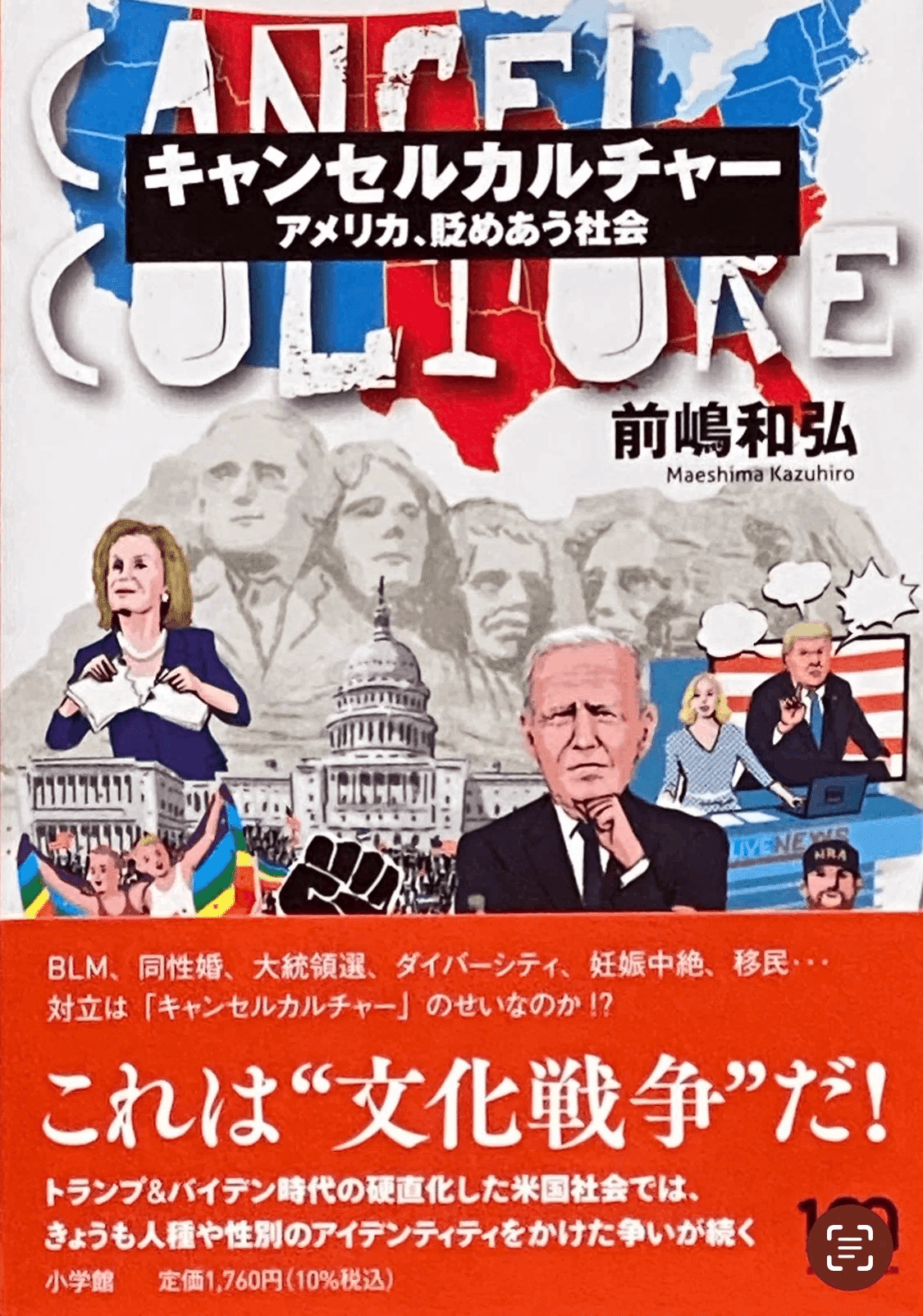
この「重さ」を、現実の歴史に即して言うなら、それは「ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争」や「ルワンダ内戦」といったことになるだろう。
このあたりの歴史に暗い人は、上のリンクを辿って、是非とも「自分で」、その基本的なところを勉強してほしい。
だが、ここでは後の説明のため、ごく簡単に紹介しておくなら、これらの紛争や内戦とは、もともとは同じ社会の中で当たり前に共存していた人々が、あるきっかけによって社会的に分断され、あとは「宗教」や「部族」の違いなどを指標として、お互いを「相容れない敵」だと認定し、徹底的に憎悪し合って、その結果、優勢な方が劣勢の方を「皆殺し」にしようとまでした争いだった。一一ということにでもなるだろうか。
昨日まで「ご近所づきあい」していた相手と、否応なく殺し合いをすることになったのだ。
つまりこれらは、終わってしまえば「どうして、こんな酷いことになってしまったのか…」という、深い悲しみと後悔、そして人間に対する絶望の感情を残した、そんな歴史的事件だったのである。
だから本作『シビルウォー アメリカ最後の日』(以下『シビルウォー』と略記)も、単なる「架空戦記」みたいな「お気楽なお話」ではなく、人間と人間社会の「リアルな変貌」を描いた、怖しい作品なのだ。
ご近所のあのお兄さんは「右派」的な思想を持っていて、あのおばさんは「左派」的な人なのかもしれない。
無論、そんな立ち入ったことまでは知らないが、しかしそれでも昔からの顔見知りとして、特に親しくはなくとも、当たり前の近所づきあいができていたのに、ある時からはそれが、武器を持って殺し殺される「敵」へと変貌してしまうのである。
当然これは、「アメリカ」だけの話ではなく、日本だって、そうなりかねないと思わせてしまうリアリティのあるところに、本作の描くの恐怖の真価があるのだ。
あともう一つ、私の、
『前嶋和弘の『キャンセルカルチャー アメリカ、貶めあう社会』という本を読んで、アメリカ社会における「分断」というのが、日本人が思っているような甘いものではないというのを知らされて、本作が、そのような問題意識から、つまり、日本人が思っているようなお易い認識ではなく、もっと「切迫した危機感」から作られた作品なのかもしれない』
という「読み」が当たっていたという証拠としては、この映画を見たあと、ひさしぶりにパンフレットを購入して、それを開いてみると、この前嶋和弘が、本作の「社会的背景」に関する解説文を寄せていた、ということもあったのだ。
この「解説文」自体は、前述の『キャンセルカルチャー アメリカ、貶めあう社会』の内容をごく簡単にまとめたようなもので、すでに同書を読んでいた私には、いささか物足りないものではあった。
だが肝心なのは、本作『シビルウォー』において見るべきポイントとは、「戦争という結果」にあるのではなく、そうした結果を招くことになる「社会の分断による、キャンセルカルチャー的な心性」を描いている、という点にある。
「対立する意見を持つ者」なら「キャンセル」してもかまわない(心が痛まない)という「感覚」になってしまうことの怖しさ。
「意見の対立する人」を「同じ人間だと思えなくなる=虫でも殺すように傷つけることが出来るようになってしまう」ことの恐怖である。

ここで「キャンセル」または「キャンセルカルチャー」について、基本的な理解を示しておこう。
『キャンセル・カルチャー(英語: cancel culture)は、2010年代後半から使われるようになった用語で、「容認されない言動を行った」とみなされた個人が「社会正義」を理由に法律に基づかない形で排斥・追放されたり解雇されたりする文化的現象を表す。この排斥は対象者の社会的・職業的な領域に及ぶこともあり、有名人に関するものが最も注目されやすい。排斥された者は「キャンセルされた」と言う。
概要
キャンセルカルチャーはアメリカ合衆国で生まれた言葉である。キャンセル・カルチャーは主にソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上に見られる。抗議行為自体は「canceling」(キャンセリング)と呼ばれ、抗議の対象になることは「canceled」(キャンセルド)と呼ばれる。キャンセルカルチャー的な活動は「ボイコット運動」や「ノープラットフォーミング(デプラットフォーミング)」などと呼ばれていた。
キャンセルの対象は、生きているの人の直近の言動、生きている人の過去の言動、すでに亡くなっている人の過去の言動、という3つの類型がある。3つ目の例としては、過去の軍人や政治家の銅像や記念碑などが、戦争や人種差別を理由として抗議対象となることが挙げられる。コールアウト・カルチャーがエスカレートしたものがキャンセル・カルチャーとする見方もある。
2015年頃までに、「キャンセル」という概念はツイッターを利用する黒人の間で広まり、人物や作品への支援を止める「個人的な」判断を指すようになった。ニューヨーク・タイムズ紙のジョン・エンゲル・ブロムウィッチによると、「キャンセル」のこうした用法は「完全に投資を止めること」を意味したという。その後、ニューヨーク・タイムズによると、「キャンセル」という言葉は「キャンセル対象者に対する怒りに満ちたネット上での反応」を指すようになった。やがて個別のキャンセル事例が蓄積されて群集心理が形成されていき、キャンセルは「文化」とみなされるようになった。
キャンセル・カルチャーは否定的な意味合いを持ち、オバマ元大統領などキャンセル・カルチャーに批判的な者(※ が言うには、キャンセル・カルチャー)は、非生産的であり真の社会変化をもたらさず、ネットいじめに等しいなどと(※ キャンセル・カルチャーに)否定的な見解を示している。一方で、サラ・マナビスのように、キャンセル・カルチャーの存在を疑問視(※ して、そんなものは存在しないと主張)する者もおり、そうした(※ 主張をする)人々は同じような形の排斥運動は「キャンセル・カルチャー」という言葉が生まれるずっと前から存在していたとと(※ ママ)いう見解を示している。』
(Wikipedia「キャンセル・カルチャー」)
見てのとおり、「キャンセルカルチャー」とは、「意見の違う者の存在を、社会的に抹殺する思想」、「抹殺してもかまわないとする思想」だと言えるだろう。
言い換えれば、「意見の違う相手」と「議論」し「意見を戦わせる」ことで、可能なかぎり相手を「説得」しようと努力し、「共により良きを目指そう」とする「民主主義の原理」を、完全否定するような考え方が、「キャンセルカルチャー」なのだ。
したがって、「キャンセルカルチャー」における「分断」とは、「対話不能」であり、その意味で「関係修復不能」ということにもなるから、その行き着く先は「敵の皆殺し(ジェノサイド)」しかない、ということになる。
そしてそれが、「国内」で行われるなら、「内戦」や「紛争」における、同国民間のジェノサイドや「民族浄化」ということにもなる。「意見の違う同国民」をすべて抹殺することで、初めて「民族」が浄化され、理想の状態が達成されると、そんな感覚になるのである。
本作には、そんな「分断の怖しさ」が描かれているのだ。
したがって、ここでいう「分断」とは、単なる「意見対立」のことではない。
そうではなく、「対話など考えられない。なぜなら、あいつらは、われわれと同じ〇〇ではないんだから」というような「感じ方」のことである。
本作に即していえば「あいつらは、真のアメリカ人ではない。あいつらは、アメリカ社会を腐らせる、ニセモノのアメリカ人であり、アメリカ社会の寄生虫なのだ。だから、抹殺するしかない」という、そんな「思考停止」を描いているのだ。

そして、当然のことながらこの問題は「アメリカ社会」の問題に止まるものではないし、また、「日本社会」の問題に止まるものでもなくて、一一たとえば「本作の評価」というレベルにおいてさえ、現に「発生している」ものなのである。
具体的に言うなら、「自分には、何が面白いのかわからなかった本作など、とうぜん駄作に決まっているのだから、こんな作品を褒めるようなやつは、映画のわからないやつに決まっている」といった類の「批評」の存在である。
そうした批評では、本作が「あの作品よりくだらない。あっちの方が余程うまくアメリカ社会を描いている」などといった、「別の権威を持ち出しての自己正当化」が図られはしても、「なぜ、この作品を褒める人がいるのか? その理由が知りたい。意見を聞かせてほしい」という発想が、皆無なのだ。
なにしろ、無自覚にも「自分と違う意見は、キャンセルするしかない」という発想なのだから、他人の意見に耳を傾ける気などさらさら無いということなのだが、私たちは、こうした人を、「日本人の映画評論家」の中にさえ見つけることができるはずなのだ。
だから、本作で描かれている「危機」とは、「他人事」でもなければ「未来の話」でもなく、「今ここにある危機」なのである。
それは、常すでに、ここにも伏在している危機なのだ。
本作が、このような作品だというのは、ガーランド監督自身が、パンフレット掲載のインタビューでも語っているとおりである。
『伝統的にカリフォルニアは民主党の州で、テキサスは共和党の州です。そんなカリフォルニアとテキサスが、映画の中でファシストの大統領と戦うために手を組みます。本作は観客に問いかけます。「民主党と共和党が『ファシズムは悪だ』と同意して、手を組むことがなぜ想像できないのでしょうか?」と。もしあなたがそんな状況は想像できないと考えているのならば、それはあなた自身の問題を反映しているのかもしれません。』
(P18「DIRECTOR INTERVIEW」)
ここでガーランド監督のいう『あなた自身の問題』とは、「カリフォルニアとテキサスが共闘することなど、ありえない」とそう思い込んでいるような人は、おのずと「論敵とは議論など不可能だ」と考えているような人であり、状況によっては「論敵はキャンセルする(抹殺するしかない)」となってしまう恐れのある人なのかもしれないと、そういう意味なのである。
自分では、まともな「民主主義者」のつもりなのかもしれないが、いざとなれば、かつて「ユダヤ人なんか抹殺してしまえばいいんだ」「朝鮮人なんて抹殺してしまえばいいんだ」と、そんなふうに考えた「多くの人たち」と、なんら選ぶところのない人間なのかもしれませんよと、そうガーランド監督は言っているのである。
『一一この映画を見た観客が、社会や政治についてどのような会話をすることを期待しますか?
良い質問ですね。私はただ観客に会話をしてもらいたいんです。ほとんどの映画はすべての問いと答えが物語の中に含まれているから、なかなか会話につながりません。私は日本の政治については詳しく把握していないので同じ状況かは分かりませんが、ヨーロッパやアメリカでは右派と左派の会話は完璧に崩壊しています。だから私は、右派と左派の観客が喧嘩をせずに議論できるような、双方に共通点がある映画を作りたかった。ただ会話してくれること。それがこの映画の答えなのです。』(同・P19)
ガーランド監督は、決して、本作の「曖昧さ」を正当化するために、このようなことを言っているのではない。
本作を見て、このパンフレットを買った後に気づいたことなのだが、ガーランド監督は、私自身、以前にレビューを書いている『MEN 同じ顔の男たち』(2022年)の監督であり、同作の次に作られたのが、本作なのだ。

私は、『MEN 同じ顔の男たち』のレビューの中で、次のように明記していた。
『要は、このように「わけのわからない、気味の悪い話」であり、ここで描かれたことを「合理的」に説明することは、およそ不可能ということになる。
つまり、この物語は「何かを暗示している」と考えるべきで、要はそれが何かを「解釈」するための考察が必要となる作品なのである。』
つまり、前作の『MEN 同じ顔の男たち』からして、「ボーッと見ているだけ」では「わけのわからない、気味の悪い話」でしかなく、少し勘の良い人なら、
『この作品を、当たり前に解釈したら、それは「男性嫌悪」映画だと言えるだろう。
「男ってのは、どいつもこいつも、無神経で暴力的で自分勝手で度し難い存在だ」という「怒り」が込められていると、一応はそのように解釈できる。』
のだが、そうした「表面的な理解」に止まることなく、さらに「読み込む」ならば、
『この映画が、「女がわからない、バカな男たち」を描いた映画ではなく、「『女がわからない、バカな男たち』という一方的な決めつけの激しい、フェミニズムかぶれの女」を描いた映画』
だということにも、気づき得るのだ。
そしてその「事実」は、同作の次のような描写にも明らかだろう。
『パーパー(※ 主人公の女性)は、夫との生活がもう続けられないと、夫に離婚を申し出るが、夫は「自分の何がいけないんだ。説明してくれなければわからない」という趣旨のことを言って、なんとかハーパーとの和解を望んでいる。
だが、ハーパーからすると、説明を求めるということ自体が「何もわかっていない」「なんでも説明できると思っていることが、夫の間違い」「説明を強要するところが我慢ならない」といったふうで、離婚に応じようとしない夫を、一方的にマンションの部屋から締め出して、自分の部屋にこもる。ハーパーが泣きながら、友人宛の、夫を非難するメールをスマホで打っていると、ハーパーの態度に激昂した夫が、部屋に押し入ってきて、「何をしているんだ!」とハーパーのスマホを取り上げ、その文面を見てさらに激昂し、ハーパーを殴り倒してしまう。
倒れて鼻血を流しているハーパーを見て、夫はあわててハーパーに謝罪するが、今度はハーパーが激昂して、夫からスマホを取り返すと、夫をマンションの部屋から追い出してしまう。
そして、ハーパーが泣きながら、ベランダの窓から夕陽を見ていると、その目の前を、夫が落下していくのを、もろに目撃してしまう。』

つまり、この『MEN 同じ顔の男たち』は、女性主人公ハーパーの視点から描かれているために、「ボーッと見ているだけではわからない」のだが、要は、このハーパーこそが「独善的な正義を振り翳して、対話を拒否する人物」であり、「論敵」つまりこの作品では「男」を、すべて「同じ顔」の「理解不能な気味悪い存在」だと見ているような、そんな「偏狭な人間」として、批判的に描かれているのである。

したがって、この『MEN 同じ顔の男たち』では、タチの悪い「アイデンティティ政治」に明け暮れる「えせフェミニスト」たちによる「男性との対話拒否(他者理解拒否=分断)のもたらす恐怖の世界」を「暗示的に」描いており、本作『シビルウォー』ではそれが、政治的な「右派と左派の分断」という関係において描かれていたと、そう言えるのだ。
そしてその上で、「カリフォルニア」と「テキサス」の、一見不可解な共闘である「西部勢力(WF)」には、「右派と左派の分断」を乗り越える「可能性と希望」が託されていた、ということなのである。
○ ○ ○
さて、ここで話を戻すと、私がなぜ、最近になって「キャンセルカルチャー」という言葉を知り、その「危険性」に注目することになったのかというと、それは『MEN 同じ顔の男たち』の主人公ハーパーを、地でいくような女性、「武蔵大学教授」で「映画評論家」でもある北村紗衣と、はからずも接触を持ってしまい、その「キャンセル」という、怖るべき手口を知ったからである。
それまで私は、北村紗衣という映画評論家など聞いたこともなかったのだが、映画マニアのブロガーである須藤にわか氏が、北村紗衣がインタビューで語っていた「アメリカン・ニューシネマ」についての見解が、あまりに「デタラメ」だと批判している、SNS「note」の記事を読み、この記事に共感したことがきっかけで、すでに2ヶ月弱にも及ぶ、北村紗衣との関係が生じることになった。
(※ なお、須藤氏は、アマチュアの書き手であるため、敬称を付している)
私も「アメリカン・ニューシネマ」には興味があったから、たまたま目についたこの記事を読み、その主張に共感して、コメント欄にその意を表明したのだが、その際に、その北村紗衣とやらは、まるで馬鹿だと、そう「根拠を示した批判」を書き込んだのだ。
ところが、この時すでに、記事主の須藤氏と揉めていた北村紗衣が、私のこのコメントを読んで、わざわざ北村紗衣の方から、私のコメントに関して「管理者通報」したというコメントを書き込んできた。
私への批判や反論などいっさい無いまま、私のコメントの言葉尻を捉えて、いきなり「管理者通報」をしたのである。
そして、さらには、それを批判した、私自身の記事にさえも、「管理者通報」で応じたのだ。
つまり、北村紗衣は、『MEN 同じ顔の男たち』の主人公パーパーと同様の、文字どおりに、お話にならない「えせフェミニスト」であり、本作『シビルウォー』においては「対話のできない、凝り固まった右派または左派」そのものの、言うなれば、確信犯的な「キャンセラー」だったのである。
ちなみに、ことの発端となった、北村紗衣のインタビュー記事とは、次の連載「あなたの感想って最高ですよね! 遊びながらやる映画批評」の第3回「メチャクチャな犯人とダメダメな刑事のポンコツ頂上対決? 『ダーティハリー』を初めて見た」のことである。
これへの、須藤にわか氏による最初の批判が、
・「北村紗衣というインフルエンサーの人がアメリカン・ニューシネマについてメチャクチャなことを書いていたのでそのウソを暴くためのニューシネマとはなんじゃろな解説記事」
(※ すでに、須藤氏自身により削除)
で、このコメント欄に、私はくだんのコメントをしたのだが、この時にはすでに、北村紗衣による須藤氏への「反論」である、
・須藤にわかさんの私に対する反論記事が、映画史的に非常におかしい件について
が公開されており、この「批判への反論」を経てさらに、北村紗衣と須藤にわか氏の間では、Twitter(現「X」)上での「対話」がなされ、これが、次の「Togetter」にまとめられた。
・北村紗衣さんとツイッターでニューシネマのお話をしたのでまとめました(編集なしの完全版)
だが、この「Twitter対話」の際の、「北村紗衣側の外野によるヤジ(ファンネル)」があまりに酷く、それでいて北村紗衣は、これを都合よく黙認して利用していたため、須藤氏は、北村紗衣を「議論の相手にはならない人物」だと判断し、上の「最初の批判記事」である、
・「北村紗衣というインフルエンサーの人がアメリカン・ニューシネマについてメチャクチャなことを書いていたのでそのウソを暴くためのニューシネマとはなんじゃろな解説記事」

のコメント欄への、北村紗衣からの苦情のコメントがなされたあと、しばらくして、北村の言い分を一部受け入れるかたちの妥協策として、最初の批判記事を、下のような「改訂版」に差し替えてしまった。
また、それにより、私の「コメント」も、おのずと「抹殺」されてしまったのである。
・シェイクスピア研究者の北村紗衣さんがアメリカン・ニューシネマについて俺の個人的なニューシネマ観とはかなり違うことを書いていたのでそれを説明しつつニューシネマのいろんな映画を紹介する記事〔改訂版〕

私は、こうして削除された「元版」のコメント欄で、私のコメントについて「管理者通報」した北村紗衣に対し、次のように、ハッキリと「議論・論戦」を呼びかけていた。
『年間読書人
2024年8月27日 09:51
北村紗衣先生
「通報」ですか、反論ではなく(笑)。
偉い先生は、無名の人間なんて、「同じ人間」としては扱えない、ということですね?
私は別に、先生の「物としての本」を切り刻むと言っているのではなく、その「内容」を「細かく批判的に分析する」という意味で書いているのですが、その意味が取れませんでしたか? それとも、「批評」自体を、否定なさるのでしょうか?
あるいは、そんなことは全部承知の上で、わかっていて「管理者権力」に訴え、暴力で、目障りな私を「潰そう」と、お考えなのでしょうか?
また、東浩紀が、そのお言葉を読んだら、どう思うでしょうね?
いずれにしろそういうのは、「弱者の権利」を守るフェミニストとしては、褒められたものではないと思いますよ。
往年の江川卓の言葉、「そう興奮しないでください。落ち着いて話し合いましょうよ」ってことですね。』
ここで言う『私は別に、先生の「物としての本」を切り刻むと言っているのではなく、その「内容」を「細かく批判的に分析する」という意味で書いている』と書いているのは、私が、
『年間読書人
2024年8月25日 05:14
それを、それこそ『ダーティハリー』すら見てなかった素人が、「アメリカン・ニューシネマ」は「こういうものだ」なんて、知ったかぶりで語るのは、まさに「盲目、蛇に怖ず」ってやつだと思います。
そして、そうした態度の根底にあるのは「差別的な上から目線」。だから、そこで「フェミニストの恥さらし」にもなるわけです。
今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)』

とコメントした、その末尾の一文である、
『今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)』
の部分について、北村紗衣が、記事主である須藤にわか氏に対して、
『北村紗衣
2024年8月27日 09:36
須藤にわかさん、あなたは私が「お姫様になることが女性の権利向上と考えているフシがある」などと私が思ってもいないことを言って人格攻撃を行いました。
それが弁護できることだとでも思っているのでしょうか。フェミニズム観の違いに逃げようとしても無駄です。
年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメントは通報いたしました。』

とコメントしてきたことについての反論である。
こんなインチキな「切り取り・改竄」によって「管理者通報」をし、それで人を黙らせようとするのは、言論人の端くれとして、恥ずかしくはないのかと、そういう意味である。
ともあれ、私は北村紗衣に対して、当初から「議論」で決着をつけようと提案要求していたのだが、北村紗衣は、その後、現在に至るまで、私との議論には、いっさい応じようとはしないままだ。
そのため、やむなく私が、北村紗衣の著作を論評するといったかたちでの「北村紗衣批判」を続け、北村紗衣という人への理解を逐次深めていくと、北村紗衣の、論戦で勝てなさそうな相手に対する「だんまり=対話拒否」や、「管理者通報」などといった(言論によらない)「キャンセル」手法は、今回たまたまのものなのではなく、「戦略的」「方法的」に採用されているものであり、どうやらそうした「自覚的な方法論」は、アメリカ発の「キャンセルカルチャー」から学ばれ採用されたもののようだと、そのようにわかってきたのだ。
そこで私は、勉強のために、前嶋和弘の『キャンセルカルチャー アメリカ、貶めあう社会』を読み、さらにそのあたりとも関連のありそうな本作『シビルウォー』を鑑賞した結果、この作品の監督が、以前に見た、「対話拒否問題」をテーマにした「えせフェミニズム」批判の映画である『MEN 同じ顔の男たち』の監督と、同一人物であったことに気づくことにもなったのである。
一一つまり、2年も前から始まっていたものが、ここにその円環を閉じて、見事に繋がったのだ。
最後に、再確認のために繰り返しておくが、本作『シビルウォー』のメッセージとは、単なる「戦争」や「分断」は怖しい、といったことではなく、
「あなたは、他者の意見に耳を傾けることができますか? 面倒でも、労を厭わず他者との対話をすることができるだろうか? しかし、それができなければ、われわれの社会の未来は、この映画のように暗いものになるおそれがありますよ」
というものなのである。

そしてこれは、「対話による民主主義」の未来について真剣に考えている者には、重すぎるくらいに重い「今ここの問題」なのだ。

(2024年10月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
