
アンソロジストの深き思惑 : 大森望 ・ 樋口恭介 ・ 清涼院流水 : 大森望編 『ベストSF2021』
書評:大森望編『ベストSF2021』(竹書房文庫)
『ベストSF2021』と聞いて、読者はこの本に、どんな作品が蒐められているとか考えるだろうか?
普通の人なら「2021年に発表された短編SF小説の中で、もっとも優れた作品が集められている、精選作品集」だと考えるだろう。だが、それでは間違い。本作品集には「国内作品」限定である。一一というのは、冗談。
しかし、真面目な話、冒頭に掲げた「問い」の答として「2021年に国内で発表された短編SF小説の中で、もっとも優れた作品が集められている、精選作品集」という答でも、正解にはならない。
なぜなら、その「優れた作品」というのは、「誰にとっての、どう優れた作品」なのかについて、そこではほとんど何も考えられてはいないからであり、そこに重大は「見落とし」があるからだ。
言うまでもないことだが、本書『ベストSF2021』において、収録作品の「優劣(良し悪し)」判断をするのは、基本的には、編者である、大森望である。
しかし、これも厳密には正しくない。と言うのも、大森が「編集後記」で「編集者の意向で、収録作品が若干変わった」という趣旨の報告をしているからだ。
『本書のラインナップが確定したのは二〇二一年五月末。最初はもう少し内輪向け(SFファン向け)の路線でまとめていたところ、竹書房編集部の水上志郎氏から、「それは前巻の序で宣言した《ベストSF》の基本方針(一年間のベスト短編を十本前後選ぶ)に反するのではないか」という趣旨の鋭いツッコミをいただき、いやまあ、それを承知のうえで軌道修正したんだけど……と思ったものの、「(SFファンとしての)予備知識がなくても、なぜこれがここに入っているのかが読んでわかる作品でかためてほしい」という要望はなるほどもっともだと考えた結果、いくつかの作品を入れ替えて、最終的にごらんのとおりの収録作が決定した。こうしてみると、たしかにこの方がよかったし、『ベストSF2021』のタイトルに恥じない陣容になったと思う。初心に返れと諭してくれた水上氏にあらためて感謝したい。』(P446〜447、「編集後記」より)
ここで注目すべきは、編集者の要求は『ベストSF2021』というタイトルからすれば、しごく真っ当であり、私たちがイメージする『ベストSF2021』に近い、という点であろう。
言い換えれば、大森望が前巻で自ら示した編集方針を、わざわざ「マニア向け」に軌道修正しようとしたところに、私たちは注目すべきなのだ。一体なぜ、わざわざ読者を減らすことにもなりかねない「マニア向け」でいこうと、大森は考えたのであろうか。
その答は、たぶん「その方が、結果として売れる」と大森が判断したからではないだろうか。
そう考えていいだろうヒントは、大森望による本書「序」文にある。
『 新たな日本SF短編年間ベストアンソロジー《ベストSF》シリーズの第二巻となる『ベストSF2021』をお届けする。二〇二〇年(月号・奥付に準拠)に日本語で発表された新作の中から、「これがこの年のベストSFだ」と編者が勝手に考える短編十一編を収録している。
なによりも、本書は〝SF〟という概念の開発と拡張を目的として制作された一一というのはウソですが(元ネタは樋口恭介編のアンソロジー『異常論文』の巻頭言)、結果的に、SFという概念の開発と拡張がなされていることは、おそらく否定できない事実である。
実際、作品を選んだ時点から半年以上経ったいま、あらためて収録作を読み返してみると、作品のジャンル的な幅の広さに驚かされる。
エッセイのように始まりエッセイのように終わる(ただし、真ん中がエッセイかどうかはよくわからない)円城塔「この小説の誕生」でスタートし、〝異常論文〟ブームの火付け役となった柴田勝家の記念碑的異常論文「クランツマンの秘仏」を経て、ある論文(学会発表)を核とする柞刈湯葉「人間たちの話」が、地球外生命探査について(あるいは小説とは何かについて)根源的な疑問をつきつける。』(P6〜7)
ここからわかるのは、大森が「異常論文」ブームの最中において、この「序」を書いている、という事実であり、本書が編まれたのは、ネット上において、SFマニアの間で、「異常論文」が徐々に注目され始め、盛り上がりを見せていった時期だと見て、大筋で間違いではないだろう点である(『SFマガジン』異常論文特集は、2021年6月号。刊行は同年4月24日)。


樋口恭介編の文庫版『異常論文』(2021年10月19日刊)所収の、小川哲の短編「SF作家の倒し方」の中で、パロディー的にではあれ、樋口が『大森望率いる裏SF作家界』の有力な若手として描かれているとおりで、大森望と樋口恭介はSF業界内で近しい間柄であり、事実、小川哲らと共に『世界SF作家会議』(単行本:2021年4月24日刊)にも参加している仲である。だから、この時期、大森と樋口は、「異常論文」という潮流を盛り上げる側として「共闘していた」と考えられるわけだ。
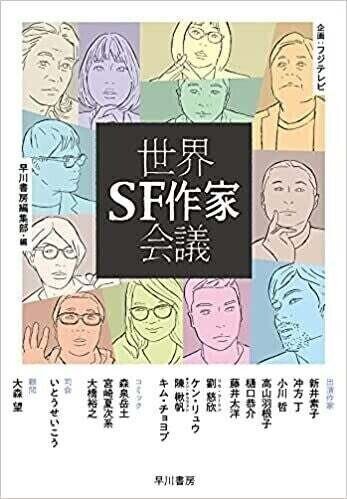
したがって、大森が本書の中に、樋口恭介に近い「異常論文」関係者や、自分が目をつけている若手作家の作品を、意識的に集めようとしたというのは、ほぼ間違いのないところであろう。
その意味で「アンソロジー=精選作品集」というのは、「一般的読者」にとってのそれではなく、「編者」にとって「好ましい」と考えられる「方向性を持った作品」の中からのそれであった、ということなのだ。
大森は、ネット上で「異常論文」で盛り上がっていたコアなSFマニアたちを喜ばせるような作家や作品、さらには勢いのある若手メンバーを本書にも集めて、側面支援の形で、「異常論文」的なものを含む日本SFの最新潮流を、樋口恭介らと共に作り上げようと考えたのではないか。その企みのせいで、仮に本書が一般的な意味での「年間ベストSFアンソロジー」にはならなかったとしてもである。
その証拠に大森は、本アンソロジーの選定基準について『「これがこの年のベストSFだ」と編者が勝手に考える短編』だと、周到に予防線も張っている。他の人がどう思うかは知らないが、私は「これがこの年のベストSFだ」と勝手に考えてますんで悪しからず、という意味である。
しかし、竹書房の編集者は、そうした意味での「SFマニア」でもなければ「ムーブメント作り」に加担する気もなく、当たり前に「SFマニアではない人が読んでも楽しめる、一般的に優れた作品を集めて、読者の裾野を広げたい」と考えて、「普通にベスト作品を選んでくださいよ」と、大森に注文をつけたのであろう。
大森としても、自らが前巻で掲げた「基本方針」を勝手に変更して、自分たちの「戦略」に竹書房を巻き込むのは、ある意味では契約違反の独走とも言えるので、そこはある程度の妥協した結果、本書のような内容になった、ということなのではないか。
実際、作品が収録されているわけでもない「樋口恭介」の名が、本書では何度もあがっていて、本書における「異常論文」ムーブメントの影は、とうてい否定し難いものなのである。
○ ○ ○
私は、樋口恭介の文庫版『異常論文』や、明らかに大森望が中心となって開催され単行本化された『世界SF作家会議』を、「仲間内の馴れ合いぶりが気持ち悪い」との趣旨で批判した。
特に、樋口恭介については、『異常論文』だけではなく、「SFプロトタイピング」を紹介した『未来は予測するものではなく創造するものである 一一考える自由を取り戻すための〈SF思考〉』や『現代思想 2021年10月臨時増刊号 総特集◎小松左京 生誕九〇年/没後一〇年』などでの態度も批判したし、その後に発生した「SFマガジン〈幻の絶版本〉特集中止問題」についても「それ、言わんこっちゃない」という感じで批判した。
だが、大森望個人については、ほとんど批判しなかった。一一なぜか。
それは、私が大森望の「新本格ミステリ」ブーム当時の活動を見ており、また、当時一度だけ酒席をご一緒したこともあって、大森の人柄を、おおむね肯定的に評価していたからだ。
無論、これは大森と「面識があったから、私の筆が鈍った」ということではない。
私は、面識がある作家であろうと、批判すべきと考えれば、まったく容赦はしない。一一というのは、笠井潔や綾辻行人などの実例でも明らかだろうし、これは個人的な友人であっても同じである。
私に論破されるのが嫌なら、私の友人ではいられなくて、おのずと遠のいていくことになる、とそのくらいに、私は相手を選ばず、仮借のない「議論」や「批判」をしてきたし、それがアマチュアであれプロであれ「言論人(文筆家)としての倫理(公正さ)」だと考えているからだ。
さて、ここまでは、言わば「前置き」。私がこのレビューで書こうと考えたのは、アンソロジスト大森望についての評価だ。
これまではボンヤリとしたものでしかなかった大森望評価を、本書を読んで、かなりクリアに整理することができたと思えたので、ここでは、本書の収録作品ではなく、編者である大森望の方を批評しようと、考えたのである。
○ ○ ○
大森望という「読者」は、端的に言って「変なもの・好き」(「変な、物好き」ではない)なのではないかと思う。もちろん、オーソドックスな活劇SFなどもお好きなようだが、その一方で「目新しいもの」「前例のないもの」「変わったもの」が大好きで、そうした新人の「可能性」を高く評価する傾向があるようだ(その端的な実例が、酉島伝法)。
これは、「SF冬の時代」に、大森が「新本格ミステリ」に接近して、解説を書いたり、推薦文を書いたりしていた当時、大森の作品評価が、およそ「オーソドックスな本格ミステリ=スタイリッシュな本格ミステリ」からは、大きくズレていたことからも窺えた。
当時、「新本格ミステリ」ブームの渦中にあった私は、初期の「メフィスト賞」受賞作品なども読んでいたが、この玉石混交の公募新人賞は、その玉石混交のゆえに「大きな可能性を秘めた賞」だったと言えるだろう。
実際、この賞からデビューして、人気作家に育っていった者は少なくないのだが、そうした受賞作の中で、おおよそ「正統派」に近い受賞作に対して推薦文を書くのは、「新本格」の生みの親である島田荘司とか、「メフィスト賞」以前の初期「新本格」作家である綾辻行人、北村薫、有栖川有栖、山口雅也といった面々であったのに対し、ちょっと「キワモノ」っぽい受賞作に推薦文を書くのは、「変格ミステリ作家」である竹本健治やSF系の大森望で、この二人が推薦文を寄せたのが、かの伝説的な「問題作」、清涼院流水の『コズミック』であった。




(下の3枚は、施川ユウキ『バーナード嬢曰く。』より)
そんなわけで、当時はまだ、一応の「本格ミステリ」ファンであった私は、竹本健治の大ファンではあったものの、新人作家の推薦者としては、竹本と大森望は「信用できない推薦者」だと評価していた。
「なんで、あんな変なものばかり推薦するのか。無論、変でも面白ければ良いし、よく出来ていればいいのだけれど、単に変なだけで、単純に未熟不出来な作品ではないか」と、彼らが推薦する作品の多くを、否定的に評価していたのである(それでも、一般的なミステリファンよりは、よほど好意的ではあった)。
しかし、今になって思うと、竹本健治や大森望は「オーソドックスに完成された作家や作品」を評価するに吝かではないけれど、しかし、それよりも「未完成でも、新しい地平を開いてくれる作家を世に出したい」という気持ちが強かったのではないかだろうか。要は、推薦作そのものの出来ではなく、その作家の「将来性」と「可能性」に期待したのである。
もちろん、そんな「未熟未完成な作品」を、さも傑作ででもあるかのように推薦された一般読者の方は、いい迷惑でしかなく、推薦者が批判されるのも当然のことなのだが、竹本や大森は、読者に一時的な犠牲を強いてでも、その可能性に投資してもらおうとしたのであろう。「そのくらいのこと」なら、やる(実験主義的な)人たちなのである。
例えば、二人の推薦でデビューした清涼院流水は、デビュー後、ミステリ界でバッシングを受け、二人の推薦者も、公言はされないものの「趣味が悪い」という評価を「新本格ミステリ作家」たちからも受けていたことだろう(そもそも、清涼院の「京都大学ミステリ研究会」の先輩である綾辻行人たちも、清涼院をまったく評価していなかった)。当時としては、清涼院流水の受賞やデビューは、明らかに「間違いだ」という評価だったのである。
ところが、その「正統派本格ミステリ」から大いにズレた清涼院流水の作品は、「ミステリマニア」とまでは言えない若い世代の読者からは一定の評価を得たし、のちに人気作家に成長する西尾維新、舞城王太郎、佐藤友哉といった「メフィスト賞」作家たちは、清涼院流水へのリスペクトを惜しまなかった。
そして、清涼院流水がいつしかミステリ界から姿を消したのと揆を一にするかのように、この三人の有力作家もミステリ界から去っていったことを考えると、清涼院流水がいなかったなら、この三人も、もしかすると作家デビューしていなかった蓋然性だって、無くはないのである。

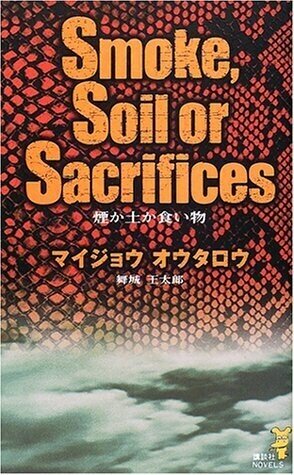
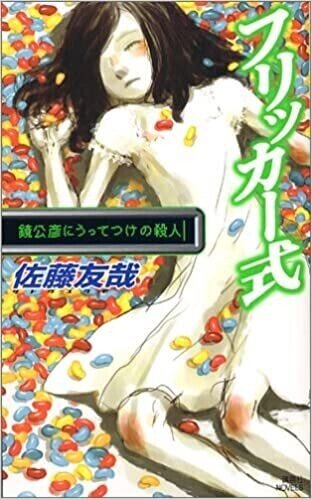
つまり、清涼院流水のデビューが発したメッセージとは「本格ミステリは、必ずしも、謎と論理の精緻なパズル小説でなくても良いんだよ。名探偵が事件を解決する、キャラクター小説でもかまわないんだ。要は、面白ければなんでもアリなんだ」というものだったのではないだろうか。
そして、こうした「ユルさ」が、西尾維新、舞城王太郎、佐藤友哉といった、「従来の本格ミステリ」べったりではなかった作家たちを、「メフィスト賞」へと導いたのではなかったろうか。
このように考えると、結果的には、清涼院流水自体は小説家として大成しなかったとしても、彼をデビューさせたことの意味は、とてつもなく大きかったと言えるだろう。
もしも、当時の「講談社・文芸第三出版部」の宇山日出臣以下の編集者(太田克史など)が、「新本格ミステリ第1世代」の作家たちのように「ゴリゴリのミステリマニア」で、清涼院流水的な「逸脱」や「偏向」を許容し得ない人たちであったなら、西尾維新、舞城王太郎、佐藤友哉といった「本格ミステリ」という枠を超えた才能や、「メフィスト賞」というユニークな賞の名を、歴史に刻むことだってできなかったはずである。
そして、こうした意味合いにおいて、竹本健治や大森望は、「新本格ミステリ」あるいは「ミステリ」という枠を超えて、文学の世界に大きな貢献を果たしたと言えるのだ。
だからこそ、大森望が、本書『ベストSF2021』において、オーソドックスな意味での「年間ベスト作品」を選ばず、権威ある「大家」や「人気作家」の中に、「若手の意欲作」を紛れ込ませて、「新しい潮流」に加担した、その編集方針の「狙い」も、おのずと理解できる。
要は、大森は「現時点でのベスト作品」ではなく「新しい潮流を生み出す可能性を秘めた作品」を出来るだけ多く収録することで、SFマニアたちに「(大森望の考える)目指すべき最前線」を示し、意図的に煽ることで、その流れを「加速」しようとしたのである。
無論、前述のとおり、こうした「先行投資」的な作品選びに、知らずに投資させられる一般読者は、たまったものではなく、なかば詐欺みたいなものなのだが、大森からすれば、こんな高い文庫本(税込1650円)を買うのは、どうせマニアが大半だろうし、そうしたマニアは、「最先端」に加担するのを、むしろ喜びとする「エリート指向」の持ち主たちなのだから、「マニア向け」に特化したところで、売り上げが極端に下がるわけではない、一一くらいの読みはあったはずだ。
しかしまた、こうした「自分の趣味」に都合の良い「読み」を、そうした趣味を共有しない編集者に、おおっぴらに押しつけるわけにはいかず、理解を求めるというわけにもいかなかった、ということだったのであろう。

で、どうして私が、「身内に甘い」大森望を批判しないのかといえば、それは、このように、彼の「党派作り」的な動きが、よくある「文壇政治」とは一線を画して、「趣味の実現」を目指すもののように感じられるからだ。
そもそも大森が、笠井潔のように「文壇政治」的に「党派」を作ろうとするような人物ならば、「新本格ミステリ」時代にだって、「新本格ミステリ」主流の神経を逆なでするような作家ばかりを、わざわざ後押しするようなことはしなかったはず(だし、笠井潔にだって擦り寄ったはず)だからである。
つまり、大森望のような「変なもの・好き」は、基本的には「保守的(形式重視の伝統主義)」な「本格ミステリ」業界には合わず、時代に応じて「前衛」が登場しては形式的な拡張と更新のなされてきた文学ジャンルとしての「SF」の方が、やはりその性向にも合致していた、ということなのであろう(ここで「形式的な拡張と更新」と評するのは、文学とはもともと「なんでもあり」であり、その意味では「本質的な拡張や更新」など存在し得ないからである。つまり、すべては不易流行である)。
現在では「特殊設定ミステリ」なども歓迎されるようになり、以前に比べればずいぶんと「寛容になった」かのように見える本格ミステリ界とは言え、「本格ミステリ」の世界は「謎と(形式)論理」という一線だけは、決して譲らない。
それに対し「SF」というのは、競って「前例のないビジョン」の提示を求めるジャンルであるからこそ、大森望の「党派作り」は、「文壇政治」ではなく「SF更新運動」としての意味を、正当に持ちうるのである。
したがって私は、大森望について「身内に甘い」と苦言を呈しながらも、その「意図や目指す方向」自体は否定しない。私は樋口恭介が大嫌いだけれども、彼が結果として「SF更新運動」の駒として活躍すること自体は否定しない。
私自身、「勘違いに生意気」と評して良いだろう清涼院流水の人も作品も嫌いだったが、しかし、清涼院流水が体現する「逸脱」を排除しようとした「新本格ミステリ第1期」作家たちの「エリート主義」を批判して清涼院を擁護したように、大森望(や東浩紀)が樋口恭介を「SF界の清涼院流水」としてプッシュしようとすることに、不満はないのである。
「ゲンロンカフェ」での鼎談(2021年11月10日開催、私は3日前の2022年1月27日に録画を視聴)で東浩紀が、樋口恭介に「もっとイキれ(本性を出せ)」を要求していたように、私も、樋口に同じことを求めたい。どうせ「イキったガキ」なのなら、小賢しく保身になど走らず、ツッパリ切れ、と言いたい。
無論、それで樋口恭介が潰れても、私としてはぜんぜん惜しくない。樋口が「SF界の捨て石」になってくれたなら、その時はきっと、私は心からの哀悼の意と感謝を捧げるはずである。

だから、まだまだ「清涼院流水の域」に達していない小粒な樋口恭介には、単なる「イキったガキ」に終わることなく、本物の「大馬鹿者」になり「馬鹿力」を発揮して、SF界を更新して欲しい。その場合「SFプロトタイピングなんて、子供騙しのヌルいことなど言ってる暇はないぞ」ということなのだ。
そして大森望も、樋口恭介に、大筋で同様の期待をしているはずである。だからこそ私は、大森望を批判しないのだ。
(2022年1月30日)
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
