
ジョルジュ・シムノン 『証人たち』 : 「裁くなかれ」は、 無欠の神にしか言い得ない。
書評:ジョルジュ・シムノン『証人たち』(河出書房新社)
「メグレ警視」シリーズで知られる、ジョルジュ・シムノンによるノンシリーズの法廷小説である。
ただし、ミステリ(推理小説)ではない。
あくまでも「法廷もの」であり、大岡昇平による法廷ものの傑作『事件』よりもさらにミステリ的な要素は薄く、本作の場合は「人間とは、どういうものであるか」ということと、その結果「人間が人間を(誤りなく)裁くことは可能なのか」ということがテーマとなっている。
本作は、重罪裁判所の裁判長である主人公の視点から、ある変死事件(殺人容疑)の「陪審員裁判」と、裁判長自身の「私生活」を描かれている。
「裁判」においては、彼の目を通して「被疑者」「陪席判事」「陪審員」「検察官」「弁護士」「警察官」「監察医」「裁判傍聴者」そして「証人」たちの姿が描かれるのだ。

本書の帯には、
『フランスに陪審員制が生きていた時代を背景に、裁判の矛盾と限界と不備を突く、シムノンの法廷物の傑作。』
とあるので、てっきりフランスでは現在「陪審員制」を採っていないのかと思ったのだが、調べてみると、現在も「陪審員制」は採られているようであり、より正確には、本作で描かれているのと同様、「評決」に裁判官も加わる「参審制」のようだ。
一方、日本では現在、凶悪犯罪に限って「裁判員制度」が採用され、すでに定着しているのだが、裁判員のプライバシー保護の関係からか、ほとんど報道されることがないので、一般には馴染みもなければ、実態のよくわからないものになっているうらみがある。ちなみに、ごく大雑把に言うと、
・「陪審制」とは「有罪無罪を陪審員だけで決め、量刑は裁判官が決める」もの。
・「参審制」とは、前記のとおり「陪審員と裁判官で評決して、量刑は裁判官が決める」もの。
・「裁判員制」とは、「裁判員と裁判官で評決し、量刑も両者の合議で決める」もの。
のようだが、詳しくは調べていないので、誤認があるかもしれないと、あらかじめ断っておく。
上の説明は、あくまでも、陪審員制度の「イメージ」を持ってもらうためのものとご理解いただきたい。
さて、本作で描かれるのは「参審制」なのだが、これがそれまでの「裁判官のみによる裁判」とどう違うのかといえば、当然のことながらそれは、判決に裁判の「素人」が加わるという点にあろう。
つまり、「法令」は無論、「判例」まで知悉している、プロフェッショナルの裁判官とは違い、基本的には、よく言えば「市民感覚」、悪く言えば「(裁判の)素人感覚」だけで、判決に加わる「非・裁判官」が、陪審員なのである。
したがって、小説としては、この方が面白いドラマに仕立てやすい、ということになる。
裁判官というのは、知識も経験もあるから、基本的には「慎重」であって、よほどのこと(決定的な新証拠の提出など)がないかぎりは、その判断が大きく変化することはないのだが、大雑把に言って「素人」は、最初は素人らしい「大胆さ」を持っている。
ただし、裁判の過程で、検察側と弁護側の両方から提出される各種の「微妙な証拠・証言」などに触れ、さらに自分の判断が一人の人間(容疑者)の人生を大きく変えるのだという「責任の重さ」を徐々に実感していくうちに、その態度もおのずと「慎重」になっていくという「変化」があり、それを小説として「劇的」に描くことができるからだ。
例えば、「法廷もの」映画として、あまりにも有名な『十二人の怒れる男』(シドニー・ルメット監督・1957年)があるけれども、この作品の魅力は、なんと言っても「当初はそれぞれの〝人生観〟や〝人間観〟から、容疑者を有罪だと決めつけていたも同然の11人の陪審員の意見を、その容疑に懐疑的な一人の陪審員が、合理的な疑問点を提出するなどして、他の陪審員たちの意見をひとつひとつ翻させてゆき、最後に容疑者の無罪判決を勝ち取る」という「理性とヒューマニズム」のドラマ、言うなれば、当時の「アメリカの良心」を象徴するようなドラマとなっていた点であろう。

つまり、「陪審員裁判もの」の面白さというものは、「最後のどんでん返し」的な一撃ではなく、むしろ「人間の物の見方」の不確かさを「徐々にあぶり出していく」のに適している点にあるのだ。
人々は、それぞれに、その「人生観」や「人間観」を持っているから、「人生とはそういうものさ」とか「人間とはこうものさ」という判断をしがちなのだが、しかしそれは、多くの場合、所詮は「偏見」であり「臆見」でしかない。
なぜなら、そうした判断の根拠となっている、その人の「人生観」や「人間観」というのは、たいがいの場合、そのひと個人の「たかだか数十年」の「ごく限られた経験(限られたデータ)」から導き出された「経験則」でしかないからである。
だが、言うまでもなく「現実」には、そのひと個人の「経験」や「視野」や「常識」では見透し得ない「事」や「物」や「人」が、いくらでも存在しているのだ。
また、そうであるからこそ、裁判官というのは、自身の「限られた了見と判断力」だけに頼ることなく、「判例」の勉強をおさおさ怠らないのである(無論これは、判例追認主義を支持しているのではない)。
そんなわけで、本作で描かれるのも、そうした個人の「判断力の限界」である。
それは、「素人」である「陪審員」たちだけの話ではなく、なによりも、経験豊かな「裁判長」自身が、おのれの「判断力」を懐疑せ得なくなる物語なのだ。
私は先に、本作は、裁判長の視点から、当該「裁判」の進展と裁判長自身の「私生活」が描かれると紹介したけれど、なぜ「裁判」だけではなく、裁判長の「私生活」が描かれるのかと言えば、それは、観察力や洞察力に富んでいるはずの彼でさえも、結局のところ、長年連れ添った妻の心さえ「よくわからなかった」という「痛切な現実」を描くためなのである。
そして、長年連れ添った妻の「心」さえ、実際のところ「わかっている(わかった)」とは言えないのに、それまで見も知らぬ「他人」でしかなった「被疑者(被告人)」が「何を考え、どのようなことをしたのか」などという「事件の真相」を、わずかばかりの証拠と証言だけで、どうして「正しく判断する(誤りなく判断する)」ことなど出来ようかと、そんな、ごく常識的な「疑問」が、本作では提出されているのだ。

だから、本作は「人生の機微」を描く小説であるとともに、「人が人を裁く」行為として「裁判」というものに代表される「人間存在の不完全性」が描かれている、と言えるだろう。
要は「神ならぬ身としての人間=必然的に誤ちを犯す蓋然性を備えた人間」が、他人の人生を大きく変えてしまうような重大な「判断」を、責任を持って下すことなど、「可能なのか?」ではなく、「して良いものなのか?」という疑義が呈されているのである。
そのあたりのことを、訳者の野口雄司は「訳者あとがき」の冒頭で、次のように書いている。
『 シムノンは生涯で一九三点のロマン(長編小説)を書いた。このうち、メグレ警視を主人公にしたロマンが七六点、計二〇〇点弱のこれらのロマンのなかで、裁判、とくに冤罪の問題を扱っているものが、メグレもので二点(「男の首」、「重罪裁判所のメグレ」)、それ以外で二点(「重罪裁判所』、本書)、併せて四点ある。メグレは犯罪捜査官であるから、その捜査の帰結するところは当然裁判にむすびつくわけだが、メグレは自分が直接裁判にかかわることをひどく嫌っていた。「重罪裁判所のメグレ』という作品で、メグレは次のような感想をもらしている。
「ここに、二百回、三百回、来ただろうか? あるいは、もっとそれ以上? 彼は数える気がしなかった。……ここへ来ることは、彼の仕事のなかで、もっとも辛い面だったからだ。……とはいえ、彼の捜査の多くは、今日のように重罪裁判所か、あるいは軽罪裁判所に行きつくのだった。できるものなら、そのことは知らずにいたかったし、いずれにせよ、この最後の儀式からは遠ざかっていたかった」(小佐井伸二訳)
このメグレの感想は、著者自身の考え方をよく表わしている。シムノンは人間を、人間の行為を「理解すること、裁くなかれ」をモットーにしていたからである。
一九四一年に発表された「重罪裁判所』では、同棲していた女が何ものかに殺され、その女の財産を横領しようとして、まぎらわしい行動をとったがために逮捕され、殺人犯として起訴された男が主人公として描かれている。この男の場合、死体を隠したり、殺人の痕跡を消そうとしたりして、犯人と間違われたわけで、裁判の過程でも真実は明らかにされず、あらゆる証拠が彼の不利にはたらく。けっきょく彼は、裁判制度という巨大な機構にまきこまれてどうすることもできず、殺人罪で重労働二十年の刑に処せられる。
人間の真実を明らかにするのに裁判制度は不備であるとシムノンは言いたいようだ。その主張がもっとも端的に表われているのが本書である。』(P242〜243)
ここまでの話なら、多くの方も「それはそうだ」と納得することだろう。だが、私は「ここから先」を論じたい。
上の「訳者あとがき」で野口は『人間の真実を明らかにするのに裁判制度は不備であるとシムノンは言いたいようだ。』と理解したようなのだが、果たして、そうなのだろうか?
私が思うに、シムノンが考えているのは「人が人を裁くというのは、原理的に不可能ことだ」ということなのだ。「裁判」だけではなく、メグレの「捜査」だって、100パーセント確実ではあり得ない。メグレが「人間なのであれば」だ。
備えようと思えば備えられる、裁判の『不備』のことではなく、ここでの問題は、人間そのものの備える「原理的不完全性」なのである。
つまり、「(誤ることのない)神ならぬ身の(誤ることのある)人間」なのであれば、「裁判」においては、「少数例外」だとは言っても、必ず「誤審」は付きもの、なのである。
いや、それには止まらず、裁判以前の「犯罪捜査」においても、そうした「人間的なミスや誤認」は付きものであり、要は「誤認逮捕」や「冤罪」といったことは、「少数例外」的なものであれ、確率論的「必然」として、発生するものなのだ、ということである。
言い換えれば、そうした「望ましからざるもの」は、「発生させてはならない」ではなく、「確実に発生する」ものなのである。
これは、良いも悪いもない事実であり、人間が「有限性の存在」であるかぎり、字義どおりの「万全」を期することは「不可能」なのだ。「99・9999パーセント」のことはやれても「100パーセント」確実なことなど原理的に行い得ず、おのずと「少数例外」ながら「ミスや誤認」は、必ず発生するのである。
一一くり返すが、これは「良い悪い」の問題ではなく、必然なのだ。「重力(の縛り)がある」という事実に「良いも悪いもない」のと同じ、これは「物理的事実(限界)」だからである。
「重力」の存在について「好悪(あるいは、好都合不都合)」の意見は別れようとも、その自然法則の存在そのものに「良い悪い」は無いのであり、その意味で、人間は「絶対確実」なことはできないのである。
(※ 例えば、衆人環視のなかで人が殺され、すべての人が「彼が殺した」と証言したとしても、クリスティの某作のように、すべての証人が口裏を合わせて嘘をついていた、という可能性は否定できない。ほとんどゼロに近い可能性でも、ゼロではないのだ)
そしてそれは、「原子力の管理」でも「裁判」でも、まったく同じことなのである。
(※ 世界中の科学者が「もう絶対に原発事故は起こらない」と断じ保証しても、起こる時は起こる。それの起こる可能性がきわめて低いというだけの話で、かつてもそう保証されていながら、福島第一原発事故は、現に起こった)

まただからこそ、問題は「それでも、それが必要なのか」という話にもなるのである。
そして結局は、「メリットとリスクの兼ね合い」という問題にしかならない。
「犯罪者を野放しにはできない」から「犯罪者は逮捕拘束し、処罰しなければならない」というのであれば、「少数例外」とは言え、「誤認逮捕」や「誤審」の発生の必然性は、認めなければならない。
「犯罪者は確実に逮捕し処罰しなければならないが、誤認逮捕は〝絶対に〟許されない」という要求は、「不可能事」の要求であり、それ自体が「不可」なのだ。
人間に「両腕で羽ばたいて空を飛べ。絶対に、両腕以外は使ってはならないし、その条件で飛ばなければならない」と言っても、それが「不可能」なのと、同じことなのである。
無論、「誤認逮捕」や「誤審」は、「可能なかぎり、減らす努力をしなければならない」というのは当然のことだが、それはあくまでも「努力義務」であって「絶対義務」ではあり得ない。
原理的に「不可能なこと」を他人に要求するのなら、「じゃあ、お前は絶対に誤らないで生きてみせろ」と言われても仕方がないし、「誤ったら、そこで殺されても文句は言うな」と言われて、「絶対に誤らないで生きて見せよう」などと約束できる者など「存在しない」のである。
また、そう「請け合う」人がいたとすれば、その人は「死ぬつもりでいる」のか「狂っている」か、しかないのだ。
だから、私たちはよく「冤罪事件は、絶対にあってはならない」とか「誤審は、絶対にあってはならない」などと「慣習的」に言うけれども、これらは所詮、「聞こえの良いレトリック」にすぎない。
そのように語る人だって、本音では「冤罪事件」や「誤審」が「100パーセント無くせる」と思って言っているわけではない。
頭がおかしくないのであれば、「100パーセントは無理だが、限りなくそれに近づける、最大の努力をしなければならない」と、そう考えて、そういう意味で言っているはずなのだ。
ただ「冤罪をなくす努力をしなければならない」とか「誤審をなくす努力をしなければならない」と言っただけでは、警察官や裁判官などから、口には出さなくても「そんなこと、言われなくてもわかっているよ」「言われなくても、できる限りのことはやっているよ」という反応しか返ってこないように思え、それでは「現状肯定」になってしまう恐れがあると考えるので、「不可能」だとわかっていても、強調表現として、あえて「完全完璧を目指せ(その義務がある)」という言い方をするのである。つまり、そういう「レトリック(文飾)」を使うのだ。
したがって、本作が描くように、「結局のところ、人は他人のことを完全に理解することはできない」とか「他人の過去の事実を、完全に正しく再現して、それを正しく理解することなどできない(つまり、犯罪捜査や裁判における誤認は、ゼロにはできない)」というのは、いわば「当たり前の話」なのだ。
だから問題は、それでも「誤認逮捕や誤審による死刑という結果を認めてまでも、私たちは犯罪容疑者を処罰しなければならないのか?」ということが、究極的な「問い」ということになる。
そしてその答えは、当然のことながら「犯罪者は野放しにはできないから、逮捕処罰は、絶対に必要」ということになるのだ。
また、そう考えるのならば、その人は、自らもまた「誤認逮捕や誤審の必然性」を消極的に支持している、という事実を認め、その自覚と責任を持たなければならない。
「冤罪事件は、絶対にあってはならない」とか「誤審は、絶対にあってはならない」と、不可能事を「一部の他人」に押しつけることで、自分の手は「汚れていない」と考えてはならない。
「司法制度」を認め、すなわち「犯罪の容認」をしないのであれば、その人は「自分の手も、他人の(無実の)血に塗れている」という事実を、認めなければならない、責任があるのである。
だから、「反原発」なら「原発は必要だが、事故は絶対ダメ」というのは「インチキ」である。
つまり「原発を認めるのであれば、事故の可能性も認めなければならない」。
同様に「司法制度」を認めるのであれば、「犯罪者の逮捕処罰は必要だが、冤罪や誤審は絶対にダメ」というのも「インチキ」である。
「犯罪者の逮捕処罰は必要」だというのなら、「冤罪や誤審の可能性(少数例外の存在)」は認めなければならない。
まただからこそ、そうした「人為的ミス」が発生した際にも「最悪の結果」を回避するための「次善の策」として、「死刑廃止」ということが言われるのだ。「殺してしまわなければ、100パーセントの償いは不可能(無理)でも、償いの可能性自体は残される」からである。
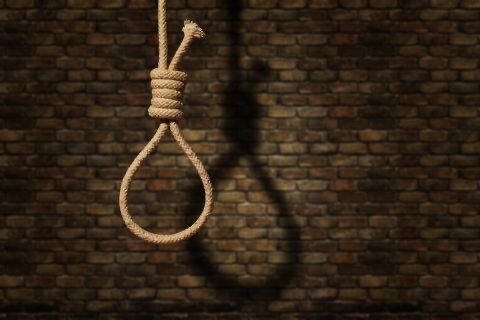
もちろん、「死刑」を無くして「無期懲役」にしたところで、「冤罪や誤審」は無くならない。
また、「無期懲役」以下の処罰において、それが誤って課されたもの(誤処罰)だったと判明した場合に「償いの可能性は残されている」とは言っても、その「償い」とは、無論「程度もの」の話でしかなく、100パーセントの「償い」ではあり得ない。
つまり、「無期懲役」までなら「冤罪や誤審が、あっても良い」ということにはならない、というのは、言うまでもない話なのだ。
しかし、「完全完璧(絶対)」を期し得ない以上、私たちは常に「取り返し不可能な(決定的な)結果を招きかねない危険物」に、手をつけるべきではない。
それがいくら、たいがいの場合には「便利なもの」であろうと、「効率的なもの」であろうと、その一歩手前で立ち止まらなければ、私たちは、明日「冤罪で逮捕されても」「誤審で死刑になっても」「原発事故の被害に遭って死んでも」、文句の言える筋合いではないのである。一一なぜなら、それは「当初から想定された話」でしかない、からである。
前述の「訳者あとがき」では、メグレは、裁判という『この最後の儀式からは遠ざかっていたかった』と考えていたことになっているが、しかし、裁判(という避けがたい現実)から逃げるのは、その一端を担う捜査官としては「無責任」であり、それは「現実逃避」でしかないということを知っていたからこそ、メグレは嫌でも「裁判」につき合わざるを得なかった。
だから、『シムノンは人間を、人間の行為を「理解すること、裁くなかれ」をモットーにしていた』のだとしたら、シムノンは「司法制度」の「必然的な矛盾」を認めて、「司法制度を否定する(犯罪の発生を容認して、神の裁きに委ねる)」か、さもなくば「冤罪や誤審の必然的可能性という現実を認めた上で、人間的な限界を持ったその制度をも認め、その結果については、その責の一端を担う」という意識を持たなければならない。
『裁くなかれ』という言葉が、人間の現実において実質的には「誤りなく裁け」という意味にしかならないのならば、その言葉は、他者への「不可能な要求(他人事の放言)」でしかなく、その態度は「無責任」のそしりを免れ得ないものなのである。
しかしまた、だからこそ私たちは「法の正義」に対する監視を、自己の責任と義務において、避けてはならないのである。
(2024年5月2日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
